4 / 14
閑話1(閑話は主にロキがいなくなった国の様子)
しおりを挟む
ドミトリー王国の元副将軍ケニウスはクーデターのどさくさに紛れて将軍を殺害し、その地位を奪い取ることに成功していた。
現在は精霊術師ロキ・ウォーレンが暮らしていた離宮を捜索している途中である。
捜索というよりも家探しだろうか。
略奪と言い換えてもいい。
ロキの持ち物を片っ端から自分の物とする権利を、この男は革命軍のリーダーであるリグルという男から褒美として貰っていたのだ。
この男が革命に協力したのはその実目先の利益のためだった。
王が無能だの、民の声を聞かなかっただのはこの男が自分と部下を納得させるために作り上げている虚構の大義名分である。
「おい、なんだこれ」
「あん?なんかの魔道具か?」
「どうした」
「あ、将軍閣下。それが、何やら魔道具のようなものが壁にめり込んでやがるんです」
「壁に?」
魔道具は非常に高価な代物だ。
壁になどめり込まれては回収できないではないか、と男は憤った。
だが同時に疑問に思う。
なぜそのようなことをしているのか。
持ち出し防止のためか、それともこの部屋自体になんらかの効力を発するものなのか。
「魔導士に調べさせろ」
「わかりました」
ケニウスはその魔道具を絶対に自分の物としてやると思った。
「なに、封印具?」
「ええ、それは私が陛下から......いえ前王から命令されて作ったものです。なんでも精霊術師の力を弱めるためのものとか」
「それをロキ・ウォーレンの部屋に?おかしいではないか。あのお方、いやあいつは精霊術をバンバン使っていたぞ。曲がりなりにもこの国一番の精霊術師だった男だ。それがずっと力を弱められていたということか」
「実際に使われていたのかどうかは私にはわかりかねます。もしかしたら、ロキ様が謀反を起こしたときのための備えだったのかもしれませんし」
ケニウスはなるほどと思った。
精霊術師ロキ・ウォーレンの力をケニウスはちっぽけなプライドから認めたくはなかったが、客観的に見てこの国一番の脅威だった。
ロキを国外追放にするため護送しているとき、ケニウスは生きた心地がしなかった。
死なばもろともという気概で向かってこられたら王軍が全滅していたかもしれない。
冗談抜きでロキという存在は一軍に匹敵する力を持った精霊術師だったのだ。
王が恐れてそのような魔道具を用意していてもおかしくはない。
ケニウスはその魔道具が使われることは無かったと判断した。
そしてもしロキに匹敵する精霊術師が出てきたとしてもその魔道具さえあれば弱体化することができるとほくそ笑んだ。
砂漠の真ん中に放置された温室育ちの精霊術師がまさか生きているとは誰も思いもしなかったのだった。
現在は精霊術師ロキ・ウォーレンが暮らしていた離宮を捜索している途中である。
捜索というよりも家探しだろうか。
略奪と言い換えてもいい。
ロキの持ち物を片っ端から自分の物とする権利を、この男は革命軍のリーダーであるリグルという男から褒美として貰っていたのだ。
この男が革命に協力したのはその実目先の利益のためだった。
王が無能だの、民の声を聞かなかっただのはこの男が自分と部下を納得させるために作り上げている虚構の大義名分である。
「おい、なんだこれ」
「あん?なんかの魔道具か?」
「どうした」
「あ、将軍閣下。それが、何やら魔道具のようなものが壁にめり込んでやがるんです」
「壁に?」
魔道具は非常に高価な代物だ。
壁になどめり込まれては回収できないではないか、と男は憤った。
だが同時に疑問に思う。
なぜそのようなことをしているのか。
持ち出し防止のためか、それともこの部屋自体になんらかの効力を発するものなのか。
「魔導士に調べさせろ」
「わかりました」
ケニウスはその魔道具を絶対に自分の物としてやると思った。
「なに、封印具?」
「ええ、それは私が陛下から......いえ前王から命令されて作ったものです。なんでも精霊術師の力を弱めるためのものとか」
「それをロキ・ウォーレンの部屋に?おかしいではないか。あのお方、いやあいつは精霊術をバンバン使っていたぞ。曲がりなりにもこの国一番の精霊術師だった男だ。それがずっと力を弱められていたということか」
「実際に使われていたのかどうかは私にはわかりかねます。もしかしたら、ロキ様が謀反を起こしたときのための備えだったのかもしれませんし」
ケニウスはなるほどと思った。
精霊術師ロキ・ウォーレンの力をケニウスはちっぽけなプライドから認めたくはなかったが、客観的に見てこの国一番の脅威だった。
ロキを国外追放にするため護送しているとき、ケニウスは生きた心地がしなかった。
死なばもろともという気概で向かってこられたら王軍が全滅していたかもしれない。
冗談抜きでロキという存在は一軍に匹敵する力を持った精霊術師だったのだ。
王が恐れてそのような魔道具を用意していてもおかしくはない。
ケニウスはその魔道具が使われることは無かったと判断した。
そしてもしロキに匹敵する精霊術師が出てきたとしてもその魔道具さえあれば弱体化することができるとほくそ笑んだ。
砂漠の真ん中に放置された温室育ちの精霊術師がまさか生きているとは誰も思いもしなかったのだった。
0
あなたにおすすめの小説

防御力を下げる魔法しか使えなかった俺は勇者パーティから追放されたけど俺の魔法に強制脱衣の追加効果が発現したので世界中で畏怖の対象になりました
かにくくり
ファンタジー
魔法使いクサナギは国王の命により勇者パーティの一員として魔獣討伐の任務を続けていた。
しかし相手の防御力を下げる魔法しか使う事ができないクサナギは仲間達からお荷物扱いをされてパーティから追放されてしまう。
しかし勇者達は今までクサナギの魔法で魔物の防御力が下がっていたおかげで楽に戦えていたという事実に全く気付いていなかった。
勇者パーティが没落していく中、クサナギは追放された地で彼の本当の力を知る新たな仲間を加えて一大勢力を築いていく。
そして防御力を下げるだけだったクサナギの魔法はいつしか次のステップに進化していた。
相手の身に着けている物を強制的に剥ぎ取るという究極の魔法を習得したクサナギの前に立ち向かえる者は誰ひとりいなかった。
※小説家になろうにも掲載しています。

幼女はリペア(修復魔法)で無双……しない
しろこねこ
ファンタジー
田舎の小さな村・セデル村に生まれた貧乏貴族のリナ5歳はある日魔法にめざめる。それは貧乏村にとって最強の魔法、リペア、修復の魔法だった。ちょっと説明がつかないでたらめチートな魔法でリナは覇王を目指……さない。だって平凡が1番だもん。騙され上手な父ヘンリーと脳筋な兄カイル、スーパー執事のゴフじいさんと乙女なおかんマール婆さんとの平和で凹凸な日々の話。

治療院の聖者様 ~パーティーを追放されたけど、俺は治療院の仕事で忙しいので今さら戻ってこいと言われてももう遅いです~
大山 たろう
ファンタジー
「ロード、君はこのパーティーに相応しくない」
唐突に主人公:ロードはパーティーを追放された。
そして生計を立てるために、ロードは治療院で働くことになった。
「なんで無詠唱でそれだけの回復ができるの!」
「これぐらいできないと怒鳴られましたから......」
一方、ロードが追放されたパーティーは、だんだんと崩壊していくのだった。
これは、一人の少年が幸せを送り、幸せを探す話である。
※小説家になろう様でも連載しております。
2021/02/12日、完結しました。

追放された私の代わりに入った女、三日で国を滅ぼしたらしいですよ?
タマ マコト
ファンタジー
王国直属の宮廷魔導師・セレス・アルトレイン。
白銀の髪に琥珀の瞳を持つ、稀代の天才。
しかし、その才能はあまりに“美しすぎた”。
王妃リディアの嫉妬。
王太子レオンの盲信。
そして、セレスを庇うはずだった上官の沈黙。
「あなたの魔法は冷たい。心がこもっていないわ」
そう言われ、セレスは**『無能』の烙印**を押され、王国から追放される。
彼女はただ一言だけ残した。
「――この国の炎は、三日で尽きるでしょう。」
誰もそれを脅しとは受け取らなかった。
だがそれは、彼女が未来を見通す“預言魔法”の言葉だったのだ。
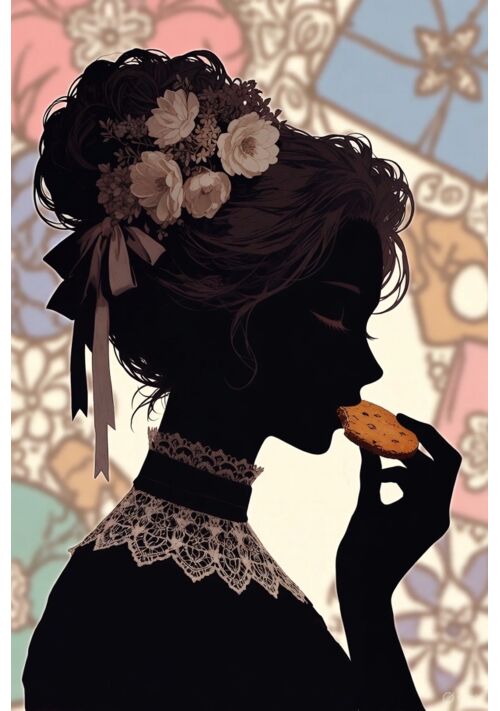
誰からも食べられずに捨てられたおからクッキーは異世界転生して肥満令嬢を幸福へ導く!
ariya
ファンタジー
誰にも食べられずゴミ箱に捨てられた「おからクッキー」は、異世界で150kgの絶望令嬢・ロザリンドと出会う。
転生チートを武器に、88kgの減量を導く!
婚約破棄され「豚令嬢」と罵られたロザリンドは、
クッキーの叱咤と分裂で空腹を乗り越え、
薔薇のように美しく咲き変わる。
舞踏会での王太子へのスカッとする一撃、
父との涙の再会、
そして最後の別れ――
「僕を食べてくれて、ありがとう」
捨てられた一枚が紡いだ、奇跡のダイエット革命!
※カクヨム・小説家になろうでも同時掲載中
※表紙イラストはAIに作成していただきました。

追放された無能鑑定士、実は世界最強の万物解析スキル持ち。パーティーと国が泣きついてももう遅い。辺境で美少女とスローライフ(?)を送る
夏見ナイ
ファンタジー
貴族の三男に転生したカイトは、【鑑定】スキルしか持てず家からも勇者パーティーからも無能扱いされ、ついには追放されてしまう。全てを失い辺境に流れ着いた彼だが、そこで自身のスキルが万物の情報を読み解く最強スキル【万物解析】だと覚醒する! 隠された才能を見抜いて助けた美少女エルフや獣人と共に、カイトは辺境の村を豊かにし、古代遺跡の謎を解き明かし、強力な魔物を従え、着実に力をつけていく。一方、カイトを切り捨てた元パーティーと王国は凋落の一途を辿り、彼の築いた豊かさに気づくが……もう遅い! 不遇から成り上がる、痛快な逆転劇と辺境スローライフ(?)が今、始まる!

悪役令息、前世の記憶により悪評が嵩んで死ぬことを悟り教会に出家しに行った結果、最強の聖騎士になり伝説になる
竜頭蛇
ファンタジー
ある日、前世の記憶を思い出したシド・カマッセイはこの世界がギャルゲー「ヒロイックキングダム」の世界であり、自分がギャルゲの悪役令息であると理解する。
評判が悪すぎて破滅する運命にあるが父親が毒親でシドの悪評を広げたり、関係を作ったものには危害を加えるので現状では何をやっても悪評に繋がるを悟り、家との関係を断って出家をすることを決意する。
身を寄せた教会で働くうちに評判が上がりすぎて、聖女や信者から崇められたり、女神から一目置かれ、やがて最強の聖騎士となり、伝説となる物語。

この聖水、泥の味がする ~まずいと追放された俺の作るポーションが、実は神々も欲しがる奇跡の霊薬だった件~
夏見ナイ
ファンタジー
「泥水神官」と蔑まれる下級神官ルーク。彼が作る聖水はなぜか茶色く濁り、ひどい泥の味がした。そのせいで無能扱いされ、ある日、無実の罪で神殿から追放されてしまう。
全てを失い流れ着いた辺境の村で、彼は自らの聖水が持つ真の力に気づく。それは浄化ではなく、あらゆる傷や病、呪いすら癒す奇跡の【創生】の力だった!
ルークは小さなポーション屋を開き、まずいけどすごい聖水で村人たちを救っていく。その噂は広まり、呪われた女騎士やエルフの薬師など、訳ありな仲間たちが次々と集結。辺境の村はいつしか「癒しの郷」へと発展していく。
一方、ルークを追放した王都では聖女が謎の病に倒れ……。
落ちこぼれ神官の、痛快な逆転スローライフ、ここに開幕!
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















