5 / 31
5
しおりを挟む
はっと目が覚めたのは、熱を発しようと体が震えたためだった。
寝ていたのかと、すっかり火の気の消えた跡を見やり、体が動かないことにギクリとした。そして腕にしっかりと抱えていたものを思い出した。マントに包まれた内側は二人分の体温で温まっていたが、外気に触れている表面はひんやりと冷えている。慌てて抱えていた少年に目を向け、桂樹はぎょっとした。
少年の目が、ぱっかりと開いていた。引き込まれるような鮮やかな緋色の瞳が、ぼんやりと桂樹を見ていた。にわかに狼狽え、この体勢に他意はないと言葉を探しかけ、桂樹は切れ長の群青の瞳をうっすらと眇めた。
そろりと手を伸ばし、少年の白磁の頬に触れる。白く滑らかな頬に、桂樹の健康的に焼けた手がよく映えた。硬い木の幹や葉を扱う桂樹の皮膚は硬く、少年の血管まで透かしそうなほど薄い肌は簡単に傷ついてしまいそうだった。
そろりと壊れ物を扱うように、指の背で頬を撫でる。
だが少年はピクリとも反応しなかった。緋色の瞳がただぼんやりと桂樹を見ている。いや、違う。彼は桂樹を見ているわけではなかった。ただ目を開けているだけだった。ぼんやりとした緋色の瞳は、焦点を失っている。
軽く頬を叩いてみるが反応はなく、桂樹は精悍さをみせる顔に困惑の表情を浮かべた。
世界中の粋を尽くして創られた、精巧で精緻な美しい人形を拾ったのかと錯覚すら覚えた。だが、少年は息付き温かい。生身であることは間違いない。
もしや木に食われかけると言う有り得ない体験に、心を閉ざしてしまったのだろうか。目を背けたい現実がある時、人はそれから逃れるように意識を逸らす。例え目の前にあったとしても、視界に入らないこともある。それほどの傷をこの少年が負っていても不思議でない。
そう思うとたまらなくて、桂樹は少年ときちんと相対した。
「俺は樹術師の桂樹・ノブリスだ。すまないが、君には東の森都ヴェルドジェーリュまで一緒に来てもらう。色々聞かなくてはいけないことがある」
相手に届いていることはないだろう。だがこれが最善であるように思われた。意識の有無に関わらず、彼を東の森都まで連れて行かなければならないのは事実だ。『森』の内で起こったことをそのままに捨て置いては、樹術師の意義にも関わる。これより数日、彼は見ず知らずの男に連れ回されることになるのだ。自身の素性を明らかにしておくことは、彼の意識がないとはいえ必要である。また、桂樹にとっても心身上安らかだ。
「君のことはなんと呼べばいいだろうか……」
切り替えが早いのは彼の長所だ。方向性さえ決まれば、迷うことはしない。彼を旅の友として連れ立って行くには、名前が必要不可欠だ。
ふむ、と考えるように目の前の美しい置物を見つめる。興味があるものを余すことなく目に入れるよう凝視するのは彼の癖だ。精悍だがそれ故強面にも見える桂樹の深い群青色の瞳に捉えられると、まるで射すくめられているようにも感じる。だが相対するのは反応のない美しい人形であり、自覚がない桂樹にそれを止めるつもりはない。
どれくらい美を楽しんだだろうか。桂樹はふと顔を上げた。
「ひぎり……」
確かそう言葉が落ちた。声音さえ残らないような音だった。それが何であるか、桂樹にはわからない。だが、彼を呼ぶに相応しい音であるように思えた。
「美しい緋色の眼をしていたしな。君のことは緋桐と呼ぼう。不服があるなら後でも構わない。名前を教えて欲しい」
まるで意識ある真っ当な人と会話するように、桂樹は少年に話しかけた。
人形のような少年、緋桐はそれに反応することはなかったが、桂樹は気にせずに腰を上げた。
「今日はここで休もう」
『森』に入ったのが昼過ぎだった。どれくらい『森』の中を探索したのかわからないが、緋桐を連れて戻った時には、陽は傾きかけていただろう。それからうとうとと眠ってしまえば、周辺はすっかり夜の帳の準備を始めるのも道理だ。
陽が湖に沈む様はひどく美しかっただろうと、見られなかったことを残念に思いながら、桂樹は天幕を用意する。
樹術師の大半の寝床は天幕だ。街から二、三日離れたところにある『森』を周るのに、それはどうしても不可欠なものだ。樹術師の多くは天幕の仕様に力を入れ、いかに日々を快適に眠るかを追求している。『森』の周辺に生き物は棲息しないため、少々大仰なことをしても、闇夜に襲われることもない。樹術師によっては、より部屋としての空間を作り上げることに熱意を燃やす者もいる。桂樹にそれほどの熱意はないが、快適に心地よく眠ることは、翌日の体調に気を使うことだ。過剰ではないが、配慮はしていた。
いつもの手順で手際よく準備をし、火を起こす。湯を沸かして持ち込んだ野菜や干し肉を刻んでスープを作り、街を出る前に買った腸詰めを焼いた。食欲を刺激する肉の焼ける匂いが漂い、腹の空き具合を知る。
ふと顔を上げ、ぼんやりとでもなく、ただ座しているだけの緋桐を見る。
緋色の瞳は相変わらず焦点を結ばずぼんやりとしているが、夜に溶けることのない銀糸の髪が存在を主張するように煌めいている。炎を受けて赤く色付く頬は白磁を思わせるように滑らかで、暗がりに茫洋と浮かぶ姿がひどく幻想的だった。
ただそこにあるだけで、純粋な美に視線を奪われずにはいられない。精巧で緻密、繊細にして優美な人形であると錯覚させるほどだ。
微動だにしない緋桐に向け、桂樹は出来立てのスープを差し出す。しかし自発的に動作をすることをしない彼は、椀を取ることもない。仕方なく、桂樹は一口すくって彼の薄く色付く唇に匙を運んだ。
「熱いぞ」
一言添えて匙を唇に触れさせると、緋桐の唇が開いた。こぼさないよう注意を払いながら匙を口内に入れると、目に毒なほど白く薄い喉元がかすかに嚥下した。
ゆっくりと時間をかけてスープを飲ませた後、桂樹はようやく自分の腹を満たすことが出来た。
(まるでただ美しいだけの人形だな……)
人形として作られたのであれば、これほど完成度の高いものもないだろう。だがどれだけ圧倒される美を誇っていようとも、ただ生きているだけの人形など魅力も価値もない。彼の価値は、その美しい緋色の瞳に光を宿してこそ発揮される。そんな日が来るといいと思いながら、桂樹は緋桐を天幕へと誘った。
なすがままの緋桐に何とも言えない気持ちを抱き、光を宿さない彼の瞳を閉じさせた。
寝ていたのかと、すっかり火の気の消えた跡を見やり、体が動かないことにギクリとした。そして腕にしっかりと抱えていたものを思い出した。マントに包まれた内側は二人分の体温で温まっていたが、外気に触れている表面はひんやりと冷えている。慌てて抱えていた少年に目を向け、桂樹はぎょっとした。
少年の目が、ぱっかりと開いていた。引き込まれるような鮮やかな緋色の瞳が、ぼんやりと桂樹を見ていた。にわかに狼狽え、この体勢に他意はないと言葉を探しかけ、桂樹は切れ長の群青の瞳をうっすらと眇めた。
そろりと手を伸ばし、少年の白磁の頬に触れる。白く滑らかな頬に、桂樹の健康的に焼けた手がよく映えた。硬い木の幹や葉を扱う桂樹の皮膚は硬く、少年の血管まで透かしそうなほど薄い肌は簡単に傷ついてしまいそうだった。
そろりと壊れ物を扱うように、指の背で頬を撫でる。
だが少年はピクリとも反応しなかった。緋色の瞳がただぼんやりと桂樹を見ている。いや、違う。彼は桂樹を見ているわけではなかった。ただ目を開けているだけだった。ぼんやりとした緋色の瞳は、焦点を失っている。
軽く頬を叩いてみるが反応はなく、桂樹は精悍さをみせる顔に困惑の表情を浮かべた。
世界中の粋を尽くして創られた、精巧で精緻な美しい人形を拾ったのかと錯覚すら覚えた。だが、少年は息付き温かい。生身であることは間違いない。
もしや木に食われかけると言う有り得ない体験に、心を閉ざしてしまったのだろうか。目を背けたい現実がある時、人はそれから逃れるように意識を逸らす。例え目の前にあったとしても、視界に入らないこともある。それほどの傷をこの少年が負っていても不思議でない。
そう思うとたまらなくて、桂樹は少年ときちんと相対した。
「俺は樹術師の桂樹・ノブリスだ。すまないが、君には東の森都ヴェルドジェーリュまで一緒に来てもらう。色々聞かなくてはいけないことがある」
相手に届いていることはないだろう。だがこれが最善であるように思われた。意識の有無に関わらず、彼を東の森都まで連れて行かなければならないのは事実だ。『森』の内で起こったことをそのままに捨て置いては、樹術師の意義にも関わる。これより数日、彼は見ず知らずの男に連れ回されることになるのだ。自身の素性を明らかにしておくことは、彼の意識がないとはいえ必要である。また、桂樹にとっても心身上安らかだ。
「君のことはなんと呼べばいいだろうか……」
切り替えが早いのは彼の長所だ。方向性さえ決まれば、迷うことはしない。彼を旅の友として連れ立って行くには、名前が必要不可欠だ。
ふむ、と考えるように目の前の美しい置物を見つめる。興味があるものを余すことなく目に入れるよう凝視するのは彼の癖だ。精悍だがそれ故強面にも見える桂樹の深い群青色の瞳に捉えられると、まるで射すくめられているようにも感じる。だが相対するのは反応のない美しい人形であり、自覚がない桂樹にそれを止めるつもりはない。
どれくらい美を楽しんだだろうか。桂樹はふと顔を上げた。
「ひぎり……」
確かそう言葉が落ちた。声音さえ残らないような音だった。それが何であるか、桂樹にはわからない。だが、彼を呼ぶに相応しい音であるように思えた。
「美しい緋色の眼をしていたしな。君のことは緋桐と呼ぼう。不服があるなら後でも構わない。名前を教えて欲しい」
まるで意識ある真っ当な人と会話するように、桂樹は少年に話しかけた。
人形のような少年、緋桐はそれに反応することはなかったが、桂樹は気にせずに腰を上げた。
「今日はここで休もう」
『森』に入ったのが昼過ぎだった。どれくらい『森』の中を探索したのかわからないが、緋桐を連れて戻った時には、陽は傾きかけていただろう。それからうとうとと眠ってしまえば、周辺はすっかり夜の帳の準備を始めるのも道理だ。
陽が湖に沈む様はひどく美しかっただろうと、見られなかったことを残念に思いながら、桂樹は天幕を用意する。
樹術師の大半の寝床は天幕だ。街から二、三日離れたところにある『森』を周るのに、それはどうしても不可欠なものだ。樹術師の多くは天幕の仕様に力を入れ、いかに日々を快適に眠るかを追求している。『森』の周辺に生き物は棲息しないため、少々大仰なことをしても、闇夜に襲われることもない。樹術師によっては、より部屋としての空間を作り上げることに熱意を燃やす者もいる。桂樹にそれほどの熱意はないが、快適に心地よく眠ることは、翌日の体調に気を使うことだ。過剰ではないが、配慮はしていた。
いつもの手順で手際よく準備をし、火を起こす。湯を沸かして持ち込んだ野菜や干し肉を刻んでスープを作り、街を出る前に買った腸詰めを焼いた。食欲を刺激する肉の焼ける匂いが漂い、腹の空き具合を知る。
ふと顔を上げ、ぼんやりとでもなく、ただ座しているだけの緋桐を見る。
緋色の瞳は相変わらず焦点を結ばずぼんやりとしているが、夜に溶けることのない銀糸の髪が存在を主張するように煌めいている。炎を受けて赤く色付く頬は白磁を思わせるように滑らかで、暗がりに茫洋と浮かぶ姿がひどく幻想的だった。
ただそこにあるだけで、純粋な美に視線を奪われずにはいられない。精巧で緻密、繊細にして優美な人形であると錯覚させるほどだ。
微動だにしない緋桐に向け、桂樹は出来立てのスープを差し出す。しかし自発的に動作をすることをしない彼は、椀を取ることもない。仕方なく、桂樹は一口すくって彼の薄く色付く唇に匙を運んだ。
「熱いぞ」
一言添えて匙を唇に触れさせると、緋桐の唇が開いた。こぼさないよう注意を払いながら匙を口内に入れると、目に毒なほど白く薄い喉元がかすかに嚥下した。
ゆっくりと時間をかけてスープを飲ませた後、桂樹はようやく自分の腹を満たすことが出来た。
(まるでただ美しいだけの人形だな……)
人形として作られたのであれば、これほど完成度の高いものもないだろう。だがどれだけ圧倒される美を誇っていようとも、ただ生きているだけの人形など魅力も価値もない。彼の価値は、その美しい緋色の瞳に光を宿してこそ発揮される。そんな日が来るといいと思いながら、桂樹は緋桐を天幕へと誘った。
なすがままの緋桐に何とも言えない気持ちを抱き、光を宿さない彼の瞳を閉じさせた。
10
あなたにおすすめの小説

林檎を並べても、
ロウバイ
BL
―――彼は思い出さない。
二人で過ごした日々を忘れてしまった攻めと、そんな彼の行く先を見守る受けです。
ソウが目を覚ますと、そこは消毒の香りが充満した病室だった。自分の記憶を辿ろうとして、はたり。その手がかりとなる記憶がまったくないことに気付く。そんな時、林檎を片手にカーテンを引いてとある人物が入ってきた。
彼―――トキと名乗るその黒髪の男は、ソウが事故で記憶喪失になったことと、自身がソウの親友であると告げるが…。

狼の護衛騎士は、今日も心配が尽きない
結衣可
BL
戦の傷跡が癒えた共生都市ルーヴェン。
人族と獣人族が共に暮らすその街で、文官ユリス・アルヴィンは、穏やかな日々の中に、いつも自分を見守る“優しい視線”の存在を感じていた。
その正体は、狼族の戦士長出身の護衛騎士、ガルド・ルヴァーン。
無口で不器用だが、誠実で優しい彼は、いつしかユリスを守ることが日課になっていた。
モフモフ好きなユリスと、心配性すぎるガルド。
灰銀の狼と金灰の文官――
異種族の二人の関係がルーヴェンの風のようにやさしく、日々の中で少しずつ変わっていく。
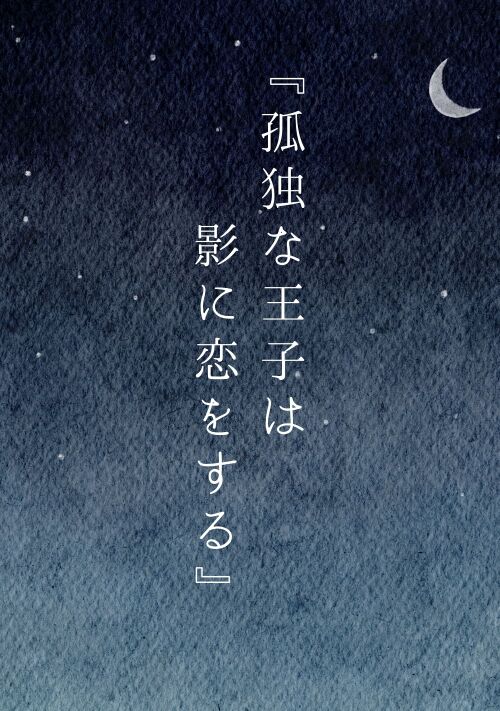
孤独な王子は影に恋をする
結衣可
BL
王国の第一王子リオネル・ヴァルハイトは、
「光」と称えられるほど完璧な存在だった。
民からも廷臣からも賞賛され、非の打ち所がない理想の王子。
しかしその仮面の裏には、孤独と重圧に押し潰されそうな本音が隠されていた。
弱音を吐きたい。誰かに甘えたい。
だが、その願いを叶えてくれる相手はいない。
――ただ一人、いつも傍に気配を寄せていた“影”に恋をするまでは。
影、王族直属の密偵として顔も名も隠し、感情を持たぬよう育てられた存在。
常に平等であれと叩き込まれ、ただ「王子を守る影」として仕えてきた。
完璧を求められる王子と、感情を禁じられてきた影。
光と影が惹かれ合い、やがて互いの鎖を断ち切ってゆく。

白花の檻(はっかのおり)
AzureHaru
BL
その世界には、生まれながらに祝福を受けた者がいる。その祝福は人ならざるほどの美貌を与えられる。
その祝福によって、交わるはずのなかった2人の運命が交わり狂っていく。
この出会いは祝福か、或いは呪いか。
受け――リュシアン。
祝福を授かりながらも、決して傲慢ではなく、いつも穏やかに笑っている青年。
柔らかな白銀の髪、淡い光を湛えた瞳。人々が息を呑むほどの美しさを持つ。
攻め――アーヴィス。
リュシアンと同じく祝福を授かる。リュシアン以上に人の域を逸脱した容姿。
黒曜石のような瞳、彫刻のように整った顔立ち。
王国に名を轟かせる貴族であり、数々の功績を誇る英雄。

happy dead end
瑞原唯子
BL
「それでも俺に一生を捧げる覚悟はあるか?」
シルヴィオは幼いころに第一王子の遊び相手として抜擢され、初めて会ったときから彼の美しさに心を奪われた。そして彼もシルヴィオだけに心を開いていた。しかし中等部に上がると、彼はとある女子生徒に興味を示すようになり——。

禁書庫の管理人は次期宰相様のお気に入り
結衣可
BL
オルフェリス王国の王立図書館で、禁書庫を預かる司書カミル・ローレンは、過去の傷を抱え、静かな孤独の中で生きていた。
そこへ次期宰相と目される若き貴族、セドリック・ヴァレンティスが訪れ、知識を求める名目で彼のもとに通い始める。
冷静で無表情なカミルに興味を惹かれたセドリックは、やがて彼の心の奥にある痛みに気づいていく。
愛されることへの恐れに縛られていたカミルは、彼の真っ直ぐな想いに少しずつ心を開き、初めて“痛みではない愛”を知る。
禁書庫という静寂の中で、カミルの孤独を、過去を癒し、共に歩む未来を誓う。

雪を溶かすように
春野ひつじ
BL
人間と獣人の争いが終わった。
和平の条件で人間の国へ人質としていった獣人国の第八王子、薫(ゆき)。そして、薫を助けた人間国の第一王子、悠(はる)。二人の距離は次第に近づいていくが、実は薫が人間国に行くことになったのには理由があった……。
溺愛・甘々です。
*物語の進み方がゆっくりです。エブリスタにも掲載しています

龍の寵愛を受けし者達
樹木緑
BL
サンクホルム国の王子のジェイドは、
父王の護衛騎士であるダリルに憧れていたけど、
ある日偶然に自分の護衛にと推す父王に反する声を聞いてしまう。
それ以来ずっと嫌われていると思っていた王子だったが少しずつ打ち解けて
いつかはそれが愛に変わっていることに気付いた。
それと同時に何故父王が最強の自身の護衛を自分につけたのか理解す時が来る。
王家はある者に裏切りにより、
無惨にもその策に敗れてしまう。
剣が苦手でずっと魔法の研究をしていた王子は、
責めて騎士だけは助けようと、
刃にかかる寸前の所でとうの昔に失ったとされる
時戻しの術をかけるが…
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















