31 / 31
31
しおりを挟む
「信じてます」
探るような紫の瞳を真っ直ぐに見つめ断言すると同時、背中に衝撃を受けて桂樹の体はぐらついた。何とか体制を保ち振り返ると、後ろから銀糸の髪ががっちりと抱きついていた。ぎゅーっと腰に手を回し、桂樹の背中に顔を埋める。
「本当意地悪さんですね、そんな試すような言い方するなんて」
いつの間にかお茶を淹れて戻って来た雛菊が、盆を両手に持ったまま柳眉を顰める。連理はソファから腰を上げると雛菊から盆を取り上げ、小さく肩をすくめる。
「だが、悪くない答えだろう?」
揃ってテーブルまで戻り、連理は湯気を立てる盆から茶器を下す。
桂樹は抱きつく緋桐を正面から抱き直し、再び腰を落ち着けてお茶を啜る総帥に向き直る。
「総帥、その仮説の上で確認します。緋桐は『鳥』ですか?」
二度目の問いかけに、反応を示したのは桂樹の腕の中にいる緋桐だった。びくりと背が震え、恐る恐る顔が上がる。零れ落ちるように大きな緋色は、何かに怯えているように潤んで見えた。
連理は飲んでいたお茶をテーブルに戻すと、鷹揚に頷いた。
「あぁ、そうだな……ッ!」
「違う! 俺は『鳥』じゃない!」
がっと、音が見えるような勢いで、緋桐がソファに乗り上げ連理の胸倉を掴み上げた。
「連理さん!」
「緋桐!!!」
ぐっと苦痛に歪んだ連理に雛菊は色をなし、突然の暴挙に桂樹も慌てた。ただ一人胸倉を掴まれた張本人だけが冷静に二人を制し、歯をくいしばって胸倉を掴む銀糸に手を置いた。
「あぁ、そうだな……お前はまだ『鳥』じゃない。さしずめ、擬きってところか」
胸倉を掴み上げられながらも穏やかで理性的な声に、頭が冷えたのか、緋桐の手から力が抜けてソファに落ちる。連理は触り心地の良い銀糸をくしゃくしゃと撫で、緋桐に顔を上げさせる。
濡れたように煌めく鮮やかな緋色に、連理の理知的な瞳が何か眩しいものを見るように細められる。
「説明はしてやる。だが、聞かないほうがよかったと思うかもしれない。それでも聞くか?」
朗々と響く声は心地良く真摯で、緋桐は迷うことをしなかった。
「聞く。知っても知らなくても、事実を変えることはできない」
自分が何であるのか、どうなっているのか、置かれている状況は何なのか。知らなくても自身を取り巻く環境や事実が変わるわけではない。ならば知った上でどうしたいのか、どう動くべきなのか、知ることで対処法も変わる。ならば聞くべきである。
強い意志に、連理は朗らかに笑った。
「良い覚悟だ。桂樹、今の仮説に矛盾はあるか?」
くしゃりと銀糸を掻き混ぜ、連理は桂樹に言葉を投げた。
問いかけに、お茶が冷めるからと無理矢理雛菊に座らされた桂樹が首を傾げる。
「矛盾……」
緋桐はその横に腰を下ろしながら、わずかに緋色を伏せた。
「俺が、言葉が理解出来ること……」
呟きに、にやりと連理が笑う。
「桂樹より優秀だな」
嘯く連理に緋桐は頭を振り、膝の上でぎゅっと拳を握った。
彼が向こうの世界から『森』を通じて渡ってきたのだとしたら、何故言葉は通じるのだろうか。緋桐は会話に困ることはないし、読むことも書くことにも不自由を感じない。
「ずっと考えた。俺は向こうの世界で生まれて生きてきたはずなのに、この世界のものに違和感を覚えないのは何でだろうって……」
宿屋での灯りの灯し方、竜種がいることを不審に思わないこと、空から見る景色の向こうに見る『世界樹』の視認。
緋桐はおそらく、この世界で生きていく為の知識に困ることはないだろう。
「……俺、やっぱり何処かおかしいのかな。向こうの世界なんてほんとはないのかな……」
俯いて声を詰まらせた緋桐を、桂樹が強く抱きしめる。そのそばで、雛菊が意地悪するから、と非難がましい目を連理に向けた。連理は小さく肩を竦めただけで動こうとはせず、雛菊は小さく嘆息して緋桐の固く握られた手にそっと触れた。
「大丈夫です。緋桐はおかしくありませんよ。混乱しているのは、情報の書き込みが途中で中断されたからです」
柔らで耳に心地の良い鈴の音が慰めの言葉を紡ぐ。
握られた雛菊の手が温かい。だが緋桐は、どっと全身から血の気が引くのを感じた。
今の彼女の言葉に、何か不穏なものを感じた。握られた雛菊の手の中で、さらに固く拳を握る。
情報の書き込みと中断。
それは、なんだ。
カタカタと震える緋桐の肩を桂樹が抱き、連理に説明を請うように顔を向ける。
「向こうの世界で、お前は確かに死んだんだ」
断言に、緋桐の頭はかすかに縦に振れた。
そうだ。あの時、縋るものは何もなかった。身も心もボロボロで、あったはずの小さな自尊心さえ蹴散らされ、踏み躙られて跡形もなかった。ただこの現実から逃げることが彼の全てで、他には何も考えられなかった。そうして彼は唯一持っていたものさえ、自ら棄てたのだ。だから、彼がここに渡ってくるはずがない。
「向こうで絶たれた生命を、『世界樹』が拾い上げて、『鳥』として『森』が生み出すんだ」
新たな生命として、新たな存在として、異世界からこの世界へ。生まれ変わりといえば聞こえがいいだろうか。『森』は『鳥』の苗床としての一面も持っている。『森』に力が貯められ、親木と呼ばれる一番力ある大樹が器を育む。『世界樹』から導かれた生命が、器と受肉し、世界の全てがそれに注がれる。世界の在り方から生活に必要な小さな一般常識まで。時に人が識るには大きすぎる世界の根源さえも、溢れることなく注がれる。
その対価として磨耗していくのは、向こうの世界での記憶だ。擦り切れた記憶が残滓のように残る頃、全ての書き込みを終えてそれは『鳥』として誕生する。
「全ての『鳥』が…?」
掠れた桂樹の声に、雛菊がそっと瞳を伏せた。
「向こうの世界で自ら生きることを放棄した生命が、今『鳥籠』にいる『鳥』たちです」
「何故……?」
わざわざ異界の地から生命を集めてくるのか。しかも生きることを放棄した憐れな生命たちばかりを。
「理由がわかれば苦労はしない。俺たちが『世界樹』の全てを知れるわけじゃない。おそらくは、『鳥』もな。ただそう言う仕組みなんだと、飲み込むしかない」
淡々とした口調だった。だが、全てを諦め達観しているような瞳の奥の奥に、言いようのない怒りと悔しさを滲ませている色が垣間見える。
「一度投げ出したものを、後にどう使おうと良いだろうと言う趣旨があるのは確かだと思いますよ。悪意ではありませんけどね」
「絶対の善意でもないだろう」
補足するように言葉を足した雛菊の台詞を、だが連理はばっさりと切って捨て、不機嫌に鼻を鳴らした。
「生命を使って新たな生命を創り出す、『鳥』はそうして生まれたものです」
ごくりと、桂樹の喉が鳴った。震える華奢な体を抱きしめたまま、では、と桂樹は思う。
緋桐が完全な『鳥』として生まれなかった訳は。親木から切り離され、書き込みを中断されたからだ。誰に。桂樹にだ。では彼が今背を震わせ、声を殺して泣いているのは、桂樹に責があるのか。
「……そ……は……も……じゃ……い……」
「緋桐?」
押し寄せた罪悪感に目の前が真っ暗になっていた桂樹は、腕の中から聞こえた小さな声にはっとして視線を落とした。
「それは……生き物と呼べる存在なのか……?」
『森』が創った身体と、行き場をなくした生命。元々別々であったものを、無理矢理繋ぎ合わせて動く塊とした。だがそれは生き物のようではあるが、生き物として何か異質なものではないか。生命として正しい輝きをもつものだろうか。
くぐもった声に桂樹はぐっと言葉に詰まり、雛菊は耐えきれないように顔を背けた。連理だけが、何か眩しいものを見るような、懐かしいものを見るように目を細めて緋桐を見る。
「己が何であるかを決めるのは他人じゃない。自分自身だ。重要なのは、自分が何であり、何でありたいのか、常に矜持を持ち続けることだ」
人であろうと『鳥』であろうと、異界から連れて来られた生命であろうと、思考して行動し、自身の道を決めて歩むのであれば、その生命は輝きを持っているはずだ。
「お前は、生命の輝きに生き物としての是非を問うのか?」
前を見据え、直向きにただ懸命に生きている生命に、生き物として正しいか否かを問う必要があるのか。すでに輝く生命を前に、その輝きは真っ当であるのかと問うのか。
言葉にならない声を上げ、緋桐の嗚咽が激しくなる。華奢な体は痙攣するように震え、見ているだけでも痛々しい。
「連理さん」
戒めは一言で足りた。連理は多少ばつが悪そうに両手を上げ、雛菊はそれを一睨みした後桂樹を隣の仮眠室へと促した。緋桐を抱き上げ、そっと簡易な寝台に乗せる。頭を撫でて、とめどなく流れる涙を拭う。しかし、嗚咽を漏らす緋桐の涙が止まることはなかった。
「緋桐は私が見てますから、桂樹は連理さんと話してください。お互いまだ話は終わっていないでしょう?」
探るような紫の瞳を真っ直ぐに見つめ断言すると同時、背中に衝撃を受けて桂樹の体はぐらついた。何とか体制を保ち振り返ると、後ろから銀糸の髪ががっちりと抱きついていた。ぎゅーっと腰に手を回し、桂樹の背中に顔を埋める。
「本当意地悪さんですね、そんな試すような言い方するなんて」
いつの間にかお茶を淹れて戻って来た雛菊が、盆を両手に持ったまま柳眉を顰める。連理はソファから腰を上げると雛菊から盆を取り上げ、小さく肩をすくめる。
「だが、悪くない答えだろう?」
揃ってテーブルまで戻り、連理は湯気を立てる盆から茶器を下す。
桂樹は抱きつく緋桐を正面から抱き直し、再び腰を落ち着けてお茶を啜る総帥に向き直る。
「総帥、その仮説の上で確認します。緋桐は『鳥』ですか?」
二度目の問いかけに、反応を示したのは桂樹の腕の中にいる緋桐だった。びくりと背が震え、恐る恐る顔が上がる。零れ落ちるように大きな緋色は、何かに怯えているように潤んで見えた。
連理は飲んでいたお茶をテーブルに戻すと、鷹揚に頷いた。
「あぁ、そうだな……ッ!」
「違う! 俺は『鳥』じゃない!」
がっと、音が見えるような勢いで、緋桐がソファに乗り上げ連理の胸倉を掴み上げた。
「連理さん!」
「緋桐!!!」
ぐっと苦痛に歪んだ連理に雛菊は色をなし、突然の暴挙に桂樹も慌てた。ただ一人胸倉を掴まれた張本人だけが冷静に二人を制し、歯をくいしばって胸倉を掴む銀糸に手を置いた。
「あぁ、そうだな……お前はまだ『鳥』じゃない。さしずめ、擬きってところか」
胸倉を掴み上げられながらも穏やかで理性的な声に、頭が冷えたのか、緋桐の手から力が抜けてソファに落ちる。連理は触り心地の良い銀糸をくしゃくしゃと撫で、緋桐に顔を上げさせる。
濡れたように煌めく鮮やかな緋色に、連理の理知的な瞳が何か眩しいものを見るように細められる。
「説明はしてやる。だが、聞かないほうがよかったと思うかもしれない。それでも聞くか?」
朗々と響く声は心地良く真摯で、緋桐は迷うことをしなかった。
「聞く。知っても知らなくても、事実を変えることはできない」
自分が何であるのか、どうなっているのか、置かれている状況は何なのか。知らなくても自身を取り巻く環境や事実が変わるわけではない。ならば知った上でどうしたいのか、どう動くべきなのか、知ることで対処法も変わる。ならば聞くべきである。
強い意志に、連理は朗らかに笑った。
「良い覚悟だ。桂樹、今の仮説に矛盾はあるか?」
くしゃりと銀糸を掻き混ぜ、連理は桂樹に言葉を投げた。
問いかけに、お茶が冷めるからと無理矢理雛菊に座らされた桂樹が首を傾げる。
「矛盾……」
緋桐はその横に腰を下ろしながら、わずかに緋色を伏せた。
「俺が、言葉が理解出来ること……」
呟きに、にやりと連理が笑う。
「桂樹より優秀だな」
嘯く連理に緋桐は頭を振り、膝の上でぎゅっと拳を握った。
彼が向こうの世界から『森』を通じて渡ってきたのだとしたら、何故言葉は通じるのだろうか。緋桐は会話に困ることはないし、読むことも書くことにも不自由を感じない。
「ずっと考えた。俺は向こうの世界で生まれて生きてきたはずなのに、この世界のものに違和感を覚えないのは何でだろうって……」
宿屋での灯りの灯し方、竜種がいることを不審に思わないこと、空から見る景色の向こうに見る『世界樹』の視認。
緋桐はおそらく、この世界で生きていく為の知識に困ることはないだろう。
「……俺、やっぱり何処かおかしいのかな。向こうの世界なんてほんとはないのかな……」
俯いて声を詰まらせた緋桐を、桂樹が強く抱きしめる。そのそばで、雛菊が意地悪するから、と非難がましい目を連理に向けた。連理は小さく肩を竦めただけで動こうとはせず、雛菊は小さく嘆息して緋桐の固く握られた手にそっと触れた。
「大丈夫です。緋桐はおかしくありませんよ。混乱しているのは、情報の書き込みが途中で中断されたからです」
柔らで耳に心地の良い鈴の音が慰めの言葉を紡ぐ。
握られた雛菊の手が温かい。だが緋桐は、どっと全身から血の気が引くのを感じた。
今の彼女の言葉に、何か不穏なものを感じた。握られた雛菊の手の中で、さらに固く拳を握る。
情報の書き込みと中断。
それは、なんだ。
カタカタと震える緋桐の肩を桂樹が抱き、連理に説明を請うように顔を向ける。
「向こうの世界で、お前は確かに死んだんだ」
断言に、緋桐の頭はかすかに縦に振れた。
そうだ。あの時、縋るものは何もなかった。身も心もボロボロで、あったはずの小さな自尊心さえ蹴散らされ、踏み躙られて跡形もなかった。ただこの現実から逃げることが彼の全てで、他には何も考えられなかった。そうして彼は唯一持っていたものさえ、自ら棄てたのだ。だから、彼がここに渡ってくるはずがない。
「向こうで絶たれた生命を、『世界樹』が拾い上げて、『鳥』として『森』が生み出すんだ」
新たな生命として、新たな存在として、異世界からこの世界へ。生まれ変わりといえば聞こえがいいだろうか。『森』は『鳥』の苗床としての一面も持っている。『森』に力が貯められ、親木と呼ばれる一番力ある大樹が器を育む。『世界樹』から導かれた生命が、器と受肉し、世界の全てがそれに注がれる。世界の在り方から生活に必要な小さな一般常識まで。時に人が識るには大きすぎる世界の根源さえも、溢れることなく注がれる。
その対価として磨耗していくのは、向こうの世界での記憶だ。擦り切れた記憶が残滓のように残る頃、全ての書き込みを終えてそれは『鳥』として誕生する。
「全ての『鳥』が…?」
掠れた桂樹の声に、雛菊がそっと瞳を伏せた。
「向こうの世界で自ら生きることを放棄した生命が、今『鳥籠』にいる『鳥』たちです」
「何故……?」
わざわざ異界の地から生命を集めてくるのか。しかも生きることを放棄した憐れな生命たちばかりを。
「理由がわかれば苦労はしない。俺たちが『世界樹』の全てを知れるわけじゃない。おそらくは、『鳥』もな。ただそう言う仕組みなんだと、飲み込むしかない」
淡々とした口調だった。だが、全てを諦め達観しているような瞳の奥の奥に、言いようのない怒りと悔しさを滲ませている色が垣間見える。
「一度投げ出したものを、後にどう使おうと良いだろうと言う趣旨があるのは確かだと思いますよ。悪意ではありませんけどね」
「絶対の善意でもないだろう」
補足するように言葉を足した雛菊の台詞を、だが連理はばっさりと切って捨て、不機嫌に鼻を鳴らした。
「生命を使って新たな生命を創り出す、『鳥』はそうして生まれたものです」
ごくりと、桂樹の喉が鳴った。震える華奢な体を抱きしめたまま、では、と桂樹は思う。
緋桐が完全な『鳥』として生まれなかった訳は。親木から切り離され、書き込みを中断されたからだ。誰に。桂樹にだ。では彼が今背を震わせ、声を殺して泣いているのは、桂樹に責があるのか。
「……そ……は……も……じゃ……い……」
「緋桐?」
押し寄せた罪悪感に目の前が真っ暗になっていた桂樹は、腕の中から聞こえた小さな声にはっとして視線を落とした。
「それは……生き物と呼べる存在なのか……?」
『森』が創った身体と、行き場をなくした生命。元々別々であったものを、無理矢理繋ぎ合わせて動く塊とした。だがそれは生き物のようではあるが、生き物として何か異質なものではないか。生命として正しい輝きをもつものだろうか。
くぐもった声に桂樹はぐっと言葉に詰まり、雛菊は耐えきれないように顔を背けた。連理だけが、何か眩しいものを見るような、懐かしいものを見るように目を細めて緋桐を見る。
「己が何であるかを決めるのは他人じゃない。自分自身だ。重要なのは、自分が何であり、何でありたいのか、常に矜持を持ち続けることだ」
人であろうと『鳥』であろうと、異界から連れて来られた生命であろうと、思考して行動し、自身の道を決めて歩むのであれば、その生命は輝きを持っているはずだ。
「お前は、生命の輝きに生き物としての是非を問うのか?」
前を見据え、直向きにただ懸命に生きている生命に、生き物として正しいか否かを問う必要があるのか。すでに輝く生命を前に、その輝きは真っ当であるのかと問うのか。
言葉にならない声を上げ、緋桐の嗚咽が激しくなる。華奢な体は痙攣するように震え、見ているだけでも痛々しい。
「連理さん」
戒めは一言で足りた。連理は多少ばつが悪そうに両手を上げ、雛菊はそれを一睨みした後桂樹を隣の仮眠室へと促した。緋桐を抱き上げ、そっと簡易な寝台に乗せる。頭を撫でて、とめどなく流れる涙を拭う。しかし、嗚咽を漏らす緋桐の涙が止まることはなかった。
「緋桐は私が見てますから、桂樹は連理さんと話してください。お互いまだ話は終わっていないでしょう?」
0
この作品の感想を投稿する
あなたにおすすめの小説

林檎を並べても、
ロウバイ
BL
―――彼は思い出さない。
二人で過ごした日々を忘れてしまった攻めと、そんな彼の行く先を見守る受けです。
ソウが目を覚ますと、そこは消毒の香りが充満した病室だった。自分の記憶を辿ろうとして、はたり。その手がかりとなる記憶がまったくないことに気付く。そんな時、林檎を片手にカーテンを引いてとある人物が入ってきた。
彼―――トキと名乗るその黒髪の男は、ソウが事故で記憶喪失になったことと、自身がソウの親友であると告げるが…。

狼の護衛騎士は、今日も心配が尽きない
結衣可
BL
戦の傷跡が癒えた共生都市ルーヴェン。
人族と獣人族が共に暮らすその街で、文官ユリス・アルヴィンは、穏やかな日々の中に、いつも自分を見守る“優しい視線”の存在を感じていた。
その正体は、狼族の戦士長出身の護衛騎士、ガルド・ルヴァーン。
無口で不器用だが、誠実で優しい彼は、いつしかユリスを守ることが日課になっていた。
モフモフ好きなユリスと、心配性すぎるガルド。
灰銀の狼と金灰の文官――
異種族の二人の関係がルーヴェンの風のようにやさしく、日々の中で少しずつ変わっていく。
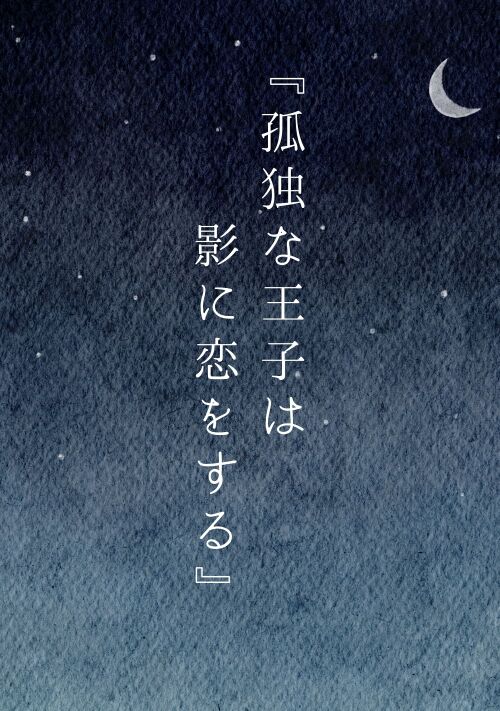
孤独な王子は影に恋をする
結衣可
BL
王国の第一王子リオネル・ヴァルハイトは、
「光」と称えられるほど完璧な存在だった。
民からも廷臣からも賞賛され、非の打ち所がない理想の王子。
しかしその仮面の裏には、孤独と重圧に押し潰されそうな本音が隠されていた。
弱音を吐きたい。誰かに甘えたい。
だが、その願いを叶えてくれる相手はいない。
――ただ一人、いつも傍に気配を寄せていた“影”に恋をするまでは。
影、王族直属の密偵として顔も名も隠し、感情を持たぬよう育てられた存在。
常に平等であれと叩き込まれ、ただ「王子を守る影」として仕えてきた。
完璧を求められる王子と、感情を禁じられてきた影。
光と影が惹かれ合い、やがて互いの鎖を断ち切ってゆく。

白花の檻(はっかのおり)
AzureHaru
BL
その世界には、生まれながらに祝福を受けた者がいる。その祝福は人ならざるほどの美貌を与えられる。
その祝福によって、交わるはずのなかった2人の運命が交わり狂っていく。
この出会いは祝福か、或いは呪いか。
受け――リュシアン。
祝福を授かりながらも、決して傲慢ではなく、いつも穏やかに笑っている青年。
柔らかな白銀の髪、淡い光を湛えた瞳。人々が息を呑むほどの美しさを持つ。
攻め――アーヴィス。
リュシアンと同じく祝福を授かる。リュシアン以上に人の域を逸脱した容姿。
黒曜石のような瞳、彫刻のように整った顔立ち。
王国に名を轟かせる貴族であり、数々の功績を誇る英雄。

happy dead end
瑞原唯子
BL
「それでも俺に一生を捧げる覚悟はあるか?」
シルヴィオは幼いころに第一王子の遊び相手として抜擢され、初めて会ったときから彼の美しさに心を奪われた。そして彼もシルヴィオだけに心を開いていた。しかし中等部に上がると、彼はとある女子生徒に興味を示すようになり——。

禁書庫の管理人は次期宰相様のお気に入り
結衣可
BL
オルフェリス王国の王立図書館で、禁書庫を預かる司書カミル・ローレンは、過去の傷を抱え、静かな孤独の中で生きていた。
そこへ次期宰相と目される若き貴族、セドリック・ヴァレンティスが訪れ、知識を求める名目で彼のもとに通い始める。
冷静で無表情なカミルに興味を惹かれたセドリックは、やがて彼の心の奥にある痛みに気づいていく。
愛されることへの恐れに縛られていたカミルは、彼の真っ直ぐな想いに少しずつ心を開き、初めて“痛みではない愛”を知る。
禁書庫という静寂の中で、カミルの孤独を、過去を癒し、共に歩む未来を誓う。

雪を溶かすように
春野ひつじ
BL
人間と獣人の争いが終わった。
和平の条件で人間の国へ人質としていった獣人国の第八王子、薫(ゆき)。そして、薫を助けた人間国の第一王子、悠(はる)。二人の距離は次第に近づいていくが、実は薫が人間国に行くことになったのには理由があった……。
溺愛・甘々です。
*物語の進み方がゆっくりです。エブリスタにも掲載しています

龍の寵愛を受けし者達
樹木緑
BL
サンクホルム国の王子のジェイドは、
父王の護衛騎士であるダリルに憧れていたけど、
ある日偶然に自分の護衛にと推す父王に反する声を聞いてしまう。
それ以来ずっと嫌われていると思っていた王子だったが少しずつ打ち解けて
いつかはそれが愛に変わっていることに気付いた。
それと同時に何故父王が最強の自身の護衛を自分につけたのか理解す時が来る。
王家はある者に裏切りにより、
無惨にもその策に敗れてしまう。
剣が苦手でずっと魔法の研究をしていた王子は、
責めて騎士だけは助けようと、
刃にかかる寸前の所でとうの昔に失ったとされる
時戻しの術をかけるが…
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















