あなたにおすすめの小説

10年引きこもりの私が外に出たら、御曹司の妻になりました
専業プウタ
恋愛
25歳の桜田未来は中学生から10年以上引きこもりだったが、2人暮らしの母親の死により外に出なくてはならなくなる。城ヶ崎冬馬は女遊びの激しい大手アパレルブランドの副社長。彼をストーカーから身を張って助けた事で未来は一時的に記憶喪失に陥る。冬馬はちょっとした興味から、未来は自分の恋人だったと偽る。冬馬は未来の純粋さと直向きさに惹かれていき、嘘が明らかになる日を恐れながらも未来の為に自分を変えていく。そして、未来は恐れもなくし、愛する人の胸に飛び込み夢を叶える扉を自ら開くのだった。

【完結済】25億で極道に売られた女。姐になります!
satomi
恋愛
昼夜問わずに働く18才の主人公南ユキ。
働けども働けどもその収入は両親に搾取されるだけ…。睡眠時間だって2時間程度しかないのに、それでもまだ働き口を増やせと言う両親。
早朝のバイトで頭は朦朧としていたけれど、そんな時にうちにやってきたのは白虎商事CEOの白川大雄さん。ポーンっと25億で私を買っていった。
そんな大雄さん、白虎商事のCEOとは別に白虎組組長の顔を持っていて、私に『姐』になれとのこと。
大丈夫なのかなぁ?

エリート役員は空飛ぶ天使を溺愛したくてたまらない
如月 そら
恋愛
「二度目は偶然だが、三度目は必然だ。三度目がないことを願っているよ」
(三度目はないからっ!)
──そう心で叫んだはずなのに目の前のエリート役員から逃げられない!
「俺と君が出会ったのはつまり必然だ」
倉木莉桜(くらきりお)は大手エアラインで日々奮闘する客室乗務員だ。
ある日、自社の機体を製造している五十里重工の重役がトラブルから莉桜を救ってくれる。
それで彼との関係は終わったと思っていたのに!?
エリート役員からの溺れそうな溺愛に戸惑うばかり。
客室乗務員(CA)倉木莉桜
×
五十里重工(取締役部長)五十里武尊
『空が好き』という共通点を持つ二人の恋の行方は……

イケメン警視、アルバイトで雇った恋人役を溺愛する。
楠ノ木雫
恋愛
蒸発した母の借金を擦り付けられた主人公瑠奈は、お見合い代行のアルバイトを受けた。だが、そのお見合い相手、矢野湊に借金の事を見破られ3ヶ月間恋人役を務めるアルバイトを提案された。瑠奈はその報酬に飛びついたが……

ある日、憧れブランドの社長が溺愛求婚してきました
蓮恭
恋愛
恋人に裏切られ、傷心のヒロイン杏子は勤め先の美容室を去り、人気の老舗美容室に転職する。
そこで真面目に培ってきた技術を買われ、憧れのヘアケアブランドの社長である統一郎の自宅を訪問して施術をする事に……。
しかも統一郎からどうしてもと頼まれたのは、その後の杏子の人生を大きく変えてしまうような事で……⁉︎
杏子は過去の臆病な自分と決別し、統一郎との新しい一歩を踏み出せるのか?
【サクサク読める現代物溺愛系恋愛ストーリーです】

【完結】俺様御曹司の隠された溺愛野望 〜花嫁は蜜愛から逃れられない〜
椿かもめ
恋愛
「こはる、俺の妻になれ」その日、大女優を母に持つ2世女優の花宮こはるは自分の所属していた劇団の解散に絶望していた。そんなこはるに救いの手を差し伸べたのは年上の幼馴染で大企業の御曹司、月ノ島玲二だった。けれど代わりに妻になることを強要してきて──。花嫁となったこはるに対し、俺様な玲二は独占欲を露わにし始める。
【幼馴染の俺様御曹司×大物女優を母に持つ2世女優】
☆☆☆ベリーズカフェで日間4位いただきました☆☆☆
※ベリーズカフェでも掲載中
※推敲、校正前のものです。ご注意下さい
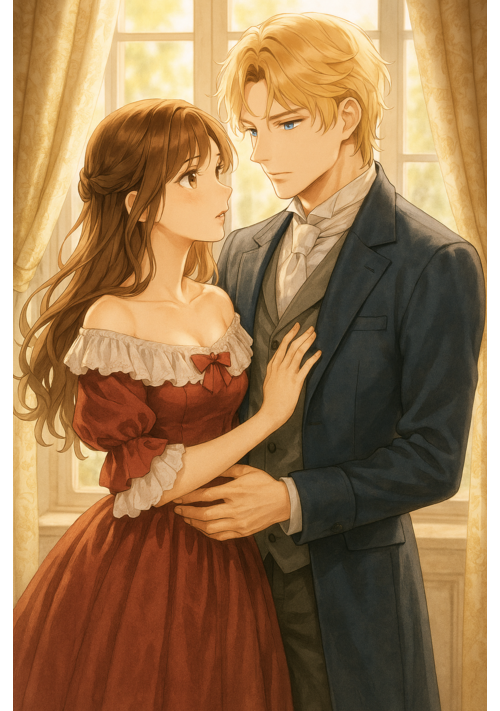
《完結》追放令嬢は氷の将軍に嫁ぐ ―25年の呪いを掘り当てた私―
月輝晃
恋愛
25年前、王国の空を覆った“黒い光”。
その日を境に、豊かな鉱脈は枯れ、
人々は「25年ごとに国が凍る」という不吉な伝承を語り継ぐようになった。
そして、今――再びその年が巡ってきた。
王太子の陰謀により、「呪われた鉱石を研究した罪」で断罪された公爵令嬢リゼル。
彼女は追放され、氷原にある北の砦へと送られる。
そこで出会ったのは、感情を失った“氷の将軍”セドリック。
無愛想な将軍、凍てつく土地、崩れゆく国。
けれど、リゼルの手で再び輝きを取り戻した一つの鉱石が、
25年続いた絶望の輪を、少しずつ断ち切っていく。
それは――愛と希望をも掘り当てる、運命の物語。

あなたがいなくなった後 〜シングルマザーになった途端、義弟から愛され始めました〜
瀬崎由美
恋愛
石橋優香は夫大輝との子供を出産したばかりの二十七歳の専業主婦。三歳歳上の大輝とは大学時代のサークルの先輩後輩で、卒業後に再会したのがキッカケで付き合い始めて結婚した。
まだ生後一か月の息子を手探りで育てて、寝不足の日々。朝、いつもと同じように仕事へと送り出した夫は職場での事故で帰らぬ人となる。乳児を抱えシングルマザーとなってしまった優香のことを支えてくれたのは、夫の弟である宏樹だった。二歳年上で公認会計士である宏樹は優香に変わって葬儀やその他を取り仕切ってくれ、事あるごとに家の様子を見にきて、二人のことを気に掛けてくれていた。
息子の為にと自立を考えた優香は、働きに出ることを考える。それを知った宏樹は自分の経営する会計事務所に勤めることを勧めてくれる。陽太が保育園に入れることができる月齢になって義弟のオフィスで働き始めてしばらく、宏樹の不在時に彼の元カノだと名乗る女性が訪れて来、宏樹へと復縁を迫ってくる。宏樹から断られて逆切れした元カノによって、彼が優香のことをずっと想い続けていたことを暴露されてしまう。
あっさりと認めた宏樹は、「今は兄貴の代役でもいい」そういって、優香の傍にいたいと願った。
夫とは真逆のタイプの宏樹だったが、優しく支えてくれるところは同じで……
夫のことを想い続けるも、義弟のことも完全には拒絶することができない優香。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















