15 / 100
第15話:メイド長の心変わり
しおりを挟む
『癒やしの時間』を終え、私は心地よい疲労感と共にサンルームを後にした。繋いでいた手から伝わるアシュレイ様の温もりが、まだ自分の手のひらに残っているような気がして、胸の奥がじんわりと温かい。
扉の外では、いつものようにメイド長のマーサが静かに控えていた。
「お疲れ様でございました。リナリア様」
彼女はそう言うと、いつも通り深々とお辞儀をした。けれど、今日の彼女の様子は、どこかいつもと違うように感じられた。硬質的だった声の響きが、ほんの少しだけ柔らかい。私を見つめるその瞳から、以前のような鋭さが消えている。
「ありがとうございます、マーサさん」
私が微笑み返すと、彼女は少しだけ逡巡するような素振りを見せた後、口を開いた。
「リナリア様。もし、お疲れでなければ、少しだけお付き合いいただきたい場所がございます」
「場所、ですか?」
てっきり自室へ案内されるものだと思っていた私は、少し驚いて聞き返した。
「はい。アシュレイ様には、リナリア様は少し休憩なさるとお伝えしております」
その言葉は、アシュレイ様には内緒だというニュアンスを含んでいた。私は興味を惹かれ、こくりと頷いた。
「はい。喜んで」
マーサは私の返事を聞くと、わずかに口元を綻ばせた。彼女が笑ったのを、私は初めて見たかもしれない。それは、とても優しくて、温かい微笑みだった。
彼女に導かれて歩き出した先は、客間や広間のある賓客用のエリアではなかった。磨き上げられた大理石の廊下から、温かみのある木の床の廊下へと変わる。ここは、使用人たちが日常的に使うための生活区域なのだろう。
やがて私たちが辿り着いたのは、屋敷の厨房の隣にある、小さな部屋だった。中からは、甘くて香ばしい匂いが漂ってくる。
「ここは?」
「メイドたちの休憩室でございます。どうぞ」
部屋の中は、華美な装飾こそないが、清潔でとても居心地が良さそうだった。中央には大きな木のテーブルが置かれ、壁際には使い込まれた様子のソファが並んでいる。
マーサは私をテーブルの席に座らせると、手際よく戸棚からティーカップと小皿を取り出した。そして、オーブンから取り出したばかりであろう、まだ温かい焼き菓子を皿に乗せ、私の前にそっと置いてくれる。こんがりと焼き色のついた、素朴なバタークッキーだった。
「まあ……! 美味しそう」
甘い香りに、思わず顔が綻ぶ。
「お口に合うか分かりませんが」
そう言って、彼女は私のカップに琥珀色のカモミールティーを注いでくれた。
メイド長自らが、私のためにお茶を淹れてくれている。その事実に、私は恐縮すると同時に、彼女の心遣いをとても嬉しく感じた。
私はクッキーを一つ手に取り、おずおずと口に運んだ。サクッとした食感の後、バターの豊かな風味と優しい甘さが口いっぱいに広がる。
「美味しいです! とても!」
私が素直な感想を伝えると、マーサは心底ほっとしたように息をついた。
「……良かった」
しばらくの間、私たちは静かにお茶を飲んだ。窓から差し込む午後の光が、部屋の中を穏やかに照らしている。
やがて、マーサが静かな口調で語り始めた。
「リナリア様がこのお屋敷にいらしてから、アシュレイ様は変わられました」
その声は、どこか遠い昔を懐かしむような響きを持っていた。
「呪いをお受けになられてから、あの方はご自分の殻に閉じこもるようになられました。心を凍らせる呪いは、その名の通り、あの方から感情だけでなく、人としての温もりさえも奪っていったのです」
私は黙って、彼女の言葉に耳を傾けた。
「私は、幼い頃のアシュレイ様を知っております。先代の公爵夫人様……あの方のお母様は、とてもお優しく、慈愛に満ちた方でした。アシュレイ様も、昔はよく笑う、心優しい少年でいらっしゃった」
マーサの瞳が、切なげに揺れる。彼女は、アシュレイ様にとって乳母のような存在だったのかもしれない。
「ですが、お母様を病で亡くされ、その後すぐに戦場へ赴き、呪いを受けてお帰りになった。それからのあの方は、まるで氷の鎧を纏っているかのようでした。誰にも心を開かず、ただ一人で、暗い闇の中を歩いておられるようでした」
その言葉から、彼女がどれほどアシュレイ様のことを案じ、心を痛めてきたかが痛いほど伝わってきた。
「夜中に、苦悶の声で目を覚まされることも少なくありませんでした。私には、ただお傍に控えていることしかできず……自分の無力さを、何度も呪いました」
彼女はそこで一度言葉を切り、カップの中の紅茶を見つめた。
「ですが、リナリア様。あなた様がいらしてから、全てが変わりました」
マーサは顔を上げ、私をまっすぐに見つめた。その瞳には、深い感謝の色が浮かんでいた。
「アシュレイ様は、夜中に苦しむことがなくなりました。穏やかに朝をお迎えになる。執務中の難しい顔も和らぎ、我々使用人に対するお言葉も、以前とは比べものにならないほどお優しくなりました。……そして何より」
彼女は、ふっと微笑んだ。
「あなた様と過ごされている時のあの方は、まるで、呪いを受ける前の、あの頃の少年に戻ったかのようです。あのような心からの笑顔を、私はもう何年も見ておりませんでした」
その言葉に、私の胸の奥がじんわりと熱くなる。
アシュレイ様は、少しずつ、本来の自分を取り戻し始めている。そして、その変化を、彼のことを誰よりも大切に思っているこの人が、こんなにも喜んでくれている。
「私が、アシュレイ様のお力になれているのなら……こんなに嬉しいことはありません」
私も、素直な気持ちを口にした。
「私は、今までずっと、自分は何の役にも立たない出来損ないだと思って生きてきました。でも、アシュレイ様は私を必要としてくださった。私の力に、意味を与えてくださいました。だから、私は……あの方の呪いを癒して、いつか、本当の笑顔を取り戻していただきたいんです」
私の決意を聞いて、マーサはゆっくりと席を立った。
そして、私の前に来ると、何のためらいもなく、その場に深く膝を折った。
「マーサさん!?」
私は驚いて立ち上がろうとするが、彼女はそれを静かに手で制した。
「リナリア様。先日、私はあなた様に申し上げました。『もし、あなたがアシュレイ様の御心を癒す存在であるのならば、生涯の主としてお仕えしましょう』と」
彼女は顔を上げ、澄んだ瞳で私を見据えた。
「その言葉に、偽りはございません。このマーサ、今日この時より、あなた様を我が主と認め、生涯をかけてお仕えする覚悟でございます」
その声は、騎士の誓いのように、厳かで、力強かった。
「どうか、これからはこのマー-サを、あなたの手足と心得て、何なりとお申し付けください。そして……」
彼女は、深々と頭を下げた。
「私どもの大切な主君、アシュレイ様のことを、どうか、よろしくお願い申し上げます」
その姿に、私は胸がいっぱいになった。
彼女は私を、アシュレイ様のパートナーとして、未来の公爵夫人として、完全に認めてくれたのだ。
「……はい」
私は涙声になるのを必死でこらえ、はっきりと頷いた。
「こちらこそ、よろしくお願いいたします、マーサさん」
この瞬間、私は公爵邸で、初めて心からの味方を得た。
それは、アシュレイ様から与えられる庇護とはまた違う、温かくて心強い繋がりだった。この屋敷が、もうただの仮の住まいではない。私の本当の『居場所』になったのだと、確信できた。
マーサという強力な味方を得て、私の心は、また一つ強く、前を向くことができたのだった。
扉の外では、いつものようにメイド長のマーサが静かに控えていた。
「お疲れ様でございました。リナリア様」
彼女はそう言うと、いつも通り深々とお辞儀をした。けれど、今日の彼女の様子は、どこかいつもと違うように感じられた。硬質的だった声の響きが、ほんの少しだけ柔らかい。私を見つめるその瞳から、以前のような鋭さが消えている。
「ありがとうございます、マーサさん」
私が微笑み返すと、彼女は少しだけ逡巡するような素振りを見せた後、口を開いた。
「リナリア様。もし、お疲れでなければ、少しだけお付き合いいただきたい場所がございます」
「場所、ですか?」
てっきり自室へ案内されるものだと思っていた私は、少し驚いて聞き返した。
「はい。アシュレイ様には、リナリア様は少し休憩なさるとお伝えしております」
その言葉は、アシュレイ様には内緒だというニュアンスを含んでいた。私は興味を惹かれ、こくりと頷いた。
「はい。喜んで」
マーサは私の返事を聞くと、わずかに口元を綻ばせた。彼女が笑ったのを、私は初めて見たかもしれない。それは、とても優しくて、温かい微笑みだった。
彼女に導かれて歩き出した先は、客間や広間のある賓客用のエリアではなかった。磨き上げられた大理石の廊下から、温かみのある木の床の廊下へと変わる。ここは、使用人たちが日常的に使うための生活区域なのだろう。
やがて私たちが辿り着いたのは、屋敷の厨房の隣にある、小さな部屋だった。中からは、甘くて香ばしい匂いが漂ってくる。
「ここは?」
「メイドたちの休憩室でございます。どうぞ」
部屋の中は、華美な装飾こそないが、清潔でとても居心地が良さそうだった。中央には大きな木のテーブルが置かれ、壁際には使い込まれた様子のソファが並んでいる。
マーサは私をテーブルの席に座らせると、手際よく戸棚からティーカップと小皿を取り出した。そして、オーブンから取り出したばかりであろう、まだ温かい焼き菓子を皿に乗せ、私の前にそっと置いてくれる。こんがりと焼き色のついた、素朴なバタークッキーだった。
「まあ……! 美味しそう」
甘い香りに、思わず顔が綻ぶ。
「お口に合うか分かりませんが」
そう言って、彼女は私のカップに琥珀色のカモミールティーを注いでくれた。
メイド長自らが、私のためにお茶を淹れてくれている。その事実に、私は恐縮すると同時に、彼女の心遣いをとても嬉しく感じた。
私はクッキーを一つ手に取り、おずおずと口に運んだ。サクッとした食感の後、バターの豊かな風味と優しい甘さが口いっぱいに広がる。
「美味しいです! とても!」
私が素直な感想を伝えると、マーサは心底ほっとしたように息をついた。
「……良かった」
しばらくの間、私たちは静かにお茶を飲んだ。窓から差し込む午後の光が、部屋の中を穏やかに照らしている。
やがて、マーサが静かな口調で語り始めた。
「リナリア様がこのお屋敷にいらしてから、アシュレイ様は変わられました」
その声は、どこか遠い昔を懐かしむような響きを持っていた。
「呪いをお受けになられてから、あの方はご自分の殻に閉じこもるようになられました。心を凍らせる呪いは、その名の通り、あの方から感情だけでなく、人としての温もりさえも奪っていったのです」
私は黙って、彼女の言葉に耳を傾けた。
「私は、幼い頃のアシュレイ様を知っております。先代の公爵夫人様……あの方のお母様は、とてもお優しく、慈愛に満ちた方でした。アシュレイ様も、昔はよく笑う、心優しい少年でいらっしゃった」
マーサの瞳が、切なげに揺れる。彼女は、アシュレイ様にとって乳母のような存在だったのかもしれない。
「ですが、お母様を病で亡くされ、その後すぐに戦場へ赴き、呪いを受けてお帰りになった。それからのあの方は、まるで氷の鎧を纏っているかのようでした。誰にも心を開かず、ただ一人で、暗い闇の中を歩いておられるようでした」
その言葉から、彼女がどれほどアシュレイ様のことを案じ、心を痛めてきたかが痛いほど伝わってきた。
「夜中に、苦悶の声で目を覚まされることも少なくありませんでした。私には、ただお傍に控えていることしかできず……自分の無力さを、何度も呪いました」
彼女はそこで一度言葉を切り、カップの中の紅茶を見つめた。
「ですが、リナリア様。あなた様がいらしてから、全てが変わりました」
マーサは顔を上げ、私をまっすぐに見つめた。その瞳には、深い感謝の色が浮かんでいた。
「アシュレイ様は、夜中に苦しむことがなくなりました。穏やかに朝をお迎えになる。執務中の難しい顔も和らぎ、我々使用人に対するお言葉も、以前とは比べものにならないほどお優しくなりました。……そして何より」
彼女は、ふっと微笑んだ。
「あなた様と過ごされている時のあの方は、まるで、呪いを受ける前の、あの頃の少年に戻ったかのようです。あのような心からの笑顔を、私はもう何年も見ておりませんでした」
その言葉に、私の胸の奥がじんわりと熱くなる。
アシュレイ様は、少しずつ、本来の自分を取り戻し始めている。そして、その変化を、彼のことを誰よりも大切に思っているこの人が、こんなにも喜んでくれている。
「私が、アシュレイ様のお力になれているのなら……こんなに嬉しいことはありません」
私も、素直な気持ちを口にした。
「私は、今までずっと、自分は何の役にも立たない出来損ないだと思って生きてきました。でも、アシュレイ様は私を必要としてくださった。私の力に、意味を与えてくださいました。だから、私は……あの方の呪いを癒して、いつか、本当の笑顔を取り戻していただきたいんです」
私の決意を聞いて、マーサはゆっくりと席を立った。
そして、私の前に来ると、何のためらいもなく、その場に深く膝を折った。
「マーサさん!?」
私は驚いて立ち上がろうとするが、彼女はそれを静かに手で制した。
「リナリア様。先日、私はあなた様に申し上げました。『もし、あなたがアシュレイ様の御心を癒す存在であるのならば、生涯の主としてお仕えしましょう』と」
彼女は顔を上げ、澄んだ瞳で私を見据えた。
「その言葉に、偽りはございません。このマーサ、今日この時より、あなた様を我が主と認め、生涯をかけてお仕えする覚悟でございます」
その声は、騎士の誓いのように、厳かで、力強かった。
「どうか、これからはこのマー-サを、あなたの手足と心得て、何なりとお申し付けください。そして……」
彼女は、深々と頭を下げた。
「私どもの大切な主君、アシュレイ様のことを、どうか、よろしくお願い申し上げます」
その姿に、私は胸がいっぱいになった。
彼女は私を、アシュレイ様のパートナーとして、未来の公爵夫人として、完全に認めてくれたのだ。
「……はい」
私は涙声になるのを必死でこらえ、はっきりと頷いた。
「こちらこそ、よろしくお願いいたします、マーサさん」
この瞬間、私は公爵邸で、初めて心からの味方を得た。
それは、アシュレイ様から与えられる庇護とはまた違う、温かくて心強い繋がりだった。この屋敷が、もうただの仮の住まいではない。私の本当の『居場所』になったのだと、確信できた。
マーサという強力な味方を得て、私の心は、また一つ強く、前を向くことができたのだった。
59
あなたにおすすめの小説

追放された公爵令息、神竜と共に辺境スローライフを満喫する〜無敵領主のまったり改革記〜
たまごころ
ファンタジー
無実の罪で辺境に追放された公爵令息アレン。
だが、その地では神竜アルディネアが眠っていた。
契約によって最強の力を得た彼は、戦いよりも「穏やかな暮らし」を選ぶ。
農地改革、温泉開発、魔導具づくり──次々と繁栄する辺境領。
そして、かつて彼を貶めた貴族たちが、その繁栄にひれ伏す時が来る。
戦わずとも勝つ、まったりざまぁ無双ファンタジー!

【完結】家族に愛されなかった辺境伯の娘は、敵国の堅物公爵閣下に攫われ真実の愛を知る
水月音子
恋愛
辺境を守るティフマ城の城主の娘であるマリアーナは、戦の代償として隣国の敵将アルベルトにその身を差し出した。
婚約者である第四王子と、父親である城主が犯した国境侵犯という罪を、自分の命でもって償うためだ。
だが――
「マリアーナ嬢を我が国に迎え入れ、現国王の甥である私、アルベルト・ルーベンソンの妻とする」
そう宣言されてマリアーナは隣国へと攫われる。
しかし、ルーベンソン公爵邸にて差し出された婚約契約書にある一文に疑念を覚える。
『婚約期間中あるいは婚姻後、子をもうけた場合、性別を問わず健康な子であれば、婚約もしくは結婚の継続の自由を委ねる』
さらには家庭教師から“精霊姫”の話を聞き、アルベルトの側近であるフランからも詳細を聞き出すと、自分の置かれた状況を理解する。
かつて自国が攫った“精霊姫”の血を継ぐマリアーナ。
そのマリアーナが子供を産めば、自分はもうこの国にとって必要ない存在のだ、と。
そうであれば、早く子を産んで身を引こう――。
そんなマリアーナの思いに気づかないアルベルトは、「婚約中に子を産み、自国へ戻りたい。結婚して公爵様の経歴に傷をつける必要はない」との彼女の言葉に激昂する。
アルベルトはアルベルトで、マリアーナの知らないところで実はずっと昔から、彼女を妻にすると決めていた。
ふたりは互いの立場からすれ違いつつも、少しずつ心を通わせていく。
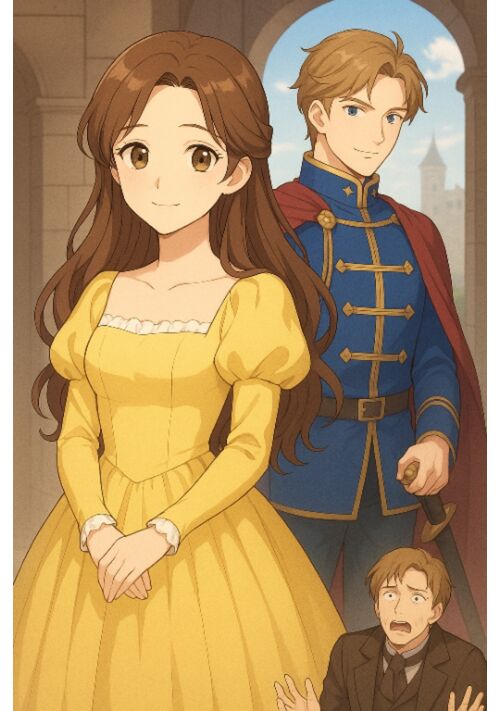
地味令嬢の私ですが、王太子に見初められたので、元婚約者様からの復縁はお断りします
有賀冬馬
恋愛
子爵令嬢の私は、いつだって日陰者。
唯一の光だった公爵子息ヴィルヘルム様の婚約者という立場も、あっけなく捨てられた。「君のようなつまらない娘は、公爵家の妻にふさわしくない」と。
もう二度と恋なんてしない。
そう思っていた私の前に現れたのは、傷を負った一人の青年。
彼を献身的に看病したことから、私の運命は大きく動き出す。
彼は、この国の王太子だったのだ。
「君の優しさに心を奪われた。君を私だけのものにしたい」と、彼は私を強く守ると誓ってくれた。
一方、私を捨てた元婚約者は、新しい婚約者に振り回され、全てを失う。
私に助けを求めてきた彼に、私は……

『婚約破棄された聖女リリアナの庭には、ちょっと変わった来訪者しか来ません。』
夢窓(ゆめまど)
恋愛
王都から少し離れた小高い丘の上。
そこには、聖女リリアナの庭と呼ばれる不思議な場所がある。
──けれど、誰もがたどり着けるわけではない。
恋するルミナ五歳、夢みるルーナ三歳。
ふたりはリリアナの庭で、今日もやさしい魔法を育てています。
この庭に来られるのは、心がちょっぴりさびしい人だけ。
まほうに傷ついた王子さま、眠ることでしか気持ちを伝えられない子、
そして──ほんとうは泣きたかった小さな精霊たち。
お姉ちゃんのルミナは、花を咲かせる明るい音楽のまほうつかい。
ちょっとだけ背伸びして、だいすきな人に恋をしています。
妹のルーナは、ねむねむ魔法で、夢の中を旅するやさしい子。
ときどき、だれかの心のなかで、静かに花を咲かせます。
ふたりのまほうは、まだ小さくて、でもあたたかい。
「だいすきって気持ちは、
きっと一番すてきなまほうなの──!」
風がふくたびに、花がひらき、恋がそっと実る。
これは、リリアナの庭で育つ、
小さなまほうつかいたちの恋と夢の物語です。

精霊の森に追放された私ですが、森の主【巨大モフモフ熊の精霊王】に気に入られました
腐ったバナナ
恋愛
王都で「魔力欠損の無能者」と蔑まれ、元婚約者と妹の裏切りにより、魔物が出る精霊の森に追放された伯爵令嬢リサ。絶望の中、極寒の森で命を落としかけたリサを救ったのは、人間を食らうと恐れられる森の主、巨大なモフモフの熊だった。
実はその熊こそ、冷酷な精霊王バルト。長年の孤独と魔力の淀みで冷え切っていた彼は、リサの体から放たれる特殊な「癒やしの匂い」と微かな温もりに依存し、リサを「最高のストーブ兼抱き枕」として溺愛し始める。

銀狼の花嫁~動物の言葉がわかる獣医ですが、追放先の森で銀狼さんを介抱したら森の聖女と呼ばれるようになりました~
川上とむ
恋愛
森に囲まれた村で獣医として働くコルネリアは動物の言葉がわかる一方、その能力を気味悪がられていた。
そんなある日、コルネリアは村の習わしによって森の主である銀狼の花嫁に選ばれてしまう。
それは村からの追放を意味しており、彼女は絶望する。
村に助けてくれる者はおらず、銀狼の元へと送り込まれてしまう。
ところが出会った銀狼は怪我をしており、それを見たコルネリアは彼の傷の手当をする。
すると銀狼は彼女に一目惚れしたらしく、その場で結婚を申し込んでくる。
村に戻ることもできないコルネリアはそれを承諾。晴れて本当の銀狼の花嫁となる。
そのまま森で暮らすことになった彼女だが、動物と会話ができるという能力を活かし、第二の人生を謳歌していく。

【悲報】氷の悪女と蔑まれた辺境令嬢のわたくし、冷徹公爵様に何故かロックオンされました!?~今さら溺愛されても困ります……って、あれ?
放浪人
恋愛
「氷の悪女」――かつて社交界でそう蔑まれ、身に覚えのない罪で北の辺境に追いやられた令嬢エレオノーラ・フォン・ヴァインベルク。凍えるような孤独と絶望に三年間耐え忍んできた彼女の前に、ある日突然現れたのは、帝国一冷徹と名高いアレクシス・フォン・シュヴァルツェンベルク公爵だった。
彼の目的は、荒廃したヴァインベルク領の視察。エレオノーラは、公爵の鋭く冷たい視線と不可解なまでの執拗な関わりに、「新たな不幸の始まりか」と身を硬くする。しかし、領地再建のために共に過ごすうち、彼の不器用な優しさや、時折見せる温かい眼差しに、エレオノーラの凍てついた心は少しずつ溶かされていく。
「お前は、誰よりも強く、優しい心を持っている」――彼の言葉は、偽りの悪評に傷ついてきたエレオノーラにとって、戸惑いと共に、かつてない温もりをもたらすものだった。「迷惑千万!」と思っていたはずの公爵の存在が、いつしか「心地よいかも…」と感じられるように。
過去のトラウマ、卑劣な罠、そして立ちはだかる身分と悪評の壁。数々の困難に見舞われながらも、アレクシス公爵の揺るぎない庇護と真っ直ぐな愛情に支えられ、エレオノーラは真の自分を取り戻し、やがて二人は互いにとってかけがえのない存在となっていく。
これは、不遇な辺境令嬢が、冷徹公爵の不器用でひたむきな「ロックオン(溺愛)」によって心の氷を溶かし、真実の愛と幸福を掴む、ちょっぴりじれったくて、とびきり甘い逆転ラブストーリー。

冷遇された公爵令嬢は、敵国最恐の「氷の軍神」に契約で嫁ぎました。偽りの結婚のはずが、なぜか彼に溺愛され、実家が没落するまで寵愛されています
メルファン
恋愛
侯爵令嬢エリアーナは、幼い頃から妹の才能を引き立てるための『地味な引き立て役』として冷遇されてきました。その冷遇は、妹が「光の魔力」を開花させたことでさらに加速し、ついに長年の婚約者である王太子からも、一方的な婚約破棄を告げられます。
「お前のような華のない女は、王妃にふさわしくない」
失意のエリアーナに与えられた次の役割は、敵国アースガルドとの『政略結婚の駒』。嫁ぎ先は、わずか五年で辺境の魔物を制圧した、冷酷非情な英雄「氷の軍神」こと、カイン・フォン・ヴィンター公爵でした。
カイン公爵は、王家を軽蔑し、感情を持たない冷徹な仮面を被った、恐ろしい男だと噂されています。エリアーナは、これは五年間の「偽りの契約結婚」であり、役目を終えれば解放されると、諦めにも似た覚悟を決めていました。
しかし、嫁いだ敵国で待っていたのは、想像とは全く違う生活でした。
「華がない」と蔑まれたエリアーナに、公爵はアースガルドの最高の仕立て屋を呼び、豪華なドレスと宝石を惜しみなく贈呈。
「不要な引き立て役」だったエリアーナを、公爵は公の場で「我が愛する妻」と呼び、侮辱する者を許しません。
冷酷非情だと噂された公爵は、夜、エリアーナを優しく抱きしめ、彼女が眠るまで離れない、極度の愛妻家へと変貌します。
実はカイン公爵は、エリアーナが幼い頃に偶然助けた命の恩人であり、長年、彼女を密かに想い続けていたのです。彼は、エリアーナを冷遇した実家への復讐の炎を胸に秘め、彼女を愛と寵愛で包み込みます。
一方、エリアーナを価値がないと捨てた実家や王太子は、彼女が敵国で女王のような寵愛を受けていることを知り、慌てて連れ戻そうと画策しますが、時すでに遅し。
「我が妻に手を出す者は、国一つ滅ぼす覚悟を持て」
これは、冷遇された花嫁が、敵国の最恐公爵に深く愛され、真の価値を取り戻し、実家と王都に「ざまぁ」を食らわせる、王道溺愛ファンタジーです。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















