15 / 25
第一章.死後の世界へ
§2.故郷は駆け足に6
しおりを挟む
太一の絶妙なカットインのおかげで、二人を取り巻いていた微妙な空気は見事に打破された。
結果的にそれが良かったのかどうかは分からないが、あれだけの滑り芸を披露されてしまって元の話題に戻れるほど両者共に経験豊富ではない。一度壊れた空気は別の話題で塗り替える。それが今の二人に出来最大限の打開策なのだ。
とはいえ、真由美は一度腹を括ったわけで、どうにも不完全燃焼感が否めない。確かに、太一の切り出した話題に乗っかってしまったのは自分自身の弱さが故で、正直ほっとしている部分も多い。
しかし、せっかく掛けてもらった言葉を有耶無耶にしてしまったのではないか。太一の気持ちが空中分解してしまうのではないか。それはそれで勿体無い気がしてならない。
という具合に、拗れた細い糸は未だ解けておらず、真由美の気持ちに妙な語弊を生み続けているのだった。
「ふはぁー、ごちそーさんっ!」
真由美の気持ちなどなどつゆ知らず、太一は元気よくデーブルに箸を置く。
現状、布団から出ることを禁じられている身ではあるが、そこは狭いワンルームの特権。部屋の中央にどかっと敷かれた布団からは、大抵の物が手を伸ばせば届く。
太一はこれを生かして、漫画を手に取り暇を潰し、剰え食事まで済ませたのだった。これぞパーフェクトヒキニートの育成法だ。
なんにせよ、死んでから真面な食事を摂ったのはこれが初めてだろうか。一応、今朝の車内で真由美から貰ったドーナツを口に通してはいるが、健康な高校男児の活発な胃がその程度で満足することはない。やはり米とおかずを交互に食してこその食事だ。
「はい、お粗末様です。残り物で申し訳ないです……」
「お? なんかこのやり取り新婚さんみたいじゃね?」
「しししし新婚さんっ!?」
取り乱す真由美を見て、太一はイヤらしい笑いを浮かべた。
どうも、この初心な少女を前にすると、つい煽ってやりたくなる嫌いがある。確かに暴走されると厄介なのだが、車中でなければどうとでもなる。なんせ、真由美は素直なのだから。
「それよりさ、朝も思ったんだけど、死人も腹減んのね?」
「ほえ? あ、は、はい! お腹減りますよ!」
真由美の純粋な性格を逆手に取り、話題を塗り替える太一。
素直な分、訊かれた質問にはちゃんと答える。というよりも、二つのことを同時に考えられず、無意識に疑問詞で終わった言葉を優先してしまうのが真由美という少女なのだ。
これこそ太一発案、度重なるトラブルの末に行き着いた可愛い妹の取り扱い説明書である。
語弊が無いようにいっておくが、決して太一は真由美をイジメているのではない。弄っているだけだ。
ともあれ、今しがた太一が発した質問は本心から感じたもので間違いない。食事という概念が太一に疑問を植えつけたのだ。
先刻の少女漫画談義を終えた二人が話題の塗り替えに取った行動は晩餐。無駄に浪費されていく時間を見て、真由美が提案したのだ。
夕食のとしては暫し遅い時間なのだろうが、それでも食べないという選択肢は真由美にない。今日起こったトラブルの嵐のせいで、昼食を摂れなかった。故に、真由美の腹の虫は極限状態。これ以上不毛なやり取りでストレスを溜めるくらいなら、大人しく食事にした方が利口だろう。
帰宅が遅くなった上に財布の中身は二千円。本当は近所のスーパーに食材を買いに行きたかったのだが、時間的にも金銭的にもそれは実現できない。
真由美は、泣く泣く昨日の残り物で我慢することにした。
テーブルに並んだのは白米とシンプルな肉野菜炒め。白米は昨日冷凍しておいたもの。肉野菜炒めに至っては、特売品だった豚バラ三百グラムの半分と小松菜、エリンギを醤油で炒めただけの超簡易的なメインディシュ。
これが女の子の一人暮らしの実態だ。
曲がりなりにも意中の人に振る舞う料理なのだからもっと頑張りなさいよ、と思わないこともないが、今の冷蔵庫の中身ではこれが限界。これには真由美も申し訳なさで胸を一杯にした。
当の太一はというと、そんなこと一切気にせずにバクバクと口に運ぶ。
中途半端で我儘な太一の性格からは想像できないかもしれないが、太一に好き嫌いはない。美味い不味いは関係なしに、とりあえず完食してしまう。
それもこれも母親が施したしつけの賜物であり、食事は楽しくあるべきで、残したら一緒に食べている母が楽しくなくなる、と口を酸っぱくして教えられてきた。母にべったりだった幼き日の太一はこれを鵜呑みにし、好き嫌いを一切せずに食事を楽しむ子に成長したのだ。
故に、先の疑問である。
誰よりも食事の時間を大切に考える太一にとって、死後もそれを楽しめること自体は素直に嬉しい。
だが、食事の用途とは別の話だ。
生者にとっての食事とは栄養を補給するため、自分を維持するための部分が多い。しかし、霊体にとってのはどうなのか。
「昨日もらった資料で考えると、霊体って霊泉とかいう生命エネルギーで生きてるんだよね? なら別に食わなくても生きていけるんじゃないの?」
霊体にとっての必要な栄養は、既に己の身の中に保管されている。そして、それが減ることはあれど増えることはないと記憶している。つまり、いくら物を食べても霊泉は回復しないのだ。
ならば、食事の用途とはどこにあるのか。
「えっと……極論を言えばそうなんですけど、ご飯を食べるのってそんな業務的なことじゃないですよね?」
「まぁ、俺も楽しく食えればとは思うけどさ……」
真由美のいわんとすることは理解できる。太一自身、食事は楽しくあるべきだと思っているのだから。しかし、栄養面の話が関係なくなってしまうと、この世の食材事情は激しく偏ってしまうのではないか。好きなもの、ジャンクフードばかりが食卓に並んでしまうのではないか。
浄土の食生活などまだ知る由もないが、好きな物ばかり食べて暮らすというのも頂けない。メタボ一直線なのは勘弁だ。霊体が太るかは謎だが――
「楽しく食べるっていうのも大切なことだとは思いますが、やっぱり食欲って人間の思考の大半を占めてるんだと思うんですよ」
人差し指を立てて、説明モードに入る真由美。昨日、霊体の説明にはあれだけ難色を示していたのに、今回はすんなり入ったものだ。彼女にとってこの話題は得意分野ということなのだろうか。
「人間の三大欲求にある通りで、食欲って凄く大きなものです。それこそ無視すればストレスが溜まって、霊泉が激減しちゃうくらいです」
苛々したときに暴食で憂さを晴らすという経験は誰にでもあることだろう。それは霊体も然り。むしろ、心の状態が大きく影響をもたらす霊体にこそ起こり易い、安易なストレス発散だ。
なにより、生前の認識で人は食事をする生き物だと刷り込まれている。
習慣を無視することが心にどれだけの負担を掛けるのか。それを事前に取り除くためにも、霊体こそ食事を怠ってはならないと力説する浄土の学者も多いという。
「そんな固く考えなくていいと思いますよ。食事が楽しいから、単に好きな物を食べたいから、考え方は人それぞれですが、美味しい物が待ってるって考えた方が毎日頑張れるじゃないですか?」
ごく稀に出る真由美の超絶名言をお見舞いされた太一は、自分の失態に気付く。食事は楽しくという固定概念に支配され、物事の本質を見失っていた。
確かに食事は必要なことだろう。だが、それは日々を生きる自分あってこそ。どれだけその時間を楽しくしようと意気込んでも、それは作り物に他ならない。
真面目に生きて、辛いことにも耐えて、そこでやっと辿り着く晩餐。そこにこそ本当の至福があるのではないだろうか。
日夜働く企業戦士のような意見だが、あながち間違いではなかろう。人生にはメリハリ、飴と鞭が必要なのだ。生死問わず、食事は人々の飴になってくれているのかもしれない。
「まぁ、中には全く食べなくても大丈夫な人もいるんですけどね」
「あ〝?」
せっかくいい感じで纏まり掛けていた太一の思考が、真由美の余計な一言で一気に崩れ去る。食事の必要性と人間の生活という議題で、素敵なエッセイが書ける気さえしていたのに台無しだ。
しかし、これによって太一の疑問が一つ解決する。
「イメージで空腹も制御できるってこと?」
ソファーや手紙の件を考えると、出来ないことではないと考えられる。霊体イメージ万能説だ。
そもそも太一自身、死んでからの二日間で空腹を感じた回数は今回を含めてわずか二度だけ。それも、目の前に食料がチラついた時にだけという条件に限る。突如襲った摩訶不思議体験のせいで割ける思考が無かったのは事実だが、それもイメージの塗り替えによる所業ではないか。
太一の中で考えは纏まり、ムラのあった空腹に合点がいく。
しかし、真由美からの回答は少しばかり違ったものだった。
「うーん、どちらかというと逆ですね。空腹の方がイメージに近いんですよ。生前に食べなきゃ生きてけないって認識です」
「つまり、霊体は腹減らないってこと?」
「私もその辺の構造までは詳しくないんでなんとも言えないんですが……ただ、生前の認識を取り除いてる人がいるって話は聞いたことがあります」
「そいつが飯食わないの?」
こくりと頷く真由美。なんとも曖昧ないい方だが、こんな無垢な少女の耳に入っているくらいなのだ。それなりには有名な話なのだろう。
生前の認識を取り除く。
真由美の言いを素直に信じるのなら、霊体としての新しい可能性が見えてくる。例えば、手から炎を出したり、宙に浮いたり。おおよそ生きているときには不可能だったことを現実に出来るのではないか。
男の子である太一は、自分という存在に新たな可能性を感じてしまう。
ただ一点、空腹を感じなくなるのはなにか違う気がしてしまうのも事実。人間らしい一面を失ってまで、なにか特出したスキルを身に付けたいと、太一にはどうしても思えなかった。
「どちらにしても、椎名さんが真っ当な生活をしてれば関係のない話だと思いますよ」
煮え切らない思いが顔に出ていたのか、太一を安心させるための言葉を掛ける真由美。どこか含みのあるその言葉に違和感を感じつつも、太一は深く追求しなかった。
きっと浄土で暮らしていけばいずれ分かることだろう。
「まぁ、そうね。真面目にやってたら人間らしさを失うことはないだろうし。それより、ご飯美味かったよ。せめてものお礼に洗い物は俺がやろうじゃぁないの!」
「い、いえ、大丈夫ですから、椎名さんは布団から出ないでください!」
しれーっと布団からの脱出を図ろうとするも敢え無く失敗。真由美のくせに太一の狙いを見抜くとは。
太一が真由美の扱いに慣れてきたのと同様、真由美も太一のひん曲がった性格を理解してきたということだろうか。兄として妹の成長は素直に喜ぶべきことだし、これだけガードが硬ければ悪い虫も付きにくい。
太一はそんなことを考えていたのだが、当の真由美はといえば、太一に課した制約のことなどすっかり忘れていた。ただ単に、自分の作った料理を美味かったと言ってくれたことに対しての照れ隠しであり、そんな太一に気を使わせないつもりで掛けた言葉なのだ。
全くもって純粋な女の子だこと。
料理を褒められたことに歓喜する少女。真由美のそんな一面に太一が気付くのは、まだ時間が足りないのかもしれない。
「さいですか……なら、ぼくは漫画の世界へと戻ります」
すっかりヘソを曲げてしまった太一は読書を再開するが、どうにも漫画に集中できない。作戦の失敗が尾を引いている。
(シャワー……浴びたかった)
思考に未練がましく割り込んでくる欲望。
本当は、ここでちゃっかりと制約を有耶無耶にしてシャワーを借りるつもりだったのだ。しかし、真由美から返ってきたのは否定の言葉。あの鋭い言い方を考えるに、彼女の憤怒はまだ治っていのいないのだろう。
本土の高速道路での惨めな嘔吐事件は記憶に新しい。あそこでかいた汗は太一の体をベタつかせ、吐き出した酸っぱい液体が口臭に直結している気がして、ついつい疑心暗鬼モードに陥ってしまう。
せめてうがいだけでもしたかったものだが、この場から動けない以上は叶わぬ夢だ。斯くなる上は、真由美が寝静まってからこっそりと浴びよう。
太一はそんなことを考えて、漫画本へと目線を戻す。
一言、真由美に正直な気持ちを言えば済むことなのに、あくまで自己完結で事を進めてしまうのだから救えない。所詮は女心の分からない残念な男。だからお友達止まりなのだ。
邪念を振り切り、太一は目の前の漫画本に意識を集中。一字一句逃すまいと、丁寧に双眸を泳がせる。
次第に意識は漫画の世界に引き込まれ、耳障りだった生活音はフェードアウトしていく。思考の大半を占めるのは白と黒で描かれたシリアスな世界。脳内で再生される凜とした声は、太一の思い描くこの物語の主人公のものだろう。
あまりに忠実に再現される理想の声に、太一はいつの間にか性別の壁を越え、主人公の少女に感情移入していた。その結果、太一の思考はより深く漫画の世界に浸っていく。
はずなのだが――
「うっせぇぇぇぇぇっ!!」
「ぽっふぉっ!?」
なんの前置きもなく声を荒げた太一に、真由美は驚き飛び上がる。ただ後ろに座り、漫画に没頭する太一の姿を眺めていただけなのになぜ怒られなければならないのか。真由美には太一の激怒の理由が分からなかった。
太一が今読んでいる本は、真由美の愛読書でありバイブルだ。愛するあまりに親心のような感情が発生していても可笑しくはない。そんな心境の真由美が、愛読書とそれを手に取る人間を見守りたくなるのは至極当然といえよう。
確かに、集中する太一の背中を少しだけ凝視しすぎていたのかもしれないが、そこは少女漫画の魔法。面白すぎて視線など気にならなくなるのだ。
真由美は作品への愛が強すぎるが故に、自分の犯したミスに気付けずにいた。
「シャコシャコシャコシャコうっせーんだよ! なんで俺の後ろで歯磨きすんの? 嫌がらせ?」
太一が激怒した理由。それは真由美の歯磨きが故だった。
漫画に集中するあまり、周りの音が思考から排除されていたのは事実。現に、真由美が洗い物を終えていたことには一切気付けなかった。
しかし、何事にも例外は存在する。今の太一にとって、歯磨きという行動は正に弁慶の泣き所。歯を磨く音から、体臭や口臭といったワードを連想するなど容易に出来てしまう。
「だいたいなぁ! 読書中は静かにするのが基本だろ? 図書館とかめっさしーんとしてんじゃん!」
「……」
「黙っててもわかんねぇよ! なんだゆとりか? 君はゆとり教育の賜物なのか!?」
「……」
太一の辛辣な言葉に、真由美は俯いたままなにも返さない。これが更に太一を煽り、結果的に怒りは急速に肥大化していく。
ヒートアップした太一は立ち上がり、その場に正座する真由美を見下しながらお説教を続ける。
側から見れば、歯ブラシを咥えたまま説教される真由美の姿はさぞかしシュールなものだろう。
「おい、 いつまで黙ってるわけ? いい加減にお兄ちゃんも怒るぞ……って、あれ?」
頭に血が上りすぎて、既に怒っていることさえ分からなくなっているのは言うまでもない。しかし、そんな太一を冷静にしたのは、他でもない真由美だった。
見間違いでなければ、一瞬真由美の唇が動いたように見えた。
残念ながら、馬鹿でかい太一の怒声と被ってしまい、なにと言ったかまでは聞き取れなかった。だが、真由美はなにか言葉を発したのではないか。もしそれが本当のならば、兄として妹の言い訳は聞いてやらねばなるまい。
太一は布団に座り直し、真っ直ぐに真由美を見つめる。
そして暫しの沈黙の後、歯ブラシを口から抜いた真由美は、ゆっくりと口を開いた。
「ど、どうしよう……び、びっくりして歯磨き粉、のののの飲んじゃいました……」
想像を遥かに凌駕する真由美の言葉。狼狽する表情を見るに、本気で不安に思っているのだろう。
不意に絶句を強いられた太一だったが、思考回路をフル動員してなんとか一命を取り留めることに成功する。
とにかくなにか言葉を掛けてやらねば。このままでは真由美が不安に押し潰されるのも時間の問題だ。
「俺……追加オプション料とか払わないよ?」
太一が懸命に絞り出したのはそんな言葉だった。
♦︎♦︎♦︎
真由美のゴックンボーナスから一転、室内は静寂に包まれていた。
太一のすげないツッコミはさて置き、ある程度まで歯磨き粉ショックを軽減した真由美は不貞寝を兼ねて早々の就寝を提案した。
夕食を終え、読んでいた少女漫画も一区切り。明日も朝から行動しなければならないというこを考えれば、太一もこの提案には素直に頷かざるを得なかった。
照明は全て消され、カーテンの隙間から差し込む月明かりだけが部屋を彩る。
静かな夜だ。
真由美の住まうアパートは東京二十三区内にありながらも、駅から徒歩二十分という立地が功を成してか、都会の喧騒を感じさせない。元々、都民でなかった太一には詳しい現在地までは把握出来ていないが、下りたインターチェンジを考えるに都心へのアクセスは上々だと予想できる。
唯一気になる点と言えば、物件が線路に隣接している為に日中は電車の通過音が少々喧しい。住めば都とはいうものの、そればかりは慣れるのに時間が掛かるだろう。
真由美自身、越してきてまだ一ヶ月と経たない故、始発の音に起こされては二度寝してを繰り返し、最近はもっぱら寝不足気味だ。
彼女の安眠が早く訪れる事を切に願う――
とはいえ、終電さえ行ってしまえば実に静かなものだ。流石に都内というだけあって、虫のさえずりや小川のせせらぎまでは聞こえないが、それでも不快感を覚えない程度には落ち着いている。
物思いに耽るには充分な空間だろう。
この二日で起きたこと、今後のこと。色々と考えなければならない太一にとって、この静寂は好都合なものだった。
太一は仰向けに寝返りを打ち、ゆっくりと思考を巡らせる。
「あ、あの……豆電つけていいですか?」
早々に遮られた太一の思考。犯人はロフトで眠る真由美だ。
床に敷かれた布団に眠る太一に対して、真由美はロフトの上。部屋の借主が真由美であることから、これが当たり前の構図なのは理解しているし、泊めてもらってる手前あまり贅沢はいえまい。
確かにロフトの方で寝たかったという気持ちも少なからずあったし、欲をいえば夕食にもう一品おかずが欲しいと思いもした。だが、太一はそれを己の中に押し留め、決して口にすることはなかった。
建前もあれば、歯磨き粉ゴックンで落ち込んでいる真由美が可哀想で言い出せなかった部分もある。つまり、太一は空気を読んだのだ。
別に豆電をつけることくらいなんでもない。特に、機能面の充実した『リオパレス』の照明は紐を引くタイプの物ではなく、リモコン式が採用されている。故に、お手軽操作でピピッと照明パターンを変更することが可能なのだ。
太一とて、そんな軽作業を億劫に思って突っ掛かったわけではない。
――何故、こんなにも噛み合わないのか。
少女漫画の一件は、お互い真相に辿り着けなかったことから除外されるが、それを抜いても太一に不信感を抱かせるやり取りは充分にあった。
考えてみれば、特殊な出会い故に一言目から既に噛み合っていなかったのではないか。
(なんだ? 俺が悪いのか? 全部俺のせいなのか?)
否、そんな筈はない。単に真由美が空気を読めていないだけのことだ。
だが、太一のマイナス思考はドツボに嵌り、全て自分のせいだと背負い込んでしまう。
「あ、あの……ま、豆電……」
太一の葛藤も虚しく、またも空気を読まず思考に割り込む真由美の声。怒られると思っているのか、真由美の声は小刻みに震えている。
怯えるのなら何故いってしまうのかという疑問はあるが、そこはKYという人種の性質上仕方のないこと。どんな場面でもエキセントリックな言動を放つ彼ら彼女らに理論を求めるのは筋違いだ。
悪いのは全て自分。出来る人間は出来ない人間を助けるべきであり、空気の読める人間は読めない人間に話を合わせてやらねばならない。
全ては不毛であり、全て自分せいなのだ。
そもそも日常会話すら噛み合わない相手に、シリアスな雰囲気を察しろというのが無謀の極み。無理難題を押し付けて、相手を困らせているだけの性悪に違いない。
自分はそうなりたくない。太一は強くそう思った。
一頻り浮き沈みを終えたメンヘラ太一は、無言で体を起こし、テーブルの上に置かれた小型のリモコンへと手を伸ばす。
リモコンに配置されているのは中央の大きなボタン一つ。太一は迷うことなくそれを押す。すると軽快な電子音と共に照明が全灯。
いきなり明るくなった室内に思わずたじろぎそうになるが、太一はすかさずボタンを連打し、光量を調節する。しかし、つい押しすぎてしまい再び全灯。結局、三種類の照明を二周してやっと要望の豆電に到達したのだった。
「あ、ありがとうございます……」
真由美から掛けられた礼の言葉。未だ震えた声からは怯えが感じ取れる。少し威圧的過ぎただろうか。
太一は心の葛藤が態度に出てしまったことを反省し、布団に戻った。
仰向けに寝転び、全身の力を抜く。ゆっくりと沈んでいく感覚が太一を取り巻き、やがて意識も少しずつ薄れていく。
思えば、昨日も碌に寝ていなかった。手紙を書くために疲れた体に鞭を打ち無理やり覚醒させた昨晩。それ以前に、ここ数日は合格発表の緊張からかどうにも寝つきが悪かった。
疲れていて当然だ。
太一の意識はゆっくりと沈む。やがて思考は無防備になり、無防備になった思考は内面に封じていたものを一つ一つ丁寧に整理する。
「あのさ……」
自分の声によって沈みかけていた思考が舞い戻る。なにを思って声を掛けたのか、なにを言いたかったのかは分からない。しかし、太一は無意識に言葉を発していた。
そして、一度開いてしまった内なる思考は中々閉じてくれない。
脳内をぐるぐると巡る思考の塊。無防備だったが故に、胸の内に秘めていた筈の疑念が吐き出され、形となり、言葉となり、喉へと押し上げる。
「多分さ……真由美ちゃんって、俺のこと苦手だよね?」
無意識にそんな言葉が溢れた。
半睡状態で発したもの故に、なぜ言ったのかは分からない。直前のやり取りが尾を引いたのかもしれない。しかし、限りなく自然体に近い状態での言葉であり、そこに偽りはあるまい。
度重なったトラブルや、噛み合わない会話。苦手意識を持たれても可笑しくない環境は充分に揃っていた。
太一は心のどこかで、そんな状態に内心で不安を感じ、怯えていたのだ。
思い出されるのは高速道路での一幕。真由美の台詞。
その後の展開が濃厚すぎて上書きさてしまったが、あのとき真由美がなにを考えていたのかは未だに分からない。
普通に考えれば、咄嗟に出た適当な言葉だったと考えるのが合理的だろう。しかし、あの時の真由美の表情は真剣味を帯びていて、言葉には妙な説得力があったように思えてもくる。
答えは一向に出ない。
結局、事の真相は本土に置き忘れてしまったのだから。
今、太一を悩ませる思考はただの希望的観測に過ぎないだろう。
真由美の気持ちを一切知らない太一だからこそ、恐怖を胸の奥に隠して見ないふりをしていてきた。
今しがた発した言葉は、そんな臆病な少年の悲痛の叫びだったのかもしれない。
(なんにしても……豆電が発端となってここまでテンション落ちるとか、俺やべぇな……)
やはり答えは出ない。
しかし、無意識だったとはいえ不安は吐露できた。胸に掛かっていた靄は幾分にもマシになったはずだ。
太一の意識は、胸に湧いた安堵によって少しずつ沈む。真由美の回答を待たずして、意識は落ちていく。
こうやって一つずつ言葉にしていけばいい。ぶつかり合うのは怖いが、知らぬところで決別するのはもっと怖い。
そんなことを思いながら、太一の意識は深い闇に落ちていく――
「どうして……そんなこと言うんですか……?」
ロフトの上から降り注ぐか細い声。弱々しくて、震えていて、静まり返ったこの部屋でなければ簡単に掻き消されてしまっただろう声。
最初、太一の言葉を聞いたときは心臓が飛び上がるほど驚いた。
単純に、うとうとしていた時に突然掛けられたから驚いただけなのかもしれない。はたまた、本能的に真意を知ることを拒んでいたのかもしれない。
だが、驚愕のあまりに活性化してしまった真由美の思考は警告を一切受け付けず、言葉の読解を始めてしまう。
言葉の意味を噛み解せば解すほどに、強く打ち付けるだけだった鼓動は揺らめき、締め付けへと痛みの種類を変える。
――どうしてこんなに苦しいのか。
苦痛に顔を歪めながらも、真由美の思考は止まらない。
人間関係を得意不得意で考えるつもりはないが、やはり太一の口からあんな風に言われてしまったことがショックだった。
自分は太一を苦手だなどと思っていないのに、どうしてそんな簡単なことが伝わらないのか。否、自分は何故そんな簡単なことを伝えられないのか。
一言、否定の言葉を言えば済む話なのに、疑問詞で相手に回答を委ねるような物言いをしてしまう。そんな自分が不甲斐なくて、悔しくて。
いつしか真由美の両目には大粒の涙が溜まっていた。
依然として太一からの返答は無い。寝てしまったのだろうか。
だが、真由美にその真相を突き止める勇気は無かった。
下に眠る太一へ背を向け、布団に体を埋める。ただただ枕を涙で濡らし、真由美は眠りへと落ちていく。
――素直になれない少年と素直過ぎる少女は、心にしこりを残したまま束の間の眠りへと落ちていく。
結果的にそれが良かったのかどうかは分からないが、あれだけの滑り芸を披露されてしまって元の話題に戻れるほど両者共に経験豊富ではない。一度壊れた空気は別の話題で塗り替える。それが今の二人に出来最大限の打開策なのだ。
とはいえ、真由美は一度腹を括ったわけで、どうにも不完全燃焼感が否めない。確かに、太一の切り出した話題に乗っかってしまったのは自分自身の弱さが故で、正直ほっとしている部分も多い。
しかし、せっかく掛けてもらった言葉を有耶無耶にしてしまったのではないか。太一の気持ちが空中分解してしまうのではないか。それはそれで勿体無い気がしてならない。
という具合に、拗れた細い糸は未だ解けておらず、真由美の気持ちに妙な語弊を生み続けているのだった。
「ふはぁー、ごちそーさんっ!」
真由美の気持ちなどなどつゆ知らず、太一は元気よくデーブルに箸を置く。
現状、布団から出ることを禁じられている身ではあるが、そこは狭いワンルームの特権。部屋の中央にどかっと敷かれた布団からは、大抵の物が手を伸ばせば届く。
太一はこれを生かして、漫画を手に取り暇を潰し、剰え食事まで済ませたのだった。これぞパーフェクトヒキニートの育成法だ。
なんにせよ、死んでから真面な食事を摂ったのはこれが初めてだろうか。一応、今朝の車内で真由美から貰ったドーナツを口に通してはいるが、健康な高校男児の活発な胃がその程度で満足することはない。やはり米とおかずを交互に食してこその食事だ。
「はい、お粗末様です。残り物で申し訳ないです……」
「お? なんかこのやり取り新婚さんみたいじゃね?」
「しししし新婚さんっ!?」
取り乱す真由美を見て、太一はイヤらしい笑いを浮かべた。
どうも、この初心な少女を前にすると、つい煽ってやりたくなる嫌いがある。確かに暴走されると厄介なのだが、車中でなければどうとでもなる。なんせ、真由美は素直なのだから。
「それよりさ、朝も思ったんだけど、死人も腹減んのね?」
「ほえ? あ、は、はい! お腹減りますよ!」
真由美の純粋な性格を逆手に取り、話題を塗り替える太一。
素直な分、訊かれた質問にはちゃんと答える。というよりも、二つのことを同時に考えられず、無意識に疑問詞で終わった言葉を優先してしまうのが真由美という少女なのだ。
これこそ太一発案、度重なるトラブルの末に行き着いた可愛い妹の取り扱い説明書である。
語弊が無いようにいっておくが、決して太一は真由美をイジメているのではない。弄っているだけだ。
ともあれ、今しがた太一が発した質問は本心から感じたもので間違いない。食事という概念が太一に疑問を植えつけたのだ。
先刻の少女漫画談義を終えた二人が話題の塗り替えに取った行動は晩餐。無駄に浪費されていく時間を見て、真由美が提案したのだ。
夕食のとしては暫し遅い時間なのだろうが、それでも食べないという選択肢は真由美にない。今日起こったトラブルの嵐のせいで、昼食を摂れなかった。故に、真由美の腹の虫は極限状態。これ以上不毛なやり取りでストレスを溜めるくらいなら、大人しく食事にした方が利口だろう。
帰宅が遅くなった上に財布の中身は二千円。本当は近所のスーパーに食材を買いに行きたかったのだが、時間的にも金銭的にもそれは実現できない。
真由美は、泣く泣く昨日の残り物で我慢することにした。
テーブルに並んだのは白米とシンプルな肉野菜炒め。白米は昨日冷凍しておいたもの。肉野菜炒めに至っては、特売品だった豚バラ三百グラムの半分と小松菜、エリンギを醤油で炒めただけの超簡易的なメインディシュ。
これが女の子の一人暮らしの実態だ。
曲がりなりにも意中の人に振る舞う料理なのだからもっと頑張りなさいよ、と思わないこともないが、今の冷蔵庫の中身ではこれが限界。これには真由美も申し訳なさで胸を一杯にした。
当の太一はというと、そんなこと一切気にせずにバクバクと口に運ぶ。
中途半端で我儘な太一の性格からは想像できないかもしれないが、太一に好き嫌いはない。美味い不味いは関係なしに、とりあえず完食してしまう。
それもこれも母親が施したしつけの賜物であり、食事は楽しくあるべきで、残したら一緒に食べている母が楽しくなくなる、と口を酸っぱくして教えられてきた。母にべったりだった幼き日の太一はこれを鵜呑みにし、好き嫌いを一切せずに食事を楽しむ子に成長したのだ。
故に、先の疑問である。
誰よりも食事の時間を大切に考える太一にとって、死後もそれを楽しめること自体は素直に嬉しい。
だが、食事の用途とは別の話だ。
生者にとっての食事とは栄養を補給するため、自分を維持するための部分が多い。しかし、霊体にとってのはどうなのか。
「昨日もらった資料で考えると、霊体って霊泉とかいう生命エネルギーで生きてるんだよね? なら別に食わなくても生きていけるんじゃないの?」
霊体にとっての必要な栄養は、既に己の身の中に保管されている。そして、それが減ることはあれど増えることはないと記憶している。つまり、いくら物を食べても霊泉は回復しないのだ。
ならば、食事の用途とはどこにあるのか。
「えっと……極論を言えばそうなんですけど、ご飯を食べるのってそんな業務的なことじゃないですよね?」
「まぁ、俺も楽しく食えればとは思うけどさ……」
真由美のいわんとすることは理解できる。太一自身、食事は楽しくあるべきだと思っているのだから。しかし、栄養面の話が関係なくなってしまうと、この世の食材事情は激しく偏ってしまうのではないか。好きなもの、ジャンクフードばかりが食卓に並んでしまうのではないか。
浄土の食生活などまだ知る由もないが、好きな物ばかり食べて暮らすというのも頂けない。メタボ一直線なのは勘弁だ。霊体が太るかは謎だが――
「楽しく食べるっていうのも大切なことだとは思いますが、やっぱり食欲って人間の思考の大半を占めてるんだと思うんですよ」
人差し指を立てて、説明モードに入る真由美。昨日、霊体の説明にはあれだけ難色を示していたのに、今回はすんなり入ったものだ。彼女にとってこの話題は得意分野ということなのだろうか。
「人間の三大欲求にある通りで、食欲って凄く大きなものです。それこそ無視すればストレスが溜まって、霊泉が激減しちゃうくらいです」
苛々したときに暴食で憂さを晴らすという経験は誰にでもあることだろう。それは霊体も然り。むしろ、心の状態が大きく影響をもたらす霊体にこそ起こり易い、安易なストレス発散だ。
なにより、生前の認識で人は食事をする生き物だと刷り込まれている。
習慣を無視することが心にどれだけの負担を掛けるのか。それを事前に取り除くためにも、霊体こそ食事を怠ってはならないと力説する浄土の学者も多いという。
「そんな固く考えなくていいと思いますよ。食事が楽しいから、単に好きな物を食べたいから、考え方は人それぞれですが、美味しい物が待ってるって考えた方が毎日頑張れるじゃないですか?」
ごく稀に出る真由美の超絶名言をお見舞いされた太一は、自分の失態に気付く。食事は楽しくという固定概念に支配され、物事の本質を見失っていた。
確かに食事は必要なことだろう。だが、それは日々を生きる自分あってこそ。どれだけその時間を楽しくしようと意気込んでも、それは作り物に他ならない。
真面目に生きて、辛いことにも耐えて、そこでやっと辿り着く晩餐。そこにこそ本当の至福があるのではないだろうか。
日夜働く企業戦士のような意見だが、あながち間違いではなかろう。人生にはメリハリ、飴と鞭が必要なのだ。生死問わず、食事は人々の飴になってくれているのかもしれない。
「まぁ、中には全く食べなくても大丈夫な人もいるんですけどね」
「あ〝?」
せっかくいい感じで纏まり掛けていた太一の思考が、真由美の余計な一言で一気に崩れ去る。食事の必要性と人間の生活という議題で、素敵なエッセイが書ける気さえしていたのに台無しだ。
しかし、これによって太一の疑問が一つ解決する。
「イメージで空腹も制御できるってこと?」
ソファーや手紙の件を考えると、出来ないことではないと考えられる。霊体イメージ万能説だ。
そもそも太一自身、死んでからの二日間で空腹を感じた回数は今回を含めてわずか二度だけ。それも、目の前に食料がチラついた時にだけという条件に限る。突如襲った摩訶不思議体験のせいで割ける思考が無かったのは事実だが、それもイメージの塗り替えによる所業ではないか。
太一の中で考えは纏まり、ムラのあった空腹に合点がいく。
しかし、真由美からの回答は少しばかり違ったものだった。
「うーん、どちらかというと逆ですね。空腹の方がイメージに近いんですよ。生前に食べなきゃ生きてけないって認識です」
「つまり、霊体は腹減らないってこと?」
「私もその辺の構造までは詳しくないんでなんとも言えないんですが……ただ、生前の認識を取り除いてる人がいるって話は聞いたことがあります」
「そいつが飯食わないの?」
こくりと頷く真由美。なんとも曖昧ないい方だが、こんな無垢な少女の耳に入っているくらいなのだ。それなりには有名な話なのだろう。
生前の認識を取り除く。
真由美の言いを素直に信じるのなら、霊体としての新しい可能性が見えてくる。例えば、手から炎を出したり、宙に浮いたり。おおよそ生きているときには不可能だったことを現実に出来るのではないか。
男の子である太一は、自分という存在に新たな可能性を感じてしまう。
ただ一点、空腹を感じなくなるのはなにか違う気がしてしまうのも事実。人間らしい一面を失ってまで、なにか特出したスキルを身に付けたいと、太一にはどうしても思えなかった。
「どちらにしても、椎名さんが真っ当な生活をしてれば関係のない話だと思いますよ」
煮え切らない思いが顔に出ていたのか、太一を安心させるための言葉を掛ける真由美。どこか含みのあるその言葉に違和感を感じつつも、太一は深く追求しなかった。
きっと浄土で暮らしていけばいずれ分かることだろう。
「まぁ、そうね。真面目にやってたら人間らしさを失うことはないだろうし。それより、ご飯美味かったよ。せめてものお礼に洗い物は俺がやろうじゃぁないの!」
「い、いえ、大丈夫ですから、椎名さんは布団から出ないでください!」
しれーっと布団からの脱出を図ろうとするも敢え無く失敗。真由美のくせに太一の狙いを見抜くとは。
太一が真由美の扱いに慣れてきたのと同様、真由美も太一のひん曲がった性格を理解してきたということだろうか。兄として妹の成長は素直に喜ぶべきことだし、これだけガードが硬ければ悪い虫も付きにくい。
太一はそんなことを考えていたのだが、当の真由美はといえば、太一に課した制約のことなどすっかり忘れていた。ただ単に、自分の作った料理を美味かったと言ってくれたことに対しての照れ隠しであり、そんな太一に気を使わせないつもりで掛けた言葉なのだ。
全くもって純粋な女の子だこと。
料理を褒められたことに歓喜する少女。真由美のそんな一面に太一が気付くのは、まだ時間が足りないのかもしれない。
「さいですか……なら、ぼくは漫画の世界へと戻ります」
すっかりヘソを曲げてしまった太一は読書を再開するが、どうにも漫画に集中できない。作戦の失敗が尾を引いている。
(シャワー……浴びたかった)
思考に未練がましく割り込んでくる欲望。
本当は、ここでちゃっかりと制約を有耶無耶にしてシャワーを借りるつもりだったのだ。しかし、真由美から返ってきたのは否定の言葉。あの鋭い言い方を考えるに、彼女の憤怒はまだ治っていのいないのだろう。
本土の高速道路での惨めな嘔吐事件は記憶に新しい。あそこでかいた汗は太一の体をベタつかせ、吐き出した酸っぱい液体が口臭に直結している気がして、ついつい疑心暗鬼モードに陥ってしまう。
せめてうがいだけでもしたかったものだが、この場から動けない以上は叶わぬ夢だ。斯くなる上は、真由美が寝静まってからこっそりと浴びよう。
太一はそんなことを考えて、漫画本へと目線を戻す。
一言、真由美に正直な気持ちを言えば済むことなのに、あくまで自己完結で事を進めてしまうのだから救えない。所詮は女心の分からない残念な男。だからお友達止まりなのだ。
邪念を振り切り、太一は目の前の漫画本に意識を集中。一字一句逃すまいと、丁寧に双眸を泳がせる。
次第に意識は漫画の世界に引き込まれ、耳障りだった生活音はフェードアウトしていく。思考の大半を占めるのは白と黒で描かれたシリアスな世界。脳内で再生される凜とした声は、太一の思い描くこの物語の主人公のものだろう。
あまりに忠実に再現される理想の声に、太一はいつの間にか性別の壁を越え、主人公の少女に感情移入していた。その結果、太一の思考はより深く漫画の世界に浸っていく。
はずなのだが――
「うっせぇぇぇぇぇっ!!」
「ぽっふぉっ!?」
なんの前置きもなく声を荒げた太一に、真由美は驚き飛び上がる。ただ後ろに座り、漫画に没頭する太一の姿を眺めていただけなのになぜ怒られなければならないのか。真由美には太一の激怒の理由が分からなかった。
太一が今読んでいる本は、真由美の愛読書でありバイブルだ。愛するあまりに親心のような感情が発生していても可笑しくはない。そんな心境の真由美が、愛読書とそれを手に取る人間を見守りたくなるのは至極当然といえよう。
確かに、集中する太一の背中を少しだけ凝視しすぎていたのかもしれないが、そこは少女漫画の魔法。面白すぎて視線など気にならなくなるのだ。
真由美は作品への愛が強すぎるが故に、自分の犯したミスに気付けずにいた。
「シャコシャコシャコシャコうっせーんだよ! なんで俺の後ろで歯磨きすんの? 嫌がらせ?」
太一が激怒した理由。それは真由美の歯磨きが故だった。
漫画に集中するあまり、周りの音が思考から排除されていたのは事実。現に、真由美が洗い物を終えていたことには一切気付けなかった。
しかし、何事にも例外は存在する。今の太一にとって、歯磨きという行動は正に弁慶の泣き所。歯を磨く音から、体臭や口臭といったワードを連想するなど容易に出来てしまう。
「だいたいなぁ! 読書中は静かにするのが基本だろ? 図書館とかめっさしーんとしてんじゃん!」
「……」
「黙っててもわかんねぇよ! なんだゆとりか? 君はゆとり教育の賜物なのか!?」
「……」
太一の辛辣な言葉に、真由美は俯いたままなにも返さない。これが更に太一を煽り、結果的に怒りは急速に肥大化していく。
ヒートアップした太一は立ち上がり、その場に正座する真由美を見下しながらお説教を続ける。
側から見れば、歯ブラシを咥えたまま説教される真由美の姿はさぞかしシュールなものだろう。
「おい、 いつまで黙ってるわけ? いい加減にお兄ちゃんも怒るぞ……って、あれ?」
頭に血が上りすぎて、既に怒っていることさえ分からなくなっているのは言うまでもない。しかし、そんな太一を冷静にしたのは、他でもない真由美だった。
見間違いでなければ、一瞬真由美の唇が動いたように見えた。
残念ながら、馬鹿でかい太一の怒声と被ってしまい、なにと言ったかまでは聞き取れなかった。だが、真由美はなにか言葉を発したのではないか。もしそれが本当のならば、兄として妹の言い訳は聞いてやらねばなるまい。
太一は布団に座り直し、真っ直ぐに真由美を見つめる。
そして暫しの沈黙の後、歯ブラシを口から抜いた真由美は、ゆっくりと口を開いた。
「ど、どうしよう……び、びっくりして歯磨き粉、のののの飲んじゃいました……」
想像を遥かに凌駕する真由美の言葉。狼狽する表情を見るに、本気で不安に思っているのだろう。
不意に絶句を強いられた太一だったが、思考回路をフル動員してなんとか一命を取り留めることに成功する。
とにかくなにか言葉を掛けてやらねば。このままでは真由美が不安に押し潰されるのも時間の問題だ。
「俺……追加オプション料とか払わないよ?」
太一が懸命に絞り出したのはそんな言葉だった。
♦︎♦︎♦︎
真由美のゴックンボーナスから一転、室内は静寂に包まれていた。
太一のすげないツッコミはさて置き、ある程度まで歯磨き粉ショックを軽減した真由美は不貞寝を兼ねて早々の就寝を提案した。
夕食を終え、読んでいた少女漫画も一区切り。明日も朝から行動しなければならないというこを考えれば、太一もこの提案には素直に頷かざるを得なかった。
照明は全て消され、カーテンの隙間から差し込む月明かりだけが部屋を彩る。
静かな夜だ。
真由美の住まうアパートは東京二十三区内にありながらも、駅から徒歩二十分という立地が功を成してか、都会の喧騒を感じさせない。元々、都民でなかった太一には詳しい現在地までは把握出来ていないが、下りたインターチェンジを考えるに都心へのアクセスは上々だと予想できる。
唯一気になる点と言えば、物件が線路に隣接している為に日中は電車の通過音が少々喧しい。住めば都とはいうものの、そればかりは慣れるのに時間が掛かるだろう。
真由美自身、越してきてまだ一ヶ月と経たない故、始発の音に起こされては二度寝してを繰り返し、最近はもっぱら寝不足気味だ。
彼女の安眠が早く訪れる事を切に願う――
とはいえ、終電さえ行ってしまえば実に静かなものだ。流石に都内というだけあって、虫のさえずりや小川のせせらぎまでは聞こえないが、それでも不快感を覚えない程度には落ち着いている。
物思いに耽るには充分な空間だろう。
この二日で起きたこと、今後のこと。色々と考えなければならない太一にとって、この静寂は好都合なものだった。
太一は仰向けに寝返りを打ち、ゆっくりと思考を巡らせる。
「あ、あの……豆電つけていいですか?」
早々に遮られた太一の思考。犯人はロフトで眠る真由美だ。
床に敷かれた布団に眠る太一に対して、真由美はロフトの上。部屋の借主が真由美であることから、これが当たり前の構図なのは理解しているし、泊めてもらってる手前あまり贅沢はいえまい。
確かにロフトの方で寝たかったという気持ちも少なからずあったし、欲をいえば夕食にもう一品おかずが欲しいと思いもした。だが、太一はそれを己の中に押し留め、決して口にすることはなかった。
建前もあれば、歯磨き粉ゴックンで落ち込んでいる真由美が可哀想で言い出せなかった部分もある。つまり、太一は空気を読んだのだ。
別に豆電をつけることくらいなんでもない。特に、機能面の充実した『リオパレス』の照明は紐を引くタイプの物ではなく、リモコン式が採用されている。故に、お手軽操作でピピッと照明パターンを変更することが可能なのだ。
太一とて、そんな軽作業を億劫に思って突っ掛かったわけではない。
――何故、こんなにも噛み合わないのか。
少女漫画の一件は、お互い真相に辿り着けなかったことから除外されるが、それを抜いても太一に不信感を抱かせるやり取りは充分にあった。
考えてみれば、特殊な出会い故に一言目から既に噛み合っていなかったのではないか。
(なんだ? 俺が悪いのか? 全部俺のせいなのか?)
否、そんな筈はない。単に真由美が空気を読めていないだけのことだ。
だが、太一のマイナス思考はドツボに嵌り、全て自分のせいだと背負い込んでしまう。
「あ、あの……ま、豆電……」
太一の葛藤も虚しく、またも空気を読まず思考に割り込む真由美の声。怒られると思っているのか、真由美の声は小刻みに震えている。
怯えるのなら何故いってしまうのかという疑問はあるが、そこはKYという人種の性質上仕方のないこと。どんな場面でもエキセントリックな言動を放つ彼ら彼女らに理論を求めるのは筋違いだ。
悪いのは全て自分。出来る人間は出来ない人間を助けるべきであり、空気の読める人間は読めない人間に話を合わせてやらねばならない。
全ては不毛であり、全て自分せいなのだ。
そもそも日常会話すら噛み合わない相手に、シリアスな雰囲気を察しろというのが無謀の極み。無理難題を押し付けて、相手を困らせているだけの性悪に違いない。
自分はそうなりたくない。太一は強くそう思った。
一頻り浮き沈みを終えたメンヘラ太一は、無言で体を起こし、テーブルの上に置かれた小型のリモコンへと手を伸ばす。
リモコンに配置されているのは中央の大きなボタン一つ。太一は迷うことなくそれを押す。すると軽快な電子音と共に照明が全灯。
いきなり明るくなった室内に思わずたじろぎそうになるが、太一はすかさずボタンを連打し、光量を調節する。しかし、つい押しすぎてしまい再び全灯。結局、三種類の照明を二周してやっと要望の豆電に到達したのだった。
「あ、ありがとうございます……」
真由美から掛けられた礼の言葉。未だ震えた声からは怯えが感じ取れる。少し威圧的過ぎただろうか。
太一は心の葛藤が態度に出てしまったことを反省し、布団に戻った。
仰向けに寝転び、全身の力を抜く。ゆっくりと沈んでいく感覚が太一を取り巻き、やがて意識も少しずつ薄れていく。
思えば、昨日も碌に寝ていなかった。手紙を書くために疲れた体に鞭を打ち無理やり覚醒させた昨晩。それ以前に、ここ数日は合格発表の緊張からかどうにも寝つきが悪かった。
疲れていて当然だ。
太一の意識はゆっくりと沈む。やがて思考は無防備になり、無防備になった思考は内面に封じていたものを一つ一つ丁寧に整理する。
「あのさ……」
自分の声によって沈みかけていた思考が舞い戻る。なにを思って声を掛けたのか、なにを言いたかったのかは分からない。しかし、太一は無意識に言葉を発していた。
そして、一度開いてしまった内なる思考は中々閉じてくれない。
脳内をぐるぐると巡る思考の塊。無防備だったが故に、胸の内に秘めていた筈の疑念が吐き出され、形となり、言葉となり、喉へと押し上げる。
「多分さ……真由美ちゃんって、俺のこと苦手だよね?」
無意識にそんな言葉が溢れた。
半睡状態で発したもの故に、なぜ言ったのかは分からない。直前のやり取りが尾を引いたのかもしれない。しかし、限りなく自然体に近い状態での言葉であり、そこに偽りはあるまい。
度重なったトラブルや、噛み合わない会話。苦手意識を持たれても可笑しくない環境は充分に揃っていた。
太一は心のどこかで、そんな状態に内心で不安を感じ、怯えていたのだ。
思い出されるのは高速道路での一幕。真由美の台詞。
その後の展開が濃厚すぎて上書きさてしまったが、あのとき真由美がなにを考えていたのかは未だに分からない。
普通に考えれば、咄嗟に出た適当な言葉だったと考えるのが合理的だろう。しかし、あの時の真由美の表情は真剣味を帯びていて、言葉には妙な説得力があったように思えてもくる。
答えは一向に出ない。
結局、事の真相は本土に置き忘れてしまったのだから。
今、太一を悩ませる思考はただの希望的観測に過ぎないだろう。
真由美の気持ちを一切知らない太一だからこそ、恐怖を胸の奥に隠して見ないふりをしていてきた。
今しがた発した言葉は、そんな臆病な少年の悲痛の叫びだったのかもしれない。
(なんにしても……豆電が発端となってここまでテンション落ちるとか、俺やべぇな……)
やはり答えは出ない。
しかし、無意識だったとはいえ不安は吐露できた。胸に掛かっていた靄は幾分にもマシになったはずだ。
太一の意識は、胸に湧いた安堵によって少しずつ沈む。真由美の回答を待たずして、意識は落ちていく。
こうやって一つずつ言葉にしていけばいい。ぶつかり合うのは怖いが、知らぬところで決別するのはもっと怖い。
そんなことを思いながら、太一の意識は深い闇に落ちていく――
「どうして……そんなこと言うんですか……?」
ロフトの上から降り注ぐか細い声。弱々しくて、震えていて、静まり返ったこの部屋でなければ簡単に掻き消されてしまっただろう声。
最初、太一の言葉を聞いたときは心臓が飛び上がるほど驚いた。
単純に、うとうとしていた時に突然掛けられたから驚いただけなのかもしれない。はたまた、本能的に真意を知ることを拒んでいたのかもしれない。
だが、驚愕のあまりに活性化してしまった真由美の思考は警告を一切受け付けず、言葉の読解を始めてしまう。
言葉の意味を噛み解せば解すほどに、強く打ち付けるだけだった鼓動は揺らめき、締め付けへと痛みの種類を変える。
――どうしてこんなに苦しいのか。
苦痛に顔を歪めながらも、真由美の思考は止まらない。
人間関係を得意不得意で考えるつもりはないが、やはり太一の口からあんな風に言われてしまったことがショックだった。
自分は太一を苦手だなどと思っていないのに、どうしてそんな簡単なことが伝わらないのか。否、自分は何故そんな簡単なことを伝えられないのか。
一言、否定の言葉を言えば済む話なのに、疑問詞で相手に回答を委ねるような物言いをしてしまう。そんな自分が不甲斐なくて、悔しくて。
いつしか真由美の両目には大粒の涙が溜まっていた。
依然として太一からの返答は無い。寝てしまったのだろうか。
だが、真由美にその真相を突き止める勇気は無かった。
下に眠る太一へ背を向け、布団に体を埋める。ただただ枕を涙で濡らし、真由美は眠りへと落ちていく。
――素直になれない少年と素直過ぎる少女は、心にしこりを残したまま束の間の眠りへと落ちていく。
0
あなたにおすすめの小説

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

【完結保証】科学で興す異世界国家 ~理不尽に死んだ技術者が、「石炭」と「ジャガイモ」で最強を証明する。優秀な兄たちが膝を折るまでの建国譚~
Lihito
ファンタジー
正しいデータを揃えた。論理も完璧だった。
それでも、組織の理不尽には勝てなかった。
——そして、使い潰されて死んだ。
目を覚ますとそこは、十年後に魔王軍による滅亡が確定している異世界。
強国の第三王子として転生した彼に与えられたのは、
因果をねじ曲げる有限の力——「運命点」だけ。
武力と経済を握る兄たちの陰で、継承権最下位。後ろ盾も発言力もない。
だが、邪魔する上司も腐った組織もない。
今度こそ証明する。科学と運命点を武器に、俺のやり方が正しいことを。
石炭と化学による国力強化。
情報と大義名分を積み重ねた対外戦略。
準備を重ね、機が熟した瞬間に運命点で押し切る。
これは、理不尽に敗れた科学者が、選択と代償を重ねる中で、
「正しさ」だけでは国は守れないと知りながら、
滅びの未来を書き換えようとする建国譚。

役立たずと言われダンジョンで殺されかけたが、実は最強で万能スキルでした !
本条蒼依
ファンタジー
地球とは違う異世界シンアースでの物語。
主人公マルクは神聖の儀で何にも反応しないスキルを貰い、絶望の淵へと叩き込まれる。
その役に立たないスキルで冒険者になるが、役立たずと言われダンジョンで殺されかけるが、そのスキルは唯一無二の万能スキルだった。
そのスキルで成り上がり、ダンジョンで裏切った人間は落ちぶれざまあ展開。
主人公マルクは、そのスキルで色んなことを解決し幸せになる。
ハーレム要素はしばらくありません。
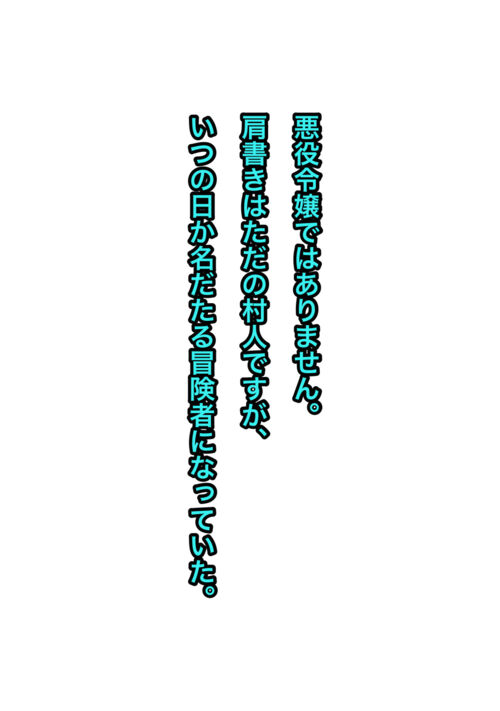
悪役令嬢ではありません。肩書きはただの村人ですが、いつの日か名だたる冒険者になっていた。
小田
ファンタジー
ポッチ村に住んでいる少女ルリ。彼女には特別な力があった。彼女が六歳の時、ルリの母親は娘の力を封印した。村長はルリの母の遺言どおり、実の娘のように大切に育ててーー。十四歳を迎えたルリはいつものように山に薬草を採取しにいった。すると、偶然倒れている騎士を発見。ルリは家に運んで介抱するが、騎士ではなく実は三代公爵家の長男であった。
村人の少女ルリが学園に行ったり、冒険をして仲間と共に成長していく物語です。

勘当された少年と不思議な少女
レイシール
ファンタジー
15歳を迎えた日、ランティスは父親から勘当を言い渡された。
理由は外れスキルを持ってるから…
眼の色が違うだけで気味が悪いと周りから避けられてる少女。
そんな2人が出会って…

つまらなかった乙女ゲームに転生しちゃったので、サクッと終わらすことにしました
蒼羽咲
ファンタジー
つまらなかった乙女ゲームに転生⁈
絵に惚れ込み、一目惚れキャラのためにハードまで買ったが内容が超つまらなかった残念な乙女ゲームに転生してしまった。
絵は超好みだ。内容はご都合主義の聖女なお花畑主人公。攻略イケメンも顔は良いがちょろい対象ばかり。てこたぁ逆にめちゃくちゃ住み心地のいい場所になるのでは⁈と気づき、テンションが一気に上がる!!
聖女など面倒な事はする気はない!サクッと攻略終わらせてぐーたら生活をGETするぞ!
ご都合主義ならチョロい!と、野望を胸に動き出す!!
+++++
・重複投稿・土曜配信 (たま~に水曜…不定期更新)

三歩先行くサンタさん ~トレジャーハンターは幼女にごまをする~
杵築しゅん
ファンタジー
戦争で父を亡くしたサンタナリア2歳は、母や兄と一緒に父の家から追い出され、母の実家であるファイト子爵家に身を寄せる。でも、そこも安住の地ではなかった。
3歳の職業選別で【過去】という奇怪な職業を授かったサンタナリアは、失われた超古代高度文明紀に生きた守護霊である魔法使いの能力を受け継ぐ。
家族には内緒で魔法の練習をし、古代遺跡でトレジャーハンターとして活躍することを夢見る。
そして、新たな家門を興し母と兄を養うと決心し奮闘する。
こっそり古代遺跡に潜っては、ピンチになったトレジャーハンターを助けるサンタさん。
身分差も授かった能力の偏見も投げ飛ばし、今日も元気に三歩先を行く。

わたしの下着 母の私をBBA~と呼ぶことのある息子がまさか...
MisakiNonagase
青春
39才の母・真知子は息子が私の下着を持ち出していることに気づいた。
ネットで同様の事象がないか調べると、案外多いようだ。
さて、真知子は息子を問い詰める? それとも気づかないふりを続けてあげるか?
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















