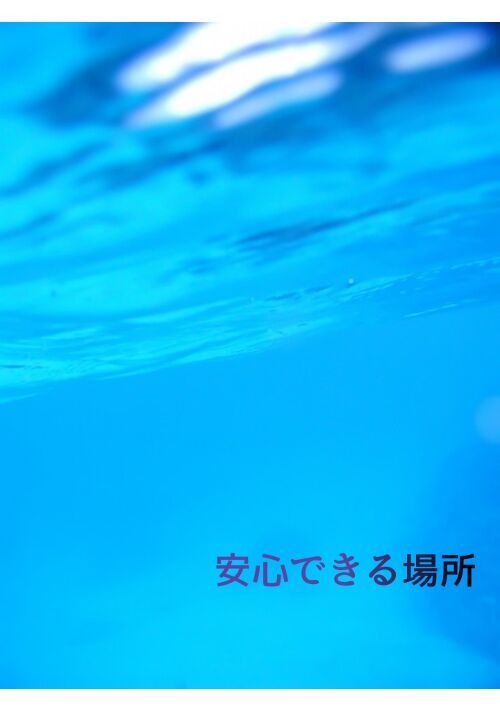16 / 18
Side カイル
07
しおりを挟む
ヴァルトーシュ王城に特攻をかけてから、五年の日々が過ぎ去っていた。
俺とレオは今、ヴァルトーシュの西側にある元王家直轄領に住んでいる。この地に俺たちが移り住んで、二年の月日が経とうとしていた。
本来、五年を試験期間として、ヴァルトーシュの各貴族当主や王族の努力する様を監視するつもりだった。しかし、彼らは俺が思っていた以上に有能だった。
二年を過ぎた頃には、ヴァルトーシュ王国内に徐々に妖精が戻り始め、その一年後にもなると、かなりの妖精たちが戻って来ていることが、俺やロルフの目には見てとれるようになっていた。
貴族たちの治める領地の様子や、王都に暮らす国民たちの様子を見ても、三年前とは同じ国と思えないくらい、その土地に暮らす人々の表情は明るくなっていた。
それを確認した俺は、試験期間を二年早く終了して、レオと共にヴァルトーシュへ移住する決意をしたのだった。
移住の時期を早めた理由はもう一つある。
それは、俺たちが暮らしていたシャルロタ王国の侯爵領での問題だった。
先に問題が起きたのは俺の方だ。
レオから聞いていた通り、レオの母親である侯爵夫人は、とにかく俺を貴族にしたいらしく、あの後すぐ俺の元に、貴族の養子になる件について書かれた手紙が送られてきた。
言うまでもなく、俺に養子になるつもりはない。だからそう返事をしたのだが、それから数ヵ月経っても、まだしつこく手紙が何度も届き続けた。養子に出ろ、貴族になれとあまりにも頻繁に届く手紙にうんざりした俺は、ついにラッセにあることを願いでた。
「奥様からの手紙があまりに煩いので、ハッキリお断りするため王都に行ってきます。それでお願いなんですが、王都に向かう旅の途中、俺は野盗に襲われて死んだことにしてもらえませんか。死体未発見で。この領地から遠く離れた場所、王都の近くで襲われた様に擬装して欲しいんです」
「……理由を説明してもらおうか」
「単純な話です。俺は貴族の養子になるつもりはありません。それなのに、断っても断っても養子をごり押ししてくる。もう面倒になったので、いっそ死んだことにしてしまおうかと」
「襲われる場所が王都近くがいいと言うのは?」
「奥様にはできるだけ領地に来て欲しくないんです。レオに会わせたくない。俺がこの付近で襲われたら、奥様は俺を探すために領地に来るかもしれない。それは嫌なんです」
領地に侯爵夫人が来るのは困る。腐っても貴族。この領地にやって来てレオに会ってしまえば、レオが精霊の愛し子であることに気づいてしまうかもしれない。それは困るのだ。知られてしまえば、すぐにレオを連れて逃げ出さなければならなくなる。
ヴァルトーシュに逃げたとしても、その後、レオがシャルロタの貴族子弟であることを盾に、所有権をシャルロタ側から主張されてしまうのは面倒だ。そうなる前に、レオが精霊の愛し子であることに気付かれないまま、侯爵家とはキッパリと縁を切り、レオを枷のない自由の身にしてあげたかった。
侯爵家の人間は、これまで少しもレオを顧みず、愛そうとはしなかった。そのクセ、レオに利用価値があると知れば、当然のことのように権利を主張してくるに決まっている。レオの気持ちなど少しも考えず、奴らなら躊躇なく、レオの利用価値だけを当たり前に欲しがるだろう。
それをされたら、今度こそ俺はキレる。絶対に侯爵家の人間を許さない。どんな残酷なことでもやってのける自信がある。しかし、それをするとレオが悲しむと知っているから、できるだけ穏便に事を進めたいと思うのだ。
「レオをそっちのけにして、俺を心配する奥様をレオに見せたくありません」
侯爵夫人に領地まで来て欲しくない理由をそう説明すると、ラッセはわずかに首を傾げた。
「お前は平民だ。なにも気にせず屋敷を出て行けばいいじゃないか。奥様には、わたしの方から失踪したと報告しておくが?」
「それをした場合、俺を失踪させたとして、ラッセさんが奥様に叱責を受けてしまいます。それは嫌なんです。それに、その場合も奥様はこの屋敷に来て、レオを蔑ろにしたまま俺を探せと騒ぎ立てるでしょう? 結局はレオが傷つく」
「なるほど、お前の言いたいことは理解できた。しかし……」
ラッセが俺を気づかうような、含みのある視線を向けてきた。
「本当にそれでいいのか。その処理を行った場合、お前の父上からの血筋が、この世から完全に途絶えることになるが」
やはりラッセは俺の出生の秘密について知らされていたらしい。
「気にしません。本家の血筋はあっちの国で続いていますし、俺はこれまで父の血筋を意識して生きたことはなかった。母だって死の間際に俺に言いました。自由に生きてくれ、と。だから俺は好きに生きようと思います」
「分かった。お前の望むように手配しよう。なにかお前のものと分かる品を渡してくれ。賊に襲われて壊れた馬車の中から見つかる品だ。お前が死んだことの証明になる」
俺はヴァルトーシュに行き、宰相に会った。そして、事の詳細を話し、父の形見であるペンダントをラッセに渡すつもりであることと、俺がもうヴァルトーシュの王族として生きるつもりがないことを伝えた。
宰相は残念がったものの、俺の意思を尊重してくれた。そしてその時、俺の父の母親であった前国王の正妃が、実は宰相の妹だったことを知らされた。父が幼かった頃、教育係を宰相が任されたのはその関係からだったらしい。
「だから、例え王族としての証がなくなったとしても、あなたは間違いなくわたしの身内なのです。困ったことがあったら、いつでも頼って下さい。息子に爵位は譲りましたが、これでも元公爵であり現宰相位に就いています。お力になれることはいくらでもあるでしょう」
そう言ってくれた宰相の言葉は、とても心強いものだった。
今後、ヴァルトーシュに居を移すことになった時、レオを守るための後ろ盾は少しでも多い方がいい。なにかあった時には、遠慮なく頼らせてもらおうと思う。
そんなわけで、俺はラッセに父の形見のペンダントを渡した。と同時に、王都の侯爵邸を訪ねる旨をしたためた手紙を侯爵夫人宛てに送った。
流石、敏腕執事のラッセは手際よく様々な手配を行ってくれて、一月後、王都への旅の途中で襲われた俺は、計画通りこの世の者ではなくなったのだった。
今や俺の形見となったペンダントは、侯爵夫人の手から母の実家である伯爵家へ届けられたらしい。
これにより、俺のシャルロタ王国でのしがらみは完全に消えてなくなった。
レオにはあまり詳しい話はしていない。死んだことにした、なんて言うと心配かけてしまうからな。その内話すこともあるかもしれないけれど、今はまだ内緒にしておこうと思う。
死んだことになった俺がどこで生活するようになったかと言うと、夜は勿論レオのベッドに潜り込んだが、それ以外の時は孤児院で過ごすようになった。
孤児院の子供たちは、いずれヴァルトーシュに連れて行くつもりでいる。共に働く仲間として期待している分、今の内に学べることは学んでもらおうと、俺はこれまでよりも力を入れて彼らに文字の読み書きや算術を教えていた。
ある程度まで勉強が身に付いた者たちには、実地により経験を積ませるため、色々な商店へと低賃金で仕事に出させている。
俺自身、午前中はレオと一緒に、ラッセから領地経営の基礎を学んでいる。ラッセは執事として優秀なだけに留まらず、領主代理の仕事をも侯爵から任されているのだ。
領主の仕事を覚えることは、いずれヴァルトーシュへと移住した際に必要となる知識の習得である。そう考えれば、仕事内容を覚えることは少しも苦にはならない。いずれすべてが俺とレオとの幸せに繋がるのだから、勉強に身が入るのも当然だった。
俺が死んだことになった日から約一年が過ぎ去った頃。今度はレオの方に問題が起こった。予測していた通り、レオに縁談が持ち上がったのだ。
相手はさる侯爵家の当主で、家格はレオの家とは同じでありながらも、血統の良さが格段に上の名門だった。建国当時から王家にも認められた国内屈指の名家であり、商売も幅広く行っている上に成功させているので莫大な資産もある。レオの家が強い繋がりを欲するのも当然の家だった。
当主の年齢は六十を少し過ぎたくらい。数年前に奥方を亡くしていて、嫡男に近々爵位を譲る予定らしい。
シャルロタ王国では同性婚が認められている。しかし、当然ながら子供ができない婚姻なので、貴族間での同性婚は、そのほとんどが政略結婚である。
今回レオにきた縁談のように、家を継ぐことのない貴族の次男や三男が、名門当主の後添えに嫁いだり、愛人として囲われる話は、特に珍しいものではなかった。
とはいえ、普通なら学園を卒業する十八才を過ぎてから嫁ぐものだが、レオは学園には入学していない。出来が悪い上に勉強の必要性が理解できず、学園への入学も拒否。領地にずっと籠っているため、人脈を広げるという活動さえできやしない。
そんなやる気のない役立ずな子供をさっさと名門他家に嫁がせ、少しでも家の役に立てようと考えたレオの両親の考えは、決しておかしなものではない。
しかし、当然ながら俺には受け入れられない話だし、それはレオにとっても同じである。
「ぼ、僕……け、結婚しろって言われるなんて、か、考えたことなかっ……」
王都の父親から届いた手紙を片手に、青褪めてぶるぶる震えるレオを、俺は安心させるように両腕で包み込んだ。
「大丈夫だよ、レオ。大丈夫」
「でもっ、だって! こっ、ここに書いてある! 結婚を承諾できないなら、か、勘当だって。縁を切るって。どうしよう、僕、か、勘当なんてされたらどうしたら…………あ!」
下を向いていたレオが勢いよく顔を上げ、俺と目を合わせて悲しい顔をした。
「ぼ、僕、どうしよう! 貴族でなくなったら、もうなにもなくなって、カイルのためになにもしてあげられない。もうなにも役に立てないよ。ど、ど、どうしよう!!」
ごめんなさい、ごめんなさいと泣きながら謝るレオを、俺は更に力を込めて抱きしめた。
「謝るな。レオはいるだけで俺の役に立ってる。だから心配するな」
「父上になんと言われても、結婚なんてできない。だから、もうここにはいられない。住む場所もない。カイルになにもしてあげられない。せめて迷惑にならないように、僕、こ、ここを出て一人でがんばって生きていくよ!」
「出て行くなら、俺も一緒に連れて行ってくれよな」
俺の言葉を聞いて、心底驚いたのかレオが飛び上がった。
「なっ、なに言ってるの?! カイルはヴァルトーシュに行かなくちゃ! 待ってくれてる人たちが、たくさんいるんでしょう?」
「まあな。でも、ヴァルトーシュに行く時はレオも一緒だ。それより、レオは結婚したくないから侯爵家を出るんだよな。未練はない? この領地から出ることになっても大丈夫?」
「それは……平気だと思う。未練はないよ。だって、僕にとってここはあくまでもカイルの故郷だもの。確かに領民の人たちのことは好きだけど、でも、カイルにとっての大切な場所って認識が一番大きいんだ。だからこそ、もっとここを発展させたいと思っていたわけだし」
「じゃあ提案。平民になってしがらみはすべて捨て去って、俺と旅に出ないか?」
「旅に?」
「ああ、世界中を旅してまわろう。レオと俺とロルフと緑の妖精とで。行ったことのない場所へ行って、珍しいものをたくさん見よう。色んな町に行って、色んな人にも会ってみよう。海も見てみたいな。寒い地方で雪というものも見てみたい」
俺の話を聞きながら、少しずつレオの目が輝いていく。
それはそうだろう。レオは生まれてからこれまで、この領都周辺から離れたことがない。外の世界を一度も見たことがないのだ。憧れの思いがあるに決まっている。
「海や雪……うわぁ、見てみたいなぁ。カイルと一緒に、色々なものを見てみたい」
「だろう? 俺もだ。俺もレオと一緒にたくさんの初めてを経験したい。きっと楽しい旅になる!」
「そうだね、きっとすごく楽しい。あ、でも、お金が……ああ、そうか、働けばいいんだね。行った先の町や村で仕事を探して、働きながら旅をすればいいんだ」
「よし、そうと決まれば……レオ、旦那様に婚姻不承諾の手紙を出すんだ。そして、縁を切ってくれるようこっちから願い出るといい。本当に家族には未練はないんだな?」
「ないよ。僕はカイルさえいてくれれば、カイルが幸せそうにしてくれてさえいれば、どこにいようと幸せなんだ!」
薄茶色の瞳をキラキラと輝かせて、とても幸せそうにレオが言った。
相変わらず可愛いことを言ってくれる。
まったく、どれだけ俺を虜にすれば気が済むんだよ、レオ!
この後、レオは王都の侯爵に手紙を出した。
レオが断ると思っていなかったのだろう。婚姻の話はかなり進んでいたらしく、怒り狂った侯爵から何度か手紙で「我儘は許さない」などと高慢に命令されていた。しかし、その都度レオが丁寧に断りの返事を書いて送ったところ、ついに怒りを爆発させた侯爵から「もう親でも子でもない、我が領地から出ていけ!」という手紙が届いたことで、レオのこの領都での生活が終わりを告げることになった。
俺がヴァルトーシュに乗り込んでから、ちょうど二年が過ぎた頃のことだった。
それから一年間、領地を追われた俺とレオは、世界各国を旅してまわった。ロルフがいるから移動手段には困らないし危険もない。いざとなれば転移魔法も使えたし、馬車でのんびりと移動するのもまた楽しかった。
俺たちは二人で色んな物を見て、色んなことをして楽しんだ。時には野宿もしたし、逆に豪勢な宿に泊まったこともある。港で荷積みの労働も経験したし、居酒屋で給仕の仕事もやってみた。
どこに行っても誰からでも、レオはとにかく人に好かれた。誰もかれもがレオに親切にしたがり、仲良くなりたがった。
当然だ。レオは精霊の愛し子であることは勿論のこと、そうじゃなくても見た目はとんでもなく綺麗で可愛いし、愛想も良くて、いつも楽しそうににこにこ笑っている。
仕事は真面目で一生懸命で、少しドジなところも愛嬌があって良いと、力仕事以外のどんな仕事をしても褒められっぱなしだった。
皆からのあまりの好かれっぷりに、俺が嫉妬のあまり不機嫌になってしまうことも珍しくなく、そんな俺を見たレオが、少し照れくさそうに喜んでいたりするのがまた可愛らしくて、俺も結局は幸せ気分になってしまうのだった。
そんな風に、俺とレオが楽しく旅行を満喫している間、侯爵領で働くラッセに、俺はひとつの仕事を依頼していた。
今後もレオと一緒に暮らすに値する人間、信用できると俺が認めた人たちの一覧表をラッセに手渡してきた。そこに記された人たちに、あることを質問してもらい、その返事をもらうことが俺からの依頼内容である。
それは、今住んでいる侯爵領を出て、俺たちと一緒にヴァルトーシュで暮らすことを選ぶかどうかの返事をもらう、といったことだった。
その答えは、俺たちが一年かけて旅行している間に、ゆっくりと考えてもらうことにしている。
一覧表の中には、領主館の使用人、自衛団、孤児院、教会のシスター、と大体これだけの人の名が記されており、その家族も一緒に来たければ、勿論それは大歓迎だ。
移住先に仕事はいくらでもある。
俺たちが暮らす土地の候補として考えられているのは、国の西側にある寂れた一帯だった。
長く続いた戦争により、妖精から見限られ、疲弊した土地では作物が碌に実らず、借金が嵩んで首が回らなくなり、家が断絶してしまった貴族は多い。そういった没落貴族が治めていた土地は、管理する人間がいなくなったために一時的に国家預かりの直轄領となっている。
そんな荒れ果てた領地のいくつかを、全部まとめて俺が管理する予定になっていた。
今は人の手が入っていないために荒れているものの、元は広大な農地だった地域である。そういった土地は、いずれレオがその地を住処と定めさえすれば、あっと言う間に息を吹き返すに違いない。
となると、農業をする人間がたくさん必要になるし、人が増えれば生活に必要な様々な物資も増える。そして、それを作る人間や売る人間も必須だ。
他にも色々な技能技術を持った人間が必要になるだろう。そのために、孤児たちを多種多様な店へ修行へ出していたわけだ。彼らが上手く技術を習得してくれていればいいと思うが、まあ、足りない部分はたくさんあるだろう。
そういったところを少しずつ埋めていきつつ、自分たち好みの村に、そしていずれは町へとゆっくりと成長させていきたいと思う。
長年ロルフと一緒に地下資源を集めていたおかげで、資金だけは潤沢にある。正直言えばやりたい放題だ。レオが幸せに暮らしていけるよう、俺たちの村を素朴ながらも素晴らしい場所に皆で一緒に作っていきたい。
各地を巡る旅の途中、レオとは色々なことを話した。この旅の終わりにヴァルトーシュに住もうと思っていることも、侯爵領からも移住希望者を募ろうと思っていることも全部話した。
他にも、今後の展望やレオの望み、俺たちのこれからの夢。
俺たちはたくさんたくさん話をした。
レオはいつも俺の話を夢見るようにして聞き入り、幸せそうに微笑んでいた。
「僕がヴァルトーシュに住むことになるなんて、考えたこともなかったな」
「嫌か?」
「とんでもない、すごく楽しみだよ!」
「最初は足りない物も多いだろうし、不自由な点もあるかと思う。けれど、安心してくれ。絶対にレオのことは幸せにするし、俺たちの村を素晴らしい所にしてみせるから」
なにもない草原のど真ん中、結界を張った中にロルフのインベントリから取り出したフカフカの布団を敷き、そこに二人で寝っ転がって星を見ながらする未来の話は、俺たちをとても幸福な気持ちに浸してくれる。
「カイルが村長さんになるんだよね」
「俺としてはラッセさんになってもらいたいんだけどなぁ」
「それだと、ヴァルトーシュの貴族たちが納得しないんじゃない? やっぱり、村の代表はカイルじゃなくちゃ」
「そうかぁ。でも、村長になってもらうのは無理だとしても、俺たちの村に来てくれると助かるな。あの人、ものすごく有能だし」
「そうだね。父上と母上が王都で遊んでいられるのも、全部ラッセのおかげだったものね」
「その有能さを、今度は俺たちの村で発揮してもらいたい。あ、そうだ。レオが泣き落とせばいいんじゃないか? ああ見えて、すごく情に厚い人だから。レオのこと、すごく可愛がってたし」
「ラッセが可愛がってたのはカイルじゃないの?」
「だったら二人で可愛くおねだりするか」
「ふっ、ふふっ、ラッセ、すごく嫌な顔しそう」
「ははっ、目に浮かぶな」
満天の星空の下、二人して抱き合いながら幸せに笑った。
レオといると心が安らぐ。いつも癒されて心が満たされる。レオがいない世界なんて考えられない。生きていける気がしない。逆にレオさえいてくれれば、俺はどんな時だって幸せでいられる自信がある。
俺とレオはもうすぐ十八才になる。
もしかすると、なにかがほんの少し違っただけで、俺とレオを取り巻く世界は違うものになっていたのかもしれない。その場合、俺たちはいがみ合っていて、別の人を好きになっていたのだそうだ。
そんな世界じゃなくて良かった。レオを好きになれて、レオに好きになってもらえて本当に良かった。俺は心からそう思う。
俺はレオをまた抱きしめた。たったそれだけのことで、レオはとても幸せそうに笑う。触れた部分に伝わってくる優しい体温。これほど深く愛せる者がいるという幸せに胸が打ち震える。
ああ、たまらなく幸せだ。俺の幸福のすべてがレオのおかげだと実感する。
「来世も絶対一緒に幸せになろうな、レオ」
そう言うと、レオは可笑しそうにクスクス笑った。
「ん? どうした?」
「だ、だって……ふふっ」
レオは首を伸ばし、俺の首筋にちゅっと軽くキスをしてくれた。
「だって僕たち、まだこの世界でもっともーっと幸せになれるのに。もう来世のこと考えてるカイルがおかしくて」
「……そうか。もっと幸せになれるのか。ははっ、そうか! 今以上の幸せがまだ俺たちにはあるんだな! なんだか信じられないな、これ以上の幸せがあるなんて。でも、そうか、そうだよな! 俺たちはもっと幸せになれるんだな!」
「そうだよ。二人でもっといっぱい幸せになろうね、カイル。大好きだよ」
「俺も好きだよ、レオ」
こうやって、俺たちは毎日幸せを確かめ合い、更なる幸せを誓い合い、一日一日と穏やかに旅の日々は過ぎて行った。
そして旅を始めてから一年、俺たちは予定通りヴァルトーシュの西辺境付近、打ち捨てられた主なき土地へと移り住んだ。シャルロタの侯爵領からも、俺の誘いを受けて多くの人が移住してきてくれた。
誘った全員が来てくれたわけではなかったけれど、それでも十分心強い。
驚いたことに、ラッセも家族と一緒に移住してくれていた。
「当家は代々、侯爵様にお仕えしてきた家です。迷う気持ちもありましたが、あなた方のことが心配で放ってはおけませんでした」
「ありがとう、ラッセ! すごく心強いよ!」
「助かります、ラッセさん」
「今後はラッセと呼び捨てて下さいませ、旦那様。国王陛下より公爵位を賜ったのでしょう? ヴァルシュ公爵でしたか」
「便宜上仕方なく。ここの土地に対して権利を主張できるようにな。ただ、俺には子供はできないから、いずれは王家から養子をもらって、その子に後を継いでもらうつもりだ」
「ご、ごめんね、カイル。僕が女の子だったらカイルの子供を産めたのに……」
「バカだな、レオ。なに言ってるんだよ。子供なんていらないんだ。もしレオが子供を産めたら、レオはものすごくその子を可愛がるだろう? 俺はそれを想像するだけで嫉妬してしまう。レオには俺だけを好きでいてもらいたい」
「カイル……」
照れて真っ赤になってしまったレオ。すごく可愛くてたまらない。
呆れ顔のラッセの隣で、俺はこれ以上ないほどの満面の笑顔でレオの細い腰を引き寄せると、その柔らかい薄茶色の髪に何度もキスをした。
ヴァルトーシュにロルフと乗り込んでから、三年が過ぎた頃のことだった。
あれから更に一年が過ぎた。
ヴァルトーシュの王城へは、旅をする前から月に一度は必ず顔を出し、朝議に参加するようにしている。
今や即位して国王となった元第二王子のエイルレインを始め、宰相や貴族たちから、顔を合わせる度にレオを連れてきて欲しいと懇願される。
「国をあげて! 大々的に! 愛し子様をお迎えして歓迎の意をお伝えしたいんです!!」
「是非とも! お願い致します、カイル殿! いや、ヴァルシュ公爵!」
「あの時はシーツにくるまれたお姿だけでした。今度はぜひとも御尊顔を!」
「今はまだ無理だな。皆で必死になって村作りしているところだし」
「そんなっ、村作りなどいくらでもお手伝いしますから!」
「ダメダメ。手は出さないって約束だろう? 全部自分たちの手でやりたいんだ。勿論、手伝いが欲しい時はこちらから正式に依頼する。でも今はまだ、楽しみながら試行錯誤している段階だから。やり手領主の皆の目から見たらヤキモキするだろうが、温かく見守っててくれるとありがたい」
がっくり肩を落としてしまった国の中枢をなす面々に、流石の俺も少しかわいそうになってしまう。精霊の愛し子に彼らが会いたいと願う気持ちは分からなくもないからだ。
しばらく考えてから、俺は国王陛下に目を向けた。
「陛下の結婚式には、レオと二人で参加させていただこうと思います」
「そ、それは真ですか、カイル殿!」
「陛下、俺のことは呼び捨てで。俺も今やこの国の国民ですから、口調も改めて下さい」
「公式な場ならいざ知らず、ここではこれでいいんです。あなたは聖獣様の契約者なのですから。それに、我が国を立て直すきっかけを下さった恩人でもあります。精霊の愛し子様と等しく、あなたも我が国にとって特別な方なのです。あなたの方こそ、口調を元に戻して下さい。あなたにそんな丁寧な言葉を使われると、なんだかむず痒くなります」
「そんなこと言われても……」
「それよりも、本当に結婚式に二人で参列いただけるのですか?!」
「ああ、約束するよ」
「おおっ!!!!!」
その場にいた俺以外の全員が盛り上がった。
ヴァルトーシュ国王エイルレインとシャルロタ王国第一王女ベルティーヌの婚約が成立したのは、今から三年前のことになる。
レオが言うには、本来このベルティーヌ王女は俺と結婚するはずだったらしい。予言の書とは別の人生を生きている俺としたら、王女のことなんてどうでもいいことでしかない。しかし、その話をしてくれた時のレオが、どうみても嫉妬して泣きそうな顔になっていたので、俺は最高に幸せ気分になれて儲けたような気分だった。
その時のことを思い出しながら、結婚式に愛し子が参列することを喜ぶ貴族領主たちを微笑ましく見ていると、皆と一緒になって大喜びしていた宰相が、ハッとしたように我に返り、俺に書類を手渡してきた。そこには、シャルロタ王国のレオの父侯爵の領地についての報告が記されてある。
目を通した俺は意地悪く鼻で嗤った。
天候不順に疫病の発生、これまでなかった魔獣の出没など、今や侯爵領はボロボロである。しかも、今まで領地運営の全てを担っていたラッセはいないし、領地を守っていた自衛団だって数少ない。
レオがあの地を去ってまだ二年くらい。そうとは思えない程の酷い荒みようだった。
「円満に袂を分かったならともかく、精霊の愛し子様を無理に土地から追い出したのです。当然の報いでしょう。むしろ、まだマシな方なのではないでしょうか。いずれにせよ、かの地は精霊王様のお怒りに触れました。もう未来はないでしょう」
宰相の言葉に、俺は黙って頷いた。
本当だったら、俺の手で直接滅ぼしてやりたかった。しかし、それをすればレオが悲しむ。そう思って俺は懸命に我慢した。
きっと精霊王は胸のすく思いだろうな。それを思うと羨ましくてたまらない。
勿論、このことはレオには内緒にしておく。知れば優しいレオのことだ。なんとかしようと奮闘するかもしれない。俺だってレオに頼まれれば、あの地を助ける手助けをせざるを得なくなる。
けれど、俺は嫌だった。長年レオに悲しい思いをさせてきたあの土地に住む人間や、侯爵一家を助けたくなどない。むしろ酷い目に合えばいいと思っているくらいだ。
宰相の言った通り、あの領地はもう終わりだ。結果的に侯爵家もそう遠くない未来に断絶することになるだろう。
長年の胸のつかえが一つ取れた思いだった。
俺とレオは今、ヴァルトーシュの西側にある元王家直轄領に住んでいる。この地に俺たちが移り住んで、二年の月日が経とうとしていた。
本来、五年を試験期間として、ヴァルトーシュの各貴族当主や王族の努力する様を監視するつもりだった。しかし、彼らは俺が思っていた以上に有能だった。
二年を過ぎた頃には、ヴァルトーシュ王国内に徐々に妖精が戻り始め、その一年後にもなると、かなりの妖精たちが戻って来ていることが、俺やロルフの目には見てとれるようになっていた。
貴族たちの治める領地の様子や、王都に暮らす国民たちの様子を見ても、三年前とは同じ国と思えないくらい、その土地に暮らす人々の表情は明るくなっていた。
それを確認した俺は、試験期間を二年早く終了して、レオと共にヴァルトーシュへ移住する決意をしたのだった。
移住の時期を早めた理由はもう一つある。
それは、俺たちが暮らしていたシャルロタ王国の侯爵領での問題だった。
先に問題が起きたのは俺の方だ。
レオから聞いていた通り、レオの母親である侯爵夫人は、とにかく俺を貴族にしたいらしく、あの後すぐ俺の元に、貴族の養子になる件について書かれた手紙が送られてきた。
言うまでもなく、俺に養子になるつもりはない。だからそう返事をしたのだが、それから数ヵ月経っても、まだしつこく手紙が何度も届き続けた。養子に出ろ、貴族になれとあまりにも頻繁に届く手紙にうんざりした俺は、ついにラッセにあることを願いでた。
「奥様からの手紙があまりに煩いので、ハッキリお断りするため王都に行ってきます。それでお願いなんですが、王都に向かう旅の途中、俺は野盗に襲われて死んだことにしてもらえませんか。死体未発見で。この領地から遠く離れた場所、王都の近くで襲われた様に擬装して欲しいんです」
「……理由を説明してもらおうか」
「単純な話です。俺は貴族の養子になるつもりはありません。それなのに、断っても断っても養子をごり押ししてくる。もう面倒になったので、いっそ死んだことにしてしまおうかと」
「襲われる場所が王都近くがいいと言うのは?」
「奥様にはできるだけ領地に来て欲しくないんです。レオに会わせたくない。俺がこの付近で襲われたら、奥様は俺を探すために領地に来るかもしれない。それは嫌なんです」
領地に侯爵夫人が来るのは困る。腐っても貴族。この領地にやって来てレオに会ってしまえば、レオが精霊の愛し子であることに気づいてしまうかもしれない。それは困るのだ。知られてしまえば、すぐにレオを連れて逃げ出さなければならなくなる。
ヴァルトーシュに逃げたとしても、その後、レオがシャルロタの貴族子弟であることを盾に、所有権をシャルロタ側から主張されてしまうのは面倒だ。そうなる前に、レオが精霊の愛し子であることに気付かれないまま、侯爵家とはキッパリと縁を切り、レオを枷のない自由の身にしてあげたかった。
侯爵家の人間は、これまで少しもレオを顧みず、愛そうとはしなかった。そのクセ、レオに利用価値があると知れば、当然のことのように権利を主張してくるに決まっている。レオの気持ちなど少しも考えず、奴らなら躊躇なく、レオの利用価値だけを当たり前に欲しがるだろう。
それをされたら、今度こそ俺はキレる。絶対に侯爵家の人間を許さない。どんな残酷なことでもやってのける自信がある。しかし、それをするとレオが悲しむと知っているから、できるだけ穏便に事を進めたいと思うのだ。
「レオをそっちのけにして、俺を心配する奥様をレオに見せたくありません」
侯爵夫人に領地まで来て欲しくない理由をそう説明すると、ラッセはわずかに首を傾げた。
「お前は平民だ。なにも気にせず屋敷を出て行けばいいじゃないか。奥様には、わたしの方から失踪したと報告しておくが?」
「それをした場合、俺を失踪させたとして、ラッセさんが奥様に叱責を受けてしまいます。それは嫌なんです。それに、その場合も奥様はこの屋敷に来て、レオを蔑ろにしたまま俺を探せと騒ぎ立てるでしょう? 結局はレオが傷つく」
「なるほど、お前の言いたいことは理解できた。しかし……」
ラッセが俺を気づかうような、含みのある視線を向けてきた。
「本当にそれでいいのか。その処理を行った場合、お前の父上からの血筋が、この世から完全に途絶えることになるが」
やはりラッセは俺の出生の秘密について知らされていたらしい。
「気にしません。本家の血筋はあっちの国で続いていますし、俺はこれまで父の血筋を意識して生きたことはなかった。母だって死の間際に俺に言いました。自由に生きてくれ、と。だから俺は好きに生きようと思います」
「分かった。お前の望むように手配しよう。なにかお前のものと分かる品を渡してくれ。賊に襲われて壊れた馬車の中から見つかる品だ。お前が死んだことの証明になる」
俺はヴァルトーシュに行き、宰相に会った。そして、事の詳細を話し、父の形見であるペンダントをラッセに渡すつもりであることと、俺がもうヴァルトーシュの王族として生きるつもりがないことを伝えた。
宰相は残念がったものの、俺の意思を尊重してくれた。そしてその時、俺の父の母親であった前国王の正妃が、実は宰相の妹だったことを知らされた。父が幼かった頃、教育係を宰相が任されたのはその関係からだったらしい。
「だから、例え王族としての証がなくなったとしても、あなたは間違いなくわたしの身内なのです。困ったことがあったら、いつでも頼って下さい。息子に爵位は譲りましたが、これでも元公爵であり現宰相位に就いています。お力になれることはいくらでもあるでしょう」
そう言ってくれた宰相の言葉は、とても心強いものだった。
今後、ヴァルトーシュに居を移すことになった時、レオを守るための後ろ盾は少しでも多い方がいい。なにかあった時には、遠慮なく頼らせてもらおうと思う。
そんなわけで、俺はラッセに父の形見のペンダントを渡した。と同時に、王都の侯爵邸を訪ねる旨をしたためた手紙を侯爵夫人宛てに送った。
流石、敏腕執事のラッセは手際よく様々な手配を行ってくれて、一月後、王都への旅の途中で襲われた俺は、計画通りこの世の者ではなくなったのだった。
今や俺の形見となったペンダントは、侯爵夫人の手から母の実家である伯爵家へ届けられたらしい。
これにより、俺のシャルロタ王国でのしがらみは完全に消えてなくなった。
レオにはあまり詳しい話はしていない。死んだことにした、なんて言うと心配かけてしまうからな。その内話すこともあるかもしれないけれど、今はまだ内緒にしておこうと思う。
死んだことになった俺がどこで生活するようになったかと言うと、夜は勿論レオのベッドに潜り込んだが、それ以外の時は孤児院で過ごすようになった。
孤児院の子供たちは、いずれヴァルトーシュに連れて行くつもりでいる。共に働く仲間として期待している分、今の内に学べることは学んでもらおうと、俺はこれまでよりも力を入れて彼らに文字の読み書きや算術を教えていた。
ある程度まで勉強が身に付いた者たちには、実地により経験を積ませるため、色々な商店へと低賃金で仕事に出させている。
俺自身、午前中はレオと一緒に、ラッセから領地経営の基礎を学んでいる。ラッセは執事として優秀なだけに留まらず、領主代理の仕事をも侯爵から任されているのだ。
領主の仕事を覚えることは、いずれヴァルトーシュへと移住した際に必要となる知識の習得である。そう考えれば、仕事内容を覚えることは少しも苦にはならない。いずれすべてが俺とレオとの幸せに繋がるのだから、勉強に身が入るのも当然だった。
俺が死んだことになった日から約一年が過ぎ去った頃。今度はレオの方に問題が起こった。予測していた通り、レオに縁談が持ち上がったのだ。
相手はさる侯爵家の当主で、家格はレオの家とは同じでありながらも、血統の良さが格段に上の名門だった。建国当時から王家にも認められた国内屈指の名家であり、商売も幅広く行っている上に成功させているので莫大な資産もある。レオの家が強い繋がりを欲するのも当然の家だった。
当主の年齢は六十を少し過ぎたくらい。数年前に奥方を亡くしていて、嫡男に近々爵位を譲る予定らしい。
シャルロタ王国では同性婚が認められている。しかし、当然ながら子供ができない婚姻なので、貴族間での同性婚は、そのほとんどが政略結婚である。
今回レオにきた縁談のように、家を継ぐことのない貴族の次男や三男が、名門当主の後添えに嫁いだり、愛人として囲われる話は、特に珍しいものではなかった。
とはいえ、普通なら学園を卒業する十八才を過ぎてから嫁ぐものだが、レオは学園には入学していない。出来が悪い上に勉強の必要性が理解できず、学園への入学も拒否。領地にずっと籠っているため、人脈を広げるという活動さえできやしない。
そんなやる気のない役立ずな子供をさっさと名門他家に嫁がせ、少しでも家の役に立てようと考えたレオの両親の考えは、決しておかしなものではない。
しかし、当然ながら俺には受け入れられない話だし、それはレオにとっても同じである。
「ぼ、僕……け、結婚しろって言われるなんて、か、考えたことなかっ……」
王都の父親から届いた手紙を片手に、青褪めてぶるぶる震えるレオを、俺は安心させるように両腕で包み込んだ。
「大丈夫だよ、レオ。大丈夫」
「でもっ、だって! こっ、ここに書いてある! 結婚を承諾できないなら、か、勘当だって。縁を切るって。どうしよう、僕、か、勘当なんてされたらどうしたら…………あ!」
下を向いていたレオが勢いよく顔を上げ、俺と目を合わせて悲しい顔をした。
「ぼ、僕、どうしよう! 貴族でなくなったら、もうなにもなくなって、カイルのためになにもしてあげられない。もうなにも役に立てないよ。ど、ど、どうしよう!!」
ごめんなさい、ごめんなさいと泣きながら謝るレオを、俺は更に力を込めて抱きしめた。
「謝るな。レオはいるだけで俺の役に立ってる。だから心配するな」
「父上になんと言われても、結婚なんてできない。だから、もうここにはいられない。住む場所もない。カイルになにもしてあげられない。せめて迷惑にならないように、僕、こ、ここを出て一人でがんばって生きていくよ!」
「出て行くなら、俺も一緒に連れて行ってくれよな」
俺の言葉を聞いて、心底驚いたのかレオが飛び上がった。
「なっ、なに言ってるの?! カイルはヴァルトーシュに行かなくちゃ! 待ってくれてる人たちが、たくさんいるんでしょう?」
「まあな。でも、ヴァルトーシュに行く時はレオも一緒だ。それより、レオは結婚したくないから侯爵家を出るんだよな。未練はない? この領地から出ることになっても大丈夫?」
「それは……平気だと思う。未練はないよ。だって、僕にとってここはあくまでもカイルの故郷だもの。確かに領民の人たちのことは好きだけど、でも、カイルにとっての大切な場所って認識が一番大きいんだ。だからこそ、もっとここを発展させたいと思っていたわけだし」
「じゃあ提案。平民になってしがらみはすべて捨て去って、俺と旅に出ないか?」
「旅に?」
「ああ、世界中を旅してまわろう。レオと俺とロルフと緑の妖精とで。行ったことのない場所へ行って、珍しいものをたくさん見よう。色んな町に行って、色んな人にも会ってみよう。海も見てみたいな。寒い地方で雪というものも見てみたい」
俺の話を聞きながら、少しずつレオの目が輝いていく。
それはそうだろう。レオは生まれてからこれまで、この領都周辺から離れたことがない。外の世界を一度も見たことがないのだ。憧れの思いがあるに決まっている。
「海や雪……うわぁ、見てみたいなぁ。カイルと一緒に、色々なものを見てみたい」
「だろう? 俺もだ。俺もレオと一緒にたくさんの初めてを経験したい。きっと楽しい旅になる!」
「そうだね、きっとすごく楽しい。あ、でも、お金が……ああ、そうか、働けばいいんだね。行った先の町や村で仕事を探して、働きながら旅をすればいいんだ」
「よし、そうと決まれば……レオ、旦那様に婚姻不承諾の手紙を出すんだ。そして、縁を切ってくれるようこっちから願い出るといい。本当に家族には未練はないんだな?」
「ないよ。僕はカイルさえいてくれれば、カイルが幸せそうにしてくれてさえいれば、どこにいようと幸せなんだ!」
薄茶色の瞳をキラキラと輝かせて、とても幸せそうにレオが言った。
相変わらず可愛いことを言ってくれる。
まったく、どれだけ俺を虜にすれば気が済むんだよ、レオ!
この後、レオは王都の侯爵に手紙を出した。
レオが断ると思っていなかったのだろう。婚姻の話はかなり進んでいたらしく、怒り狂った侯爵から何度か手紙で「我儘は許さない」などと高慢に命令されていた。しかし、その都度レオが丁寧に断りの返事を書いて送ったところ、ついに怒りを爆発させた侯爵から「もう親でも子でもない、我が領地から出ていけ!」という手紙が届いたことで、レオのこの領都での生活が終わりを告げることになった。
俺がヴァルトーシュに乗り込んでから、ちょうど二年が過ぎた頃のことだった。
それから一年間、領地を追われた俺とレオは、世界各国を旅してまわった。ロルフがいるから移動手段には困らないし危険もない。いざとなれば転移魔法も使えたし、馬車でのんびりと移動するのもまた楽しかった。
俺たちは二人で色んな物を見て、色んなことをして楽しんだ。時には野宿もしたし、逆に豪勢な宿に泊まったこともある。港で荷積みの労働も経験したし、居酒屋で給仕の仕事もやってみた。
どこに行っても誰からでも、レオはとにかく人に好かれた。誰もかれもがレオに親切にしたがり、仲良くなりたがった。
当然だ。レオは精霊の愛し子であることは勿論のこと、そうじゃなくても見た目はとんでもなく綺麗で可愛いし、愛想も良くて、いつも楽しそうににこにこ笑っている。
仕事は真面目で一生懸命で、少しドジなところも愛嬌があって良いと、力仕事以外のどんな仕事をしても褒められっぱなしだった。
皆からのあまりの好かれっぷりに、俺が嫉妬のあまり不機嫌になってしまうことも珍しくなく、そんな俺を見たレオが、少し照れくさそうに喜んでいたりするのがまた可愛らしくて、俺も結局は幸せ気分になってしまうのだった。
そんな風に、俺とレオが楽しく旅行を満喫している間、侯爵領で働くラッセに、俺はひとつの仕事を依頼していた。
今後もレオと一緒に暮らすに値する人間、信用できると俺が認めた人たちの一覧表をラッセに手渡してきた。そこに記された人たちに、あることを質問してもらい、その返事をもらうことが俺からの依頼内容である。
それは、今住んでいる侯爵領を出て、俺たちと一緒にヴァルトーシュで暮らすことを選ぶかどうかの返事をもらう、といったことだった。
その答えは、俺たちが一年かけて旅行している間に、ゆっくりと考えてもらうことにしている。
一覧表の中には、領主館の使用人、自衛団、孤児院、教会のシスター、と大体これだけの人の名が記されており、その家族も一緒に来たければ、勿論それは大歓迎だ。
移住先に仕事はいくらでもある。
俺たちが暮らす土地の候補として考えられているのは、国の西側にある寂れた一帯だった。
長く続いた戦争により、妖精から見限られ、疲弊した土地では作物が碌に実らず、借金が嵩んで首が回らなくなり、家が断絶してしまった貴族は多い。そういった没落貴族が治めていた土地は、管理する人間がいなくなったために一時的に国家預かりの直轄領となっている。
そんな荒れ果てた領地のいくつかを、全部まとめて俺が管理する予定になっていた。
今は人の手が入っていないために荒れているものの、元は広大な農地だった地域である。そういった土地は、いずれレオがその地を住処と定めさえすれば、あっと言う間に息を吹き返すに違いない。
となると、農業をする人間がたくさん必要になるし、人が増えれば生活に必要な様々な物資も増える。そして、それを作る人間や売る人間も必須だ。
他にも色々な技能技術を持った人間が必要になるだろう。そのために、孤児たちを多種多様な店へ修行へ出していたわけだ。彼らが上手く技術を習得してくれていればいいと思うが、まあ、足りない部分はたくさんあるだろう。
そういったところを少しずつ埋めていきつつ、自分たち好みの村に、そしていずれは町へとゆっくりと成長させていきたいと思う。
長年ロルフと一緒に地下資源を集めていたおかげで、資金だけは潤沢にある。正直言えばやりたい放題だ。レオが幸せに暮らしていけるよう、俺たちの村を素朴ながらも素晴らしい場所に皆で一緒に作っていきたい。
各地を巡る旅の途中、レオとは色々なことを話した。この旅の終わりにヴァルトーシュに住もうと思っていることも、侯爵領からも移住希望者を募ろうと思っていることも全部話した。
他にも、今後の展望やレオの望み、俺たちのこれからの夢。
俺たちはたくさんたくさん話をした。
レオはいつも俺の話を夢見るようにして聞き入り、幸せそうに微笑んでいた。
「僕がヴァルトーシュに住むことになるなんて、考えたこともなかったな」
「嫌か?」
「とんでもない、すごく楽しみだよ!」
「最初は足りない物も多いだろうし、不自由な点もあるかと思う。けれど、安心してくれ。絶対にレオのことは幸せにするし、俺たちの村を素晴らしい所にしてみせるから」
なにもない草原のど真ん中、結界を張った中にロルフのインベントリから取り出したフカフカの布団を敷き、そこに二人で寝っ転がって星を見ながらする未来の話は、俺たちをとても幸福な気持ちに浸してくれる。
「カイルが村長さんになるんだよね」
「俺としてはラッセさんになってもらいたいんだけどなぁ」
「それだと、ヴァルトーシュの貴族たちが納得しないんじゃない? やっぱり、村の代表はカイルじゃなくちゃ」
「そうかぁ。でも、村長になってもらうのは無理だとしても、俺たちの村に来てくれると助かるな。あの人、ものすごく有能だし」
「そうだね。父上と母上が王都で遊んでいられるのも、全部ラッセのおかげだったものね」
「その有能さを、今度は俺たちの村で発揮してもらいたい。あ、そうだ。レオが泣き落とせばいいんじゃないか? ああ見えて、すごく情に厚い人だから。レオのこと、すごく可愛がってたし」
「ラッセが可愛がってたのはカイルじゃないの?」
「だったら二人で可愛くおねだりするか」
「ふっ、ふふっ、ラッセ、すごく嫌な顔しそう」
「ははっ、目に浮かぶな」
満天の星空の下、二人して抱き合いながら幸せに笑った。
レオといると心が安らぐ。いつも癒されて心が満たされる。レオがいない世界なんて考えられない。生きていける気がしない。逆にレオさえいてくれれば、俺はどんな時だって幸せでいられる自信がある。
俺とレオはもうすぐ十八才になる。
もしかすると、なにかがほんの少し違っただけで、俺とレオを取り巻く世界は違うものになっていたのかもしれない。その場合、俺たちはいがみ合っていて、別の人を好きになっていたのだそうだ。
そんな世界じゃなくて良かった。レオを好きになれて、レオに好きになってもらえて本当に良かった。俺は心からそう思う。
俺はレオをまた抱きしめた。たったそれだけのことで、レオはとても幸せそうに笑う。触れた部分に伝わってくる優しい体温。これほど深く愛せる者がいるという幸せに胸が打ち震える。
ああ、たまらなく幸せだ。俺の幸福のすべてがレオのおかげだと実感する。
「来世も絶対一緒に幸せになろうな、レオ」
そう言うと、レオは可笑しそうにクスクス笑った。
「ん? どうした?」
「だ、だって……ふふっ」
レオは首を伸ばし、俺の首筋にちゅっと軽くキスをしてくれた。
「だって僕たち、まだこの世界でもっともーっと幸せになれるのに。もう来世のこと考えてるカイルがおかしくて」
「……そうか。もっと幸せになれるのか。ははっ、そうか! 今以上の幸せがまだ俺たちにはあるんだな! なんだか信じられないな、これ以上の幸せがあるなんて。でも、そうか、そうだよな! 俺たちはもっと幸せになれるんだな!」
「そうだよ。二人でもっといっぱい幸せになろうね、カイル。大好きだよ」
「俺も好きだよ、レオ」
こうやって、俺たちは毎日幸せを確かめ合い、更なる幸せを誓い合い、一日一日と穏やかに旅の日々は過ぎて行った。
そして旅を始めてから一年、俺たちは予定通りヴァルトーシュの西辺境付近、打ち捨てられた主なき土地へと移り住んだ。シャルロタの侯爵領からも、俺の誘いを受けて多くの人が移住してきてくれた。
誘った全員が来てくれたわけではなかったけれど、それでも十分心強い。
驚いたことに、ラッセも家族と一緒に移住してくれていた。
「当家は代々、侯爵様にお仕えしてきた家です。迷う気持ちもありましたが、あなた方のことが心配で放ってはおけませんでした」
「ありがとう、ラッセ! すごく心強いよ!」
「助かります、ラッセさん」
「今後はラッセと呼び捨てて下さいませ、旦那様。国王陛下より公爵位を賜ったのでしょう? ヴァルシュ公爵でしたか」
「便宜上仕方なく。ここの土地に対して権利を主張できるようにな。ただ、俺には子供はできないから、いずれは王家から養子をもらって、その子に後を継いでもらうつもりだ」
「ご、ごめんね、カイル。僕が女の子だったらカイルの子供を産めたのに……」
「バカだな、レオ。なに言ってるんだよ。子供なんていらないんだ。もしレオが子供を産めたら、レオはものすごくその子を可愛がるだろう? 俺はそれを想像するだけで嫉妬してしまう。レオには俺だけを好きでいてもらいたい」
「カイル……」
照れて真っ赤になってしまったレオ。すごく可愛くてたまらない。
呆れ顔のラッセの隣で、俺はこれ以上ないほどの満面の笑顔でレオの細い腰を引き寄せると、その柔らかい薄茶色の髪に何度もキスをした。
ヴァルトーシュにロルフと乗り込んでから、三年が過ぎた頃のことだった。
あれから更に一年が過ぎた。
ヴァルトーシュの王城へは、旅をする前から月に一度は必ず顔を出し、朝議に参加するようにしている。
今や即位して国王となった元第二王子のエイルレインを始め、宰相や貴族たちから、顔を合わせる度にレオを連れてきて欲しいと懇願される。
「国をあげて! 大々的に! 愛し子様をお迎えして歓迎の意をお伝えしたいんです!!」
「是非とも! お願い致します、カイル殿! いや、ヴァルシュ公爵!」
「あの時はシーツにくるまれたお姿だけでした。今度はぜひとも御尊顔を!」
「今はまだ無理だな。皆で必死になって村作りしているところだし」
「そんなっ、村作りなどいくらでもお手伝いしますから!」
「ダメダメ。手は出さないって約束だろう? 全部自分たちの手でやりたいんだ。勿論、手伝いが欲しい時はこちらから正式に依頼する。でも今はまだ、楽しみながら試行錯誤している段階だから。やり手領主の皆の目から見たらヤキモキするだろうが、温かく見守っててくれるとありがたい」
がっくり肩を落としてしまった国の中枢をなす面々に、流石の俺も少しかわいそうになってしまう。精霊の愛し子に彼らが会いたいと願う気持ちは分からなくもないからだ。
しばらく考えてから、俺は国王陛下に目を向けた。
「陛下の結婚式には、レオと二人で参加させていただこうと思います」
「そ、それは真ですか、カイル殿!」
「陛下、俺のことは呼び捨てで。俺も今やこの国の国民ですから、口調も改めて下さい」
「公式な場ならいざ知らず、ここではこれでいいんです。あなたは聖獣様の契約者なのですから。それに、我が国を立て直すきっかけを下さった恩人でもあります。精霊の愛し子様と等しく、あなたも我が国にとって特別な方なのです。あなたの方こそ、口調を元に戻して下さい。あなたにそんな丁寧な言葉を使われると、なんだかむず痒くなります」
「そんなこと言われても……」
「それよりも、本当に結婚式に二人で参列いただけるのですか?!」
「ああ、約束するよ」
「おおっ!!!!!」
その場にいた俺以外の全員が盛り上がった。
ヴァルトーシュ国王エイルレインとシャルロタ王国第一王女ベルティーヌの婚約が成立したのは、今から三年前のことになる。
レオが言うには、本来このベルティーヌ王女は俺と結婚するはずだったらしい。予言の書とは別の人生を生きている俺としたら、王女のことなんてどうでもいいことでしかない。しかし、その話をしてくれた時のレオが、どうみても嫉妬して泣きそうな顔になっていたので、俺は最高に幸せ気分になれて儲けたような気分だった。
その時のことを思い出しながら、結婚式に愛し子が参列することを喜ぶ貴族領主たちを微笑ましく見ていると、皆と一緒になって大喜びしていた宰相が、ハッとしたように我に返り、俺に書類を手渡してきた。そこには、シャルロタ王国のレオの父侯爵の領地についての報告が記されてある。
目を通した俺は意地悪く鼻で嗤った。
天候不順に疫病の発生、これまでなかった魔獣の出没など、今や侯爵領はボロボロである。しかも、今まで領地運営の全てを担っていたラッセはいないし、領地を守っていた自衛団だって数少ない。
レオがあの地を去ってまだ二年くらい。そうとは思えない程の酷い荒みようだった。
「円満に袂を分かったならともかく、精霊の愛し子様を無理に土地から追い出したのです。当然の報いでしょう。むしろ、まだマシな方なのではないでしょうか。いずれにせよ、かの地は精霊王様のお怒りに触れました。もう未来はないでしょう」
宰相の言葉に、俺は黙って頷いた。
本当だったら、俺の手で直接滅ぼしてやりたかった。しかし、それをすればレオが悲しむ。そう思って俺は懸命に我慢した。
きっと精霊王は胸のすく思いだろうな。それを思うと羨ましくてたまらない。
勿論、このことはレオには内緒にしておく。知れば優しいレオのことだ。なんとかしようと奮闘するかもしれない。俺だってレオに頼まれれば、あの地を助ける手助けをせざるを得なくなる。
けれど、俺は嫌だった。長年レオに悲しい思いをさせてきたあの土地に住む人間や、侯爵一家を助けたくなどない。むしろ酷い目に合えばいいと思っているくらいだ。
宰相の言った通り、あの領地はもう終わりだ。結果的に侯爵家もそう遠くない未来に断絶することになるだろう。
長年の胸のつかえが一つ取れた思いだった。
応援ありがとうございます!
198
お気に入りに追加
8,163
1 / 5
この作品を読んでいる人はこんな作品も読んでいます!
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる