2 / 8
second
しおりを挟む王の部屋のあるフロアに珍しい来人がいた。
王のお気に入りの従者だ。
7年前に滅んだラルセント帝国の唯一の生き残りでありその後数々の戦場で紅き血を滴らせた悪魔。
『ラルセントの悪魔』
略して『ラルア』
ラルアを雇ったのは戦争に役立つ上に名前だけで他国への牽制材料となる。
その為に態々 王 自らが戦地に赴き交渉したのだ。
交渉内容は
・ラルアはエルリカに最強部族として名高かったラルセントの武術を伝授する
・王はラルアの生活費と地位、莫大な金を払い望むこと全てを叶える
だった。
しかしラルアは「生活費だけでいい」とぶっきらぼうに答えただけだった。
王はまさかの返事に歓喜し早速ラルアを迎え入れ、もう5年になる。
名を言わぬ少年に偽名を与えまだ12歳だったエルの武術の師につけた。
「…お呼びでしょうか。」
ラルアは戸惑っていた。王からのアプローチなど4年前から途絶えていたのにこのタイミングで何があるのだ、と。
「…さして難しい話ではない。エルリカの武術はどうだ」
しかしその問いを聞きラルアは察した。婚約者を探すつもりか、と。
この王家には試練があった。公の場で師に勝つこと。そうすれば1人前と認められる。
今までその年齢は平均して15歳頃だった。
しかし今、エルは17歳。確かに遅い。別にエルリカが弱いわけではないのだ。きっと歴代の王より遥かに強いだろう。しかし、問題は師なのだ。
ラルアが強すぎる。
それもそうだろう。戦闘力世界最強と謳われた帝国の生き残りであり齢10にして数々の名の知れた兵士を屠ってきたのだ。
戦場から離れようとその強さは依然として変わらない。
「エルリカ様はどんどんお強くなられております。私ももうすぐ追いつかれることでしょう」
嘘偽りなくラルアは本心を述べた。
エルは着々と強くなっている。自分はいつ負けるのだろうか、常に恐れている。
「そうか。…だがあまりに時間がかかりすぎた。次の武道会で態と負けてくれ。」
「はっ?」
気張っていたはずなのに一瞬で力が抜けてしまった。
今この人は何と言った?
次期王として大切な通過儀礼を侮辱するかのような発言にラルアは不愉快になった。
「できません。私は剣士です。剣において態と負けるなどエル様への無礼にあたります。」
剣士として、従者として、エルの恋人として、絶対に認める訳にはいかない案件だった。
その返答さえ分かっていたかのように王はさほど驚く様子もなかった。
「そうか。じゃあ死んでくれ。」
そして夕餉をリクエストする時のように何の緊張感もなく言い放った。
ラルアはますます困惑した。
「………あの…先程から…何を仰っているのか…失礼ながら理解出来かねますが……?」
いきなり死ねと言われてはい死にますとなる人はきっと限りなく少ないだろう。いやいないと思う。
「態と負けるのは嫌なんだろう?ならお前が死ねばエルリカの不戦勝だ。」
そういうことか、このクソジジイ。
ラルアは久しく感じていなかったどうしようもない憤りを感じた。
「…しかしそれではエル様はいつまでも半人前で終わってしまいます。」
エルリカの負けず嫌いな性格上、そのような勝ち方をしても嬉しくないだろう。まして2人は恋人なのだ。きっと嘆き悲しむだろう。
しかし、その返答さえも分かっていたかのように王は動揺しない。もうこれは決定事項なのだろう。
「じゃあここに致死量の毒液がある。それをお前が飲み、瀕死の状態でエルリカを暗殺に行け。エルリカはお前を殺すだろう。そうすれば自信もつく。」
この人はどこまで非道なことを思いつくのだろう。
どちらにしろラルアが死ぬことは決定のようだ。
「…………大変申し訳ございませんが、このお話はお受けできません。」
自分はまだ生きていたい。最後まで弟子の成長を見届けたい。出来ることなら死ぬ時まで愛しい人と過ごしたい。
こんなに生に執着するきっかけになったエル様にお礼をしたい。
しかし運命は変えられようがない。
だって抗えないから運命なのだ。ラルアは今夜死ぬ運命なのだ。それは揺るぎないことなのだ。
「……そういえばラルセントの悪魔よ。」
「………何でしょうか」
もう随分と聞いていなかった自分の異名はどこか威圧感を醸し出していた。
「噂ではエルリカと恋仲だと聞いたが本当か?」
身体の芯が一気に冷えた。
どこから、だれが、いつ、なぜ、そんな考えが巡る。
冷や汗が止まらなかった。
死ね、と命じられた時よりも関係がバレそうな今の方が圧倒的恐怖を感じていた。
「…本当では…ありません…」
声を震わせないよう気をつけながらラルアは答えた。
指先がありえないほど冷えてきた。
冷や汗が止まらない。
心臓の音がうるさい。
1秒が嫌になるほど長く感じる。
ゆっくりと王が口を開く。
意地汚い笑みを浮かべて。
「だよなぁ?だって俺の息子だもんなぁ?なれるはずねぇよな!?無理矢理レイプされた奴の息子なんてよォ!!」
先程までの威圧感を捨て去り、今度は違う恐怖がラルアに襲った。
屈辱的な日々を思い出し、思わず唇を噛み俯く。握りしめた拳がギリギリとなる。
悔しい。幼子の時であってもこんな奴に甚振られた自分が情けない。
「あいつには身体を見せたことあんのかァ?」
「…っありません……!!」
「それもそうだよなぁ!!」
ギャハハハハと大声で笑う姿は5年前と何も変わっていなかった。
身体など見せられるはずがない。ラルアの背には5年前王に入れられた家畜に押すための烙印が押されているのだ。
ぶっきらぼうで生意気だったラルアを躾するために食事に筋弛緩剤を入れ鎖で繋ぎ様々な凌辱を行った。
その傷は心身ともに未だラルアを辱め続けている。
「…っはぁ、おもしれー。でさ、毒飲んでエルリカ暗殺に行くかその背中をエルリカに見せて『僕は卑しい家畜以下の雄豚です。エル様の肉棒で僕のヒクヒク疼いている雄豚ケツマンコに突っ込んで下さい』って言うかどっちがいい?」
ラルアは青ざめた。
2つの選択肢に絶望したこともそうであるが、その台詞は昔言わされたことがあった。
エル様ではなく、目の前の王、リシア様の肉棒と。
『ああ、いいぜ?お望み通り突っ込んでやるよ、ただの棒だけどな!!』
そう言ってリシアはラルアの後孔にラルアの愛刀の柄を勢いよく刺したのだ。
奇しくもラルアの愛刀は珍しい型のもので鍔がなく、柄が普通の物より短かった。
そのため、ラルアが抜こうとすれば刀身で手が切れる。
すると追い打ちをかけるように『手を使わないで排泄するみたいに出せよ。そうすれば終わらしてやる。』と言ったのだ。
まだ純粋だったラルアは健気にその言葉を信じ、屈辱を受けながらも終わると信じていた。
ただの嘘だったけれども。
ラルアは覚悟を決めた。
「……っエル様を暗殺します…」
「お前ならそうすると思ったよ。相変わらず詰まんねぇ奴だなァ」
思わずラルアはリシアを睨みつけた。5年前の恨み、今の恨み、全ての負の感情がぐっちゃぐちゃに混ざりあい恐ろしい殺意としてリシアを射抜いていた。
リシアは少し怯んだがすぐにいつもの調子に戻った。
「良い目だな…!!」
リシアがニヒルに嗤った。
自室に戻りラルアは部屋の整理を始めた。
全ての物を廃棄する袋に纏め、申し訳程度に掃除もしておいた。
自分は今夜死ぬ。それなのにどうしてこんなに落ち着いているのだろうか。
エル様に見苦しい所を見せないで済むから?
やっとあの屑な王と永遠に離れられるから?
一族の元へ行けるから?
何を思ってもこれだ、という解答は出てこなかった。
自分は今まで何故生きてきたのか、それすらもラルアは分からなくなった。
何故なら8年前自分も一族と一緒に死ぬはずだった。
なのに自分はのうのうと今日まで生きてきた。
いつ死んでもおかしくなかった2年を戦場で過ごし金さえ貰えばどんな仕事も成し遂げてきた。
でもどこにいても暖かさなんてなくて皆ラルアを戦闘機と同じように扱う連中ばかりだった。
頼まれたからそれ以上の働きをしようと頑張って戦っただけなのに依頼した側は化け物を見るような目でラルアをみる。
その目が嫌いだった。
リシアの交渉を受け入れたのは彼の勧誘の際の言葉が嬉しかったから。
『君が今までどんなことをしていたって構わないさ。私の愛息子に君の綺麗な素晴らしい剣技を教えてやってくれないかな?もちろん報酬なら─』
皆があいつの剣は人殺しの剣だ、邪悪な剣技だ、野蛮だ、と罵って来る中で初めて褒められた。
幼い頃のラルアでもそれが本心でないと分かっていた。
分かっていたんだ。
しかし、修行から帰ると一族が皆死んでいて毎日戦場へ赴き人を斬り依頼人に薄気味悪がれる生活は9歳の少年にはとても耐えきれなかった。
だから嘘でも自分の剣を褒めてくれ尚且つ軽蔑の眼差しを向けなかったリシアの交渉を二つ返事で受け入れた。
凌辱されたときは戦場に帰りたいとまで願った。
しかしエルの笑顔を見るとここに来て良かったと心から思った。
思考が纏まらなくなりラルアは頭痛を感じた。
風に当たり落ち着こうと窓を開けると窓の外でエルが剣の型を練習しているのが見えた。
完璧とは言えないが随分と上達している。
その懸命な姿にラルアは胸が痛くなった。これで彼の剣技を見るのは最後なのだから。
そして唐突に紙とペンを取り一心不乱にペンを走らせた。
0
あなたにおすすめの小説

【完結】オーロラ魔法士と第3王子
N2O
BL
全16話
※2022.2.18 完結しました。ありがとうございました。
※2023.11.18 文章を整えました。
辺境伯爵家次男のリーシュ・ギデオン(16)が、突然第3王子のラファド・ミファエル(18)の専属魔法士に任命された。
「なんで、僕?」
一人狼第3王子×黒髪美人魔法士
設定はふんわりです。
小説を書くのは初めてなので、何卒ご容赦ください。
嫌な人が出てこない、ふわふわハッピーエンドを書きたくて始めました。
感想聞かせていただけると大変嬉しいです。
表紙絵
⇨ キラクニ 様 X(@kirakunibl)

貴族軍人と聖夜の再会~ただ君の幸せだけを~
倉くらの
BL
「こんな姿であの人に会えるわけがない…」
大陸を2つに分けた戦争は終結した。
終戦間際に重症を負った軍人のルーカスは心から慕う上官のスノービル少佐と離れ離れになり、帝都の片隅で路上生活を送ることになる。
一方、少佐は屋敷の者の策略によってルーカスが死んだと知らされて…。
互いを思う2人が戦勝パレードが開催された聖夜祭の日に再会を果たす。
純愛のお話です。
主人公は顔の右半分に火傷を負っていて、右手が無いという状態です。
全3話完結。

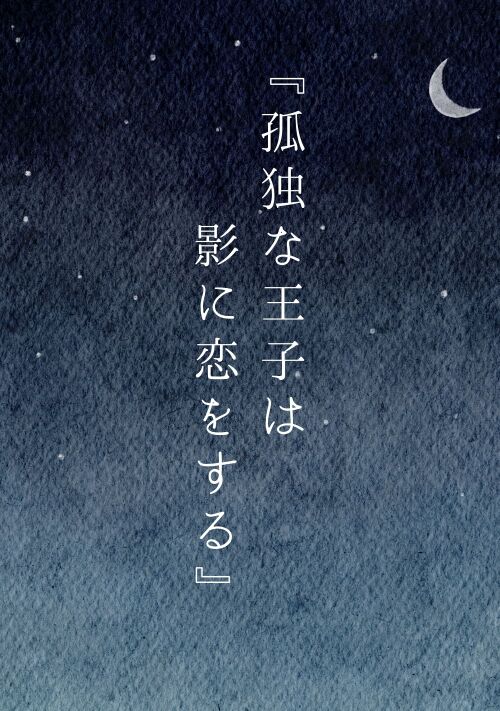
孤独な王子は影に恋をする
結衣可
BL
王国の第一王子リオネル・ヴァルハイトは、
「光」と称えられるほど完璧な存在だった。
民からも廷臣からも賞賛され、非の打ち所がない理想の王子。
しかしその仮面の裏には、孤独と重圧に押し潰されそうな本音が隠されていた。
弱音を吐きたい。誰かに甘えたい。
だが、その願いを叶えてくれる相手はいない。
――ただ一人、いつも傍に気配を寄せていた“影”に恋をするまでは。
影、王族直属の密偵として顔も名も隠し、感情を持たぬよう育てられた存在。
常に平等であれと叩き込まれ、ただ「王子を守る影」として仕えてきた。
完璧を求められる王子と、感情を禁じられてきた影。
光と影が惹かれ合い、やがて互いの鎖を断ち切ってゆく。

サラリーマン二人、酔いどれ同伴
風
BL
久しぶりの飲み会!
楽しむ佐万里(さまり)は後輩の迅蛇(じんだ)と翌朝ベッドの上で出会う。
「……え、やった?」
「やりましたね」
「あれ、俺は受け?攻め?」
「受けでしたね」
絶望する佐万里!
しかし今週末も仕事終わりには飲み会だ!
こうして佐万里は同じ過ちを繰り返すのだった……。

【16話完結】あの日、王子の隣を去った俺は、いまもあなたを想っている
キノア9g
BL
かつて、誰よりも大切だった人と別れた――それが、すべての始まりだった。
今はただ、冒険者として任務をこなす日々。けれどある日、思いがけず「彼」と再び顔を合わせることになる。
魔法と剣が支配するリオセルト大陸。
平和を取り戻しつつあるこの世界で、心に火種を抱えたふたりが、交差する。
過去を捨てたはずの男と、捨てきれなかった男。
すれ違った時間の中に、まだ消えていない想いがある。
――これは、「終わったはずの恋」に、もう一度立ち向かう物語。
切なくも温かい、“再会”から始まるファンタジーBL。
お題『復縁/元恋人と3年後に再会/主人公は冒険者/身を引いた形』設定担当AI /チャッピー
AI比較企画作品

禁書庫の管理人は次期宰相様のお気に入り
結衣可
BL
オルフェリス王国の王立図書館で、禁書庫を預かる司書カミル・ローレンは、過去の傷を抱え、静かな孤独の中で生きていた。
そこへ次期宰相と目される若き貴族、セドリック・ヴァレンティスが訪れ、知識を求める名目で彼のもとに通い始める。
冷静で無表情なカミルに興味を惹かれたセドリックは、やがて彼の心の奥にある痛みに気づいていく。
愛されることへの恐れに縛られていたカミルは、彼の真っ直ぐな想いに少しずつ心を開き、初めて“痛みではない愛”を知る。
禁書庫という静寂の中で、カミルの孤独を、過去を癒し、共に歩む未来を誓う。

happy dead end
瑞原唯子
BL
「それでも俺に一生を捧げる覚悟はあるか?」
シルヴィオは幼いころに第一王子の遊び相手として抜擢され、初めて会ったときから彼の美しさに心を奪われた。そして彼もシルヴィオだけに心を開いていた。しかし中等部に上がると、彼はとある女子生徒に興味を示すようになり——。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















