7 / 138
5月
1.
しおりを挟む
翌週の連休明け、今年は特にサークルが低調なのかまだ勧誘熱のさめやらぬ大学構内を抜けて、駅までの一本道を歩きはじめてすぐだった。
軽いクラクションの音に千晶が思わず振り返ると、例のジャケットを着た彼が車から降りてきた。
「すごい所だね」
千晶の出てきた場所は、高いコンクリート塀の更に上までカイズカイブキの緑の壁が続き、その奥に更に高い樹木がそびえていて外から塀の内側は伺い知れない。敷地全体をぐるっと囲むかたちで、年代を重ねた樹木は二三階建ての建物も隠していた。
開かれた門戸から見える、よくある鉄筋コンクリートの建物も古さと味気なさとで、昼夜怪しげな実験が行われている不気味さをその大学名が肯定しているように見える。
「まぁ……入ってみますかぁ?」
怪しさは否定しない。内部は普通のボロ校舎と運動場に薬草園でなんということはない、樹木は防風で植えられているのが巨木化しただけ。
にんまりと含みを持たせると無言で彼が助手席のドアを開けた。
車に乗せられて、ではなく、なんとなく乗ってしまったのだ。
どこへ行くとも聞かず言わず、連休後半から始めたばかりのバイトの疲れが残ってたからって、日暮れにはまだ早い適度な温かさの車内に、記憶があるのは二本目の橋を渡ったあたりまで。まさか寝ちゃうとは千晶自身も警戒心が無さすぎて呆れるばかり。
「…、…キ、着いたよ」
「ぅ…ん」
で、寝ぼけたまま、地下駐車場からそのままエレベーターへ。
着いたフロアに見覚えがある。
(まさか、ね、マンションの内装なんてどこも似たり寄ったりだもの)
アルミ製の黒いドアが開いて、ちらっと見えた風景にはっきりと覚醒した。クロス壁とリノリウムの床から一転、大理石貼の室内は、やっぱり来たことがあったと膝からくずれ落ちそうになる、のを踏みどどまってドアの前で固ま――
(でも私が顔を覚えていなかった位だし、そもそもこういう人はいちいち顔を覚ようとはしないだろうから)
――らずに秒速で記憶を封印した。やましいことは何もない。
(何でまたのこのこついてきちゃったかな。いやいやそういうつもりじゃなくてとか言うべき? そんなつもりで来たんじゃない、が通用するのは中学生まででしょ。高校生だって二度目の抵抗には使えない)
知りもしないの人の車に乗ることがおかしいのだ、いいや、知ってる人でも安心しちゃいけない、それは判ってる。でも、なぜか抗えない。そんな自問自答の結果。
「帰ってもいいかな?」
ためらう素振りでなく用事が済んだあとの確認のように、内開きのドアを手で抑えた彼のほうを向くことなく言った。
「だめ」どんな表情かはわからないが、強制するような声色ではない。
「そこはお茶だけでもって言う所ですよね」
「お茶くらい飲んでいってよ」
「お茶だけですよね」
「さぁ、どうかな」
「何もしないから、っていう一言はないの?」 無防備な自分を棚にあげて言う。
「変なことはしないよ」
やや高めの身長の千晶が目線を一段上げる程度に、彼の身長もまた平均より高かった。見合った目線はとても自然なものだった。なんの含みもない位。
*
危機感とか判断力とか学習しないのは、歴史にも経験にも学ばないのは、愚かを通り越して憐れだろうか。常識が崩れる何か、
直感でわかるならこの世に格言なんて生まれていないのに。
*
部屋は以前と同じだった。外に見えるビル群が少し変わったのと、引っ越し直後の段ボールがなくなっていたことだけ。
明るいマーブルの床に、黒い革のソファ、フレームと家具はウォールナット材、足元のシルクのカーペットに観葉植物。
千晶の家の一階部分がまるまると収まってまだ余裕があるだろう広さを意識させないのは、コの字のソファーは10人掛け、窓側のベンチソファも3×2、2×2人掛けが二面分と、ダインニングテーブルも8人掛けとカウンター席、部屋の広さに見合った人数の椅子があるからだ。
羽根を伸ばしたいから、そう一人暮らしの理由を口にしていたのに。モデルルームみたいな趣味の主張のない部屋からは今も念願の大学生一人暮らし感は全く感じられない。
「何のむ?」と尋ねた手には既にビールの瓶があった。アイランドキッチンの向こうのキャビネットにはグラス類に酒瓶がそれなりに並んでいる。「シャンパンもあるよ」
(飲むのか、お茶じゃないのかよ)
「トマトジュースがあれば飲みたいな」
「全部飲んじゃって」
無理難題で帰る口実にするつもりが、んー、もらいものがあったはず…と棚下から瓶入りを出してきた。しかも大瓶、900か1000cc。
「ジン?ウォッカ?」
「トマトジュースだけでいいよ」
もう一度冷蔵庫を開けレモンとライムを千晶に渡して、カッティングボードとナイフブロックを目でやる。切ってと言葉にしない男と勝手に櫛形に切る女。
彼は氷を入れたグラスを片手に、わざわざ千晶の後にまわりこんで首筋に顔を埋める。
「包丁を持った相手に勇気があるね」
「ふふ」
そのままビールともども目の前で栓が開く、無理に酒を勧める気はないようだ。ビールにライムを添え、氷を入れたグラスにトマトジュースを注いでレモンを絞る。
「医学生なんだって?」
(余計なこと言いやがって)会ったことすら黙っておけなかったのかあの優男め、喰えない人の予感は確信に変わった。
「うん、みえないでしょ」
「それはこれから変わっていくんじゃない?」
「そうかな」
なりたい姿と求められる姿、どちらに近づいていくのだろう。
「遅くなったけど、入学おめでとう」
高そうな瓶のトマトジュースはフルーツのように甘かった。
軽いクラクションの音に千晶が思わず振り返ると、例のジャケットを着た彼が車から降りてきた。
「すごい所だね」
千晶の出てきた場所は、高いコンクリート塀の更に上までカイズカイブキの緑の壁が続き、その奥に更に高い樹木がそびえていて外から塀の内側は伺い知れない。敷地全体をぐるっと囲むかたちで、年代を重ねた樹木は二三階建ての建物も隠していた。
開かれた門戸から見える、よくある鉄筋コンクリートの建物も古さと味気なさとで、昼夜怪しげな実験が行われている不気味さをその大学名が肯定しているように見える。
「まぁ……入ってみますかぁ?」
怪しさは否定しない。内部は普通のボロ校舎と運動場に薬草園でなんということはない、樹木は防風で植えられているのが巨木化しただけ。
にんまりと含みを持たせると無言で彼が助手席のドアを開けた。
車に乗せられて、ではなく、なんとなく乗ってしまったのだ。
どこへ行くとも聞かず言わず、連休後半から始めたばかりのバイトの疲れが残ってたからって、日暮れにはまだ早い適度な温かさの車内に、記憶があるのは二本目の橋を渡ったあたりまで。まさか寝ちゃうとは千晶自身も警戒心が無さすぎて呆れるばかり。
「…、…キ、着いたよ」
「ぅ…ん」
で、寝ぼけたまま、地下駐車場からそのままエレベーターへ。
着いたフロアに見覚えがある。
(まさか、ね、マンションの内装なんてどこも似たり寄ったりだもの)
アルミ製の黒いドアが開いて、ちらっと見えた風景にはっきりと覚醒した。クロス壁とリノリウムの床から一転、大理石貼の室内は、やっぱり来たことがあったと膝からくずれ落ちそうになる、のを踏みどどまってドアの前で固ま――
(でも私が顔を覚えていなかった位だし、そもそもこういう人はいちいち顔を覚ようとはしないだろうから)
――らずに秒速で記憶を封印した。やましいことは何もない。
(何でまたのこのこついてきちゃったかな。いやいやそういうつもりじゃなくてとか言うべき? そんなつもりで来たんじゃない、が通用するのは中学生まででしょ。高校生だって二度目の抵抗には使えない)
知りもしないの人の車に乗ることがおかしいのだ、いいや、知ってる人でも安心しちゃいけない、それは判ってる。でも、なぜか抗えない。そんな自問自答の結果。
「帰ってもいいかな?」
ためらう素振りでなく用事が済んだあとの確認のように、内開きのドアを手で抑えた彼のほうを向くことなく言った。
「だめ」どんな表情かはわからないが、強制するような声色ではない。
「そこはお茶だけでもって言う所ですよね」
「お茶くらい飲んでいってよ」
「お茶だけですよね」
「さぁ、どうかな」
「何もしないから、っていう一言はないの?」 無防備な自分を棚にあげて言う。
「変なことはしないよ」
やや高めの身長の千晶が目線を一段上げる程度に、彼の身長もまた平均より高かった。見合った目線はとても自然なものだった。なんの含みもない位。
*
危機感とか判断力とか学習しないのは、歴史にも経験にも学ばないのは、愚かを通り越して憐れだろうか。常識が崩れる何か、
直感でわかるならこの世に格言なんて生まれていないのに。
*
部屋は以前と同じだった。外に見えるビル群が少し変わったのと、引っ越し直後の段ボールがなくなっていたことだけ。
明るいマーブルの床に、黒い革のソファ、フレームと家具はウォールナット材、足元のシルクのカーペットに観葉植物。
千晶の家の一階部分がまるまると収まってまだ余裕があるだろう広さを意識させないのは、コの字のソファーは10人掛け、窓側のベンチソファも3×2、2×2人掛けが二面分と、ダインニングテーブルも8人掛けとカウンター席、部屋の広さに見合った人数の椅子があるからだ。
羽根を伸ばしたいから、そう一人暮らしの理由を口にしていたのに。モデルルームみたいな趣味の主張のない部屋からは今も念願の大学生一人暮らし感は全く感じられない。
「何のむ?」と尋ねた手には既にビールの瓶があった。アイランドキッチンの向こうのキャビネットにはグラス類に酒瓶がそれなりに並んでいる。「シャンパンもあるよ」
(飲むのか、お茶じゃないのかよ)
「トマトジュースがあれば飲みたいな」
「全部飲んじゃって」
無理難題で帰る口実にするつもりが、んー、もらいものがあったはず…と棚下から瓶入りを出してきた。しかも大瓶、900か1000cc。
「ジン?ウォッカ?」
「トマトジュースだけでいいよ」
もう一度冷蔵庫を開けレモンとライムを千晶に渡して、カッティングボードとナイフブロックを目でやる。切ってと言葉にしない男と勝手に櫛形に切る女。
彼は氷を入れたグラスを片手に、わざわざ千晶の後にまわりこんで首筋に顔を埋める。
「包丁を持った相手に勇気があるね」
「ふふ」
そのままビールともども目の前で栓が開く、無理に酒を勧める気はないようだ。ビールにライムを添え、氷を入れたグラスにトマトジュースを注いでレモンを絞る。
「医学生なんだって?」
(余計なこと言いやがって)会ったことすら黙っておけなかったのかあの優男め、喰えない人の予感は確信に変わった。
「うん、みえないでしょ」
「それはこれから変わっていくんじゃない?」
「そうかな」
なりたい姿と求められる姿、どちらに近づいていくのだろう。
「遅くなったけど、入学おめでとう」
高そうな瓶のトマトジュースはフルーツのように甘かった。
0
あなたにおすすめの小説

【R18】純粋無垢なプリンセスは、婚礼した冷徹と噂される美麗国王に三日三晩の初夜で蕩かされるほど溺愛される
奏音 美都
恋愛
数々の困難を乗り越えて、ようやく誓約の儀を交わしたグレートブルタン国のプリンセスであるルチアとシュタート王国、国王のクロード。
けれど、それぞれの執務に追われ、誓約の儀から二ヶ月経っても夫婦の時間を過ごせずにいた。
そんなある日、ルチアの元にクロードから別邸への招待状が届けられる。そこで三日三晩の甘い蕩かされるような初夜を過ごしながら、クロードの過去を知ることになる。
2人の出会いを描いた作品はこちら
「純粋無垢なプリンセスを野盗から助け出したのは、冷徹と噂される美麗国王でした」https://www.alphapolis.co.jp/novel/702276663/443443630
2人の誓約の儀を描いた作品はこちら
「純粋無垢なプリンセスは、冷徹と噂される美麗国王と誓約の儀を結ぶ」
https://www.alphapolis.co.jp/novel/702276663/183445041

【完結】退職を伝えたら、無愛想な上司に囲われました〜逃げられると思ったのが間違いでした〜
来栖れいな
恋愛
逃げたかったのは、
疲れきった日々と、叶うはずのない憧れ――のはずだった。
無愛想で冷静な上司・東條崇雅。
その背中に、ただ静かに憧れを抱きながら、
仕事の重圧と、自分の想いの行き場に限界を感じて、私は退職を申し出た。
けれど――
そこから、彼の態度は変わり始めた。
苦手な仕事から外され、
負担を減らされ、
静かに、けれど確実に囲い込まれていく私。
「辞めるのは認めない」
そんな言葉すらないのに、
無言の圧力と、不器用な優しさが、私を縛りつけていく。
これは愛?
それともただの執着?
じれじれと、甘く、不器用に。
二人の距離は、静かに、でも確かに近づいていく――。
無愛想な上司に、心ごと囲い込まれる、じれじれ溺愛・執着オフィスラブ。
※この物語はフィクションです。
登場する人物・団体・名称・出来事などはすべて架空であり、実在のものとは一切関係ありません。

人狼な幼妻は夫が変態で困り果てている
井中かわず
恋愛
古い魔法契約によって強制的に結ばれたマリアとシュヤンの14歳年の離れた夫婦。それでも、シュヤンはマリアを愛していた。
それはもう深く愛していた。
変質的、偏執的、なんとも形容しがたいほどの狂気の愛情を注ぐシュヤン。異常さを感じながらも、なんだかんだでシュヤンが好きなマリア。
これもひとつの夫婦愛の形…なのかもしれない。
全3章、1日1章更新、完結済
※特に物語と言う物語はありません
※オチもありません
※ただひたすら時系列に沿って変態したりイチャイチャしたりする話が続きます。
※主人公の1人(夫)が気持ち悪いです。

橘若頭と怖がり姫
真木
恋愛
八歳の希乃は、母を救うために極道・橘家の門を叩き、「大人になったら自分のすべてを差し出す」と約束する。
その言葉を受け取った橘家の若頭・司は、希乃を保護し、慈しみ、外界から遠ざけて育ててきた。
高校生になった希乃は、虚弱体質で寝込んでばかり。思いつめて、今まで養ってもらったお金を返そうと夜の街に向かうが、そこに司が現れて……。

俺様上司に今宵も激しく求められる。
美凪ましろ
恋愛
鉄面皮。無表情。一ミリも笑わない男。
蒔田一臣、あたしのひとつうえの上司。
ことあるごとに厳しくあたしを指導する、目の上のたんこぶみたいな男――だったはずが。
「おまえの顔、えっろい」
神様仏様どうしてあたしはこの男に今宵も激しく愛しこまれているのでしょう。
――2000年代初頭、IT系企業で懸命に働く新卒女子×厳しめの俺様男子との恋物語。
**2026.01.02start~2026.01.17end**
◆エブリスタ様にも掲載。人気沸騰中です!
https://estar.jp/novels/26513389

ちょっと大人な物語はこちらです
神崎 未緒里
恋愛
本当にあった!?かもしれない
ちょっと大人な短編物語集です。
日常に突然訪れる刺激的な体験。
少し非日常を覗いてみませんか?
あなたにもこんな瞬間が訪れるかもしれませんよ?
※本作品ではGemini PRO、Pixai.artで作成した生成AI画像ならびに
Pixabay並びにUnsplshのロイヤリティフリーの画像を使用しています。
※不定期更新です。
※文章中の人物名・地名・年代・建物名・商品名・設定などはすべて架空のものです。
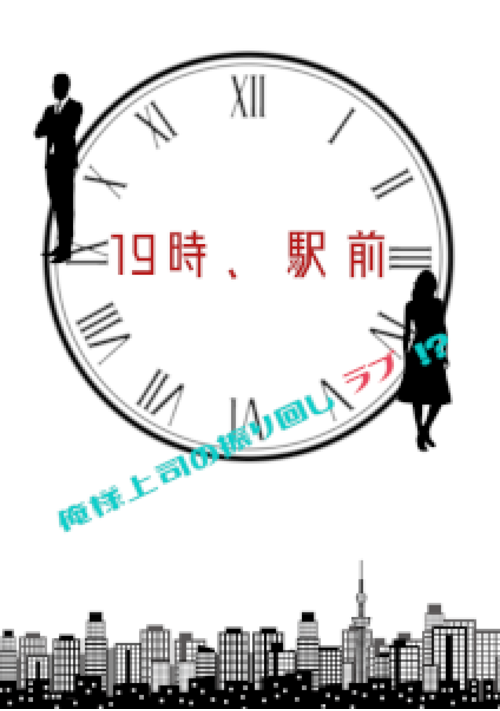
19時、駅前~俺様上司の振り回しラブ!?~
霧内杳/眼鏡のさきっぽ
恋愛
【19時、駅前。片桐】
その日、机の上に貼られていた付箋に戸惑った。
片桐っていうのは隣の課の俺様課長、片桐課長のことでいいんだと思う。
でも私と片桐課長には、同じ営業部にいるってこと以外、なにも接点がない。
なのに、この呼び出しは一体、なんですか……?
笹岡花重
24歳、食品卸会社営業部勤務。
真面目で頑張り屋さん。
嫌と言えない性格。
あとは平凡な女子。
×
片桐樹馬
29歳、食品卸会社勤務。
3課課長兼部長代理
高身長・高学歴・高収入と昔の三高を満たす男。
もちろん、仕事できる。
ただし、俺様。
俺様片桐課長に振り回され、私はどうなっちゃうの……!?

元恋人と、今日から同僚です
紗和木 りん
恋愛
女性向けライフスタイル誌・編集部で働く結城真帆(29)。
仕事一筋で生きてきた彼女の前に、ある日突然、五年前に別れた元恋人が現れた。
「今日から、この部署に配属になった」
そう告げたのは、穏やかで理性的な朝倉。
かつて、将来や価値観のすれ違いから別れた相手だ。
仕事として割り切ろうと距離を取る真帆だったが、過去の別れが誤解と説明不足によるものだったことが少しずつ見えてくる。
恋愛から逃げてきた女と、想いを言葉にできなかった男。
仕事も感情も投げ出さず、逃げずに選び直した先にあるのは「やり直し」ではなく……。
元恋人と同僚になった二人。
仕事から始まる新しい恋の物語。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















