2 / 42
第二話 平等という信仰
しおりを挟む
第二話 平等という信仰
マリアは、学院の回廊を一人で歩きながら、胸の奥に残る違和感をどうしても拭えずにいた。
朝の中庭で交わした、アリエノール・ダキテーヌ公爵令嬢との会話。その一つ一つが、頭の中で何度も反芻される。
――ここは、平等ではありませんわ。
その言葉は、静かで、穏やかで、決して人を傷つけるためのものではなかった。
それは、マリアにも理解できる。
理解できるからこそ、なおさら納得がいかなかった。
同じ机で学び、同じ教師の話を聞き、同じ課題を与えられている。
それなのに、なぜ最初から「違う」と決めつけられなければならないのか。
マリアは、聖堂で育った。
教会で教えられたのは、神の前ではすべての人が等しいという教えだった。
生まれや身分ではなく、行いと心が人を形作るのだと、何度も繰り返し聞かされてきた。
だからこそ、王立貴族学院に入学が決まったとき、彼女は希望を抱いた。
ここは、未来を担う者たちが集い、学ぶ場所。
ならば、理想が通じる場所なのだと、疑いもせずに信じていた。
「……おかしいわ」
思わず、独り言が漏れる。
学院の中では、誰もが礼儀正しい。
表向きの微笑みも、言葉遣いも整っている。
だが、その裏にある見えない線は、はっきりと存在していた。
席次。
会話の中心。
教師が名を呼ぶ順番。
どれもが、身分によって自然に決まっている。
マリアは、それを「古い慣習」だと思っていた。
変えていくべきものだと。
だから、恐れずに声を上げたつもりだった。
「みんな平等ですよね?」
その言葉が、あれほど場の空気を凍らせるとは、思っていなかった。
放課後、マリアは学院の礼拝室に立ち寄った。
静かな空間に身を置くと、心が少し落ち着く。
祈りの言葉を口にしながら、今日の出来事を神に委ねるような気持ちだった。
だが、祈れば祈るほど、アリエノールの言葉が浮かび上がる。
――それを知らずに前に出ることは、あなたを守ることにはなりません。
「守る……?」
マリアは首を傾げる。
誰から、何を守るというのだろう。
正しいことを言うのに、守られなければならない理由があるのだろうか。
彼女には、それが理解できなかった。
そのとき、礼拝室の扉が静かに開いた。
「ここにいたのか」
聞き覚えのある声に、マリアは顔を上げる。
そこに立っていたのは、ルイス王太子だった。
「殿下……」
慌てて立ち上がり、頭を下げる。
王太子は軽く手を振り、形式ばった礼を制した。
「そんなに畏まらなくていい。ここでは、誰も見ていない」
その言葉に、マリアは少し救われた気持ちになる。
彼は、他の貴族たちとは違う。
そう感じさせる何かがあった。
「どうした? 何か悩み事か」
マリアは一瞬、迷ったが、意を決して口を開いた。
「殿下は……学院は平等だと思われますか?」
ルイスは驚いたように目を瞬かせた後、すぐに笑みを浮かべる。
「もちろんだ。学ぶ場に、身分の差など持ち込むべきではない」
その即答に、マリアの胸が温かくなる。
「やはり、そうですよね」
「誰もが同じ学生だ。才能や努力で評価されるべきだろう」
ルイスの言葉は、マリアが信じてきた教えと重なっていた。
彼は王太子でありながら、理想を語ることをためらわない。
その姿が、まぶしく映る。
「でも……」
マリアは躊躇いながらも、続けた。
「アリエノール様は、違うとおっしゃいました」
その名を出した瞬間、ルイスの表情がわずかに曇る。
「彼女が?」
「はい。ここは平等ではない、と」
マリアは、あの場で感じた戸惑いと悲しさを、言葉を選びながら伝えた。
ルイスは黙って聞いていたが、次第に眉をひそめていく。
「それは……行き過ぎだな」
低く、しかしはっきりとした声だった。
「身分を理由に、人を遠ざけるなど、正しいはずがない」
その言葉に、マリアは強く頷いた。
「私も、そう思います。だから……」
「心配するな」
ルイスは断言する。
「そのようなことは、見過ごさない」
その瞬間、マリアの中で何かが確信に変わった。
正義は、ここにある。
自分は、間違っていない。
だがその確信が、どれほど危ういものかを、
彼女はまだ知らない。
礼拝室を出たあと、マリアは軽い足取りで廊下を歩いた。
背中には、守られているという安心感があった。
一方その頃、アリエノールは自室の机に向かい、静かに書類を読んでいた。
学院内の些細な動き。
生徒たちの関係性。
彼女はすでに、嫌な予感を覚えていた。
善意が、最も鋭い刃になることを。
理想が、現実を壊す引き金になることを。
それを知っているからこそ、
彼女はこれ以上、踏み込まなかった。
だが――
世界は、彼女一人の慎重さで止まるほど、優しくはない。
その夜、貴族学院は静かに眠りにつく。
平等という言葉が、
やがて国家を揺るがす重みを持つことも知らぬまま。
マリアは、学院の回廊を一人で歩きながら、胸の奥に残る違和感をどうしても拭えずにいた。
朝の中庭で交わした、アリエノール・ダキテーヌ公爵令嬢との会話。その一つ一つが、頭の中で何度も反芻される。
――ここは、平等ではありませんわ。
その言葉は、静かで、穏やかで、決して人を傷つけるためのものではなかった。
それは、マリアにも理解できる。
理解できるからこそ、なおさら納得がいかなかった。
同じ机で学び、同じ教師の話を聞き、同じ課題を与えられている。
それなのに、なぜ最初から「違う」と決めつけられなければならないのか。
マリアは、聖堂で育った。
教会で教えられたのは、神の前ではすべての人が等しいという教えだった。
生まれや身分ではなく、行いと心が人を形作るのだと、何度も繰り返し聞かされてきた。
だからこそ、王立貴族学院に入学が決まったとき、彼女は希望を抱いた。
ここは、未来を担う者たちが集い、学ぶ場所。
ならば、理想が通じる場所なのだと、疑いもせずに信じていた。
「……おかしいわ」
思わず、独り言が漏れる。
学院の中では、誰もが礼儀正しい。
表向きの微笑みも、言葉遣いも整っている。
だが、その裏にある見えない線は、はっきりと存在していた。
席次。
会話の中心。
教師が名を呼ぶ順番。
どれもが、身分によって自然に決まっている。
マリアは、それを「古い慣習」だと思っていた。
変えていくべきものだと。
だから、恐れずに声を上げたつもりだった。
「みんな平等ですよね?」
その言葉が、あれほど場の空気を凍らせるとは、思っていなかった。
放課後、マリアは学院の礼拝室に立ち寄った。
静かな空間に身を置くと、心が少し落ち着く。
祈りの言葉を口にしながら、今日の出来事を神に委ねるような気持ちだった。
だが、祈れば祈るほど、アリエノールの言葉が浮かび上がる。
――それを知らずに前に出ることは、あなたを守ることにはなりません。
「守る……?」
マリアは首を傾げる。
誰から、何を守るというのだろう。
正しいことを言うのに、守られなければならない理由があるのだろうか。
彼女には、それが理解できなかった。
そのとき、礼拝室の扉が静かに開いた。
「ここにいたのか」
聞き覚えのある声に、マリアは顔を上げる。
そこに立っていたのは、ルイス王太子だった。
「殿下……」
慌てて立ち上がり、頭を下げる。
王太子は軽く手を振り、形式ばった礼を制した。
「そんなに畏まらなくていい。ここでは、誰も見ていない」
その言葉に、マリアは少し救われた気持ちになる。
彼は、他の貴族たちとは違う。
そう感じさせる何かがあった。
「どうした? 何か悩み事か」
マリアは一瞬、迷ったが、意を決して口を開いた。
「殿下は……学院は平等だと思われますか?」
ルイスは驚いたように目を瞬かせた後、すぐに笑みを浮かべる。
「もちろんだ。学ぶ場に、身分の差など持ち込むべきではない」
その即答に、マリアの胸が温かくなる。
「やはり、そうですよね」
「誰もが同じ学生だ。才能や努力で評価されるべきだろう」
ルイスの言葉は、マリアが信じてきた教えと重なっていた。
彼は王太子でありながら、理想を語ることをためらわない。
その姿が、まぶしく映る。
「でも……」
マリアは躊躇いながらも、続けた。
「アリエノール様は、違うとおっしゃいました」
その名を出した瞬間、ルイスの表情がわずかに曇る。
「彼女が?」
「はい。ここは平等ではない、と」
マリアは、あの場で感じた戸惑いと悲しさを、言葉を選びながら伝えた。
ルイスは黙って聞いていたが、次第に眉をひそめていく。
「それは……行き過ぎだな」
低く、しかしはっきりとした声だった。
「身分を理由に、人を遠ざけるなど、正しいはずがない」
その言葉に、マリアは強く頷いた。
「私も、そう思います。だから……」
「心配するな」
ルイスは断言する。
「そのようなことは、見過ごさない」
その瞬間、マリアの中で何かが確信に変わった。
正義は、ここにある。
自分は、間違っていない。
だがその確信が、どれほど危ういものかを、
彼女はまだ知らない。
礼拝室を出たあと、マリアは軽い足取りで廊下を歩いた。
背中には、守られているという安心感があった。
一方その頃、アリエノールは自室の机に向かい、静かに書類を読んでいた。
学院内の些細な動き。
生徒たちの関係性。
彼女はすでに、嫌な予感を覚えていた。
善意が、最も鋭い刃になることを。
理想が、現実を壊す引き金になることを。
それを知っているからこそ、
彼女はこれ以上、踏み込まなかった。
だが――
世界は、彼女一人の慎重さで止まるほど、優しくはない。
その夜、貴族学院は静かに眠りにつく。
平等という言葉が、
やがて国家を揺るがす重みを持つことも知らぬまま。
3
あなたにおすすめの小説

【完結】もう…我慢しなくても良いですよね?
アノマロカリス
ファンタジー
マーテルリア・フローレンス公爵令嬢は、幼い頃から自国の第一王子との婚約が決まっていて幼少の頃から厳しい教育を施されていた。
泣き言は許されず、笑みを浮かべる事も許されず、お茶会にすら参加させて貰えずに常に完璧な淑女を求められて教育をされて来た。
16歳の成人の義を過ぎてから王子との婚約発表の場で、事あろうことか王子は聖女に選ばれたという男爵令嬢を連れて来て私との婚約を破棄して、男爵令嬢と婚約する事を選んだ。
マーテルリアの幼少からの血の滲むような努力は、一瞬で崩壊してしまった。
あぁ、今迄の苦労は一体なんの為に…
もう…我慢しなくても良いですよね?
この物語は、「虐げられる生活を曽祖母の秘術でざまぁして差し上げますわ!」の続編です。
前作の登場人物達も多数登場する予定です。
マーテルリアのイラストを変更致しました。

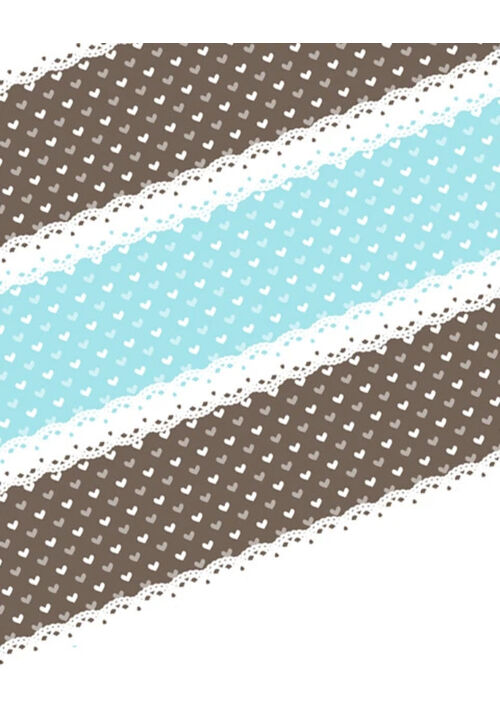
【完結】「私は善意に殺された」
まほりろ
恋愛
筆頭公爵家の娘である私が、母親は身分が低い王太子殿下の後ろ盾になるため、彼の婚約者になるのは自然な流れだった。
誰もが私が王太子妃になると信じて疑わなかった。
私も殿下と婚約してから一度も、彼との結婚を疑ったことはない。
だが殿下が病に倒れ、その治療のため異世界から聖女が召喚され二人が愛し合ったことで……全ての運命が狂い出す。
どなたにも悪意はなかった……私が不運な星の下に生まれた……ただそれだけ。
※無断転載を禁止します。
※朗読動画の無断配信も禁止します。
※他サイトにも投稿中。
※表紙素材はあぐりりんこ様よりお借りしております。
「Copyright(C)2022-九頭竜坂まほろん」
※小説家になろうにて2022年11月19日昼、日間異世界恋愛ランキング38位、総合59位まで上がった作品です!


悪役令嬢は手加減無しに復讐する
田舎の沼
恋愛
公爵令嬢イザベラ・フォックストーンは、王太子アレクサンドルの婚約者として完璧な人生を送っていたはずだった。しかし、華やかな誕生日パーティーで突然の婚約破棄を宣告される。
理由は、聖女の力を持つ男爵令嬢エマ・リンドンへの愛。イザベラは「嫉妬深く陰険な悪役令嬢」として糾弾され、名誉を失う。
婚約破棄をされたことで彼女の心の中で何かが弾けた。彼女の心に燃え上がるのは、容赦のない復讐の炎。フォックストーン家の膨大なネットワークと経済力を武器に、裏切り者たちを次々と追い詰めていく。アレクサンドルとエマの秘密を暴き、貴族社会を揺るがす陰謀を巡らせ、手加減なしの報復を繰り広げる。

欠席魔の公爵令嬢、冤罪断罪も欠席す 〜メイリーン戦記〜
水戸直樹
ファンタジー
王太子との婚約――それは、彼に恋したからでも、権力のためでもなかった。
魔王乱立の時代。
王も公爵も外征に出ている王都で、公爵令嬢メイリーンは“地味な婚約者”として王城に現れる。
だが、王太子は初顔合わせに現れなかった。
にもかかわらず、記録に残ったのは「公爵令嬢の欠席」。
抗議はしない。
訂正もしない。
ただ一つ、欠席という事実だけを積み上げていく。
――それが、誰にとっての不合格なのか。
まだ、誰も気づいていない。
欠席から始まる、静かなるファンタジー戦記。

婚約破棄の後始末 ~息子よ、貴様何をしてくれってんだ!
タヌキ汁
ファンタジー
国一番の権勢を誇る公爵家の令嬢と政略結婚が決められていた王子。だが政略結婚を嫌がり、自分の好き相手と結婚する為に取り巻き達と共に、公爵令嬢に冤罪をかけ婚約破棄をしてしまう、それが国を揺るがすことになるとも思わずに。
これは馬鹿なことをやらかした息子を持つ父親達の嘆きの物語である。

聖女追放 ~私が去ったあとは病で国は大変なことになっているでしょう~
白横町ねる
ファンタジー
聖女エリスは民の幸福を日々祈っていたが、ある日突然、王子から解任を告げられる。
王子の説得もままならないまま、国を追い出されてしまうエリス。
彼女は亡命のため、鞄一つで遠い隣国へ向かうのだった……。
#表紙絵は、もふ様に描いていただきました。
#エブリスタにて連載しました。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















