1 / 1
虹翡翠
しおりを挟む
『虹翡翠』
琥珀 燦(こはくあき)
第一章
イズム少年が猟銃を初めて手にしたのは九歳の時だ。その経験が早過ぎるのか、そうでもないのかは、
小さな村からほとんど出たことのないイズム自身、誰かと比べることはできないし、どうでもいいと彼は思っている。
彼に銃を手渡したのは鳥撃ち猟師として評判の高い父親だった。父のまた父親である祖父も、その父であるひいじいさんも、イズムの家の男は代々鳥撃ちで生計を立てていた。
ただ、イズムの父は生まれつき胸の病を患っていた。それでも、イズムの血筋の中では一番腕は良かったので、ぜいたくさえ望まなければ暮らしぶりは苦しくはなかった。
イズムにとっては小さい頃は、いっしょにくらしていた祖父と若い父が連れ立って猟の支度をする姿を見るのはワクワクするものだったし、祖父が病に倒れ、亡くなってからは、その少し細い身体のわりに、きたえられた腕で数本の猟銃を選び背負って出かけていく父の姿は誇りだった。
しかし、ある夜。突然、父はイズムを呼んだ。
「イズム、明日から、鳥撃ちを教える。一緒に来なさい」
虫取りしかしたことのないイズムは、それは驚いた。まだ九歳のほんの子どもだ。
その驚きはすぐ興奮にすりかわった。(俺は父さんに一人前に見てもらったんだ)
と。翌朝は早いから、すぐ寝るように言われても目はらんらんと開き、心臓がどきどきした。
初めての猟は、草原に立てられたわら束の的で、イズムは意気消沈した。しかし、それは直後、更に絶望に変わった。
「これがお前の銃だ。俺が最初に親父に持たされたヤツで、今もちゃんと手入れしている。
お前に銃の持ち方を教える日のために」と両腕に持たされた銃身の重さ。
音消しの耳当てで塞いでいたとはいえ、火薬が耳元で破裂する音の大きさに驚いたイズムは銃を持ったまま、後ろに吹っ飛んでしりもちをついた。
イズムの身体の震えは長い間止まらなかった。父は冷たく彼を見下ろしていたが、
やがてしゃがんで冷たい水の入った水筒をイズムの口に当てた。
「ゆっくり飲め。急ぐな。せき込むから」
そして、冷や汗まみれで震える息子の身体をしっかりと抱きとめた。
「イズム。いいか、俺の胸の病はもう治らない。俺はもう長く生きられない。
お前が、母さんと、妹を食べさせていくんだ。
鳥を撃って、必要な分だけ家族の食料として取り、残りは町へ行って売って、その金で暮らしていくんだ。俺は、死ぬまでにお前に俺の持っている技術のすべてをお前に教える。時間はそれほどない。覚悟しろ」
その前の日の猟で、父は血を吐いていたのだ。
それから半年の猛特訓の末、イズムは父に一人で猟に出る事を許された。
もともと血筋の良さもあったのだろうが、本当につらい修行の日々で、イズムの身体には大小の生傷が絶えず、しかしその小さな身体にはみるみるうちに筋肉が付き、やがて身長も伸びていった。たくましく成長していく息子の姿に満足そうな笑みを浮かべる父の身体は少しずつやせ細り、一年後、父は大量の血を吐いて死んだ。
第二章
イズムは今年、十三歳になった。村の外でも評判の鳥撃ちとして認められている。
ただし、今、彼は家族の為にわずかに食用の鳥を撃ち、大方の収入は、剥製用の珍しい鳥を撃つことで得ている。
今日も獲物の鳥を街の剥製屋に運び、夜遅く帰ってきたイズムの為に、サカが夕食を用意して待っていた。
「兄さん、どうして鳥が食べられないの? 母さんの鳥料理は美味しいのに」
妹のサカは十一歳、母親の手伝いもよくこなすが、勉強の好きな娘で、村人たちは
「あの娘はやがて村を出て街の学校へ行くだろう」と噂しているようだ。
「・・・わからない」
父に鳥を撃つ事を許され、初めて打ち落とした鳥が、不自然な形に翼を曲げ、
草の上に横たわりけいれんするのを見て以来、イズムは鳥肉が食べられなくなった。
「父さんだって、母さんの鳥料理は好物だって言ってたのに」
サカはイズムの好物のシシ肉のスープと野菜の煮物を揃える。
向かいに座ってイズムの様子を見ている母親が意を決して言う。
「イズム、お前はまだ十三だ。お前には重過ぎる仕事を背負わせていることは、
母さんもわかっているつもりだよ。
ただ、ちゃんと肉は食べないと、お前の身体は持たないよ」
「大丈夫だよ母さん。鳥を食べなくても、
ちゃんと川魚やシシ肉は食べてるじゃないか」
食欲は間違いなく旺盛な育ち盛りのイズムは、早いペースで食事をたいらげていく。
自分で食器を運びさっさと洗い、後片付けを済ませると、
「銃の手入れをして来る。街で新しい部品を買ってきたから、改造する」
と言い残し、部屋に向かおうとする。
「イズム。剥製のための猟はお辞め。父さんが一番嫌っていたことじゃないか」
うつむいたまま、強い口調で母親が言い放つ。
「剥製用の鳥撃ちは金になるんだ。サカの学費や、あの娘が将来嫁に行く時の費用にしたい」
「お前だって、学校に行きたいだろうに。銃を持つまでは、あんなに勉強が好きだったじゃないか」
辛そうに言う母に、イズムは静かに笑って答えた。
「俺は、いいんだよ。母さんやサカが少しでも幸せに暮らせるように金をかせげるのが、俺の幸せなんだ。
サカには街の大きな学校へ行って医者になる勉強をちゃんとしてもらいたいんだ。
父さんのような病気の人を助けられるように」
そして、扉の向こうに姿を消した。
「あんなに優しい子が、殺生の仕事など…」
母親は両手を組み、大きく溜め息をついた。
第三章
父親から譲られた、仕事場を兼ねた寝室で、
銃を分解し、部品をていねいに磨きながら、
イズムは今日呼ばれたある得意先の豪邸での会話を思い出していた。
「虹翡翠、ですか?」
数々の、鳥の剥製に囲まれた部屋で、出された熱い茶の湯気を嗅ぎながら、聞き返した。
部屋に並べられた剥製の半分はイズムの獲物で、今にも動き出しそうに翼を広げる様や、生きているかのような目の輝きなどは、鳥の皮膚の表面の傷を極力小さくするイズムの銃の技術とともに、隣に座っている剥製屋の腕の良さである。
一人暮らしの初老の大金持ちは、美しい色彩や形状を持つ鳥の剥製に囲まれたこの部屋で過ごすとき、最も安らぐと言う。そういう客の想いに応えるため、剥製屋も心をこめて丁寧な仕事をしている。
「名前は聞いたことがあるかな?」
いいえ、とイズムは首を横に振った。
「翡翠と言うと、カワセミの一種ですか?」
「ほう、やはりそういうことには詳しいんだね。普通の人はヒスイと聞けば宝石のメノウを思い出すが、あの石の色はカワセミの羽根の色を由来にしている」
依頼主は灰色の品良く手入れされたヒゲを撫でながら、まぶたを伏せて歌うように語る。
「しかし、虹翡翠がカワセミの仲間かどうかは不明なんだ。とにかく謎の多い鳥でね。
虹翡翠に詳しい者はなかなかいない。この鳥を近くで見たり、捕獲して観察した者がいないのだ。しかし飛んでいる姿を見た者は多く、
大きさはカワセミと同じくらいで、
全身の羽根は太陽の光の角度の加減で虹の七色に輝くという。数も少なくはなく、捕獲禁止の対象にはなっていない。ただ、知能が高くて捕獲できたものがいないのだ」
そして、彼は目を開き、穏やかに言った。
「ぜひ、手に入れたい。ただ、本当に小さく捕獲が困難な鳥なので、今回も、どうしても君の腕に頼るしかない。
やってくれるか? イズム君。報酬はいつも以上にはずむよ」
依頼を引き受けてすぐ、イズムはすぐ、街の図書館へ行き、虹翡翠に関する情報を調べ、
わずかながらも知識を得ることが出来た。
そして、銃の部品を売っている店へ行き、部品や弾を選び始めた。
(カワセミと同じ程度の大きさだとすれば、弾の大きさはほぼ針に近いほどの小さなものがいい。飛んでいる姿しか目撃されないとなると、どこかに止まっているところを狙うのは不可能だし、引き金を引くタイミングを計るのがかなり困難だから、長期戦は覚悟しなくてはならない。飛んでいる目標に即座に狙いを定めて、速度や方向まで、最小限の誤差内で正確に射弾するのに必要な部品は…)
イズムの自由になる範囲の小遣いは、
そういった銃のグレードアップのために遣われ、彼の旺盛な知識欲は、次の猟の成功の為の分析の作業に費やされる。そんな風に長い長い時間を、この部品屋で過ごすのは、
イズムにとっては充実したものである。
時々、独学で考え出した計算式を書き込んだメモを片手に、棚と棚の狭い隙間に座り込みながら、イズムは
(父さんもこんな時を過ごしていたんだろうか)
と考え、茶色い天井を見上げた。
(父さんは、俺の様に、食うためじゃなく、金のために、飾られる為だけのために鳥を撃ったことは無かったんだっけ)
父親が亡くなって1年ほどした頃、この銃の部品屋の店長に紹介されたのが、
今、イズムの獲物を買い取ってくれている剥製屋である。
彼に連れられて、あの大金持ちの依頼主の元へ行った。彼の剥製のコレクションへ傾ける、寂しくも愛情に満ちた視線を見て、
初回の仕事を引き受けて帰ると、母親の猛反対が待っていた。
「生き物は、すべて、他の命によって生かされている。我が家の人間たちは、生きていくのに必要な分だけの鳥を撃って、その肉のおかげで生かされているのだよ、イズム。父さんが、お前が高い報酬に目がくらんで、剥製撃ちになるなどと聞いたら、お前を殴って、すぐにでも鳥撃ちを辞めさせるだろうよ」
「でも、今回の仕事を母さんがどうしても止めるなら、俺は二度と銃を持たない」
イズムは頑として母親の反対にあらがい続けた。そして、翌日、母が起きるより早く起きた彼は、一人で支度をし、最初の剥製撃ちに旅立った。寝たふりをする母に気付かずに。
数日後、いつもより高額の報酬を得て帰ってきたイズムは、家族の分の食肉の包みと、
報酬の入った袋を母親にいつものように手渡した。
母親はいつもより、厳かな顔で、それらを受け取った。
それから何度、こんな猟を続けただろう。
母親とイズムの会話は、彼が剥製撃ちを始めてから急激に少なくなった。
たまに母親はさっきのように、
「父さんは剥製撃ちを嫌っていた、剥製撃ちはお辞め」と説得を試みるが、
イズムは一切聞き入れなかった。
父を亡くした時、わずか七歳だった妹のサカが言った
「わたし、お医者さんになりたい。わたしが、とても腕のいいお医者さんだったら、お父さんを助けられたかもしれない」
という言葉が、頭から離れなかったからだ。
第四章
虹翡翠がよく見られるという山は街に出て、列車で二時間、そこから乗り合いバスに揺られた終点が山のふもと。そして、目撃情報の多いポイントまで猟銃一式と野宿のための道具を背負って三時間ほど歩く。長い道のりだが、体力と経験には自信があった。
携帯食糧と川の水で急いで食事を済ませると、荷物は木の根元に隠した。夕暮れまでまだ時間はある。今から野宿の支度をしても、空から見れば「ここは危険」と知られるだけだ。ひとまず高い草むらに身をかがめ、大空を仰ぐ。
ここまで、猟のために遠出をしたのは初めてだった。今までにも、めずらしい鳥を探すために野宿を行いながら長期戦で粘ったことはあるが、この山に来たのは初めてだ。父親は家の近所の裏山で、必要な食料の為の猟しかしなかったから、泊りがけが必要なことは無かった。野宿を張ってまでして猟を行うのは自分の代からなので、アウトドアやサバイバルの知識も独学で学んだ。
(空が、高いなあ)
そんなことを思うのも、初めてではない。しかし、この山の青空は本当に、抜けるように美しくどこまでも青かった。イズムはそっと草の中に仰向けに横たわった。
そろりそろり、大きく両腕を広げる。秋晴れの空に、落ちていくような錯覚に、一瞬陥る。大地と空が逆転する。
そう思った瞬間、赤い光がシュッと空高く走った。残光は細く鋭い緑色で弧を描いた。
あ!
こんなに簡単に発見できる場所に…あれが虹翡翠?
しかし、凄いスピードだった。あれは、確かに今まで見た中でも難しい標的の部類に入る。
耳元で、背負った銃のチャリッと冷たい音がした。そうだ。俺は空に同化して生きる者ではない、地面から、空に生きるものを狙う者。
イズムは座り込み、一番弾の小さくスピードや照準を正確に合わせやすい銃を手に取り、次のチャンスを待った。
虹翡翠は、その日のうちにも、何度もイズムの視界を掠めた。物凄いスピードで。チカリ、と青や黄色や紫の光を残しながら。
イズムは数回、構えた銃の引き金に手をかけたが、すぐに、撃ち落とすのは困難だと判断し、しばらく虹翡翠の行動を観察することにした。
やがて、イズムは何となく、思った。
(俺の方も観察されている?)
今までの猟では、自分が、隠れる、というよりも、自然の中に溶け込み、相手を油断させれば、相手は自分のペースで行動を始め、必ず隙が出来る。そこを狙えば、一発だった。
しかし、何となく、今回は直感した。「観察」されている、と。虹翡翠は高い知性の持ち主で、捕獲が難しいとは聞いていたが、もしかしたら、それは人間並みの物なのではないだろうか?
そう思った瞬間、イズムの目の前五十センチの距離を、バサバサと音を立て、真珠色の羽根が通り過ぎた。
イズムはあっけにとられた。(からかわれている…?)
イズムは仕方なく、周りをちょろちょろ走っていたイタチを一匹だけ撃って、夕食の準備にかかった。生きる為に他の命を奪うのは、気持ちのいいものでは決してないが、もう慣れてしまった。
(だけど、なぜ鳥だけは?)
獲物をさばいて得た肉と血液で空腹を満たしながら、改めてイズムは考える。
寝袋に入り、満天の星空に包まれて眠れば、青空に落ちる夢を見る。風をシャツにはらませて、どこまでも果ての無い空への、永遠の下降。冷や汗をぐっしょりかいて、目覚めて思った。昼間見た、あの青空のせいだ。
第五章
イズムは二日目にして困惑していた。たぶん、昨日ここを飛び回っていた虹翡翠は一羽。相手は、自分の存在を知っている。知っていて、逃げようともせず、自分の存在を誇示して見せるような行動を取る。そんな相手をどうやって捕まえる? 完全に身を隠して、何とか相手を油断させ、隙を狙う…万に一つどころの可能性ではない。まるで人間同士の腹の探り合いだ。
食料になりそうな鳥も何回も空を過ぎった。猟に慣れたイズムにとってはスローモーションの動きに感じるが、それには一切目を向けない。そういうイズムの行動を見守るように、七色の光を持つ小鳥は、その日も数回姿を見せた。
頭脳戦になる猟も何度か経験したが、こんな相手は初めてだ。今までは常に標的に対して、自分は優位に立っていられたから、余裕を持って考え、行動して切り抜けた。しかし、今回はまるで人間相手の心理作戦だ。そして、それは家族や仕事の上で出会う少人数の人間関係の中で生きてきたイズムには弱点の一つだ。
困り果てながら三日四日が過ぎていった。人間を警戒して、すっかり近くから動物たちも姿を消してしまった。
携帯食糧と川の水で飢えを満たしながら、(俺は、子どもだ)と強く感じた。俺は小さい。この空の下で、俺は小さくて、何と頼りない存在だろう?
そんなイズムの頭上を鳥たちは何度も通り過ぎたが、鳥だけは食料として撃つことは出来ない。
虹翡翠の姿を見る度に銃を構えてみるが、無駄な抵抗だと、わかり始めていた。
(俺は何をしているんだろう?)
一週間目、イズムは仰向けになって空を見上げていた。夕べは予測し得ない激しい雨にやられ、木の下に避難しても、足元を浸し続ける水が体力を奪い、食料も、もう尽きかけていてる。今まで、依頼された獲物を諦めたことは無かった。しかし、これは無理だ。今の自分はどう考えても負けている。勝算は無い。しかも引き返す機会を見逃し、もう帰る体力さえも残っていない。鳥撃ちを職業として父親から正式に受け継いで以来初めて、イズムは子どものように泣きたくなった。
『あなたが鳥を食べられないのは、あなたが翼を持たぬ者だからよ』
声が、する。美しい鈴のような声。胸の奥に直接響く声。横たわったまま、まぶたを開くと、目の前に小さな鳥がいて自分の顔をじっと見つめていた。
(虹翡翠?)
形は、ごくありきたりの愛らしい小鳥だったが、その全身を覆う羽根の色の美しさ。白、というか真珠色というか、そんな色がベースなのだろうが、それを認識する前に七色と言うだけでは表現できない様々な色のきらめきが目に飛び込んでくる。
「お前が、虹翡翠か。言葉を話すのか?」
『私はあなたの心に直接心を伝えているだけ』
「へえ、便利だな」
イズムは口元だけで力なく笑った。虹翡翠は笑いもせず(鳥に笑顔があるかどうかは知らないが)こちらを見ている。その目は、底のない、漆黒だ。
『私には、あなたの過去が見えるのよ。今まで生きてきた生き様まで。最初の日に、あなたの近くを飛んだでしょう? あの時、あなたの記憶を全部見たのよ』
「それで、最初の日から俺をからかい続けたわけか」
『まさか、作戦の見込みも立たないまま、ここまで粘るおバカさんだとは思わなかったのよ。どうして途中で諦めて帰らなかったのよ。どうして、私たちの仲間を獲らなかったの? きっかけはいく度でもあったのに。あなたは生きる為に狩りをしているんじゃないの?』
「あいにくと、俺はそうじゃない。鳥の肉は苦手だしね」
『あなたたち人間は、食べるためにだけ獣を撃つのではないの?』
呆れ果てた様子で、虹翡翠が小首を傾げた。
『それなら、猫にでも捕まって食べられる方がまだ納得がいくわ』
「お前は、食べられる為に殺されるのが怖くないのか?」
『怖いに決まってるでしょ? 猫なんて、ハンターとしては人間のあなたなんかよりどれだけ小賢しいか。それでも、他の命の糧として血肉を奪われる方が、人間の屋敷に飾られる為に死ぬよりずっと、まし。あなた達の言葉で、食物連鎖って言うんでしょ? こういう決まりごと。私たち獣はそんな言葉無くても、生まれたときから、そういう決まりごとはちゃんと知っているのよ』
虹翡翠は小さな翼をはためかせながら青白いくちばしをパクパクさせた。薄紅色の光の粒子がパッと散る。ああ、怒ってるんだなあ、こいつ、ということはイズムにも漠然とわかった。
『私にはわからないのよ。あなたの記憶の中にあった、剥製っていうもの? はらわたと肉を捨てて、死骸を空っぽにして、つめものなんかして、わざわざ生きている姿に似せて再現して飾って…』
「それは、人間が寂しがりだからだ。美しいものをいとおしんで、絶対に逃げない状態で、周りに置いておきたい、そうでないと安心できない」
『変なの。死体をいっぱい飾ってるより、生きてさえずって、はばたく鳥と仲良く共存した方が幸せに決まってるじゃない』
「いつまでも、友達でいられるわけじゃないじゃないか。鳥は翼を持って、いつでも気まぐれに逃げ去ってしまう…人同士だってそうだ。いつまでも一緒にいられる保障は無い。ケンカ別れならともかく、それこそ、死が突然かけがえのない存在に翼を付けて天へ連れ去ってしまうこともある。それなら、偽せ物であっても、生前の美しい姿を残したまま、死体でもそばに置いておける方が幸せな人間だっているんだ」
イズムは、さして体力が残っていないはずの体で自分がどうしてここまで饒舌(じょうぜつ)になっているのかわからなくなっていた。あるいはもう、自分も心の声で話しているのを、虹翡翠が読み取ってくれているのかもしれない。
「俺だって、美しいものは好きだ。美しいものを手元に置きたい人の気持ちもわかるし、
その為に高い金を払ってもいいという金持ちの気持ちもわかる。そういう生活をするために、奴らは努力して金持ちになったんだろうから。人間の中には、死に至る病にかかったかけがえのない存在を、その病気を治せる技術が生まれる未来まで、冷凍して保存する者もいるという位だ。そこまでは俺にも理解は出来ないが、まあ、死んだ父さんの写真を片時も手放さない母さんも、あまり変わらないかもな」
『あなたは、私を、美しいと思うの? だから、私を撃ち獲りたいの?』
「ああ。こんなキレイなもの、見たことがない。いつまでも見ていたいよ…けど」
けど、意識が薄くなってきた。俺も、ここで死ぬんだろうか。そうしたら、この身体は野獣たちに食いちぎられて大地の中に溶け去り、魂は…父さんのところへ行けるのだろうか?
『あなたはなぜ鳥を撃つの? 他に生きる手段なんていくらでもあるし、第一、あなたまだ子どもじゃないの』
虹翡翠の質問は弱った意識にも容赦は無い。
「父さんから託された唯一の形見だから。この銃と、鳥撃ちの技術は。…父さんの気配や名残を俺の中に残すには、鳥撃ちの血筋を絶やさないようにすることしかなかったんだ。俺には他の道を選ぶ余裕なんてなかった」
『イズム…教えてあげるわ。あなたが鳥を食べられないのは、翼を持つ物があなたの最後の希望だから。あなたは飛びたいのよ。目指す場所がどこなのかは、私にもわからないけれど』
虹翡翠の真っ黒いつぶらな瞳がイズムをじっと見つめる。イズムには、この鳥のキラキラと絶え間なく変化し続ける翼の色よりも、この揺るがない瞳の漆黒の方がいとおしく感じられるのが不思議だった。
「そうか…自由への憧れの反動が、俺に鳥の肉を受け付けさせなかった、と」
イズムは横を向いていた顔を、やっとの力で仰向かせた。雨上がりの空に長く大きな虹が消えかかる瞬間であった。
その時、虹翡翠の凛とした声が、心に、いや、イズムの体中に響いた。
『私の肉を食べなさい。あなたの血肉として私は生きることに、たった今、決めた』
「何を言い出すんだ?」
『気に病むことはないわ。同種間の動物も飢えれば共食いをするし、人間だって色々事情が有って、生きる為に、やむを得ず殺し合うこともあるでしょう? 私も食物連鎖の中で死んでゆくのでなくては、納得が出来ない』
イズムの心が、震え出す。
「こんな風に言葉を交わしてしまった相手を撃って食えというのか?」
『ええ、私を撃ちなさい。あなたのような存在を生かす為になら、この命を捧げてもいいと思う』
「…こんなに近くで撃っては、その皮膚に大きな傷がついて売り物にならないんだ」
イズムの心が、空笑いをするように言った。すると、虹翡翠は
『そうだったわね。わかった。じゃあ』
とだけ言い残して、すっくりと天を仰ぎ、翼を広げ、すうっと地を離れた。
次の瞬間、ぱーん。晩秋の空に、透き通った破裂音が響いた。
動く体力など残ってなかったはずの体が反射的に銃を取り、空を舞う小鳥目掛けて引き金を引いていたのだ。
(虹翡翠!)
銃を投げ捨て、よろける身体を引きずりながら、光る点が弧を描いて落ちた地点を目指して歩み寄った。
草むらの中にまだ光を放ちながら、その小さななきがらはビクリとも動かなかった。針のような銃弾が心臓を一突きしている。イズムはそのなきがらを両手でそっと抱き上げ、無表情でつぶやいた。
「今まで、何も考えず、依頼された鳥をただ撃ち続けてきた。…殺したくないと思ったのはお前が初めてだよ。虹翡翠」
そのまま、地面に膝をつき、イズムは気を失った。
銃弾の音をたまたま聞きつけて、興味本位で近づいてきた、その山村の住人にイズムは救出された。
驚いて集まってきた村人たちに近くの療養所に担ぎ込まれたが、幸い風邪をこじらせかけていたのと、栄養失調だけという診断であった。
ただ、イズムは気を失っている間も、固く握り締めた両手を決して開こうとせず、村人や医者を困らせたという。イズムは誰もいない病室のベッドで目覚めてすぐ、その光り輝く小さな塊を、届けられていた荷物の中の、保冷用の袋の中に収めた。絶命してどれほどの時間が過ぎたかはわからないが、その輝きは、薄れる意識の中で語り合った、あの毅然とした姿と何の変わりもなかった。
第六章
街に帰り着いてすぐ、剥製屋へ向かった。「遅くなりました。すみません」
深々と頭を下げ、保冷用の袋を差し出す。剥製屋はしわだらけの顔を更にくしゃくしゃにしながら言った。
「今回は、大変だったそうだなあ」
診療所から、既に連絡を受けていたという。
「では、村の人たちは、俺が虹翡翠を捕まえていたことを知っていたんですか?」
「まあな。だが、誰もお前から虹翡翠を取り上げようとはしなかったろう? それはお前が本当に大切そうにこいつを抱えていたからだ。あの村では虹翡翠は、神の使いという伝説もあったらしいが、もう古い話だから、ということだ。ただ、村長は、賢い鳥だから、命を捧げる相手としてお前を選んだんだろう、と思って、そのまま持ち帰らせたのだと」
そう言いながら、袋の中を覗き込んだ。
「素晴らしい輝きだ。鮮度も問題ない」
「三日も過ぎたと聞いています。すみません」
「大丈夫、お前が体を張って獲た虹翡翠だ。後は、俺の腕を信じろ」
生きていれば、自分の祖父と同じ年だという剥製屋は、優しく包むようにイズムの頭を撫でた。
「あの」
「ん? 何だ?」
イズムは思い切って言った。
「俺の今まで獲ってきた鳥は、中を抜くとき、肉はどうしていたんですか? やっぱり…捨てていたんでしょうか?」
剥製屋は顔を上げて言った。
「お前は鳥の肉が嫌いだと聞いていたがどうした? まあ今までの獲物は、量や鮮度にもよるが、出来るだけ、食うようにしていたよ。ばあさんと二人で食うにはちょうどいい量だったが」
「あの、虹翡翠の肉を…もらえませんか?」
コーヒーカップを握りしめるイズムの手がガタガタ震える。指に少し零れたが、熱ささえ感じなかった。
「こんな小さな鳥じゃたいした量にはならないぞ」
剥製屋は優しく微笑んで言った。
「疲れた身体で急いでここまで帰ってきたのだろうが、肉が欲しいとなるともう少し時間がかかる。ソファででも横になるといい」
「ありがとう、ございます」
数十分後、イズムは泥のような眠りから起こされ、小さな包みを握らされた。
「出来るだけ新鮮なうちに食ってやれ」
イズムは胸がいっぱいになって、言葉が口から出なくなった。深々と礼をし、大荷物を背負って、故郷の村への乗り合いバスに乗り込んだ。
家のドアを開くと、剥製屋からの連絡を受けていた母と妹が黙って彼の少しやせた身体を抱きとめた。
「母さん、頼みがあるんだ」
赤ん坊の握りこぶし程度の包みを、イズムは母に手渡した。
「この肉、料理して欲しい」
母親は包みを開き、
「何か、めずらしいものなのかい? これは、お前、鳥の肉じゃないか」
と不思議そうに言った。
「俺が食べる」
小さな声でイズムが言うと、
「何か特別な意味があるんだね」
と、うなずいて、削ぎ切りにしたものをバターで炒めて真っ白の皿に並べてくれた。
イズムは震える手でフォークを取り、肉片を一切れ、口の中にゆっくり入れた。
決して美味しいものではない。むしろ、味をほとんど感じなかった。だけど、その肉はイズムの舌にまとわりつくようにほろりと崩れ、しみこむように飲み下された。
『私の肉を食べなさい。あなたの血肉として私は生きることに、たった今、決めた』
虹翡翠の声が胸の中によみがえる。瞬間、涙が両目から溢れ出した。溢れる涙をぬぐうこともせず、すべての肉片を口に入れる。咀嚼する必要なく肉片はイズムの口の中で溶けていく。
「ごちそうさま」
イズムは震える両手をゆっくりと合わせ、うつむいた。
「虹翡翠…ありがとう。ごめん」
自分が今まで鳥が食べられないからと言って食べてきたシシやウサギも、魚も貝も野菜も麦も米も、みんな命を持っていたんだ。俺たちはその命の犠牲の上に立って、生きているんだ。虹翡翠は、俺にそのことを本当に身にしみて理解させようと、自分の身を捧げてくれたんだ。
(それでも、俺は、虹翡翠、お前の言うとおりには生きられない)
第七章(終章)
イズムはある日、いつもの依頼主を訪ねた。
「よく来てくれたね。昨日、虹翡翠の剥製が届いたばかりだ」
広い居間に通されると、部屋の真ん中に据えた台の上、鳥かごの模様を模したガラスケースの中に、わずかに翼を開き、小首を傾げ、止まり木に止まっている虹翡翠の姿があった。
「あの剥製屋が、今回は今まで以上に心をこめて作ってくれた。君が危険を冒して手に入れてくれたものだからね」
「違います。俺は、軽率で、未熟だったんです。…虹翡翠を手に入れられたのは、俺の力では、ありません…」
イズムは溢れてくる涙を隠さずに、ガラスケースにへばりついた。この涙は、何だろう。その意味が、彼にはわからない。
「何か、話があったんだろう? 君がこんな風に、出来上がった剥製をわざわざ見に来るのも、そうやって、自分の獲物を前に涙するのも、初めて見たよ」
依頼主が、熱い茶を勧めながら言う。
「剥製撃ちを辞めるつもりかい?」
イズムはガラスに両手を貼り付けたまま、首を横に振った。
「わからないんです。わからなくなってしまったんです。俺は、あなたのように、こうやって美しい鳥の剥製たちに囲まれて、それらを優しく見つめる人間がいることを知っている。だから、自分の仕事に誇りを持って取り組んできたつもりでした。でも…俺の…俺たちのしていることは、自然の摂理に反していることなんでしょうか? 今更聞くのはおかしなことかもしれませんが、どうしてあなたは鳥の剥製を集めているのですか? 鳥は羽ばたいたり、美しい声でさえずったりしてこそ、生きていてこそ美しいんじゃないですか?」
「まあ座りなさい。少し、落ち着いて話そうか」
依頼主はイズムの肩に手をかけ、近くの椅子に腰掛けさせた。
「私は、昔小鳥を飼っていたことがあるんだよ。…ちょうど君くらいの年頃…いや、君がお父さんから銃を渡された頃くらいに飼い始めたのだったかもしれない。何しろ古い記憶だからね。私の父はとても立派な医者で、人々の信頼も厚かったが、その分とにかく忙しい人だったから、一人息子が寂しがらないように、誕生祝にカナリヤをプレゼントしてくれたんだ。本当によく懐いてくれて、美しい歌声でさえずって、私にとっては友達以上の宝物だったし、その小鳥にとっても私のそばにいることが幸せなんだと思い込んでいた。だがある日、私が鳥かごの蓋を閉め忘れてね、あっさり逃げ出されてしまって、その直後、家の庭で野良猫に襲われてあっという間に食われるのを、私は見てしまったんだよ。自分の不始末からその悲劇までの一部始終はほんの数分の出来事だったのに、後には小さな骨と、むしられた数枚の羽根しか残らなかった」
「それは…」
幼い少年にとっては心の大きな傷になる光景であったろう。
「…父の仕事を継ぐことになって必死で勉強に励んでいたときには、正直、そのカナリヤのことは忘れていた。しかし、本格的に医者の仕事を始めてしばらく経った頃に、今の剥製屋の作品を見てね。まだ彼も若い職人だったが、当時から、あの腕以上に、あの愛情を込めて作り出される偽せ物の生命感は変わりなく存在していた。のめりこんで集め始めずにはいられなくなったよ…私は忙しさにかまけて結婚すらすることも出来ず、仕事では人々の命を救ったり、臨終を看取ったりしているが、自宅ではこうして死んだ鳥たちの偽せ物の命に囲まれて癒されている。君が、こんな大人をどう思うかは君の自由だが、私はあの剥製屋の作品に出会い、近年になって君のように研究熱心で才能ある素晴らしい鳥撃ちに出会って、幸せだと思っているよ」
「ありがとうございます」
イズムはもう目から溢れ出る涙を止めることは出来なかった。
「イズム君、君は今、混乱しているんだね。迷う時はとことん迷えばいい。とことんまで迷って、考えて、考え抜いて出した答えが君にとっての一番の正義なんだ。…君は気付いているんだろうか? お父さんは君の未来を縛る事を望んではいない。君はちゃんと魂に翼を持っているんだよ。君の名前、『イズム』の意味は『主義』。『自由意志』という意味だ。君は、いつも自由なんだよ」
依頼主である老紳士は、しゃくりあげるイズムの肩を優しく右手で叩いた。その様子を、今はもう命を持たない虹翡翠の漆黒の瞳が静かに見守っていた。
イズムはそれからも、剥製の為の鳥を撃つのを辞めることは無かった。青年になる頃にはその道で専門の、鳥撃ち名人として、国中のあちこちから依頼が来るほどの名声を得た。妹のサカは、剥製の依頼主である医者から紹介された街の学校で学び、努力を重ねた末に女医になったという。その直後、イズムは優しい娘を妻に迎え、母親と三人で暮らし始めた。生活に必要なだけの収入を、剥製撃ちで稼ぎ続けた。やがて、妻は男の子を産み、その子は丈夫にすくすくと育った。イズムは決して、息子に銃を持たせようとはしなかったが、息子はいつの間にか独学で猟を学び、鳥に限らず、様々な動物の猟をするようになった。そんな、息子の姿を黙って見守り、イズムは老いて、やがて静かに死んだ。彼は、結局あの日以来、生涯鳥の肉を口にすることはなかったという。
《終わり》
琥珀 燦(こはくあき)
第一章
イズム少年が猟銃を初めて手にしたのは九歳の時だ。その経験が早過ぎるのか、そうでもないのかは、
小さな村からほとんど出たことのないイズム自身、誰かと比べることはできないし、どうでもいいと彼は思っている。
彼に銃を手渡したのは鳥撃ち猟師として評判の高い父親だった。父のまた父親である祖父も、その父であるひいじいさんも、イズムの家の男は代々鳥撃ちで生計を立てていた。
ただ、イズムの父は生まれつき胸の病を患っていた。それでも、イズムの血筋の中では一番腕は良かったので、ぜいたくさえ望まなければ暮らしぶりは苦しくはなかった。
イズムにとっては小さい頃は、いっしょにくらしていた祖父と若い父が連れ立って猟の支度をする姿を見るのはワクワクするものだったし、祖父が病に倒れ、亡くなってからは、その少し細い身体のわりに、きたえられた腕で数本の猟銃を選び背負って出かけていく父の姿は誇りだった。
しかし、ある夜。突然、父はイズムを呼んだ。
「イズム、明日から、鳥撃ちを教える。一緒に来なさい」
虫取りしかしたことのないイズムは、それは驚いた。まだ九歳のほんの子どもだ。
その驚きはすぐ興奮にすりかわった。(俺は父さんに一人前に見てもらったんだ)
と。翌朝は早いから、すぐ寝るように言われても目はらんらんと開き、心臓がどきどきした。
初めての猟は、草原に立てられたわら束の的で、イズムは意気消沈した。しかし、それは直後、更に絶望に変わった。
「これがお前の銃だ。俺が最初に親父に持たされたヤツで、今もちゃんと手入れしている。
お前に銃の持ち方を教える日のために」と両腕に持たされた銃身の重さ。
音消しの耳当てで塞いでいたとはいえ、火薬が耳元で破裂する音の大きさに驚いたイズムは銃を持ったまま、後ろに吹っ飛んでしりもちをついた。
イズムの身体の震えは長い間止まらなかった。父は冷たく彼を見下ろしていたが、
やがてしゃがんで冷たい水の入った水筒をイズムの口に当てた。
「ゆっくり飲め。急ぐな。せき込むから」
そして、冷や汗まみれで震える息子の身体をしっかりと抱きとめた。
「イズム。いいか、俺の胸の病はもう治らない。俺はもう長く生きられない。
お前が、母さんと、妹を食べさせていくんだ。
鳥を撃って、必要な分だけ家族の食料として取り、残りは町へ行って売って、その金で暮らしていくんだ。俺は、死ぬまでにお前に俺の持っている技術のすべてをお前に教える。時間はそれほどない。覚悟しろ」
その前の日の猟で、父は血を吐いていたのだ。
それから半年の猛特訓の末、イズムは父に一人で猟に出る事を許された。
もともと血筋の良さもあったのだろうが、本当につらい修行の日々で、イズムの身体には大小の生傷が絶えず、しかしその小さな身体にはみるみるうちに筋肉が付き、やがて身長も伸びていった。たくましく成長していく息子の姿に満足そうな笑みを浮かべる父の身体は少しずつやせ細り、一年後、父は大量の血を吐いて死んだ。
第二章
イズムは今年、十三歳になった。村の外でも評判の鳥撃ちとして認められている。
ただし、今、彼は家族の為にわずかに食用の鳥を撃ち、大方の収入は、剥製用の珍しい鳥を撃つことで得ている。
今日も獲物の鳥を街の剥製屋に運び、夜遅く帰ってきたイズムの為に、サカが夕食を用意して待っていた。
「兄さん、どうして鳥が食べられないの? 母さんの鳥料理は美味しいのに」
妹のサカは十一歳、母親の手伝いもよくこなすが、勉強の好きな娘で、村人たちは
「あの娘はやがて村を出て街の学校へ行くだろう」と噂しているようだ。
「・・・わからない」
父に鳥を撃つ事を許され、初めて打ち落とした鳥が、不自然な形に翼を曲げ、
草の上に横たわりけいれんするのを見て以来、イズムは鳥肉が食べられなくなった。
「父さんだって、母さんの鳥料理は好物だって言ってたのに」
サカはイズムの好物のシシ肉のスープと野菜の煮物を揃える。
向かいに座ってイズムの様子を見ている母親が意を決して言う。
「イズム、お前はまだ十三だ。お前には重過ぎる仕事を背負わせていることは、
母さんもわかっているつもりだよ。
ただ、ちゃんと肉は食べないと、お前の身体は持たないよ」
「大丈夫だよ母さん。鳥を食べなくても、
ちゃんと川魚やシシ肉は食べてるじゃないか」
食欲は間違いなく旺盛な育ち盛りのイズムは、早いペースで食事をたいらげていく。
自分で食器を運びさっさと洗い、後片付けを済ませると、
「銃の手入れをして来る。街で新しい部品を買ってきたから、改造する」
と言い残し、部屋に向かおうとする。
「イズム。剥製のための猟はお辞め。父さんが一番嫌っていたことじゃないか」
うつむいたまま、強い口調で母親が言い放つ。
「剥製用の鳥撃ちは金になるんだ。サカの学費や、あの娘が将来嫁に行く時の費用にしたい」
「お前だって、学校に行きたいだろうに。銃を持つまでは、あんなに勉強が好きだったじゃないか」
辛そうに言う母に、イズムは静かに笑って答えた。
「俺は、いいんだよ。母さんやサカが少しでも幸せに暮らせるように金をかせげるのが、俺の幸せなんだ。
サカには街の大きな学校へ行って医者になる勉強をちゃんとしてもらいたいんだ。
父さんのような病気の人を助けられるように」
そして、扉の向こうに姿を消した。
「あんなに優しい子が、殺生の仕事など…」
母親は両手を組み、大きく溜め息をついた。
第三章
父親から譲られた、仕事場を兼ねた寝室で、
銃を分解し、部品をていねいに磨きながら、
イズムは今日呼ばれたある得意先の豪邸での会話を思い出していた。
「虹翡翠、ですか?」
数々の、鳥の剥製に囲まれた部屋で、出された熱い茶の湯気を嗅ぎながら、聞き返した。
部屋に並べられた剥製の半分はイズムの獲物で、今にも動き出しそうに翼を広げる様や、生きているかのような目の輝きなどは、鳥の皮膚の表面の傷を極力小さくするイズムの銃の技術とともに、隣に座っている剥製屋の腕の良さである。
一人暮らしの初老の大金持ちは、美しい色彩や形状を持つ鳥の剥製に囲まれたこの部屋で過ごすとき、最も安らぐと言う。そういう客の想いに応えるため、剥製屋も心をこめて丁寧な仕事をしている。
「名前は聞いたことがあるかな?」
いいえ、とイズムは首を横に振った。
「翡翠と言うと、カワセミの一種ですか?」
「ほう、やはりそういうことには詳しいんだね。普通の人はヒスイと聞けば宝石のメノウを思い出すが、あの石の色はカワセミの羽根の色を由来にしている」
依頼主は灰色の品良く手入れされたヒゲを撫でながら、まぶたを伏せて歌うように語る。
「しかし、虹翡翠がカワセミの仲間かどうかは不明なんだ。とにかく謎の多い鳥でね。
虹翡翠に詳しい者はなかなかいない。この鳥を近くで見たり、捕獲して観察した者がいないのだ。しかし飛んでいる姿を見た者は多く、
大きさはカワセミと同じくらいで、
全身の羽根は太陽の光の角度の加減で虹の七色に輝くという。数も少なくはなく、捕獲禁止の対象にはなっていない。ただ、知能が高くて捕獲できたものがいないのだ」
そして、彼は目を開き、穏やかに言った。
「ぜひ、手に入れたい。ただ、本当に小さく捕獲が困難な鳥なので、今回も、どうしても君の腕に頼るしかない。
やってくれるか? イズム君。報酬はいつも以上にはずむよ」
依頼を引き受けてすぐ、イズムはすぐ、街の図書館へ行き、虹翡翠に関する情報を調べ、
わずかながらも知識を得ることが出来た。
そして、銃の部品を売っている店へ行き、部品や弾を選び始めた。
(カワセミと同じ程度の大きさだとすれば、弾の大きさはほぼ針に近いほどの小さなものがいい。飛んでいる姿しか目撃されないとなると、どこかに止まっているところを狙うのは不可能だし、引き金を引くタイミングを計るのがかなり困難だから、長期戦は覚悟しなくてはならない。飛んでいる目標に即座に狙いを定めて、速度や方向まで、最小限の誤差内で正確に射弾するのに必要な部品は…)
イズムの自由になる範囲の小遣いは、
そういった銃のグレードアップのために遣われ、彼の旺盛な知識欲は、次の猟の成功の為の分析の作業に費やされる。そんな風に長い長い時間を、この部品屋で過ごすのは、
イズムにとっては充実したものである。
時々、独学で考え出した計算式を書き込んだメモを片手に、棚と棚の狭い隙間に座り込みながら、イズムは
(父さんもこんな時を過ごしていたんだろうか)
と考え、茶色い天井を見上げた。
(父さんは、俺の様に、食うためじゃなく、金のために、飾られる為だけのために鳥を撃ったことは無かったんだっけ)
父親が亡くなって1年ほどした頃、この銃の部品屋の店長に紹介されたのが、
今、イズムの獲物を買い取ってくれている剥製屋である。
彼に連れられて、あの大金持ちの依頼主の元へ行った。彼の剥製のコレクションへ傾ける、寂しくも愛情に満ちた視線を見て、
初回の仕事を引き受けて帰ると、母親の猛反対が待っていた。
「生き物は、すべて、他の命によって生かされている。我が家の人間たちは、生きていくのに必要な分だけの鳥を撃って、その肉のおかげで生かされているのだよ、イズム。父さんが、お前が高い報酬に目がくらんで、剥製撃ちになるなどと聞いたら、お前を殴って、すぐにでも鳥撃ちを辞めさせるだろうよ」
「でも、今回の仕事を母さんがどうしても止めるなら、俺は二度と銃を持たない」
イズムは頑として母親の反対にあらがい続けた。そして、翌日、母が起きるより早く起きた彼は、一人で支度をし、最初の剥製撃ちに旅立った。寝たふりをする母に気付かずに。
数日後、いつもより高額の報酬を得て帰ってきたイズムは、家族の分の食肉の包みと、
報酬の入った袋を母親にいつものように手渡した。
母親はいつもより、厳かな顔で、それらを受け取った。
それから何度、こんな猟を続けただろう。
母親とイズムの会話は、彼が剥製撃ちを始めてから急激に少なくなった。
たまに母親はさっきのように、
「父さんは剥製撃ちを嫌っていた、剥製撃ちはお辞め」と説得を試みるが、
イズムは一切聞き入れなかった。
父を亡くした時、わずか七歳だった妹のサカが言った
「わたし、お医者さんになりたい。わたしが、とても腕のいいお医者さんだったら、お父さんを助けられたかもしれない」
という言葉が、頭から離れなかったからだ。
第四章
虹翡翠がよく見られるという山は街に出て、列車で二時間、そこから乗り合いバスに揺られた終点が山のふもと。そして、目撃情報の多いポイントまで猟銃一式と野宿のための道具を背負って三時間ほど歩く。長い道のりだが、体力と経験には自信があった。
携帯食糧と川の水で急いで食事を済ませると、荷物は木の根元に隠した。夕暮れまでまだ時間はある。今から野宿の支度をしても、空から見れば「ここは危険」と知られるだけだ。ひとまず高い草むらに身をかがめ、大空を仰ぐ。
ここまで、猟のために遠出をしたのは初めてだった。今までにも、めずらしい鳥を探すために野宿を行いながら長期戦で粘ったことはあるが、この山に来たのは初めてだ。父親は家の近所の裏山で、必要な食料の為の猟しかしなかったから、泊りがけが必要なことは無かった。野宿を張ってまでして猟を行うのは自分の代からなので、アウトドアやサバイバルの知識も独学で学んだ。
(空が、高いなあ)
そんなことを思うのも、初めてではない。しかし、この山の青空は本当に、抜けるように美しくどこまでも青かった。イズムはそっと草の中に仰向けに横たわった。
そろりそろり、大きく両腕を広げる。秋晴れの空に、落ちていくような錯覚に、一瞬陥る。大地と空が逆転する。
そう思った瞬間、赤い光がシュッと空高く走った。残光は細く鋭い緑色で弧を描いた。
あ!
こんなに簡単に発見できる場所に…あれが虹翡翠?
しかし、凄いスピードだった。あれは、確かに今まで見た中でも難しい標的の部類に入る。
耳元で、背負った銃のチャリッと冷たい音がした。そうだ。俺は空に同化して生きる者ではない、地面から、空に生きるものを狙う者。
イズムは座り込み、一番弾の小さくスピードや照準を正確に合わせやすい銃を手に取り、次のチャンスを待った。
虹翡翠は、その日のうちにも、何度もイズムの視界を掠めた。物凄いスピードで。チカリ、と青や黄色や紫の光を残しながら。
イズムは数回、構えた銃の引き金に手をかけたが、すぐに、撃ち落とすのは困難だと判断し、しばらく虹翡翠の行動を観察することにした。
やがて、イズムは何となく、思った。
(俺の方も観察されている?)
今までの猟では、自分が、隠れる、というよりも、自然の中に溶け込み、相手を油断させれば、相手は自分のペースで行動を始め、必ず隙が出来る。そこを狙えば、一発だった。
しかし、何となく、今回は直感した。「観察」されている、と。虹翡翠は高い知性の持ち主で、捕獲が難しいとは聞いていたが、もしかしたら、それは人間並みの物なのではないだろうか?
そう思った瞬間、イズムの目の前五十センチの距離を、バサバサと音を立て、真珠色の羽根が通り過ぎた。
イズムはあっけにとられた。(からかわれている…?)
イズムは仕方なく、周りをちょろちょろ走っていたイタチを一匹だけ撃って、夕食の準備にかかった。生きる為に他の命を奪うのは、気持ちのいいものでは決してないが、もう慣れてしまった。
(だけど、なぜ鳥だけは?)
獲物をさばいて得た肉と血液で空腹を満たしながら、改めてイズムは考える。
寝袋に入り、満天の星空に包まれて眠れば、青空に落ちる夢を見る。風をシャツにはらませて、どこまでも果ての無い空への、永遠の下降。冷や汗をぐっしょりかいて、目覚めて思った。昼間見た、あの青空のせいだ。
第五章
イズムは二日目にして困惑していた。たぶん、昨日ここを飛び回っていた虹翡翠は一羽。相手は、自分の存在を知っている。知っていて、逃げようともせず、自分の存在を誇示して見せるような行動を取る。そんな相手をどうやって捕まえる? 完全に身を隠して、何とか相手を油断させ、隙を狙う…万に一つどころの可能性ではない。まるで人間同士の腹の探り合いだ。
食料になりそうな鳥も何回も空を過ぎった。猟に慣れたイズムにとってはスローモーションの動きに感じるが、それには一切目を向けない。そういうイズムの行動を見守るように、七色の光を持つ小鳥は、その日も数回姿を見せた。
頭脳戦になる猟も何度か経験したが、こんな相手は初めてだ。今までは常に標的に対して、自分は優位に立っていられたから、余裕を持って考え、行動して切り抜けた。しかし、今回はまるで人間相手の心理作戦だ。そして、それは家族や仕事の上で出会う少人数の人間関係の中で生きてきたイズムには弱点の一つだ。
困り果てながら三日四日が過ぎていった。人間を警戒して、すっかり近くから動物たちも姿を消してしまった。
携帯食糧と川の水で飢えを満たしながら、(俺は、子どもだ)と強く感じた。俺は小さい。この空の下で、俺は小さくて、何と頼りない存在だろう?
そんなイズムの頭上を鳥たちは何度も通り過ぎたが、鳥だけは食料として撃つことは出来ない。
虹翡翠の姿を見る度に銃を構えてみるが、無駄な抵抗だと、わかり始めていた。
(俺は何をしているんだろう?)
一週間目、イズムは仰向けになって空を見上げていた。夕べは予測し得ない激しい雨にやられ、木の下に避難しても、足元を浸し続ける水が体力を奪い、食料も、もう尽きかけていてる。今まで、依頼された獲物を諦めたことは無かった。しかし、これは無理だ。今の自分はどう考えても負けている。勝算は無い。しかも引き返す機会を見逃し、もう帰る体力さえも残っていない。鳥撃ちを職業として父親から正式に受け継いで以来初めて、イズムは子どものように泣きたくなった。
『あなたが鳥を食べられないのは、あなたが翼を持たぬ者だからよ』
声が、する。美しい鈴のような声。胸の奥に直接響く声。横たわったまま、まぶたを開くと、目の前に小さな鳥がいて自分の顔をじっと見つめていた。
(虹翡翠?)
形は、ごくありきたりの愛らしい小鳥だったが、その全身を覆う羽根の色の美しさ。白、というか真珠色というか、そんな色がベースなのだろうが、それを認識する前に七色と言うだけでは表現できない様々な色のきらめきが目に飛び込んでくる。
「お前が、虹翡翠か。言葉を話すのか?」
『私はあなたの心に直接心を伝えているだけ』
「へえ、便利だな」
イズムは口元だけで力なく笑った。虹翡翠は笑いもせず(鳥に笑顔があるかどうかは知らないが)こちらを見ている。その目は、底のない、漆黒だ。
『私には、あなたの過去が見えるのよ。今まで生きてきた生き様まで。最初の日に、あなたの近くを飛んだでしょう? あの時、あなたの記憶を全部見たのよ』
「それで、最初の日から俺をからかい続けたわけか」
『まさか、作戦の見込みも立たないまま、ここまで粘るおバカさんだとは思わなかったのよ。どうして途中で諦めて帰らなかったのよ。どうして、私たちの仲間を獲らなかったの? きっかけはいく度でもあったのに。あなたは生きる為に狩りをしているんじゃないの?』
「あいにくと、俺はそうじゃない。鳥の肉は苦手だしね」
『あなたたち人間は、食べるためにだけ獣を撃つのではないの?』
呆れ果てた様子で、虹翡翠が小首を傾げた。
『それなら、猫にでも捕まって食べられる方がまだ納得がいくわ』
「お前は、食べられる為に殺されるのが怖くないのか?」
『怖いに決まってるでしょ? 猫なんて、ハンターとしては人間のあなたなんかよりどれだけ小賢しいか。それでも、他の命の糧として血肉を奪われる方が、人間の屋敷に飾られる為に死ぬよりずっと、まし。あなた達の言葉で、食物連鎖って言うんでしょ? こういう決まりごと。私たち獣はそんな言葉無くても、生まれたときから、そういう決まりごとはちゃんと知っているのよ』
虹翡翠は小さな翼をはためかせながら青白いくちばしをパクパクさせた。薄紅色の光の粒子がパッと散る。ああ、怒ってるんだなあ、こいつ、ということはイズムにも漠然とわかった。
『私にはわからないのよ。あなたの記憶の中にあった、剥製っていうもの? はらわたと肉を捨てて、死骸を空っぽにして、つめものなんかして、わざわざ生きている姿に似せて再現して飾って…』
「それは、人間が寂しがりだからだ。美しいものをいとおしんで、絶対に逃げない状態で、周りに置いておきたい、そうでないと安心できない」
『変なの。死体をいっぱい飾ってるより、生きてさえずって、はばたく鳥と仲良く共存した方が幸せに決まってるじゃない』
「いつまでも、友達でいられるわけじゃないじゃないか。鳥は翼を持って、いつでも気まぐれに逃げ去ってしまう…人同士だってそうだ。いつまでも一緒にいられる保障は無い。ケンカ別れならともかく、それこそ、死が突然かけがえのない存在に翼を付けて天へ連れ去ってしまうこともある。それなら、偽せ物であっても、生前の美しい姿を残したまま、死体でもそばに置いておける方が幸せな人間だっているんだ」
イズムは、さして体力が残っていないはずの体で自分がどうしてここまで饒舌(じょうぜつ)になっているのかわからなくなっていた。あるいはもう、自分も心の声で話しているのを、虹翡翠が読み取ってくれているのかもしれない。
「俺だって、美しいものは好きだ。美しいものを手元に置きたい人の気持ちもわかるし、
その為に高い金を払ってもいいという金持ちの気持ちもわかる。そういう生活をするために、奴らは努力して金持ちになったんだろうから。人間の中には、死に至る病にかかったかけがえのない存在を、その病気を治せる技術が生まれる未来まで、冷凍して保存する者もいるという位だ。そこまでは俺にも理解は出来ないが、まあ、死んだ父さんの写真を片時も手放さない母さんも、あまり変わらないかもな」
『あなたは、私を、美しいと思うの? だから、私を撃ち獲りたいの?』
「ああ。こんなキレイなもの、見たことがない。いつまでも見ていたいよ…けど」
けど、意識が薄くなってきた。俺も、ここで死ぬんだろうか。そうしたら、この身体は野獣たちに食いちぎられて大地の中に溶け去り、魂は…父さんのところへ行けるのだろうか?
『あなたはなぜ鳥を撃つの? 他に生きる手段なんていくらでもあるし、第一、あなたまだ子どもじゃないの』
虹翡翠の質問は弱った意識にも容赦は無い。
「父さんから託された唯一の形見だから。この銃と、鳥撃ちの技術は。…父さんの気配や名残を俺の中に残すには、鳥撃ちの血筋を絶やさないようにすることしかなかったんだ。俺には他の道を選ぶ余裕なんてなかった」
『イズム…教えてあげるわ。あなたが鳥を食べられないのは、翼を持つ物があなたの最後の希望だから。あなたは飛びたいのよ。目指す場所がどこなのかは、私にもわからないけれど』
虹翡翠の真っ黒いつぶらな瞳がイズムをじっと見つめる。イズムには、この鳥のキラキラと絶え間なく変化し続ける翼の色よりも、この揺るがない瞳の漆黒の方がいとおしく感じられるのが不思議だった。
「そうか…自由への憧れの反動が、俺に鳥の肉を受け付けさせなかった、と」
イズムは横を向いていた顔を、やっとの力で仰向かせた。雨上がりの空に長く大きな虹が消えかかる瞬間であった。
その時、虹翡翠の凛とした声が、心に、いや、イズムの体中に響いた。
『私の肉を食べなさい。あなたの血肉として私は生きることに、たった今、決めた』
「何を言い出すんだ?」
『気に病むことはないわ。同種間の動物も飢えれば共食いをするし、人間だって色々事情が有って、生きる為に、やむを得ず殺し合うこともあるでしょう? 私も食物連鎖の中で死んでゆくのでなくては、納得が出来ない』
イズムの心が、震え出す。
「こんな風に言葉を交わしてしまった相手を撃って食えというのか?」
『ええ、私を撃ちなさい。あなたのような存在を生かす為になら、この命を捧げてもいいと思う』
「…こんなに近くで撃っては、その皮膚に大きな傷がついて売り物にならないんだ」
イズムの心が、空笑いをするように言った。すると、虹翡翠は
『そうだったわね。わかった。じゃあ』
とだけ言い残して、すっくりと天を仰ぎ、翼を広げ、すうっと地を離れた。
次の瞬間、ぱーん。晩秋の空に、透き通った破裂音が響いた。
動く体力など残ってなかったはずの体が反射的に銃を取り、空を舞う小鳥目掛けて引き金を引いていたのだ。
(虹翡翠!)
銃を投げ捨て、よろける身体を引きずりながら、光る点が弧を描いて落ちた地点を目指して歩み寄った。
草むらの中にまだ光を放ちながら、その小さななきがらはビクリとも動かなかった。針のような銃弾が心臓を一突きしている。イズムはそのなきがらを両手でそっと抱き上げ、無表情でつぶやいた。
「今まで、何も考えず、依頼された鳥をただ撃ち続けてきた。…殺したくないと思ったのはお前が初めてだよ。虹翡翠」
そのまま、地面に膝をつき、イズムは気を失った。
銃弾の音をたまたま聞きつけて、興味本位で近づいてきた、その山村の住人にイズムは救出された。
驚いて集まってきた村人たちに近くの療養所に担ぎ込まれたが、幸い風邪をこじらせかけていたのと、栄養失調だけという診断であった。
ただ、イズムは気を失っている間も、固く握り締めた両手を決して開こうとせず、村人や医者を困らせたという。イズムは誰もいない病室のベッドで目覚めてすぐ、その光り輝く小さな塊を、届けられていた荷物の中の、保冷用の袋の中に収めた。絶命してどれほどの時間が過ぎたかはわからないが、その輝きは、薄れる意識の中で語り合った、あの毅然とした姿と何の変わりもなかった。
第六章
街に帰り着いてすぐ、剥製屋へ向かった。「遅くなりました。すみません」
深々と頭を下げ、保冷用の袋を差し出す。剥製屋はしわだらけの顔を更にくしゃくしゃにしながら言った。
「今回は、大変だったそうだなあ」
診療所から、既に連絡を受けていたという。
「では、村の人たちは、俺が虹翡翠を捕まえていたことを知っていたんですか?」
「まあな。だが、誰もお前から虹翡翠を取り上げようとはしなかったろう? それはお前が本当に大切そうにこいつを抱えていたからだ。あの村では虹翡翠は、神の使いという伝説もあったらしいが、もう古い話だから、ということだ。ただ、村長は、賢い鳥だから、命を捧げる相手としてお前を選んだんだろう、と思って、そのまま持ち帰らせたのだと」
そう言いながら、袋の中を覗き込んだ。
「素晴らしい輝きだ。鮮度も問題ない」
「三日も過ぎたと聞いています。すみません」
「大丈夫、お前が体を張って獲た虹翡翠だ。後は、俺の腕を信じろ」
生きていれば、自分の祖父と同じ年だという剥製屋は、優しく包むようにイズムの頭を撫でた。
「あの」
「ん? 何だ?」
イズムは思い切って言った。
「俺の今まで獲ってきた鳥は、中を抜くとき、肉はどうしていたんですか? やっぱり…捨てていたんでしょうか?」
剥製屋は顔を上げて言った。
「お前は鳥の肉が嫌いだと聞いていたがどうした? まあ今までの獲物は、量や鮮度にもよるが、出来るだけ、食うようにしていたよ。ばあさんと二人で食うにはちょうどいい量だったが」
「あの、虹翡翠の肉を…もらえませんか?」
コーヒーカップを握りしめるイズムの手がガタガタ震える。指に少し零れたが、熱ささえ感じなかった。
「こんな小さな鳥じゃたいした量にはならないぞ」
剥製屋は優しく微笑んで言った。
「疲れた身体で急いでここまで帰ってきたのだろうが、肉が欲しいとなるともう少し時間がかかる。ソファででも横になるといい」
「ありがとう、ございます」
数十分後、イズムは泥のような眠りから起こされ、小さな包みを握らされた。
「出来るだけ新鮮なうちに食ってやれ」
イズムは胸がいっぱいになって、言葉が口から出なくなった。深々と礼をし、大荷物を背負って、故郷の村への乗り合いバスに乗り込んだ。
家のドアを開くと、剥製屋からの連絡を受けていた母と妹が黙って彼の少しやせた身体を抱きとめた。
「母さん、頼みがあるんだ」
赤ん坊の握りこぶし程度の包みを、イズムは母に手渡した。
「この肉、料理して欲しい」
母親は包みを開き、
「何か、めずらしいものなのかい? これは、お前、鳥の肉じゃないか」
と不思議そうに言った。
「俺が食べる」
小さな声でイズムが言うと、
「何か特別な意味があるんだね」
と、うなずいて、削ぎ切りにしたものをバターで炒めて真っ白の皿に並べてくれた。
イズムは震える手でフォークを取り、肉片を一切れ、口の中にゆっくり入れた。
決して美味しいものではない。むしろ、味をほとんど感じなかった。だけど、その肉はイズムの舌にまとわりつくようにほろりと崩れ、しみこむように飲み下された。
『私の肉を食べなさい。あなたの血肉として私は生きることに、たった今、決めた』
虹翡翠の声が胸の中によみがえる。瞬間、涙が両目から溢れ出した。溢れる涙をぬぐうこともせず、すべての肉片を口に入れる。咀嚼する必要なく肉片はイズムの口の中で溶けていく。
「ごちそうさま」
イズムは震える両手をゆっくりと合わせ、うつむいた。
「虹翡翠…ありがとう。ごめん」
自分が今まで鳥が食べられないからと言って食べてきたシシやウサギも、魚も貝も野菜も麦も米も、みんな命を持っていたんだ。俺たちはその命の犠牲の上に立って、生きているんだ。虹翡翠は、俺にそのことを本当に身にしみて理解させようと、自分の身を捧げてくれたんだ。
(それでも、俺は、虹翡翠、お前の言うとおりには生きられない)
第七章(終章)
イズムはある日、いつもの依頼主を訪ねた。
「よく来てくれたね。昨日、虹翡翠の剥製が届いたばかりだ」
広い居間に通されると、部屋の真ん中に据えた台の上、鳥かごの模様を模したガラスケースの中に、わずかに翼を開き、小首を傾げ、止まり木に止まっている虹翡翠の姿があった。
「あの剥製屋が、今回は今まで以上に心をこめて作ってくれた。君が危険を冒して手に入れてくれたものだからね」
「違います。俺は、軽率で、未熟だったんです。…虹翡翠を手に入れられたのは、俺の力では、ありません…」
イズムは溢れてくる涙を隠さずに、ガラスケースにへばりついた。この涙は、何だろう。その意味が、彼にはわからない。
「何か、話があったんだろう? 君がこんな風に、出来上がった剥製をわざわざ見に来るのも、そうやって、自分の獲物を前に涙するのも、初めて見たよ」
依頼主が、熱い茶を勧めながら言う。
「剥製撃ちを辞めるつもりかい?」
イズムはガラスに両手を貼り付けたまま、首を横に振った。
「わからないんです。わからなくなってしまったんです。俺は、あなたのように、こうやって美しい鳥の剥製たちに囲まれて、それらを優しく見つめる人間がいることを知っている。だから、自分の仕事に誇りを持って取り組んできたつもりでした。でも…俺の…俺たちのしていることは、自然の摂理に反していることなんでしょうか? 今更聞くのはおかしなことかもしれませんが、どうしてあなたは鳥の剥製を集めているのですか? 鳥は羽ばたいたり、美しい声でさえずったりしてこそ、生きていてこそ美しいんじゃないですか?」
「まあ座りなさい。少し、落ち着いて話そうか」
依頼主はイズムの肩に手をかけ、近くの椅子に腰掛けさせた。
「私は、昔小鳥を飼っていたことがあるんだよ。…ちょうど君くらいの年頃…いや、君がお父さんから銃を渡された頃くらいに飼い始めたのだったかもしれない。何しろ古い記憶だからね。私の父はとても立派な医者で、人々の信頼も厚かったが、その分とにかく忙しい人だったから、一人息子が寂しがらないように、誕生祝にカナリヤをプレゼントしてくれたんだ。本当によく懐いてくれて、美しい歌声でさえずって、私にとっては友達以上の宝物だったし、その小鳥にとっても私のそばにいることが幸せなんだと思い込んでいた。だがある日、私が鳥かごの蓋を閉め忘れてね、あっさり逃げ出されてしまって、その直後、家の庭で野良猫に襲われてあっという間に食われるのを、私は見てしまったんだよ。自分の不始末からその悲劇までの一部始終はほんの数分の出来事だったのに、後には小さな骨と、むしられた数枚の羽根しか残らなかった」
「それは…」
幼い少年にとっては心の大きな傷になる光景であったろう。
「…父の仕事を継ぐことになって必死で勉強に励んでいたときには、正直、そのカナリヤのことは忘れていた。しかし、本格的に医者の仕事を始めてしばらく経った頃に、今の剥製屋の作品を見てね。まだ彼も若い職人だったが、当時から、あの腕以上に、あの愛情を込めて作り出される偽せ物の生命感は変わりなく存在していた。のめりこんで集め始めずにはいられなくなったよ…私は忙しさにかまけて結婚すらすることも出来ず、仕事では人々の命を救ったり、臨終を看取ったりしているが、自宅ではこうして死んだ鳥たちの偽せ物の命に囲まれて癒されている。君が、こんな大人をどう思うかは君の自由だが、私はあの剥製屋の作品に出会い、近年になって君のように研究熱心で才能ある素晴らしい鳥撃ちに出会って、幸せだと思っているよ」
「ありがとうございます」
イズムはもう目から溢れ出る涙を止めることは出来なかった。
「イズム君、君は今、混乱しているんだね。迷う時はとことん迷えばいい。とことんまで迷って、考えて、考え抜いて出した答えが君にとっての一番の正義なんだ。…君は気付いているんだろうか? お父さんは君の未来を縛る事を望んではいない。君はちゃんと魂に翼を持っているんだよ。君の名前、『イズム』の意味は『主義』。『自由意志』という意味だ。君は、いつも自由なんだよ」
依頼主である老紳士は、しゃくりあげるイズムの肩を優しく右手で叩いた。その様子を、今はもう命を持たない虹翡翠の漆黒の瞳が静かに見守っていた。
イズムはそれからも、剥製の為の鳥を撃つのを辞めることは無かった。青年になる頃にはその道で専門の、鳥撃ち名人として、国中のあちこちから依頼が来るほどの名声を得た。妹のサカは、剥製の依頼主である医者から紹介された街の学校で学び、努力を重ねた末に女医になったという。その直後、イズムは優しい娘を妻に迎え、母親と三人で暮らし始めた。生活に必要なだけの収入を、剥製撃ちで稼ぎ続けた。やがて、妻は男の子を産み、その子は丈夫にすくすくと育った。イズムは決して、息子に銃を持たせようとはしなかったが、息子はいつの間にか独学で猟を学び、鳥に限らず、様々な動物の猟をするようになった。そんな、息子の姿を黙って見守り、イズムは老いて、やがて静かに死んだ。彼は、結局あの日以来、生涯鳥の肉を口にすることはなかったという。
《終わり》
0
この作品の感想を投稿する
あなたにおすすめの小説

青色のマグカップ
紅夢
児童書・童話
毎月の第一日曜日に開かれる蚤の市――“カーブーツセール”を練り歩くのが趣味の『私』は毎月必ずマグカップだけを見て歩く老人と知り合う。
彼はある思い出のマグカップを探していると話すが……
薄れていく“思い出”という宝物のお話。

ぼくのだいじなヒーラー
もちっぱち
絵本
台所でお母さんと喧嘩した。
遊んでほしくて駄々をこねただけなのに
怖い顔で怒っていたお母さん。
そんな時、不思議な空間に包まれてふわりと気持ちが軽くなった。
癒される謎の生き物に会えたゆうくんは楽しくなった。
お子様向けの作品です
ひらがな表記です。
ぜひ読んでみてください。
イラスト:ChatGPT(OpenAI)生成

緑色の友達
石河 翠
児童書・童話
むかしむかしあるところに、大きな森に囲まれた小さな村がありました。そこに住む女の子ララは、祭りの前日に不思議な男の子に出会います。ところが男の子にはある秘密があったのです……。
こちらは小説家になろうにも投稿しております。
表紙は、貴様 二太郎様に描いて頂きました。

パンティージャムジャムおじさん
KOU/Vami
児童書・童話
夜の街に、歌いながら歩く奇妙なおじさんが現れる。
口癖は「パラダイス~☆♪♡」――名乗る名は「パンティージャムジャムおじさん」。
子供たちは笑いながら彼の後についていき、歌を真似し、踊り、列は少しずつ長くなる。
そして翌朝、街は初めて気づく。昨夜の歌が、ただの遊びではなかったことに。

「いっすん坊」てなんなんだ
こいちろう
児童書・童話
ヨシキは中学一年生。毎年お盆は瀬戸内海の小さな島に帰省する。去年は帰れなかったから二年ぶりだ。石段を上った崖の上にお寺があって、書院の裏は狭い瀬戸を見下ろす絶壁だ。その崖にあった小さなセミ穴にいとこのユキちゃんと一緒に吸い込まれた。長い長い穴の底。そこにいたのがいっすん坊だ。ずっとこの島の歴史と、生きてきた全ての人の過去を記録しているという。ユキちゃんは神様だと信じているが、どうもうさんくさいやつだ。するといっすん坊が、「それなら、おまえの振り返りたい過去を三つだけ、再現してみせてやろう」という。
自分の過去の振り返りから、両親への愛を再認識するヨシキ・・・

ノースキャンプの見張り台
こいちろう
児童書・童話
時代劇で見かけるような、古めかしい木づくりの橋。それを渡ると、向こう岸にノースキャンプがある。アーミーグリーンの北門と、その傍の監視塔。まるで映画村のセットだ。
進駐軍のキャンプ跡。周りを鉄さびた有刺鉄線に囲まれた、まるで要塞みたいな町だった。進駐軍が去ってからは住宅地になって、たくさんの子どもが暮らしていた。
赤茶色にさび付いた監視塔。その下に広がる広っぱは、子どもたちの最高の遊び場だ。見張っているのか、見守っているのか、鉄塔の、あのてっぺんから、いつも誰かに見られているんじゃないか?ユーイチはいつもそんな風に感じていた。
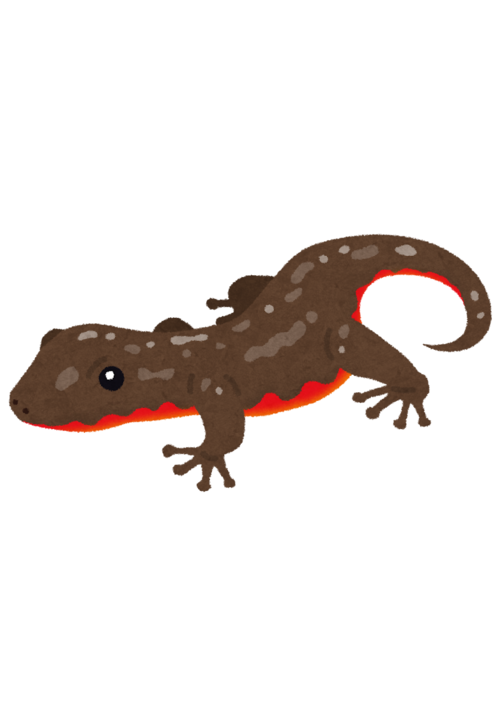

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















