8 / 61
芽吹く春 ミツキの告白
初デート【中編】
しおりを挟む
本屋を出ると、次の目的地であるドラッグストアに向かうためにエスカレーターを目指す。やはり、高校生が多く、自分の学校の生徒のほかにも、他校の生徒も多く目に入った。予想通りミツキに視線が集中して、そのあと僕に投げかける視線は、お前は彼氏か、というものだろう。まさか、このかわいい子が花神楽美月《はなかぐらみつき》とは誰も思ってはいないだろうが、こんなかわいい子と倉美月春夜《くらみつきしゅんや》が歩いているという噂が流れないことを願う。
倉美月くん、昨日一緒に歩いていた人は彼女ですか。違います。違くないです、写真撮りました、はい共有。————っていうのはやめて。
「あそこはなんなのですか?」
ミツキが指差した場所は、フードコートである。ああ、そこはゾンビの群生地、いや聖地だ。レストランと違って席はどこに座ろうが、誰と座ろうが、どこに椅子を移動しようが自由なのだから、僕たちは恰好の餌食となってしまう。
僕とミツキを一周するように椅子に座るゾンビたちが今か、今かと、よだれを垂らしてミツキを狙っている。僕がライフルで一匹仕留めている間に、残りのゾンビがミツキを食い散らかす。僕はその凄惨な光景を目の当たりにして、一言呟く。だからフードコートはやめておけと言ったのに、と。
「フードコートといって、ファーストフードとかを自由に食べ……」
「行ってみたいですっ!!」
言うと思った。絶対に避けなければいけないのに、なぜこんなところにフードコートなんていう餌場を設けたイオン。僕が席を立った瞬間を見計らって、アイスクリームを食べているミツキの姿を見た魔王の手下が拉致しようと、飛んで来たらどうするの。ああ怖い。
「ええっと。危険区域だけど、大丈夫かな?」
「シュン君が守ってくれるのですよね?」
「いや、あの高校生の群衆は危険だと思うけど」
ミツキの表情が少しだけ曇った気がした。わたしショッピングモールに来るのはじめてなんです、と言うミツキの言葉が自然と脳内を駆け巡って、喉元に降りて来たときには僕の中で反芻していた。そして、週刊誌の記事が頭をよぎる。
少しでもミツキが楽しい時間を過ごすことがそんなに悪いことなの?
倉美月春夜はどうだったの?
特別扱いされたかったの?
今でも、みんなと一緒に溶け込みたいんでしょ?
心の外側にオブラートに包んだ優しく無責任な言葉を置いていかないで。
薄く触れれば壊れてしまいそうなビードロを扱うように接しないで。
「やはり難しいでしょうか」
「いや、行ってみよう。きっと大丈夫だよ!」
「いいのですか!? 嬉しい!!」
恐る恐るフードコート内に侵入すると、群がる高校生たちが僕たちを一瞥していく。まるで自分たちの縄張りに入ってきた獲物に舌なめずりをして狙うように。視線を掻い潜りながら抜けた先には、大パノラマのように広がるお店が、手招きをするように誘っている。
肉の焼ける香ばしいにおいのステーキ屋や、ソースが塗られたたこやき、色鮮やかで思わずスマホを向けたくなるタピオカ、季節限定のシェイクが気になるハンバーガーのお店、全部試したくなるスムージー専門店。
「こ、ここはオアシスですか!!」
何をどう見たらオアシスになるのか理解不能であったが、小腹が空いた僕たちにとって、目移りすることは確かだ。
「何食べたいの?」
「食べたことがないものばかりです。フォーティーワンアイスクリームも食べてみたいし、タピオカだって飲んでみたいです。あ、ドーナツもこうやって売っているのですね!」
結局、悩みに悩んでミツキが選んだのは、アイスクリームとタピオカだった。ドーナツは、大量に買い込んで持ち帰ることにした。フォーティーワンアイスクリームを食べるのは、実は僕も初めてだったりする。ダンスをしていたころは、身体を作ることに集中をしていて食べたことがなかったし、ダンスをしなくなった今は、運動ができないから食べようとは思わなかった。決してストイックではないのだけれど、気持ちがアイスクリームに向かなかっただけである。おいしいとは聞いていたけれど。
「なんですかこのおいしさ。こんなにおいしいなんて、ずるいです!」
なにが反則なのか不明であったが、アイスクリームを食べてとろけるような笑顔に、僕も頬が綻んだ。今頃気付いたのだが、これはデートというものなのではないだろうか。こんなところで、アイドルとデートするとは、人生何が起こるか分からない。
シュン君のアイスはどんな味なのですか。少しだけもらっていいですか。わあおいしい。わたしのもどうぞ。え、食べていいですよ。ね、おいしいでしょ。
って間接キスじゃないか。間接キスっていうのは、口と口が重ならないだけで、キスに変わりはないのだろうか。これがファースト間接キスの味。うん、抹茶とストロベリーの中間の味。ああ、アイスだから一瞬でなくなっちゃう。ほろ苦くて甘酸っぱいんだね。キスって。
「僕もはじめて食べたけれど、すごくおいしいんだね。ミツキちゃんと一緒に来なかったら一生食べなかったかも」
「じゃあ、お互い初体験ですね!」
ああ、僕は発狂してしまうかもしれない。薄い桃色の唇の中に吸われていく氷菓は、今どんな気持ちなのだろう。嬉しいのかな。彼女の唇はどんな感触なのだろう。柔らかいのかな。
僕はそんなミツキの顔を見て、自分がどんな表情をしているのだろうと気になった。彼女は僕をどう思っているのだろう。そう思うと、少しだけ胸の奥が締まる気がした。この時間が永遠に続けばいいのに、なんてどこかの恋愛小説みたいな語彙しか出てこないけど、そんなことを本当に思う日が来るなんて嘘みたい。まるで僕たちの周りの目がどうでもよくなるくらい、甘くて苦くて、少し……切なくて。
「そうだね。初体験はすごく甘いけど、おいしかった」
食べ終わったカップを捨てに行くと、僕たちをチラチラと見る女子高校生が気になった。明らかに訝しんでいる。もしかしたら花神楽美月とバレてしまったのかもしれないし、ただかわいい子がいると思っているだけなのかもしれない。しかし、明らかに視線は僕とミツキに向いていて、取って食おうとしているのだとしたら、ミツキが危険だ。今すぐ武器を持て、構えろ、引き金を引け!
「あの、すいません」
突然、声を掛けられたのは僕の方だった。はい、と振り向く。やはり先ほどからチラ見している女子高生だった。制服からすると、うちの高校ではなく、隣町の高校の生徒のようだ。長いブラウンの髪の毛が編み込まれていて、制服姿ではあるものの相当な威圧感がある。これが俗に言う、ヤ、ヤンキーというものなのか。さすが茨城。
「倉美月春夜さん……ですよね?」
なぜ僕の名前を知っているのか。僕はそこまで有名人ではないはずなのに。まさか、ミツキよりも僕の肉のほうがおいしそうだとか思っていないよね。怖いよ。
「そう……ですけれど」
「隣にいる方は彼女ですか? もしそうだとしたら、すごくショックなんですけど」
「はあ!?」
思わず僕は素っ頓狂な声を上げてしまった。僕の想像していた言葉とはだいぶ違うものだったから。普通、逆だろう。
花神楽美月さんですか? 隣にいるのは彼氏ですか? もしそうだとしたらショックです、と。
「あたし、倉美月春夜さんのファンです! 今でも。春夜さんのダンス好きです。あたしもダンスやっているんですけど、目標にしていました。だから、もし、また踊れることがあれば、応援しています! がんばってください」
僕は思わずおののいた。まさかそんなことを言ってくる人が未だにいるなんて信じられなかった。俯いて何も言えなかった。どう返したらいいのか分からない。なんで絶滅していないの。僕なんて今や、ミジンコ以下の存在なのに。
ありがとう。応援よろしくね。僕もまたダンスしたいな。イベントで会うの楽しみだね。君はどんなダンスをやっているの。今度見せてよ。応援するからさ。
どの言葉も口から出ることはなく、ただ頭の中から喉元にかけてを行ったり来たりするだけで、冷や汗だけが滴っていた。唇が震えて、過呼吸気味な気管支がうまく働かない。酸素と二酸化炭素が交互に口腔内で入り乱れて、思わず倒れそうになる。頭が真っ白。血の気が引く。今すぐ踵を返して逃げ出したい。ミツキごめん、秒で逃げるよ。
「彼は、倉美月春夜は、絶対に復活します! だから応援してあげてください! よろしくお願いしますっ!」
ミツキが大きく声を張り上げて、深々と頭を下げている。呆気に取られた女子高生は、瞬きを繰り返すだけで、僕よりもミツキのことが気になった様子だ。顔を上げたミツキを見て、女子高生はゆっくりと頷く。
「ショックなんて言ってごめん。春夜さんの力になってくれる人だったんだね。こんな彼女がいるなら、春夜さんも復活が早いかも。なんて」
ヤンキーだと思っていた女子高生はすこしだけ、はにかんだ。そうか、僕がダンスもやらずに女にかまけていたと思っていたのか。それでショック、と。そういう風に見られているとは思いもよらなかった。この女子高生は、本当に僕のことを見ていてくれたんだ。僕のことをこうして、今でも応援してくれる人がいるという事実は、本当につらい。
「ふふ。そうですね。きっとシュン君は復活します。だから、見捨てないでくださいね」
代弁するミツキを横目に、一言も話せない自分が悔しかった。僕は自分の言葉が見つからない。復活するのか。本当に復活できるのか。一曲を踊り切るのがやっとなのに。僕を応援してくれるこの子を失望させないだろうか。怖いよ。吐きそう。
「あれ、彼女さん、花神楽美月に似ているね」
————ッ!!!!
まずいまずいまずいまずいまずい。
「よく言われます。嬉しいのですけど、ちょっと——」
「不倫だっけ。まあ、見た目は別だからさ、素直に喜んでいいんじゃない?」
「ありがとうございます!」
ミツキは少しも表情を変えることなく、会話を続けて、さらに微笑んだ。ミツキはなんて強い子なのだろうと再び思う。自分のことなのに、そうやって他人事のように話せるなんて。僕も少しは、強くなりたい。少しだけでいい。ミツキの半分でいいから。少し切り分けてよ。ホールのケーキを四等分するみたいに。
「お、応援してくれてありがとう。僕なりにがんばるから……」
「うん。活動再開したら絶対に見に行くから」
倉美月くん、昨日一緒に歩いていた人は彼女ですか。違います。違くないです、写真撮りました、はい共有。————っていうのはやめて。
「あそこはなんなのですか?」
ミツキが指差した場所は、フードコートである。ああ、そこはゾンビの群生地、いや聖地だ。レストランと違って席はどこに座ろうが、誰と座ろうが、どこに椅子を移動しようが自由なのだから、僕たちは恰好の餌食となってしまう。
僕とミツキを一周するように椅子に座るゾンビたちが今か、今かと、よだれを垂らしてミツキを狙っている。僕がライフルで一匹仕留めている間に、残りのゾンビがミツキを食い散らかす。僕はその凄惨な光景を目の当たりにして、一言呟く。だからフードコートはやめておけと言ったのに、と。
「フードコートといって、ファーストフードとかを自由に食べ……」
「行ってみたいですっ!!」
言うと思った。絶対に避けなければいけないのに、なぜこんなところにフードコートなんていう餌場を設けたイオン。僕が席を立った瞬間を見計らって、アイスクリームを食べているミツキの姿を見た魔王の手下が拉致しようと、飛んで来たらどうするの。ああ怖い。
「ええっと。危険区域だけど、大丈夫かな?」
「シュン君が守ってくれるのですよね?」
「いや、あの高校生の群衆は危険だと思うけど」
ミツキの表情が少しだけ曇った気がした。わたしショッピングモールに来るのはじめてなんです、と言うミツキの言葉が自然と脳内を駆け巡って、喉元に降りて来たときには僕の中で反芻していた。そして、週刊誌の記事が頭をよぎる。
少しでもミツキが楽しい時間を過ごすことがそんなに悪いことなの?
倉美月春夜はどうだったの?
特別扱いされたかったの?
今でも、みんなと一緒に溶け込みたいんでしょ?
心の外側にオブラートに包んだ優しく無責任な言葉を置いていかないで。
薄く触れれば壊れてしまいそうなビードロを扱うように接しないで。
「やはり難しいでしょうか」
「いや、行ってみよう。きっと大丈夫だよ!」
「いいのですか!? 嬉しい!!」
恐る恐るフードコート内に侵入すると、群がる高校生たちが僕たちを一瞥していく。まるで自分たちの縄張りに入ってきた獲物に舌なめずりをして狙うように。視線を掻い潜りながら抜けた先には、大パノラマのように広がるお店が、手招きをするように誘っている。
肉の焼ける香ばしいにおいのステーキ屋や、ソースが塗られたたこやき、色鮮やかで思わずスマホを向けたくなるタピオカ、季節限定のシェイクが気になるハンバーガーのお店、全部試したくなるスムージー専門店。
「こ、ここはオアシスですか!!」
何をどう見たらオアシスになるのか理解不能であったが、小腹が空いた僕たちにとって、目移りすることは確かだ。
「何食べたいの?」
「食べたことがないものばかりです。フォーティーワンアイスクリームも食べてみたいし、タピオカだって飲んでみたいです。あ、ドーナツもこうやって売っているのですね!」
結局、悩みに悩んでミツキが選んだのは、アイスクリームとタピオカだった。ドーナツは、大量に買い込んで持ち帰ることにした。フォーティーワンアイスクリームを食べるのは、実は僕も初めてだったりする。ダンスをしていたころは、身体を作ることに集中をしていて食べたことがなかったし、ダンスをしなくなった今は、運動ができないから食べようとは思わなかった。決してストイックではないのだけれど、気持ちがアイスクリームに向かなかっただけである。おいしいとは聞いていたけれど。
「なんですかこのおいしさ。こんなにおいしいなんて、ずるいです!」
なにが反則なのか不明であったが、アイスクリームを食べてとろけるような笑顔に、僕も頬が綻んだ。今頃気付いたのだが、これはデートというものなのではないだろうか。こんなところで、アイドルとデートするとは、人生何が起こるか分からない。
シュン君のアイスはどんな味なのですか。少しだけもらっていいですか。わあおいしい。わたしのもどうぞ。え、食べていいですよ。ね、おいしいでしょ。
って間接キスじゃないか。間接キスっていうのは、口と口が重ならないだけで、キスに変わりはないのだろうか。これがファースト間接キスの味。うん、抹茶とストロベリーの中間の味。ああ、アイスだから一瞬でなくなっちゃう。ほろ苦くて甘酸っぱいんだね。キスって。
「僕もはじめて食べたけれど、すごくおいしいんだね。ミツキちゃんと一緒に来なかったら一生食べなかったかも」
「じゃあ、お互い初体験ですね!」
ああ、僕は発狂してしまうかもしれない。薄い桃色の唇の中に吸われていく氷菓は、今どんな気持ちなのだろう。嬉しいのかな。彼女の唇はどんな感触なのだろう。柔らかいのかな。
僕はそんなミツキの顔を見て、自分がどんな表情をしているのだろうと気になった。彼女は僕をどう思っているのだろう。そう思うと、少しだけ胸の奥が締まる気がした。この時間が永遠に続けばいいのに、なんてどこかの恋愛小説みたいな語彙しか出てこないけど、そんなことを本当に思う日が来るなんて嘘みたい。まるで僕たちの周りの目がどうでもよくなるくらい、甘くて苦くて、少し……切なくて。
「そうだね。初体験はすごく甘いけど、おいしかった」
食べ終わったカップを捨てに行くと、僕たちをチラチラと見る女子高校生が気になった。明らかに訝しんでいる。もしかしたら花神楽美月とバレてしまったのかもしれないし、ただかわいい子がいると思っているだけなのかもしれない。しかし、明らかに視線は僕とミツキに向いていて、取って食おうとしているのだとしたら、ミツキが危険だ。今すぐ武器を持て、構えろ、引き金を引け!
「あの、すいません」
突然、声を掛けられたのは僕の方だった。はい、と振り向く。やはり先ほどからチラ見している女子高生だった。制服からすると、うちの高校ではなく、隣町の高校の生徒のようだ。長いブラウンの髪の毛が編み込まれていて、制服姿ではあるものの相当な威圧感がある。これが俗に言う、ヤ、ヤンキーというものなのか。さすが茨城。
「倉美月春夜さん……ですよね?」
なぜ僕の名前を知っているのか。僕はそこまで有名人ではないはずなのに。まさか、ミツキよりも僕の肉のほうがおいしそうだとか思っていないよね。怖いよ。
「そう……ですけれど」
「隣にいる方は彼女ですか? もしそうだとしたら、すごくショックなんですけど」
「はあ!?」
思わず僕は素っ頓狂な声を上げてしまった。僕の想像していた言葉とはだいぶ違うものだったから。普通、逆だろう。
花神楽美月さんですか? 隣にいるのは彼氏ですか? もしそうだとしたらショックです、と。
「あたし、倉美月春夜さんのファンです! 今でも。春夜さんのダンス好きです。あたしもダンスやっているんですけど、目標にしていました。だから、もし、また踊れることがあれば、応援しています! がんばってください」
僕は思わずおののいた。まさかそんなことを言ってくる人が未だにいるなんて信じられなかった。俯いて何も言えなかった。どう返したらいいのか分からない。なんで絶滅していないの。僕なんて今や、ミジンコ以下の存在なのに。
ありがとう。応援よろしくね。僕もまたダンスしたいな。イベントで会うの楽しみだね。君はどんなダンスをやっているの。今度見せてよ。応援するからさ。
どの言葉も口から出ることはなく、ただ頭の中から喉元にかけてを行ったり来たりするだけで、冷や汗だけが滴っていた。唇が震えて、過呼吸気味な気管支がうまく働かない。酸素と二酸化炭素が交互に口腔内で入り乱れて、思わず倒れそうになる。頭が真っ白。血の気が引く。今すぐ踵を返して逃げ出したい。ミツキごめん、秒で逃げるよ。
「彼は、倉美月春夜は、絶対に復活します! だから応援してあげてください! よろしくお願いしますっ!」
ミツキが大きく声を張り上げて、深々と頭を下げている。呆気に取られた女子高生は、瞬きを繰り返すだけで、僕よりもミツキのことが気になった様子だ。顔を上げたミツキを見て、女子高生はゆっくりと頷く。
「ショックなんて言ってごめん。春夜さんの力になってくれる人だったんだね。こんな彼女がいるなら、春夜さんも復活が早いかも。なんて」
ヤンキーだと思っていた女子高生はすこしだけ、はにかんだ。そうか、僕がダンスもやらずに女にかまけていたと思っていたのか。それでショック、と。そういう風に見られているとは思いもよらなかった。この女子高生は、本当に僕のことを見ていてくれたんだ。僕のことをこうして、今でも応援してくれる人がいるという事実は、本当につらい。
「ふふ。そうですね。きっとシュン君は復活します。だから、見捨てないでくださいね」
代弁するミツキを横目に、一言も話せない自分が悔しかった。僕は自分の言葉が見つからない。復活するのか。本当に復活できるのか。一曲を踊り切るのがやっとなのに。僕を応援してくれるこの子を失望させないだろうか。怖いよ。吐きそう。
「あれ、彼女さん、花神楽美月に似ているね」
————ッ!!!!
まずいまずいまずいまずいまずい。
「よく言われます。嬉しいのですけど、ちょっと——」
「不倫だっけ。まあ、見た目は別だからさ、素直に喜んでいいんじゃない?」
「ありがとうございます!」
ミツキは少しも表情を変えることなく、会話を続けて、さらに微笑んだ。ミツキはなんて強い子なのだろうと再び思う。自分のことなのに、そうやって他人事のように話せるなんて。僕も少しは、強くなりたい。少しだけでいい。ミツキの半分でいいから。少し切り分けてよ。ホールのケーキを四等分するみたいに。
「お、応援してくれてありがとう。僕なりにがんばるから……」
「うん。活動再開したら絶対に見に行くから」
0
あなたにおすすめの小説

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

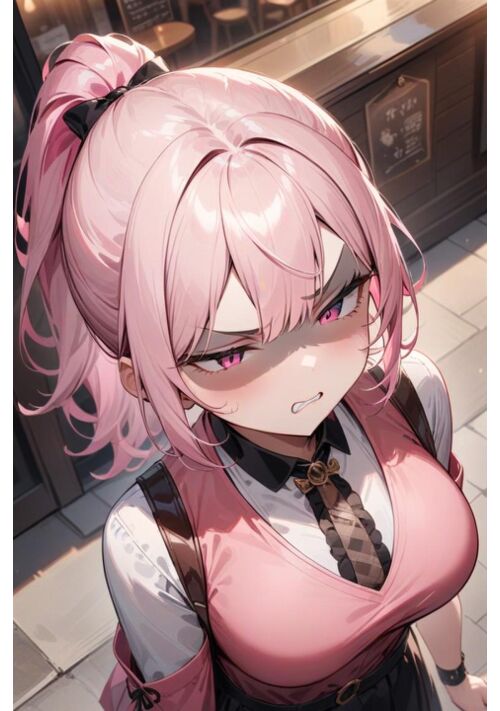
【朗報】俺をこっぴどく振った幼馴染がレンカノしてたので2時間15,000円でレンタルしてみました
田中又雄
恋愛
俺には幼稚園の頃からの幼馴染がいた。
しかし、高校進学にあたり、別々の高校に行くことになったため、中学卒業のタイミングで思い切って告白してみた。
だが、返ってきたのは…「はぁ!?誰があんたみたいなのと付き合うのよ!」という酷い言葉だった。
それからは家は近所だったが、それからは一度も話をすることもなく、高校を卒業して、俺たちは同じ大学に行くことになった。
そんなある日、とある噂を聞いた。
どうやら、あいつがレンタル彼女なるものを始めたとか…。
気持ち悪いと思いながらも俺は予約を入れるのであった。
そうして、デート当日。
待ち合わせ場所に着くと、後ろから彼女がやってきた。
「あ、ごめんね!待たせちゃっ…た…よ…ね」と、どんどんと顔が青ざめる。
「…待ってないよ。マイハニー」
「なっ…!?なんであんたが…!ばっかじゃないの!?」
「あんた…?何を言っているんだい?彼女が彼氏にあんたとか言わないよね?」
「頭おかしいんじゃないの…」
そうして、ドン引きする幼馴染と俺は初デートをするのだった。

JKメイドはご主人様のオモチャ 命令ひとつで脱がされて、触られて、好きにされて――
のぞみ
恋愛
「今日から、お前は俺のメイドだ。ベッドの上でもな」
高校二年生の蒼井ひなたは、借金に追われた家族の代わりに、ある大富豪の家で住み込みメイドとして働くことに。
そこは、まるでおとぎ話に出てきそうな大きな洋館。
でも、そこで待っていたのは、同じ高校に通うちょっと有名な男の子――完璧だけど性格が超ドSな御曹司、天城 蓮だった。
昼間は生徒会長、夜は…ご主人様?
しかも、彼の命令はちょっと普通じゃない。
「掃除だけじゃダメだろ? ご主人様の癒しも、メイドの大事な仕事だろ?」
手を握られるたび、耳元で囁かれるたび、心臓がバクバクする。
なのに、ひなたの体はどんどん反応してしまって…。
怒ったり照れたりしながらも、次第に蓮に惹かれていくひなた。
だけど、彼にはまだ知られていない秘密があって――
「…ほんとは、ずっと前から、私…」
ただのメイドなんかじゃ終わりたくない。
恋と欲望が交差する、ちょっぴり危険な主従ラブストーリー。

敵に貞操を奪われて癒しの力を失うはずだった聖女ですが、なぜか前より漲っています
藤谷 要
恋愛
サルサン国の聖女たちは、隣国に征服される際に自国の王の命で殺されそうになった。ところが、侵略軍将帥のマトルヘル侯爵に助けられた。それから聖女たちは侵略国に仕えるようになったが、一か月後に筆頭聖女だったルミネラは命の恩人の侯爵へ嫁ぐように国王から命じられる。
結婚披露宴では、陛下に側妃として嫁いだ旧サルサン国王女が出席していたが、彼女は侯爵に腕を絡めて「陛下の手がつかなかったら一年後に妻にしてほしい」と頼んでいた。しかも、侯爵はその手を振り払いもしない。
聖女は愛のない交わりで神の加護を失うとされているので、当然白い結婚だと思っていたが、初夜に侯爵のメイアスから体の関係を迫られる。彼は命の恩人だったので、ルミネラはそのまま彼を受け入れた。
侯爵がかつての恋人に似ていたとはいえ、侯爵と孤児だった彼は全く別人。愛のない交わりだったので、当然力を失うと思っていたが、なぜか以前よりも力が漲っていた。
※全11話 2万字程度の話です。

診察室の午後<菜の花の丘編>その1
スピカナ
恋愛
神的イケメン医師・北原春樹と、病弱で天才的なアーティストである妻・莉子。
そして二人を愛してしまったイケメン御曹司・浅田夏輝。
「菜の花クリニック」と「サテライトセンター」を舞台に、三人の愛と日常が描かれます。
時に泣けて、時に笑える――溺愛とBL要素を含む、ほのぼの愛の物語。
多くのスタッフの人生がここで楽しく花開いていきます。
この小説は「医師の兄が溺愛する病弱な義妹を毎日診察する甘~い愛の物語」の1000話以降の続編です。
※医学描写と他もすべて架空です。

【完結】退職を伝えたら、無愛想な上司に囲われました〜逃げられると思ったのが間違いでした〜
来栖れいな
恋愛
逃げたかったのは、
疲れきった日々と、叶うはずのない憧れ――のはずだった。
無愛想で冷静な上司・東條崇雅。
その背中に、ただ静かに憧れを抱きながら、
仕事の重圧と、自分の想いの行き場に限界を感じて、私は退職を申し出た。
けれど――
そこから、彼の態度は変わり始めた。
苦手な仕事から外され、
負担を減らされ、
静かに、けれど確実に囲い込まれていく私。
「辞めるのは認めない」
そんな言葉すらないのに、
無言の圧力と、不器用な優しさが、私を縛りつけていく。
これは愛?
それともただの執着?
じれじれと、甘く、不器用に。
二人の距離は、静かに、でも確かに近づいていく――。
無愛想な上司に、心ごと囲い込まれる、じれじれ溺愛・執着オフィスラブ。
※この物語はフィクションです。
登場する人物・団体・名称・出来事などはすべて架空であり、実在のものとは一切関係ありません。

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















