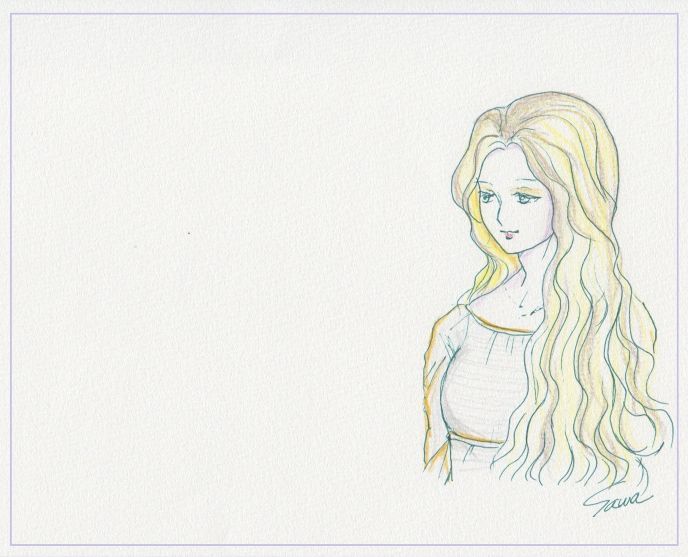60 / 480
第3章 フィガロは広場に行く1 ニコラス・コレーリャ
舞台から去るひとびと 1508年 フォルリからミラノへ
しおりを挟む
<ソッラ、ミケーレ・ダ・コレーリア、ルクレツィア・ボルジア、カテリーナ・スフォルツァ>
イタリア半島の東側を進んでいるミケーレ・ダ・コレーリアとソッラ、ふたりはリミニでいったんアドリア海に出たあと、また内陸に行く道を取った。フォルリ、イーモラに行くためだ。
この頃、イタリア半島に住むスペイン人の多くはナポリに集中していた。この地がスペインの領有となっていたからである。イタリア戦争で名を馳せた英雄で、「グラン・カピターノ」と呼ばれた総督のゴンサロ・フェルナンデス・コルドーバはつい先ごろ任を解かれてナポリを後にしていたが、スペインによる支配体制はその間に磐石になっていた。
ナポリほどの人数ではないが、イタリア半島の各地にスペイン人はいた。いかにもスペイン人である、というそぶりはしない。フィレンツェの人、ミラノの人、ヴェネツィアの人、ジェノヴァの人……というようにその土地に順応して暮らしている。
この頃、イベリア半島ではカスティーリャとアラゴンの両王国がひとつになり、スペインという領邦国家が形成されている。その後、アラゴンに接するナヴァーラ王国もそれに加えられることになる。
イタリア半島はまだそうではない。ローマの教皇庁とそれをとりまく教皇領、ヴェネツィア、フィレンツェ、ミラノ、ナポリをはじめとする共和国や公国に細かく分割されている。それは何世紀も変わっていない。ナポリはスペインに、ミラノはフランスに支配権を渡していた。そこに神聖ローマ帝国(現在のドイツ)も参入しようと様子をうかがっている状態だ。イタリア半島はこの後も長く統一されることがない。紆余曲折(うよきょくせつ)を経てその端緒が見えてくるのは19世紀のガリバルディの時代まで待たなければならない。
チェーザレ・ボルジアはイタリアをひとつにするべきだと考えていた。
その先には古(いにしえ)のローマ帝国の姿を描いていたにせよ、まずイタリアを統一しなければならないと考えていた。スペインやフランスではない、あくまでもローマを中心とした統一である。
フォルリの街に入ると、ミケーレはどことなく懐かしさを覚えた。
彼自身はこの街で激しい戦闘を行ったわけではない。敵方に籠城されて手を焼いたのはチェーザレである。そしてチェーザレがその立場を追われた後、この街の民だけが最後まで彼に忠誠を誓ってローマに抵抗したのである。今はもうそんな話も過去のことになったが、チェーザレを最後まで見捨てなかった街はミケーレにも居心地のよさを感じさせるのだ。
ソッラは広場に面するサン・メルクリアーレ教会に入りたいと言った。細い鐘楼が天を突き刺すように建っていて、彼女はフィレンツェでするときと同じように少し脇によけた。倒れてきたらどうしようかと心配になるのだ。ミケーレもソッラのその習慣はもう理解している。
ソッラは新しい町に至ると、必ず教会に寄りたいと言うようになった。チェゼーナの教会でミケーレと祈りを捧げたことによほど感動したらしい。ミケーレにとっても、それはこれまで感じたことのないような深い経験だった。カトリックの中心地(ローマ)がずっと生活の場で、そのときにはまったく感じなかったのに不思議なものである。それがサン・ピエトロ聖堂であれ村の小さな教会であれ、入る人間がどう思うかによって「聖なるもの」の見え方はまったく異なるようだ。
サン・メルクリアーレ教会のフレスコ画にソッラは目を奪われた。
「ミケーレは、絵は描かないの?」と彼女は隣にいる恋人に聞く。
「描かない。なぜ?」とミケーレが聞き返す。
「そうしたら、私の絵も描いてもらえるのに。この絵は本当に美しいわ。ほら、マルガリータが聖母のモデルにならないかって言われたでしょう。男に騙されるのはイヤだけど、聖母のモデルにならないかって言われたらたいていの女性は迷ってしまうと思うわ。評判の画家ならなおさら。マルガリータは災難だったけど、迷ったのは当然のことだと思う。でも……もし、ミケーレが私の絵を描いてくれるなら、どんなにへたくそでもかまわないけれど」とソッラが言う。ミケーレはその無邪気な様子に微笑む。
「じゃあ、描いてみようか」
ミケーレ・ダ・コレーリアが絵を描く! チェーザレ・ボルジアが聞いたらどんな顔をするだろうか。「そのような手の使い方もできるな」ぐらいのことは言うのかもしれない。ミケーレはおかしくなって失笑した。そう、手の使い方にもいろいろある。人を殺すこともできれば、女を愛することもできるし、絵や彫刻を創ることもできる。鍛冶屋もパン屋もその手があってこその仕事だ。
俺ももう少し、手の使い方を学ばなければいけない。
考え事をするミケーレの顔をソッラがのぞき込む。
「ミケーレに絵を描かせた女性は他にいなかったみたいね。それならなおさら楽しみにしているわ……でも、本当に見事なフレスコ画。きっとここの貴族がたくさんお金を払ったのでしょうね」とソッラがうっとりと絵を眺める。
「これは……カテリーナ・スフォルツァが描かせたものだろう」
ソッラはカテリーナ・スフォルツァを知らなかった。
カテリーナ・スフォルツァ、ミラノを治めていたガレアッツォ・スフォルツァの庶出の娘で、かつてイーモラとフォルリの領主だった女性だ。武勇に秀でたスフォルツァの血を引く彼女は、女だてらに(という表現は適切ではないが)甲冑を着込んでいくつもの反乱を収拾した。その人生は戦いの連続といえよう。肖像画を見ると肌が透き通るように白く醒めた表情が魅力的な、たいへん美しい女性である。彼女が考案した白い肌を保つための美容法はその後も長くヨーロッパの宮廷に伝えられ、お手本となった。
彼女は愛に生きた人でもあった。特にジョヴァンニ・デ・メディチとの関係は政治的な問題のために公にできなかったが、どんな禁忌も吹き飛ばすほどの激しいものだった。二人の愛の結晶である息子は後年、「黒隊のジョヴァンニ」(父と同じ名である)と呼ばれ、イタリア半島きっての武人として名を馳せる。
このときまだカテリーナは生きている。しかし、もう表舞台に出てくることはない。
ソッラはフィレンツェに住んでいたから、分からないのも無理はない。しかしここフォルリの市民はまだ覚えているだろう。フォルリの領主だった彼女とチェーザレ・ボルジアがここで戦ってからまだ8年しか経っていない。
いや、それ以前にカテリーナが領主の頃、家臣とその一族郎党数十人を処刑してさらしたことがある。愛人を暗殺されたことに対する報復だった。そちらのほうが市民により長く語り継がれる話だろう。怒りにまかせて躊躇(ちゅうちょ)なく家臣やその家族まで吊るし首にし、馬で八つ裂きにし、井戸に放り込んだ。それを見せ付けられた「恐怖」があったから、市民はカテリーナを拒否し、チェーザレを解放者として歓迎するにいたったのだ。
領民にも背を向けられてチェーザレに屈したカテリーナはその後短期間、カスタル・サンタンジェロの地下牢に投獄された。そして今は修道院に移されて余生を過ごしている。「入ったら、生きて二度と出られない」と怖れられたカスタル・サンタンジェロでの経験は彼女の生気をほぼ全て奪い取ってしまった。
確かにあの地下牢に入れられれば、貴族としての誇りなどどこかに吹っ飛んでしまうに違いない。
カスタル・サンタンジェロに投獄されたうえに、拷問まで受けていたミケーレである。カテリーナの身の上には同情すべきものがあった。
フォルリにはスペイン人の同胞が何人か暮らしていた。最後までチェーザレの帰還を待ちわびていた街である。スペイン人が派手に表に出ることはなかったが、市民として普通の生活を送っている。ミケーレはその中の一人にあたろうと思っていた。しかし、あたらなくとも、向こうのほうが先に見つけてこちらに寄ってきた。広場を歩いていると必ず誰かの目に触れるし、その伝手(つて)が思いもよらぬ方向に飛んでいき、目当ての人間やそうでない人間が寄ってくるという仕組みである。
「ドン・ミケロット、フィレンツェを出たそうですね」と近寄ってきた男がいた。ホアンという名のスペイン人である。ミケーレとは深い知り合いではないが、スペイン語で話しかけられることに深い安堵感を覚える。一方のソッラはきょとんとしている。彼女の親はスペイン語を話すが子供の前では使わなかった。それなので、ソッラは簡単な単語以外はスペイン語を理解できないのである。
二人はその日同胞の家に泊まることとなった。久しぶりに家庭で食べるような料理がふるまわれる。温かいスープ、野菜を煮たもの、パンをご馳走になり、話も弾んだ。そして、食事も終わってホアンの妻とソッラが片付けに下がったあと、ホアンはミケーレに話をした。
「ドン・ミケロット、あなたはミラノに向かってください」とホアンがいう。
ホアンの話はこうである。ミラノ総督のフランス人、シャルル・ダンボワーズ伯がドン・ミケロット、すなわちミケーレ・ダ・コレーリアを傭兵隊長として招きたい。しかし、フィレンツェを出て以降の足取りがよく分からない。イタリア半島で彼が寄りそうな街にはすでに人が出されており、ミケーレを見つけしだいミラノに連れてくるようにと――。
「まるでおたずね者のようだな」とミケーレは苦笑する。
「どうやら、ドン・ミケロットをフランス軍の傭兵隊長にしたいようです。スイス兵をまとめるような仕事になるのかもしれません。もしかしたらミラノだけではなく、フランスに行くことになるかもしれませんね」とホアンが言う。
「そうか、ミラノか……ミラノやヴェネツィアから話が来ることはないと思っていたが、今の状態では願ってもない話だ。さっそくミラノに向かうことにする」とミケーレはうなずく。
ソッラがホアンの妻と談笑しながら戻ってきた。ミケーレはそれを見て思い出したようにホアンに声をかける。
「ホアン、申し訳ないが、ペンかチョークと、紙か、あるいは板と端切れの布をもらえないだろうか」
「ありますよ。でも、何をするのですか?」とホアンが聞く。
「絵を描くんだ」
ミケーレの一言にホアンは目を丸くした。
「ドン・ミケロットが絵を描かれるのですか? そんな趣味があったとは……」
ソッラがくすくす笑う。ミケーレもふっとため息をついて苦笑する。
和やかな夜が過ぎていく。
そして、ふたりはミラノへの道を歩くことになった。フォルリ~イーモラ~ボローニャ~モデナ~パルマ~ピアチェンツァ~ミラノと続く道である。ミケーレは途中でフェラーラも回ったほうがいいのかと悩んだ。フェラーラにはチェーザレ・ボルジアの妹ルクレツィアがいる。そして現在はフェラーラ公アルフォンソ・デステの妻である。悲劇に見舞われたイタリアのボルジア一族の中で唯一安泰に暮らしているといえる。
悲劇だ、とミケーレは思う。
ルクレツィアの家族の現在を思うと、である。
父の元教皇アレクサンデル6世は1503年に3日ごとの熱(マラリア)で死亡。
長兄のペドロ・ルイス(初代ガンディア公)は若くして1488年に死亡。
次兄のチェーザレはスペインに追放になったのちに1507年に死亡(といわれている)。
その次の兄ホアン(2代目ガンディア公)は若くして1497年に殺害される。
弟ホフレはまだ存命だが、ボルジア家への報復を恐れてひっそりと小さな領地に暮らしている(1517年死去)。
母のヴァノッツァも存命だがひっそりと暮らしている(1518年死去)。
それが大きな野望の代償だったのだろうか。
チェーザレ・ボルジアの、古(いにしえ)のローマ帝国を興すという野望の……いや、それは結局チェーザレの手に入らなかった。運命の女神というのがいるのであれば、彼女が突然彼を見限ったようにしか思えないほどの急転だった。
ミケーレはルクレツィアのことを幼い頃から知っている。淋しがり屋で勝気で、それでいて無邪気で、人に愛されることの意味を理解している少女だった。父や兄(チェーザレ)の都合で2回の結婚をして、いずれも情勢の変化によって引き離される結果に終わった。3度目でようやく、引き離されることのないところに嫁ぐことができたのだ。元教皇アレクサンデル6世は娘のことを心から愛していた。2度目の結婚が悲惨な結末を迎えた後、彼女が修道院に引きこもってしまったのを見て、父親として心から反省したのかもしれない。3度目の夫には、彼女を守りきれるだろう男を選んだのだ。それは間違いではなかった。武人であるアルフォンソ・デステはボルジア家に何があろうと、妻を見捨てたりはしなかった。
ミケーレはそれを思い浮かべながら、フェラーラに立ち寄るのを止めた。
彼女の2番目の夫を殺したのがミケーレだったからだ。
チェーザレ・ボルジアの命令だったが、誰の命令にせよ、殺したのは自分なのだ。
そう思うと、ルクレツィアに会うことはできないと思う。命じたのがチェーザレだと分かっていても、直接手を下した人間を許せるものなのか、ミケーレには分からなかった。
「そうね……あなたの意思でしたことではないと、頭では理解できても……気持ちはそうではないかもしれないわね。ミケーレ、あなたの気持ちもそう。今整理がつかないのなら、少し時を待てばいいと思う。いずれにしても、ルクレツィアさまは今、フェラーラの公妃として幸せに暮らしているのだから」
ミケーレはソッラの言葉を聞きながら、彼女の存在を心からありがたいと思っていた。ミケーレはチェゼーナの夜以降、ソッラに何でも話すようにしている。彼の話はときどき暗殺や戦闘などの凄まじい内容になり、ソッラは何度も息が止まるほど驚いた。彼が本当にチェーザレ・ボルジアのために一身を捧げてきたことはよく理解できたし、それを誰にも言わずにずっと溜め込んでいたことも分かった。どれほど苦しかったことか、とソッラは思う。
ソッラは海のようだった。どんなに激しい奔流でも穏やかに飲み込んでしまう。ミケーレはソッラなしで今まで生きてこられたことが不思議に思えた。それほど彼女を必要としていたのである。彼女は間違いなく、ミケーレ・ダ・コレーリアを誰よりも知っている人間になっていた。
彼の奔流はソッラだけに注がれていた。フォルリからミラノにいたる旅の間、恋人たちには濃密な時間が流れる。彼らは夜を心待ちにして歩き続けた。夜はふたりにとって、思う存分に愛しあえる大切な空間だ。その間はずっと起きている。そして太陽が出てきてから、やっと眠りにつくのである。
ソッラはどんどん艶めかしく変わっていく。すれ違う男が例外なく振り返るほどに。
もう季節は厳冬になっている。
ふたりの旅が終わりに近づこうとしていた。
イタリア半島の東側を進んでいるミケーレ・ダ・コレーリアとソッラ、ふたりはリミニでいったんアドリア海に出たあと、また内陸に行く道を取った。フォルリ、イーモラに行くためだ。
この頃、イタリア半島に住むスペイン人の多くはナポリに集中していた。この地がスペインの領有となっていたからである。イタリア戦争で名を馳せた英雄で、「グラン・カピターノ」と呼ばれた総督のゴンサロ・フェルナンデス・コルドーバはつい先ごろ任を解かれてナポリを後にしていたが、スペインによる支配体制はその間に磐石になっていた。
ナポリほどの人数ではないが、イタリア半島の各地にスペイン人はいた。いかにもスペイン人である、というそぶりはしない。フィレンツェの人、ミラノの人、ヴェネツィアの人、ジェノヴァの人……というようにその土地に順応して暮らしている。
この頃、イベリア半島ではカスティーリャとアラゴンの両王国がひとつになり、スペインという領邦国家が形成されている。その後、アラゴンに接するナヴァーラ王国もそれに加えられることになる。
イタリア半島はまだそうではない。ローマの教皇庁とそれをとりまく教皇領、ヴェネツィア、フィレンツェ、ミラノ、ナポリをはじめとする共和国や公国に細かく分割されている。それは何世紀も変わっていない。ナポリはスペインに、ミラノはフランスに支配権を渡していた。そこに神聖ローマ帝国(現在のドイツ)も参入しようと様子をうかがっている状態だ。イタリア半島はこの後も長く統一されることがない。紆余曲折(うよきょくせつ)を経てその端緒が見えてくるのは19世紀のガリバルディの時代まで待たなければならない。
チェーザレ・ボルジアはイタリアをひとつにするべきだと考えていた。
その先には古(いにしえ)のローマ帝国の姿を描いていたにせよ、まずイタリアを統一しなければならないと考えていた。スペインやフランスではない、あくまでもローマを中心とした統一である。
フォルリの街に入ると、ミケーレはどことなく懐かしさを覚えた。
彼自身はこの街で激しい戦闘を行ったわけではない。敵方に籠城されて手を焼いたのはチェーザレである。そしてチェーザレがその立場を追われた後、この街の民だけが最後まで彼に忠誠を誓ってローマに抵抗したのである。今はもうそんな話も過去のことになったが、チェーザレを最後まで見捨てなかった街はミケーレにも居心地のよさを感じさせるのだ。
ソッラは広場に面するサン・メルクリアーレ教会に入りたいと言った。細い鐘楼が天を突き刺すように建っていて、彼女はフィレンツェでするときと同じように少し脇によけた。倒れてきたらどうしようかと心配になるのだ。ミケーレもソッラのその習慣はもう理解している。
ソッラは新しい町に至ると、必ず教会に寄りたいと言うようになった。チェゼーナの教会でミケーレと祈りを捧げたことによほど感動したらしい。ミケーレにとっても、それはこれまで感じたことのないような深い経験だった。カトリックの中心地(ローマ)がずっと生活の場で、そのときにはまったく感じなかったのに不思議なものである。それがサン・ピエトロ聖堂であれ村の小さな教会であれ、入る人間がどう思うかによって「聖なるもの」の見え方はまったく異なるようだ。
サン・メルクリアーレ教会のフレスコ画にソッラは目を奪われた。
「ミケーレは、絵は描かないの?」と彼女は隣にいる恋人に聞く。
「描かない。なぜ?」とミケーレが聞き返す。
「そうしたら、私の絵も描いてもらえるのに。この絵は本当に美しいわ。ほら、マルガリータが聖母のモデルにならないかって言われたでしょう。男に騙されるのはイヤだけど、聖母のモデルにならないかって言われたらたいていの女性は迷ってしまうと思うわ。評判の画家ならなおさら。マルガリータは災難だったけど、迷ったのは当然のことだと思う。でも……もし、ミケーレが私の絵を描いてくれるなら、どんなにへたくそでもかまわないけれど」とソッラが言う。ミケーレはその無邪気な様子に微笑む。
「じゃあ、描いてみようか」
ミケーレ・ダ・コレーリアが絵を描く! チェーザレ・ボルジアが聞いたらどんな顔をするだろうか。「そのような手の使い方もできるな」ぐらいのことは言うのかもしれない。ミケーレはおかしくなって失笑した。そう、手の使い方にもいろいろある。人を殺すこともできれば、女を愛することもできるし、絵や彫刻を創ることもできる。鍛冶屋もパン屋もその手があってこその仕事だ。
俺ももう少し、手の使い方を学ばなければいけない。
考え事をするミケーレの顔をソッラがのぞき込む。
「ミケーレに絵を描かせた女性は他にいなかったみたいね。それならなおさら楽しみにしているわ……でも、本当に見事なフレスコ画。きっとここの貴族がたくさんお金を払ったのでしょうね」とソッラがうっとりと絵を眺める。
「これは……カテリーナ・スフォルツァが描かせたものだろう」
ソッラはカテリーナ・スフォルツァを知らなかった。
カテリーナ・スフォルツァ、ミラノを治めていたガレアッツォ・スフォルツァの庶出の娘で、かつてイーモラとフォルリの領主だった女性だ。武勇に秀でたスフォルツァの血を引く彼女は、女だてらに(という表現は適切ではないが)甲冑を着込んでいくつもの反乱を収拾した。その人生は戦いの連続といえよう。肖像画を見ると肌が透き通るように白く醒めた表情が魅力的な、たいへん美しい女性である。彼女が考案した白い肌を保つための美容法はその後も長くヨーロッパの宮廷に伝えられ、お手本となった。
彼女は愛に生きた人でもあった。特にジョヴァンニ・デ・メディチとの関係は政治的な問題のために公にできなかったが、どんな禁忌も吹き飛ばすほどの激しいものだった。二人の愛の結晶である息子は後年、「黒隊のジョヴァンニ」(父と同じ名である)と呼ばれ、イタリア半島きっての武人として名を馳せる。
このときまだカテリーナは生きている。しかし、もう表舞台に出てくることはない。
ソッラはフィレンツェに住んでいたから、分からないのも無理はない。しかしここフォルリの市民はまだ覚えているだろう。フォルリの領主だった彼女とチェーザレ・ボルジアがここで戦ってからまだ8年しか経っていない。
いや、それ以前にカテリーナが領主の頃、家臣とその一族郎党数十人を処刑してさらしたことがある。愛人を暗殺されたことに対する報復だった。そちらのほうが市民により長く語り継がれる話だろう。怒りにまかせて躊躇(ちゅうちょ)なく家臣やその家族まで吊るし首にし、馬で八つ裂きにし、井戸に放り込んだ。それを見せ付けられた「恐怖」があったから、市民はカテリーナを拒否し、チェーザレを解放者として歓迎するにいたったのだ。
領民にも背を向けられてチェーザレに屈したカテリーナはその後短期間、カスタル・サンタンジェロの地下牢に投獄された。そして今は修道院に移されて余生を過ごしている。「入ったら、生きて二度と出られない」と怖れられたカスタル・サンタンジェロでの経験は彼女の生気をほぼ全て奪い取ってしまった。
確かにあの地下牢に入れられれば、貴族としての誇りなどどこかに吹っ飛んでしまうに違いない。
カスタル・サンタンジェロに投獄されたうえに、拷問まで受けていたミケーレである。カテリーナの身の上には同情すべきものがあった。
フォルリにはスペイン人の同胞が何人か暮らしていた。最後までチェーザレの帰還を待ちわびていた街である。スペイン人が派手に表に出ることはなかったが、市民として普通の生活を送っている。ミケーレはその中の一人にあたろうと思っていた。しかし、あたらなくとも、向こうのほうが先に見つけてこちらに寄ってきた。広場を歩いていると必ず誰かの目に触れるし、その伝手(つて)が思いもよらぬ方向に飛んでいき、目当ての人間やそうでない人間が寄ってくるという仕組みである。
「ドン・ミケロット、フィレンツェを出たそうですね」と近寄ってきた男がいた。ホアンという名のスペイン人である。ミケーレとは深い知り合いではないが、スペイン語で話しかけられることに深い安堵感を覚える。一方のソッラはきょとんとしている。彼女の親はスペイン語を話すが子供の前では使わなかった。それなので、ソッラは簡単な単語以外はスペイン語を理解できないのである。
二人はその日同胞の家に泊まることとなった。久しぶりに家庭で食べるような料理がふるまわれる。温かいスープ、野菜を煮たもの、パンをご馳走になり、話も弾んだ。そして、食事も終わってホアンの妻とソッラが片付けに下がったあと、ホアンはミケーレに話をした。
「ドン・ミケロット、あなたはミラノに向かってください」とホアンがいう。
ホアンの話はこうである。ミラノ総督のフランス人、シャルル・ダンボワーズ伯がドン・ミケロット、すなわちミケーレ・ダ・コレーリアを傭兵隊長として招きたい。しかし、フィレンツェを出て以降の足取りがよく分からない。イタリア半島で彼が寄りそうな街にはすでに人が出されており、ミケーレを見つけしだいミラノに連れてくるようにと――。
「まるでおたずね者のようだな」とミケーレは苦笑する。
「どうやら、ドン・ミケロットをフランス軍の傭兵隊長にしたいようです。スイス兵をまとめるような仕事になるのかもしれません。もしかしたらミラノだけではなく、フランスに行くことになるかもしれませんね」とホアンが言う。
「そうか、ミラノか……ミラノやヴェネツィアから話が来ることはないと思っていたが、今の状態では願ってもない話だ。さっそくミラノに向かうことにする」とミケーレはうなずく。
ソッラがホアンの妻と談笑しながら戻ってきた。ミケーレはそれを見て思い出したようにホアンに声をかける。
「ホアン、申し訳ないが、ペンかチョークと、紙か、あるいは板と端切れの布をもらえないだろうか」
「ありますよ。でも、何をするのですか?」とホアンが聞く。
「絵を描くんだ」
ミケーレの一言にホアンは目を丸くした。
「ドン・ミケロットが絵を描かれるのですか? そんな趣味があったとは……」
ソッラがくすくす笑う。ミケーレもふっとため息をついて苦笑する。
和やかな夜が過ぎていく。
そして、ふたりはミラノへの道を歩くことになった。フォルリ~イーモラ~ボローニャ~モデナ~パルマ~ピアチェンツァ~ミラノと続く道である。ミケーレは途中でフェラーラも回ったほうがいいのかと悩んだ。フェラーラにはチェーザレ・ボルジアの妹ルクレツィアがいる。そして現在はフェラーラ公アルフォンソ・デステの妻である。悲劇に見舞われたイタリアのボルジア一族の中で唯一安泰に暮らしているといえる。
悲劇だ、とミケーレは思う。
ルクレツィアの家族の現在を思うと、である。
父の元教皇アレクサンデル6世は1503年に3日ごとの熱(マラリア)で死亡。
長兄のペドロ・ルイス(初代ガンディア公)は若くして1488年に死亡。
次兄のチェーザレはスペインに追放になったのちに1507年に死亡(といわれている)。
その次の兄ホアン(2代目ガンディア公)は若くして1497年に殺害される。
弟ホフレはまだ存命だが、ボルジア家への報復を恐れてひっそりと小さな領地に暮らしている(1517年死去)。
母のヴァノッツァも存命だがひっそりと暮らしている(1518年死去)。
それが大きな野望の代償だったのだろうか。
チェーザレ・ボルジアの、古(いにしえ)のローマ帝国を興すという野望の……いや、それは結局チェーザレの手に入らなかった。運命の女神というのがいるのであれば、彼女が突然彼を見限ったようにしか思えないほどの急転だった。
ミケーレはルクレツィアのことを幼い頃から知っている。淋しがり屋で勝気で、それでいて無邪気で、人に愛されることの意味を理解している少女だった。父や兄(チェーザレ)の都合で2回の結婚をして、いずれも情勢の変化によって引き離される結果に終わった。3度目でようやく、引き離されることのないところに嫁ぐことができたのだ。元教皇アレクサンデル6世は娘のことを心から愛していた。2度目の結婚が悲惨な結末を迎えた後、彼女が修道院に引きこもってしまったのを見て、父親として心から反省したのかもしれない。3度目の夫には、彼女を守りきれるだろう男を選んだのだ。それは間違いではなかった。武人であるアルフォンソ・デステはボルジア家に何があろうと、妻を見捨てたりはしなかった。
ミケーレはそれを思い浮かべながら、フェラーラに立ち寄るのを止めた。
彼女の2番目の夫を殺したのがミケーレだったからだ。
チェーザレ・ボルジアの命令だったが、誰の命令にせよ、殺したのは自分なのだ。
そう思うと、ルクレツィアに会うことはできないと思う。命じたのがチェーザレだと分かっていても、直接手を下した人間を許せるものなのか、ミケーレには分からなかった。
「そうね……あなたの意思でしたことではないと、頭では理解できても……気持ちはそうではないかもしれないわね。ミケーレ、あなたの気持ちもそう。今整理がつかないのなら、少し時を待てばいいと思う。いずれにしても、ルクレツィアさまは今、フェラーラの公妃として幸せに暮らしているのだから」
ミケーレはソッラの言葉を聞きながら、彼女の存在を心からありがたいと思っていた。ミケーレはチェゼーナの夜以降、ソッラに何でも話すようにしている。彼の話はときどき暗殺や戦闘などの凄まじい内容になり、ソッラは何度も息が止まるほど驚いた。彼が本当にチェーザレ・ボルジアのために一身を捧げてきたことはよく理解できたし、それを誰にも言わずにずっと溜め込んでいたことも分かった。どれほど苦しかったことか、とソッラは思う。
ソッラは海のようだった。どんなに激しい奔流でも穏やかに飲み込んでしまう。ミケーレはソッラなしで今まで生きてこられたことが不思議に思えた。それほど彼女を必要としていたのである。彼女は間違いなく、ミケーレ・ダ・コレーリアを誰よりも知っている人間になっていた。
彼の奔流はソッラだけに注がれていた。フォルリからミラノにいたる旅の間、恋人たちには濃密な時間が流れる。彼らは夜を心待ちにして歩き続けた。夜はふたりにとって、思う存分に愛しあえる大切な空間だ。その間はずっと起きている。そして太陽が出てきてから、やっと眠りにつくのである。
ソッラはどんどん艶めかしく変わっていく。すれ違う男が例外なく振り返るほどに。
もう季節は厳冬になっている。
ふたりの旅が終わりに近づこうとしていた。
0
あなたにおすすめの小説

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

百合ランジェリーカフェにようこそ!
楠富 つかさ
青春
主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?
ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!
※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。
表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

四代目 豊臣秀勝
克全
歴史・時代
アルファポリス第5回歴史時代小説大賞参加作です。
読者賞を狙っていますので、アルファポリスで投票とお気に入り登録してくださると助かります。
史実で三木城合戦前後で夭折した木下与一郎が生き延びた。
秀吉の最年長の甥であり、秀長の嫡男・与一郎が生き延びた豊臣家が辿る歴史はどう言うモノになるのか。
小牧長久手で秀吉は勝てるのか?
朝日姫は徳川家康の嫁ぐのか?
朝鮮征伐は行われるのか?
秀頼は生まれるのか。
秀次が後継者に指名され切腹させられるのか?

もし石田三成が島津義弘の意見に耳を傾けていたら
俣彦
歴史・時代
慶長5年9月14日。
赤坂に到着した徳川家康を狙うべく夜襲を提案する宇喜多秀家と島津義弘。
史実では、これを退けた石田三成でありましたが……。
もしここで彼らの意見に耳を傾けていたら……。

甲斐ノ副将、八幡原ニテ散……ラズ
朽縄咲良
歴史・時代
【第8回歴史時代小説大賞奨励賞受賞作品】
戦国の雄武田信玄の次弟にして、“稀代の副将”として、同時代の戦国武将たちはもちろん、後代の歴史家の間でも評価の高い武将、武田典厩信繁。
永禄四年、武田信玄と強敵上杉輝虎とが雌雄を決する“第四次川中島合戦”に於いて討ち死にするはずだった彼は、家臣の必死の奮闘により、その命を拾う。
信繁の生存によって、甲斐武田家と日本が辿るべき歴史の流れは徐々にずれてゆく――。
この作品は、武田信繁というひとりの武将の生存によって、史実とは異なっていく戦国時代を書いた、大河if戦記である。
*ノベルアッププラス・小説家になろうにも、同内容の作品を掲載しております(一部差異あり)。

滝川家の人びと
卯花月影
歴史・時代
勝利のために走るのではない。
生きるために走る者は、
傷を負いながらも、歩みを止めない。
戦国という時代の只中で、
彼らは何を失い、
走り続けたのか。
滝川一益と、その郎党。
これは、勝者の物語ではない。
生き延びた者たちの記録である。

電子の帝国
Flight_kj
歴史・時代
少しだけ電子技術が早く技術が進歩した帝国はどのように戦うか
明治期の工業化が少し早く進展したおかげで、日本の電子技術や精密機械工業は順調に進歩した。世界規模の戦争に巻き込まれた日本は、そんな技術をもとにしてどんな戦いを繰り広げるのか? わずかに早くレーダーやコンピューターなどの電子機器が登場することにより、戦場の様相は大きく変わってゆく。

If太平洋戦争 日本が懸命な判断をしていたら
みにみ
歴史・時代
もし、あの戦争で日本が異なる選択をしていたら?
国力の差を直視し、無謀な拡大を避け、戦略と外交で活路を開く。
真珠湾、ミッドウェー、ガダルカナル…分水嶺で下された「if」の決断。
破滅回避し、国家存続をかけたもう一つの終戦を描く架空戦記。
現在1945年夏まで執筆
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる