18 / 23
18.大河鳴動
しおりを挟む
ココは城壁からウガイ川の上流を眺めた。そして、十年前に来たときとは風景が変わっていることに気づいた。
「ヴァンバルシアが船団を造っているあいだ、こちらもなにもしていなかったわけではありませんぞ」
オーガストがアルバートに説明していた。
城から上流へ向かって五百メートルほど、川岸に城壁が築かれていた。
なにもなかった向こう岸にも城があり、やはり城壁が延びていた。
対岸は森の中にあり、補給はすべてこちらから船でおこなわなくてはならないようだ。一度戦闘がはじまると物資や人員を運び込むのは困難になるだろう。
「敵の投石機の射程が三百メートル、増設した城壁が五百メートル——あと五百メートルは欲しかったところですが、まあ、相手も待ってはくれませんのでしかたありません」
オーガストは口ひげをいじりながら言った。
「現状でも勝算は十分あるかと」
アルバートは城壁に手をかけ上流を見つめたまま黙ってうなずいた。
「ウガイ城が見えました」
報告を受けて、ランデルは豪華な椅子から立ち上がり前方の手すりまで歩いた。
そこはバルコニーのようになっていて、巨大な水上要塞の上から広大な森が一望できた。眼下に自軍の大船団。その先にウガイ城がある。
「敵の動きは?」
「エキドナの船団に動きはありません。籠城するもようです」
対岸に新たに城が築かれ、両岸に長い城壁ができていることはランデルも知っていた。
「小細工を弄するか、ふん、ならば城ごと投石で埋め尽くしてやれ」
「はっ」
ヴァンバルシア軍はさらに前進した。
「投石発射準備!」
司令官のシドニー・モルガンが号令をかけた。
「放て!」
ウガイ城がヴァンバルシア軍の投石機の射程に入るより早く、グレッグの指示がエキドナ全軍に届いた。
川沿いの城壁から無数の火矢が放たれた。
両岸からだと川全体をカバーできる。
ヴァンバルシア船団に炎の雨が降りそそいだ。
ただし、それだけで船が炎上することはない。
軍船は布や皮で覆われており、それを水で濡らすと火矢くらいでは簡単に火がつかないのだった。
だが、エキドナ軍の攻撃はそれだけではなかった。
両岸の城壁の上には投石機が備えられていた。それは石だけでなく油の入った樽も飛ばしていた。さらに城壁に空いた穴からは据え置き式の大型の弩である床弩が二メートルにもおよぶ槍のような火矢を撃ち出した。これはときに軍船の外壁を貫通するほどの威力があり、内部から火災を起こすことができた。
ヴァンバルシア軍の船から火の手が上がりはじめた。しかし、投石の反撃も凄まじかった。城壁は強固に造ってあり、兵器はしっかり囲ってあったが、たまたま投石機や床弩に当たれば一撃で破壊された。
「どうした、前進しろ。ここからではウガイ城は狙えんぞ」
椅子にもどったランデルは、苛立ったようにつま先で何度も床を叩いていた。
「は、しかし……」
モルガンは言葉に詰まった。
燃えている船を押すように前進したらその船に火が移ってしまう。現に最前列のものは操舵が利かずに隣の船にぶつかり延焼している。
「ここは、私が」
ババロアが立ち上がった。
手すり近くまで歩き、両手を広げ、手のひらを左右の城壁に向ける。
「おお!」
モルガンが感嘆の声をあげた。
「む」
ランデルは腰を浮かしてその様子を見た。
両岸からの攻撃がなくなっていた。
正確には攻撃はつづいていたが、ヴァンバルシア軍には届いていなかった。
城壁の前に巨大な半透明の壁が現れ、エキドナ軍の攻撃を防いでいるのである。
「聖霊防壁か!」
ランデルの言葉を聞いて、モルガンがもう一度「おお……」と声を漏らした。
「よし、前進だ!」
「はっ! 前進! 消火作業も急げ」
これなら敵がいくら攻撃しようともなにも恐れずに進軍することができる。むしろ、敵よりも燃えている自軍の船のほうが邪魔なくらいだった。
「いいぞ! さすが我が妻だ」
ランデルが隣にきて称賛すると、ババロアは両手を伸ばしたまま「フフフ」と笑い、「お役に立てて光栄です」と言った。
「なんだ?」
ウガイ城で指揮をとっていたオーガスト・ペダンは身を乗り出して戦場を見渡した。
その城壁の下で船団を待機させているグレッグも同様だった。
「どうなっている?」
エキドナ軍が激しい攻撃を浴びせているにもかかわらず、ヴァンバルシア軍は火災の起きている大型船を押しのけ何事もないかのように悠々と迫ってきていた。
「これは……」
城壁の上で眺めていたアルバートもそれを見て唸った。
「聖霊防壁……ババロア」
ココが隣でつぶやく。
「ここは危険です。殿下は城内へお入りください!」
下からグレッグが叫ぶ声が聞こえた。このまま前進されれば、まもなくウガイ城がヴァンバルシア軍の投石機の射程に入る。
すでに気の早い船は投石を開始し、ウガイ城の前にザバン、ザバンと水柱を上げていた。
「殿下、手を」
ココはヴァンバルシア軍を見据えたまま少し左手を浮かした。
「手?」
ココは右手が義手なので、アルバートは左手を握れるようにいつも左側に立っていた。
王子は言われるまま妻の手を握った。
ココの身体がほんのりと光りだした。
「!」
アルバートはビクッと肩を揺らした。
ココの身体が光ったからではない。アルバートはよくココと手を繋ぐので、そのときにほんのり光るのは見慣れていた。
彼が驚いたのは、動かないはずの義手がゆっくりと持ち上がったからだった。
それが、ほぼ水平まで上がり、前方へ手のひらを向けた。
つぎの瞬間、ババロアが作った左右の聖霊防壁が砕け散った。
「おお……!」
アルバートが、グレッグが、オーガストが、それを見ていた兵士たちがいっせいに声をあげた。
ヴァンバルシア軍はふたたび両岸からの攻撃にさらされることになった。
人々の争う声が風に乗ってココの耳に届いた。
投石に押しつぶされる兵士、巨大な矢に射抜かれ吹き飛ぶ兵士、船上で火に巻かれる兵士、たまらず川に飛び込むも船と船に挟まれて圧死する兵士。それらの声が混ざり合って、あの魔物の怨嗟の雄叫びのようなものとなりココの全身を打った。
(これが、戦争……)
ココの身体は震えていた。
かつて、ヴァンバルシアが六国に攻められたとき、ココはその戦いに参加した。しかし、あのときは王都サナト・モレアの大神殿で防壁を張るのに精一杯で、こうして目の前で人が死んでいくのを見ることはなかった。
いま、彼女が防壁を無効化したために、ヴァンバルシアの兵士たちは死にさらされている。
彼らにも家族があり、友人や恋人がいるだろう。あのなかにもしかしたら自分を護送した役人がいるかもしれない。
そう思うと、心臓をかぎ爪のついた手で握りしめられているような苦しさがあった。
ココを勇気づけるように、アルバートの手が強く握ってきた。
彼女もそれにすがるように握り返した。
心を強く持たなければならない。戦わなければ、エキドナの兵士も危険にさらされているのだから。
「どうした!」
ランデルに言われてババロアは焦っていた。
何度試みても聖霊防壁が張れない。
「ナタ・デ・ココ……」
あいつが邪魔しているにちがいない。追放される前に見たときは、戦争が終わって二年も経っていたのに霊力は全然回復していなかった。
「そこまで霊力を回復していたなんて、たいしたものだわ……でも、あたしひとりだと思わないことね!」
ババロアは両手を突き出して叫んだ。
「ヴァンバルシア王国大聖女の名において命ずる! 八方すべての聖女はここに聖霊防壁を張れ!」
ふたたび防壁があらわれた。
しかし、それはババロアの霊力のみで作られたものだった。これだけではまたココに粉砕される。
案の定、すぐに防壁は粉々に崩れ去った。
「なにをしているの!」
ババロアは声を荒げた。
「さっさと八人の力をよこしなさい!」
「それはできません」
ババロアの頭の中にひとりの聖女の声が響いた。
「なんですって?」
「私たちは国防以外の目的で聖霊防壁を張ることを禁じられています。侵略行為に加担することはできません」
それは東の聖女ノエルの声だった。
「ブッシュ・ド・ノエル……どいつもこいつも……」
ババロアは歯ぎしりした。
「大聖女の命令よ! 野良犬がつべこべ言わずに力を貸せ!」
しかし、八人すべての聖女が「ノー」と答えた。
「この……忌々しいメス豚どもが!」
ババロアがもたついていると、ランデルのもとに伝令の兵士から連絡があった。
「国境付近で周辺国の軍事活動が活発になっています」
「なに、もうか? だが、それくらいわかっていたことだ。これだけ準備しておいて手ぶらで帰るわけにはいかん」
ランデルはドンと床を踏み鳴らした。
「せめて、目の前の城だけでも獲るぞ。そうすればつぎに侵攻するときの足掛かりになる。女神の力などに頼らずとも、これだけの戦力だ。一気に攻め落としてくれる」
「両岸の敵に構うな! 先に城を落とす。全速前進!」
モルガンが指示を出した。
ウガイ城を通過してしまえば両岸に城壁はない。下流からならもっと安全に攻略できるのだ。補給を断たれる心配はあるが、すぐに城を落とせば問題ないとモルガンも判断した。
行く手を阻むようにエキドナ船団が陣形を組んでいた。
増援が合流していくらか数が増えているようだが、やはり中型・小型船ばかりだった。
「蹴散らせ!」
ランデルが叫んだ。
「ヴァンバルシア軍、こちらへ向かってきます!」
報告する兵士の声がココとアルバートの耳に入ってきた。
ヴァンバルシアの船団が押し寄せてきているのが城壁の上からよく見える。
「そうは、させない……!」
ココはアルバートと繋ぐ手に力を込めた。
前に向けられた動かないはずの義手の指が大きく開かれた。
直後、川幅いっぱいに雲にも届きそうな高さの聖霊防壁が現れた。
ヴァンバルシア船団が前進する速度を上げたとき、目の前にさっきとはくらべものにならないほど巨大な防壁がそびえ立った。
「な、なんだこれは……お前がやっているのか?」
ランデルはその威容に気圧されながらババロアにたずねた。
「いえ……こんな、これほどのものを……どうやって」
ババロアもうまく言葉が出ないでいた。
「ココ……お前がやっているの?」
「これ以上の抵抗は無駄だから、あきらめてお家へ帰りなさい」
ココはアルバートの横で腕に力を込めたままつぶやいた。
燃える味方の船を避けて速度を出したばかりのヴァンバルシア船団は、止まることができずに聖霊防壁に激突した。
「止まれ! 止まれ!」
船尾の兵士が声を枯らして叫ぶが、後続の船も急に止まることはできず、それに追突する。
「なにをしている、船を止めろ! 早く!」
ランデルは声を枯らして叫んだ。
「全軍停止! 全軍停止!」
モルガンの命令も虚しく、ヴァンバルシア軍の船はつぎつぎに防壁に、または船同士衝突し粉砕され、兵士たちは川に投げ出された。
その様子を後方から見て、ランデルは握った両手を震わせながら妻の方を向いた。
「ババロア! どうにかならんのか!」
「も、申しわけありません! 私の力だけでは……」
ババロアは両手を前にかざしてなんとかしようとしているようだが、状況はよくならなかった。
ランデルは「チッ」と舌打ちして、視線を前面にもどした。
やがて、巨大な防壁が揺るがないことを確認すると、ドンと足を踏み鳴らし撤退を告げた。
「リック城へもどるぞ!」
その言葉を伝えながら、シドニー・モルガンは内心ほっとしていた。
ちゃんと引き際はわきまえている。頭に血が上って「徹底抗戦」などと言われればどれだけ被害が出るかわからないのだった。
「勝敗は決したな」
グレッグは戦況を眺めてつぶやいた。
ヴァンバルシア軍の旗艦をはじめ、無事だった船は徐々に後退していた。
「俺たちの船団は戦闘にではなく救助につかわれることになりそうだ」
「よいことではありませんか」
副官のダリウス・シルトンが言った。
「そうだな、聖女様々だ。殿下は良い妻をお持ちになった」
グレッグは城壁のほうへ顔を上げた。
「ココ、よくやってくれた!」
城壁の上では、引き上げていくヴァンバルシア軍を見て、アルバートがココの手を握りしめていた。
ココが「ふぅ」と息を吐いて肩の力を抜くと、義手が支えを失ったようにだらりと下がった。
大国を撃退できたのでアルバートは興奮気味だったが、立ち尽くす妻に気づいて、はっとしたように姿勢をあらためた。
ココは戦場を見つめたまま、大きな瞳から涙を流していた。
「すまない……つらい思いをさせたな」
アルバートは膝を折ると妻の身体をぎゅっと抱きしめた。
「ヴァンバルシアが船団を造っているあいだ、こちらもなにもしていなかったわけではありませんぞ」
オーガストがアルバートに説明していた。
城から上流へ向かって五百メートルほど、川岸に城壁が築かれていた。
なにもなかった向こう岸にも城があり、やはり城壁が延びていた。
対岸は森の中にあり、補給はすべてこちらから船でおこなわなくてはならないようだ。一度戦闘がはじまると物資や人員を運び込むのは困難になるだろう。
「敵の投石機の射程が三百メートル、増設した城壁が五百メートル——あと五百メートルは欲しかったところですが、まあ、相手も待ってはくれませんのでしかたありません」
オーガストは口ひげをいじりながら言った。
「現状でも勝算は十分あるかと」
アルバートは城壁に手をかけ上流を見つめたまま黙ってうなずいた。
「ウガイ城が見えました」
報告を受けて、ランデルは豪華な椅子から立ち上がり前方の手すりまで歩いた。
そこはバルコニーのようになっていて、巨大な水上要塞の上から広大な森が一望できた。眼下に自軍の大船団。その先にウガイ城がある。
「敵の動きは?」
「エキドナの船団に動きはありません。籠城するもようです」
対岸に新たに城が築かれ、両岸に長い城壁ができていることはランデルも知っていた。
「小細工を弄するか、ふん、ならば城ごと投石で埋め尽くしてやれ」
「はっ」
ヴァンバルシア軍はさらに前進した。
「投石発射準備!」
司令官のシドニー・モルガンが号令をかけた。
「放て!」
ウガイ城がヴァンバルシア軍の投石機の射程に入るより早く、グレッグの指示がエキドナ全軍に届いた。
川沿いの城壁から無数の火矢が放たれた。
両岸からだと川全体をカバーできる。
ヴァンバルシア船団に炎の雨が降りそそいだ。
ただし、それだけで船が炎上することはない。
軍船は布や皮で覆われており、それを水で濡らすと火矢くらいでは簡単に火がつかないのだった。
だが、エキドナ軍の攻撃はそれだけではなかった。
両岸の城壁の上には投石機が備えられていた。それは石だけでなく油の入った樽も飛ばしていた。さらに城壁に空いた穴からは据え置き式の大型の弩である床弩が二メートルにもおよぶ槍のような火矢を撃ち出した。これはときに軍船の外壁を貫通するほどの威力があり、内部から火災を起こすことができた。
ヴァンバルシア軍の船から火の手が上がりはじめた。しかし、投石の反撃も凄まじかった。城壁は強固に造ってあり、兵器はしっかり囲ってあったが、たまたま投石機や床弩に当たれば一撃で破壊された。
「どうした、前進しろ。ここからではウガイ城は狙えんぞ」
椅子にもどったランデルは、苛立ったようにつま先で何度も床を叩いていた。
「は、しかし……」
モルガンは言葉に詰まった。
燃えている船を押すように前進したらその船に火が移ってしまう。現に最前列のものは操舵が利かずに隣の船にぶつかり延焼している。
「ここは、私が」
ババロアが立ち上がった。
手すり近くまで歩き、両手を広げ、手のひらを左右の城壁に向ける。
「おお!」
モルガンが感嘆の声をあげた。
「む」
ランデルは腰を浮かしてその様子を見た。
両岸からの攻撃がなくなっていた。
正確には攻撃はつづいていたが、ヴァンバルシア軍には届いていなかった。
城壁の前に巨大な半透明の壁が現れ、エキドナ軍の攻撃を防いでいるのである。
「聖霊防壁か!」
ランデルの言葉を聞いて、モルガンがもう一度「おお……」と声を漏らした。
「よし、前進だ!」
「はっ! 前進! 消火作業も急げ」
これなら敵がいくら攻撃しようともなにも恐れずに進軍することができる。むしろ、敵よりも燃えている自軍の船のほうが邪魔なくらいだった。
「いいぞ! さすが我が妻だ」
ランデルが隣にきて称賛すると、ババロアは両手を伸ばしたまま「フフフ」と笑い、「お役に立てて光栄です」と言った。
「なんだ?」
ウガイ城で指揮をとっていたオーガスト・ペダンは身を乗り出して戦場を見渡した。
その城壁の下で船団を待機させているグレッグも同様だった。
「どうなっている?」
エキドナ軍が激しい攻撃を浴びせているにもかかわらず、ヴァンバルシア軍は火災の起きている大型船を押しのけ何事もないかのように悠々と迫ってきていた。
「これは……」
城壁の上で眺めていたアルバートもそれを見て唸った。
「聖霊防壁……ババロア」
ココが隣でつぶやく。
「ここは危険です。殿下は城内へお入りください!」
下からグレッグが叫ぶ声が聞こえた。このまま前進されれば、まもなくウガイ城がヴァンバルシア軍の投石機の射程に入る。
すでに気の早い船は投石を開始し、ウガイ城の前にザバン、ザバンと水柱を上げていた。
「殿下、手を」
ココはヴァンバルシア軍を見据えたまま少し左手を浮かした。
「手?」
ココは右手が義手なので、アルバートは左手を握れるようにいつも左側に立っていた。
王子は言われるまま妻の手を握った。
ココの身体がほんのりと光りだした。
「!」
アルバートはビクッと肩を揺らした。
ココの身体が光ったからではない。アルバートはよくココと手を繋ぐので、そのときにほんのり光るのは見慣れていた。
彼が驚いたのは、動かないはずの義手がゆっくりと持ち上がったからだった。
それが、ほぼ水平まで上がり、前方へ手のひらを向けた。
つぎの瞬間、ババロアが作った左右の聖霊防壁が砕け散った。
「おお……!」
アルバートが、グレッグが、オーガストが、それを見ていた兵士たちがいっせいに声をあげた。
ヴァンバルシア軍はふたたび両岸からの攻撃にさらされることになった。
人々の争う声が風に乗ってココの耳に届いた。
投石に押しつぶされる兵士、巨大な矢に射抜かれ吹き飛ぶ兵士、船上で火に巻かれる兵士、たまらず川に飛び込むも船と船に挟まれて圧死する兵士。それらの声が混ざり合って、あの魔物の怨嗟の雄叫びのようなものとなりココの全身を打った。
(これが、戦争……)
ココの身体は震えていた。
かつて、ヴァンバルシアが六国に攻められたとき、ココはその戦いに参加した。しかし、あのときは王都サナト・モレアの大神殿で防壁を張るのに精一杯で、こうして目の前で人が死んでいくのを見ることはなかった。
いま、彼女が防壁を無効化したために、ヴァンバルシアの兵士たちは死にさらされている。
彼らにも家族があり、友人や恋人がいるだろう。あのなかにもしかしたら自分を護送した役人がいるかもしれない。
そう思うと、心臓をかぎ爪のついた手で握りしめられているような苦しさがあった。
ココを勇気づけるように、アルバートの手が強く握ってきた。
彼女もそれにすがるように握り返した。
心を強く持たなければならない。戦わなければ、エキドナの兵士も危険にさらされているのだから。
「どうした!」
ランデルに言われてババロアは焦っていた。
何度試みても聖霊防壁が張れない。
「ナタ・デ・ココ……」
あいつが邪魔しているにちがいない。追放される前に見たときは、戦争が終わって二年も経っていたのに霊力は全然回復していなかった。
「そこまで霊力を回復していたなんて、たいしたものだわ……でも、あたしひとりだと思わないことね!」
ババロアは両手を突き出して叫んだ。
「ヴァンバルシア王国大聖女の名において命ずる! 八方すべての聖女はここに聖霊防壁を張れ!」
ふたたび防壁があらわれた。
しかし、それはババロアの霊力のみで作られたものだった。これだけではまたココに粉砕される。
案の定、すぐに防壁は粉々に崩れ去った。
「なにをしているの!」
ババロアは声を荒げた。
「さっさと八人の力をよこしなさい!」
「それはできません」
ババロアの頭の中にひとりの聖女の声が響いた。
「なんですって?」
「私たちは国防以外の目的で聖霊防壁を張ることを禁じられています。侵略行為に加担することはできません」
それは東の聖女ノエルの声だった。
「ブッシュ・ド・ノエル……どいつもこいつも……」
ババロアは歯ぎしりした。
「大聖女の命令よ! 野良犬がつべこべ言わずに力を貸せ!」
しかし、八人すべての聖女が「ノー」と答えた。
「この……忌々しいメス豚どもが!」
ババロアがもたついていると、ランデルのもとに伝令の兵士から連絡があった。
「国境付近で周辺国の軍事活動が活発になっています」
「なに、もうか? だが、それくらいわかっていたことだ。これだけ準備しておいて手ぶらで帰るわけにはいかん」
ランデルはドンと床を踏み鳴らした。
「せめて、目の前の城だけでも獲るぞ。そうすればつぎに侵攻するときの足掛かりになる。女神の力などに頼らずとも、これだけの戦力だ。一気に攻め落としてくれる」
「両岸の敵に構うな! 先に城を落とす。全速前進!」
モルガンが指示を出した。
ウガイ城を通過してしまえば両岸に城壁はない。下流からならもっと安全に攻略できるのだ。補給を断たれる心配はあるが、すぐに城を落とせば問題ないとモルガンも判断した。
行く手を阻むようにエキドナ船団が陣形を組んでいた。
増援が合流していくらか数が増えているようだが、やはり中型・小型船ばかりだった。
「蹴散らせ!」
ランデルが叫んだ。
「ヴァンバルシア軍、こちらへ向かってきます!」
報告する兵士の声がココとアルバートの耳に入ってきた。
ヴァンバルシアの船団が押し寄せてきているのが城壁の上からよく見える。
「そうは、させない……!」
ココはアルバートと繋ぐ手に力を込めた。
前に向けられた動かないはずの義手の指が大きく開かれた。
直後、川幅いっぱいに雲にも届きそうな高さの聖霊防壁が現れた。
ヴァンバルシア船団が前進する速度を上げたとき、目の前にさっきとはくらべものにならないほど巨大な防壁がそびえ立った。
「な、なんだこれは……お前がやっているのか?」
ランデルはその威容に気圧されながらババロアにたずねた。
「いえ……こんな、これほどのものを……どうやって」
ババロアもうまく言葉が出ないでいた。
「ココ……お前がやっているの?」
「これ以上の抵抗は無駄だから、あきらめてお家へ帰りなさい」
ココはアルバートの横で腕に力を込めたままつぶやいた。
燃える味方の船を避けて速度を出したばかりのヴァンバルシア船団は、止まることができずに聖霊防壁に激突した。
「止まれ! 止まれ!」
船尾の兵士が声を枯らして叫ぶが、後続の船も急に止まることはできず、それに追突する。
「なにをしている、船を止めろ! 早く!」
ランデルは声を枯らして叫んだ。
「全軍停止! 全軍停止!」
モルガンの命令も虚しく、ヴァンバルシア軍の船はつぎつぎに防壁に、または船同士衝突し粉砕され、兵士たちは川に投げ出された。
その様子を後方から見て、ランデルは握った両手を震わせながら妻の方を向いた。
「ババロア! どうにかならんのか!」
「も、申しわけありません! 私の力だけでは……」
ババロアは両手を前にかざしてなんとかしようとしているようだが、状況はよくならなかった。
ランデルは「チッ」と舌打ちして、視線を前面にもどした。
やがて、巨大な防壁が揺るがないことを確認すると、ドンと足を踏み鳴らし撤退を告げた。
「リック城へもどるぞ!」
その言葉を伝えながら、シドニー・モルガンは内心ほっとしていた。
ちゃんと引き際はわきまえている。頭に血が上って「徹底抗戦」などと言われればどれだけ被害が出るかわからないのだった。
「勝敗は決したな」
グレッグは戦況を眺めてつぶやいた。
ヴァンバルシア軍の旗艦をはじめ、無事だった船は徐々に後退していた。
「俺たちの船団は戦闘にではなく救助につかわれることになりそうだ」
「よいことではありませんか」
副官のダリウス・シルトンが言った。
「そうだな、聖女様々だ。殿下は良い妻をお持ちになった」
グレッグは城壁のほうへ顔を上げた。
「ココ、よくやってくれた!」
城壁の上では、引き上げていくヴァンバルシア軍を見て、アルバートがココの手を握りしめていた。
ココが「ふぅ」と息を吐いて肩の力を抜くと、義手が支えを失ったようにだらりと下がった。
大国を撃退できたのでアルバートは興奮気味だったが、立ち尽くす妻に気づいて、はっとしたように姿勢をあらためた。
ココは戦場を見つめたまま、大きな瞳から涙を流していた。
「すまない……つらい思いをさせたな」
アルバートは膝を折ると妻の身体をぎゅっと抱きしめた。
2
あなたにおすすめの小説

存在感のない聖女が姿を消した後 [完]
風龍佳乃
恋愛
聖女であるディアターナは
永く仕えた国を捨てた。
何故って?
それは新たに現れた聖女が
ヒロインだったから。
ディアターナは
いつの日からか新聖女と比べられ
人々の心が離れていった事を悟った。
もう私の役目は終わったわ…
神託を受けたディアターナは
手紙を残して消えた。
残された国は天災に見舞われ
てしまった。
しかし聖女は戻る事はなかった。
ディアターナは西帝国にて
初代聖女のコリーアンナに出会い
運命を切り開いて
自分自身の幸せをみつけるのだった。

王家を追放された落ちこぼれ聖女は、小さな村で鍛冶屋の妻候補になります
cotonoha garden
恋愛
「聖女失格です。王家にも国にも、あなたはもう必要ありません」——そう告げられた日、リーネは王女でいることさえ許されなくなりました。
聖女としても王女としても半人前。婚約者の王太子には冷たく切り捨てられ、居場所を失った彼女がたどり着いたのは、森と鉄の匂いが混ざる辺境の小さな村。
そこで出会ったのは、無骨で無口なくせに、さりげなく怪我の手当てをしてくれる鍛冶屋ユリウス。
村の事情から「書類上の仮妻」として迎えられたリーネは、鍛冶場の雑用や村人の看病をこなしながら、少しずつ「誰かに必要とされる感覚」を取り戻していきます。
かつては「落ちこぼれ聖女」とさげすまれた力が、今度は村の子どもたちの笑顔を守るために使われる。
そんな新しい日々の中で、ぶっきらぼうな鍛冶屋の優しさや、村人たちのさりげない気遣いが、冷え切っていたリーネの心をゆっくりと溶かしていきます。
やがて、国難を前に王都から使者が訪れ、「再び聖女として戻ってこい」と告げられたとき——
リーネが選ぶのは、きらびやかな王宮か、それとも鉄音の響く小さな家か。
理不尽な追放と婚約破棄から始まる物語は、
「大切にされなかった記憶」を持つ読者に寄り添いながら、
自分で選び取った居場所と、静かであたたかな愛へとたどり着く物語です。

【完結】使えない令嬢として一家から追放されたけど、あまりにも領民からの信頼が厚かったので逆転してざまぁしちゃいます
腕押のれん
ファンタジー
アメリスはマハス公国の八大領主の一つであるロナデシア家の三姉妹の次女として生まれるが、頭脳明晰な長女と愛想の上手い三女と比較されて母親から疎まれており、ついに追放されてしまう。しかしアメリスは取り柄のない自分にもできることをしなければならないという一心で領民たちに対し援助を熱心に行っていたので、領民からは非常に好かれていた。そのため追放された後に他国に置き去りにされてしまうものの、偶然以前助けたマハス公国出身のヨーデルと出会い助けられる。ここから彼女の逆転人生が始まっていくのであった!
私が死ぬまでには完結させます。
追記:最後まで書き終わったので、ここからはペース上げて投稿します。
追記2:ひとまず完結しました!

聖女の力を妹に奪われ魔獣の森に捨てられたけど、何故か懐いてきた白狼(実は呪われた皇帝陛下)のブラッシング係に任命されました
AK
恋愛
「--リリアナ、貴様との婚約は破棄する! そして妹の功績を盗んだ罪で、この国からの追放を命じる!」
公爵令嬢リリアナは、腹違いの妹・ミナの嘘によって「偽聖女」の汚名を着せられ、婚約者の第二王子からも、実の父からも絶縁されてしまう。 身一つで放り出されたのは、凶暴な魔獣が跋扈する北の禁足地『帰らずの魔の森』。
死を覚悟したリリアナが出会ったのは、伝説の魔獣フェンリル——ではなく、呪いによって巨大な白狼の姿になった隣国の皇帝・アジュラ四世だった!
人間には効果が薄いが、動物に対しては絶大な癒やし効果を発揮するリリアナの「聖女の力」。 彼女が何気なく白狼をブラッシングすると、苦しんでいた皇帝の呪いが解け始め……?
「余の呪いを解くどころか、極上の手触りで撫でてくるとは……。貴様、責任を取って余の専属ブラッシング係になれ」
こうしてリリアナは、冷徹と恐れられる氷の皇帝(中身はツンデレもふもふ)に拾われ、帝国で溺愛されることに。 豪華な離宮で美味しい食事に、最高のもふもふタイム。虐げられていた日々が嘘のような幸せスローライフが始まる。
一方、本物の聖女を追放してしまった祖国では、妹のミナが聖女の力を発揮できず、大地が枯れ、疫病が蔓延し始めていた。 元婚約者や父が慌ててミレイユを連れ戻そうとするが、時すでに遅し。 「私の主人は、この可愛い狼様(皇帝陛下)だけですので」 これは、すべてを奪われた令嬢が、最強のパートナーを得て幸せになり、自分を捨てた者たちを見返す逆転の物語。
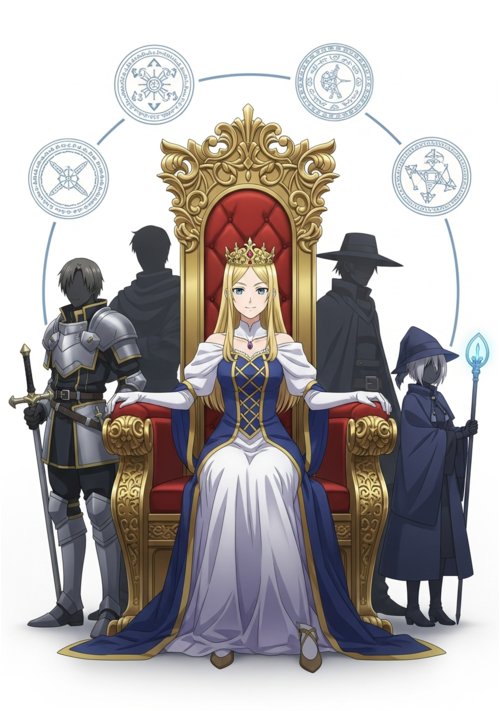
「君は悪役令嬢だ」と離婚されたけど、追放先で伝説の力をゲット!最強の女王になって国を建てたら、後悔した元夫が求婚してきました
黒崎隼人
ファンタジー
「君は悪役令嬢だ」――冷酷な皇太子だった夫から一方的に離婚を告げられ、すべての地位と財産を奪われたアリシア。悪役の汚名を着せられ、魔物がはびこる辺境の地へ追放された彼女が見つけたのは、古代文明の遺跡と自らが「失われた王家の末裔」であるという衝撃の真実だった。
古代魔法の力に覚醒し、心優しき領民たちと共に荒れ地を切り拓くアリシア。
一方、彼女を陥れた偽りの聖女の陰謀に気づき始めた元夫は、後悔と焦燥に駆られていく。
追放された令嬢が運命に抗い、最強の女王へと成り上がる。
愛と裏切り、そして再生の痛快逆転ファンタジー、ここに開幕!

さよなら、悪女に夢中な王子様〜婚約破棄された令嬢は、真の聖女として平和な学園生活を謳歌する〜
平山和人
恋愛
公爵令嬢アイリス・ヴェスペリアは、婚約者である第二王子レオンハルトから、王女のエステルのために理不尽な糾弾を受け、婚約破棄と社交界からの追放を言い渡される。
心身を蝕まれ憔悴しきったその時、アイリスは前世の記憶と、自らの家系が代々受け継いできた『浄化の聖女』の真の力を覚醒させる。自分が陥れられた原因が、エステルの持つ邪悪な魔力に触発されたレオンハルトの歪んだ欲望だったことを知ったアイリスは、力を隠し、追放先の辺境の学園へ進学。
そこで出会ったのは、学園の異端児でありながら、彼女の真の力を見抜く魔術師クライヴと、彼女の過去を知り静かに見守る優秀な生徒会長アシェル。
一方、アイリスを失った王都では、エステルの影響力が増し、国政が混乱を極め始める。アイリスは、愛と権力を失った代わりに手に入れた静かな幸せと、聖女としての使命の間で揺れ動く。
これは、真実の愛と自己肯定を見つけた令嬢が、元婚約者の愚かさに裁きを下し、やがて来る国の危機を救うまでの物語。

【完結】真の聖女だった私は死にました。あなたたちのせいですよ?
時
恋愛
聖女として国のために尽くしてきたフローラ。
しかしその力を妬むカリアによって聖女の座を奪われ、顔に傷をつけられたあげく、さらには聖女を騙った罪で追放、彼女を称えていたはずの王太子からは婚約破棄を突きつけられてしまう。
追放が正式に決まった日、絶望した彼女はふたりの目の前で死ぬことを選んだ。
フローラの亡骸は水葬されるが、奇跡的に一命を取り留めていた彼女は船に乗っていた他国の騎士団長に拾われる。
ラピスと名乗った青年はフローラを気に入って自分の屋敷に居候させる。
記憶喪失と顔の傷を抱えながらも前向きに生きるフローラを周りは愛し、やがてその愛情に応えるように彼女のほんとうの力が目覚めて……。
一方、真の聖女がいなくなった国は滅びへと向かっていた──
※小説家になろうにも投稿しています
いいねやエール嬉しいです!ありがとうございます!

お飾りの婚約者で結構です! 殿下のことは興味ありませんので、お構いなく!
にのまえ
恋愛
すでに寵愛する人がいる、殿下の婚約候補決めの舞踏会を開くと、王家の勅命がドーリング公爵家に届くも、姉のミミリアは嫌がった。
公爵家から一人娘という言葉に、舞踏会に参加することになった、ドーリング公爵家の次女・ミーシャ。
家族の中で“役立たず”と蔑まれ、姉の身代わりとして差し出された彼女の唯一の望みは――「舞踏会で、美味しい料理を食べること」。
だが、そんな慎ましい願いとは裏腹に、
舞踏会の夜、思いもよらぬ出来事が起こりミーシャは前世、読んでいた小説の世界だと気付く。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















