328 / 586
第六章 アランの力は遂に一つの頂点に
第四十三話 試練の時、来たる(19)
しおりを挟む
ルイスはすぐにそれらしいものを見つけた。
本能の近くに大量の虫のような「部品」が転がっている。
これだ、とルイスは思った。
専用の虫を送り込んで解析させる。
すると答えはすぐに明らかになった。
(やはりな)
当たりであった。混沌の部品では無い。こいつらが実行犯だ。
一つ一つの部品に意味は無いが、上手く繋げるとシャロンの闘争本能に問題を起こす厄介な組織と化す。
点検時には闘争本能の回路から離れ、ばらばらになってやり過ごしていたのだろう。
その仕組みの精巧さは芸術に見えたが、ルイスは淡々と攻撃用の虫を送り込み、それらを破壊した。
(とりあえず破壊は完了、と)
しかしこれで問題が解決したわけでは無いことをルイスは分かっていた。
同じ攻撃をされれば、また同じ問題が再発してしまうからだ。防御を強化しなくてはならない。
それはつまり、シャロンを「改造」するということ。本人の性格に影響が出る可能性が高い。
ルイスがそれを伺うよりも早く、分かっていたシャロンは答えた。
「構わないわ。ただし、戦闘に関わる部分は慎重にお願い。弱くなるようなことはしないで」
これにルイスは、
「……」
分かったと、即答することが出来なかった。
難しいからだ。
そもそも、問題の根源は「第四の存在が戦うことを嫌がっている」ことである。
これを完全に解決しようと思ったら、第四の存在からの攻撃が二度と起きないようにしようとするならば、シャロンを「元の彼女」に戻すしか無い。
それは出来ない。それに、元の彼女がどうであったか、元の神経回路がどうなっていたか、実はもう覚えていない。
ならば今後も攻撃を受け続けるのが前提となる。
対処法は一応ある。だが、それはこれまでにも「調整」としてやってきたことだ。
ゆえにルイスは肯定の返事では無く、警告を口に出した。
「シャロン、これまでに何度も言ったが、この体は私がちゃんと『厳選』したものじゃない。都合の良い身分や立場であったから、電撃魔法の素質も備えていたから、ただそれだけで君が選んだものだ」
これにシャロンは、
「……」
ただ、沈黙を返した。
そしてその無言に感情が無い事を感じ取ったルイスは言葉を続けた。
「この体は気質に関しては全く戦闘に向いていない。このような問題が起き、それが徐々に深刻化していくことも最初に言ったはずだ。……シャロン、正直に言おう。この体と君の関係は、もう限界に近い」
ルイスのこの警告は本心からのものであった。
「……」
しかしシャロンは先と同じ沈黙を返した。
そしてしばらくしてシャロンは口を開いた。
「……別に構わないわ。あと一回戦えればそれでいい」
独り言のように漏れたその言葉に、ルイスが「あと一回?」と理由を尋ね返すと、シャロンは答えた。
次の仕事は派手なものになるかもしれないことを。
その仕事でアランを始末するつもりであることを。
そしてそれがこの体での最後の仕事になる可能性が高いことを、奴らの味方のフリを続けることが限界に近いことを、自身の推測とともに答えた。
シャロンが述べたそれらの言葉にルイスは、
「……」
全て沈黙を返した。
ルイスは考えていた。
そのアランはいま自分の教会にいる。
アランがまだ生きているということは、シャロンはまだアランの正確な位置を掴んでいないということ。つまり、ここに来たばかりであるということ。
ならば教えてあげようか、とルイスは一瞬思ったが、
「……」
やめておくことにした。
アランは自分と何か話したいことがあるらしいから、それを済ませてからでもいいだろう、と思った。
それに正直なところ、シャロンが身を置いている戦いは自分にとってはどうでもいいことだ。
はっきりいって、この「調整」も長い付き合いから生じる義理感だけでやっていること。
そしてこの作業は徹夜になるかもしれない。
面倒くさい。明日はつらそうだ。
「……ふう」
直後、その思いがため息となってルイスの口から漏れた。
ルイスはシャロンに対して心を開いていない。脳波を抑え、虫に心を読まれないように監視している。
対するシャロンもルイスの心を読もうとはしていない。「調整」を受ける側であるゆえに、失礼にあたる恐れのある行為を避けているだけだが。
それでもそのため息に込められている思いは分かった。
だからシャロンは口を開いた。
「……面倒くさいのは分かるけど、ちゃんとやってよ?」
これにルイスは「分かってる。信じろ」と、少し怪しい返事を返しながら意識を再びシャロンの頭の中に向けた。
ため息を吐いたせいか、幾分か気が楽になっていた。
それにあと一回だけでいいのであればどうにでもなる、という気持ちも湧き上がっていた。
普段は以前よりも大人しく、しかし戦闘時の気質は以前通りに、そうなるように条件付けしてみよう。効果があるかどうかは正直知らないが、もしかしたら上手くごまかせるかもしれない。
「……」
そう決めたルイスは、淡々と作業を進めた。
その手つきは慣れたものであった。勝手知ったる我が家のように、シャロンの頭の中の構造を理解しているからだ。
だから他のことを考える余裕があった。
(そういえば……)
あの時、シャロンが放った虫は私のそばにいたアランを認識出来ていなかった。
本当にシャロンは焦っていたのだろう。だから虫に余分な機能を持たせられなかったのだ。
そしてあの虫は本当にうるさかった。「早く、速く」と叫び続けていた。
(まったく、都合の良い時に呼ばれる方の身にもなってほしいものだ)
シャロンが私のように自分で調整出来ればこんな煩わしい思いをせずに済むのだが。
ならば、教えてみるか?
(……いや、それはそれでかなり面倒だな)
ルイスは自分がこの技術を習得するのにどれだけの時間を要したかをすぐに思い出した。
同時に、懐かしい記憶も奥底から浮き上がってきた。
それは苦い記憶でもあった。
「……」
ゆえに、ルイスの手は止まった。
それは一瞬であったが、何かあったのかと心配になったシャロンは口を開いた。
「どうしたの? 何か、私の頭の中でマズいことでもあった?」
これにルイスは首を振って答えた。
「いいや、そうじゃない。ちょっと昔を思い出しただけだ」
これに興味を抱いたシャロンは尋ねた。
「……昔? そういえば私、会う前のあなたのことをあまり知らないわ。良ければ話してくれない?」
その言葉に引っかかるものがあったルイスは尋ね返した。
「あまり? あまりってどういうことだ?」
シャロンに昔のことを話したことはほとんど無い。だが、まるでそれ以上知っているかのような口ぶりだ。
自分の心を、記憶を盗み見たのだろうか、ルイスはそう思ったが、シャロンは少し違う答えを述べた。
「『あいつ』から聞いたのよ。少しだけね」
その確認のために、寝ているルイスの記憶をこっそり覗いたことはあるのだが、それは黙っておくことにした。
そしてルイスは『それ』が蜘蛛の化け物のことを指していることを、聞き返さずとも理解した。
ゆえにルイスは、「ああ、あいつか」と、何かをあきらめたかのような言葉を漏らした。
そういえば『あいつ』はどこにいるんだろうか。シャロンを探していたはずだが。
ルイスがそう思った瞬間、
「呼んだかい?」
と、『あいつ』の声が魂に響いた。
これに二人は、
「「!?」」
同時に同じ表情を浮かべた。
近くにいたことに全く気が付かなかったからだ。
そしてその声の発生源は――
((下?!))
ゆえにシャロンとルイスは同時に下を向いた。
すると『あいつ』は地面の中から染み出すように、這い出るように、二人の目の前に姿を表した。
人の形を成しながら。
そしてその人の形をしたものは、シャロンに向かって口を開いた。
「久しぶりだねシャロン」
本能の近くに大量の虫のような「部品」が転がっている。
これだ、とルイスは思った。
専用の虫を送り込んで解析させる。
すると答えはすぐに明らかになった。
(やはりな)
当たりであった。混沌の部品では無い。こいつらが実行犯だ。
一つ一つの部品に意味は無いが、上手く繋げるとシャロンの闘争本能に問題を起こす厄介な組織と化す。
点検時には闘争本能の回路から離れ、ばらばらになってやり過ごしていたのだろう。
その仕組みの精巧さは芸術に見えたが、ルイスは淡々と攻撃用の虫を送り込み、それらを破壊した。
(とりあえず破壊は完了、と)
しかしこれで問題が解決したわけでは無いことをルイスは分かっていた。
同じ攻撃をされれば、また同じ問題が再発してしまうからだ。防御を強化しなくてはならない。
それはつまり、シャロンを「改造」するということ。本人の性格に影響が出る可能性が高い。
ルイスがそれを伺うよりも早く、分かっていたシャロンは答えた。
「構わないわ。ただし、戦闘に関わる部分は慎重にお願い。弱くなるようなことはしないで」
これにルイスは、
「……」
分かったと、即答することが出来なかった。
難しいからだ。
そもそも、問題の根源は「第四の存在が戦うことを嫌がっている」ことである。
これを完全に解決しようと思ったら、第四の存在からの攻撃が二度と起きないようにしようとするならば、シャロンを「元の彼女」に戻すしか無い。
それは出来ない。それに、元の彼女がどうであったか、元の神経回路がどうなっていたか、実はもう覚えていない。
ならば今後も攻撃を受け続けるのが前提となる。
対処法は一応ある。だが、それはこれまでにも「調整」としてやってきたことだ。
ゆえにルイスは肯定の返事では無く、警告を口に出した。
「シャロン、これまでに何度も言ったが、この体は私がちゃんと『厳選』したものじゃない。都合の良い身分や立場であったから、電撃魔法の素質も備えていたから、ただそれだけで君が選んだものだ」
これにシャロンは、
「……」
ただ、沈黙を返した。
そしてその無言に感情が無い事を感じ取ったルイスは言葉を続けた。
「この体は気質に関しては全く戦闘に向いていない。このような問題が起き、それが徐々に深刻化していくことも最初に言ったはずだ。……シャロン、正直に言おう。この体と君の関係は、もう限界に近い」
ルイスのこの警告は本心からのものであった。
「……」
しかしシャロンは先と同じ沈黙を返した。
そしてしばらくしてシャロンは口を開いた。
「……別に構わないわ。あと一回戦えればそれでいい」
独り言のように漏れたその言葉に、ルイスが「あと一回?」と理由を尋ね返すと、シャロンは答えた。
次の仕事は派手なものになるかもしれないことを。
その仕事でアランを始末するつもりであることを。
そしてそれがこの体での最後の仕事になる可能性が高いことを、奴らの味方のフリを続けることが限界に近いことを、自身の推測とともに答えた。
シャロンが述べたそれらの言葉にルイスは、
「……」
全て沈黙を返した。
ルイスは考えていた。
そのアランはいま自分の教会にいる。
アランがまだ生きているということは、シャロンはまだアランの正確な位置を掴んでいないということ。つまり、ここに来たばかりであるということ。
ならば教えてあげようか、とルイスは一瞬思ったが、
「……」
やめておくことにした。
アランは自分と何か話したいことがあるらしいから、それを済ませてからでもいいだろう、と思った。
それに正直なところ、シャロンが身を置いている戦いは自分にとってはどうでもいいことだ。
はっきりいって、この「調整」も長い付き合いから生じる義理感だけでやっていること。
そしてこの作業は徹夜になるかもしれない。
面倒くさい。明日はつらそうだ。
「……ふう」
直後、その思いがため息となってルイスの口から漏れた。
ルイスはシャロンに対して心を開いていない。脳波を抑え、虫に心を読まれないように監視している。
対するシャロンもルイスの心を読もうとはしていない。「調整」を受ける側であるゆえに、失礼にあたる恐れのある行為を避けているだけだが。
それでもそのため息に込められている思いは分かった。
だからシャロンは口を開いた。
「……面倒くさいのは分かるけど、ちゃんとやってよ?」
これにルイスは「分かってる。信じろ」と、少し怪しい返事を返しながら意識を再びシャロンの頭の中に向けた。
ため息を吐いたせいか、幾分か気が楽になっていた。
それにあと一回だけでいいのであればどうにでもなる、という気持ちも湧き上がっていた。
普段は以前よりも大人しく、しかし戦闘時の気質は以前通りに、そうなるように条件付けしてみよう。効果があるかどうかは正直知らないが、もしかしたら上手くごまかせるかもしれない。
「……」
そう決めたルイスは、淡々と作業を進めた。
その手つきは慣れたものであった。勝手知ったる我が家のように、シャロンの頭の中の構造を理解しているからだ。
だから他のことを考える余裕があった。
(そういえば……)
あの時、シャロンが放った虫は私のそばにいたアランを認識出来ていなかった。
本当にシャロンは焦っていたのだろう。だから虫に余分な機能を持たせられなかったのだ。
そしてあの虫は本当にうるさかった。「早く、速く」と叫び続けていた。
(まったく、都合の良い時に呼ばれる方の身にもなってほしいものだ)
シャロンが私のように自分で調整出来ればこんな煩わしい思いをせずに済むのだが。
ならば、教えてみるか?
(……いや、それはそれでかなり面倒だな)
ルイスは自分がこの技術を習得するのにどれだけの時間を要したかをすぐに思い出した。
同時に、懐かしい記憶も奥底から浮き上がってきた。
それは苦い記憶でもあった。
「……」
ゆえに、ルイスの手は止まった。
それは一瞬であったが、何かあったのかと心配になったシャロンは口を開いた。
「どうしたの? 何か、私の頭の中でマズいことでもあった?」
これにルイスは首を振って答えた。
「いいや、そうじゃない。ちょっと昔を思い出しただけだ」
これに興味を抱いたシャロンは尋ねた。
「……昔? そういえば私、会う前のあなたのことをあまり知らないわ。良ければ話してくれない?」
その言葉に引っかかるものがあったルイスは尋ね返した。
「あまり? あまりってどういうことだ?」
シャロンに昔のことを話したことはほとんど無い。だが、まるでそれ以上知っているかのような口ぶりだ。
自分の心を、記憶を盗み見たのだろうか、ルイスはそう思ったが、シャロンは少し違う答えを述べた。
「『あいつ』から聞いたのよ。少しだけね」
その確認のために、寝ているルイスの記憶をこっそり覗いたことはあるのだが、それは黙っておくことにした。
そしてルイスは『それ』が蜘蛛の化け物のことを指していることを、聞き返さずとも理解した。
ゆえにルイスは、「ああ、あいつか」と、何かをあきらめたかのような言葉を漏らした。
そういえば『あいつ』はどこにいるんだろうか。シャロンを探していたはずだが。
ルイスがそう思った瞬間、
「呼んだかい?」
と、『あいつ』の声が魂に響いた。
これに二人は、
「「!?」」
同時に同じ表情を浮かべた。
近くにいたことに全く気が付かなかったからだ。
そしてその声の発生源は――
((下?!))
ゆえにシャロンとルイスは同時に下を向いた。
すると『あいつ』は地面の中から染み出すように、這い出るように、二人の目の前に姿を表した。
人の形を成しながら。
そしてその人の形をしたものは、シャロンに向かって口を開いた。
「久しぶりだねシャロン」
0
あなたにおすすめの小説

(完結)醜くなった花嫁の末路「どうぞ、お笑いください。元旦那様」
音爽(ネソウ)
ファンタジー
容姿が気に入らないと白い結婚を強いられた妻。
本邸から追い出されはしなかったが、夫は離れに愛人を囲い顔さえ見せない。
しかし、3年と待たず離縁が決定する事態に。そして元夫の家は……。
*6月18日HOTランキング入りしました、ありがとうございます。

無魔力の令嬢、婚約者に裏切られた瞬間、契約竜が激怒して王宮を吹き飛ばしたんですが……
タマ マコト
ファンタジー
王宮の祝賀会で、無魔力と蔑まれてきた伯爵令嬢エリーナは、王太子アレクシオンから突然「婚約破棄」を宣告される。侍女上がりの聖女セレスが“新たな妃”として選ばれ、貴族たちの嘲笑がエリーナを包む。絶望に胸が沈んだ瞬間、彼女の奥底で眠っていた“竜との契約”が目を覚まし、空から白銀竜アークヴァンが降臨。彼はエリーナの涙に激怒し、王宮を半壊させるほどの力で彼女を守る。王国は震え、エリーナは自分が竜の真の主であるという運命に巻き込まれていく。

【完結】辺境に飛ばされた子爵令嬢、前世の経営知識で大商会を作ったら王都がひれ伏したし、隣国のハイスペ王子とも結婚できました
いっぺいちゃん
ファンタジー
婚約破棄、そして辺境送り――。
子爵令嬢マリエールの運命は、結婚式直前に無惨にも断ち切られた。
「辺境の館で余生を送れ。もうお前は必要ない」
冷酷に告げた婚約者により、社交界から追放された彼女。
しかし、マリエールには秘密があった。
――前世の彼女は、一流企業で辣腕を振るった経営コンサルタント。
未開拓の農産物、眠る鉱山資源、誠実で働き者の人々。
「必要ない」と切り捨てられた辺境には、未来を切り拓く力があった。
物流網を整え、作物をブランド化し、やがて「大商会」を設立!
数年で辺境は“商業帝国”と呼ばれるまでに発展していく。
さらに隣国の完璧王子から熱烈な求婚を受け、愛も手に入れるマリエール。
一方で、税収激減に苦しむ王都は彼女に救いを求めて――
「必要ないとおっしゃったのは、そちらでしょう?」
これは、追放令嬢が“経営知識”で国を動かし、
ざまぁと恋と繁栄を手に入れる逆転サクセスストーリー!
※表紙のイラストは画像生成AIによって作られたものです。

新約・精霊眼の少女
みつまめ つぼみ
ファンタジー
孤児院で育った14歳の少女ヒルデガルトは、豊穣の神の思惑で『精霊眼』を授けられてしまう。
力を与えられた彼女の人生は、それを転機に運命の歯車が回り始める。
孤児から貴族へ転身し、貴族として強く生きる彼女を『神の試練』が待ち受ける。
可憐で凛々しい少女ヒルデガルトが、自分の運命を乗り越え『可愛いお嫁さん』という夢を叶える為に奮闘する。
頼もしい仲間たちと共に、彼女は国家を救うために動き出す。
これは、運命に導かれながらも自分の道を切り開いていく少女の物語。
----
本作は「精霊眼の少女」を再構成しリライトした作品です。

【魔女ローゼマリー伝説】~5歳で存在を忘れられた元王女の私だけど、自称美少女天才魔女として世界を救うために冒険したいと思います!~
ハムえっぐ
ファンタジー
かつて魔族が降臨し、7人の英雄によって平和がもたらされた大陸。その一国、ベルガー王国で物語は始まる。
王国の第一王女ローゼマリーは、5歳の誕生日の夜、幸せな時間のさなかに王宮を襲撃され、目の前で両親である国王夫妻を「漆黒の剣を持つ謎の黒髪の女」に殺害される。母が最後の力で放った転移魔法と「魔女ディルを頼れ」という遺言によりローゼマリーは辛くも死地を脱した。
15歳になったローゼは師ディルと別れ、両親の仇である黒髪の女を探し出すため、そして悪政により荒廃しつつある祖国の現状を確かめるため旅立つ。
国境の街ビオレールで冒険者として活動を始めたローゼは、運命的な出会いを果たす。因縁の仇と同じ黒髪と漆黒の剣を持つ少年傭兵リョウ。自由奔放で可愛いが、何か秘密を抱えていそうなエルフの美少女ベレニス。クセの強い仲間たちと共にローゼの新たな人生が動き出す。
これは王女の身分を失った最強天才魔女ローゼが、復讐の誓いを胸に仲間たちとの絆を育みながら、王国の闇や自らの運命に立ち向かう物語。友情、復讐、恋愛、魔法、剣戟、謀略が織りなす、ダークファンタジー英雄譚が、今、幕を開ける。

伯爵令嬢アンマリアのダイエット大作戦
未羊
ファンタジー
気が付くとまん丸と太った少女だった?!
痩せたいのに食事を制限しても運動をしても太っていってしまう。
一体私が何をしたというのよーっ!
驚愕の異世界転生、始まり始まり。
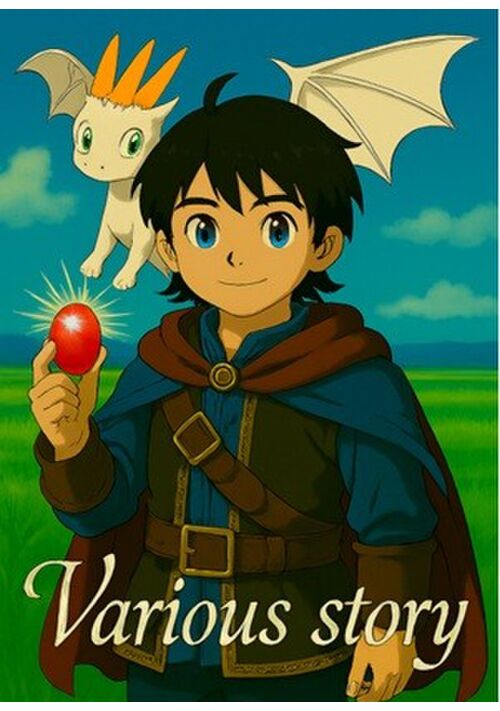
炎光に誘われし少年と竜の蒼天の約束 ヴェアリアスストーリー番外編
きみゆぅ
ファンタジー
かつて世界を滅ぼしかけたセイシュとイシュの争い。
その痕跡は今もなお、荒野の奥深くに眠り続けていた。
少年が掘り起こした“結晶”――それは国を揺るがすほどの力を秘めた禁断の秘宝「火の原石」。
平穏だった村に突如訪れる陰謀と争奪戦。
白竜と少年は未来を掴むのか、それとも再び戦乱の炎を呼び覚ますのか?
本作は、本編と並行して紡がれるもう一つの物語を描く番外編。
それぞれに選ばれし者たちの運命は別々の道を進みながらも、やがて大いなる流れの中で交わり、
世界を再び揺るがす壮大な物語へと収束していく。

【完結】領主の妻になりました
青波鳩子
恋愛
「私が君を愛することは無い」
司祭しかいない小さな教会で、夫になったばかりのクライブにフォスティーヌはそう告げられた。
===============================================
オルティス王の側室を母に持つ第三王子クライブと、バーネット侯爵家フォスティーヌは婚約していた。
挙式を半年後に控えたある日、王宮にて事件が勃発した。
クライブの異母兄である王太子ジェイラスが、国王陛下とクライブの実母である側室を暗殺。
新たに王の座に就いたジェイラスは、異母弟である第二王子マーヴィンを公金横領の疑いで捕縛、第三王子クライブにオールブライト辺境領を治める沙汰を下した。
マーヴィンの婚約者だったブリジットは共犯の疑いがあったが確たる証拠が見つからない。
ブリジットが王都にいてはマーヴィンの子飼いと接触、画策の恐れから、ジェイラスはクライブにオールブライト領でブリジットの隔離監視を命じる。
捜査中に大怪我を負い、生涯歩けなくなったブリジットをクライブは密かに想っていた。
長兄からの「ブリジットの隔離監視」を都合よく解釈したクライブは、オールブライト辺境伯の館のうち豪華な別邸でブリジットを囲った。
新王である長兄の命令に逆らえずフォスティーヌと結婚したクライブは、本邸にフォスティーヌを置き、自分はブリジットと別邸で暮らした。
フォスティーヌに「別邸には近づくことを許可しない」と告げて。
フォスティーヌは「お飾りの領主の妻」としてオールブライトで生きていく。
ブリジットの大きな嘘をクライブが知り、そこからクライブとフォスティーヌの関係性が変わり始める。
========================================
*荒唐無稽の世界観の中、ふんわりと書いていますのでふんわりとお読みください
*約10万字で最終話を含めて全29話です
*他のサイトでも公開します
*10月16日より、1日2話ずつ、7時と19時にアップします
*誤字、脱字、衍字、誤用、素早く脳内変換してお読みいただけるとありがたいです
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















