435 / 586
第七章 アランが父に代わって歴史の表舞台に立つ
第四十九話 懐かしき地獄(4)
しおりを挟む
◆◆◆
そして遠方からアランが見守る中、戦いはゆっくりと始まった。
開始の合図の派手さとは対照的に、静かな始まり。
クリス達は相手が近付いてくるのを待っている。射程に入るのを待っている。
クリス達は溝の中に隠れているため、ガストン軍からは見えない。
そしてガストン軍の兵士達はどこに潜んでいるか分からないクリス達を警戒していた。
警戒心が兵士達の足を遅くしている。
その牛歩のような歩みに対し、クリスは、
(……さっさと来い)
そんなことを思った後、笑みを浮かべた。
本当に可笑しかったからだ。
子供の頃は戦いが嫌で仕方無かった。
父を失い、覚悟が決まっても恐怖が消えることは無かった。
なのに、今ではどうだ。
自分はこの戦いを待ち望んでいた。そして今、楽しいと本気で感じている。
(どうしてこんなにも変わった?)
ふと湧いたその疑問の答えは、すぐに浮かび上がった。
自信があるからだ。
以前は違った。勝てるかどうか分からない戦いばかりだった。地獄のような死線を何度もくぐらされた。
だから敵を恐ろしいと感じていた。
しかし今は違う。逆なのだ。
今は自分が相手に恐怖を与える側なのだ。地獄を見せつける側なのだ。
「……ふふっ」
その答えに、クリスはとうとう笑い声をこぼした。
そしてその声がそばに控えるクラウスの耳に入ったのとほぼ同時に、敵の最前列が射程内に入った。
だからクリスは笑みを顔に貼り付けたまま、
「攻撃開始!」
叫び声を場に響かせた。
クリスの兵士達が一斉に溝の中から顔を出し、敵部隊に向かって光弾を発射する。
ガストン軍の兵士達はこれを大盾や防御魔法で受け止めた。
数発の同時着弾を浴び、盾を破られた者達が倒れる。
その苦痛の声を聞きながら兵士達が反撃を放つ。
しかし既にクリス達の姿は無い。既に頭を引っ込めてしまっている。
放たれた光弾が虚しく地面に着弾。
その直後、クリス達は再び顔を出し、光弾を放った。
ガストン軍の兵士達が再び倒れる。
再び反撃を放つも結果は同じ。
そしてガストン軍の総大将はこの二度の攻防で自軍の不利を悟った。
総大将は気付いた。相手は地の利を作ったのだと。
地の利とはすなわち、安全なところから一方的に攻撃出来る地形、または相手を強制的に不利な隊形にしてしまう地形のことである。
前者は崖上などの高所や森、後者は狭い谷間の通路などが代表的である。
クリスは前者の地形を作ったのだと、総大将は判断した。
それは正解であった。
だが、
(残念だが、)
それだけでは無いことを、クリスは心の声で述べた。
感知能力者特有の利点がこの戦術に発揮されていた。
顔を出す時間が短いのだ。
なぜなら、狙いが既に定まっているからだ。
クリスが感知した情報が共有されているため、溝の中に身を隠している状態でも相手の位置を把握出来ている。
兵士達は光弾を投げるためだけに顔を出しているのだ。肩に自信がある者は腕だけしか出していない。
それ以外の時間は大地という強固な盾に守られることになる。
どちらが不利なのかは馬鹿でも分かる。だからガストン軍の総大将はすぐに気付くことが出来た。
しかし対応策まですぐに思いつくかは別だ。
ゆえに、
「……っ」
ガストン軍の総大将は暫しの間、兵士達の悲鳴を聞きながら歯をかみ締めることになった。
そして耳に入る悲鳴が焦りを生む直前になってようやく、一つの手が浮かんだ。
総大将は即座にそれを叫んだ。
「弓兵部隊、前進! 上から狙え!」
横からの攻撃はほぼ有効打にならない、ならば上から雨のように攻撃を降らせることが出来る弓兵ならば、総大将はそう思い、指示を出した。
「大盾兵と魔法使いは壁を作って援護しろ!」
そしてその指示は悪く無いように思えた。
だから兵士達は即座に反応した。
弓兵達が空を仰ぐように弓を上に向ける。
大盾兵と魔法使い達が最前に並ぶ。
そして盾と防御魔法が隙間の無い壁を形成した直後、弓兵達は引き絞った力を解放した。
一斉に放たれた矢が弧を描き、雨のように塹壕に降り注ぐ。
(どうだ?)
総大将は願うようにその成果を期待した。
が、
「っ!」
直後放たれたクリス達の反撃に、総大将は顔をしかめた。
反撃がまったく弱まっていない。
それはつまり、相手の数が減っていないということ。矢が当たっていないということ。
だが、今の総大将にはこの手しか無かった。
ゆえに、
「ひるむな、撃ち続けろ!」
そう叫ぶことしか出来なかった。
言われるまでも無く、弓兵達が矢を放ち続ける。
されど反撃は緩まない。緩む気配が無い。
何度撃ち合っても、被害が増すのは自軍ばかり。
なので総大将はその原因を考えざるを得なかった。
(思っていたよりも深い? そのせいで矢が当たってない?)
それは至極普通な考え方であり正解であったのだが、一つ、総大将は大事なことに気付けなかった。
クリス達が矢に対して光の盾をかざすなどの防御行動を一切取っていないことだ。
これも感知によるものである。矢の軌道が分かっているからだ。当たる心配がまったく無いと分かっているからなのだ。
しかし総大将は気付けない。感知のことを知らない。
だから、総大将は自身の常識に基づいて思考を積み重ねることしか出来なかった。
ゆえに、総大将が直後に発した新たな指示は至極普通のものであった。
「全軍前進! もっと接近しろ!」
矢の雨の角度をもっと急勾配にするためと思われる指示。
それはこの状況を変えるにはあまりにも弱すぎる手であるのだが、兵士達にもその判断がつかないため、従うしか無かった。
弓兵達の足が、彼らを守る壁が前に進み始める。
当然、距離が詰まれば光弾の集弾率が増し、被害が加速する。
だが、直後、
(良し!)
総大将が待ち望んでいた変化が遂に表れた。
クリス達が遂に防御魔法を展開したのだ。
しかし、
「!?」
同時に反撃も受けた。
されど、その反撃は直前までのものと比べると火力が落ちているように見えた。
その理由はすぐに分かった。
クリスが部隊を二列に分けたのだ。
前列が矢を受ける囮となり、後列がひたすらに反撃を行う形。
それを見た瞬間、総大将は「もしや」と思った。
総大将は即座にその思いを指示に変えた。
「全軍、さらに前進!」
すると、総大将の予想は的中した。
前進に対しクリス達が後退したのだ。
陣地を死守する意思が感じられない、総大将はそう思った。
ゆえに、総大将は即座に続けて声を上げた。
「全軍、突撃しろ!」
これに、兵士達は戸惑う様子を見せた。
「なぜ?」という疑問がその足に、目に表れていた。
だから、総大将は目を合わせながらその理由を叫んだ。
「乗り込むのだ! あの強力な陣地を奪い取れ!」
そしてその叫びは、この現状を打破するのに最も有効な手であるように思えた。
兵士達の目から疑問の色が消える。
そしてその顔に希望と勇気の色が滲に始めると同時に、総大将は再び声を上げた。
「隊列は気にしなくていい! 走れ!」
「「「雄応ッ!」」」
戦場に勇敢なる者の気勢が響き、その爪先が前に飛び出す。
それから数瞬遅れて、各部隊長が発した「「前進ーーッ!」」という叫び声が、兵士達の足音と混じって戦場を揺らした。
そして遠方からアランが見守る中、戦いはゆっくりと始まった。
開始の合図の派手さとは対照的に、静かな始まり。
クリス達は相手が近付いてくるのを待っている。射程に入るのを待っている。
クリス達は溝の中に隠れているため、ガストン軍からは見えない。
そしてガストン軍の兵士達はどこに潜んでいるか分からないクリス達を警戒していた。
警戒心が兵士達の足を遅くしている。
その牛歩のような歩みに対し、クリスは、
(……さっさと来い)
そんなことを思った後、笑みを浮かべた。
本当に可笑しかったからだ。
子供の頃は戦いが嫌で仕方無かった。
父を失い、覚悟が決まっても恐怖が消えることは無かった。
なのに、今ではどうだ。
自分はこの戦いを待ち望んでいた。そして今、楽しいと本気で感じている。
(どうしてこんなにも変わった?)
ふと湧いたその疑問の答えは、すぐに浮かび上がった。
自信があるからだ。
以前は違った。勝てるかどうか分からない戦いばかりだった。地獄のような死線を何度もくぐらされた。
だから敵を恐ろしいと感じていた。
しかし今は違う。逆なのだ。
今は自分が相手に恐怖を与える側なのだ。地獄を見せつける側なのだ。
「……ふふっ」
その答えに、クリスはとうとう笑い声をこぼした。
そしてその声がそばに控えるクラウスの耳に入ったのとほぼ同時に、敵の最前列が射程内に入った。
だからクリスは笑みを顔に貼り付けたまま、
「攻撃開始!」
叫び声を場に響かせた。
クリスの兵士達が一斉に溝の中から顔を出し、敵部隊に向かって光弾を発射する。
ガストン軍の兵士達はこれを大盾や防御魔法で受け止めた。
数発の同時着弾を浴び、盾を破られた者達が倒れる。
その苦痛の声を聞きながら兵士達が反撃を放つ。
しかし既にクリス達の姿は無い。既に頭を引っ込めてしまっている。
放たれた光弾が虚しく地面に着弾。
その直後、クリス達は再び顔を出し、光弾を放った。
ガストン軍の兵士達が再び倒れる。
再び反撃を放つも結果は同じ。
そしてガストン軍の総大将はこの二度の攻防で自軍の不利を悟った。
総大将は気付いた。相手は地の利を作ったのだと。
地の利とはすなわち、安全なところから一方的に攻撃出来る地形、または相手を強制的に不利な隊形にしてしまう地形のことである。
前者は崖上などの高所や森、後者は狭い谷間の通路などが代表的である。
クリスは前者の地形を作ったのだと、総大将は判断した。
それは正解であった。
だが、
(残念だが、)
それだけでは無いことを、クリスは心の声で述べた。
感知能力者特有の利点がこの戦術に発揮されていた。
顔を出す時間が短いのだ。
なぜなら、狙いが既に定まっているからだ。
クリスが感知した情報が共有されているため、溝の中に身を隠している状態でも相手の位置を把握出来ている。
兵士達は光弾を投げるためだけに顔を出しているのだ。肩に自信がある者は腕だけしか出していない。
それ以外の時間は大地という強固な盾に守られることになる。
どちらが不利なのかは馬鹿でも分かる。だからガストン軍の総大将はすぐに気付くことが出来た。
しかし対応策まですぐに思いつくかは別だ。
ゆえに、
「……っ」
ガストン軍の総大将は暫しの間、兵士達の悲鳴を聞きながら歯をかみ締めることになった。
そして耳に入る悲鳴が焦りを生む直前になってようやく、一つの手が浮かんだ。
総大将は即座にそれを叫んだ。
「弓兵部隊、前進! 上から狙え!」
横からの攻撃はほぼ有効打にならない、ならば上から雨のように攻撃を降らせることが出来る弓兵ならば、総大将はそう思い、指示を出した。
「大盾兵と魔法使いは壁を作って援護しろ!」
そしてその指示は悪く無いように思えた。
だから兵士達は即座に反応した。
弓兵達が空を仰ぐように弓を上に向ける。
大盾兵と魔法使い達が最前に並ぶ。
そして盾と防御魔法が隙間の無い壁を形成した直後、弓兵達は引き絞った力を解放した。
一斉に放たれた矢が弧を描き、雨のように塹壕に降り注ぐ。
(どうだ?)
総大将は願うようにその成果を期待した。
が、
「っ!」
直後放たれたクリス達の反撃に、総大将は顔をしかめた。
反撃がまったく弱まっていない。
それはつまり、相手の数が減っていないということ。矢が当たっていないということ。
だが、今の総大将にはこの手しか無かった。
ゆえに、
「ひるむな、撃ち続けろ!」
そう叫ぶことしか出来なかった。
言われるまでも無く、弓兵達が矢を放ち続ける。
されど反撃は緩まない。緩む気配が無い。
何度撃ち合っても、被害が増すのは自軍ばかり。
なので総大将はその原因を考えざるを得なかった。
(思っていたよりも深い? そのせいで矢が当たってない?)
それは至極普通な考え方であり正解であったのだが、一つ、総大将は大事なことに気付けなかった。
クリス達が矢に対して光の盾をかざすなどの防御行動を一切取っていないことだ。
これも感知によるものである。矢の軌道が分かっているからだ。当たる心配がまったく無いと分かっているからなのだ。
しかし総大将は気付けない。感知のことを知らない。
だから、総大将は自身の常識に基づいて思考を積み重ねることしか出来なかった。
ゆえに、総大将が直後に発した新たな指示は至極普通のものであった。
「全軍前進! もっと接近しろ!」
矢の雨の角度をもっと急勾配にするためと思われる指示。
それはこの状況を変えるにはあまりにも弱すぎる手であるのだが、兵士達にもその判断がつかないため、従うしか無かった。
弓兵達の足が、彼らを守る壁が前に進み始める。
当然、距離が詰まれば光弾の集弾率が増し、被害が加速する。
だが、直後、
(良し!)
総大将が待ち望んでいた変化が遂に表れた。
クリス達が遂に防御魔法を展開したのだ。
しかし、
「!?」
同時に反撃も受けた。
されど、その反撃は直前までのものと比べると火力が落ちているように見えた。
その理由はすぐに分かった。
クリスが部隊を二列に分けたのだ。
前列が矢を受ける囮となり、後列がひたすらに反撃を行う形。
それを見た瞬間、総大将は「もしや」と思った。
総大将は即座にその思いを指示に変えた。
「全軍、さらに前進!」
すると、総大将の予想は的中した。
前進に対しクリス達が後退したのだ。
陣地を死守する意思が感じられない、総大将はそう思った。
ゆえに、総大将は即座に続けて声を上げた。
「全軍、突撃しろ!」
これに、兵士達は戸惑う様子を見せた。
「なぜ?」という疑問がその足に、目に表れていた。
だから、総大将は目を合わせながらその理由を叫んだ。
「乗り込むのだ! あの強力な陣地を奪い取れ!」
そしてその叫びは、この現状を打破するのに最も有効な手であるように思えた。
兵士達の目から疑問の色が消える。
そしてその顔に希望と勇気の色が滲に始めると同時に、総大将は再び声を上げた。
「隊列は気にしなくていい! 走れ!」
「「「雄応ッ!」」」
戦場に勇敢なる者の気勢が響き、その爪先が前に飛び出す。
それから数瞬遅れて、各部隊長が発した「「前進ーーッ!」」という叫び声が、兵士達の足音と混じって戦場を揺らした。
0
あなたにおすすめの小説

(完結)醜くなった花嫁の末路「どうぞ、お笑いください。元旦那様」
音爽(ネソウ)
ファンタジー
容姿が気に入らないと白い結婚を強いられた妻。
本邸から追い出されはしなかったが、夫は離れに愛人を囲い顔さえ見せない。
しかし、3年と待たず離縁が決定する事態に。そして元夫の家は……。
*6月18日HOTランキング入りしました、ありがとうございます。

無魔力の令嬢、婚約者に裏切られた瞬間、契約竜が激怒して王宮を吹き飛ばしたんですが……
タマ マコト
ファンタジー
王宮の祝賀会で、無魔力と蔑まれてきた伯爵令嬢エリーナは、王太子アレクシオンから突然「婚約破棄」を宣告される。侍女上がりの聖女セレスが“新たな妃”として選ばれ、貴族たちの嘲笑がエリーナを包む。絶望に胸が沈んだ瞬間、彼女の奥底で眠っていた“竜との契約”が目を覚まし、空から白銀竜アークヴァンが降臨。彼はエリーナの涙に激怒し、王宮を半壊させるほどの力で彼女を守る。王国は震え、エリーナは自分が竜の真の主であるという運命に巻き込まれていく。

【完結】辺境に飛ばされた子爵令嬢、前世の経営知識で大商会を作ったら王都がひれ伏したし、隣国のハイスペ王子とも結婚できました
いっぺいちゃん
ファンタジー
婚約破棄、そして辺境送り――。
子爵令嬢マリエールの運命は、結婚式直前に無惨にも断ち切られた。
「辺境の館で余生を送れ。もうお前は必要ない」
冷酷に告げた婚約者により、社交界から追放された彼女。
しかし、マリエールには秘密があった。
――前世の彼女は、一流企業で辣腕を振るった経営コンサルタント。
未開拓の農産物、眠る鉱山資源、誠実で働き者の人々。
「必要ない」と切り捨てられた辺境には、未来を切り拓く力があった。
物流網を整え、作物をブランド化し、やがて「大商会」を設立!
数年で辺境は“商業帝国”と呼ばれるまでに発展していく。
さらに隣国の完璧王子から熱烈な求婚を受け、愛も手に入れるマリエール。
一方で、税収激減に苦しむ王都は彼女に救いを求めて――
「必要ないとおっしゃったのは、そちらでしょう?」
これは、追放令嬢が“経営知識”で国を動かし、
ざまぁと恋と繁栄を手に入れる逆転サクセスストーリー!
※表紙のイラストは画像生成AIによって作られたものです。

新約・精霊眼の少女
みつまめ つぼみ
ファンタジー
孤児院で育った14歳の少女ヒルデガルトは、豊穣の神の思惑で『精霊眼』を授けられてしまう。
力を与えられた彼女の人生は、それを転機に運命の歯車が回り始める。
孤児から貴族へ転身し、貴族として強く生きる彼女を『神の試練』が待ち受ける。
可憐で凛々しい少女ヒルデガルトが、自分の運命を乗り越え『可愛いお嫁さん』という夢を叶える為に奮闘する。
頼もしい仲間たちと共に、彼女は国家を救うために動き出す。
これは、運命に導かれながらも自分の道を切り開いていく少女の物語。
----
本作は「精霊眼の少女」を再構成しリライトした作品です。

【魔女ローゼマリー伝説】~5歳で存在を忘れられた元王女の私だけど、自称美少女天才魔女として世界を救うために冒険したいと思います!~
ハムえっぐ
ファンタジー
かつて魔族が降臨し、7人の英雄によって平和がもたらされた大陸。その一国、ベルガー王国で物語は始まる。
王国の第一王女ローゼマリーは、5歳の誕生日の夜、幸せな時間のさなかに王宮を襲撃され、目の前で両親である国王夫妻を「漆黒の剣を持つ謎の黒髪の女」に殺害される。母が最後の力で放った転移魔法と「魔女ディルを頼れ」という遺言によりローゼマリーは辛くも死地を脱した。
15歳になったローゼは師ディルと別れ、両親の仇である黒髪の女を探し出すため、そして悪政により荒廃しつつある祖国の現状を確かめるため旅立つ。
国境の街ビオレールで冒険者として活動を始めたローゼは、運命的な出会いを果たす。因縁の仇と同じ黒髪と漆黒の剣を持つ少年傭兵リョウ。自由奔放で可愛いが、何か秘密を抱えていそうなエルフの美少女ベレニス。クセの強い仲間たちと共にローゼの新たな人生が動き出す。
これは王女の身分を失った最強天才魔女ローゼが、復讐の誓いを胸に仲間たちとの絆を育みながら、王国の闇や自らの運命に立ち向かう物語。友情、復讐、恋愛、魔法、剣戟、謀略が織りなす、ダークファンタジー英雄譚が、今、幕を開ける。

伯爵令嬢アンマリアのダイエット大作戦
未羊
ファンタジー
気が付くとまん丸と太った少女だった?!
痩せたいのに食事を制限しても運動をしても太っていってしまう。
一体私が何をしたというのよーっ!
驚愕の異世界転生、始まり始まり。
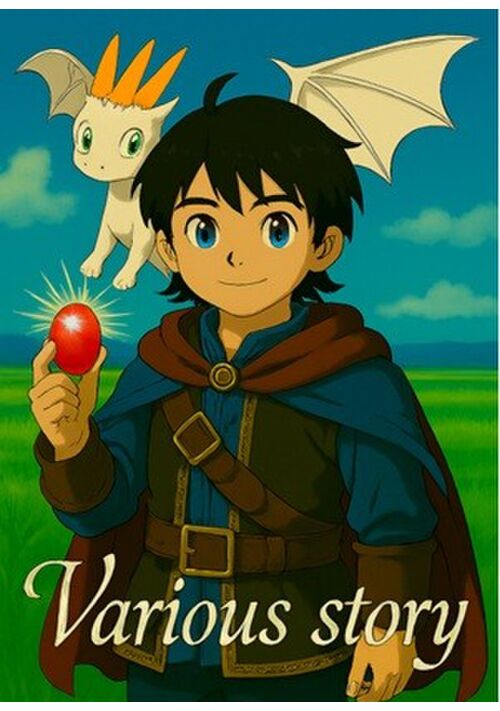
炎光に誘われし少年と竜の蒼天の約束 ヴェアリアスストーリー番外編
きみゆぅ
ファンタジー
かつて世界を滅ぼしかけたセイシュとイシュの争い。
その痕跡は今もなお、荒野の奥深くに眠り続けていた。
少年が掘り起こした“結晶”――それは国を揺るがすほどの力を秘めた禁断の秘宝「火の原石」。
平穏だった村に突如訪れる陰謀と争奪戦。
白竜と少年は未来を掴むのか、それとも再び戦乱の炎を呼び覚ますのか?
本作は、本編と並行して紡がれるもう一つの物語を描く番外編。
それぞれに選ばれし者たちの運命は別々の道を進みながらも、やがて大いなる流れの中で交わり、
世界を再び揺るがす壮大な物語へと収束していく。

【完結】領主の妻になりました
青波鳩子
恋愛
「私が君を愛することは無い」
司祭しかいない小さな教会で、夫になったばかりのクライブにフォスティーヌはそう告げられた。
===============================================
オルティス王の側室を母に持つ第三王子クライブと、バーネット侯爵家フォスティーヌは婚約していた。
挙式を半年後に控えたある日、王宮にて事件が勃発した。
クライブの異母兄である王太子ジェイラスが、国王陛下とクライブの実母である側室を暗殺。
新たに王の座に就いたジェイラスは、異母弟である第二王子マーヴィンを公金横領の疑いで捕縛、第三王子クライブにオールブライト辺境領を治める沙汰を下した。
マーヴィンの婚約者だったブリジットは共犯の疑いがあったが確たる証拠が見つからない。
ブリジットが王都にいてはマーヴィンの子飼いと接触、画策の恐れから、ジェイラスはクライブにオールブライト領でブリジットの隔離監視を命じる。
捜査中に大怪我を負い、生涯歩けなくなったブリジットをクライブは密かに想っていた。
長兄からの「ブリジットの隔離監視」を都合よく解釈したクライブは、オールブライト辺境伯の館のうち豪華な別邸でブリジットを囲った。
新王である長兄の命令に逆らえずフォスティーヌと結婚したクライブは、本邸にフォスティーヌを置き、自分はブリジットと別邸で暮らした。
フォスティーヌに「別邸には近づくことを許可しない」と告げて。
フォスティーヌは「お飾りの領主の妻」としてオールブライトで生きていく。
ブリジットの大きな嘘をクライブが知り、そこからクライブとフォスティーヌの関係性が変わり始める。
========================================
*荒唐無稽の世界観の中、ふんわりと書いていますのでふんわりとお読みください
*約10万字で最終話を含めて全29話です
*他のサイトでも公開します
*10月16日より、1日2話ずつ、7時と19時にアップします
*誤字、脱字、衍字、誤用、素早く脳内変換してお読みいただけるとありがたいです
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















