15 / 31
目の前に
しおりを挟む
”ヒューレーの森の動物たちは、困り果てていた。町に住む人間たちが、毎日狩りをしにやって来るようになったからだ。人間の数は日に日に増えた。森の外周に住む小鳥やキツネは真っ先に数を減らした”
グランドキャニオンのテゾーロ博士の物語とはまったく違うものだった。
ユイは思わず速度を落とした。
ペン太も「どうしたんだい?」といぶかしげに見上げる。
「なんだろ……何か引っかかって……」
「ユイ?」
「ううん……何でもない。いこっ」
ユイは正体の分からない不安を無理やり振り払った。考えても答えが出そうになかった。
気持ちの良い草原の風を浴びて、さらに駆けた。
本の声が続く。
”動物たちは恐れおののいた。風の噂で、人間の町の王が森にやってきて、森を支配するという話を聞いた。森一番の猿の賢人アエルは、年老いた体に鞭をうって、多くの動物たちの中から戦えそうなものを集めた。しかし、砂煙をあげて近づく人間の兵の数を見て、すぐに考えを改めた”
ずっと無言で本の声に耳をすませていたユイが、また速度を落とした。歩みが止まりかける。
「ユイ、体調が悪いのかい? 無理なら少し休んで……」
案じ顔のペン太が、前に回る。
ユイの顔が青白い。
「ペン太……さっきの水色のバッジって見える?」
「ん? 当たり前だろ? 森のちょうど真ん中あたりに光が射してる。その中にちゃんと見えてるよ」
「森の中央で間違いない?」
ユイが小さな声で確認する。ペン太がうなずいた。
「……まずいかも」
「ユイ?」
ペン太がのぞきこむ。
ユイは冷や汗を浮かべて顔をあげた。
「たぶんこの世界って――」
ユイが口にしかけた時だ。再び本の声が鳴り響いた。
”人間の群れは自分たちの力ではどうにもならない。助けを求めるしかない。賢人アエルは、最も頼りになる仲間、ピロスに頼んだ。ピロスは快く引き受けた。「体が大きいだけの私がきみたちの役に立つのなら」ピロスはのそりと体を起こした。森の中央で、最大の生物が数百年ぶりにほえた”
――グガァァァァア!
ユイは思わず耳をふさいだ。ペン太は立ち尽くし、尾を動かしながら、両手をばたつかせた。
「こ、これはどうなってるんだ?」
「ドラゴンだ……」
ユイは巨大生物に目をくぎ付けにして言った。
心臓ははげしく音をたて、耳奥には未だに大声が反響していた。
森の中央で、銀色の首がにゅうっと伸びた。巨大な体が持ち上がり、木々が次々と折れる音がする。体の向きを変えるだけで、地面がぐらぐらと揺れ、地響きのような音が周囲に広がった。
無数の小鳥がそれを歓迎するように、ぐるぐると上空を飛び回っていた。
「あっ!」
ペン太が声をあげた。
ドラゴンの背に、空から降る光が射していた。磨き上げたガラスのような銀色の鱗が太陽光を反射する。
水色の光が、その中でちかちかと輝いた。
「うそだろ……」
ペン太がとんでもない事態に顔をゆがめた。
「たぶん背中に引っかかってるね……」
ユイもどうしようもないと首を振った。
「ユイ……この本の内容を知ってるのかい?」
「うん。最近図書室で読んだ本。三日前に出たばっかりだったはず」
「つまり、図書界にまだやってきてない本ってことか。知らなくて当然か……どんな内容なんだい?」
ペン太がまばたきをせずユイを見つめる。やるせない顔で「信じられない偶然だな」とつぶやいた。
「ピロスっていうドラゴンが、森の仲間と協力して人間を追い払う話。最後は、ピロスが森の守り神としてあがめられて、森はずっと残って人間とも仲良くなるってお話」
「それって……」
「最悪かも」
ユイがため息をつく。
ペン太の瞳がうつろになった。
「さっきから、なぜかぼくらは本の住人に干渉されるようになったんだぞ?」
「わかってる。だから最悪かもって」
「最悪どころじゃないぞ!」
ペン太が両手をばたつかせる。視線が泳ぎ、慌てふためいている。
遠くでピロスが動き出し、人間たちに向かった。
「ドラゴンだと!? リスに追いかけられる方が、まだマシだ!」
ユイがうなずく。
言いたいことはよくわかる。
ピロスがどんなドラゴンかはわからない。物語の中では長い年月を生きているが、根は弱虫のドラゴンだ。事情を話せば背中に引っかかったバッジを取らせてくれるかもしれない。
しかし、グランドキャニオンの一件を思い出せば、本の住人が自分たちの話を素直に聞いてくれるとは思えない。
見つかればまた追いかけられるかもしれない。
まして、『ピロスと森の仲間たち』は、人間と敵対するところから話が始まる。ペン太はともかく、ユイは人間だ。見た瞬間に敵として襲われるかもしれない。
小さなリスならまだしも、マンションほどに大きなドラゴンと追いかけっこなど無理だ。相手が一歩詰めるだけで、二人はぺしゃんこになるだろう。
自分の後ろを地響きを立てて巨大なドラゴンが走ってくるなど想像もしたくない。
ペン太も同じだろう。どう見ても顔がひきつっている。
「ユイ……ど、どうしよう?」
「どうするって……ペン太はバッジいるんでしょ?」
「そうだけど……」
「何かうまい方法はないの? たとえば……ドラゴンを少しだけ気絶させるとか? 図書ペンギン道具に眠らせるものないの? おやすみヒマワリとか」
「そんなに都合のいい道具はない」
ペン太がやるせない顔で首を振った。「それに」と続ける。
「ケガをさせたり、眠らせたり、本の登場人物に直接手を出すのはタブー中のタブーだ。図書ペンギン司書が絶対にやっちゃならないことだって教わるんだ。ただ……」
ペン太が苦し気に言って、下を向いた。
しかし、言葉は続かない。
「ペン太……」
本当は、ユイが知らない方法があるのかもしれない。
でもそれをすれば、たぶん罰が与えられるのだろう。もしかすると、図書ペンギン司書の夢が潰えるのかもしれない。
「これが最後のチャンスになるかもしれない……『図書ペンギンにしかできない冒険をしなさい』っていう試験の本当の意味は、どんなピンチでもチャンスに変えなさいってことかもしれない……ぼくは知らず知らずのうちに、チャンスを逃してきたかもしれない……」
ペン太がのどから声を絞り出すように言った。
自分に言い聞かせているのかもしれない。
ドラゴンをにらみ、視線を落とす。何度も繰り返した。
思えば、ペン太はずっと図書ペンギン司書にあこがれていた。見習いの自分が嫌いなのかもしれない。ユイに知識をほめられるたびに、「図書ペンギン司書を目指しているからな」と胸を張っていた。
危険な図書界を何年も一人で歩いてきたのだ。
そして、目の前にようやくチャンスが訪れた。
ただ、もし失敗すれば――
ユイは胸がしめ付けられた。そっと視線を外した。
「……ペン太、もし登場人物に手を出しちゃったらどうなるの?」
「噂は知ってるけど、ほんとのところはわからない。最大のタブーだから、どうなるかなんて試したことはないよ。でもたぶん……見習いすら辞めさせられると思う……」
「そうなんだ……」
「ただ、協会にばれずにバッジを手に入れられれば――」
ペン太の瞳に怪しい輝きが灯った。
グランドキャニオンのテゾーロ博士の物語とはまったく違うものだった。
ユイは思わず速度を落とした。
ペン太も「どうしたんだい?」といぶかしげに見上げる。
「なんだろ……何か引っかかって……」
「ユイ?」
「ううん……何でもない。いこっ」
ユイは正体の分からない不安を無理やり振り払った。考えても答えが出そうになかった。
気持ちの良い草原の風を浴びて、さらに駆けた。
本の声が続く。
”動物たちは恐れおののいた。風の噂で、人間の町の王が森にやってきて、森を支配するという話を聞いた。森一番の猿の賢人アエルは、年老いた体に鞭をうって、多くの動物たちの中から戦えそうなものを集めた。しかし、砂煙をあげて近づく人間の兵の数を見て、すぐに考えを改めた”
ずっと無言で本の声に耳をすませていたユイが、また速度を落とした。歩みが止まりかける。
「ユイ、体調が悪いのかい? 無理なら少し休んで……」
案じ顔のペン太が、前に回る。
ユイの顔が青白い。
「ペン太……さっきの水色のバッジって見える?」
「ん? 当たり前だろ? 森のちょうど真ん中あたりに光が射してる。その中にちゃんと見えてるよ」
「森の中央で間違いない?」
ユイが小さな声で確認する。ペン太がうなずいた。
「……まずいかも」
「ユイ?」
ペン太がのぞきこむ。
ユイは冷や汗を浮かべて顔をあげた。
「たぶんこの世界って――」
ユイが口にしかけた時だ。再び本の声が鳴り響いた。
”人間の群れは自分たちの力ではどうにもならない。助けを求めるしかない。賢人アエルは、最も頼りになる仲間、ピロスに頼んだ。ピロスは快く引き受けた。「体が大きいだけの私がきみたちの役に立つのなら」ピロスはのそりと体を起こした。森の中央で、最大の生物が数百年ぶりにほえた”
――グガァァァァア!
ユイは思わず耳をふさいだ。ペン太は立ち尽くし、尾を動かしながら、両手をばたつかせた。
「こ、これはどうなってるんだ?」
「ドラゴンだ……」
ユイは巨大生物に目をくぎ付けにして言った。
心臓ははげしく音をたて、耳奥には未だに大声が反響していた。
森の中央で、銀色の首がにゅうっと伸びた。巨大な体が持ち上がり、木々が次々と折れる音がする。体の向きを変えるだけで、地面がぐらぐらと揺れ、地響きのような音が周囲に広がった。
無数の小鳥がそれを歓迎するように、ぐるぐると上空を飛び回っていた。
「あっ!」
ペン太が声をあげた。
ドラゴンの背に、空から降る光が射していた。磨き上げたガラスのような銀色の鱗が太陽光を反射する。
水色の光が、その中でちかちかと輝いた。
「うそだろ……」
ペン太がとんでもない事態に顔をゆがめた。
「たぶん背中に引っかかってるね……」
ユイもどうしようもないと首を振った。
「ユイ……この本の内容を知ってるのかい?」
「うん。最近図書室で読んだ本。三日前に出たばっかりだったはず」
「つまり、図書界にまだやってきてない本ってことか。知らなくて当然か……どんな内容なんだい?」
ペン太がまばたきをせずユイを見つめる。やるせない顔で「信じられない偶然だな」とつぶやいた。
「ピロスっていうドラゴンが、森の仲間と協力して人間を追い払う話。最後は、ピロスが森の守り神としてあがめられて、森はずっと残って人間とも仲良くなるってお話」
「それって……」
「最悪かも」
ユイがため息をつく。
ペン太の瞳がうつろになった。
「さっきから、なぜかぼくらは本の住人に干渉されるようになったんだぞ?」
「わかってる。だから最悪かもって」
「最悪どころじゃないぞ!」
ペン太が両手をばたつかせる。視線が泳ぎ、慌てふためいている。
遠くでピロスが動き出し、人間たちに向かった。
「ドラゴンだと!? リスに追いかけられる方が、まだマシだ!」
ユイがうなずく。
言いたいことはよくわかる。
ピロスがどんなドラゴンかはわからない。物語の中では長い年月を生きているが、根は弱虫のドラゴンだ。事情を話せば背中に引っかかったバッジを取らせてくれるかもしれない。
しかし、グランドキャニオンの一件を思い出せば、本の住人が自分たちの話を素直に聞いてくれるとは思えない。
見つかればまた追いかけられるかもしれない。
まして、『ピロスと森の仲間たち』は、人間と敵対するところから話が始まる。ペン太はともかく、ユイは人間だ。見た瞬間に敵として襲われるかもしれない。
小さなリスならまだしも、マンションほどに大きなドラゴンと追いかけっこなど無理だ。相手が一歩詰めるだけで、二人はぺしゃんこになるだろう。
自分の後ろを地響きを立てて巨大なドラゴンが走ってくるなど想像もしたくない。
ペン太も同じだろう。どう見ても顔がひきつっている。
「ユイ……ど、どうしよう?」
「どうするって……ペン太はバッジいるんでしょ?」
「そうだけど……」
「何かうまい方法はないの? たとえば……ドラゴンを少しだけ気絶させるとか? 図書ペンギン道具に眠らせるものないの? おやすみヒマワリとか」
「そんなに都合のいい道具はない」
ペン太がやるせない顔で首を振った。「それに」と続ける。
「ケガをさせたり、眠らせたり、本の登場人物に直接手を出すのはタブー中のタブーだ。図書ペンギン司書が絶対にやっちゃならないことだって教わるんだ。ただ……」
ペン太が苦し気に言って、下を向いた。
しかし、言葉は続かない。
「ペン太……」
本当は、ユイが知らない方法があるのかもしれない。
でもそれをすれば、たぶん罰が与えられるのだろう。もしかすると、図書ペンギン司書の夢が潰えるのかもしれない。
「これが最後のチャンスになるかもしれない……『図書ペンギンにしかできない冒険をしなさい』っていう試験の本当の意味は、どんなピンチでもチャンスに変えなさいってことかもしれない……ぼくは知らず知らずのうちに、チャンスを逃してきたかもしれない……」
ペン太がのどから声を絞り出すように言った。
自分に言い聞かせているのかもしれない。
ドラゴンをにらみ、視線を落とす。何度も繰り返した。
思えば、ペン太はずっと図書ペンギン司書にあこがれていた。見習いの自分が嫌いなのかもしれない。ユイに知識をほめられるたびに、「図書ペンギン司書を目指しているからな」と胸を張っていた。
危険な図書界を何年も一人で歩いてきたのだ。
そして、目の前にようやくチャンスが訪れた。
ただ、もし失敗すれば――
ユイは胸がしめ付けられた。そっと視線を外した。
「……ペン太、もし登場人物に手を出しちゃったらどうなるの?」
「噂は知ってるけど、ほんとのところはわからない。最大のタブーだから、どうなるかなんて試したことはないよ。でもたぶん……見習いすら辞めさせられると思う……」
「そうなんだ……」
「ただ、協会にばれずにバッジを手に入れられれば――」
ペン太の瞳に怪しい輝きが灯った。
0
あなたにおすすめの小説

ノースキャンプの見張り台
こいちろう
児童書・童話
時代劇で見かけるような、古めかしい木づくりの橋。それを渡ると、向こう岸にノースキャンプがある。アーミーグリーンの北門と、その傍の監視塔。まるで映画村のセットだ。
進駐軍のキャンプ跡。周りを鉄さびた有刺鉄線に囲まれた、まるで要塞みたいな町だった。進駐軍が去ってからは住宅地になって、たくさんの子どもが暮らしていた。
赤茶色にさび付いた監視塔。その下に広がる広っぱは、子どもたちの最高の遊び場だ。見張っているのか、見守っているのか、鉄塔の、あのてっぺんから、いつも誰かに見られているんじゃないか?ユーイチはいつもそんな風に感じていた。

9日間
柏木みのり
児童書・童話
サマーキャンプから友達の健太と一緒に隣の世界に迷い込んだ竜(リョウ)は文武両道の11歳。魔法との出会い。人々との出会い。初めて経験する様々な気持ち。そして究極の選択——夢か友情か。
(also @ なろう)
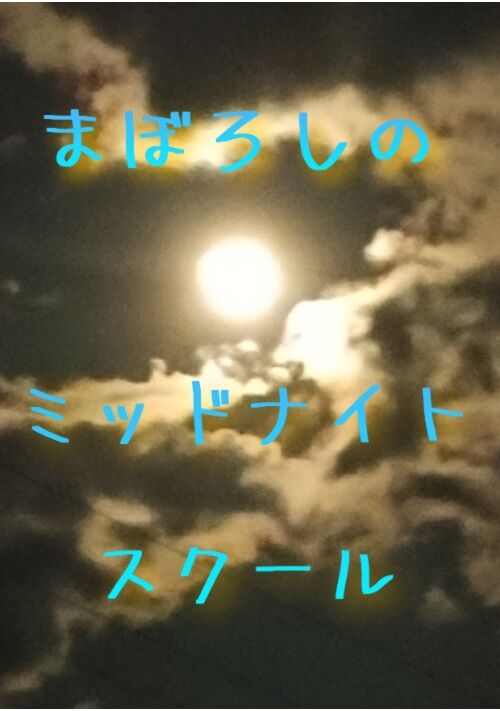
まぼろしのミッドナイトスクール
木野もくば
児童書・童話
深夜0時ちょうどに突然あらわれる不思議な学校。そこには、不思議な先生と生徒たちがいました。飼い猫との最後に後悔がある青年……。深い森の中で道に迷う少女……。人間に恋をした水の神さま……。それぞれの道に迷い、そして誰かと誰かの想いがつながったとき、暗闇の空に光る星くずの方から学校のチャイムが鳴り響いてくるのでした。

幸せのろうそく
マイマイン
児童書・童話
とある森の中にある町に住むおばあさんは、お祭りの日に「死んだ孫娘のキャンベルとまた暮らしたい」と、祈りをささげると、そのキャンベルが妖精に生まれ変わっておばあさんの前に現れました。
これは、キャンベルが恵まれない人々を幸せにしていく短編童話です。

「いっすん坊」てなんなんだ
こいちろう
児童書・童話
ヨシキは中学一年生。毎年お盆は瀬戸内海の小さな島に帰省する。去年は帰れなかったから二年ぶりだ。石段を上った崖の上にお寺があって、書院の裏は狭い瀬戸を見下ろす絶壁だ。その崖にあった小さなセミ穴にいとこのユキちゃんと一緒に吸い込まれた。長い長い穴の底。そこにいたのがいっすん坊だ。ずっとこの島の歴史と、生きてきた全ての人の過去を記録しているという。ユキちゃんは神様だと信じているが、どうもうさんくさいやつだ。するといっすん坊が、「それなら、おまえの振り返りたい過去を三つだけ、再現してみせてやろう」という。
自分の過去の振り返りから、両親への愛を再認識するヨシキ・・・

四尾がつむぐえにし、そこかしこ
月芝
児童書・童話
その日、小学校に激震が走った。
憧れのキラキラ王子さまが転校する。
女子たちの嘆きはひとしお。
彼に淡い想いを抱いていたユイもまた動揺を隠せない。
だからとてどうこうする勇気もない。
うつむき複雑な気持ちを抱えたままの帰り道。
家の近所に見覚えのない小路を見つけたユイは、少し寄り道してみることにする。
まさかそんな小さな冒険が、あんなに大ごとになるなんて……。
ひょんなことから石の祠に祀られた三尾の稲荷にコンコン見込まれて、
三つのお仕事を手伝うことになったユイ。
達成すれば、なんと一つだけ何でも願い事を叶えてくれるという。
もしかしたら、もしかしちゃうかも?
そこかしこにて泡沫のごとくあらわれては消えてゆく、えにしたち。
結んで、切って、ほどいて、繋いで、笑って、泣いて。
いろんな不思議を知り、数多のえにしを目にし、触れた先にて、
はたしてユイは何を求め願うのか。
少女のちょっと不思議な冒険譚。
ここに開幕。

ゼロになるレイナ
崎田毅駿
児童書・童話
お向かいの空き家に母娘二人が越してきた。僕・ジョエルはその女の子に一目惚れした。彼女の名はレイナといって、同じ小学校に転校してきて、同じクラスになった。近所のよしみもあって男子と女子の割には親しい友達になれた。けれども約一年後、レイナは消えてしまう。僕はそのとき、彼女の家にいたというのに。

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















