9 / 12
第三章 美しすぎる海と湖
知床五湖
しおりを挟む
いよいよ、「知床の岬に~」の知床だ。弟子屈から知床は約120kmの道のり。斜里からはオホーツク海を左に見ながらの快適なドライブ。2時間程で知床五湖の駐車場に着いた。ヒグマの活動期は過ぎていたが、五湖を巡るには注意が必要なようで、ガイドが伴った。
五湖をすべて巡るのに約90分を要したが、青い空をバックにした知床連山も湖面に映る景色も、時折遠くで聞こえるコノハズクの鳴き声も、更に「知床」を強く感じさせてくれた。ただ、一つだけ大変な思いをしたのは、太陽。五湖巡りでは、日陰がほとんどなかった。真夏の太陽が容赦なく降り注いだ。五湖巡りを終えてクルマに戻ってエアコンを入れてしばらく休まなければ動く気になれなかった。
今は知床横断道路が出来て簡単に羅臼に行けるが、当時は羅臼に抜ける知床横断道路はなかった。したがって、羅臼に行くには来た道を戻って反対側の道路を使って行かなくてはならない。
羅臼に何故行きたかったのかよく覚えていないが、羅臼行きにこだわった。斜里に戻って反対側の羅臼に着いた頃はもう真っ暗だった。これから戻っても、羅臼にいても今夜の車中泊が変わることはなかった。しかも、急に土砂降りの雨が降って来た。食料と飲み物は十分用意しておいたので大丈夫たが、知床半島の羅臼町で土砂降りの雨の中の車中泊は紫野がとても可哀想だった。でも、この時も紫野は「先生、スリル満点でいいですよ!」という。「先生、でも手をつないでいいですか?」といった。私は一晩中紫野の手を離さなかった。
羅臼の朝は早かった。雨もすっかりあがり、4時過ぎには空が明るくなった。紫野はまだよく眠っている。私もこのまま静かにもう少し眠ることにした。
7時、太陽の照りつけで目が覚めた。車内はすでに暑くなってきた。お腹が好いているのに気づいて、昨夜の残りのパンを二人でかじった。紫野に「先生、ところで羅臼で何が見たかったんですか?」と聞かれた。「何もなかったね」「え、何か目的があった訳じゃないんですか?」と言われ「とにかく羅臼ってどんなところか来て見たかったんだよ」と言うと、「でも、スリルがあって面白かったです」と言ってくれた。「先生、次はどこに行くんですか」と言われ、「野付半島だよ」と答えた。
「野付半島っていうのは知床半島と根室半島の間にある砂嘴(さし)だよ。砂嘴とは、岸沿いに流れる海水によって運ばれた土砂が堆積してできた、海上に長く突き出た地形のことなんだ。トドワラといって、トドマツの立ち枯れが有名なんだよ。」「立ち枯れって何ですか。」「かつては立派に葉を茂らせていた樹木か立ったまま枯れているんだよ」「だから立ち枯れって言うんだ」「それが半島のいたるところで見られるんだよ」標津から左に折れると野付半島に至る。「先生、あれですか。」と紫野はいち早くトドワラを見つけたようだ。一本の長い道路の両脇にたくさんの枯れた木が立ち並んでいる。確かに異様な光景だ。群馬県の赤城山の木が酸性雨のために立ち枯れしたのとよく似ている。一体何故こんなことになったのかと考えて見た。立ち枯れする前は立派なトドマツが生えていた訳だから、この辺りは樹木が生息できる環境であった訳だ。それが立ち枯れしてしまうほどの環境の変化とは一体どんなものだったのだろうか。野付半島は徐々に面積が小さくなっているらしい。海面の上昇によるものか、海流によるものかはわからないが、いずれは半島が島になってしまうともいわれている。となるとトドマツが枯れたのは土壌に海水がしみこんできたことによるもと考えるのが妥当だろう。ただ、地球温暖化は平成に入った頃から大きく問題視されるようになったことであり、トドワラはそれよりずっと以前に作られたものなので、やはりトドワラの成因が何なのか知りたいと思った。
野付半島を出て私たちは風蓮湖の横を通って根室半島の突端、納沙布岬に向かった。ここも、何か特別な目的があったわけではないが知床半島と違って、半島の先端部まで車で行けるので、行ってみたくなった。肉眼では見えなかったが海の向こうに歯舞群島があるはず。岬のいたるところに「北方領土」の文字が刻まれていた。相互不可侵条約を破って侵攻してきたソ連がここを返還する日は絶対に来ないだろうと思った。
そんな思いを岬の見晴らし台に残して、納沙布岬をあとにした。
五湖をすべて巡るのに約90分を要したが、青い空をバックにした知床連山も湖面に映る景色も、時折遠くで聞こえるコノハズクの鳴き声も、更に「知床」を強く感じさせてくれた。ただ、一つだけ大変な思いをしたのは、太陽。五湖巡りでは、日陰がほとんどなかった。真夏の太陽が容赦なく降り注いだ。五湖巡りを終えてクルマに戻ってエアコンを入れてしばらく休まなければ動く気になれなかった。
今は知床横断道路が出来て簡単に羅臼に行けるが、当時は羅臼に抜ける知床横断道路はなかった。したがって、羅臼に行くには来た道を戻って反対側の道路を使って行かなくてはならない。
羅臼に何故行きたかったのかよく覚えていないが、羅臼行きにこだわった。斜里に戻って反対側の羅臼に着いた頃はもう真っ暗だった。これから戻っても、羅臼にいても今夜の車中泊が変わることはなかった。しかも、急に土砂降りの雨が降って来た。食料と飲み物は十分用意しておいたので大丈夫たが、知床半島の羅臼町で土砂降りの雨の中の車中泊は紫野がとても可哀想だった。でも、この時も紫野は「先生、スリル満点でいいですよ!」という。「先生、でも手をつないでいいですか?」といった。私は一晩中紫野の手を離さなかった。
羅臼の朝は早かった。雨もすっかりあがり、4時過ぎには空が明るくなった。紫野はまだよく眠っている。私もこのまま静かにもう少し眠ることにした。
7時、太陽の照りつけで目が覚めた。車内はすでに暑くなってきた。お腹が好いているのに気づいて、昨夜の残りのパンを二人でかじった。紫野に「先生、ところで羅臼で何が見たかったんですか?」と聞かれた。「何もなかったね」「え、何か目的があった訳じゃないんですか?」と言われ「とにかく羅臼ってどんなところか来て見たかったんだよ」と言うと、「でも、スリルがあって面白かったです」と言ってくれた。「先生、次はどこに行くんですか」と言われ、「野付半島だよ」と答えた。
「野付半島っていうのは知床半島と根室半島の間にある砂嘴(さし)だよ。砂嘴とは、岸沿いに流れる海水によって運ばれた土砂が堆積してできた、海上に長く突き出た地形のことなんだ。トドワラといって、トドマツの立ち枯れが有名なんだよ。」「立ち枯れって何ですか。」「かつては立派に葉を茂らせていた樹木か立ったまま枯れているんだよ」「だから立ち枯れって言うんだ」「それが半島のいたるところで見られるんだよ」標津から左に折れると野付半島に至る。「先生、あれですか。」と紫野はいち早くトドワラを見つけたようだ。一本の長い道路の両脇にたくさんの枯れた木が立ち並んでいる。確かに異様な光景だ。群馬県の赤城山の木が酸性雨のために立ち枯れしたのとよく似ている。一体何故こんなことになったのかと考えて見た。立ち枯れする前は立派なトドマツが生えていた訳だから、この辺りは樹木が生息できる環境であった訳だ。それが立ち枯れしてしまうほどの環境の変化とは一体どんなものだったのだろうか。野付半島は徐々に面積が小さくなっているらしい。海面の上昇によるものか、海流によるものかはわからないが、いずれは半島が島になってしまうともいわれている。となるとトドマツが枯れたのは土壌に海水がしみこんできたことによるもと考えるのが妥当だろう。ただ、地球温暖化は平成に入った頃から大きく問題視されるようになったことであり、トドワラはそれよりずっと以前に作られたものなので、やはりトドワラの成因が何なのか知りたいと思った。
野付半島を出て私たちは風蓮湖の横を通って根室半島の突端、納沙布岬に向かった。ここも、何か特別な目的があったわけではないが知床半島と違って、半島の先端部まで車で行けるので、行ってみたくなった。肉眼では見えなかったが海の向こうに歯舞群島があるはず。岬のいたるところに「北方領土」の文字が刻まれていた。相互不可侵条約を破って侵攻してきたソ連がここを返還する日は絶対に来ないだろうと思った。
そんな思いを岬の見晴らし台に残して、納沙布岬をあとにした。
0
あなたにおすすめの小説

わたしの下着 母の私をBBA~と呼ぶことのある息子がまさか...
MisakiNonagase
青春
39才の母・真知子は息子が私の下着を持ち出していることに気づいた。
ネットで同様の事象がないか調べると、案外多いようだ。
さて、真知子は息子を問い詰める? それとも気づかないふりを続けてあげるか?
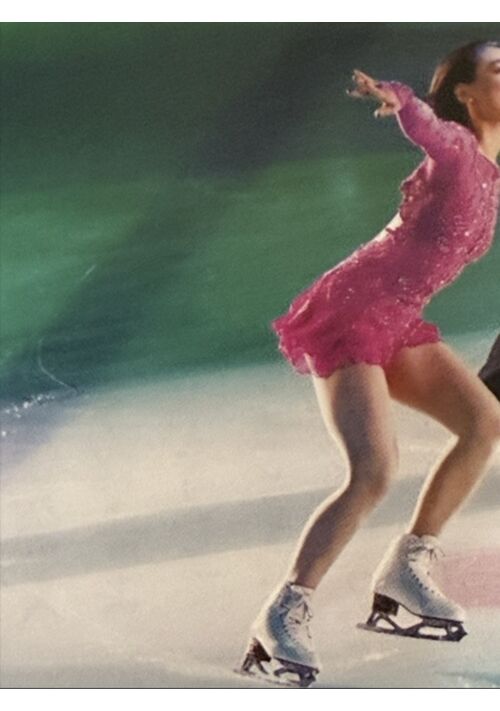
あるフィギュアスケーターの性事情
蔵屋
恋愛
この小説はフィクションです。
しかし、そのようなことが現実にあったかもしれません。
何故ならどんな人間も、悪魔や邪神や悪神に憑依された偽善者なのですから。
この物語は浅岡結衣(16才)とそのコーチ(25才)の恋の物語。
そのコーチの名前は高木文哉(25才)という。
この物語はフィクションです。
実在の人物、団体等とは、一切関係がありません。

ちょっと大人な物語はこちらです
神崎 未緒里
恋愛
本当にあった!?かもしれない
ちょっと大人な短編物語集です。
日常に突然訪れる刺激的な体験。
少し非日常を覗いてみませんか?
あなたにもこんな瞬間が訪れるかもしれませんよ?
※本作品ではGemini PRO、Pixai.artで作成した生成AI画像ならびに
Pixabay並びにUnsplshのロイヤリティフリーの画像を使用しています。
※不定期更新です。
※文章中の人物名・地名・年代・建物名・商品名・設定などはすべて架空のものです。
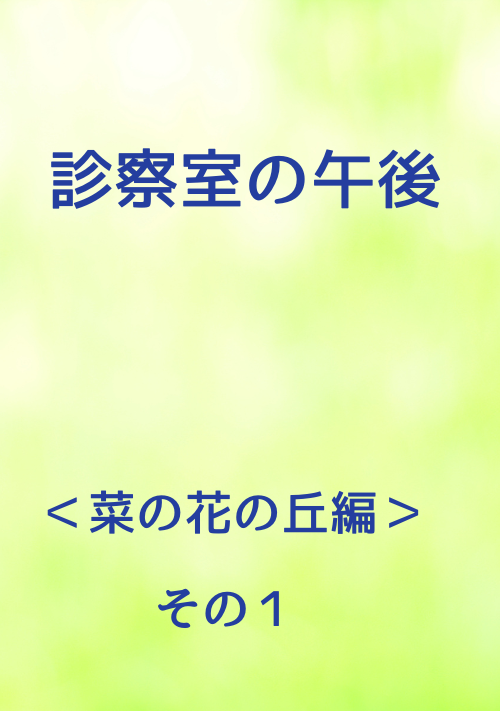
診察室の午後<菜の花の丘編>その1
スピカナ
恋愛
神的イケメン医師・北原春樹と、病弱で天才的なアーティストである妻・莉子。
そして二人を愛してしまったイケメン御曹司・浅田夏輝。
「菜の花クリニック」と「サテライトセンター」を舞台に、三人の愛と日常が描かれます。
時に泣けて、時に笑える――溺愛とBL要素を含む、ほのぼの愛の物語。
多くのスタッフの人生がここで楽しく花開いていきます。
この小説は「医師の兄が溺愛する病弱な義妹を毎日診察する甘~い愛の物語」の1000話以降の続編です。
※医学描写はすべて架空です。
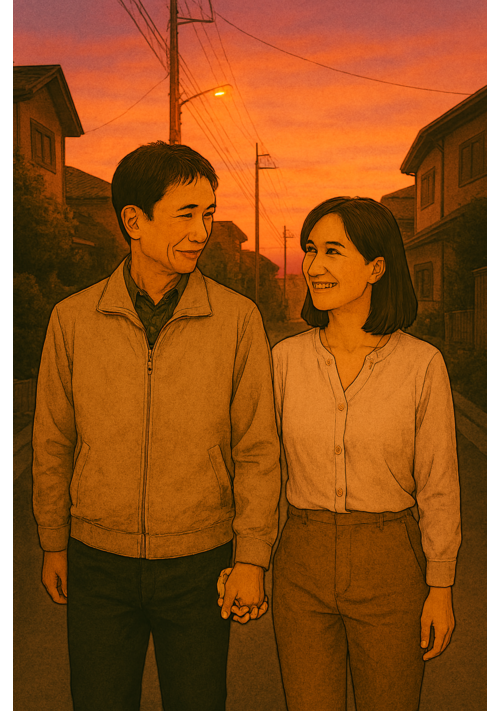

敗戦国の姫は、敵国将軍に掠奪される
clayclay
恋愛
架空の国アルバ国は、ブリタニア国に侵略され、国は壊滅状態となる。
状況を打破するため、アルバ国王は娘のソフィアに、ブリタニア国使者への「接待」を命じたが……。

JKメイドはご主人様のオモチャ 命令ひとつで脱がされて、触られて、好きにされて――
のぞみ
恋愛
「今日から、お前は俺のメイドだ。ベッドの上でもな」
高校二年生の蒼井ひなたは、借金に追われた家族の代わりに、ある大富豪の家で住み込みメイドとして働くことに。
そこは、まるでおとぎ話に出てきそうな大きな洋館。
でも、そこで待っていたのは、同じ高校に通うちょっと有名な男の子――完璧だけど性格が超ドSな御曹司、天城 蓮だった。
昼間は生徒会長、夜は…ご主人様?
しかも、彼の命令はちょっと普通じゃない。
「掃除だけじゃダメだろ? ご主人様の癒しも、メイドの大事な仕事だろ?」
手を握られるたび、耳元で囁かれるたび、心臓がバクバクする。
なのに、ひなたの体はどんどん反応してしまって…。
怒ったり照れたりしながらも、次第に蓮に惹かれていくひなた。
だけど、彼にはまだ知られていない秘密があって――
「…ほんとは、ずっと前から、私…」
ただのメイドなんかじゃ終わりたくない。
恋と欲望が交差する、ちょっぴり危険な主従ラブストーリー。

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















