1 / 6
転生の日、ぐるぐる
しおりを挟む
「さて、帰りますか。しかし、見事に期待を裏切る程の友達甲斐の無さだな。まさか本人を置いて帰るとは」
友人であるA氏はなにを思ったのか、生徒会の仕事をほっぽり出したまま、俺を置いて別の約束とやらを守るために出かけてしまった。去り際に一言。
〝今度メシ奢るから頼むよダイソン。何かどうしても今日じゃないと駄目なんだ〝
ちなみにその用事とはどうも異性がらみの様である。今までとんとそう言った事柄に縁の無かったダイソン事、大村はため息混じりに〝わかった〝と返しただけだった。
高校二年生にもなれば、そんな事は当たり前の様に自分の身の回りで起こる為、ダイソンにとってもいつもの事でもあった。
運動部の居なくなった校庭には、誰が捨てたのか分からないマスクだけが旗のようにフェンスに引っ掛かり旗めいているのが見え、人通りの少ない住宅街に佇む校舎は、広い土地を有する事から、まるで縄張りを主張するジャイ○ンの様にも思えた。
あらかた作業を終えたダイソンは、荷物を纏めると少し手狭になった鞄を脇に抱えたまま、教室の扉を先に借りていた鍵で施錠し職員室に向かおうとしたその時だった。
〝、、、、、、、、マッテ〝
ふと、誰かが自分の歩いてきたはずの廊下から、憂い混じりの呼び止める様なか細い声が何度も聞こえてきた。
振り返る。勿論、誰もいない廊下には西日が差し込み自分が歩かない事で静まり返った空間には静寂だけが残った。
「まさかね。反響か何かかな」
ウォーターハンマー現象の如く、誰かが校舎の何処かで誰か違う人物を呼んでいるのだと思い、聞き違いという結論で自身を納得させると再び歩き出した。
ーーーーーーーしかし、どうにもおかしかった。
歩き始めてから暫くすると声が聞こえ始め、立ち止まり振り向くと何故か声は消えてしまう。この場合、考えられるのはおそらく3つである。
一つ目は、先程の現象を利用して自分をからかっている輩がいて、見えない何処かから隠れて笑いものにしている。
二つ目は、至極簡単な話である。自分の溜め込んだストレスか何かの影響で、脳や耳が錯覚を起こしているのかも知れない。
三つ目は、夏の定番。人ならざるものの仕業で、ダイソンの積み重ねた日頃の徳によりシックスセンスが突然の覚醒を起こし、霊験あらたかな体験をしている。
マジ三つ目だけは勘弁願いたい。自分で対処できる出来事は、自分の理解できる範疇でしか無い。常識を越えた先は常人には理解も納得もしようがない為である。
「よし、やっぱり今回は二つ目で行こう」
誰に語りかけるでもなく、心細さからそう言うと再び歩き出す。声が聞こえ始めるとやがて小走りになり、いつの間にか全速力で廊下を駆け抜け階段を一気に降りたった。
校舎出口の下駄箱が見えた瞬間。突然、体が後ろに引っ張っられ何事かと振り返ると、そこには見知った顔があった。
「大村。誰もいなくても廊下を走っちゃいかんよ」
担任の馬場がそこに居た。馬場は教師の中でも変わり者であったが、不思議と的確な意見を述べる為、エスパー疑惑や心理カウンセラー疑惑もあったが嫌われてはいなかった。
また、ダイソンにとっても先程の不可解な出来事の、たった一人であるという恐怖から逃れられ内心少し安堵を覚えた。
ボサボサ頭のロマンスグレーは、いつものヨレヨレの半袖カッターシャツを着ていた。伸びた細腕に、鍵と鞄が抱えられていた為、馬場も今帰りなのだとわかった。
「スミマセン。先生と俺の他に生徒誰か残ってなかった?それともこれから戸締りですか」
「分かってるならいい。一応、見て回ったが大村の他は誰も居なかったぞ。私の前にも田中先生にも見てもらってるから間違いは無いと思うが」
話を聞くと、二人で一周ずつし2回確認と戸締りを行っている為、他に誰も居ない事は確かだと馬場は言う。
話をしながら校舎から出ると、そのまま戸締りをし、もしかすると教員の田中が残っていたのかも知れないため聞いてみたが、田中はすでに先に帰っているとの事だった。
「生徒会の仕事だから今回は待ったが、次回からはもう少し早く終わらせてくれ、じゃあな気をつけて帰る様に」
馬場は車通勤の為、校舎から少し離れた学校専用の駐車場に向かっていった。ダイソンは一人で恐いと馬場に言えるはずもなく、早く人通りの多い道に小走りに向かった。
一人になると途端に不安が襲って来たが、校舎内とは違い周りに人がいるせいか、他人の話す世間話や生活音でなんとか気を紛らわせる事はできた。
「やっぱ気のせいだよな。まぁ校舎につく幽霊とかなら、もう遭遇することも無いだろうし」
口に出しても変な話であったが、自然と自分が一番最悪だと思うことを信じ込むのはダイソンの人間性であり、人としての性でもある。つまり一番今恐れている事への現実逃避でもある。
急勾配な道の先を登り切ると、今度は足元の悪い下り坂を降りる。悪路と呼ぶ程では無かったが歩きにくい道の為、この場所は人気が無かった。
降りた先にある踏切が閉まってしまった為
、待つ間にスマホを取り出し時間とメールが来ていないか確認することにした。
「特に何もないかな。〝ささやき〝も気になるのは無いし、早く帰って充電しないと」
ささやきの投稿でもして見ようかとも考えてみたが、此処では落ち着かない事とバッテリーの残りが三分の一程になっていたので後回しとする事にし顔を上げたその瞬間だった。
「、、、、、、、、、マッテ」
再びあの声が聞こえ始め、振り返ると住宅街であるにも関わらず、ひと気のない閑散とした景色が広がりふとそれに気がついた。
辺りは誰も居ない。つまり今ここに居るのは自分一人であるのだと言う事実と共に、十分近く鳴り続けている踏切には未だ電車は通らず。サイレンはずっと鳴り止む事はなかった。
何も考えられ無いまま、全身に痺れる様な感覚を覚えると、身体中から汗が噴き出し、体温がドンドン奪われて行くのが解るほど全身は冷え切っていった。
「、、、、、、、、マッテ。ヒキカエセ」
今度は等々、声がはっきりと聞こえた。女性の声で、か細いのかと思われたが、どうやら何か叫んでいる感じであったが此方が聞き取れなかっただけの様である。
動悸まで起こると、段々と立つのもままならず早くなり続ける鼓動を感じながらガードレールに手を付くと世界の異変を目の当たりにする。
「な、、、、、、、、嘘、、、、だろ」
高いマンションの上部が消えていく様にみえたが、消えるというよりも混じると言った方がしっくりとくる様な、空と建物の境界線が揺らぎながら混ざるのが見えた。
頭痛が鳴り止まない。全身は小刻みに震え始め、力が入らないまま自身の血の気が引いていく事がわかった。このままでは死ぬんじゃないかと思い取り出したスマホは、握りしめる事がやっとであった。
やがて地面に膝をついたままのダイソンは、景色が混ざり合いながら酔う様ないびつに歪む世界の中で確かにそれを視認するに至った。
段々と近づいてくる悲鳴と木々の軋む音。それは、今まで見たどの異変や現象よりも、奇異で珍妙で不気味なものであった。
黒い火の玉の様な物体が近づいてきたかと思うと、ダイソンの目の前の線路を悠然かつ優雅に、まるで自身を見せつける様にゆっくりと俺の目の前を通った。
簡単な例えがあるとすれば死神。左半分が壊れた骸骨の様な頭だったが、黒い炎の下には蜘蛛の足を模した様な、何本もの骨が地を這う様に不気味に蠢いていた。
声は出なかった。ただ呼吸をするのにも必死で、此方に振り向かれない様に、必死で喉を押さえながら過呼吸を抑えつけた。しかし、ソレ此方の隣りで立ち止まる様に動きを止めた。
ーーーーーー音を立てては死ぬ。
ーーーーーー呼吸を悟られても死ぬ。
ーーーーーー汗が流れても死ぬ。
ーーーーーー全てを止めなければ死ぬ。
止めろ止めろ止めろ止めろ止めろ止めろ止めろ止めろ止めろ止めろ止めろ止めろ止めろ止めろ止めろ止めろ止めろ止めろ止めろ止めろ止めろ止めろ止めろ止めろ止めろ止めろ止めろ止めろ止めろ止めろ止めろ止めろ止めろ止めろ止めろ止めろ止めろ止めろ止めろ止めろ止めろ止めろ止めろ止めろ止めろ!!!!!!
人間としての機能を全て止めてでも、アレをやり過ごさねば死ぬ事よりも恐ろしい事態になってしまうと、人としての警鐘音が全身から鳴り響き続けていた。
死んだ様に息継ぎも出来ないまま、このまま一生この場所から動けないのではないのかと思う程に、自身も世界も進む事を失ってしまったように感じた。
しかし、不気味なソレは首を動かす事もなくゆっくりと再び進み出した。何処まで離れても呼吸をする事が出来ない。
恐怖と怪異の塊ような化け物が見えなくなり、ようやく抑えていた呼吸を再開させると、胸が裂ける寸前まで息を吸い込みようやく生き残れたのだと錯覚した。
そう、錯覚に過ぎない。何故ならあの化け物が通り過ぎた後には、絵の具を混ぜたような景色が広がりそれは段々と弧を描くと渦状に変化を遂げた。
もう、逃げる事も逃げる場所もなくダイソンはそれをただ茫然自失のまま眺める他できることなど無かった。
ーーーーーーそうして俺は世界に溶けたまま入り混じる事となった。
友人であるA氏はなにを思ったのか、生徒会の仕事をほっぽり出したまま、俺を置いて別の約束とやらを守るために出かけてしまった。去り際に一言。
〝今度メシ奢るから頼むよダイソン。何かどうしても今日じゃないと駄目なんだ〝
ちなみにその用事とはどうも異性がらみの様である。今までとんとそう言った事柄に縁の無かったダイソン事、大村はため息混じりに〝わかった〝と返しただけだった。
高校二年生にもなれば、そんな事は当たり前の様に自分の身の回りで起こる為、ダイソンにとってもいつもの事でもあった。
運動部の居なくなった校庭には、誰が捨てたのか分からないマスクだけが旗のようにフェンスに引っ掛かり旗めいているのが見え、人通りの少ない住宅街に佇む校舎は、広い土地を有する事から、まるで縄張りを主張するジャイ○ンの様にも思えた。
あらかた作業を終えたダイソンは、荷物を纏めると少し手狭になった鞄を脇に抱えたまま、教室の扉を先に借りていた鍵で施錠し職員室に向かおうとしたその時だった。
〝、、、、、、、、マッテ〝
ふと、誰かが自分の歩いてきたはずの廊下から、憂い混じりの呼び止める様なか細い声が何度も聞こえてきた。
振り返る。勿論、誰もいない廊下には西日が差し込み自分が歩かない事で静まり返った空間には静寂だけが残った。
「まさかね。反響か何かかな」
ウォーターハンマー現象の如く、誰かが校舎の何処かで誰か違う人物を呼んでいるのだと思い、聞き違いという結論で自身を納得させると再び歩き出した。
ーーーーーーーしかし、どうにもおかしかった。
歩き始めてから暫くすると声が聞こえ始め、立ち止まり振り向くと何故か声は消えてしまう。この場合、考えられるのはおそらく3つである。
一つ目は、先程の現象を利用して自分をからかっている輩がいて、見えない何処かから隠れて笑いものにしている。
二つ目は、至極簡単な話である。自分の溜め込んだストレスか何かの影響で、脳や耳が錯覚を起こしているのかも知れない。
三つ目は、夏の定番。人ならざるものの仕業で、ダイソンの積み重ねた日頃の徳によりシックスセンスが突然の覚醒を起こし、霊験あらたかな体験をしている。
マジ三つ目だけは勘弁願いたい。自分で対処できる出来事は、自分の理解できる範疇でしか無い。常識を越えた先は常人には理解も納得もしようがない為である。
「よし、やっぱり今回は二つ目で行こう」
誰に語りかけるでもなく、心細さからそう言うと再び歩き出す。声が聞こえ始めるとやがて小走りになり、いつの間にか全速力で廊下を駆け抜け階段を一気に降りたった。
校舎出口の下駄箱が見えた瞬間。突然、体が後ろに引っ張っられ何事かと振り返ると、そこには見知った顔があった。
「大村。誰もいなくても廊下を走っちゃいかんよ」
担任の馬場がそこに居た。馬場は教師の中でも変わり者であったが、不思議と的確な意見を述べる為、エスパー疑惑や心理カウンセラー疑惑もあったが嫌われてはいなかった。
また、ダイソンにとっても先程の不可解な出来事の、たった一人であるという恐怖から逃れられ内心少し安堵を覚えた。
ボサボサ頭のロマンスグレーは、いつものヨレヨレの半袖カッターシャツを着ていた。伸びた細腕に、鍵と鞄が抱えられていた為、馬場も今帰りなのだとわかった。
「スミマセン。先生と俺の他に生徒誰か残ってなかった?それともこれから戸締りですか」
「分かってるならいい。一応、見て回ったが大村の他は誰も居なかったぞ。私の前にも田中先生にも見てもらってるから間違いは無いと思うが」
話を聞くと、二人で一周ずつし2回確認と戸締りを行っている為、他に誰も居ない事は確かだと馬場は言う。
話をしながら校舎から出ると、そのまま戸締りをし、もしかすると教員の田中が残っていたのかも知れないため聞いてみたが、田中はすでに先に帰っているとの事だった。
「生徒会の仕事だから今回は待ったが、次回からはもう少し早く終わらせてくれ、じゃあな気をつけて帰る様に」
馬場は車通勤の為、校舎から少し離れた学校専用の駐車場に向かっていった。ダイソンは一人で恐いと馬場に言えるはずもなく、早く人通りの多い道に小走りに向かった。
一人になると途端に不安が襲って来たが、校舎内とは違い周りに人がいるせいか、他人の話す世間話や生活音でなんとか気を紛らわせる事はできた。
「やっぱ気のせいだよな。まぁ校舎につく幽霊とかなら、もう遭遇することも無いだろうし」
口に出しても変な話であったが、自然と自分が一番最悪だと思うことを信じ込むのはダイソンの人間性であり、人としての性でもある。つまり一番今恐れている事への現実逃避でもある。
急勾配な道の先を登り切ると、今度は足元の悪い下り坂を降りる。悪路と呼ぶ程では無かったが歩きにくい道の為、この場所は人気が無かった。
降りた先にある踏切が閉まってしまった為
、待つ間にスマホを取り出し時間とメールが来ていないか確認することにした。
「特に何もないかな。〝ささやき〝も気になるのは無いし、早く帰って充電しないと」
ささやきの投稿でもして見ようかとも考えてみたが、此処では落ち着かない事とバッテリーの残りが三分の一程になっていたので後回しとする事にし顔を上げたその瞬間だった。
「、、、、、、、、、マッテ」
再びあの声が聞こえ始め、振り返ると住宅街であるにも関わらず、ひと気のない閑散とした景色が広がりふとそれに気がついた。
辺りは誰も居ない。つまり今ここに居るのは自分一人であるのだと言う事実と共に、十分近く鳴り続けている踏切には未だ電車は通らず。サイレンはずっと鳴り止む事はなかった。
何も考えられ無いまま、全身に痺れる様な感覚を覚えると、身体中から汗が噴き出し、体温がドンドン奪われて行くのが解るほど全身は冷え切っていった。
「、、、、、、、、マッテ。ヒキカエセ」
今度は等々、声がはっきりと聞こえた。女性の声で、か細いのかと思われたが、どうやら何か叫んでいる感じであったが此方が聞き取れなかっただけの様である。
動悸まで起こると、段々と立つのもままならず早くなり続ける鼓動を感じながらガードレールに手を付くと世界の異変を目の当たりにする。
「な、、、、、、、、嘘、、、、だろ」
高いマンションの上部が消えていく様にみえたが、消えるというよりも混じると言った方がしっくりとくる様な、空と建物の境界線が揺らぎながら混ざるのが見えた。
頭痛が鳴り止まない。全身は小刻みに震え始め、力が入らないまま自身の血の気が引いていく事がわかった。このままでは死ぬんじゃないかと思い取り出したスマホは、握りしめる事がやっとであった。
やがて地面に膝をついたままのダイソンは、景色が混ざり合いながら酔う様ないびつに歪む世界の中で確かにそれを視認するに至った。
段々と近づいてくる悲鳴と木々の軋む音。それは、今まで見たどの異変や現象よりも、奇異で珍妙で不気味なものであった。
黒い火の玉の様な物体が近づいてきたかと思うと、ダイソンの目の前の線路を悠然かつ優雅に、まるで自身を見せつける様にゆっくりと俺の目の前を通った。
簡単な例えがあるとすれば死神。左半分が壊れた骸骨の様な頭だったが、黒い炎の下には蜘蛛の足を模した様な、何本もの骨が地を這う様に不気味に蠢いていた。
声は出なかった。ただ呼吸をするのにも必死で、此方に振り向かれない様に、必死で喉を押さえながら過呼吸を抑えつけた。しかし、ソレ此方の隣りで立ち止まる様に動きを止めた。
ーーーーーー音を立てては死ぬ。
ーーーーーー呼吸を悟られても死ぬ。
ーーーーーー汗が流れても死ぬ。
ーーーーーー全てを止めなければ死ぬ。
止めろ止めろ止めろ止めろ止めろ止めろ止めろ止めろ止めろ止めろ止めろ止めろ止めろ止めろ止めろ止めろ止めろ止めろ止めろ止めろ止めろ止めろ止めろ止めろ止めろ止めろ止めろ止めろ止めろ止めろ止めろ止めろ止めろ止めろ止めろ止めろ止めろ止めろ止めろ止めろ止めろ止めろ止めろ止めろ止めろ!!!!!!
人間としての機能を全て止めてでも、アレをやり過ごさねば死ぬ事よりも恐ろしい事態になってしまうと、人としての警鐘音が全身から鳴り響き続けていた。
死んだ様に息継ぎも出来ないまま、このまま一生この場所から動けないのではないのかと思う程に、自身も世界も進む事を失ってしまったように感じた。
しかし、不気味なソレは首を動かす事もなくゆっくりと再び進み出した。何処まで離れても呼吸をする事が出来ない。
恐怖と怪異の塊ような化け物が見えなくなり、ようやく抑えていた呼吸を再開させると、胸が裂ける寸前まで息を吸い込みようやく生き残れたのだと錯覚した。
そう、錯覚に過ぎない。何故ならあの化け物が通り過ぎた後には、絵の具を混ぜたような景色が広がりそれは段々と弧を描くと渦状に変化を遂げた。
もう、逃げる事も逃げる場所もなくダイソンはそれをただ茫然自失のまま眺める他できることなど無かった。
ーーーーーーそうして俺は世界に溶けたまま入り混じる事となった。
0
あなたにおすすめの小説


敵に貞操を奪われて癒しの力を失うはずだった聖女ですが、なぜか前より漲っています
藤谷 要
恋愛
サルサン国の聖女たちは、隣国に征服される際に自国の王の命で殺されそうになった。ところが、侵略軍将帥のマトルヘル侯爵に助けられた。それから聖女たちは侵略国に仕えるようになったが、一か月後に筆頭聖女だったルミネラは命の恩人の侯爵へ嫁ぐように国王から命じられる。
結婚披露宴では、陛下に側妃として嫁いだ旧サルサン国王女が出席していたが、彼女は侯爵に腕を絡めて「陛下の手がつかなかったら一年後に妻にしてほしい」と頼んでいた。しかも、侯爵はその手を振り払いもしない。
聖女は愛のない交わりで神の加護を失うとされているので、当然白い結婚だと思っていたが、初夜に侯爵のメイアスから体の関係を迫られる。彼は命の恩人だったので、ルミネラはそのまま彼を受け入れた。
侯爵がかつての恋人に似ていたとはいえ、侯爵と孤児だった彼は全く別人。愛のない交わりだったので、当然力を失うと思っていたが、なぜか以前よりも力が漲っていた。
※全11話 2万字程度の話です。


奪われ系令嬢になるのはごめんなので逃げて幸せになるぞ!
よもぎ
ファンタジー
とある伯爵家の令嬢アリサは転生者である。薄々察していたヤバい未来が現実になる前に逃げおおせ、好き勝手生きる決意をキメていた彼女は家を追放されても想定通りという顔で旅立つのだった。

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

召喚失敗!?いや、私聖女みたいなんですけど・・・まぁいっか。
SaToo
ファンタジー
聖女を召喚しておいてお前は聖女じゃないって、それはなくない?
その魔道具、私の力量りきれてないよ?まぁ聖女じゃないっていうならそれでもいいけど。
ってなんで地下牢に閉じ込められてるんだろ…。
せっかく異世界に来たんだから、世界中を旅したいよ。
こんなところさっさと抜け出して、旅に出ますか。

妹の初恋は私の婚約者
あんど もあ
ファンタジー
卒業パーティーで、第一王子から婚約破棄を宣言されたカミーユ。王子が選んだのは、カミーユの妹ジョフロアだった。だが、ジョフロアには王子との婚約が許されない秘密があった。
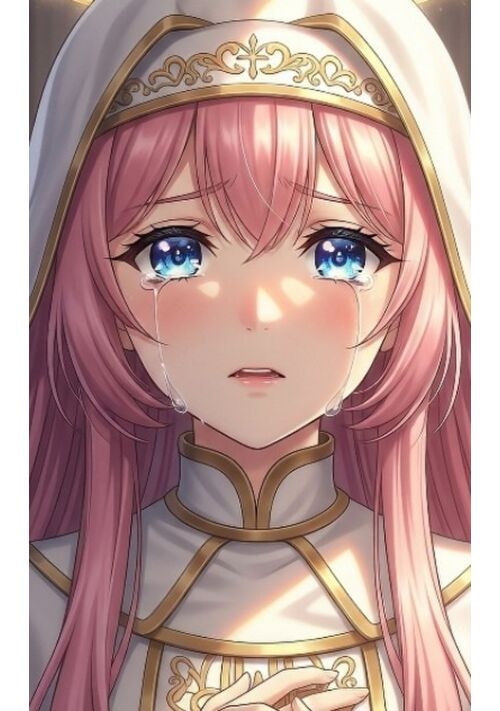
聖女は聞いてしまった
夕景あき
ファンタジー
「道具に心は不要だ」
父である国王に、そう言われて育った聖女。
彼女の周囲には、彼女を心を持つ人間として扱う人は、ほとんどいなくなっていた。
聖女自身も、自分の心の動きを無視して、聖女という治癒道具になりきり何も考えず、言われた事をただやり、ただ生きているだけの日々を過ごしていた。
そんな日々が10年過ぎた後、勇者と賢者と魔法使いと共に聖女は魔王討伐の旅に出ることになる。
旅の中で心をとり戻し、勇者に恋をする聖女。
しかし、勇者の本音を聞いてしまった聖女は絶望するのだった·····。
ネガティブ思考系聖女の恋愛ストーリー!
※ハッピーエンドなので、安心してお読みください!
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















