169 / 215
第4章 国主編
第151話 ヌヴェール女伯の決断 ~アニェスの結婚~
しおりを挟む
ラテン帝国皇帝ピエール・ド・クルトネーの娘で、ヌヴェール女伯のマティルド・ド・ヌヴェール(マティルドⅠ世)は苦悩していた。
隣国のブルゴーニュ公国の紛争の結果、同国は神聖帝国のロートリンゲン公が共同統治者となり、事実上、ロートリンゲン公国の支配下に入った。
破竹の勢いで支配領域を広げているロートリンゲン公の次のターゲットは我がヌヴェール伯領なのではないか?
共同統治者で夫のエルヴェ・ド・ドンジー(エルヴェⅣ世)はブーヴィーヌの戦いにおいてイングランド王ジョン側として戦い、フランス王フィリップⅡ世の不興を買っていた。後にジョンの仲介により許しを得たもののフランス王家との関係はギクシャクしている。
したがって、フランス王ルイⅨ世と摂政ブランシュに後ろ盾になってもらうことは難しい。加えて、ブランシュはロートリンゲン公と不謹慎な関係にあるとさえ噂されているのだ。
一方で、夫のエルヴェⅣ世はまもなく50歳をむかえ、老害の兆候も見えていて、全く頼りにならない。
子息は、まもなく20歳となる娘のアニェスただ1人だけだった。
このまま何も手を打たずに座していてはロートリンゲン公にヌヴェール伯領は奪われてしまうのではないか?
それにしてもブルゴーニュ女公のアリックスは上手くやった。
好色と評判のロートリンゲン公に我が身を捧げることで、国が滅びることを回避したのだ。滅びさえしなければ子孫の代で挽回することはいくらでもできる。
その前のブローニュ女伯もそうだ。
彼女は少数の護衛のみでロートリンゲンに乗り込み、ロートリンゲン公に共同統治者となることを飲ませたという。これも並大抵のことではない。
マティルドはエルヴェⅣ世の考えを確かめることにした。
「あなた。ロートリンゲン公についてどう思いますの」
「所詮はまだ20代の小僧だろう。なにを恐れることがある?」
「でもロートリンゲン公はいまだ負け知らずですのよ。しかも、暗黒騎士団には闇の者までいるというではないですか。それが攻めてきたらと思うと恐ろしくて…」
「わしもブーヴィーヌでは負けたが、アルビジョア十字軍ではかなりの戦功をあげたつもりだ。フランス王とて、蚕食されるのを黙ってみていることはないだろう」
「しかし、フランドル候国の時も、ブルゴーニュ公国の時も王は動かなかったではないですか?」
「やつらは事実上独立して勝手をやっておったのだ。見捨てられても自業自得というものだ。我が国にはアルビジョア十字軍での軍功がある」
──ベジエで住民を虐殺したことを軍功と言うの?
それでブーヴィーヌのときの裏切りを払拭できるわけがない。
「プロヴァンスでは暗黒騎士団とは戦いませんでしたの?」
「あの時は後詰めだったからなあ。出番はなかった。摂政のブランシュも所詮は女。闇の者の姿を見て恐れをなしたのだろう」
──やっぱり信用されていないんじゃない!
ダメだ。戦ったこともないのに相手を軽んじるこの根拠のない自信…
昔から自信家ではあったが、老害でそれがひどくなっている…
いちおう言うだけ言ってみるか…
「私たちももう歳が歳でしょう。そろそろ引退したらどうかと思うのよ」
「何を言っておる。わしは日々体を鍛えておる。若い者にはまだ負けはせぬ」
「でもアニェスももういい歳だし、しっかりした婿を見つけて国を継がせないと…」
「婿は婿で探せばよい。わしはまだ領主の座は降りないぞ」
──やはりダメか…
「では、婿探しは私に任せていただけますか?」
「そういう面倒なことはおまえに任せる。ラテン帝国でもどこからでも引っ張ってくるがよかろう」
「承知しましたわ」
◆
マティルドはアニェスがどう思っているかも確認したいと思い、彼女の部屋に向かった。
「お母さま。どうされましたの。お母さまの方からいらっしゃるなんて…」
「おなたももう歳が歳でしょう。薹が立つ前にお婿さんを探さないとと思って…
誰かいい人はいないの?」
「おりませんわ…というか、お母さま。回りくどい言い方はやめてください。
私にロートリンゲン公の嫁になれとおっしゃりたいのでしょう?」
マティルドは感心した。我が子ながら何と察しのいい…
「なぜそう思うの?」
「そんなこと、我が国のことを思えばすぐにわかることではありませんか」
「そうね…でも、あなたの気持ちを踏みにじってまでとは考えていないの。あなたの気持ちはどうなの?
ロートリンゲン公はあまたの側室や愛妾を抱える好色な人物だと聞くけれど…」
「数が多くとも側室や愛妾の一人一人が幸福に暮らせていれば問題はないと思うのです。要は男の甲斐性の問題です」
「あら。意外ね。もっと嫌がられると思っていたのだけれど…」
「残念ながら、私が今思いを寄せている人はいません…ですからロートリンゲン公に嫁入りすることもやぶさかではないのですが…」
「それで…どうしたの?」
「お返事をする前にナンツィヒの町に行ってみたいのです」
「ナンツィヒの町に? それはどうして?」
「ナンツィヒの町は今や素晴らしい町に発展していると聞きます。私が来ているヴィオラのブランドの服を始めとして素晴らしいものがたくさんあると…そこに行ってみたら町を作ったロートリンゲン公の人となりがわかるよう気がするのです」
「そうね。公式に訪問したら相手も表面を取り繕うだろうし、私的に訪問するのも面白いかもしれないわね」
「では、お母さま…」
「いいわ。いってらっしゃい。そしてあなたの目で確かめてくるのです」
「お母さま。ありがとうございます」
◆
タンバヤ商会情報部のベルント・バウムガルテンがフリードリヒの執務室を訪れた。
「申し上げます」
「何だ。ベルント」
「ヌヴェール伯国のアニェス姫が私的にナンツィヒの町を訪問するとの情報が入りました」
「ほう…面白いな。だが、あくまでも私的にということなのだな?」
「左様にございます」
「では、好きなようにやらせてやろう。だが、万が一のことがあっては困る。最低限の警備は付けよう。そうだな…マグダレーネを呼べ」
マグダレーネことアスタロトは、フリードリヒを警備する親衛隊を率いる高位の女悪魔である。
フリードリヒは、アスタロトにアニェス姫の警護に、彼女の配下の女悪魔を10人ほど隠形して張り付かせるよう命じた。
◆
1週間後。
ナンツィヒの町にアニェスの姿があった。侍女が1人と警備のための従者5人を引き連れている。
途中、盗賊に襲われるなどのトラブルが一切ない順調な旅だった。
「フリードリヒ道路というのは素晴らしいわね。馬車の旅があんなに快適なんて初めての経験だわ」
この時代の道路は一般的に舗装状態が極めて悪く、馬車で走ると揺れが酷いため、貴婦人などを除き、馬車ではなく、徒歩で旅をするのが常識だった。
従者の一人が答える。
「あれほどきちんと舗装された道路は他に例をみません。ロートリンゲン公というのはよほど潤沢な資金をおもちなのですな」
「そうね」
途中の道路からしてこうなのだ、町本体はどれだけ凄いのだろうと期待が膨らんだ。
アニェスは、まずその街並みに目を見張った。
特に新街区は大都市にありがちな無秩序な開発がされておらず、整然と整備された道路に面して意匠統一された建物が整然と並んでいる。
街区は商業地区、工業地区、居住地区と用途別に区分され、それぞれに適した環境が整備されている。
特にナンツィヒの鉄工業は有名で、良質な鉄をリーズナブルな価格で提供することで有名だ。
商業地区も立派で、活気に満ち満ちていた。
様々な国の商人が出入りしており、多様な言語が飛び交っている。少数だがイスラム商人までいるではないか。
しかも周りのドイツ人はその存在を当たり前のように受け入れている。
外国製と思われる見たこともない物やタンバヤ商会で開発されたという新製品が飛ぶように売れている。
──なんと活気のある国なのだ…
アニェスを驚かせたのが亜人たちの存在だ。
相当数の亜人が明るい表情で胸を張って町をいきかっている。
身なりからして明らかに奴隷ではないし、人族がこれを差別する様子もみられない。
その時。前方から異形の闇の者が複数こちらにやってくる。
警備の従者たちは抜剣して、警戒した。
「姫様。お下がりください」
始めてみる闇の者にアニェスは恐怖した。
心臓は早鐘を打ち、冷や汗がにじみ出ている。
しかし、その闇の者たちはこちらを一瞥もせずに通り過ぎてしまった。
極限まで緊張していた従者たちは、拍子抜けしてしまい、大きなため息をつくと、その場に座り込んでしまう。
そこに女性から声をかけられた。
経済産業卿ゴットハルトの妻ベリンダである。
「あなたたちお上りさんっすね」
「『おのぼりさん』?」
「ああ。ナンツィヒの町では田舎からナンツィヒの町に出てきたばかりの者を『お上りさん』って言うんすよ」
「そうなんですか。私たちは今日ヌヴェール伯領から着いたばかりなんです。そういう意味では、お上りさんですね」
「さっき『姫』って聞こえたっすけど…」
「私的な訪問なので、それはどうかご内密に…
ところで、あの闇の者はいったい何なのですか? 白昼堂々闇の者が跋扈しているなんて…」
「ああ。さっきのダークナイトのことっすか?」
「あれはダークナイトというのですか?」
「ええ。あれは町を巡回警備してるんっすよ。あなたたちも町で騒ぎを起こしたらダークナイトにやられるから気をつけた方がいいっすよ」
「しかし、闇の者が警備なんて…」
「はっはっはっはっ。本当に何も知らないんすね。
闇の者は上の者…つまり大公閣下の命令に絶対服従っすから、何もしないのに向こうから攻撃してくることはないんすよ。町の者も誰も怖がっていなかったでしょ」
「そう…なのですか…」
アニェスは未だに信じられないという表情をしている。
「ところで、今日はどこか目的地でも…」
「いえ。これといって…そうだ、ヴィオラの服が欲しいです」
「そういえば今着てる服もヴィオラっすね」
「わかります? セクシーなのに上品さもあって、私大ファンなんです」
「ヴィオラの店なら良く知ってるっすから案内しますよ」
「そんな…お手間を取らせていいんですか」
「ちょうどあたしも買いたいものがあるし、ついでっすよ」
「それならお願いいたします」
◆
そしてヴィオラの店に着くと…
「ここがヴィオラの店…」
アニェスの目は憧れのあまりキラキラしている。
早速好みの服を夢中で物色するアニェス…
「えっ。この上等な服がこの値段!」
「ああ。ここはヴィオラの直営店っすから、中間マージンが入らない分安いんすよ。これがヴィオラ本来の値段っす」
「ヌヴェール伯領ではとてもこの値段では買えないわ」
「ヌヴェール伯領で売るには間に商人が入るっすから、その取り分だけ値段が上がるっす」
「なるほど。では、ヌヴェール伯領にヴィオラの直営店ができれば安く買える訳ですね」
「へーっ。なかなか鋭いっすね。それはそのとおりっすけど、それができるかどうかは大公閣下と交渉っすね」
「そこでなぜ大公閣下が出てくるのですか?」
「ヴィオラはタンバヤ商会の直営ブランドなんすよ」
「ですからなぜ?」
「タンバヤ商会の会長は大公閣下っすから。それにヴィオラの服は全て正妻のヴィオランテ様の監修っすからね」
「えっ。そうなのですか!」
「ほんとに何にも知らないんっすね」
「ええ。帝国内の事情には疎くって…」
結局、アニェスとベリンダ、それにアニェスの侍女の3人はヴィオラの服から化粧道具の類まで買い漁り、気がつけば夕刻となっていた。
店を出てみるとアニェスの従者が座り込んで居眠りをしていたので、それをベリンダが叩き起こした。
「まあ、もうこんな時間だわ」
「夕食や宿の手配はしてるっすか?」
「いえ。ぜんぜん…どうしましょう…」
「なら、今夜、身内の夕食会があるから招待するっすよ」
「でも、身内の会なのでしょう。悪いわ」
「いやあ。そんなこと気にする人はいないから、大丈夫っす」
「それなら甘えさせてもらおうかしら」
「それがいいっす」
荷物は全て従者に持たせたので、女性軍は手ぶらである。
それをいいことに、ベリンダはスタスタと早足で歩いていく。
するとナンツィヒの城に到着した。
「あのう。ここって…」
「見てのとおり、ナンツィヒのお城っすよ」
「夕食会というのはここで?」
「もちろんっす」
アニェスの頬を冷や汗が伝った。
「失礼ながら、あなたのお名前をまだ聞いていませんでしたわ。あなた何者ですの?」
「あたしはベリンダ。旦那はロートリンゲン公国の経済産業担当宮中伯をやってるっす」
「まあ。そうでしたのね」
「どうするっす。怖気づいたのなら止めておきますか?」
気がついたら敵本陣の真っただ中という状況に戸惑うアニェスだったが、本来の目的はロートリンゲン公の人となりを確かめることだ。そういう意味では千載一遇の好機ではないか。
「いえ。出席させていただきます」
「それがいいっす」
◆
会場についてみると、出席者の多数を女性が占めていた。
皆、夜会用のドレスを着ているではないか。
ベリンダに案内してもらって、慌てて着替える。
ちょうど今日ヴィオラの夜会服を買っておいたのが役に立った。
アニェスはベリンダに聞いてみた。
「女性が多いわね」
「あたしみたいに宮中伯の家族もいるっすけど、半分くらいは大公閣下の側室と愛妾っすね」
──そんな…多いとは聞いていたけれど…
「こんなに多くては…その…あぶれてしまう人もいるのでは?」
「いやあ。詳しくは知らないっすけど、ローテーションを組んで平等にしてるみたいっす」
「それだといつまでも順番が回ってこないのでは?」
「それが不思議なところで、からくりはわからないっすけど、週1回くらいは回ってくるらしいっす」
──それならまあ普通だわ。しかし、この人数をどうやって…?
考え込んでしまうアニェス…
その時、声の大きな女性が声をかけてきた。人狼のヴェロニアである。
「見ない顔だな。まさか新入りかよ」
「いえ…私は…その…」
ヴェロニアの迫力に気圧されるアニェス…
ベリンダが助け舟を出す。
「ヴェロニアさん。脅かさないでやってくださいよ。彼女はヌヴェール伯領の姫様っす」
「初めまして。アニェス・ド・ヌヴェールにございます。どうぞよろしくお願いいたします」
「あたいはヴェロニアだ。旦那の愛妾をやってる。
おめえ、まさか旦那の側室になろうってんじゃねえだろうな?」
「いえ。今日はベリンダさんに招待されまして…」
「ならいいけどよう」
と言うとヴェロニアは去っていった。
「あんなお下品な方が愛妾なのですか?」
「ああ。ヴェロニアさんは閣下が冒険者時代からの古株っす。ハルバードを使わせたら右に出る者はいないっすよ」
「えっ。それって、まさか魔獣を倒せないと愛妾になれないとか…」
「さすがに、それはないっすよ」
──ああ。良かった…
冷静になって見渡してみると、ライバル関係にあるはずの側室・愛妾どうしがにこやかに談笑しているようだ。
「皆さん仲がよろしいのですね?」
「確かに。国王や貴族の側室・愛妾どうしがこんなに仲良しなんて聞かないっすね。これも閣下の人徳のたまものっすよ」
「ところで、大公閣下はどちらに?」
「は? あそこの上座に座っているのが大公閣下っすよ」
そう言われ、見てみるとアニェスと同年輩に見える若い男が据わっている。
それを見て、アニェスは目を見張った。
「えっ。あの方が!?」
──噂には聞いていたけれど、なんて見目麗しい男性なのだろう。
確か歳は25歳と聞いていたはずだが、どう見ても20歳前後にしかみえない。
観察してみると、大公のところには入れ替わり立ち替わりに女性が訪れ、話しかけているが、大公は軽く相槌を打つばかりで、たまにボソッと話すばかりだ。
だが、その一言が女性たちにはこの上もなく嬉しいらしく、満面の笑みを浮かべている。
──あまり話好きな方ではいらっしゃらないのね…
確かにおしゃべりな男など詐欺師のようで信用ならない。
男はどっしりと構えてもらって、いざという時に頼りになればそれでいいのだ。
アニェスは男性に対し、そういう古風な感覚を持っていた。
しばらくすると、大公と会話しようという女性の列が途切れ、大公はアニェスの方を振り向き、目があってしまった。
それだけで顔が赤らんでしまうアニェス。
しかも、大公は席を立ってこちらに向かってくるではないか。
大公が近づいてくるにつれ緊張が高まる。
フリードリヒは挨拶をする。
「ヌヴェール伯領のアニェス姫ですね。初めまして。ロートリンゲン大公のフリードリヒ・エルデ・フォン・ザクセンです。以後、良しなにお願いいたします」
「ア、アニェス・ド・ヌヴェールにございます。た、大公閣下におかれましてはご機嫌麗しゅう」
「お嬢さん。そんなに緊張しないでください。今日の夜会はあくまでも私的な会合ですから、お気を使われる必要はありません」
「そう言っていただけると、助かります」
「ところでお嬢さん。これからダンスが始まるのですが、お付き合いいただけますか?」
「私…ダンスなど踊ったことがなくって…」
「大丈夫ですよ。簡単な踊りですから。直ぐに覚えられます」
「そうですか。では、やってみます」
「感謝いたします」
フリードリヒが楽隊に合図を出すと、音楽が始まった。
出席者たちは、慣れているので早速踊り出した。
踊りは基本的に男女ペアで踊るのだが、人数が不均等なので女性同士のペアも多い。美貌の女性どうしがペアでダンスを踊る姿は、それはそれで百合っぽい。
この時代はまだオーケストラなどの本格的な楽団やワルツのような洗練された踊りはない。
あくまでもフォークダンスに毛が生えたような素朴な踊りだった。
だが、この時代男女がペアを組んで手をつなぎあうだけでも十分に煽情的だったのだ。
「さあ。私たちも踊りましょう」とフリードリヒはアニェスに声をかける。
アニェスは恥ずかしくて顔を赤らめながらも手を差し出した。
アニェスは周りのカップルの見様見真似で必死に踊る。
踊り自体は単純なものだったのですぐに覚えることができた。
「そうそう。若いだけあって覚えがはやいじゃないですか」
「いえ。そんなことは…」
緊張と恥ずかしさで手が汗ばんできた。
だが、フリードリヒが嫌がる様子はない。
アニェスはままよと開き直り、この際踊りを楽しむことにした。
姫であるアニェスは、若い男と手を握るなどという機会はこれまで皆無である。恥ずかしいと思いつつも、誰憚りなく手を握りあえる機会を貴重だと思った。
フリードリヒもずっとアニェスとばかり踊っている訳にもいかない。
フリードリヒもアニェスもパートナーを入れ替えた。
今度のパートナーも若くてハンサムな男だったが、フリードリヒのときのようにはときめかなかった。
そして夜会は終わり。
アニェス一行は用意されていた城の寝室に案内された。
だが、アニェスはなかなか寝付けなかった。
あまりに刺激的な一日だった。
いろいろなことが頭を駆け巡る。
ことにフリードリヒの姿が頭を離れない。
──もしかして、私、恋しちゃったのかな…
◆
私的な夜会といっても、そう毎晩開かれるものではなく、アニェスはフリードリヒとはそれきりとなった。
フリードリヒの方も、あくまでも私的な訪問ということで、過剰な接待を控えたのである。
アニェス一行は、それからナンツィヒの町を何日か見分してヌヴェール伯領に戻った。
◆
アニェスは、ヌヴェール伯領に戻ると一連の体験をマティルドに報告した。
「まさか、大公ご本人にお会いするとはね」
「偶然そうなっただけです」
「それにしても、それは神の采配としか言いようがないわ。
それで肝心のあなたの気持ちはどうなの?」
「それが…恋をしてしまったかもしれません」
「かもしれないとは、頼りないわね」
「自分でも心の整理がつかなくて…よくわからないのです。
ただ、寝ても覚めてもロートリンゲン公のことが頭を離れないのは本当です」
「バカね。それは恋以外の何ものでもないわ」
「そう…なのですか…」
アニェスは、今まで気になる男性は何人かいたものの、ここまで心を寄せることは初めての体験だった。
そうなのか…これが恋…
アニェスは目から鱗が落ちる思いがした。
◆
マティルドとアニェスは早速このことをエルヴェⅣ世に報告した。
しかし、結果は惨憺たるものだった。
「よりによって我が領土を狙っているロートリンゲン公に領地を差し出すと言うのか。あり得ん。わしの目が黒いうちは絶対に認めんからな」
「しかし、あなた。アニェスの気持ちもお考えになって」
「やつはアニェスの純真な心につけ込んでいるだけだ。美味いところだけ持っていって、アニェスは冷たく遇されるに決まっておる」
アニェスは意気消沈し、懊悩した。
マティルドはそんなアニェスを見るたびに心を痛めた。
しかし、それから半年ほど経ったとき、事態は急変した。
エルヴェⅣ世が急死したのである。
公式発表は病死ということだったが、彼の死体は見るも無残に腫れ上がっており、これはカンタレラにより毒殺された特徴と酷似していた。
人々は毒殺であると噂したが、真相を究明されることはなく、闇の中に葬られた。
少なくともフリードリヒは何の指示も出していないので、おそらくは国を思ったマティルドが断腸の思いで実行したのだと思料されたが、フリードリヒはあえて追及しなかった。
そしてエルヴェⅣ世の死に係る喪が明けた時、事態は一挙に動き出した。
まずは、マティルドがヌヴェール伯領の女伯の地位をアニェスに相続させた。
そのうえで、ヌヴェール伯領はロートリンゲン公へアニェスとの婚姻を申し入れる使者を送った。
ロートリンゲンとしては、この政略結婚にデメリットはなく、断る理由もなかったので、あっさりと婚約は成立し、程なくして結婚式が挙行された。
そのアニェスであるが、ヌヴェール伯領の女伯であるため、他の共同統治者と同様に、ヌヴェール伯領を離れることはできず、フリードリヒの方から通う形になるのだが、ナンツィヒとヌヴェール伯領は決して近い距離ではない。
アニェスは結婚といっても多分に形式的なものになると覚悟していた。会えるとしても数か月に1程度かそれよりも悪いのではないかと勝手に想像していたのだ。
しかし、蓋を開けて見るとおよそ週1回のペースで通ってくるではないか。アニェスはフリードリヒの情けに涙した。
そして1年後。
ヌヴェール伯領の統治が軌道に乗ったことを確かめて満足したように、マティルドも亡くなった。
こちらも死因は病死と発表した。フリードリヒは自殺を疑っていたが、深くは追及しなかった。
今ごろマティルドはあの世でエルヴェⅣ世に詫びを入れているのではないか。
そんな場面をフリードリヒは想像した。
隣国のブルゴーニュ公国の紛争の結果、同国は神聖帝国のロートリンゲン公が共同統治者となり、事実上、ロートリンゲン公国の支配下に入った。
破竹の勢いで支配領域を広げているロートリンゲン公の次のターゲットは我がヌヴェール伯領なのではないか?
共同統治者で夫のエルヴェ・ド・ドンジー(エルヴェⅣ世)はブーヴィーヌの戦いにおいてイングランド王ジョン側として戦い、フランス王フィリップⅡ世の不興を買っていた。後にジョンの仲介により許しを得たもののフランス王家との関係はギクシャクしている。
したがって、フランス王ルイⅨ世と摂政ブランシュに後ろ盾になってもらうことは難しい。加えて、ブランシュはロートリンゲン公と不謹慎な関係にあるとさえ噂されているのだ。
一方で、夫のエルヴェⅣ世はまもなく50歳をむかえ、老害の兆候も見えていて、全く頼りにならない。
子息は、まもなく20歳となる娘のアニェスただ1人だけだった。
このまま何も手を打たずに座していてはロートリンゲン公にヌヴェール伯領は奪われてしまうのではないか?
それにしてもブルゴーニュ女公のアリックスは上手くやった。
好色と評判のロートリンゲン公に我が身を捧げることで、国が滅びることを回避したのだ。滅びさえしなければ子孫の代で挽回することはいくらでもできる。
その前のブローニュ女伯もそうだ。
彼女は少数の護衛のみでロートリンゲンに乗り込み、ロートリンゲン公に共同統治者となることを飲ませたという。これも並大抵のことではない。
マティルドはエルヴェⅣ世の考えを確かめることにした。
「あなた。ロートリンゲン公についてどう思いますの」
「所詮はまだ20代の小僧だろう。なにを恐れることがある?」
「でもロートリンゲン公はいまだ負け知らずですのよ。しかも、暗黒騎士団には闇の者までいるというではないですか。それが攻めてきたらと思うと恐ろしくて…」
「わしもブーヴィーヌでは負けたが、アルビジョア十字軍ではかなりの戦功をあげたつもりだ。フランス王とて、蚕食されるのを黙ってみていることはないだろう」
「しかし、フランドル候国の時も、ブルゴーニュ公国の時も王は動かなかったではないですか?」
「やつらは事実上独立して勝手をやっておったのだ。見捨てられても自業自得というものだ。我が国にはアルビジョア十字軍での軍功がある」
──ベジエで住民を虐殺したことを軍功と言うの?
それでブーヴィーヌのときの裏切りを払拭できるわけがない。
「プロヴァンスでは暗黒騎士団とは戦いませんでしたの?」
「あの時は後詰めだったからなあ。出番はなかった。摂政のブランシュも所詮は女。闇の者の姿を見て恐れをなしたのだろう」
──やっぱり信用されていないんじゃない!
ダメだ。戦ったこともないのに相手を軽んじるこの根拠のない自信…
昔から自信家ではあったが、老害でそれがひどくなっている…
いちおう言うだけ言ってみるか…
「私たちももう歳が歳でしょう。そろそろ引退したらどうかと思うのよ」
「何を言っておる。わしは日々体を鍛えておる。若い者にはまだ負けはせぬ」
「でもアニェスももういい歳だし、しっかりした婿を見つけて国を継がせないと…」
「婿は婿で探せばよい。わしはまだ領主の座は降りないぞ」
──やはりダメか…
「では、婿探しは私に任せていただけますか?」
「そういう面倒なことはおまえに任せる。ラテン帝国でもどこからでも引っ張ってくるがよかろう」
「承知しましたわ」
◆
マティルドはアニェスがどう思っているかも確認したいと思い、彼女の部屋に向かった。
「お母さま。どうされましたの。お母さまの方からいらっしゃるなんて…」
「おなたももう歳が歳でしょう。薹が立つ前にお婿さんを探さないとと思って…
誰かいい人はいないの?」
「おりませんわ…というか、お母さま。回りくどい言い方はやめてください。
私にロートリンゲン公の嫁になれとおっしゃりたいのでしょう?」
マティルドは感心した。我が子ながら何と察しのいい…
「なぜそう思うの?」
「そんなこと、我が国のことを思えばすぐにわかることではありませんか」
「そうね…でも、あなたの気持ちを踏みにじってまでとは考えていないの。あなたの気持ちはどうなの?
ロートリンゲン公はあまたの側室や愛妾を抱える好色な人物だと聞くけれど…」
「数が多くとも側室や愛妾の一人一人が幸福に暮らせていれば問題はないと思うのです。要は男の甲斐性の問題です」
「あら。意外ね。もっと嫌がられると思っていたのだけれど…」
「残念ながら、私が今思いを寄せている人はいません…ですからロートリンゲン公に嫁入りすることもやぶさかではないのですが…」
「それで…どうしたの?」
「お返事をする前にナンツィヒの町に行ってみたいのです」
「ナンツィヒの町に? それはどうして?」
「ナンツィヒの町は今や素晴らしい町に発展していると聞きます。私が来ているヴィオラのブランドの服を始めとして素晴らしいものがたくさんあると…そこに行ってみたら町を作ったロートリンゲン公の人となりがわかるよう気がするのです」
「そうね。公式に訪問したら相手も表面を取り繕うだろうし、私的に訪問するのも面白いかもしれないわね」
「では、お母さま…」
「いいわ。いってらっしゃい。そしてあなたの目で確かめてくるのです」
「お母さま。ありがとうございます」
◆
タンバヤ商会情報部のベルント・バウムガルテンがフリードリヒの執務室を訪れた。
「申し上げます」
「何だ。ベルント」
「ヌヴェール伯国のアニェス姫が私的にナンツィヒの町を訪問するとの情報が入りました」
「ほう…面白いな。だが、あくまでも私的にということなのだな?」
「左様にございます」
「では、好きなようにやらせてやろう。だが、万が一のことがあっては困る。最低限の警備は付けよう。そうだな…マグダレーネを呼べ」
マグダレーネことアスタロトは、フリードリヒを警備する親衛隊を率いる高位の女悪魔である。
フリードリヒは、アスタロトにアニェス姫の警護に、彼女の配下の女悪魔を10人ほど隠形して張り付かせるよう命じた。
◆
1週間後。
ナンツィヒの町にアニェスの姿があった。侍女が1人と警備のための従者5人を引き連れている。
途中、盗賊に襲われるなどのトラブルが一切ない順調な旅だった。
「フリードリヒ道路というのは素晴らしいわね。馬車の旅があんなに快適なんて初めての経験だわ」
この時代の道路は一般的に舗装状態が極めて悪く、馬車で走ると揺れが酷いため、貴婦人などを除き、馬車ではなく、徒歩で旅をするのが常識だった。
従者の一人が答える。
「あれほどきちんと舗装された道路は他に例をみません。ロートリンゲン公というのはよほど潤沢な資金をおもちなのですな」
「そうね」
途中の道路からしてこうなのだ、町本体はどれだけ凄いのだろうと期待が膨らんだ。
アニェスは、まずその街並みに目を見張った。
特に新街区は大都市にありがちな無秩序な開発がされておらず、整然と整備された道路に面して意匠統一された建物が整然と並んでいる。
街区は商業地区、工業地区、居住地区と用途別に区分され、それぞれに適した環境が整備されている。
特にナンツィヒの鉄工業は有名で、良質な鉄をリーズナブルな価格で提供することで有名だ。
商業地区も立派で、活気に満ち満ちていた。
様々な国の商人が出入りしており、多様な言語が飛び交っている。少数だがイスラム商人までいるではないか。
しかも周りのドイツ人はその存在を当たり前のように受け入れている。
外国製と思われる見たこともない物やタンバヤ商会で開発されたという新製品が飛ぶように売れている。
──なんと活気のある国なのだ…
アニェスを驚かせたのが亜人たちの存在だ。
相当数の亜人が明るい表情で胸を張って町をいきかっている。
身なりからして明らかに奴隷ではないし、人族がこれを差別する様子もみられない。
その時。前方から異形の闇の者が複数こちらにやってくる。
警備の従者たちは抜剣して、警戒した。
「姫様。お下がりください」
始めてみる闇の者にアニェスは恐怖した。
心臓は早鐘を打ち、冷や汗がにじみ出ている。
しかし、その闇の者たちはこちらを一瞥もせずに通り過ぎてしまった。
極限まで緊張していた従者たちは、拍子抜けしてしまい、大きなため息をつくと、その場に座り込んでしまう。
そこに女性から声をかけられた。
経済産業卿ゴットハルトの妻ベリンダである。
「あなたたちお上りさんっすね」
「『おのぼりさん』?」
「ああ。ナンツィヒの町では田舎からナンツィヒの町に出てきたばかりの者を『お上りさん』って言うんすよ」
「そうなんですか。私たちは今日ヌヴェール伯領から着いたばかりなんです。そういう意味では、お上りさんですね」
「さっき『姫』って聞こえたっすけど…」
「私的な訪問なので、それはどうかご内密に…
ところで、あの闇の者はいったい何なのですか? 白昼堂々闇の者が跋扈しているなんて…」
「ああ。さっきのダークナイトのことっすか?」
「あれはダークナイトというのですか?」
「ええ。あれは町を巡回警備してるんっすよ。あなたたちも町で騒ぎを起こしたらダークナイトにやられるから気をつけた方がいいっすよ」
「しかし、闇の者が警備なんて…」
「はっはっはっはっ。本当に何も知らないんすね。
闇の者は上の者…つまり大公閣下の命令に絶対服従っすから、何もしないのに向こうから攻撃してくることはないんすよ。町の者も誰も怖がっていなかったでしょ」
「そう…なのですか…」
アニェスは未だに信じられないという表情をしている。
「ところで、今日はどこか目的地でも…」
「いえ。これといって…そうだ、ヴィオラの服が欲しいです」
「そういえば今着てる服もヴィオラっすね」
「わかります? セクシーなのに上品さもあって、私大ファンなんです」
「ヴィオラの店なら良く知ってるっすから案内しますよ」
「そんな…お手間を取らせていいんですか」
「ちょうどあたしも買いたいものがあるし、ついでっすよ」
「それならお願いいたします」
◆
そしてヴィオラの店に着くと…
「ここがヴィオラの店…」
アニェスの目は憧れのあまりキラキラしている。
早速好みの服を夢中で物色するアニェス…
「えっ。この上等な服がこの値段!」
「ああ。ここはヴィオラの直営店っすから、中間マージンが入らない分安いんすよ。これがヴィオラ本来の値段っす」
「ヌヴェール伯領ではとてもこの値段では買えないわ」
「ヌヴェール伯領で売るには間に商人が入るっすから、その取り分だけ値段が上がるっす」
「なるほど。では、ヌヴェール伯領にヴィオラの直営店ができれば安く買える訳ですね」
「へーっ。なかなか鋭いっすね。それはそのとおりっすけど、それができるかどうかは大公閣下と交渉っすね」
「そこでなぜ大公閣下が出てくるのですか?」
「ヴィオラはタンバヤ商会の直営ブランドなんすよ」
「ですからなぜ?」
「タンバヤ商会の会長は大公閣下っすから。それにヴィオラの服は全て正妻のヴィオランテ様の監修っすからね」
「えっ。そうなのですか!」
「ほんとに何にも知らないんっすね」
「ええ。帝国内の事情には疎くって…」
結局、アニェスとベリンダ、それにアニェスの侍女の3人はヴィオラの服から化粧道具の類まで買い漁り、気がつけば夕刻となっていた。
店を出てみるとアニェスの従者が座り込んで居眠りをしていたので、それをベリンダが叩き起こした。
「まあ、もうこんな時間だわ」
「夕食や宿の手配はしてるっすか?」
「いえ。ぜんぜん…どうしましょう…」
「なら、今夜、身内の夕食会があるから招待するっすよ」
「でも、身内の会なのでしょう。悪いわ」
「いやあ。そんなこと気にする人はいないから、大丈夫っす」
「それなら甘えさせてもらおうかしら」
「それがいいっす」
荷物は全て従者に持たせたので、女性軍は手ぶらである。
それをいいことに、ベリンダはスタスタと早足で歩いていく。
するとナンツィヒの城に到着した。
「あのう。ここって…」
「見てのとおり、ナンツィヒのお城っすよ」
「夕食会というのはここで?」
「もちろんっす」
アニェスの頬を冷や汗が伝った。
「失礼ながら、あなたのお名前をまだ聞いていませんでしたわ。あなた何者ですの?」
「あたしはベリンダ。旦那はロートリンゲン公国の経済産業担当宮中伯をやってるっす」
「まあ。そうでしたのね」
「どうするっす。怖気づいたのなら止めておきますか?」
気がついたら敵本陣の真っただ中という状況に戸惑うアニェスだったが、本来の目的はロートリンゲン公の人となりを確かめることだ。そういう意味では千載一遇の好機ではないか。
「いえ。出席させていただきます」
「それがいいっす」
◆
会場についてみると、出席者の多数を女性が占めていた。
皆、夜会用のドレスを着ているではないか。
ベリンダに案内してもらって、慌てて着替える。
ちょうど今日ヴィオラの夜会服を買っておいたのが役に立った。
アニェスはベリンダに聞いてみた。
「女性が多いわね」
「あたしみたいに宮中伯の家族もいるっすけど、半分くらいは大公閣下の側室と愛妾っすね」
──そんな…多いとは聞いていたけれど…
「こんなに多くては…その…あぶれてしまう人もいるのでは?」
「いやあ。詳しくは知らないっすけど、ローテーションを組んで平等にしてるみたいっす」
「それだといつまでも順番が回ってこないのでは?」
「それが不思議なところで、からくりはわからないっすけど、週1回くらいは回ってくるらしいっす」
──それならまあ普通だわ。しかし、この人数をどうやって…?
考え込んでしまうアニェス…
その時、声の大きな女性が声をかけてきた。人狼のヴェロニアである。
「見ない顔だな。まさか新入りかよ」
「いえ…私は…その…」
ヴェロニアの迫力に気圧されるアニェス…
ベリンダが助け舟を出す。
「ヴェロニアさん。脅かさないでやってくださいよ。彼女はヌヴェール伯領の姫様っす」
「初めまして。アニェス・ド・ヌヴェールにございます。どうぞよろしくお願いいたします」
「あたいはヴェロニアだ。旦那の愛妾をやってる。
おめえ、まさか旦那の側室になろうってんじゃねえだろうな?」
「いえ。今日はベリンダさんに招待されまして…」
「ならいいけどよう」
と言うとヴェロニアは去っていった。
「あんなお下品な方が愛妾なのですか?」
「ああ。ヴェロニアさんは閣下が冒険者時代からの古株っす。ハルバードを使わせたら右に出る者はいないっすよ」
「えっ。それって、まさか魔獣を倒せないと愛妾になれないとか…」
「さすがに、それはないっすよ」
──ああ。良かった…
冷静になって見渡してみると、ライバル関係にあるはずの側室・愛妾どうしがにこやかに談笑しているようだ。
「皆さん仲がよろしいのですね?」
「確かに。国王や貴族の側室・愛妾どうしがこんなに仲良しなんて聞かないっすね。これも閣下の人徳のたまものっすよ」
「ところで、大公閣下はどちらに?」
「は? あそこの上座に座っているのが大公閣下っすよ」
そう言われ、見てみるとアニェスと同年輩に見える若い男が据わっている。
それを見て、アニェスは目を見張った。
「えっ。あの方が!?」
──噂には聞いていたけれど、なんて見目麗しい男性なのだろう。
確か歳は25歳と聞いていたはずだが、どう見ても20歳前後にしかみえない。
観察してみると、大公のところには入れ替わり立ち替わりに女性が訪れ、話しかけているが、大公は軽く相槌を打つばかりで、たまにボソッと話すばかりだ。
だが、その一言が女性たちにはこの上もなく嬉しいらしく、満面の笑みを浮かべている。
──あまり話好きな方ではいらっしゃらないのね…
確かにおしゃべりな男など詐欺師のようで信用ならない。
男はどっしりと構えてもらって、いざという時に頼りになればそれでいいのだ。
アニェスは男性に対し、そういう古風な感覚を持っていた。
しばらくすると、大公と会話しようという女性の列が途切れ、大公はアニェスの方を振り向き、目があってしまった。
それだけで顔が赤らんでしまうアニェス。
しかも、大公は席を立ってこちらに向かってくるではないか。
大公が近づいてくるにつれ緊張が高まる。
フリードリヒは挨拶をする。
「ヌヴェール伯領のアニェス姫ですね。初めまして。ロートリンゲン大公のフリードリヒ・エルデ・フォン・ザクセンです。以後、良しなにお願いいたします」
「ア、アニェス・ド・ヌヴェールにございます。た、大公閣下におかれましてはご機嫌麗しゅう」
「お嬢さん。そんなに緊張しないでください。今日の夜会はあくまでも私的な会合ですから、お気を使われる必要はありません」
「そう言っていただけると、助かります」
「ところでお嬢さん。これからダンスが始まるのですが、お付き合いいただけますか?」
「私…ダンスなど踊ったことがなくって…」
「大丈夫ですよ。簡単な踊りですから。直ぐに覚えられます」
「そうですか。では、やってみます」
「感謝いたします」
フリードリヒが楽隊に合図を出すと、音楽が始まった。
出席者たちは、慣れているので早速踊り出した。
踊りは基本的に男女ペアで踊るのだが、人数が不均等なので女性同士のペアも多い。美貌の女性どうしがペアでダンスを踊る姿は、それはそれで百合っぽい。
この時代はまだオーケストラなどの本格的な楽団やワルツのような洗練された踊りはない。
あくまでもフォークダンスに毛が生えたような素朴な踊りだった。
だが、この時代男女がペアを組んで手をつなぎあうだけでも十分に煽情的だったのだ。
「さあ。私たちも踊りましょう」とフリードリヒはアニェスに声をかける。
アニェスは恥ずかしくて顔を赤らめながらも手を差し出した。
アニェスは周りのカップルの見様見真似で必死に踊る。
踊り自体は単純なものだったのですぐに覚えることができた。
「そうそう。若いだけあって覚えがはやいじゃないですか」
「いえ。そんなことは…」
緊張と恥ずかしさで手が汗ばんできた。
だが、フリードリヒが嫌がる様子はない。
アニェスはままよと開き直り、この際踊りを楽しむことにした。
姫であるアニェスは、若い男と手を握るなどという機会はこれまで皆無である。恥ずかしいと思いつつも、誰憚りなく手を握りあえる機会を貴重だと思った。
フリードリヒもずっとアニェスとばかり踊っている訳にもいかない。
フリードリヒもアニェスもパートナーを入れ替えた。
今度のパートナーも若くてハンサムな男だったが、フリードリヒのときのようにはときめかなかった。
そして夜会は終わり。
アニェス一行は用意されていた城の寝室に案内された。
だが、アニェスはなかなか寝付けなかった。
あまりに刺激的な一日だった。
いろいろなことが頭を駆け巡る。
ことにフリードリヒの姿が頭を離れない。
──もしかして、私、恋しちゃったのかな…
◆
私的な夜会といっても、そう毎晩開かれるものではなく、アニェスはフリードリヒとはそれきりとなった。
フリードリヒの方も、あくまでも私的な訪問ということで、過剰な接待を控えたのである。
アニェス一行は、それからナンツィヒの町を何日か見分してヌヴェール伯領に戻った。
◆
アニェスは、ヌヴェール伯領に戻ると一連の体験をマティルドに報告した。
「まさか、大公ご本人にお会いするとはね」
「偶然そうなっただけです」
「それにしても、それは神の采配としか言いようがないわ。
それで肝心のあなたの気持ちはどうなの?」
「それが…恋をしてしまったかもしれません」
「かもしれないとは、頼りないわね」
「自分でも心の整理がつかなくて…よくわからないのです。
ただ、寝ても覚めてもロートリンゲン公のことが頭を離れないのは本当です」
「バカね。それは恋以外の何ものでもないわ」
「そう…なのですか…」
アニェスは、今まで気になる男性は何人かいたものの、ここまで心を寄せることは初めての体験だった。
そうなのか…これが恋…
アニェスは目から鱗が落ちる思いがした。
◆
マティルドとアニェスは早速このことをエルヴェⅣ世に報告した。
しかし、結果は惨憺たるものだった。
「よりによって我が領土を狙っているロートリンゲン公に領地を差し出すと言うのか。あり得ん。わしの目が黒いうちは絶対に認めんからな」
「しかし、あなた。アニェスの気持ちもお考えになって」
「やつはアニェスの純真な心につけ込んでいるだけだ。美味いところだけ持っていって、アニェスは冷たく遇されるに決まっておる」
アニェスは意気消沈し、懊悩した。
マティルドはそんなアニェスを見るたびに心を痛めた。
しかし、それから半年ほど経ったとき、事態は急変した。
エルヴェⅣ世が急死したのである。
公式発表は病死ということだったが、彼の死体は見るも無残に腫れ上がっており、これはカンタレラにより毒殺された特徴と酷似していた。
人々は毒殺であると噂したが、真相を究明されることはなく、闇の中に葬られた。
少なくともフリードリヒは何の指示も出していないので、おそらくは国を思ったマティルドが断腸の思いで実行したのだと思料されたが、フリードリヒはあえて追及しなかった。
そしてエルヴェⅣ世の死に係る喪が明けた時、事態は一挙に動き出した。
まずは、マティルドがヌヴェール伯領の女伯の地位をアニェスに相続させた。
そのうえで、ヌヴェール伯領はロートリンゲン公へアニェスとの婚姻を申し入れる使者を送った。
ロートリンゲンとしては、この政略結婚にデメリットはなく、断る理由もなかったので、あっさりと婚約は成立し、程なくして結婚式が挙行された。
そのアニェスであるが、ヌヴェール伯領の女伯であるため、他の共同統治者と同様に、ヌヴェール伯領を離れることはできず、フリードリヒの方から通う形になるのだが、ナンツィヒとヌヴェール伯領は決して近い距離ではない。
アニェスは結婚といっても多分に形式的なものになると覚悟していた。会えるとしても数か月に1程度かそれよりも悪いのではないかと勝手に想像していたのだ。
しかし、蓋を開けて見るとおよそ週1回のペースで通ってくるではないか。アニェスはフリードリヒの情けに涙した。
そして1年後。
ヌヴェール伯領の統治が軌道に乗ったことを確かめて満足したように、マティルドも亡くなった。
こちらも死因は病死と発表した。フリードリヒは自殺を疑っていたが、深くは追及しなかった。
今ごろマティルドはあの世でエルヴェⅣ世に詫びを入れているのではないか。
そんな場面をフリードリヒは想像した。
1
あなたにおすすめの小説

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

男女比がおかしい世界の貴族に転生してしまった件
美鈴
ファンタジー
転生したのは男性が少ない世界!?貴族に生まれたのはいいけど、どういう風に生きていこう…?
最新章の第五章も夕方18時に更新予定です!
☆の話は苦手な人は飛ばしても問題無い様に物語を紡いでおります。
※ホットランキング1位、ファンタジーランキング3位ありがとうございます!
※カクヨム様にも投稿しております。内容が大幅に異なり改稿しております。
※各種ランキング1位を頂いた事がある作品です!

【㊗️受賞!】神のミスで転生したけど、幼児化しちゃった!〜もふもふと一緒に、異世界ライフを楽しもう!〜
一ノ蔵(いちのくら)
ファンタジー
※第18回ファンタジー小説大賞にて、奨励賞を受賞しました!投票して頂いた皆様には、感謝申し上げますm(_ _)m
✩物語は、ゆっくり進みます。冒険より、日常に重きありの異世界ライフです。
【あらすじ】
神のミスにより、異世界転生が決まったミオ。調子に乗って、スキルを欲張り過ぎた結果、幼児化してしまった!
そんなハプニングがありつつも、ミオは、大好きな異世界で送る第二の人生に、希望いっぱい!
事故のお詫びに遣わされた、守護獣神のジョウとともに、ミオは異世界ライフを楽しみます!
カクヨム(吉野 ひな)にて、先行投稿しています。

英雄召喚〜帝国貴族の異世界統一戦記〜
駄作ハル
ファンタジー
異世界の大貴族レオ=ウィルフリードとして転生した平凡サラリーマン。
しかし、待っていたのは平和な日常などではなかった。急速な領土拡大を目論む帝国の貴族としての日々は、戦いの連続であった───
そんなレオに与えられたスキル『英雄召喚』。それは現世で英雄と呼ばれる人々を呼び出す能力。『鬼の副長』土方歳三、『臥龍』所轄孔明、『空の魔王』ハンス=ウルリッヒ・ルーデル、『革命の申し子』ナポレオン・ボナパルト、『万能人』レオナルド・ダ・ヴィンチ。
前世からの知識と英雄たちの逸話にまつわる能力を使い、大切な人を守るべく争いにまみれた異世界に平和をもたらす為の戦いが幕を開ける!
完結まで毎日投稿!

45歳のおっさん、異世界召喚に巻き込まれる
よっしぃ
ファンタジー
2巻決定しました!
【書籍版 大ヒット御礼!オリコン18位&続刊決定!】
皆様の熱狂的な応援のおかげで、書籍版『45歳のおっさん、異世界召喚に巻き込まれる』が、オリコン週間ライトノベルランキング18位、そしてアルファポリス様の書店売上ランキングでトップ10入りを記録しました!
本当に、本当にありがとうございます!
皆様の応援が、最高の形で「続刊(2巻)」へと繋がりました。
市丸きすけ先生による、素晴らしい書影も必見です!
【作品紹介】
欲望に取りつかれた権力者が企んだ「スキル強奪」のための勇者召喚。
だが、その儀式に巻き込まれたのは、どこにでもいる普通のサラリーマン――白河小次郎、45歳。
彼に与えられたのは、派手な攻撃魔法ではない。
【鑑定】【いんたーねっと?】【異世界売買】【テイマー】…etc.
その一つ一つが、世界の理すら書き換えかねない、規格外の「便利スキル」だった。
欲望者から逃げ切るか、それとも、サラリーマンとして培った「知識」と、チート級のスキルを武器に、反撃の狼煙を上げるか。
気のいいおっさんの、優しくて、ずる賢い、まったり異世界サバイバルが、今、始まる!
【書誌情報】
タイトル: 『45歳のおっさん、異世界召喚に巻き込まれる』
著者: よっしぃ
イラスト: 市丸きすけ 先生
出版社: アルファポリス
ご購入はこちらから:
Amazon: https://www.amazon.co.jp/dp/4434364235/
楽天ブックス: https://books.rakuten.co.jp/rb/18361791/
【作者より、感謝を込めて】
この日を迎えられたのは、長年にわたり、Webで私の拙い物語を応援し続けてくださった、読者の皆様のおかげです。
そして、この物語を見つけ出し、最高の形で世に送り出してくださる、担当編集者様、イラストレーターの市丸きすけ先生、全ての関係者の皆様に、心からの感謝を。
本当に、ありがとうございます。
【これまでの主な実績】
アルファポリス ファンタジー部門 1位獲得
小説家になろう 異世界転移/転移ジャンル(日間) 5位獲得
アルファポリス 第16回ファンタジー小説大賞 奨励賞受賞
第6回カクヨムWeb小説コンテスト 中間選考通過
復活の大カクヨムチャレンジカップ 9位入賞
ファミ通文庫大賞 一次選考通過

元おっさんの俺、公爵家嫡男に転生~普通にしてるだけなのに、次々と問題が降りかかってくる~
おとら@ 書籍発売中
ファンタジー
アルカディア王国の公爵家嫡男であるアレク(十六歳)はある日突然、前触れもなく前世の記憶を蘇らせる。
どうやら、それまでの自分はグータラ生活を送っていて、ろくでもない評判のようだ。
そんな中、アラフォー社畜だった前世の記憶が蘇り混乱しつつも、今の生活に慣れようとするが……。
その行動は以前とは違く見え、色々と勘違いをされる羽目に。
その結果、様々な女性に迫られることになる。
元婚約者にしてツンデレ王女、専属メイドのお調子者エルフ、決闘を仕掛けてくるクーデレ竜人姫、世話をすることなったドジっ子犬耳娘など……。
「ハーレムは嫌だァァァァ! どうしてこうなった!?」
今日も、そんな彼の悲鳴が響き渡る。

【完結】幼馴染にフラれて異世界ハーレム風呂で優しく癒されてますが、好感度アップに未練タラタラなのが役立ってるとは気付かず、世界を救いました。
三矢さくら
ファンタジー
【本編完結】⭐︎気分どん底スタート、あとはアガるだけの異世界純情ハーレム&バトルファンタジー⭐︎
長年思い続けた幼馴染にフラれたショックで目の前が全部真っ白になったと思ったら、これ異世界召喚ですか!?
しかも、フラれたばかりのダダ凹みなのに、まさかのハーレム展開。まったくそんな気分じゃないのに、それが『シキタリ』と言われては断りにくい。毎日混浴ですか。そうですか。赤面しますよ。
ただ、召喚されたお城は、落城寸前の風前の灯火。伝説の『マレビト』として召喚された俺、百海勇吾(18)は、城主代行を任されて、城に襲い掛かる謎のバケモノたちに立ち向かうことに。
といっても、発現するらしいチートは使えないし、お城に唯一いた呪術師の第4王女様は召喚の呪術の影響で、眠りっ放し。
とにかく、俺を取り囲んでる女子たちと、お城の皆さんの気持ちをまとめて闘うしかない!
フラれたばかりで、そんな気分じゃないんだけどなぁ!
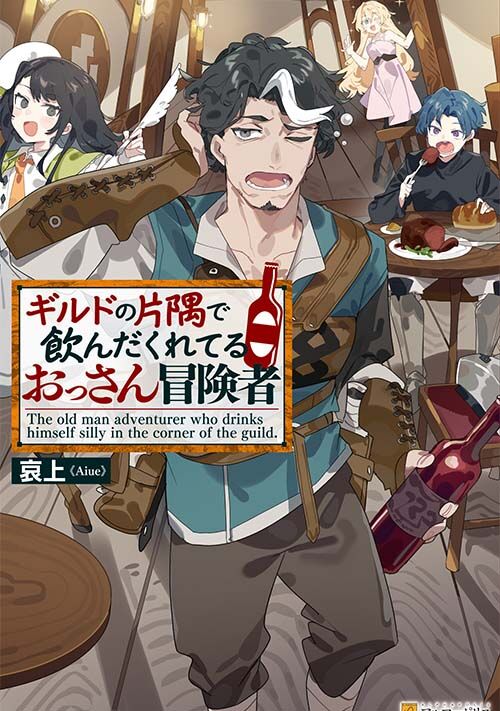
ギルドの片隅で飲んだくれてるおっさん冒険者
哀上
ファンタジー
チートを貰い転生した。
何も成し遂げることなく35年……
ついに前世の年齢を超えた。
※ 第5回次世代ファンタジーカップにて“超個性的キャラクター賞”を受賞。
※この小説は他サイトにも投稿しています。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















