60 / 166
第五十九話:料理という名の戦場
しおりを挟む祝賀の宴、前日。
俺は、エレナ様、セバスチャン、そして護衛役のギデオンを伴い、辺境伯の城が誇る、巨大な厨房へと足を踏み入れていた。
そこは、俺が今まで見てきたどんな場所とも異質な、一つの独立した王国のようだった。天井は高く、何十もの竈(かまど)が赤々と炎を燃やし、その熱気は工房の炉にも匹敵するほどだ。壁一面には、磨き上げられた銅鍋や、用途の分からぬ奇妙な調理器具が、まるで武器庫のように整然と並べられている。そして、白い帽子を被った数十人もの料理人たちが、慌ただしく行き交い、その喧騒は戦場のそれに近かった。
俺たちの来訪に、その喧騒が一瞬だけ、ぴたりと止まる。全ての視線が、闖入者である俺に、値踏みするように、あるいは敵意を込めて突き刺さった。
「これはこれは、ようこそお越しくださいました、救世主様」
料理人たちの輪の中から、一人の男が、ゆっくりと歩み出てきた。年の頃は四十代だろうか。背は高く、贅肉のない引き締まった体つき。その、一点の染みもない純白のコックコートは、彼のこの厨房における絶対的な地位を物語っていた。彼が、この城の料理長、オーギュスト。
「私(わたくし)が、この厨房を預かるオーギュストと申します。明日の宴の件、辺境伯様より伺っております。我ら一同、あなた様の『奇跡』のお手並み、拝見させていただくのを、楽しみにしておりましたぞ」
その言葉は、どこまでも丁寧だった。だが、その薄い唇に浮かんだ笑みは、刃物のように冷たく、その瞳の奥には、自らの聖域を土足で踏み荒らされたことへの、隠しようのない侮蔑と嫉妬の炎が揺めいていた。
ギデオンが警告した通りだ。この男は、俺を歓迎などしていない。
「……こちらこそ、よろしくお願いします。オーギュスト料理長」
俺は、彼の敵意を正面から受け止め、深々と頭を下げた。戦いの火蓋は、切られた。
◇
「材料は、全て最高級のものをご用意いたしました。さあ、存分にお使いください」
オーギュストが指し示した作業台の上には、プリンの材料となる、卵、乳、そして砂糖が、山と積まれていた。
俺は、まず、籠に盛られた卵を一つ、手に取った。見た目は、瑞々しく、新鮮そのものだ。だが、俺の脳裏には、ギデオンの言葉が蘇る。『職人の嫉妬は、静かで、そして陰湿だ』。
スキル『識別』は、もうない。頼れるのは、己の五感だけ。ブラック企業で、連日の徹夜作業とストレスで研ぎ澄まされた、異常なまでの感覚だけが、俺の武器だった。
俺は、卵を一つ一つ、光にかざし、その殻の表面の僅かなざらつきを確かめる。そして、耳元で軽く振り、中の黄身が揺れる、微かな音を聞き分ける。
(……五つに一つ、古いものが混じっているな)
産みたての卵は、気室が小さく、振ってもほとんど音がしない。だが、少し日が経ったものは、水分が蒸発し、黄身が揺れる音がする。前世で、賞味期限切れの卵を無駄にしまいと、必死で学んだ、貧乏学生の知恵だった。
俺は、何も言わずに、古い卵だけを籠の脇へと避けていく。その、あまりにも的確な選別に、オーギュストの眉が、ぴくりと動いた。
次に、乳の入った銀の水差し。蓋を開け、匂いを嗅ぐ。
(……わずかに、酸っぱい匂い。それも、腐敗臭じゃない。ヤギの乳に、ごく少量の、古い牛乳を混ぜてあるな)
加熱すれば、分離してしまうだろう。俺は、その水差しには手を付けず、別の場所に用意されていた、搾りたてのヤギの乳が入った甕(かめ)を指さした。
「申し訳ありませんが、そちらを使わせていただけますか。僕のプリンには、ヤギの乳の、新鮮な甘みだけが必要なんです」
俺の、穏やかだが、全てを見透かしたかのような言葉に、オーギュストの額に、一筋の汗が浮かんだ。
そして、最後の砂糖。彼は、辺境伯から下賜された、南国産の純白の砂糖ではなく、この辺境で採れる、少し茶色がかった岩糖の塊を、当然のように用意していた。
俺は、その塊から指でほんの少しだけ削り取ると、それを舐めた。
(……甘さの奥に、微かな塩気。そして、岩塩特有の、僅かな苦味)
これでは、完璧なカラメルソースは作れない。
「……料理長」
俺は、顔を上げ、彼の目を真っ直ぐに見つめた。
「『おもてなし』の基本は、最高の材料を用意することではなく、相手が何を求めているかを、正確に理解することだと、僕は教わりました。……僕が求めているのは、辺境伯様からいただいた、あの砂糖です。それ以外では、奇跡は起きません」
俺の、静かな、しかし刃物よりも鋭い指摘。
オーギュストの顔から、血の気が引いていくのが分かった。彼の、料理人としてのプライドの根幹を、八歳の子供に、完膚なきまでに否定されたのだ。
彼は、しばらくの間、屈辱に唇を震わせていたが、やて、観念したように、近くにいた部下に、目配せをした。「……例の、砂糖を持ってこい」
前哨戦は、終わった。俺の、完全勝利だった。
◇
だが、本当の戦いは、ここからだった。
完璧な材料を手に入れた俺は、まず、カラメルソース作りから取り掛かった。
銅の小鍋に、砂糖と少量の水を入れる。問題は、火加減だ。この世界の竈は、火力を調整する機能などない。頼りになるのは、炉の中の薪の燃え方、火の色、そして、鍋から立ち上る湯気の匂いだけ。
俺は、鍋を火から上げたり、近づけたりしながら、五感を極限まで研ぎ澄ませる。砂糖が溶け、泡立ち、そして、徐々に色づいていく。甘い香りが、香ばしい香りへと変わる、その一瞬。
(……今だ!)
鍋を火から下ろし、少量の熱湯を注ぐ。ジュッという激しい音と共に、湯気が立ち上った。鍋の中には、焦げる寸前の、完璧な琥珀色をしたカラメルソースが、完成していた。
次に、プリン液。卵を割り、黄身と白身を、切るように混ぜ合わせる。泡立ててはいけない。滑らかな食感を損なうからだ。温めた乳に、砂糖を溶かし、それを卵液に、少しずつ、糸を垂らすようにして加えていく。
全ての工程を、俺は、まるで何十年もこの厨房に立ってきた熟練の職人のように、淀みなく、そして正確にこなしていく。その姿に、最初は俺を嘲笑の目で見ていた周りの料理人たちも、次第にその私語をやめ、固唾を飲んで俺の手元を見守り始めていた。
そして、最後の難関。蒸し上げる工程だ。
蒸し器などない。俺は、大きな深鍋の底に布を敷き、そこにカラメルソースを入れた器を並べ、器の半分が浸かるくらいまで、ぬるま湯を注いだ。
問題は、ここでも温度管理だった。火が強すぎれば、プリンに「す」が入ってしまう。弱すぎれば、固まらない。
俺は、鍋の蓋の隙間に、木の匙を一本、挟んだ。
鍋から聞こえる、湯が沸騰する音。蓋の隙間から漏れる、湯気の量と勢い。蓋の内側についた水滴が、プリン液の表面に落ちる、その音の間隔。
その全ての情報を、俺は脳内で統合し、最適な火加減を維持するために、薪をくべたり、あるいは濡れた布で炉の入り口を塞いだりして、微調整を繰り返した。
それは、もはや料理ではなかった。精密な化学実験。あるいは、オーケストラの指揮者が、全ての楽器の音を聞き分け、一つの完璧なハーモニーを創り出す作業に、似ていた。
やがて、鍋から立ち上る香りが、卵の生臭さから、甘く、そしてどこか懐かしい、焼きたての菓子のような香りへと変わった。
(……よし)
俺は、鍋を火から下ろし、蓋を開けた。
湯気の中から現れたのは、表面が鏡のように滑らかで、一切の「す」が入っていない、黄金色に輝く、完璧なプリンだった。
◇
「……どれ、毒味を、させていただこうか」
粗熱が取れたプリンを前に、オーギュストが、震える声で言った。その顔には、もはや俺への侮蔑の色はなかった。代わりにあったのは、自らの常識を超えた存在を前にした、職人としての、純粋な畏怖だった。
彼は、銀の匙を手に取り、プリンの表面に、そっと刃を入れた。ぷるん、とした心地よい抵抗。そして、一口。
次の瞬間。
彼の動きが、完全に、止まった。
辺境伯が、そしてクラウスが見せたのと、全く同じ反応。彼は、スプーンを口に含んだまま、まるで時が止まったかのように、微動だにしなくなる。その見開かれた目には、信じられない、理解できない、未知との遭遇を果たした人間の、純粋な衝撃の色だけが浮かんでいた。
やがて、彼はゆっくりとスプーンを口から引き抜くと、わなわなと震える指で、それをテーブルに置いた。カチャン、と。静かな厨房に、その音だけが響き渡った。
「……馬鹿な……」
絞り出すような声が、彼の口から漏れた。
「魔法、か……?いや、違う。これは、魔法などという安っぽい言葉で、片付けていいものではない。……全ての素材が、完璧な調和の中で、その最高の味を主張しながら、しかし、一つの至高の味へと昇華されている。……こんな、こんな芸当が、人間に可能なのか……?」
彼は、その場に、膝から崩れ落ちた。
何十年もかけて築き上げてきた、この辺境一という、彼のプライドの城が、たった一口のプリンによって、音もなく、完全に、崩れ落ちた瞬間だった。
俺は、そんな彼の前に、そっとしゃがみ込んだ。そして、静かに、しかしはっきりと、告げた。
「魔法じゃありませんよ、料理長」
「これは、ただの、『おもてなしの心』です。食べる人の、笑顔を想像して、心を込めて作る。……僕が、母さんから教わった、たった一つの、秘訣です」
その、あまりにも純粋で、あまりにも根源的な答え。
だが、オーギュストの心を本当に砕いたのは、その言葉ではなかった。彼が絶望したのは、この少年が、その純粋な『心』を、寸分の狂いもない完璧な『技術』へと昇華させてみせた、その圧倒的な事実に対してだった。火加減、素材の見極め、そして温度管理。それら全てを、己の五感だけを頼りに、何十年もこの厨房に立ってきた自分以上に、正確に、そして完璧に支配してみせた。この少年は、魔法使いなどではない。自分とは比べ物にならない高みに立つ、本物の『料理人』だったのだ。
「……完敗だ」
彼は、そう言うと、子供のように、声を上げて泣き始めた。
その光景を、エレナ様が、ギデオンが、そしてセバスチャンが、静かに見守っていた。
俺は、知っている。これは、まだ前哨戦に過ぎない。
本当の戦場は、明日の祝宴。
そして、この誇り高き料理長を、裏で操っていた、本当の敵の存在を。
だが、今は、それで良かった。
俺は、また一つ、この街で、守るべきものを、そして、共に戦うべき仲間を、手に入れたのかもしれない。
俺は、静かに立ち上がると、窓の外に広がる、夕暮れの空を見つめた。
戦いの前の、静かな、しかし確かな手応えが、俺の心を満たしていた。
---
【読者へのメッセージ】
第五十九話、お読みいただきありがとうございました!
ついに始まった、料理という名の戦場。スキルに頼れぬ絶体絶命の状況で、ルークスが己の知恵と五感だけを武器に、プライドの高い料理長の心を打ち砕く、その静かなる激闘。楽しんでいただけましたでしょうか。
「ルークスの五感、チートすぎる!」「料理長のプライドが崩れる瞬間、爽快!」「おもてなしの心、泣ける…!」など、皆さんの感想や応援が、明日の祝宴で、ルークスのプリンをさらに美味しくします。下の評価(☆)やブックマークも、ぜひよろしくお願いいたします!
ついに前哨戦を乗り越えたルークス。しかし、本当の敵は、まだ影の中に潜んでいます。明日の祝賀の宴で、一体何が待ち受けているのか。物語は、いよいよ大きな山場を迎えます。次回、どうぞお見逃しなく!
49
あなたにおすすめの小説

元侯爵令嬢の異世界薬膳料理~転生先はみんな食事に興味が無い世界だったので、美味しいご飯で人の身も心も癒します~
向原 行人
ファンタジー
異世界へ転生して数日。十七歳の侯爵令嬢、アリスとして目覚めた私は、早くも限界を迎えていた。
というのも、この世界……みんな食事に興味が無くて、毎食パンとハムだけとか、ハムがチーズに変わるとか、せいぜいその程度だ。
料理というより、食材を並べているだけって感じがする。
元日本人の私としては温かいご飯がたべたいので、自分で食事を作るというと、「貴族が料理など下賤なことをするのは恥だ!」と、意味不明な怒られ方をした。
わかった……だったら、私は貴族を辞める!
家には兄が二人もいるし、姉だっているから問題無いでしょ。
宛てもなく屋敷を飛び出した私は、小さな村で更に酷い食事事情を目の当たりにする。
育ち盛りの子供たちや、身体を使う冒険者たちが、それだけしか食べないなんて……よし、美味しいご飯でみんなも私も幸せになろう!
医食同源! 大食いモフモフ聖獣に、胃袋を掴んでしまった騎士隊長と一緒に、異世界で美味しくて身体に良い食材探しだ!
※第○話:主人公視点
挿話○:タイトルに書かれたキャラの視点
となります。

転生したら領主の息子だったので快適な暮らしのために知識チートを実践しました
SOU 5月17日10作同時連載開始❗❗
ファンタジー
不摂生が祟ったのか浴槽で溺死したブラック企業務めの社畜は、ステップド騎士家の長男エルに転生する。
不便な異世界で生活環境を改善するためにエルは知恵を絞る。
14万文字執筆済み。2025年8月25日~9月30日まで毎日7:10、12:10の一日二回更新。

底辺から始まった俺の異世界冒険物語!
ちかっぱ雪比呂
ファンタジー
40歳の真島光流(ましまみつる)は、ある日突然、他数人とともに異世界に召喚された。
しかし、彼自身は勇者召喚に巻き込まれた一般人にすぎず、ステータスも低かったため、利用価値がないと判断され、追放されてしまう。
おまけに、道を歩いているとチンピラに身ぐるみを剥がされる始末。いきなり異世界で路頭に迷う彼だったが、路上生活をしているらしき男、シオンと出会ったことで、少しだけ道が開けた。
漁れる残飯、眠れる舗道、そして裏ギルドで受けられる雑用仕事など――生きていく方法を、教えてくれたのだ。
この世界では『ミーツ』と名乗ることにし、安い賃金ながらも洗濯などの雑用をこなしていくうちに、金が貯まり余裕も生まれてきた。その頃、ミーツは気付く。自分の使っている魔法が、非常識なほどチートなことに――

【土壌改良】で死の荒野がSランク農園に!食べただけでレベルアップする野菜で、世界最強ギルド設立
黒崎隼人
ファンタジー
「え? これ、ただのトマトですよ?」
「いいえ、それは食べただけで魔力が全回復する『神の果実』です!」
ブラック企業で働き詰めだった青年は、異世界の名門貴族の三男・ノアとして転生する。
しかし、授かったスキルは【土壌改良】という地味なもの。
「攻撃魔法も使えない役立たず」と罵られ、魔物すら寄り付かない死の荒野へ追放されてしまう。
だが、彼らは知らなかった。
ノアのスキルは、現代の農業知識と合わせることで、荒れ果てた土地を「Sランク食材」が溢れる楽園に変えるチート能力だったことを!
伝説の魔獣(もふもふ)をキュウリ一本で手懐け、行き倒れた天才エルフを極上スープで救い出し、気づけば荒野には巨大な「農業ギルド」が誕生していた。
これは、本人がただ美味しい野菜を作ってのんびり暮らしたいだけなのに、周囲からは「世界を救う大賢者」と崇められてしまう、無自覚・最強の農業ファンタジー!

侯爵家三男からはじまる異世界チート冒険録 〜元プログラマー、スキルと現代知識で理想の異世界ライフ満喫中!〜【奨励賞】
のびすけ。
ファンタジー
気づけば侯爵家の三男として異世界に転生していた元プログラマー。
そこはどこか懐かしく、けれど想像以上に自由で――ちょっとだけ危険な世界。
幼い頃、命の危機をきっかけに前世の記憶が蘇り、
“とっておき”のチートで人生を再起動。
剣も魔法も、知識も商才も、全てを武器に少年は静かに準備を進めていく。
そして12歳。ついに彼は“新たなステージ”へと歩み出す。
これは、理想を形にするために動き出した少年の、
少し不思議で、ちょっとだけチートな異世界物語――その始まり。
【なろう掲載】

『急所』を突いてドロップ率100%。魔物から奪ったSSRスキルと最強装備で、俺だけが規格外の冒険者になる
仙道
ファンタジー
気がつくと、俺は森の中に立っていた。目の前には実体化した女神がいて、ここがステータスやスキルの存在する異世界だと告げてくる。女神は俺に特典として【鑑定】と、魔物の『ドロップ急所』が見える眼を与えて消えた。 この世界では、魔物は倒した際に稀にアイテムやスキルを落とす。俺の眼には、魔物の体に赤い光の点が見えた。そこを攻撃して倒せば、【鑑定】で表示されたレアアイテムが確実に手に入るのだ。 俺は実験のために、森でオークに襲われているエルフの少女を見つける。オークのドロップリストには『剛力の腕輪(攻撃力+500)』があった。俺はエルフを助けるというよりも、その腕輪が欲しくてオークの急所を剣で貫く。 オークは光となって消え、俺の手には強力な腕輪が残った。 腰を抜かしていたエルフの少女、リーナは俺の圧倒的な一撃と、伝説級の装備を平然と手に入れる姿を見て、俺に同行を申し出る。 俺は効率よく強くなるために、彼女を前衛の盾役として採用した。 こうして、欲しいドロップ品を狙って魔物を狩り続ける、俺の異世界冒険が始まる。
12/23 HOT男性向け1位
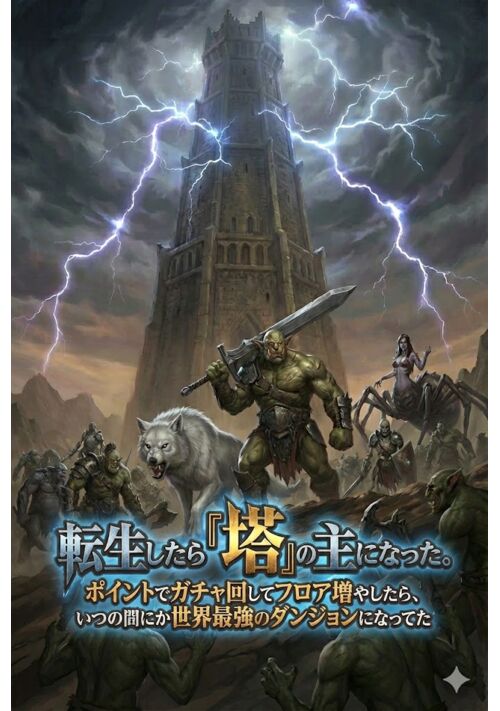
転生したら『塔』の主になった。ポイントでガチャ回してフロア増やしたら、いつの間にか世界最強のダンジョンになってた
季未
ファンタジー
【書き溜めがなくなるまで高頻度更新!♡٩( 'ω' )و】
気がつくとダンジョンコア(石)になっていた。
手持ちの資源はわずか。迫りくる野生の魔物やコアを狙う冒険者たち。 頼れるのは怪しげな「魔物ガチャ」だけ!?
傷ついた少女・リナを保護したことをきっかけにダンジョンは急速に進化を始める。
罠を張り巡らせた塔を建築し、資源を集め、強力な魔物をガチャで召喚!
人間と魔族、どこの勢力にも属さない独立した「最強のダンジョン」が今、産声を上げる!

転生貴族の領地経営〜現代日本の知識で異世界を豊かにする
初
ファンタジー
ローラシア王国の北のエルラント辺境伯家には天才的な少年、リーゼンしかしその少年は現代日本から転生してきた転生者だった。
リーゼンが洗礼をしたさい、圧倒的な量の加護やスキルが与えられた。その力を見込んだ父の辺境伯は12歳のリーゼンを辺境伯家の領地の北を治める代官とした。
これはそんなリーゼンが異世界の領地を経営し、豊かにしていく物語である。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















