26 / 67
26 ノーキンの心配
しおりを挟む
キッチンルームでの会議が終わって、ノーキンとマッドとあかりは、医療機器研究室へ移動した。
わかりやすくはあるが、山積み出てくるだろう問題をどうクリアするかの説明もなく、鑑定書一枚でクルラを受け入れる気になってひきあげていくさとる達を、ノーキンはもの珍しげに観察していた。
「お人好し、ってか、無謀、だなぁ。クルラって子、頭ん中、相当さわられているだろうに」
洗脳、暗示、条件付け。ゴテゴテにこじれた自己認識。
ノーキンから見ると、あまり仲よくしないほうが良いパーソナリティだ。
「受け入れに反対かい?頭を開いてみたいなとか、言うと思ったけど?」
意外そうな顔でマッドが聞く。
「症例として気に食わないとは言ってない。が、珍しくお前が正気を失って見えるし、誰が抱えるのかっていう純粋な疑問。あかりは、シューバの愛人としてあの子を飼っとく覚悟でもあるわけか?」
ノーキンは、しゃべりながら視線をあかりにスライドさせる。
「あるわけないでしょ。ってか、彼女の状態、そんなにひどいの?正直、マッドさんが、もちょっと踏み込んでる予想だったけど、遠慮がちよね。シューバも彼女の抱え方硬いし、実情どうよ?」
あかりがごねれば、シューバはクルラを秘書にすることも、同居させることもなかっただろうが、3年前はそれが最善の緊急避難だった。
あの時のクルラは、シューバ以外の人間に預けられたらパニックになったと思う。
ただ父親に連れてこられ、甚振られる女たちを見せられ、冷たい目が揺らがないのをほめられて帰っていく子ども。そのシューバを、レノは自分たちと同じ加害者側として認識していたが、クルラにとっては自分側の被害者だった。
飼い主のレノに命令され、かろうじて、自分と同じ闇を持つシューバの元に這って行く。それがやっと。
長年の虐待で、クルラは心が潰える寸前で、生きるためのエネルギーとでもいうべき耐性が、もうほとんど残ってはいなかったのだ。
それでも、落ち着いてくれば、と。
レノの支配と虐待から逃れて、食べて寝てやさしい時間が過ぎれば、きっと、光のもとに放ってやれるだろうと。あかりとマッドは、そう考えていた。
だがどうやら、二人の考えは少々甘かったらしい。
「シューバが、マッドにクルラを会わせたがらないんだよ。メイが大丈夫ならさとるに夜の世話させるか?」
無遠慮なノーキンの発言に、眉をひそめたのはマッドの方で、あかりの疑問はより直接的だ。
「夜の世話って、え、クルラ、性依存も入ってんの?」
もしそうなら、当然今その相手をしているのは愛しのシューバという結論になるわけだが、普通に事実確認をしようとするあかりが、ノーキンには興味深くて仕方がない。
「ぷ。あかり、君、シューバにもその調子でいくわけ?普通の男なら逃げちゃうよ?」
「逃げれるもんなら逃げてみ・・・じゃなかった、どんどん脱線してるじゃないのよ、ノーキン。何が引っかかってるわけ?」
「んー?だからマッドのこの顔だってば」
そういって、ノーキンはマッドの鼻先に人差し指を突きつけた。
確かにマッドは、彼にしては本当に珍しく、途方に暮れたような、行動をためらうような、そんな顔をしていた。
☆
じつはマッドは一度シューバのところに乗り込んでいる。
クルラの体は半年もたたずに正常に近づいたから、薬物依存の治療に入ろうとしたのだ。
「もうクルラがあなたの家に来て1年以上経ちました。大概クルラの治療に入りたいのですが。彼女は、どこですか?」
診察は、何度もした。
今のところクルラの薬物への依存度は、彼女のメンタルの安定に大きく左右されているように見える。
「・・・レノのところへ薬を取りに行った。すまない、どうしても本人が、行きたがった」
マッドとしては、シューバがクルラを誘導できるならあまり踏み込まずにいようと思っていたが、大概手を打たないと、心身の発達にひどい害が出かねない。
「いつまでそんなことを?あなたが無理なら、いいかげん、私が止めます」
シューバの瞳が揺れる。
「迎えに行くのは、やめてやってくれないか。本人も見られたくはないはずだ。薬をもらう前には必ず、再矯正されるといっていた。鞭打たれて這いつくばって薬を乞うところなど、見られたいはずがない」
「わかっていて行かせた?」
マッドの口ぶりに非難の響きが混ざる。
「いかせたくないに決まっている。だが、私の父親はな、私が薬を勝手に盛って、勝手に切り上げたから死んだ。あの我慢強いクルラが、もうだめだと言うのだぞ。止めたら、あいつも死んでしまうかもしれない」
はぁ。マッドがため息をつく。
やれやれ、あかりが手を離したシューバのメンタルはこんなにもヒビだらけか。彼は大丈夫だなどと、あかりの買い被りに思える。
「あなたの主張はわかりました。ショック症状にも自殺にも気を付けますし、万一のために集中治療室も開けておきます。つれもどしますね」
そういって屋敷を出て。
何のひねりもなく、まっすぐにレノの屋敷に向かう途中で、マッドはクルラに追いついた。
「こんにちは、クルラ。私を覚えていますか?」
「マッド先生・・」
シューバの家で何度も診察をした。覚えていないはずがない。それでも、警戒のまなざしと、硬い声。
「クルラ。どうしても今日、行かないとだめですか?私と一緒に、もう1日、頑張れるか試しませんか?」
「もう、むり、です」
首を横に振りながら、クルラが答える。
「レノのところへ行ったら、また意味もなく鞭でぶたれますよ」
「それでいいです」
「私が、してあげましょうか?」
「先生も、シューバさまも、やさしいから、むりです。まともな人は、みんな、むりです。」
「大丈夫ですよ。世間の人が言うには、私はサイコパスらしいですよ。気がまぎれるなら好きなだけ虐めてあげますから、帰りましょう?」
「夜も一緒にいてくれますか?」
「もちろんいいですよ。夜が怖いのですか?」
「はい、すごく」
「わかりました。おまかせなさい。ほら、いきますよ」
マッドはクルラを車に乗せて引きかえした。
家に着くまでに、クルラの体が何度も継続して震えた。
額に汗をうかべてうめき声を我慢しているクルラを、マッドは横抱きにかかえてシューバの家に入る。
膝上抱っこの状態でクルラに水を飲ませてやっているマッドを見て、その時はシューバも安心してドアを閉めた。
この日を境に、クルラは合法の薬でも禁断症状を我慢できるようになり、レノの屋敷に薬を取りに行くことはなくなった。
だがその一方で、クルラがひどくマッドにおびえるようになったのだ。
一体何をしたのか、マッドが説明することはなかった。
夜に悲鳴が上がった訳でも、血痕が残っていたわけでも、クルラの体に怪我ができた訳でもない。それでもシューバは、クルラの怯え具合から、さかのぼってマッドを警戒するようになった。
わかりやすくはあるが、山積み出てくるだろう問題をどうクリアするかの説明もなく、鑑定書一枚でクルラを受け入れる気になってひきあげていくさとる達を、ノーキンはもの珍しげに観察していた。
「お人好し、ってか、無謀、だなぁ。クルラって子、頭ん中、相当さわられているだろうに」
洗脳、暗示、条件付け。ゴテゴテにこじれた自己認識。
ノーキンから見ると、あまり仲よくしないほうが良いパーソナリティだ。
「受け入れに反対かい?頭を開いてみたいなとか、言うと思ったけど?」
意外そうな顔でマッドが聞く。
「症例として気に食わないとは言ってない。が、珍しくお前が正気を失って見えるし、誰が抱えるのかっていう純粋な疑問。あかりは、シューバの愛人としてあの子を飼っとく覚悟でもあるわけか?」
ノーキンは、しゃべりながら視線をあかりにスライドさせる。
「あるわけないでしょ。ってか、彼女の状態、そんなにひどいの?正直、マッドさんが、もちょっと踏み込んでる予想だったけど、遠慮がちよね。シューバも彼女の抱え方硬いし、実情どうよ?」
あかりがごねれば、シューバはクルラを秘書にすることも、同居させることもなかっただろうが、3年前はそれが最善の緊急避難だった。
あの時のクルラは、シューバ以外の人間に預けられたらパニックになったと思う。
ただ父親に連れてこられ、甚振られる女たちを見せられ、冷たい目が揺らがないのをほめられて帰っていく子ども。そのシューバを、レノは自分たちと同じ加害者側として認識していたが、クルラにとっては自分側の被害者だった。
飼い主のレノに命令され、かろうじて、自分と同じ闇を持つシューバの元に這って行く。それがやっと。
長年の虐待で、クルラは心が潰える寸前で、生きるためのエネルギーとでもいうべき耐性が、もうほとんど残ってはいなかったのだ。
それでも、落ち着いてくれば、と。
レノの支配と虐待から逃れて、食べて寝てやさしい時間が過ぎれば、きっと、光のもとに放ってやれるだろうと。あかりとマッドは、そう考えていた。
だがどうやら、二人の考えは少々甘かったらしい。
「シューバが、マッドにクルラを会わせたがらないんだよ。メイが大丈夫ならさとるに夜の世話させるか?」
無遠慮なノーキンの発言に、眉をひそめたのはマッドの方で、あかりの疑問はより直接的だ。
「夜の世話って、え、クルラ、性依存も入ってんの?」
もしそうなら、当然今その相手をしているのは愛しのシューバという結論になるわけだが、普通に事実確認をしようとするあかりが、ノーキンには興味深くて仕方がない。
「ぷ。あかり、君、シューバにもその調子でいくわけ?普通の男なら逃げちゃうよ?」
「逃げれるもんなら逃げてみ・・・じゃなかった、どんどん脱線してるじゃないのよ、ノーキン。何が引っかかってるわけ?」
「んー?だからマッドのこの顔だってば」
そういって、ノーキンはマッドの鼻先に人差し指を突きつけた。
確かにマッドは、彼にしては本当に珍しく、途方に暮れたような、行動をためらうような、そんな顔をしていた。
☆
じつはマッドは一度シューバのところに乗り込んでいる。
クルラの体は半年もたたずに正常に近づいたから、薬物依存の治療に入ろうとしたのだ。
「もうクルラがあなたの家に来て1年以上経ちました。大概クルラの治療に入りたいのですが。彼女は、どこですか?」
診察は、何度もした。
今のところクルラの薬物への依存度は、彼女のメンタルの安定に大きく左右されているように見える。
「・・・レノのところへ薬を取りに行った。すまない、どうしても本人が、行きたがった」
マッドとしては、シューバがクルラを誘導できるならあまり踏み込まずにいようと思っていたが、大概手を打たないと、心身の発達にひどい害が出かねない。
「いつまでそんなことを?あなたが無理なら、いいかげん、私が止めます」
シューバの瞳が揺れる。
「迎えに行くのは、やめてやってくれないか。本人も見られたくはないはずだ。薬をもらう前には必ず、再矯正されるといっていた。鞭打たれて這いつくばって薬を乞うところなど、見られたいはずがない」
「わかっていて行かせた?」
マッドの口ぶりに非難の響きが混ざる。
「いかせたくないに決まっている。だが、私の父親はな、私が薬を勝手に盛って、勝手に切り上げたから死んだ。あの我慢強いクルラが、もうだめだと言うのだぞ。止めたら、あいつも死んでしまうかもしれない」
はぁ。マッドがため息をつく。
やれやれ、あかりが手を離したシューバのメンタルはこんなにもヒビだらけか。彼は大丈夫だなどと、あかりの買い被りに思える。
「あなたの主張はわかりました。ショック症状にも自殺にも気を付けますし、万一のために集中治療室も開けておきます。つれもどしますね」
そういって屋敷を出て。
何のひねりもなく、まっすぐにレノの屋敷に向かう途中で、マッドはクルラに追いついた。
「こんにちは、クルラ。私を覚えていますか?」
「マッド先生・・」
シューバの家で何度も診察をした。覚えていないはずがない。それでも、警戒のまなざしと、硬い声。
「クルラ。どうしても今日、行かないとだめですか?私と一緒に、もう1日、頑張れるか試しませんか?」
「もう、むり、です」
首を横に振りながら、クルラが答える。
「レノのところへ行ったら、また意味もなく鞭でぶたれますよ」
「それでいいです」
「私が、してあげましょうか?」
「先生も、シューバさまも、やさしいから、むりです。まともな人は、みんな、むりです。」
「大丈夫ですよ。世間の人が言うには、私はサイコパスらしいですよ。気がまぎれるなら好きなだけ虐めてあげますから、帰りましょう?」
「夜も一緒にいてくれますか?」
「もちろんいいですよ。夜が怖いのですか?」
「はい、すごく」
「わかりました。おまかせなさい。ほら、いきますよ」
マッドはクルラを車に乗せて引きかえした。
家に着くまでに、クルラの体が何度も継続して震えた。
額に汗をうかべてうめき声を我慢しているクルラを、マッドは横抱きにかかえてシューバの家に入る。
膝上抱っこの状態でクルラに水を飲ませてやっているマッドを見て、その時はシューバも安心してドアを閉めた。
この日を境に、クルラは合法の薬でも禁断症状を我慢できるようになり、レノの屋敷に薬を取りに行くことはなくなった。
だがその一方で、クルラがひどくマッドにおびえるようになったのだ。
一体何をしたのか、マッドが説明することはなかった。
夜に悲鳴が上がった訳でも、血痕が残っていたわけでも、クルラの体に怪我ができた訳でもない。それでもシューバは、クルラの怯え具合から、さかのぼってマッドを警戒するようになった。
0
あなたにおすすめの小説

転生皇女セラフィナ
秋月真鳥
恋愛
公爵家のメイド・クラリッサは、幼い主君アルベルトを庇って十五歳で命を落とした。
目覚めたとき、彼女は皇女セラフィナとして生まれ変わっていた——死の、わずか翌日に。
赤ん坊の身体に十五歳の記憶を持ったまま、セラフィナは新しい人生を歩み始める。
皇帝に溺愛され、優しい母に抱かれ、兄に慈しまれる日々。
前世で冷遇されていた彼女にとって、家族の愛は眩しすぎるほどだった。
しかし、セラフィナの心は前世の主・アルベルトへの想いに揺れ続ける。
一歳のお披露目で再会した彼は、痩せ細り、クラリッサの死を今も引きずっていた。
「わたしは生涯結婚もしなければ子どもを持つこともない。わたしにはそんな幸福は許されない」
そう語るアルベルトの姿に、セラフィナは決意する。
言葉も満足に話せない。自由に動くこともできない。前世の記憶を明かすこともできない。
それでも、彼を救いたい。彼に幸せになってほしい。
転生した皇女が、小さな身体で挑む、長い長い物語が始まる。
※ノベルアップ+、小説家になろうでも掲載しています。

『冷徹社長の秘書をしていたら、いつの間にか専属の妻に選ばれました』
鍛高譚
恋愛
秘書課に異動してきた相沢結衣は、
仕事一筋で冷徹と噂される社長・西園寺蓮の専属秘書を務めることになる。
厳しい指示、膨大な業務、容赦のない会議――
最初はただ必死に食らいつくだけの日々だった。
だが、誰よりも真剣に仕事と向き合う蓮の姿に触れるうち、
結衣は秘書としての誇りを胸に、確かな成長を遂げていく。
そして、蓮もまた陰で彼女を支える姿勢と誠実な仕事ぶりに心を動かされ、
次第に結衣は“ただの秘書”ではなく、唯一無二の存在になっていく。
同期の嫉妬による妨害、ライバル会社の不正、社内の疑惑。
数々の試練が二人を襲うが――
蓮は揺るがない意志で結衣を守り抜き、
結衣もまた社長としてではなく、一人の男性として蓮を信じ続けた。
そしてある夜、蓮がようやく口にした言葉は、
秘書と社長の関係を静かに越えていく。
「これからの人生も、そばで支えてほしい。」
それは、彼が初めて見せた弱さであり、
結衣だけに向けた真剣な想いだった。
秘書として。
一人の女性として。
結衣は蓮の差し伸べた未来を、涙と共に受け取る――。
仕事も恋も全力で駆け抜ける、
“冷徹社長×秘書”のじれ甘オフィスラブストーリー、ここに完結。

魔法師団長の家政婦辞めたら溺愛されました
iru
恋愛
小説家になろうですでに完結済みの作品です。よければお気に入りブックマークなどお願いします。
両親と旅をしている途中、魔物に襲われているところを、魔法師団に助けられたティナ。
両親は亡くなってしまったが、両親が命をかけて守ってくれた自分の命を無駄にせず強く生きていこうと決めた。
しかし、肉親も家もないティナが途方に暮れていると、魔物から助けてくれ、怪我の入院まで面倒を見てくれた魔法師団の団長レオニスから彼の家政婦として住み込みで働かないと誘われた。
魔物から助けられた時から、ひどく憧れていたレオニスの誘いを、ティナはありがたく受ける事にした。
自分はただの家政婦だと強く言い聞かせて、日に日に膨らむ恋心を抑え込むティナだった。
一方、レオニスもティナにどんどん惹かれていっていた。
初めはなくなった妹のようで放っては置けないと家政婦として雇ったが、その健気な様子に強く惹かれていった。
恋人になりたいが、年上で雇い主。
もしティナも同じ気持ちでないなら仕事まで奪ってしまうのではないか。
そんな思いで一歩踏み出せないレオニスだった。
そんな中ある噂から、ティナはレオニスの家政婦を辞めて家を出る決意をする。
レオニスは思いを伝えてティナを引き止めることができるのか?
両片思いのすれ違いのお話です。

人狼な幼妻は夫が変態で困り果てている
井中かわず
恋愛
古い魔法契約によって強制的に結ばれたマリアとシュヤンの14歳年の離れた夫婦。それでも、シュヤンはマリアを愛していた。
それはもう深く愛していた。
変質的、偏執的、なんとも形容しがたいほどの狂気の愛情を注ぐシュヤン。異常さを感じながらも、なんだかんだでシュヤンが好きなマリア。
これもひとつの夫婦愛の形…なのかもしれない。
全3章、1日1章更新、完結済
※特に物語と言う物語はありません
※オチもありません
※ただひたすら時系列に沿って変態したりイチャイチャしたりする話が続きます。
※主人公の1人(夫)が気持ち悪いです。
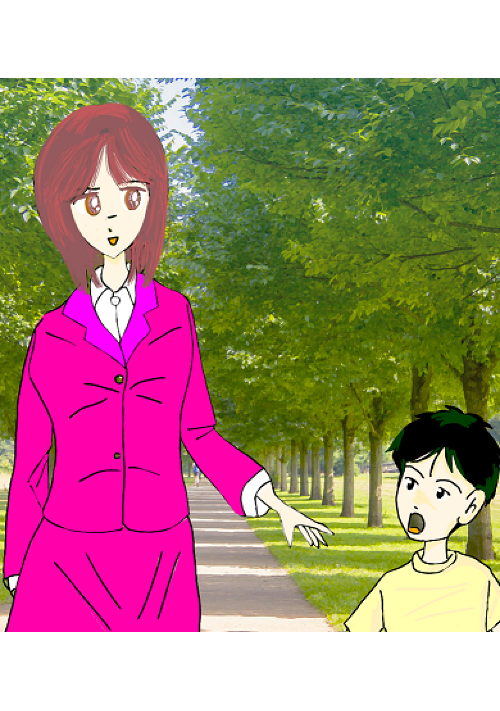
初恋の先生と結婚する為に幼稚園児からやり直すことになった俺
NOV
恋愛
俺の名前は『五十鈴 隆』 四十九歳の独身だ。
俺は最近、リストラにあい、それが理由で新たな職も探すことなく引きこもり生活が続いていた。
そんなある日、家に客が来る。
その客は喪服を着ている女性で俺の小・中学校時代の大先輩の鎌田志保さんだった。
志保さんは若い頃、幼稚園の先生をしていたんだが……
その志保さんは今から『幼稚園の先生時代』の先輩だった人の『告別式』に行くということだった。
しかし告別式に行く前にその亡くなった先輩がもしかすると俺の知っている先生かもしれないと思い俺に確認しに来たそうだ。
でも亡くなった先生の名前は『山本香織』……俺は名前を聞いても覚えていなかった。
しかし志保さんが帰り際に先輩の旧姓を言った途端、俺の身体に衝撃が走る。
旧姓「常谷香織」……
常谷……つ、つ、つねちゃん!! あの『つねちゃん』が……
亡くなった先輩、その人こそ俺が大好きだった人、一番お世話になった人、『常谷香織』先生だったのだ。
その時から俺の頭のでは『つねちゃん』との思い出が次から次へと甦ってくる。
そして俺は気付いたんだ。『つねちゃん』は俺の初恋の人なんだと……
それに気付くと同時に俺は卒園してから一度も『つねちゃん』に会っていなかったことを後悔する。
何で俺はあれだけ好きだった『つねちゃん』に会わなかったんだ!?
もし会っていたら……ずっと付き合いが続いていたら……俺がもっと大事にしていれば……俺が『つねちゃん』と結婚していたら……俺が『つねちゃん』を幸せにしてあげたかった……
あくる日、最近、頻繁に起こる頭痛に悩まされていた俺に今までで一番の激痛が起こった!!
あまりの激痛に布団に潜り込み目を閉じていたが少しずつ痛みが和らいできたので俺はゆっくり目を開けたのだが……
目を開けた瞬間、どこか懐かしい光景が目の前に現れる。
何で部屋にいるはずの俺が駅のプラットホームにいるんだ!?
母さんが俺よりも身長が高いうえに若く見えるぞ。
俺の手ってこんなにも小さかったか?
そ、それに……な、なぜ俺の目の前に……あ、あの、つねちゃんがいるんだ!?
これは夢なのか? それとも……

【完結済】25億で極道に売られた女。姐になります!
satomi
恋愛
昼夜問わずに働く18才の主人公南ユキ。
働けども働けどもその収入は両親に搾取されるだけ…。睡眠時間だって2時間程度しかないのに、それでもまだ働き口を増やせと言う両親。
早朝のバイトで頭は朦朧としていたけれど、そんな時にうちにやってきたのは白虎商事CEOの白川大雄さん。ポーンっと25億で私を買っていった。
そんな大雄さん、白虎商事のCEOとは別に白虎組組長の顔を持っていて、私に『姐』になれとのこと。
大丈夫なのかなぁ?

何もしない公爵夫人ですが、なぜか屋敷がうまく回っています
鷹 綾
恋愛
辺境公爵カーネル・クリスの妻となったフィレ・バーナード。
けれど彼女は、屋敷を仕切ることも、改革を行うことも、声高に意見を述べることもしなかった。
指示を出さない。
判断を奪わない。
必要以上に関わらない。
「何もしない夫人」として、ただ静かにそこにいるだけ。
それなのに――
いつの間にか屋敷は落ち着き、
使用人たちは迷わなくなり、
人は出入りし、戻り、また進んでいくようになる。
誰かに依存しない。
誰かを支配しない。
それでも確かに“安心できる場所”は、彼女の周りに残っていた。
必要とされなくてもいい。
役に立たなくてもいい。
それでも、ここにいていい。
これは、
「何もしない」ことで壊れなかった関係と、
「奪わない」ことで続いていった日常を描く、
静かでやさしい結婚生活の物語。

転移先で日本語を読めるというだけで最強の男に囚われました
桜あずみ
恋愛
異世界に転移して2年。
言葉も話せなかったこの国で、必死に努力して、やっとこの世界に馴染んできた。
しかし、ただ一つ、抜けなかった癖がある。
──ふとした瞬間に、日本語でメモを取ってしまうこと。
その一行が、彼の目に留まった。
「この文字を書いたのは、あなたですか?」
美しく、完璧で、どこか現実離れした男。
日本語という未知の文字に強い関心を示した彼は、やがて、少しずつ距離を詰めてくる。
最初はただの好奇心だと思っていた。
けれど、気づけば私は彼の手の中にいた。
彼の正体も、本当の目的も知らないまま。すべてを知ったときには、もう逃げられなかった。
毎日19時に更新予定です。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















