70 / 71
“花火の夜に”
【オマケDiary⑦】閉じ込めたい
しおりを挟む
「あれ……? ここって……」
亜楼に連れてこられた場所にうっすらと見覚えがあった海斗は、辺りをきょろきょろと見回しながらそう言った。少し前から花火は始まっていて、空に華やかな光が開くたびに、近くの観客たちから感嘆の声が上がるのが聞こえてくる。
「そ。ガキの頃、みんなで来たとこ」
大通りからは大きく外れ、住宅街の中にひっそりと存在している小さな公園に、亜楼は弟を連れてきていた。ジャングルジムと滑り台が一緒になった遊具と、ブランコとベンチだけで構成されているこじんまりとしたその公園では、確かに穴場なのか、人込みから逃れてきたような数組のカップルが一定の距離を保ってそれぞれに夜空を楽しんでいる。
「ははっ、懐かし……オレなんとなく記憶あるよ」
ここは、まだ家族になりたてだった頃、五人で花火を見に来たときに連れてきてもらった公園だった。やんちゃ盛りで長時間じっとしていられない海斗のことを配慮し、窮屈なメイン会場で観覧するのを避け、子供たちが自由にのびのびと花火が見られるようにと、秀春がわざわざ事前に調べて連れてきてくれた場所だ。
実際海斗は最初の方こそ花火に釘付けになって興奮していたが、しばらくすると飽きてジャングルジムやブランコで遊んでいた。
「おまえだけ秒で飽きて遊具で遊んでたよな。眞空と冬夜は行儀よく、秀春さんの隣で花火見てたのにさ」
亜楼が昔を思い返し、笑いながら言う。
「そんなこともあったな! ……あ、そういやさ」
ふと何かを思い出した海斗がまたきょろきょろと周りを見回し、目当てのものをすぐに見つけると、亜楼の手首をつかんで楽しそうに引っ張った。
「ちょっとこっち来て」
「あ? おい……」
嬉々としている弟には逆らえず、亜楼が素直に引っ張られてやる。
海斗が兄を引っ張って連れてきたのは、公園の隅に設置してある防災器具庫の裏側だった。家庭用の物置ほどの大きさの倉庫だったが、その後ろは完全な死角になっていて、公園の中ほどの様子はこちらからは何も見えない。
「覚えてる? オレが勝手にひとりでかくれんぼ始めて、ここに隠れてたの。……亜楼が慌てて探しにきてさ、こんな暗がりの中でかくれんぼなんてすんじゃねぇ危ねぇだろうがって、めちゃくちゃに怒って、さ……──っ!?」
思い出をなぞっている途中で、強い力で引き寄せられた。亜楼に、正面からがばっと抱きしめられる。
「ちょ、……っ」
「……あー、……やっとさわれた」
亜楼は心底安堵したように、海斗の肩にあごをのせて、ぐりぐりと頬を擦りつけた。死角なのをいいことに、遠慮なくじっくりと、弟の肌の感触を味わう。
「な、なんだよ……」
「すっげぇイラついてたから。……おまえも、簡単に他の男にさわらせてんじゃねぇよ」
「だから言い方っ……! 他の男って……」
照れながらもまんざらではない海斗が、すり寄ってくる亜楼をあっさりと受け入れる。浴衣姿の亜楼にときめいてしまったときから、今日はずっとこうされたかった気がした。
「他のやつにベタベタくっつかれてたら腹立つだろ、普通に」
「うぅ……、んなこと言われても……」
「俺だって今日はまだ、おまえにさわってなかったのに……」
甘えた声で亜楼がなおも海斗にすり寄れば、兄をなだめるように海斗のてのひらが亜楼の背をそっと抱く。浴衣越しに感じる弟の手にほっとしたのか、亜楼が小さくため息をついた。
「……なんもねぇとか、嘘じゃん」
ここに来る途中で聞かされた祥太との過去のあれこれに、亜楼が大人げなく拗ねてみせる。さっき互いの過去について掘り下げようとしたとき海斗は何もないと謙遜していたが、自覚がないだけで、本当はいろいろなところで様々な好意をその身に受けていたのだろうと思い、亜楼の胸が落ち着きなくざわついた。
「あいつぜってぇ海斗に気あっただろ。……つうか、今もあるな、あれは」
「しょ、小学生ンときの話だぞ!?」
「だったらなおさらヤダ。んな小せぇときからおまえのこと気に入ってるやつがいて、イラっとした。……むかつく」
「何と張り合ってんだか」
「……ずっと、俺の弟だったのに」
誰より近くに、いたはずなのに。
「俺より先に、おまえのいいとこに気づいてるやついて、むかつく……」
もっと早くに気づきたかったと、亜楼が自身の見る目のなさに落胆する。呑気にしているうちに、見知らぬ誰かにずいぶんと抜かされていたのだと思うと、悔しさだけが静かに募る。
「でも、普通思わねぇだろ、……弟のこと、好きになっていいなんてさ」
「……っ」
弱々しく耳元でそう言った亜楼につられて、海斗もわずかに声を震わせた。
「オレだって知らなかったよ……兄貴を好きになってもいいって知らなかったから、気づくの、すげぇ遅くなっちまった」
からだを少しだけ離し、互いの表情をそっと確認する。電灯も届いていない倉庫の裏の闇の中で、兄と弟は視線を絡め、やんわりと笑い合った。ぐるぐると迷走したのはお互い様だ。
「ま、早いうちに気づけてよかったわ。ジジィになるまでただの家族だったら、……こういうことも、できねぇし……」
そう言うと亜楼は、ちょっとだけ、と海斗に断りを入れてから、弟の浴衣の衿に手をかけた。激しく着崩れないように少しだけ衿元を開けると、海斗の鎖骨に口唇を寄せる。
「ん!?」
驚いて固まっている海斗に構わず、亜楼は弟の首や鎖骨辺りをちゅうちゅうと音を立てて吸い始めた。衿の下の肌を、唾液でしっとりと、広範囲に湿らせていく。
「おいっ、こんなとこ、っ、誰かに見られたら……っ」
「……みんな花火見てる」
返事のためだけに一旦口唇を離し、ダメか? と亜楼が海斗をせつなげに見た。
「……っ、なんで首……!?」
「ほんとはめちゃくちゃ口にキスしてぇけど、したら舌入れるし……、舌入れたら、ここでおまえのことひん剥いて犯しちまうから」
「おか……っ!?」
首で我慢してやってるのを偉いと褒めてくれと言わんばかりに、亜楼がしれっと物騒なことを言う。
「大丈夫、俺はジョーシキある大人なんでそこまでは。……けど、イラっとしてんのおさまんねぇから、首くらいは貸せよ」
「……っ、ばか……ジョーシキある大人は、こんなとこで首も吸わねぇんだよ……っ」
それでも首くらいならまぁいいかと結局海斗も絆されて、兄の荒ぶる愛を取りこぼすことのないように、しっかりと肌で受け止めた。
「……、……っ」
首だけとはいえ、好きな人にしつこく愛され続ければ海斗も平穏ではいられない。首をきつく吸い上げられたり、鎖骨を甘噛みされたりしているうちに、からだに力が入らなくなってくる。
花火が打ち上がる音が、絶えず聞こえていた。花火はここへ来る途中の道でなんとなく見上げただけで、それ以降は亜楼のことしか見ていない。
「あろ、……っ、ちょ……っと、」
兄の終わらない執着に、海斗の息があまく乱れ始める。これ以上されたら首以外のところにも口唇を期待してしまう気がして、一瞬だけ理性を取り戻した海斗が、亜楼の両肩に手を置いてぐいっと押し返した。常識を忘れかけている兄の手綱を引くのも、弟の役目だ。
「……なんだよ、いいとこなのに」
「もうダメだって。……ってか、そんなにイヤだった? その……祥太が、近くて」
いつにも増して自分にご執心な亜楼に、まさかこんなささいなことで嫉妬でもしてくれたのかと、海斗がおそるおそる尋ねる。
「亜楼も、オレのことで不安になったり、すんの……?」
訊かれた亜楼が、ふと険しい顔をして海斗の目を見た。訊いた海斗自身の目が、すでに不安そうに揺れている。
「ふざけてんのか?」
「え」
「はぁー……、なんでわっかんねぇかなぁ」
これ見よがしに盛大なため息をついたあと、亜楼は片手で海斗の腰を抱き、また自分の方に強く引き寄せた。もう片方の手は背中に滑らせ、ぎゅっと弟を掻き抱く。
「……おまえ、大学行くの? ……行くよなぁ……」
海斗の肩にあごを預けながら、急に亜楼がひどく淋しそうな声を出した。
「大学!? なんで今そんな話……」
話をすり替えられたのかと思い、亜楼の腕の中に大人しく収まりながらも、海斗が不審がる。
「もう行くのやめろよ……全部落ちたらいい……」
「縁起でもねぇこと言うなっ、……ほんとに全部落ちたらどうすんだよ!?」
全部落ちることが有り得ないことではないそこそこ崖っぷちの海斗が、ぎょっとして言い返した。
「……俺が養うからいい」
「なっ……」
亜楼がまた淋しそうに、ぽつりとこぼす。茶化しているのではないということは、すがるように背を抱く指の熱から充分に伝わってきていた。
「小さかったおまえがさ、堂園家っていう狭い空間の中で、俺の背中ちょろちょろ追っかけて、年上の俺にちょっとした憧れみてぇなの抱いて、……それで好きって思ってくれたんだとしたら、」
選択肢のないその狭い世界の中だけで、俺を選んでくれたんだとしたら。
「この先大学行ったり、バイト始めたり、就職したり……って、おまえが外の新しい世界どんどん知ってくのが、……俺は怖ぇよ」
海斗が広い世界を無邪気に知っていって、もっと魅力的な選択肢を見つけてしまって、いつか自分の元からすっと離れていってしまう未来を、想像なんてしたくないのに、ふとしたときに亜楼は想像してしまう。
さっき祥太を見たときだってそうだ。とられたくないと、本能が叫んだ。
「大学行ったら、さっきみてぇなチャラそうなやつ腐るほどいるだろうし、バイト先には俺より頼りになるような大人がゴロゴロいやがるだろうし……そういうの、全部、不安。なびかねぇ保証なんてねぇだろ? おまえ隙だらけだし……不安しかねぇよ」
「……!」
亜楼の口から出た不安という単語を、海斗が噛みしめるように聞く。
「……あの家ん中に、ずっと、閉じ込めときてぇな……」
できることなら、閉じ込めて、自分しか見えないようにしてやりたい。無垢で、外の世界を知らない幼い弟のまま、自分だけに焦がれていればいい。
「そしたらずっと、俺だけの弟で、俺だけのモンなのにな」
そうはできないもどかしさに、常に不安を心に飼っていることを、亜楼が包み隠さず教えてやる。
「……っ」
──あぁ、亜楼も、同じなんだ。
ささいなことで心が揺れて、あれこれ悩んで、沈んだり、浮上したり。それでもその都度想いをすり合わせて、一緒にいる。
これからもそうやって、恋をしていく。呆れるほど、好きでいる。
「亜楼、おまえ……っ、……オレのこと、すげぇ好きじゃん……」
海斗が耳たぶを茹で上げながら、渾身の照れ隠しを兄の耳元に食らわすと、
「だからずっとそう言ってる……、好きだよ……すげぇ好き」
と、予想外に本気のトーンで返ってきてしまい、海斗の瞳に不意打ちの感情がぶわっと染み出した。
「マジレスすんな……ばか」
次に海斗の顔を見たら口唇を食んでしまうことは目に見えていたが、亜楼はもう止められなかった。抱きしめていた腕を緩め、弟の顔をぐっとのぞき込むと、海斗は潤む瞳を隠すように、まつげを下方に向けている。
「……わりぃ、我慢すんの、やっぱ無理、っ……」
口唇を押しつければ、舌はすぐに混ざり合った。海斗も自分と同じように理性を飛ばしているのだとわかり、亜楼の息づかいがさらに荒くなる。
「んっ、……ん、ぅ……」
夜空は花火を響かせたままで、公園の中には他のカップルも何組かいるのに、二人の絡まった舌は離れることを知らない。
「ふっ、……ん、……」
花火と花火の間の、一瞬の静寂の中で、互いの唾を吸い上げる音がいやらしく耳に残る。それは花火の轟音よりも、鮮明で。
「ん、……んんっ、ん、……」
強く求め合っているくちづけが脳みそを盛大に溶かし、こっからどうする? マジでここでひん剥くか? と亜楼が血迷い始めたとき、帯に挟んでいた亜楼のスマホがまた震え出した。兄に抱き寄せられている弟にもその振動は伝わり、口唇がやっと離れる。
「あー……、……さっきのトラブルの、続きかも……」
ひどく困った顔をして渋々携帯に手を伸ばした亜楼の右手を、海斗の手がぐっと押さえつけた。
「!?」
「……っ、出んなよ、っ……」
キスでぐずぐずになってしまった目をさらに潤ませて、海斗が切に訴える。
「他の男の電話になんか、出んな……っ」
電話越しでも、今この瞬間の亜楼を、誰にもとられたくなくて。
亜楼が素直に不安を打ち明けてくれたように、海斗ももう遠慮なく、恋人を独占したいと主張する。
今は、オレだけ……、オレだけ見て──。
「っ、……やめんなよ、っ……キス」
「!」
亜楼は一瞬だけ目を見張ったが、すぐに表情を崩してふっと海斗に笑いかけた。スマホではなく、自分の手を乱暴に押さえつけてきた海斗の手を取り、指をそっと絡める。
「かわいーとこ、あんじゃん」
口唇と口唇は、そのまま磁石のように強い力で合わさった。どこまで深く入っても足りなくて、口内をまさぐる舌は、貪欲にもうひとつの舌を追いかけ回す。
「ん……、っ……ん……はぁっ」
亜楼の帯の中では、着信を知らせる振動が長く続いていた。何度か切れても、しつこくまた掛かってきている。
やまない振動を浴びながら夢中でくちづければ、特別な罪悪感が二人の情欲を最高に煽った。
「電話鳴ってんの無視してキスすんのって、すっげぇ興奮しねぇ……?」
「する……やばい……」
すっかりくたっとしてしまった海斗のからだを支えながら、ご機嫌な亜楼が弟の耳元でやさしくささやく。
「……今から、ホテルでも行くか」
「はっ!? なっ、んで……」
海斗が大きく肩を震わせて、あからさまにびくっとした。
「なんでって……、ここでひん剥かれるよりはマシだろ?」
「う……」
「それに、たまにはおまえに思いきり声出させてやりてぇし」
すっかり機嫌を直した亜楼は饒舌に、調子のいいことばかりを次々と連ねる。
「いいだろー? 世の中のカップルはみんな、花火とクリスマスの夜はヤるって決まってんだよ」
「んだよそれ……。つーか、オレ花火ちゃんと見てねぇし、まだりんご飴しか食ってねぇんだけど」
まだ全然花火大会を満喫してないのに、と海斗が小さく膨れてみせると、
「ははっ、……ま、それはまた来年な?」
と、亜楼が屈託なく笑って答える。
……来年、か。
なんの迷いもなく未来の約束をくれた亜楼に、じんと胸をあたたかくさせながら。
亜楼に触れられたままだった手を、海斗が静かにぎゅっと握り返した。離れがたい指先は、これから始まる長い夜を想像して、互いにもうじりじりと熱い。
「……いいよ。ホテル、行こ……」
亜楼に連れてこられた場所にうっすらと見覚えがあった海斗は、辺りをきょろきょろと見回しながらそう言った。少し前から花火は始まっていて、空に華やかな光が開くたびに、近くの観客たちから感嘆の声が上がるのが聞こえてくる。
「そ。ガキの頃、みんなで来たとこ」
大通りからは大きく外れ、住宅街の中にひっそりと存在している小さな公園に、亜楼は弟を連れてきていた。ジャングルジムと滑り台が一緒になった遊具と、ブランコとベンチだけで構成されているこじんまりとしたその公園では、確かに穴場なのか、人込みから逃れてきたような数組のカップルが一定の距離を保ってそれぞれに夜空を楽しんでいる。
「ははっ、懐かし……オレなんとなく記憶あるよ」
ここは、まだ家族になりたてだった頃、五人で花火を見に来たときに連れてきてもらった公園だった。やんちゃ盛りで長時間じっとしていられない海斗のことを配慮し、窮屈なメイン会場で観覧するのを避け、子供たちが自由にのびのびと花火が見られるようにと、秀春がわざわざ事前に調べて連れてきてくれた場所だ。
実際海斗は最初の方こそ花火に釘付けになって興奮していたが、しばらくすると飽きてジャングルジムやブランコで遊んでいた。
「おまえだけ秒で飽きて遊具で遊んでたよな。眞空と冬夜は行儀よく、秀春さんの隣で花火見てたのにさ」
亜楼が昔を思い返し、笑いながら言う。
「そんなこともあったな! ……あ、そういやさ」
ふと何かを思い出した海斗がまたきょろきょろと周りを見回し、目当てのものをすぐに見つけると、亜楼の手首をつかんで楽しそうに引っ張った。
「ちょっとこっち来て」
「あ? おい……」
嬉々としている弟には逆らえず、亜楼が素直に引っ張られてやる。
海斗が兄を引っ張って連れてきたのは、公園の隅に設置してある防災器具庫の裏側だった。家庭用の物置ほどの大きさの倉庫だったが、その後ろは完全な死角になっていて、公園の中ほどの様子はこちらからは何も見えない。
「覚えてる? オレが勝手にひとりでかくれんぼ始めて、ここに隠れてたの。……亜楼が慌てて探しにきてさ、こんな暗がりの中でかくれんぼなんてすんじゃねぇ危ねぇだろうがって、めちゃくちゃに怒って、さ……──っ!?」
思い出をなぞっている途中で、強い力で引き寄せられた。亜楼に、正面からがばっと抱きしめられる。
「ちょ、……っ」
「……あー、……やっとさわれた」
亜楼は心底安堵したように、海斗の肩にあごをのせて、ぐりぐりと頬を擦りつけた。死角なのをいいことに、遠慮なくじっくりと、弟の肌の感触を味わう。
「な、なんだよ……」
「すっげぇイラついてたから。……おまえも、簡単に他の男にさわらせてんじゃねぇよ」
「だから言い方っ……! 他の男って……」
照れながらもまんざらではない海斗が、すり寄ってくる亜楼をあっさりと受け入れる。浴衣姿の亜楼にときめいてしまったときから、今日はずっとこうされたかった気がした。
「他のやつにベタベタくっつかれてたら腹立つだろ、普通に」
「うぅ……、んなこと言われても……」
「俺だって今日はまだ、おまえにさわってなかったのに……」
甘えた声で亜楼がなおも海斗にすり寄れば、兄をなだめるように海斗のてのひらが亜楼の背をそっと抱く。浴衣越しに感じる弟の手にほっとしたのか、亜楼が小さくため息をついた。
「……なんもねぇとか、嘘じゃん」
ここに来る途中で聞かされた祥太との過去のあれこれに、亜楼が大人げなく拗ねてみせる。さっき互いの過去について掘り下げようとしたとき海斗は何もないと謙遜していたが、自覚がないだけで、本当はいろいろなところで様々な好意をその身に受けていたのだろうと思い、亜楼の胸が落ち着きなくざわついた。
「あいつぜってぇ海斗に気あっただろ。……つうか、今もあるな、あれは」
「しょ、小学生ンときの話だぞ!?」
「だったらなおさらヤダ。んな小せぇときからおまえのこと気に入ってるやつがいて、イラっとした。……むかつく」
「何と張り合ってんだか」
「……ずっと、俺の弟だったのに」
誰より近くに、いたはずなのに。
「俺より先に、おまえのいいとこに気づいてるやついて、むかつく……」
もっと早くに気づきたかったと、亜楼が自身の見る目のなさに落胆する。呑気にしているうちに、見知らぬ誰かにずいぶんと抜かされていたのだと思うと、悔しさだけが静かに募る。
「でも、普通思わねぇだろ、……弟のこと、好きになっていいなんてさ」
「……っ」
弱々しく耳元でそう言った亜楼につられて、海斗もわずかに声を震わせた。
「オレだって知らなかったよ……兄貴を好きになってもいいって知らなかったから、気づくの、すげぇ遅くなっちまった」
からだを少しだけ離し、互いの表情をそっと確認する。電灯も届いていない倉庫の裏の闇の中で、兄と弟は視線を絡め、やんわりと笑い合った。ぐるぐると迷走したのはお互い様だ。
「ま、早いうちに気づけてよかったわ。ジジィになるまでただの家族だったら、……こういうことも、できねぇし……」
そう言うと亜楼は、ちょっとだけ、と海斗に断りを入れてから、弟の浴衣の衿に手をかけた。激しく着崩れないように少しだけ衿元を開けると、海斗の鎖骨に口唇を寄せる。
「ん!?」
驚いて固まっている海斗に構わず、亜楼は弟の首や鎖骨辺りをちゅうちゅうと音を立てて吸い始めた。衿の下の肌を、唾液でしっとりと、広範囲に湿らせていく。
「おいっ、こんなとこ、っ、誰かに見られたら……っ」
「……みんな花火見てる」
返事のためだけに一旦口唇を離し、ダメか? と亜楼が海斗をせつなげに見た。
「……っ、なんで首……!?」
「ほんとはめちゃくちゃ口にキスしてぇけど、したら舌入れるし……、舌入れたら、ここでおまえのことひん剥いて犯しちまうから」
「おか……っ!?」
首で我慢してやってるのを偉いと褒めてくれと言わんばかりに、亜楼がしれっと物騒なことを言う。
「大丈夫、俺はジョーシキある大人なんでそこまでは。……けど、イラっとしてんのおさまんねぇから、首くらいは貸せよ」
「……っ、ばか……ジョーシキある大人は、こんなとこで首も吸わねぇんだよ……っ」
それでも首くらいならまぁいいかと結局海斗も絆されて、兄の荒ぶる愛を取りこぼすことのないように、しっかりと肌で受け止めた。
「……、……っ」
首だけとはいえ、好きな人にしつこく愛され続ければ海斗も平穏ではいられない。首をきつく吸い上げられたり、鎖骨を甘噛みされたりしているうちに、からだに力が入らなくなってくる。
花火が打ち上がる音が、絶えず聞こえていた。花火はここへ来る途中の道でなんとなく見上げただけで、それ以降は亜楼のことしか見ていない。
「あろ、……っ、ちょ……っと、」
兄の終わらない執着に、海斗の息があまく乱れ始める。これ以上されたら首以外のところにも口唇を期待してしまう気がして、一瞬だけ理性を取り戻した海斗が、亜楼の両肩に手を置いてぐいっと押し返した。常識を忘れかけている兄の手綱を引くのも、弟の役目だ。
「……なんだよ、いいとこなのに」
「もうダメだって。……ってか、そんなにイヤだった? その……祥太が、近くて」
いつにも増して自分にご執心な亜楼に、まさかこんなささいなことで嫉妬でもしてくれたのかと、海斗がおそるおそる尋ねる。
「亜楼も、オレのことで不安になったり、すんの……?」
訊かれた亜楼が、ふと険しい顔をして海斗の目を見た。訊いた海斗自身の目が、すでに不安そうに揺れている。
「ふざけてんのか?」
「え」
「はぁー……、なんでわっかんねぇかなぁ」
これ見よがしに盛大なため息をついたあと、亜楼は片手で海斗の腰を抱き、また自分の方に強く引き寄せた。もう片方の手は背中に滑らせ、ぎゅっと弟を掻き抱く。
「……おまえ、大学行くの? ……行くよなぁ……」
海斗の肩にあごを預けながら、急に亜楼がひどく淋しそうな声を出した。
「大学!? なんで今そんな話……」
話をすり替えられたのかと思い、亜楼の腕の中に大人しく収まりながらも、海斗が不審がる。
「もう行くのやめろよ……全部落ちたらいい……」
「縁起でもねぇこと言うなっ、……ほんとに全部落ちたらどうすんだよ!?」
全部落ちることが有り得ないことではないそこそこ崖っぷちの海斗が、ぎょっとして言い返した。
「……俺が養うからいい」
「なっ……」
亜楼がまた淋しそうに、ぽつりとこぼす。茶化しているのではないということは、すがるように背を抱く指の熱から充分に伝わってきていた。
「小さかったおまえがさ、堂園家っていう狭い空間の中で、俺の背中ちょろちょろ追っかけて、年上の俺にちょっとした憧れみてぇなの抱いて、……それで好きって思ってくれたんだとしたら、」
選択肢のないその狭い世界の中だけで、俺を選んでくれたんだとしたら。
「この先大学行ったり、バイト始めたり、就職したり……って、おまえが外の新しい世界どんどん知ってくのが、……俺は怖ぇよ」
海斗が広い世界を無邪気に知っていって、もっと魅力的な選択肢を見つけてしまって、いつか自分の元からすっと離れていってしまう未来を、想像なんてしたくないのに、ふとしたときに亜楼は想像してしまう。
さっき祥太を見たときだってそうだ。とられたくないと、本能が叫んだ。
「大学行ったら、さっきみてぇなチャラそうなやつ腐るほどいるだろうし、バイト先には俺より頼りになるような大人がゴロゴロいやがるだろうし……そういうの、全部、不安。なびかねぇ保証なんてねぇだろ? おまえ隙だらけだし……不安しかねぇよ」
「……!」
亜楼の口から出た不安という単語を、海斗が噛みしめるように聞く。
「……あの家ん中に、ずっと、閉じ込めときてぇな……」
できることなら、閉じ込めて、自分しか見えないようにしてやりたい。無垢で、外の世界を知らない幼い弟のまま、自分だけに焦がれていればいい。
「そしたらずっと、俺だけの弟で、俺だけのモンなのにな」
そうはできないもどかしさに、常に不安を心に飼っていることを、亜楼が包み隠さず教えてやる。
「……っ」
──あぁ、亜楼も、同じなんだ。
ささいなことで心が揺れて、あれこれ悩んで、沈んだり、浮上したり。それでもその都度想いをすり合わせて、一緒にいる。
これからもそうやって、恋をしていく。呆れるほど、好きでいる。
「亜楼、おまえ……っ、……オレのこと、すげぇ好きじゃん……」
海斗が耳たぶを茹で上げながら、渾身の照れ隠しを兄の耳元に食らわすと、
「だからずっとそう言ってる……、好きだよ……すげぇ好き」
と、予想外に本気のトーンで返ってきてしまい、海斗の瞳に不意打ちの感情がぶわっと染み出した。
「マジレスすんな……ばか」
次に海斗の顔を見たら口唇を食んでしまうことは目に見えていたが、亜楼はもう止められなかった。抱きしめていた腕を緩め、弟の顔をぐっとのぞき込むと、海斗は潤む瞳を隠すように、まつげを下方に向けている。
「……わりぃ、我慢すんの、やっぱ無理、っ……」
口唇を押しつければ、舌はすぐに混ざり合った。海斗も自分と同じように理性を飛ばしているのだとわかり、亜楼の息づかいがさらに荒くなる。
「んっ、……ん、ぅ……」
夜空は花火を響かせたままで、公園の中には他のカップルも何組かいるのに、二人の絡まった舌は離れることを知らない。
「ふっ、……ん、……」
花火と花火の間の、一瞬の静寂の中で、互いの唾を吸い上げる音がいやらしく耳に残る。それは花火の轟音よりも、鮮明で。
「ん、……んんっ、ん、……」
強く求め合っているくちづけが脳みそを盛大に溶かし、こっからどうする? マジでここでひん剥くか? と亜楼が血迷い始めたとき、帯に挟んでいた亜楼のスマホがまた震え出した。兄に抱き寄せられている弟にもその振動は伝わり、口唇がやっと離れる。
「あー……、……さっきのトラブルの、続きかも……」
ひどく困った顔をして渋々携帯に手を伸ばした亜楼の右手を、海斗の手がぐっと押さえつけた。
「!?」
「……っ、出んなよ、っ……」
キスでぐずぐずになってしまった目をさらに潤ませて、海斗が切に訴える。
「他の男の電話になんか、出んな……っ」
電話越しでも、今この瞬間の亜楼を、誰にもとられたくなくて。
亜楼が素直に不安を打ち明けてくれたように、海斗ももう遠慮なく、恋人を独占したいと主張する。
今は、オレだけ……、オレだけ見て──。
「っ、……やめんなよ、っ……キス」
「!」
亜楼は一瞬だけ目を見張ったが、すぐに表情を崩してふっと海斗に笑いかけた。スマホではなく、自分の手を乱暴に押さえつけてきた海斗の手を取り、指をそっと絡める。
「かわいーとこ、あんじゃん」
口唇と口唇は、そのまま磁石のように強い力で合わさった。どこまで深く入っても足りなくて、口内をまさぐる舌は、貪欲にもうひとつの舌を追いかけ回す。
「ん……、っ……ん……はぁっ」
亜楼の帯の中では、着信を知らせる振動が長く続いていた。何度か切れても、しつこくまた掛かってきている。
やまない振動を浴びながら夢中でくちづければ、特別な罪悪感が二人の情欲を最高に煽った。
「電話鳴ってんの無視してキスすんのって、すっげぇ興奮しねぇ……?」
「する……やばい……」
すっかりくたっとしてしまった海斗のからだを支えながら、ご機嫌な亜楼が弟の耳元でやさしくささやく。
「……今から、ホテルでも行くか」
「はっ!? なっ、んで……」
海斗が大きく肩を震わせて、あからさまにびくっとした。
「なんでって……、ここでひん剥かれるよりはマシだろ?」
「う……」
「それに、たまにはおまえに思いきり声出させてやりてぇし」
すっかり機嫌を直した亜楼は饒舌に、調子のいいことばかりを次々と連ねる。
「いいだろー? 世の中のカップルはみんな、花火とクリスマスの夜はヤるって決まってんだよ」
「んだよそれ……。つーか、オレ花火ちゃんと見てねぇし、まだりんご飴しか食ってねぇんだけど」
まだ全然花火大会を満喫してないのに、と海斗が小さく膨れてみせると、
「ははっ、……ま、それはまた来年な?」
と、亜楼が屈託なく笑って答える。
……来年、か。
なんの迷いもなく未来の約束をくれた亜楼に、じんと胸をあたたかくさせながら。
亜楼に触れられたままだった手を、海斗が静かにぎゅっと握り返した。離れがたい指先は、これから始まる長い夜を想像して、互いにもうじりじりと熱い。
「……いいよ。ホテル、行こ……」
16
あなたにおすすめの小説
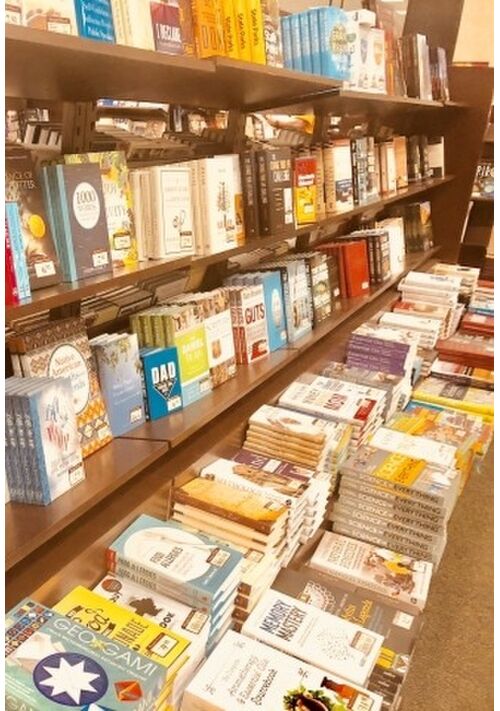
【完結】言えない言葉
未希かずは(Miki)
BL
双子の弟・水瀬碧依は、明るい兄・翼と比べられ、自信がない引っ込み思案な大学生。
同じゼミの気さくで眩しい如月大和に密かに恋するが、話しかける勇気はない。
ある日、碧依は兄になりすまし、本屋のバイトで大和に近づく大胆な計画を立てる。
兄の笑顔で大和と心を通わせる碧依だが、嘘の自分に葛藤し……。
すれ違いを経て本当の想いを伝える、切なく甘い青春BLストーリー。
第1回青春BLカップ参加作品です。
1章 「出会い」が長くなってしまったので、前後編に分けました。
2章、3章も長くなってしまって、分けました。碧依の恋心を丁寧に書き直しました。(2025/9/2 18:40)

夢の続きの話をしよう
木原あざみ
BL
歯止めのきかなくなる前に離れようと思った。
隣になんていたくないと思った。
**
サッカー選手×大学生。すれ違い過多の両方向片思いなお話です。他サイトにて完結済みの作品を転載しています。本編総文字数25万字強。
表紙は同人誌にした際に木久劇美和さまに描いていただいたものを使用しています(※こちらに載せている本文は同人誌用に改稿する前のものになります)。

【完】君に届かない声
未希かずは(Miki)
BL
内気で友達の少ない高校生・花森眞琴は、優しくて完璧な幼なじみの長谷川匠海に密かな恋心を抱いていた。
ある日、匠海が誰かを「そばで守りたい」と話すのを耳にした眞琴。匠海の幸せのために身を引こうと、クラスの人気者・和馬に偽の恋人役を頼むが…。
すれ違う高校生二人の不器用な恋のお話です。
執着囲い込み☓健気。ハピエンです。

告白ごっこ
みなみ ゆうき
BL
ある事情から極力目立たず地味にひっそりと学園生活を送っていた瑠衣(るい)。
ある日偶然に自分をターゲットに告白という名の罰ゲームが行われることを知ってしまう。それを実行することになったのは学園の人気者で同級生の昴流(すばる)。
更に1ヶ月以内に昴流が瑠衣を口説き落とし好きだと言わせることが出来るかということを新しい賭けにしようとしている事に憤りを覚えた瑠衣は一計を案じ、自分の方から先に告白をし、その直後に全てを知っていると種明かしをすることで、早々に馬鹿げたゲームに決着をつけてやろうと考える。しかし、この告白が原因で事態は瑠衣の想定とは違った方向に動きだし……。
テンプレの罰ゲーム告白ものです。
表紙イラストは、かさしま様より描いていただきました!
ムーンライトノベルズでも同時公開。



シスルの花束を
碧月 晶
BL
年下俺様モデル×年上訳あり青年
~人物紹介~
○氷室 三門(ひむろ みかど)
・攻め(主人公)
・23歳、身長178cm
・モデル
・俺様な性格、短気
・訳あって、雨月の所に転がり込んだ
○寒河江 雨月(さがえ うげつ)
・受け
・26歳、身長170cm
・常に無表情で、人形のように顔が整っている
・童顔
※作中に英会話が出てきますが、翻訳アプリで訳したため正しいとは限りません。
※濡れ場があるシーンはタイトルに*マークが付きます。
※基本、三門視点で進みます。
※表紙絵は作者が生成AIで試しに作ってみたものです。

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















