130 / 157
【番外】わたしはあなたのものであなたはわたしのもの(後)*性的な描写があります*
しおりを挟む
乱れた息も、それまでの彼とは全く違う荒々しさだ。貪るような口付けに翻弄されるしかないシィンの視界に、ダンジァの手が枕元に備えられている香油瓶に伸びるのが見える。それを取ると、彼は手荒く自身の性器にぶちまけた。普段の丁寧な、丁重な振る舞いの彼とは別人のようだ。
蜜のような甘い香りが広がる中、ダンジァは溢れた香油で確かめるようにシィンの後孔を探る。そしてシィンの脚を大きく開かさせるように抱えると、次の瞬間、一気に挿し入ってきた。
「ぁあぁあァん……っ……!」
その強烈な快感に、堪えていた欲望が一気に噴き上がる。
ダンジァと一緒に達したかったのに、入れられただけで吐精してしまった。堪えられなかった自身の身体の淫蕩さに、シィンは耳まで真っ赤になる。
だがダンジァは、そんなシィンの狼狽さえ愛おしむように、熱い耳朶に、頬に、繰り返し口付けてくる。
「シィン様……あぁ……シィン様はあんなことをどこで覚えられたのですか……? あんなに淫らな——可愛らしい——蠱惑的な様を——」
そして途切れ途切れに聞こえるのは、興奮極まったような熱っぽい彼の声だ。
と同時に繰り返し抜き挿しされ、揺さぶられ、抉られては突き上げられ、シィンはダンジァの腕の中で溢れんばかりの快感をただただ注がれ続ける。
「優しく抱いて差し上げなくてはと思っていても、あんな姿を見せられては……」
「ぁ……あ、あ、ァ……ダン……ダンジァ……ぁ……」
「あれは自分だけに見せたものだと仰ってください。これまでもこれからも、自分だけが見られるシィン様の特別なお姿なのだと——」
でなければ嫉妬でおかしくなります——。
と、ますます情熱的に腰をすすめてくるダンジァに、シィンの胸は甘酸っぱく軋む。わかりきっている答えを望む彼が可愛らしい。わかりきっている言葉を欲しがる彼が愛しい。
「ダ……ん、ぁ……そ、んな、の、決まって……っ……んっ……」
だからすぐさま応じようとしたシィンの声は、ダンジァの唇に奪われる。
繋がっていてもまだ足りないとばかりに深く舌を挿し入れられ、同時に激しく腰を打ち付けられると、目が眩むほどの強烈な快楽に、喘ぐことすら満足にできなくなる。
一度達したはずの性器も既にまた硬く形を変え、再びの吐精を望んで震えている。
「ダン……ぁ……ダ、メ……ぁ……ああっ……ぁ……いぃ……っ」
何を発しているのか、自分がどんな格好をしているのかもよくわからない。
久しぶりの逢瀬。久しぶりの二人だけの時間。久しぶりの彼との抱擁、口付け。そして繋がり——。その悦びの全てを受け止め堪能し尽くしながら、シィンは甘く切なく鳴き声を上げ続ける。
「シィン様……中が、こんなに熱く……」
「あぁ……っ……ぁひ、ぁ……」
「溶けそうです……うねって……締め付けてきて……」
「ぁ……ダンジァ、ぁ……ぁ、そこ、ぁ……」
「ここですか?」
「あぁっ……! ァ、ぁ、んっ、そこ……そこ、が……ぃ……きもち、ぃ……っ」
内壁を突かれるたびに髪を乱してガクガク頷くシィンの口の端から、淫らな声と共に飲み下せなかった涎が滴り落ちる。繰り返される口付けの合間、それをぺろぺろと舐めとるダンジァの姿は、どこか甘える馬の仕草のようでもある。
けれど彼は——ただの大人しい馬じゃない。
思慮深く穏やかなだけの騏驥じゃない。
二人きりでいる時だけに見せる、別の姿。別の横顔。
自分が、こうして彼と二人きりでいる時は、王子でなくただのシィンになるように。
誰も知らない自分の姿。
自分しか知らない彼の姿。
それを見せ合え、愛し合える相手の、なんと素晴らしく得難いことか。
「ダンジァ……ダン……ダン……」
「シィン様……シィン様——愛しています……」
「ダンジァ……好きだ……わたしの——わたしのダンジァ——」
「シィン……様……っ」
次第に激しさを増す抽送に、互いの息も上がり、声も上擦り掠れていく。
しっとりと湿った肌が吸い付き合い、香りとともに混じり合うようだ。
ダンジァの額にも汗が浮いている。彼が動くたび、繋がっている部分が快感を伝える淫猥な水音を立て、シィンを官能の沼へ沈めていく。
酔ったようにクラクラする。
気持ちがいい——もっと——気持ちがいい——。そんなことしか考えられくなる。
達したい。けれどずっとこのままでいたい。ずっとこのままがいい。ずっとずっと——彼の腕の中で彼の香りに包まれて彼と繋がり一つになっていたい——。
「ダンジァ……ぁ……抱き、しめて……っ……きつく……っ」
「シィン様——」
「ダンジァ……ダンジァ……あぁ……」
感極まって溢れた涙を、温かな唇が静かに掬っていく。こめかみに、額に口付けられる。髪を撫で上げられる。
黒く美しい瞳が見つめてくる。
激しさも優しさも同じ彼で、全部全部わたしのもの——。
「ダ……ぁ……も、ぅ……っ……」
くり返される律動と絶え間のない愛撫に堪らず、シィンはとうとう懇願の声をあげる。
達したい——今度こそ一緒に——。
縋るように見つめると、情熱を宿していた夜の色の瞳が微笑むように細められる。抱きつくと、いっそう強く抱き返される。絶対に離さないとでも言うように。あなたはわたしのものなのだと、伝えてくるかのように。
そう——。
それでいい。
ここにいるのはただの恋人同士の二人。
だからわたしはあなたのものであなたはわたしのもの。
「ぁ……あ、ぁ、ああっ——ァ——」
再開される律動にされるまま、シィンは声を上げ身をくねらせる。より深く咥え込もうとするかのように自ら腰を揺すり、抱きしめる身体に爪をたて、気持ちがよくて堪らないのだと伝えると、熟れた肉筒を満たすダンジァの屹立がいっそう大きさと硬さを増す。
「シィン様——」
「ダンジァ……ダン……っぁ……すご……すご、ぃ……っ」
「ッ——」
「な、か……熱、ぃ……大き……凄ぃ……ぃ……っ」
忘我の快感の中、羞恥も忘れた淫らな声を上げ、ぎゅうっとしがみついたその瞬間。
「ァ……ぁ、ひァ……ああぁっ——!」
背が軋むほど抱きしめられ、奥の奥に熱が叩き込まれる。
同時に、昂りきったシィンの性器から熱い飛沫が噴き零れる。
目が眩むような、絶頂。
「ふぁ……ぁ……っん……ぁ……」
吐精の余韻に、シィンの身体がヒクヒクと震える。
その身体をきつくきつく抱きしめられ、ダンジァの呻くような低い声が届いた直後——。身体の奥で性器が脈打ち、どくりと温かなものが注がれる。
体奥に染み渡っていくダンジァの欲。その感触にうっとりと背を震わせるシィンの唇に、愛の囁きとともに、吐息混じりのダンジァの唇が触れた。
⭐︎
「……そういえば、新しい調教はどうだ。何か変わりそうか?」
久しぶりの逢瀬のためか互いを求め合う気持ちは一度ではおさまらず、二度三度と立て続けに交わり、ようやく一息ついた寝台の上。
もうぐちゃぐちゃになった夜具をなんとか横になっても身体が痛くなさそうな状態にし(もちろんダンジァがやった)、枕はダンジァの腕をその代わりにして、彼の胸の中に抱き寄せられた格好でシィンが尋ねると、王子の最愛の騏驥は疲れなど一切伺わせない落ち着いた面持ちで、
「そうですね……」
と穏やかに応えた。
シィンを嫌というほど悦ばせ、何度となく絶頂へ導きながら全く疲労していないように見えるその体力に、シィンは熱い息を零す。
「……お前は昼も夜も逞しいな……」
話の途中であっても思わずそう伝えずにいられない。
息するたびに僅かに上下する鍛えられた胸元に指を這わせながらシィンが言うと、ダンジァは照れたように——もしくは困ったように苦笑した。
「お褒めいただき光栄です」
そしてシィンの手を取ると、その指先にちゅっと口付けてくる。
……そんなことをされると、またしたくなる。
とはいえ体力的に難しいのはシィンの方なので、シィンはチロリと自身の唇を舐めただけでそれ以上のことはせず、休憩代わりに話を続けようとする。
その意を込めて見つめると、賢い騏驥は話を続ける。
「ユェン先生と話し合って、今はまだ色々と試しているところですので……すぐに何か変化があるかといえば何とも言えません。ですが、先生が来てからというもの、王の騏驥たちの意識も少し変わってきているようですし、いずれは良い方向に向かうのではないかと。……自分もそのためには協力を惜しまないつもりです」
「ん……。だが……」
「——はい。承知いたしております。決して無理は致しません。それに……シィン様との時間は何をおいても確保いたしますのでご安心ください」
「っ……さ、最初のことはともかく、後のことはわたしは何も言ってはいないぞ!?」
何があっても自分と会うための時間だけは最優先にしろ——なんて、そんなあまりにも正直すぎる本音は流石に口にしてはいない……はずだ。
だが、ダンジァは「左様でしたか?」とことさら不思議そうに——笑いを堪えたような顔で、わざとらしく首を傾げて見せる。
シィンは耳が熱くなるのを感じながら、ぷぅ、と唇を尖らせた。
我儘を見透かされ、さらには先回りされたことに恥ずかしさを覚えていると、その唇にそっと口付けが触れた。
「そんな顔をなさらないでください。拗ねても可愛らしいなんて、シィン様は本当に罪作りなお方です……」
そして宥めるように何度も頬に軽く口付けられる。やがて、シィンはその唇にちゅっと口づけ返すと、間近からダンジァを見つめた。
「別に……拗ねてなどおらぬ」
「…………」
「お前がそうしたいなら、そうすれば良い。お前がどうしてもわたしとの時間を確保したいというなら……」
「もちろんです」
「ん。ならそうするがいい」
「はい」
シィンが言うと、ダンジァは神妙な顔で返事をする。それがおかしくて、二人ともに笑いが溢れた。
ひとしきり笑いあうと、シィンはふうっと息をつく。心地いい。彼の側は、なんの不安も気負いもなくいられて……。
情事の後の心地よい疲れの中、シィンは取り止めのない話を続ける。
「医館の改修も順調に進んでいるし、今後は色々と楽しみが多い……。そういえば、お前の身体は大丈夫か。ニコロ医師に登城を命じているが、彼は来ているか?」
「週に二度は体調を診ていただいています。厩舎にいた頃よりもむしろ頻度が増した気がするのですが……先生にはご迷惑ではないのでしょうか?」
「気にすることはない」
ダンジァは、城にも騏驥の医師がいるにもかかわらず、厩舎地区の医師であるニコロがわざわざやってくることを気にしているのだろう。しかも診るのはダンジァだけなのだ。
いくらか不安そうに言ったダンジァに、シィンはさらりと言った。
その口調があまりにあっさりしていたからか、ダンジァは目を丸くする。シィンは、ふふ……と笑って続けた。
「あの医師は、お前のことを気にしている。以前に診た患者の一人として気にしているという面もあるのだろうが、『薬や魔術力の影響によって後天的に毛色が変化した騏驥』への興味という点でも気にしているのだ。医師らしいというか……とにかく騏驥に興味があるのだろうな……」
ダンジァに説明しながら、シィンは、城の医師たちから聞かされた話を思い出していた。
彼らは、自分たちだけでは解毒薬を作成し完成させることは無理だと察したとき、迷った挙句、最後の手段として騏驥の医師であるニコロに協力を仰いだらしい。
騏驥の薬が毒として用いられているなら、騏驥に詳しい医師の手を借りるべきだろうと判断したのだ。それも、城の獣医よりも多く騏驥たちを診ているに違いない、厩舎地区の獣医がいい、と考えて。
しかし当初、彼は城の揉め事に巻き込まれることを嫌がり、頑なに首を縦には振らなかったようだ。
だが、事態に騏驥が大きく関わっていると教えられると、態度を一変させたらしい。
医師は言った。
『おそらく……おそらくですが、あの騏驥の医師は、殿下をお救いするというよりも騏驥を助けたかったのではないかと思われます……。王家に弓引く者は極刑——とはいえ、殿下の治癒が叶えばもしかしたら恩赦も、と思ったのでしょう……』
結果は、あんなことになってしまったようですが。
ニコロが助けたいと思った、実行犯の王の騏驥。
彼が、同じ王の騏驥の手によって既に殺されていたことは、医師たちも知っていることだ。
そして、シュウインも結局は「処分」を免れなかった……。
つまり何一つニコロの願った通りにはならなかったのだが、彼もおそらく、それは薄々分かっていただろう。故意であろうがなかろうが、騏驥が騎士に叛する——それも王子を害するなどあってはならないことなのだから。
ただそれでも、彼は「もしかしたら」に賭けて医師たちに協力してくれたのだ。
さらには、用いられた毒の特性から、回復には時間制限があり、このまま解毒薬を用いても間に合わないと判断するや否や、効果を高め、深めるための魔術まで駆使して薬を完成させたのだという。
そしてその結果が——。
「——それに、あの医館を半壊させたのはニコロ医師だ。確かにわたしの命の恩人である……とはいえ、王城の建物にあれほどの損害を与えた者に対して、なんの咎めも無しというわけにはいかぬだろう。……と言うわけで、お前の体調の管理を任せることにした。彼も同意しているのだし、お前が気にすることはない」
シィンの言葉に、ダンジァはますます目を丸くし、絶句する。
シィンは小さく笑った。
そう。医館はニコロが魔術によって半壊させたのだ。
シィンの薬を完成させるための魔術発動の、その余波で。
あの日、シィンが医館の方からなんとなく魔術の気配を感じていたのは、気のせいではなかったということだ。
(それだけ解毒の難しい薬を作ったのだな……。ツォ……)
シィンは、以前は確かに友人だったと思える男に想いを馳せ、心の中で呟く。
面影も、今はまだはっきりと思い出せる。声も、仕草も。
けれどやがて思い出せなくなるだろう。
調教師として間違いなく優れた才能を持ちながら、騏驥や魔術、それらへの切望と絶望に翻弄され、道を誤った男…………。
向けられた憎しみ。まだ生乾きの傷。しくり、とシィンが胸の痛みを覚えた時。
傍のダンジァが身じろいだかと思うと、静かに肩を抱き寄せられる。
見れば、ダンジァは気遣うようにこちらを見つめていた。さっきまではニコロの仕業に驚いたような顔をしていたのに……。
(まったく……お前は……)
シィンは聡い恋人に感嘆しつつ、そっと身を擦り寄せる。
温かい……。
シィンが微笑むと、ダンジァも笑みを見せながら言った。
「……そういうことであれば、ありがたく診ていただくことにいたします。自分はシィン様のためにも元気でいなければなりませんから」
「うん……。うん——そうだ。お前にはわたしの騏驥としてずっと元気でいてもらわなければならないのだからな」
「はい」
「ずっと側にいてもらわなければな」
「はい」
「ずっと……ずっとだ……。お前はずっと、わたしの側にいるのだ」
命令。願い。約束。
そしてなにより——愛情。
それら全てを込めてシィンが言うと、ダンジァは目を細めて「はい」と頷く。
今までよりも深く、しっかりと。
シィンもこくりと頷いた。
これからもずっと——彼と共にいる。そう思えば、たとえどんな困難が待っていようが立ち向かえると思うのだ。どんなわたしも愛してくれる彼が、側にいると思えば。
シィンはダンジァの額に触れる。髪を撫で、梳き上げる。
ダンジァの手がシィンの頬に触れる。撫でて、なぞって。愛おしげに。いつまでも。
微笑み合い見つめ合う二人の貌が、どちらからともなく——ゆっくりと近づいていく。
肌の香り。互いの吐息が混じり合う。
夜は長い。
二人の情欲の火が再び煽られる。
唇が触れる。
ああ——また溶ける。
自らすすんで溶け合うように、シィンはダンジァに身を委ね、その首筋に腕を絡めた。
END
蜜のような甘い香りが広がる中、ダンジァは溢れた香油で確かめるようにシィンの後孔を探る。そしてシィンの脚を大きく開かさせるように抱えると、次の瞬間、一気に挿し入ってきた。
「ぁあぁあァん……っ……!」
その強烈な快感に、堪えていた欲望が一気に噴き上がる。
ダンジァと一緒に達したかったのに、入れられただけで吐精してしまった。堪えられなかった自身の身体の淫蕩さに、シィンは耳まで真っ赤になる。
だがダンジァは、そんなシィンの狼狽さえ愛おしむように、熱い耳朶に、頬に、繰り返し口付けてくる。
「シィン様……あぁ……シィン様はあんなことをどこで覚えられたのですか……? あんなに淫らな——可愛らしい——蠱惑的な様を——」
そして途切れ途切れに聞こえるのは、興奮極まったような熱っぽい彼の声だ。
と同時に繰り返し抜き挿しされ、揺さぶられ、抉られては突き上げられ、シィンはダンジァの腕の中で溢れんばかりの快感をただただ注がれ続ける。
「優しく抱いて差し上げなくてはと思っていても、あんな姿を見せられては……」
「ぁ……あ、あ、ァ……ダン……ダンジァ……ぁ……」
「あれは自分だけに見せたものだと仰ってください。これまでもこれからも、自分だけが見られるシィン様の特別なお姿なのだと——」
でなければ嫉妬でおかしくなります——。
と、ますます情熱的に腰をすすめてくるダンジァに、シィンの胸は甘酸っぱく軋む。わかりきっている答えを望む彼が可愛らしい。わかりきっている言葉を欲しがる彼が愛しい。
「ダ……ん、ぁ……そ、んな、の、決まって……っ……んっ……」
だからすぐさま応じようとしたシィンの声は、ダンジァの唇に奪われる。
繋がっていてもまだ足りないとばかりに深く舌を挿し入れられ、同時に激しく腰を打ち付けられると、目が眩むほどの強烈な快楽に、喘ぐことすら満足にできなくなる。
一度達したはずの性器も既にまた硬く形を変え、再びの吐精を望んで震えている。
「ダン……ぁ……ダ、メ……ぁ……ああっ……ぁ……いぃ……っ」
何を発しているのか、自分がどんな格好をしているのかもよくわからない。
久しぶりの逢瀬。久しぶりの二人だけの時間。久しぶりの彼との抱擁、口付け。そして繋がり——。その悦びの全てを受け止め堪能し尽くしながら、シィンは甘く切なく鳴き声を上げ続ける。
「シィン様……中が、こんなに熱く……」
「あぁ……っ……ぁひ、ぁ……」
「溶けそうです……うねって……締め付けてきて……」
「ぁ……ダンジァ、ぁ……ぁ、そこ、ぁ……」
「ここですか?」
「あぁっ……! ァ、ぁ、んっ、そこ……そこ、が……ぃ……きもち、ぃ……っ」
内壁を突かれるたびに髪を乱してガクガク頷くシィンの口の端から、淫らな声と共に飲み下せなかった涎が滴り落ちる。繰り返される口付けの合間、それをぺろぺろと舐めとるダンジァの姿は、どこか甘える馬の仕草のようでもある。
けれど彼は——ただの大人しい馬じゃない。
思慮深く穏やかなだけの騏驥じゃない。
二人きりでいる時だけに見せる、別の姿。別の横顔。
自分が、こうして彼と二人きりでいる時は、王子でなくただのシィンになるように。
誰も知らない自分の姿。
自分しか知らない彼の姿。
それを見せ合え、愛し合える相手の、なんと素晴らしく得難いことか。
「ダンジァ……ダン……ダン……」
「シィン様……シィン様——愛しています……」
「ダンジァ……好きだ……わたしの——わたしのダンジァ——」
「シィン……様……っ」
次第に激しさを増す抽送に、互いの息も上がり、声も上擦り掠れていく。
しっとりと湿った肌が吸い付き合い、香りとともに混じり合うようだ。
ダンジァの額にも汗が浮いている。彼が動くたび、繋がっている部分が快感を伝える淫猥な水音を立て、シィンを官能の沼へ沈めていく。
酔ったようにクラクラする。
気持ちがいい——もっと——気持ちがいい——。そんなことしか考えられくなる。
達したい。けれどずっとこのままでいたい。ずっとこのままがいい。ずっとずっと——彼の腕の中で彼の香りに包まれて彼と繋がり一つになっていたい——。
「ダンジァ……ぁ……抱き、しめて……っ……きつく……っ」
「シィン様——」
「ダンジァ……ダンジァ……あぁ……」
感極まって溢れた涙を、温かな唇が静かに掬っていく。こめかみに、額に口付けられる。髪を撫で上げられる。
黒く美しい瞳が見つめてくる。
激しさも優しさも同じ彼で、全部全部わたしのもの——。
「ダ……ぁ……も、ぅ……っ……」
くり返される律動と絶え間のない愛撫に堪らず、シィンはとうとう懇願の声をあげる。
達したい——今度こそ一緒に——。
縋るように見つめると、情熱を宿していた夜の色の瞳が微笑むように細められる。抱きつくと、いっそう強く抱き返される。絶対に離さないとでも言うように。あなたはわたしのものなのだと、伝えてくるかのように。
そう——。
それでいい。
ここにいるのはただの恋人同士の二人。
だからわたしはあなたのものであなたはわたしのもの。
「ぁ……あ、ぁ、ああっ——ァ——」
再開される律動にされるまま、シィンは声を上げ身をくねらせる。より深く咥え込もうとするかのように自ら腰を揺すり、抱きしめる身体に爪をたて、気持ちがよくて堪らないのだと伝えると、熟れた肉筒を満たすダンジァの屹立がいっそう大きさと硬さを増す。
「シィン様——」
「ダンジァ……ダン……っぁ……すご……すご、ぃ……っ」
「ッ——」
「な、か……熱、ぃ……大き……凄ぃ……ぃ……っ」
忘我の快感の中、羞恥も忘れた淫らな声を上げ、ぎゅうっとしがみついたその瞬間。
「ァ……ぁ、ひァ……ああぁっ——!」
背が軋むほど抱きしめられ、奥の奥に熱が叩き込まれる。
同時に、昂りきったシィンの性器から熱い飛沫が噴き零れる。
目が眩むような、絶頂。
「ふぁ……ぁ……っん……ぁ……」
吐精の余韻に、シィンの身体がヒクヒクと震える。
その身体をきつくきつく抱きしめられ、ダンジァの呻くような低い声が届いた直後——。身体の奥で性器が脈打ち、どくりと温かなものが注がれる。
体奥に染み渡っていくダンジァの欲。その感触にうっとりと背を震わせるシィンの唇に、愛の囁きとともに、吐息混じりのダンジァの唇が触れた。
⭐︎
「……そういえば、新しい調教はどうだ。何か変わりそうか?」
久しぶりの逢瀬のためか互いを求め合う気持ちは一度ではおさまらず、二度三度と立て続けに交わり、ようやく一息ついた寝台の上。
もうぐちゃぐちゃになった夜具をなんとか横になっても身体が痛くなさそうな状態にし(もちろんダンジァがやった)、枕はダンジァの腕をその代わりにして、彼の胸の中に抱き寄せられた格好でシィンが尋ねると、王子の最愛の騏驥は疲れなど一切伺わせない落ち着いた面持ちで、
「そうですね……」
と穏やかに応えた。
シィンを嫌というほど悦ばせ、何度となく絶頂へ導きながら全く疲労していないように見えるその体力に、シィンは熱い息を零す。
「……お前は昼も夜も逞しいな……」
話の途中であっても思わずそう伝えずにいられない。
息するたびに僅かに上下する鍛えられた胸元に指を這わせながらシィンが言うと、ダンジァは照れたように——もしくは困ったように苦笑した。
「お褒めいただき光栄です」
そしてシィンの手を取ると、その指先にちゅっと口付けてくる。
……そんなことをされると、またしたくなる。
とはいえ体力的に難しいのはシィンの方なので、シィンはチロリと自身の唇を舐めただけでそれ以上のことはせず、休憩代わりに話を続けようとする。
その意を込めて見つめると、賢い騏驥は話を続ける。
「ユェン先生と話し合って、今はまだ色々と試しているところですので……すぐに何か変化があるかといえば何とも言えません。ですが、先生が来てからというもの、王の騏驥たちの意識も少し変わってきているようですし、いずれは良い方向に向かうのではないかと。……自分もそのためには協力を惜しまないつもりです」
「ん……。だが……」
「——はい。承知いたしております。決して無理は致しません。それに……シィン様との時間は何をおいても確保いたしますのでご安心ください」
「っ……さ、最初のことはともかく、後のことはわたしは何も言ってはいないぞ!?」
何があっても自分と会うための時間だけは最優先にしろ——なんて、そんなあまりにも正直すぎる本音は流石に口にしてはいない……はずだ。
だが、ダンジァは「左様でしたか?」とことさら不思議そうに——笑いを堪えたような顔で、わざとらしく首を傾げて見せる。
シィンは耳が熱くなるのを感じながら、ぷぅ、と唇を尖らせた。
我儘を見透かされ、さらには先回りされたことに恥ずかしさを覚えていると、その唇にそっと口付けが触れた。
「そんな顔をなさらないでください。拗ねても可愛らしいなんて、シィン様は本当に罪作りなお方です……」
そして宥めるように何度も頬に軽く口付けられる。やがて、シィンはその唇にちゅっと口づけ返すと、間近からダンジァを見つめた。
「別に……拗ねてなどおらぬ」
「…………」
「お前がそうしたいなら、そうすれば良い。お前がどうしてもわたしとの時間を確保したいというなら……」
「もちろんです」
「ん。ならそうするがいい」
「はい」
シィンが言うと、ダンジァは神妙な顔で返事をする。それがおかしくて、二人ともに笑いが溢れた。
ひとしきり笑いあうと、シィンはふうっと息をつく。心地いい。彼の側は、なんの不安も気負いもなくいられて……。
情事の後の心地よい疲れの中、シィンは取り止めのない話を続ける。
「医館の改修も順調に進んでいるし、今後は色々と楽しみが多い……。そういえば、お前の身体は大丈夫か。ニコロ医師に登城を命じているが、彼は来ているか?」
「週に二度は体調を診ていただいています。厩舎にいた頃よりもむしろ頻度が増した気がするのですが……先生にはご迷惑ではないのでしょうか?」
「気にすることはない」
ダンジァは、城にも騏驥の医師がいるにもかかわらず、厩舎地区の医師であるニコロがわざわざやってくることを気にしているのだろう。しかも診るのはダンジァだけなのだ。
いくらか不安そうに言ったダンジァに、シィンはさらりと言った。
その口調があまりにあっさりしていたからか、ダンジァは目を丸くする。シィンは、ふふ……と笑って続けた。
「あの医師は、お前のことを気にしている。以前に診た患者の一人として気にしているという面もあるのだろうが、『薬や魔術力の影響によって後天的に毛色が変化した騏驥』への興味という点でも気にしているのだ。医師らしいというか……とにかく騏驥に興味があるのだろうな……」
ダンジァに説明しながら、シィンは、城の医師たちから聞かされた話を思い出していた。
彼らは、自分たちだけでは解毒薬を作成し完成させることは無理だと察したとき、迷った挙句、最後の手段として騏驥の医師であるニコロに協力を仰いだらしい。
騏驥の薬が毒として用いられているなら、騏驥に詳しい医師の手を借りるべきだろうと判断したのだ。それも、城の獣医よりも多く騏驥たちを診ているに違いない、厩舎地区の獣医がいい、と考えて。
しかし当初、彼は城の揉め事に巻き込まれることを嫌がり、頑なに首を縦には振らなかったようだ。
だが、事態に騏驥が大きく関わっていると教えられると、態度を一変させたらしい。
医師は言った。
『おそらく……おそらくですが、あの騏驥の医師は、殿下をお救いするというよりも騏驥を助けたかったのではないかと思われます……。王家に弓引く者は極刑——とはいえ、殿下の治癒が叶えばもしかしたら恩赦も、と思ったのでしょう……』
結果は、あんなことになってしまったようですが。
ニコロが助けたいと思った、実行犯の王の騏驥。
彼が、同じ王の騏驥の手によって既に殺されていたことは、医師たちも知っていることだ。
そして、シュウインも結局は「処分」を免れなかった……。
つまり何一つニコロの願った通りにはならなかったのだが、彼もおそらく、それは薄々分かっていただろう。故意であろうがなかろうが、騏驥が騎士に叛する——それも王子を害するなどあってはならないことなのだから。
ただそれでも、彼は「もしかしたら」に賭けて医師たちに協力してくれたのだ。
さらには、用いられた毒の特性から、回復には時間制限があり、このまま解毒薬を用いても間に合わないと判断するや否や、効果を高め、深めるための魔術まで駆使して薬を完成させたのだという。
そしてその結果が——。
「——それに、あの医館を半壊させたのはニコロ医師だ。確かにわたしの命の恩人である……とはいえ、王城の建物にあれほどの損害を与えた者に対して、なんの咎めも無しというわけにはいかぬだろう。……と言うわけで、お前の体調の管理を任せることにした。彼も同意しているのだし、お前が気にすることはない」
シィンの言葉に、ダンジァはますます目を丸くし、絶句する。
シィンは小さく笑った。
そう。医館はニコロが魔術によって半壊させたのだ。
シィンの薬を完成させるための魔術発動の、その余波で。
あの日、シィンが医館の方からなんとなく魔術の気配を感じていたのは、気のせいではなかったということだ。
(それだけ解毒の難しい薬を作ったのだな……。ツォ……)
シィンは、以前は確かに友人だったと思える男に想いを馳せ、心の中で呟く。
面影も、今はまだはっきりと思い出せる。声も、仕草も。
けれどやがて思い出せなくなるだろう。
調教師として間違いなく優れた才能を持ちながら、騏驥や魔術、それらへの切望と絶望に翻弄され、道を誤った男…………。
向けられた憎しみ。まだ生乾きの傷。しくり、とシィンが胸の痛みを覚えた時。
傍のダンジァが身じろいだかと思うと、静かに肩を抱き寄せられる。
見れば、ダンジァは気遣うようにこちらを見つめていた。さっきまではニコロの仕業に驚いたような顔をしていたのに……。
(まったく……お前は……)
シィンは聡い恋人に感嘆しつつ、そっと身を擦り寄せる。
温かい……。
シィンが微笑むと、ダンジァも笑みを見せながら言った。
「……そういうことであれば、ありがたく診ていただくことにいたします。自分はシィン様のためにも元気でいなければなりませんから」
「うん……。うん——そうだ。お前にはわたしの騏驥としてずっと元気でいてもらわなければならないのだからな」
「はい」
「ずっと側にいてもらわなければな」
「はい」
「ずっと……ずっとだ……。お前はずっと、わたしの側にいるのだ」
命令。願い。約束。
そしてなにより——愛情。
それら全てを込めてシィンが言うと、ダンジァは目を細めて「はい」と頷く。
今までよりも深く、しっかりと。
シィンもこくりと頷いた。
これからもずっと——彼と共にいる。そう思えば、たとえどんな困難が待っていようが立ち向かえると思うのだ。どんなわたしも愛してくれる彼が、側にいると思えば。
シィンはダンジァの額に触れる。髪を撫で、梳き上げる。
ダンジァの手がシィンの頬に触れる。撫でて、なぞって。愛おしげに。いつまでも。
微笑み合い見つめ合う二人の貌が、どちらからともなく——ゆっくりと近づいていく。
肌の香り。互いの吐息が混じり合う。
夜は長い。
二人の情欲の火が再び煽られる。
唇が触れる。
ああ——また溶ける。
自らすすんで溶け合うように、シィンはダンジァに身を委ね、その首筋に腕を絡めた。
END
0
あなたにおすすめの小説

前世が教師だった少年は辺境で愛される
結衣可
BL
雪深い帝国北端の地で、傷つき行き倒れていた少年ミカを拾ったのは、寡黙な辺境伯ダリウスだった。妻を亡くし、幼い息子リアムと静かに暮らしていた彼は、ミカの知識と優しさに驚きつつも、次第にその穏やかな笑顔に心を癒されていく。
ミカは実は異世界からの転生者。前世の記憶を抱え、この世界でどう生きるべきか迷っていたが、リアムの教育係として過ごすうちに、“誰かに必要とされる”温もりを思い出していく。
雪の館で共に過ごす日々は、やがてお互いにとってかけがえのない時間となり、新しい日々へと続いていく――。

ヒールオメガは敵騎士の腕の中~平民上がりの癒し手は、王の器に密かに溺愛される
七角@書籍化進行中!
BL
君とどうにかなるつもりはない。わたしはソコロフ家の、君はアナトリエ家の近衛騎士なのだから。
ここは二大貴族が百年にわたり王位争いを繰り広げる国。
平民のオメガにして近衛騎士に登用されたスフェンは、敬愛するアルファの公子レクスに忠誠を誓っている。
しかしレクスから賜った密令により、敵方の騎士でアルファのエリセイと行動を共にする破目になってしまう。
エリセイは腹が立つほど呑気でのらくら。だが密令を果たすため仕方なく一緒に過ごすうち、彼への印象が変わっていく。
さらに、蔑まれるオメガが実は、この百年の戦いに終止符を打てる存在だと判明するも――やはり、剣を向け合う運命だった。
特別な「ヒールオメガ」が鍵を握る、ロミジュリオメガバース。
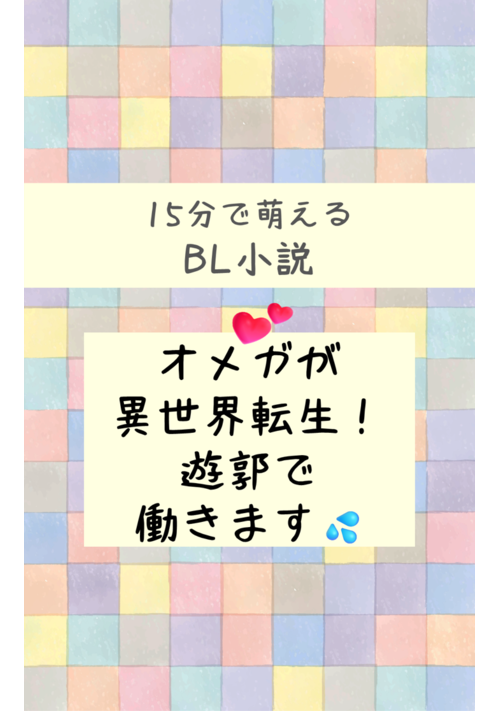
異世界の遊郭に拾われたオメガは、ただ一人に愛される
雪代鞠絵/15分で萌えるBL小説
BL
オメガであることでさんざんな目に遭ってきたオメガちゃん。
オメガである自分が大嫌い!
ある日事故に遭い、目が覚めたらそこは異世界。
何故か遊郭に拾われますが、そこはオメガだけが働くお店で戸惑う
ことばかり。
しかも、お客であるアルファ氏には毎日からかわれて?

転生したら、主人公の宿敵(でも俺の推し)の側近でした
リリーブルー
BL
「しごとより、いのち」厚労省の過労死等防止対策のスローガンです。過労死をゼロにし、健康で充実して働き続けることのできる社会へ。この小説の主人公は、仕事依存で過労死し異世界転生します。
仕事依存だった主人公(20代社畜)は、過労で倒れた拍子に異世界へ転生。目を覚ますと、そこは剣と魔法の世界——。愛読していた小説のラスボス貴族、すなわち原作主人公の宿敵(ライバル)レオナルト公爵に仕える側近の美青年貴族・シリル(20代)になっていた!
原作小説では悪役のレオナルト公爵。でも主人公はレオナルトに感情移入して読んでおり彼が推しだった! なので嬉しい!
だが問題は、そのラスボス貴族・レオナルト公爵(30代)が、物語の中では原作主人公にとっての宿敵ゆえに、原作小説では彼の冷酷な策略によって国家間の戦争へと突き進み、最終的にレオナルトと側近のシリルは処刑される運命だったことだ。
「俺、このままだと死ぬやつじゃん……」
死を回避するために、主人公、すなわち転生先の新しいシリルは、レオナルト公爵の信頼を得て歴史を変えようと決意。しかし、レオナルトは原作とは違い、どこか寂しげで孤独を抱えている様子。さらに、主人公が意外な才覚を発揮するたびに、公爵の態度が甘くなり、なぜか距離が近くなっていく。主人公は気づく。レオナルト公爵が悪に染まる原因は、彼の孤独と裏切られ続けた過去にあるのではないかと。そして彼を救おうと奔走するが、それは同時に、公爵からの執着を招くことになり——!?
原作主人公ラセル王太子も出てきて話は複雑に!
見どころ
・転生
・主従
・推しである原作悪役に溺愛される
・前世の経験と知識を活かす
・政治的な駆け引きとバトル要素(少し)
・ダークヒーロー(攻め)の変化(冷酷な公爵が愛を知り、主人公に執着・溺愛する過程)
・黒猫もふもふ
番外編では。
・もふもふ獣人化
・切ない裏側
・少年時代
などなど
最初は、推しの信頼を得るために、ほのぼの日常スローライフ、かわいい黒猫が出てきます。中盤にバトルがあって、解決、という流れ。後日譚は、ほのぼのに戻るかも。本編は完結しましたが、後日譚や番外編、ifルートなど、続々更新中。

仮面王子は下僕志願
灰鷹
BL
父親の顔は知らず、奔放な母のもとで育った渡辺響は、安定した職業に就くために勉強だけはずっと頑張ってきた。その甲斐あって有名進学校に進学できたものの、クラスメイトとは話題も合わず、ボッチキャラとして浮いていた。クラスの中で唯一、委員長の川嶋昴陽だけが響のことを気にかけてくれて、面倒見のよい彼に秘かに恋心を抱いていた。しかし、修学旅行の最終日に川嶋が隣で寝ていた朝倉にキスしようとしているところを目撃し、反射的にそれを写真に収めてしまう。写真を消せと川嶋に詰め寄られるが、怒りをあらわにした彼の態度に反発し――。女子から「王子」と呼ばれる人気者優等生×寂しさを抱えるボッチな茶髪男子、の失恋から始まるハートフル青春BL。
※ アルファポリス様で開催されている『青春BLカップ』コンテストに応募しています。今回は投票制ではないですが、閲覧ポイントでランキングが変わるそうなので、完結後にまとめてではなくリアルタイムでお読みいただけると、めちゃくちゃ励みになります。
※ 視点は攻め受け両方で章ごとに変わります。完結した作品に加筆してコンテスト期間中の完結を目指します。不定期更新。

【完結】抱っこからはじまる恋
* ゆるゆ
BL
満員電車で、立ったまま寄りかかるように寝てしまった高校生の愛希を抱っこしてくれたのは、かっこいい社会人の真紀でした。接点なんて、まるでないふたりの、抱っこからはじまる、しあわせな恋のお話です。
ふたりの動画をつくりました!
インスタ @yuruyu0 絵もあがります。
YouTube @BL小説動画 アカウントがなくても、どなたでもご覧になれます。
プロフのwebサイトから飛べるので、もしよかったら!
完結しました!
おまけのお話を時々更新しています。
BLoveさまのコンテストに応募しているお話を倍以上の字数増量でお送りする、アルファポリスさま限定版です!
名前が * ゆるゆ になりましたー!
中身はいっしょなので(笑)これからもどうぞよろしくお願い致しますー!

追放された『呪物鑑定』持ちの公爵令息、魔王の呪いを解いたら執着溺愛ルートに入りました
水凪しおん
BL
「お前のそのスキルは不吉だ」
身に覚えのない罪を着せられ、聖女リリアンナによって国を追放された公爵令息カイル。
死を覚悟して彷徨い込んだ魔の森で、彼は呪いに蝕まれ孤独に生きる魔王レイルと出会う。
カイルの持つ『呪物鑑定』スキル――それは、魔王を救う唯一の鍵だった。
「カイル、お前は我の光だ。もう二度と離さない」
献身的に尽くすカイルに、冷徹だった魔王の心は溶かされ、やがて執着にも似た溺愛へと変わっていく。
これは、全てを奪われた青年が魔王を救い、世界一幸せになる逆転と愛の物語。

虚ろな檻と翡翠の魔石
篠雨
BL
「本来の寿命まで、悪役の身体に入ってやり過ごしてよ」
不慮の事故で死んだ僕は、いい加減な神様の身勝手な都合により、異世界の悪役・レリルの器へ転生させられてしまう。
待っていたのは、一生を塔で過ごし、魔力を搾取され続ける孤独な日々。だが、僕を管理する強面の辺境伯・ヨハンが運んでくる薪や食事、そして不器用な優しさが、凍てついた僕の心を次第に溶かしていく。
しかし、穏やかな時間は長くは続かない。魔力を捧げるたびに脳内に流れ込む本物のレリルの記憶と領地を襲う未曾有の魔物の群れ。
「僕が、この場所と彼を守る方法はこれしかない」
記憶に翻弄され頭は混乱する中、魔石化するという残酷な決断を下そうとするが――。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















