8 / 11
8. 応援なんて、誰のため?
しおりを挟む
夏休みに入った中学校の校舎は、静けさの中に蝉の鳴き声が響いていた。窓の外の空は真っ青で、照り返す日差しがグラウンドを揺らしている。
ミユたちは体育館に集まり、夏祭りのパフォーマンスに向けた練習を本格的に始めていた。
「じゃあ、今日はセリフから通してやってみよう!」
ヒイラギが声を上げる。
応援団のメンバーは汗を拭いながら立ち位置に着いた。音楽が流れ、ステージの流れに沿って動き出す。
「この夏、走ってるのは君だけじゃない──!」
ミユの声が体育館に響く。動きもそろってきた。仕上がりは、順調だ。
……そのはずだった。
⸻
練習が終わって片づけをしていたとき、ユキがぽつりと言った。
「ねえ……これって、誰のためにやってるのかな?」
その言葉に、空気が一瞬止まる。
「だって、見に来る人たちって、たぶん応援されたいと思ってるわけじゃないでしょ? ただの出し物として見に来るだけ。だったら、応援じゃなくて演劇とかダンスのほうがいいんじゃないのかなって」
その場にいた全員が、何かを言いかけて、やめた。
たしかに、そうかもしれない。
応援って、頼まれてないのにするものだ。
「応援って、ありがた迷惑かもってこと?」
カンジが確認するように言うと、ユキはちょっと困ったように笑った。
「ううん、そうじゃなくて……うまく言えないんだけど、最近、“応援”ってなんなのかわかんなくなってきて」
⸻
その夜、ミユはノートに“応援って、誰のため?”と書いた。
走る人のため? 団のため? 自分のため? 見てくれる人のため?
正解がわからない。
思えば、これまでは「誰かの役に立ちたい」「元気になってほしい」と願って動いてきた。
でも今、応援団として“見せる応援”をしようとすると、自分たちの中に少しずつズレが生まれてきている。
⸻
翌日の練習も、どこかぎこちなかった。声がそろわず、動きにも力がない。
指導に来てくれていた先生も、静かに様子を見ている。
「いったん、みんなで話してみたらどう?」
先生の一言で、ミユたちは円になって座った。
「わたしは……自分たちが楽しんでなかったら、応援なんて届かないと思うんだ」
サキが言った。
「でも、見てる人が“うるさいな”って思ってたら、逆効果かも」
ユキが返す。
「それでも、声を出すことに意味があるって……思ってたけどな」
ヒイラギがつぶやくように言う。
そして、ミユも口を開いた。
「わたし……最近ちょっと、自分のことばっかり考えてた。うまくやらなきゃとか、失敗したらどうしようとか。でも、本当は、“誰かの心に届いたら”っていう気持ちで始めたんだよね。最初のころの、あの気持ち……忘れてたかも」
⸻
その日、練習の後にミユは一人で図書館に向かった。
本棚のすみっこにある、小さな本を手に取る。
『応援されるということ』
薄いエッセイ集だった。著者はスポーツのコーチで、長年選手たちを支えてきたという。
「“応援は魔法ではない。でも、届く瞬間がある”」
ミユは、その一文をそっとノートに写した。
⸻
翌日。
「みんなで、ちょっとだけ“誰かのためじゃない応援”をやってみない?」
ミユの提案で、応援団は“観客のいない応援”に挑戦した。
体育館に誰もいない状態で、自分たちだけのために、声を出す。
不思議な空気だった。
でも、だんだん、ひとりひとりの声が大きく、そしてやわらかくなっていく。
最後のポーズのあと、しばらく誰も動かなかった。
「……なんかさ」
カンジが言う。
「今日のが、一番“応援”だった気がする」
⸻
そして数日後、ユキがミユにそっと話しかけた。
「ねえ……この前、ちょっと意地張っちゃった。ほんとは、怖かったんだ。“誰のために”って考えると、自分が空っぽみたいに思えて。でも今日の練習で、少しだけ思い出せた。“わたしが応援したいから、やってるんだ”って」
「うん。わたしも、そう思った」
二人は、静かに笑い合った。
⸻
夏祭りの本番まで、あと十日。
準備は順調とは言えなかったけれど、少しずつ、仲間たちの心はひとつになってきていた。
「次は、本番用の横断幕作ろう! 大きいやつ!」
「“一歩の勇気にエールを!”とか、どう?」
ミユたちの声が、空に吸い込まれていく。
蝉が、ますます激しく鳴いていた。
“誰かのために”じゃなく、“自分たちが信じてること”のために。
その夏、応援団のチカラは静かに、でも確かに育っていた。
ミユたちは体育館に集まり、夏祭りのパフォーマンスに向けた練習を本格的に始めていた。
「じゃあ、今日はセリフから通してやってみよう!」
ヒイラギが声を上げる。
応援団のメンバーは汗を拭いながら立ち位置に着いた。音楽が流れ、ステージの流れに沿って動き出す。
「この夏、走ってるのは君だけじゃない──!」
ミユの声が体育館に響く。動きもそろってきた。仕上がりは、順調だ。
……そのはずだった。
⸻
練習が終わって片づけをしていたとき、ユキがぽつりと言った。
「ねえ……これって、誰のためにやってるのかな?」
その言葉に、空気が一瞬止まる。
「だって、見に来る人たちって、たぶん応援されたいと思ってるわけじゃないでしょ? ただの出し物として見に来るだけ。だったら、応援じゃなくて演劇とかダンスのほうがいいんじゃないのかなって」
その場にいた全員が、何かを言いかけて、やめた。
たしかに、そうかもしれない。
応援って、頼まれてないのにするものだ。
「応援って、ありがた迷惑かもってこと?」
カンジが確認するように言うと、ユキはちょっと困ったように笑った。
「ううん、そうじゃなくて……うまく言えないんだけど、最近、“応援”ってなんなのかわかんなくなってきて」
⸻
その夜、ミユはノートに“応援って、誰のため?”と書いた。
走る人のため? 団のため? 自分のため? 見てくれる人のため?
正解がわからない。
思えば、これまでは「誰かの役に立ちたい」「元気になってほしい」と願って動いてきた。
でも今、応援団として“見せる応援”をしようとすると、自分たちの中に少しずつズレが生まれてきている。
⸻
翌日の練習も、どこかぎこちなかった。声がそろわず、動きにも力がない。
指導に来てくれていた先生も、静かに様子を見ている。
「いったん、みんなで話してみたらどう?」
先生の一言で、ミユたちは円になって座った。
「わたしは……自分たちが楽しんでなかったら、応援なんて届かないと思うんだ」
サキが言った。
「でも、見てる人が“うるさいな”って思ってたら、逆効果かも」
ユキが返す。
「それでも、声を出すことに意味があるって……思ってたけどな」
ヒイラギがつぶやくように言う。
そして、ミユも口を開いた。
「わたし……最近ちょっと、自分のことばっかり考えてた。うまくやらなきゃとか、失敗したらどうしようとか。でも、本当は、“誰かの心に届いたら”っていう気持ちで始めたんだよね。最初のころの、あの気持ち……忘れてたかも」
⸻
その日、練習の後にミユは一人で図書館に向かった。
本棚のすみっこにある、小さな本を手に取る。
『応援されるということ』
薄いエッセイ集だった。著者はスポーツのコーチで、長年選手たちを支えてきたという。
「“応援は魔法ではない。でも、届く瞬間がある”」
ミユは、その一文をそっとノートに写した。
⸻
翌日。
「みんなで、ちょっとだけ“誰かのためじゃない応援”をやってみない?」
ミユの提案で、応援団は“観客のいない応援”に挑戦した。
体育館に誰もいない状態で、自分たちだけのために、声を出す。
不思議な空気だった。
でも、だんだん、ひとりひとりの声が大きく、そしてやわらかくなっていく。
最後のポーズのあと、しばらく誰も動かなかった。
「……なんかさ」
カンジが言う。
「今日のが、一番“応援”だった気がする」
⸻
そして数日後、ユキがミユにそっと話しかけた。
「ねえ……この前、ちょっと意地張っちゃった。ほんとは、怖かったんだ。“誰のために”って考えると、自分が空っぽみたいに思えて。でも今日の練習で、少しだけ思い出せた。“わたしが応援したいから、やってるんだ”って」
「うん。わたしも、そう思った」
二人は、静かに笑い合った。
⸻
夏祭りの本番まで、あと十日。
準備は順調とは言えなかったけれど、少しずつ、仲間たちの心はひとつになってきていた。
「次は、本番用の横断幕作ろう! 大きいやつ!」
「“一歩の勇気にエールを!”とか、どう?」
ミユたちの声が、空に吸い込まれていく。
蝉が、ますます激しく鳴いていた。
“誰かのために”じゃなく、“自分たちが信じてること”のために。
その夏、応援団のチカラは静かに、でも確かに育っていた。
0
あなたにおすすめの小説


独占欲強めの最強な不良さん、溺愛は盲目なほど。
猫菜こん
児童書・童話
小さな頃から、巻き込まれで絡まれ体質の私。
中学生になって、もう巻き込まれないようにひっそり暮らそう!
そう意気込んでいたのに……。
「可愛すぎる。もっと抱きしめさせてくれ。」
私、最強の不良さんに見初められちゃったみたいです。
巻き込まれ体質の不憫な中学生
ふわふわしているけど、しっかりした芯の持ち主
咲城和凜(さきしろかりん)
×
圧倒的な力とセンスを持つ、負け知らずの最強不良
和凜以外に容赦がない
天狼絆那(てんろうきずな)
些細な事だったのに、どうしてか私にくっつくイケメンさん。
彼曰く、私に一目惚れしたらしく……?
「おい、俺の和凜に何しやがる。」
「お前が無事なら、もうそれでいい……っ。」
「この世に存在している言葉だけじゃ表せないくらい、愛している。」
王道で溺愛、甘すぎる恋物語。
最強不良さんの溺愛は、独占的で盲目的。

おっとりドンの童歌
花田 一劫
児童書・童話
いつもおっとりしているドン(道明寺僚) が、通学途中で暴走車に引かれてしまった。
意識を失い気が付くと、この世では見たことのない奇妙な部屋の中。
「どこ。どこ。ここはどこ?」と自問していたら、こっちに雀が近づいて来た。
なんと、その雀は歌をうたい狂ったように踊って(跳ねて)いた。
「チュン。チュン。はあ~。らっせーら。らっせいら。らせらせ、らせーら。」と。
その雀が言うことには、ドンが死んだことを(津軽弁や古いギャグを交えて)伝えに来た者だという。
道明寺が下の世界を覗くと、テレビのドラマで観た昔話の風景のようだった。
その中には、自分と瓜二つのドン助や同級生の瓜二つのハナちゃん、ヤーミ、イート、ヨウカイ、カトッぺがいた。
みんながいる村では、ヌエという妖怪がいた。
ヌエとは、顔は鬼、身体は熊、虎の手や足をもち、何とシッポの先に大蛇の頭がついてあり、人を食べる恐ろしい妖怪のことだった。
ある時、ハナちゃんがヌエに攫われて、ドン助とヤーミがヌエを退治に行くことになるが、天界からドラマを観るように楽しんで鑑賞していた道明寺だったが、道明寺の体は消え、意識はドン助の体と同化していった。
ドン助とヤーミは、ハナちゃんを救出できたのか?恐ろしいヌエは退治できたのか?
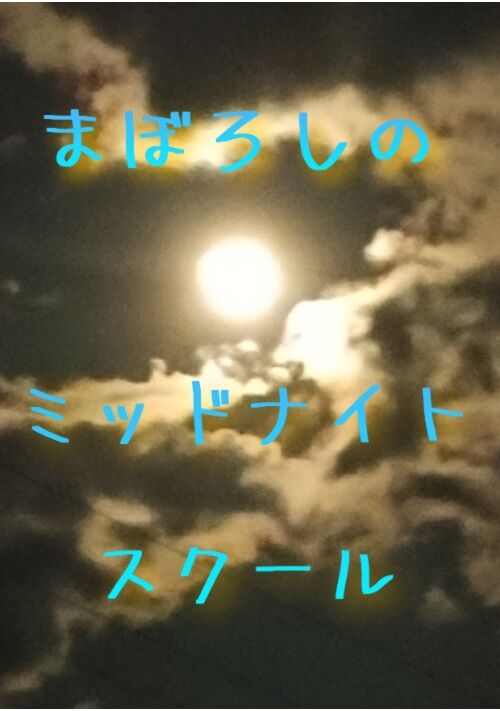
まぼろしのミッドナイトスクール
木野もくば
児童書・童話
深夜0時ちょうどに突然あらわれる不思議な学校。そこには、不思議な先生と生徒たちがいました。飼い猫との最後に後悔がある青年……。深い森の中で道に迷う少女……。人間に恋をした水の神さま……。それぞれの道に迷い、そして誰かと誰かの想いがつながったとき、暗闇の空に光る星くずの方から学校のチャイムが鳴り響いてくるのでした。


不幸でしあわせな子どもたち 「しあわせのふうせん」
山口かずなり
絵本
小説 不幸でしあわせな子どもたち
スピンオフ作品
・
ウルが友だちのメロウからもらったのは、
緑色のふうせん
だけどウルにとっては、いらないもの
いらないものは、誰かにとっては、
ほしいもの。
だけど、気づいて
ふうせんの正体に‥。

こちら第二編集部!
月芝
児童書・童話
かつては全国でも有数の生徒数を誇ったマンモス小学校も、
いまや少子化の波に押されて、かつての勢いはない。
生徒数も全盛期の三分の一にまで減ってしまった。
そんな小学校には、ふたつの校内新聞がある。
第一編集部が発行している「パンダ通信」
第二編集部が発行している「エリマキトカゲ通信」
片やカジュアルでおしゃれで今時のトレンドにも敏感にて、
主に女生徒たちから絶大な支持をえている。
片や手堅い紙面造りが仇となり、保護者らと一部のマニアには
熱烈に支持されているものの、もはや風前の灯……。
編集部の規模、人員、発行部数も人気も雲泥の差にて、このままでは廃刊もありうる。
この危機的状況を打破すべく、第二編集部は起死回生の企画を立ち上げた。
それは――
廃刊の危機を回避すべく、立ち上がった弱小第二編集部の面々。
これは企画を押しつけ……げふんげふん、もといまかされた女子部員たちが、
取材絡みでちょっと不思議なことを体験する物語である。

未来スコープ ―キスした相手がわからないって、どういうこと!?―
米田悠由
児童書・童話
「あのね、すごいもの見つけちゃったの!」
平凡な女子高生・月島彩奈が偶然手にした謎の道具「未来スコープ」。
それは、未来を“見る”だけでなく、“課題を通して導く”装置だった。
恋の予感、見知らぬ男子とのキス、そして次々に提示される不可解な課題──
彩奈は、未来スコープを通して、自分の運命に深く関わる人物と出会っていく。
未来スコープが映し出すのは、甘いだけではない未来。
誰かを想う気持ち、誰かに選ばれない痛み、そしてそれでも誰かを支えたいという願い。
夢と現実が交錯する中で、彩奈は「自分の気持ちを信じること」の意味を知っていく。
この物語は、恋と選択、そしてすれ違う想いの中で、自分の軸を見つけていく少女たちの記録です。
感情の揺らぎと、未来への確信が交錯するSFラブストーリー、シリーズ第2作。
読後、きっと「誰かを想うとはどういうことか」を考えたくなる一冊です。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















