1 / 1
花咲か列車
しおりを挟む
享年十七歳。
俗名は、ポチ。
ミックスの白い犬は、十五歳の私より長く生きたことになる。
私が物心ついた頃からすでに居て、人生の先輩であり、お兄さんであり、良き友であった。
ポチが闘病の末に亡くなったとき、ほっと胸をなで下ろす自分が居た。
排便も立ち上がるのも困難な辛い姿をもう見なくてもいいから。
だから冷たくなっても涙がこぼれることはなかった。
ただ、心にポッカリと穴が空いたのは確かだ。
簡単な葬儀をあげ、父親と一緒に火葬場へと向かう。
もう3月の半ばだけど、窓をよぎる冬枯れの桜並木が寒々しい。
山の中の火葬場にもところどころに桜の木が植えられており、舞い散る桜の花びらと戯れていたポチの姿が思い起こされ、昨日のことのように懐かしんだ。
焼き場では早々にポチの固くなった体を台車に横たえる。
そして遺体を焼却炉に入れたとき――ふいに震えが来た。
もうポチはポチで無くなるのだ。
骨と灰になってしまうのだ。
写真ならいくらでもあるが、あの日向の匂いがした柔らかな毛に顔をうずめることはもうできない。
そう思うと、今まで冷静だったのが嘘のように動揺がこみ上げて来た。
体が震え、これ以上父親とポチが焼き終わるのを待っていられなかった。
私は弾けるようにその場をあとにし、敷地内を走りに走った。
息が切れたところでようやく火葬場を振り返る。
すると――、突風が吹きつけ思わず腕で顔をおおった。
次に景色を目にしたとき、私はまんまると見開いた。
そこは火葬場の敷地ではなく、古びたプラットホームだったからだ。
しかも停車しているのは実物を初めて目にする蒸気機関車に他ならない。
ふいに甲高い笛の音が鳴り響いた。
するとこれに乗らねばという衝動に駆られ、急いで乗り込む。
機関車は蒸気を吐き出し、ゆっくりゆっくり動き出した。
勢いに任せて乗ったものの、この行き先は知りようも無い。
他に乗客も見当たらず、とりあえず窓側の席に腰をおろした。
窓の外では冬枯れの木々が後ろの方に流れてゆく。
まだ春は遠いように思われ、なんだかわびしい気持ちになった。
ふと、どこからか犬の鳴き声が聞こえて来る。
窓の外では白い影が駆けていた。
あれは、そんな、ポチ!
だけど一匹じゃ無い。
小さな女の子もポチと一緒に走っていた。
私だ。幼い私がポチと駆けっこをしている。
やがてその懐かしい光景は後ろへと流れ去ってしまった。
それからもポチが現れ、少しずつ成長してゆく私も併走している。
けれどあるときを境に、ポチ一匹だけとなった。
ポチは時折こちらを見やりながら、機関車とともに走り続けていた。
窓の外は過去を通り越して、死者の時間に突入したのかもしれない。
やがてポチは加速し始め、機関車よりも速くなり、ずっと先へ先へと行ってしまった。
待って!
私は立て付けの悪い窓をこじ開ける。
顔を出しポチの背中を追うがもう見当たらなかった。
ふいに灰色の煙が吹きつけ、顔を背後にそむける。
そこで私の目は驚きに見開かれた。
機関車が通り過ぎた景色に満開の桜が咲き誇っていたからだ。
よくよく見ていれば、機関車の排煙が触れた枯れ木はたちまち桜の花を咲かせていた。
この機関車はひょっとしたら桜前線なのかもしれない。
死者の遺灰を燃料に日本列島を上ってゆくのだ。
そう思い至ったら、急な眠気に襲われる。
私は座席に崩れ落ち、意識がゆるりと遠のいていった。
自分の名を呼ばれ目を覚ました。
私はいつの間にかベンチで眠りこけていたらしい。
お父さんがもう春だなぁと私の背後を見つめていた。
振り向くと、桜の木にいくつかの花が咲いている。
これはきっとポチが咲かせた花だ。
ポチは遠いところに行ってしまったけれど、いずれ私がそこに至ったとき、また桜並木の間を駆けっこしようと思った。
俗名は、ポチ。
ミックスの白い犬は、十五歳の私より長く生きたことになる。
私が物心ついた頃からすでに居て、人生の先輩であり、お兄さんであり、良き友であった。
ポチが闘病の末に亡くなったとき、ほっと胸をなで下ろす自分が居た。
排便も立ち上がるのも困難な辛い姿をもう見なくてもいいから。
だから冷たくなっても涙がこぼれることはなかった。
ただ、心にポッカリと穴が空いたのは確かだ。
簡単な葬儀をあげ、父親と一緒に火葬場へと向かう。
もう3月の半ばだけど、窓をよぎる冬枯れの桜並木が寒々しい。
山の中の火葬場にもところどころに桜の木が植えられており、舞い散る桜の花びらと戯れていたポチの姿が思い起こされ、昨日のことのように懐かしんだ。
焼き場では早々にポチの固くなった体を台車に横たえる。
そして遺体を焼却炉に入れたとき――ふいに震えが来た。
もうポチはポチで無くなるのだ。
骨と灰になってしまうのだ。
写真ならいくらでもあるが、あの日向の匂いがした柔らかな毛に顔をうずめることはもうできない。
そう思うと、今まで冷静だったのが嘘のように動揺がこみ上げて来た。
体が震え、これ以上父親とポチが焼き終わるのを待っていられなかった。
私は弾けるようにその場をあとにし、敷地内を走りに走った。
息が切れたところでようやく火葬場を振り返る。
すると――、突風が吹きつけ思わず腕で顔をおおった。
次に景色を目にしたとき、私はまんまると見開いた。
そこは火葬場の敷地ではなく、古びたプラットホームだったからだ。
しかも停車しているのは実物を初めて目にする蒸気機関車に他ならない。
ふいに甲高い笛の音が鳴り響いた。
するとこれに乗らねばという衝動に駆られ、急いで乗り込む。
機関車は蒸気を吐き出し、ゆっくりゆっくり動き出した。
勢いに任せて乗ったものの、この行き先は知りようも無い。
他に乗客も見当たらず、とりあえず窓側の席に腰をおろした。
窓の外では冬枯れの木々が後ろの方に流れてゆく。
まだ春は遠いように思われ、なんだかわびしい気持ちになった。
ふと、どこからか犬の鳴き声が聞こえて来る。
窓の外では白い影が駆けていた。
あれは、そんな、ポチ!
だけど一匹じゃ無い。
小さな女の子もポチと一緒に走っていた。
私だ。幼い私がポチと駆けっこをしている。
やがてその懐かしい光景は後ろへと流れ去ってしまった。
それからもポチが現れ、少しずつ成長してゆく私も併走している。
けれどあるときを境に、ポチ一匹だけとなった。
ポチは時折こちらを見やりながら、機関車とともに走り続けていた。
窓の外は過去を通り越して、死者の時間に突入したのかもしれない。
やがてポチは加速し始め、機関車よりも速くなり、ずっと先へ先へと行ってしまった。
待って!
私は立て付けの悪い窓をこじ開ける。
顔を出しポチの背中を追うがもう見当たらなかった。
ふいに灰色の煙が吹きつけ、顔を背後にそむける。
そこで私の目は驚きに見開かれた。
機関車が通り過ぎた景色に満開の桜が咲き誇っていたからだ。
よくよく見ていれば、機関車の排煙が触れた枯れ木はたちまち桜の花を咲かせていた。
この機関車はひょっとしたら桜前線なのかもしれない。
死者の遺灰を燃料に日本列島を上ってゆくのだ。
そう思い至ったら、急な眠気に襲われる。
私は座席に崩れ落ち、意識がゆるりと遠のいていった。
自分の名を呼ばれ目を覚ました。
私はいつの間にかベンチで眠りこけていたらしい。
お父さんがもう春だなぁと私の背後を見つめていた。
振り向くと、桜の木にいくつかの花が咲いている。
これはきっとポチが咲かせた花だ。
ポチは遠いところに行ってしまったけれど、いずれ私がそこに至ったとき、また桜並木の間を駆けっこしようと思った。
0
この作品の感想を投稿する
あなたにおすすめの小説

ローズお姉さまのドレス
有沢真尋
児童書・童話
*「第3回きずな児童書大賞」エントリー中です*
最近のルイーゼは少しおかしい。
いつも丈の合わない、ローズお姉さまのドレスを着ている。
話し方もお姉さまそっくり。
わたしと同じ年なのに、ずいぶん年上のように振舞う。
表紙はかんたん表紙メーカーさまで作成


緑色の友達
石河 翠
児童書・童話
むかしむかしあるところに、大きな森に囲まれた小さな村がありました。そこに住む女の子ララは、祭りの前日に不思議な男の子に出会います。ところが男の子にはある秘密があったのです……。
こちらは小説家になろうにも投稿しております。
表紙は、貴様 二太郎様に描いて頂きました。

魔女は小鳥を慈しむ
石河 翠
児童書・童話
母親に「あなたのことが大好きだよ」と言ってもらいたい少女は、森の魔女を訪ねます。
本当の気持ちを知るために、魔法をかけて欲しいと願ったからです。
当たり前の普通の幸せが欲しかったのなら、魔法なんて使うべきではなかったのに。
こちらの作品は、小説家になろうとエブリスタにも投稿しております。

王女様は美しくわらいました
トネリコ
児童書・童話
無様であろうと出来る全てはやったと満足を抱き、王女様は美しくわらいました。
それはそれは美しい笑みでした。
「お前程の悪女はおるまいよ」
王子様は最後まで嘲笑う悪女を一刀で断罪しました。
きたいの悪女は処刑されました 解説版

お姫様の願い事
月詠世理
児童書・童話
赤子が生まれた時に母親は亡くなってしまった。赤子は実の父親から嫌われてしまう。そのため、赤子は血の繋がらない女に育てられた。 決められた期限は十年。十歳になった女の子は母親代わりに連れられて城に行くことになった。女の子の実の父親のもとへ——。女の子はさいごに何を願うのだろうか。

そうして、女の子は人形へ戻ってしまいました。
桗梛葉 (たなは)
児童書・童話
神様がある日人形を作りました。
それは女の子の人形で、あまりに上手にできていたので神様はその人形に命を与える事にしました。
でも笑わないその子はやっぱりお人形だと言われました。
そこで神様は心に1つの袋をあげたのです。
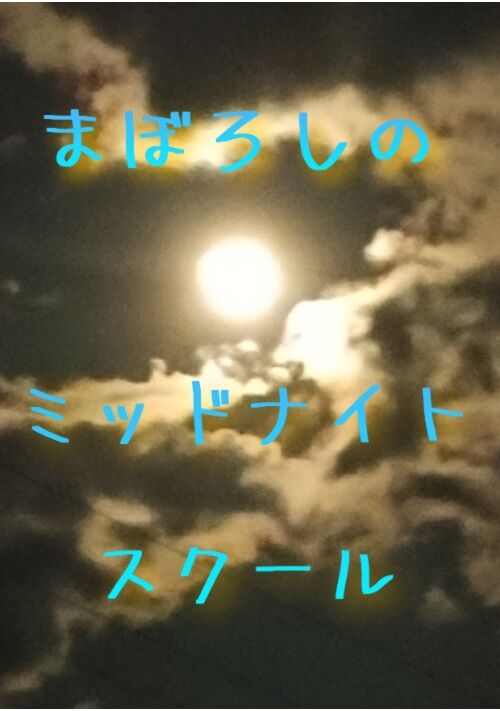
まぼろしのミッドナイトスクール
木野もくば
児童書・童話
深夜0時ちょうどに突然あらわれる不思議な学校。そこには、不思議な先生と生徒たちがいました。飼い猫との最後に後悔がある青年……。深い森の中で道に迷う少女……。人間に恋をした水の神さま……。それぞれの道に迷い、そして誰かと誰かの想いがつながったとき、暗闇の空に光る星くずの方から学校のチャイムが鳴り響いてくるのでした。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















