3 / 4
第3章:明かされる裏切りと真実の愛
しおりを挟む婚約破棄から時が経ち、ミアータ・クラレットの周囲には少しずつ変化の兆しが現れていた。かつては「完璧な公爵令嬢」として息苦しいほどに礼儀や体裁を守り、社交界の華やかな舞台に立ち続けていた彼女。だが、現在は孤児院への支援活動を自らの意思で行い、子供たちと触れ合う中で新たな自分を発見しつつある。
公爵家の両親も最初こそ心配を隠せなかったものの、今では「これは娘にとって大事な成長かもしれない」と、ある程度見守ってくれているようだった。使用人たちも、以前の“完璧さを求めるお嬢様”とは少し違う、柔らかな雰囲気のミアータに戸惑いながらも、彼女がどこか活き活きとしていることを感じ取っていた。
――しかし、そんな平穏とは裏腹に、社交界では少々穏やかならぬ噂が広まりつつある。かつてミアータの婚約者だったアレン・ヴァーサー侯爵家の嫡男が、平民出身の令嬢リリー・ハートとの新しい婚約を取り交わしたものの、どうもその相手に不審な点があるらしい。しかも、アレン自身の態度もどこか落ち着きを失っているというのだ。
婚約破棄後、表面上は「双方の合意により解消した」という形になっているが、実際には「アレンが平民令嬢に心を奪われ、ミアータを捨てた」という事実に近い噂が大半を占める。しかも、かの令嬢リリーは“財産目当て”なのではないかという疑いが一部で囁かれていた。とはいえ、アレンがどれほど周囲からやんわり警告されても、「リリーは純粋で可憐な女性だ」と耳を貸さないらしい。
そうした状況を知りつつも、ミアータはあえて深く立ち入ろうとはしなかった。もう自分には関係のない話だと思うようにしていたし、そもそも彼女自身、孤児院の支援や日々の新しい学びに忙しくしている。そこへ無理やり首を突っ込む必要などない――そう信じていた。
けれども、運命というものは時に残酷で、当事者同士を再び引き合わせる力を持っている。やがてミアータは、アレンとリリーの裏切りにまつわる真実を、予想もしない形で目の当たりにすることになるのだった。
---
王宮からの招待
ある日の朝、ミアータはいつものように早起きをして、孤児院へ届ける書類の整理をしていた。書類といっても、孤児院の修繕に関する見積もりや、募金に協力してくれる貴族への依頼文、さらには子供たちの学習道具の購入リストなど、多岐にわたる。
最近のミアータは、使用人まかせにせず、自分で書類を読み解き、必要に応じて手紙を書き、送る――そうした実務的な作業に興味を持ち始めていた。元々、教養や文字の素養は十分すぎるほど叩き込まれているので、やってみると意外に面白い。むしろ、こういう地道な仕事のほうが、華やかな社交よりも充実感が得られると感じていた。
そんなとき、執事がノックをして部屋へ入り、恭しく一礼をした。
「お嬢様、王宮から晩餐会の招待状が届いております。数日後に行われるそうで、貴族はほぼ全員招かれるとのことです」
「晩餐会……ですか」
ミアータは一瞬、過去の記憶がよみがえる。そういえば、少し前にも王宮での舞踏会で、アレンから婚約破棄を告げられたのだった。あの時の苦い思い出がまだ完全には癒えていない。
しかし、この晩餐会はけっこう大規模で、国王陛下や王妃をはじめとする王族も出席する公式行事であるらしい。出席しないとなれば、公爵家としては立場が悪くなる可能性もある。
「わかりました。出席いたしましょう。それに……」
と、ミアータは書類に視線を戻しつつ、思案顔になる。普段なら「公爵令嬢として、社交を嫌がるわけにはいかない」と言い聞かせて終わるところだが、今は気持ちが少し違う。
「この晩餐会には、きっとアレン様もリリー様も来るかもしれないわね……。正直、会いたいとは思わないけれど……」
胸にわずかに疼くものを感じながらも、彼女は決意を固める。「逃げるわけにはいかない。私の人生はもう、あの人とは別方向に動き出しているのだから」と。
---
招かれざる再会
当日、王宮の大広間は照明が燦然と輝き、絢爛たる装飾が隅々まで施され、上流貴族たちが集っていた。ミアータは淡いピンク色のドレスに身を包んでいる。派手すぎないが、優美なラインを強調する仕立てで、彼女の銀色の髪と透き通るような肌をより一層美しく見せていた。
周囲が彼女を見つめる視線は、以前と変わらず「微笑みの薔薇」への称賛に満ちている。ただ、彼女自身はその視線を殊更に意識することなく、控えめに会場を歩き回っていた。両親も別の貴族たちと会話し、ミアータは適宜挨拶を交わしながら、ある一点が気にかかっていた。
「やはり、アレン様もいらしているようね……」
遠目に見えるあの金髪の男性――間違いない。隣には小柄で儚げな美貌の令嬢が寄り添っている。周囲の視線は、どうやら好奇の入り混じったものが多い。
それこそが“彼女”、リリー・ハートだ。緊張しているのか、アレンの腕をぎゅっとつかんで離そうとせず、愛らしい笑みを浮かべている。確かに可憐で清純な雰囲気の女性ではあるが、やや視線が泳いでいるようにも見えた。
「あ……」
リリーがミアータに気づき、微かに目を伏せる。アレンも遅れて彼女に視線を向け、その瞬間、空気がひりついたのを感じる。婚約破棄の当事者同士が、こうして多くの人がいる場で真正面から顔を合わせるのは初めてだった。
ミアータはわずかに胸がざわつくが、すぐに完璧な令嬢らしい微笑みを浮かべて会釈をする。
「ごきげんよう、アレン様。リリー様も、ご無沙汰しております。ご婚約の噂、拝聴いたしましたわ。おめでとうございます」
――完全に取り乱すことはない。心の中では複雑な想いが渦巻いているが、彼女は堂々とした態度を崩さない。
一方、アレンはわずかに口を開いたものの、うまく言葉が出ないのか、「あ……ああ……」と曖昧に返事をして、目を逸らす。リリーも戸惑ったように視線を彷徨わせた。
「……ご丁寧にありがとうございます、ミアータ様。私たちは……その、まだまだ未熟な二人ですが、どうか見守っていただければ……」
リリーはか細い声でそう言い、ミアータに向かっておずおずと頭を下げる。その仕草は儚げだが、どこか計算めいた色も感じられ、ミアータは胸中でふと疑問を抱いた。
しかし、この場で問いただす理由はない。ミアータはただ「どうぞお幸せに」と言葉を残し、さらりと踵を返してその場を離れた。これ以上、視線を集めて周囲の噂になるのは望まないし、何より自分の心が大きく乱されるのを避けたかったからだ。
---
若き侯爵カイルの存在
ミアータが大広間を出て、息を整えながら廊下を歩いていると、後ろから軽やかな足音が近づいてきた。
「ミアータ様、先ほどは大丈夫でしたか?」
声の主は、前章でも登場したカイル・エルネスト侯爵である。若いながらも立派な侯爵領を受け継ぎ、経営手腕や人望に優れていると評判の人物だ。
ミアータは驚きながらも、「ああ、カイル様……。お気遣いありがとうございます」と少し硬い笑みを返す。
「やはり、アレン殿たちにお会いになりましたね。お二人が会場にいらしたのを見て、ミアータ様がどんなお気持ちか気になっていたのです。無理に心配するようで失礼かもしれませんが……」
彼の声には本心からの優しさが滲んでいる。そこには下心のようなものは感じられず、ただ純粋に彼女の状況を案じているようだった。
「お気にかけてくださり、恐縮です。大丈夫ですよ。もう、あの方とは終わったことですから」
ミアータはそっと胸に手を当て、深呼吸をする。実際、アレンに会ったことで多少心が揺れたのは事実だが、彼女は自分の心を必死に立て直していた。
「そうでしたか。よかった。もし何か辛いことがあれば、私に相談していただいても構いませんよ。いつでも協力を惜しみませんから」
カイルは笑みを浮かべる。その穏やかな表情を見て、ミアータは「なんと話しやすい人なのだろう」と感じた。婚約破棄以来、彼は公爵家を訪ねる機会が増え、時々「孤児院支援の件で力になれませんか」と声をかけてくれることもあった。
「ありがとうございます。本当にそうおっしゃっていただけると心強いわ。ところで、今度また孤児院へ行く予定があるのですが、もしよろしければカイル様もご一緒にいかがですか?」
思い切って誘ってみたのは、純粋に支援活動の参考意見がほしかったからだ。カイルは貴族でありながら領地経営に長け、地域住民の生活を向上させる施策を進めていると噂で聞く。それならば、孤児院や貧困層の問題にも、何か的確なアドバイスをくれるかもしれない。
「ええ、ぜひ。お誘いいただけるなんて嬉しいです。具体的な日程を決めてご連絡いただければ、都合のつく限り同行させていただきますよ」
カイルは快諾した。そのときの笑顔は、先ほどのアレンの曖昧な表情とは対照的に、どこまでも澄んでいて頼もしかった。ミアータはその笑顔にほんの少しだけ癒される思いがした。
---
舞台裏の陰影
晩餐会が進むにつれ、ミアータはできるだけ控えめに行動し、必要最低限の挨拶を済ませると、疲れを理由に早めに会場を後にしようとした。
すると、帰り支度を整えていた彼女の耳に、ちらりと聞こえてきた会話があった。
「リリー・ハートという娘、最近やけに派手に買い物をしているらしいぞ……。どこからそのお金が出ているのやら」
「ヴァーサー侯爵家はさほど浪費を許す家柄ではないと聞くが……。まさか、誰かスポンサーがいるとか?」
噂好きな貴族たちのひそひそ話だった。直接リリーの名が出ている以上、アレンやヴァーサー家を指しているのは明らかだ。
ミアータは自分の胸がざわつくのを感じたが、そこで立ち聞きを続けるのは品位に欠けると判断し、そっと踵を返した。真相はともかく、リリーに何らかの後ろ暗い事情があるらしい。それが事実なら、アレンは危うい状況に置かれているかもしれない。
「だけど……もう私には関係のないことよね」
そう自分に言い聞かせるようにして、ミアータは馬車に乗り込み、王宮を後にした。だが、この時、胸に宿った微かな不安は、やがて大きな事件へと繋がっていく――彼女はまだそのことを知らない。
---
新たな孤児院訪問
晩餐会から数日後、ミアータはカイル・エルネスト侯爵と共に孤児院を訪問することになった。カイルは「お土産に」と大量の教材や子供向けの本を持参し、しかもそれを自ら抱えて馬車を降りる。
「これだけあれば、子供たちも退屈しないでしょう。読み書きの練習にも使えそうですしね」
カイルは満面の笑みだ。遠巻きに見ていた子供たちが、最初は「わぁ……誰?」と戸惑い気味だったが、やがて「その箱、なあに?」と興味津々に寄ってくる。
ミアータも思わず微笑んでしまう。もともとカイルの明るく物怖じしない性格は聞いていたが、ここまで子供たちとすぐに打ち解ける様子を見ると、「彼は本当に人を惹きつける力があるのだな」と実感させられる。
孤児院の院長も大喜びで、「これはありがたい……! 勉強道具や絵本はとても助かります。お子たちもきっと大事に使います」と礼を述べた。もっとも、この孤児院はまだまだ修繕が追いつかず、建物の老朽化は深刻だ。特に廊下や屋根の痛みは目に余る状態だが、それを直すには大掛かりな資金が必要になる。
ミアータは院長と話し合いながら、「修繕のための募金活動をどう進めればいいか」をカイルにも相談してみた。
「私だけの私財で賄うことも不可能ではないのですが、いずれ孤児院の方々が自立し、安定して運営していくためには、外部からの寄付を幅広く募る仕組みづくりが不可欠だと思うのです。でも、私はそのような計画を立てた経験がなくて……」
ミアータが正直に打ち明けると、カイルは真剣な表情で頷く。
「確かに、単発の大金だけでは長続きしません。定期的に支援を受けるルートを作り、孤児院側がそれをうまく活用できるようになれば理想的です。自治体や商人ギルドなどの協力も得られれば、さらに効果的でしょう。私の領地でも似たような仕組みを作ったことがありますから、後ほど資料を共有しましょうか」
「ぜひ……! それはとても助かります」
ミアータは嬉しそうに答える。彼女の横顔を見つめるカイルの瞳は、どこか温かな光を宿していた。
その日、二人は孤児院で子供たちと昼食をともにし、簡単な勉強会や遊びを手伝ったあと、まだ手をつけられていない施設部分を視察して回った。カイルは合間合間に的確なアドバイスをくれる。
「配管や壁の修繕は専門業者に頼まないと危険ですね。費用を押さえたいなら、信頼できる業者の一括見積もりを取るといいかもしれません」
「これだけの規模だと工期も長くなるでしょうけれど、子供たちの生活空間が安全でないと、大きな事故にも繋がりかねませんよね……」
話を交わすうちに、ミアータの心にある思いが強くなる。「私が本当に求めていたのは、こういう人との協力や、誰かの役に立つ生き方なのかもしれない」と。彼女は決して足りないものを“与えるだけ”の存在でいたくはない。いっしょに学び、いっしょに成長し、よりよい未来を築く一員として関わりたいのだ。
---
不穏な影――動き出す噂
充実した孤児院訪問を終え、公爵家の屋敷へと戻る道すがら。ミアータは馬車の窓を開け、心地よい夕風に当たりながら思いにふけっていた。
――いつの間にか、アレンのことは頭から離れている。以前であれば「彼は今、どんな様子でいるのだろう」とくよくよ考えそうなものだが、今はそれ以上にやるべきことが多いし、新たな道を切り拓こうとする意欲のほうが勝っている。
しかし、その夜。彼女が明かりを落とす直前、使用人が慌てた様子で駆け寄ってきた。
「お嬢様、大変失礼いたします。夜分に申し訳ないのですが……少し、お耳に入れたいことがありまして……」
どうやら、またしてもアレンとリリーにまつわる噂が社交界で大きく取り沙汰され始めたという。リリーは平民出身であるにもかかわらず、やたらと贅沢三昧をしている。その金の出所がどこなのか不可解だというのが、貴族たちの興味を煽っているらしい。
「それだけなら、よくある噂話の範疇かもしれませんが……」と、使用人は話を続ける。「一部では、リリーが複数の貴族や商人から“借金”という名目で金を巻き上げているのではないか、という疑いが出ているんです。中にはかなり悪質な条件のものもあるとか……」
ミアータは思わず眉をひそめる。「それが本当なら、アレン様は気づいているのかしら?」と。
もちろん、婚約破棄して別々の道を歩む身だが、もしアレンがリリーに利用されているのだとしたら、それはあまりに気の毒だ。さらに、下手をすればヴァーサー侯爵家の信用問題にも関わるだろう。
「公爵令嬢として何ができるのか、そこまでは……」
使用人は歯切れ悪く言葉を濁すが、ミアータは静かに頷いた。
「わかりました。知らせてくれてありがとう。私から動くのは難しいけれど、正しい情報を得る努力はしてみます」
心に暗雲が広がるのを感じつつも、ミアータは冷静さを失わないように努めた。かつての自分なら、元婚約者の事情など見て見ぬふりをして、“自分には関係ない”と済ませるかもしれない。だが、今のミアータは、過去を知り、社交界の一員として責任を感じ始めていた。
---
明かされる裏切り
噂がどんどん拡大していく中、事態は意外な方向から急転していく。
ある日、ミアータが書斎で孤児院の資料を読んでいると、執事が急ぎの来訪を告げに来た。
「ミアータ様、アレン・ヴァーサー侯爵家のご子息が、当邸を訪ねておいでです。今、応接室へご案内しておりますが……」
「……アレン様が? どうして突然……」
ミアータは驚きを隠せない。婚約破棄以来、一度も直接会話を交わすことのなかった人物が、突如として訪問してきたのだ。何かよほどの事情があるに違いない。
心を落ち着けるために、ミアータは軽く深呼吸をし、ドレスの裾を整えてから応接室へ向かった。扉を開けると、そこには憔悴しきった様子のアレンが座っている。頰はこけ、姿勢もやや乱れ、かつてのキラキラした貴公子の面影はだいぶ薄れていた。
「アレン様……。お久しぶりですわね」
当たり障りのない挨拶をしながら、ミアータは相手の表情を探る。
「……ああ、久しぶりだな、ミアータ」
アレンの声は弱々しく、目の下には隈ができている。まるで眠れぬ夜を過ごしてきたかのようだ。
「今日はどうされたのですか? 私に何か用がおありなのでしょう」
ミアータはソファに腰掛け、静かに問いかける。アレンは顔を伏せながら、微かに震える手を握りしめていた。
「……リリーのことだ。お前も、噂は聞いているかもしれないが……彼女があちこちで金を借りているらしい。俺は最初、それをまったく知らなかった」
やはり、表沙汰になったリリーの借金問題だろう。それが原因でアレンが追い詰められているのか。
「それが真実だとしたら……アレン様はどうするつもりなの?」
ミアータは努めて冷静に尋ねる。だが、アレンは苦しげに唸るように言葉を漏らす。
「彼女は『私たちが結婚すれば、あなたの家の財産で返済できるから大丈夫』と言うんだ。俺はそれを聞いて初めて、自分が利用されているんじゃないかと疑い始めた……。けど、もう遅かった。リリーの借金は、総額が想像を絶するほど膨れ上がっていて、返済の期日も迫っているんだ」
その衝撃的な告白に、ミアータは思わず言葉を失う。財産目当てだという噂は半ば本当だったようだ。しかも、その金額はヴァーサー侯爵家にとっても大きな負担になりかねないレベルらしい。
「それで……私のところに相談にいらしたの?」
「正直、俺にはもうどうしていいかわからない。父にも報告したが、激怒されて、リリーとの婚約は解消しろと言われている。でも……俺は、もしかしたら彼女が純粋に俺を愛してくれている可能性もあると思うと……。だけど、これ以上彼女を庇えば、家が傾きかねない」
アレンの瞳はうつろで、精神的に追い詰められているのが見て取れる。婚約破棄の当事者に今さら助けを求められても困る、というのが正直なところではあるが、彼がすがる思いでやって来たことは明白だった。
「あなたはどうしたいの? 家のためにリリー様を切り捨てるのか、それとも、彼女に全てを賭けるのか……。私に言えるのは、それしかありませんわ」
ミアータは冷静さを失わないまま、言葉を投げかける。自分がその決断を代わりに下すことはできないし、すべきではない。
アレンはしばし沈黙し、やがてうなだれながら呟いた。
「……わからない。わからないんだ。俺はリリーを……好きだと思った。だけど、こんな形で彼女に裏切られるなんて……。もし俺が、あのときお前との婚約を壊さなければ、こんなことにはならなかったかもしれないと思うと……」
思わずその言葉に、ミアータの心がちくりと痛む。あの夜、自分の前で「お前の完璧さが息苦しい」と言い放った彼が、今はすっかり弱った姿で後悔を口にしているのだ。
「アレン様……、私にできることはあまりありません。あなたの家とリリー様の問題ですから。ただひとつ言えるのは、何を選んでも、その結果は自分で受け止めなければならないということ」
それが、かつて“完璧でいること”に縛られ、自らも追い詰められていたミアータが学んだ真実だった。逃げることは簡単だが、必ずどこかで代償が訪れる。
アレンは暗い表情のまま、「……そうだな」と小さく答えたきり、部屋を後にしていった。結局、彼は具体的な救いを得られなかったが、もはやミアータが手を差し伸べる義理はない。むしろ、かつて自分を捨てた彼が、今は別の女性によって追い詰められている――皮肉な巡り合わせである。
けれども、ミアータは決して「あの人にざまあみろと思う」ような安直な喜びは抱かなかった。むしろ、「こんな形で壊れなくてもいいのに」と胸が痛んだ。人と人との絆が傷つけられるのを、彼女は決して望まないのだ。
---
真実の愛――カイルとの距離
アレンの訪問に動揺を隠せないまま、ミアータは夜を迎えた。屋敷の灯火が次々と消される中、彼女は書斎に一人腰掛けて、考えを巡らせる。
「アレン様は、このままリリー様と破滅の道を歩んでしまうのか……。かといって、私が何かできるわけでもない。あれはもう、彼自身が清算すべき問題だわ」
頭ではそう割り切っていても、かつて親しかった相手が苦しんでいることを完全に放っておくのは心苦しい。それでも、自分から干渉すれば、かえって相手を混乱させるだけかもしれない。
そんな葛藤を抱える中、ふいに扉がノックされる。入ってきたのは母である公爵夫人だった。
「こんな時間まで起きているのね。大丈夫? 顔色がすぐれないわ」
母親は心配そうな眼差しで近づき、娘の肩にそっと手を置く。ミアータは一瞬戸惑いながらも、静かに首を振った。
「少し考えごとをしていただけよ。婚約破棄の件で……アレン様がこちらを訪ねてきたの」
「そう……やはり何かあったのね」
母親はため息交じりに言うと、続けて優しい声で言葉をかける。
「あなたはもう十分、前へ進んでいるじゃない。孤児院を手助けして、新しい道を模索して……。たとえアレン殿が苦しんでいても、あなたが背負う必要はないわ。ここは一度、距離をおきなさい」
その言葉は、ミアータの心に静かに染み込んだ。母は、娘を単に突き放すのではなく、「あなたにはあなたの人生がある」ということを優しく伝えたかったのだろう。
「ええ……そうね。ありがとう、母様。私は私の道を……」
そう呟いたとき、自然とある人物の姿が脳裏に浮かぶ。孤児院で頼もしいアドバイスをくれ、子供たちと笑顔で触れ合っていたカイル・エルネスト侯爵。彼の存在は、ミアータの中で日増しに大きくなりつつあるのを感じていた。
「彼は私を支えてくれるのかしら。それとも、私が彼に近づきたいと思うのは、まだ早いのか……」
これまで“完璧な婚約者”として振る舞ってきたミアータにとって、新しい恋や愛への踏み出し方はまったく未知の領域だ。だが、そっと目を閉じると、カイルの温かい笑顔と穏やかな声が脳裏に蘇り、胸がきゅんと疼くのを感じる。
「あの時の私には、アレン様への気持ちが本物だったのか、それとも世間体のための義務感だったのか……。少なくとも今、私の心は別の人に強く惹かれている気がする」
母親の前で露わにするわけにはいかないが、ミアータは自室に戻ると、ベッドに腰を下ろし、一人そっと胸を押さえた。そして小さな声で告げる。
「真実の愛……。そんなものが私にも見つかるのかしら。でも、きっと……今の私なら、恐れずに探してみたいと思えるわ」
---
そして夜が明ける
アレンが直面する“裏切り”は、いよいよ取り返しのつかないところまで進んでいるようだ。リリーは多額の借金を整理できず、ヴァーサー侯爵家の名声を利用して返済の猶予を得ようと画策しているらしい。だが、それがうまく運ばなければ、アレンは貴族社会からの信用を失いかねない。
一方、ミアータはそれに巻き込まれないよう心を砦のように固めつつ、孤児院の支援活動や自分の将来への模索に打ち込んでいた。そこには、新たに芽生えた恋の可能性がかすかな光を放ち、彼女を支えてくれている。
---
0
あなたにおすすめの小説

あなたが幸せになるために
月山 歩
恋愛
幼い頃から共に育った二人は、互いに想い合いながらも、王子と平民という越えられない身分の壁に阻まれ、結ばれることは叶わない。
やがて王子の婚姻が目前に迫ると、オーレリアは決意する。
自分の存在が、最愛の人を不貞へと追い込む姿だけは、どうしても見たくなかったから。
彼女は最後に、二人きりで静かな食事の時間を過ごし、王子の前から姿を消した。

復讐のための五つの方法
炭田おと
恋愛
皇后として皇帝カエキリウスのもとに嫁いだイネスは、カエキリウスに愛人ルジェナがいることを知った。皇宮ではルジェナが権威を誇示していて、イネスは肩身が狭い思いをすることになる。
それでも耐えていたイネスだったが、父親に反逆の罪を着せられ、家族も、彼女自身も、処断されることが決まった。
グレゴリウス卿の手を借りて、一人生き残ったイネスは復讐を誓う。
72話で完結です。
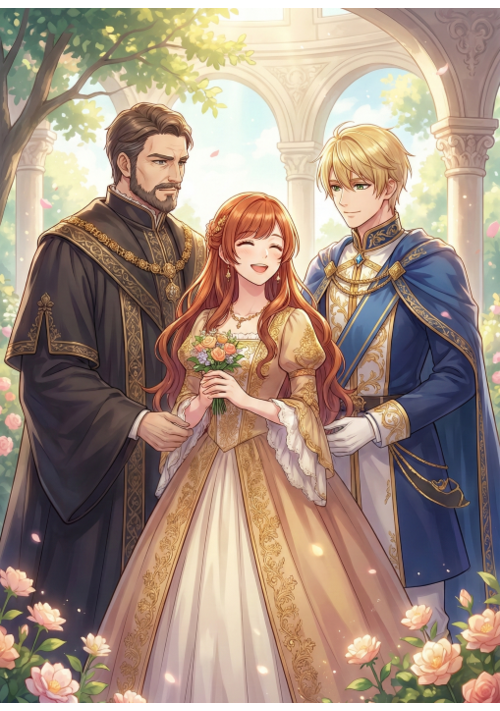
処刑された悪役令嬢、二周目は「ぼっち」を卒業して最強チームを作ります!
みかぼう。
恋愛
地方を救おうとして『反逆者』に仕立て上げられ、断頭台で散ったエリアナ・ヴァルドレイン。
彼女の失敗は、有能すぎるがゆえに「独りで背負いすぎたこと」だった。
ループから始まった二周目。
彼女はこれまで周囲との間に引いていた「線」を、踏み越えることを決意した。
「お父様、私に『線を引け』と教えた貴方に、処刑台から見た真実をお話しします」
「殿下、私が貴方の『目』となります。王国に張り巡らされた謀略の糸を、共に断ち切りましょう」
淑女の仮面を脱ぎ捨て、父と王太子を「共闘者」へと変貌させる政争の道。
未来知識という『目』を使い、一歩ずつ確実に、破滅への先手を取っていく。
これは、独りで戦い、独りで死んだ令嬢が、信頼と連帯によって王国の未来を塗り替える――緻密かつ大胆なリベンジ政争劇。
「私を神輿にするのなら、覚悟してくださいませ。……その行き先は、貴方の破滅ですわ」
(※カクヨムにも掲載中です。)

【完結】顔が良ければそれでいいと思っていたけれど、気づけば彼に本気で恋していました。
朝日みらい
恋愛
魔物を討伐し国を救った若き魔術師アリア・フェルディナンド。
国王から「望むものを何でも与える」と言われた彼女が選んだ褒美は――
「国一番の美男子を、夫にください」
という前代未聞のひと言だった。
急遽開かれた婿候補サロンで、アリアが一目で心を奪われたのは、
“夜の街の帝王”と呼ばれる美貌の青年ルシアン・クロード。
女たらし、金遣いが荒い、家の恥――
そんな悪評だらけの彼を、アリアは迷わず指名する。
「顔が好きだからです」
直球すぎる理由に戸惑うルシアン。
だが彼には、誰にも言えない孤独と過去があった。
これは、
顔だけで選んだはずの英雄と、
誰にも本気で愛されたことのない美貌の青年が、
“契約婚”から始める恋の物語。

幼馴染以上、婚約者未満の王子と侯爵令嬢の関係
紫月 由良
恋愛
第二王子エインの婚約者は、貴族には珍しい赤茶色の髪を持つ侯爵令嬢のディアドラ。だが彼女の冷たい瞳と無口な性格が気に入らず、エインは婚約者の義兄フィオンとともに彼女を疎んじていた。そんな中、ディアドラが学院内で留学してきた男子学生たちと親しくしているという噂が広まる。注意しに行ったエインは彼女の見知らぬ一面に心を乱された。しかし婚約者の異母兄妹たちの思惑が問題を引き起こして……。
顔と頭が良く性格が悪い男の失恋ストーリー。
※流血シーンがあります。(各話の前書きに注意書き+次話前書きにあらすじがあるので、飛ばし読み可能です)

永遠に君を手放さないと誓った、あの日の僕へ――裏切られ令嬢の逆転婚約劇
exdonuts
恋愛
婚約者に裏切られ、婚約破棄を告げられた夜。涙を堪えて背を向けたはずの彼女は、やがて社交界の華として再び姿を現す。
彼女を見捨てた元婚約者が後悔に苛まれる中、最も望んでいた“第二王子”の隣には、眩しいほどに美しくなった彼女の姿が。
――ざまぁは終わりじゃない。そこから始まる溺愛の物語。
強くなった令嬢と、彼女を二度と離さないと誓う男。
運命の再会が、愛と後悔をすべて覆す。

妹のために愛の無い結婚をすることになりました
バンブー竹田
恋愛
「エミリー、君との婚約は破棄することに決まった」
愛するラルフからの唐突な通告に私は言葉を失ってしまった。
婚約が破棄されたことはもちろんショックだけど、それだけじゃない。
私とラルフの結婚は妹のシエルの命がかかったものでもあったから・・・。
落ちこむ私のもとに『アレン』という大金持ちの平民からの縁談が舞い込んできた。
思い悩んだ末、私は会ったこともない殿方と結婚することに決めた。

【完結】第一王子と侍従令嬢の将来の夢
かずえ
恋愛
第一王子は、常に毒を盛られ、すっかり生きることに疲れていた。子爵令嬢は目が悪く、日常生活にも支障が出るほどであったが、育児放棄され、とにかく日々を送ることに必死だった。
12歳で出会った二人は、大人になることを目標に、協力しあう契約を交わす。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















