77 / 89
75、交錯する想い、終焉の時
しおりを挟む
だが——
「……っ!」
エリオットの前に、別の影が割り込んだ。
ヴェロニクの動きを止めたのは、他ならぬ アドリアン だった。
「アドリアン!?」
ヴェロニクの目が大きく見開かれる。
「なぜ——!!」
ナイフはアドリアンのわき腹に突き立っていた。
刃は深く刺さってはいなかったが、それでも白いシャツを赤く染め始めている。
彼は痛みを感じさせる素振りも見せず、ただ ヴェロニクを抱きしめた 。
「……お前は、こんなことをする人間じゃなかった」
低く、静かに囁かれた言葉が、ヴェロニクの耳に届いた。
「違う……!」
ヴェロニクはかぶりを振る。
「私は……こんなはずじゃ……!」
彼の声が震え、指先から力が抜ける。
ナイフが、カラン、と床に落ちた。
「……僕がここにいなければ、あなたは公爵夫人として満足できたんですか?」
エリオットが静かに問いかけた。
ヴェロニクは歯を食いしばる。
「お前がいたからだ! お前がいたから、アドリアンは私を——」
「違う」
アドリアンの声が鋭く割り込んだ。
「エリオットがいたからではない。……ヴェロニク、違う……」
その言葉が、ヴェロニクの胸に突き刺さる。
「嘘だ……嘘だ……!」
彼は必死に否定しようとした。
だが、アドリアンは揺るがない。
「私はお前を愛していた。だが、それは エリオットを否定するものではなかった ……エリオットが公爵夫人として振る舞い、お前は私の隣にいる——それが私の、愚かな理想だった」
ヴェロニクの目に、涙が滲む。
「そんなの……私は、そんなの望んでいなかった……!」
「……そうだろうな」
アドリアンは苦笑し、ヴェロニクの肩を掴んだ。
「だが、お前はそれを エリオットのせいにした 。私のせいではなく、お前自身の歪みを、エリオットのせいにした。違うか? 私は、ずっと欲望のためにお前を利用していたのに」
「私は……私は……」
ヴェロニクの唇が震える。
その時、静かな声が響いた。
「……いい加減にしたらどうですか?」
エリオットが小さく息を吐く。
「ヴェロニク」
冷静なまなざしが、彼を貫く。
「あなたのしてきたことを悔いるなら、それに相応しい責任を取るべきだ」
「責任……?」
ヴェロニクは苦々しく口にする。
「何を……今さら……」
歯を食いしばりながら、ヴェロニクは睨みつけるようにエリオットを見た。
「お前のせいだろう! すべて、お前がいたから……!」
声が震えている。
「お前がいなければ、私は……私は、公爵夫人としてアドリアンの傍に——」
「僕があなたに何かしましたか?」
エリオットの言葉は静かだった。
「僕は、決められた通りにここに嫁いできた。それだけです」
ヴェロニクの視界が揺らぐ。
エリオットの冷静な声が、頭の奥に響いて離れない。
「そして、僕は僕に向けられた刃を防ぎました。その結果があなたに向かった。それだけのことではないですか?」
ヴェロニクの呼吸が浅くなる。
(そんなはずはない……私は……私は……)
エリオットがすべてを奪ったのだ。
自分が、公爵夫人としてアドリアンの隣に立つはずだったのに。
アドリアンの愛を独占するはずだったのに。
「何も、していない……?」
ヴェロニクは愕然としたように目を見開く。
そうだ。エリオットは……何もしていない。
ヴェロニクを愛人の座から引きずり落とそうとしたわけでもない。
ただそこにいて、運命の通りに公爵夫人として存在していただけだ。
(私が……間違っていた?)
ヴェロニクの脳裏に、これまでの出来事が鮮やかに蘇る。
エリオットが初めて公爵邸に足を踏み入れた日。
自分が「番」としてアドリアンに紹介された日。
その瞬間にエリオットの瞳に浮かんだ、わずかな戸惑い。
そしてそれに感じた優越感。
何をすれば良かったのだろうか、自分は。
自分を選んでくれとアドリアンに直訴をすれば良かったのか。
それとも、アドリアンの望みを聞けばよかったのか。
──どちらにしろ、それは受け入れられたのか?
ヴェロニクはアドリアンを見る。
何も、わからなかった。
「違う! お前がいたから、私は——!」
言い募ろうとしたヴェロニクの声を、別の声が遮った。
「違う」
それは、アドリアンだった。
ヴェロニクは、その低く静かな声に凍りついたように口を閉じる。
「エリオットがいたからではない。……そうだろう? ヴェロニク」
アドリアンの瞳が、ヴェロニクを真っすぐに捉える。
「お前を選ばなかったのは、私だ」
アドリアンの声音は冷静だった。
そこには、今までヴェロニクが知っていた甘い響きはなかった。
心臓を、誰かの手で握り潰されたような感覚だった。
「私は……どちらも大事にできると思い込んでいた。自分の理想こそが最適だと信じていた」
ヴェロニクは、かぶりを振る。
(違う……そんなの、違う!)
「でも、私はお前を選ばなかった。エリオットを大切にすることも、お前を選ぶこともできなかった」
「やめろ……」
「私は、ただの愚か者だった」
ヴェロニクの膝が、がくりと揺らぐ。
アドリアンは……ヴェロニクを愛していた。
でも、それは「選ぶ」こととは違ったのだ。
最初から——ヴェロニクは「特別」ではなかったのか?
ヴェロニクはただ、床を見つめた。
そこに、彼の望んでいた「公爵夫人」の姿はなかった。
あるのは——壊れた理想の残骸だけだった。
「公爵閣下」
エリオットはアドリアンに向き直った。
「僕は、あなたを見捨てたのではなく、あなたが最初に僕を捨てたのです。結婚式の日に。これは恨み事ではない。唯の事実として申し上げますよ」
アドリアンの目がわずかに揺れた。
「……そう、だな」
彼は静かに言った。
「私は、自分がすべてを両立できると 思い上がっていた 。お前を傷つけ、お前の心を見ようともしなかった。ヴェロニクのことも……」
エリオットは静かに息を吐く。
「ええ。でも、もうそれも終わりです」
「ヴェロニク・クレイヴン」
シグルドが前に出て、冷ややかな声で言った。
「貴様を国家反逆の罪で拘束する」
開けられたままの扉から入ってきた兵士たちがヴェロニクの両腕を捕らえる。
「……っ!」
ヴェロニクは最後の抵抗を試みるように暴れかけたが、アドリアンがそっと首を振った。
「ヴェロニク、行くんだ」
「……っ……!」
ヴェロニクは、アドリアンを見つめる。
(なぜ……? なぜ、そんな顔をするんだ……?)
アドリアンの表情には、もはや怒りも、憎しみもない。
ただ、深い 慈しみ があった。
「ヴェロニク」
アドリアンは、静かに言葉を紡ぐ。
「……私は、待っている」
ヴェロニクの目が揺れる。
アドリアンは静かに微笑んでいた。
それは 慈しみと、どこか寂しげな笑み だった。
「……待つ?」
「お前が償うべきことを償い、やるべきことを終えたら……私が迎えに行く」
アドリアンの声は柔らかく、だが 確信を持っていた 。
「私にも何らかの沙汰はあるだろうが」
「……そんな」
ヴェロニクは、言葉を失った。
ヴェロニクはアドリアンを見上げた。
目の前の男は、これまで何度も自分のために微笑んでくれたはずの男だ。
なのに今は、その表情がどこか遠い。
ヴェロニクの視界がぼやける。
頬を伝うものの正体が、涙であることに気づいたのは、それから数秒後のことだった。
「……連れて行け」
シグルドの一声で、兵士たちがヴェロニクを連れ去る。
ヴェロニクは最後に、ほんの一瞬だけ振り返った。
アドリアンが、まだそこにいるのを見て、再び前を向いた。
彼はただ、静かに歩き続けるしかなかった——。
エリオットは静かにアドリアンを見た。
「……あなたは、どうするのですか?」
「私は——私も罪を償うべきなのだろう……ヴェロニクがああいった行動をとったのは私のせいでもある」
アドリアンは小さく息を吐き、ヴェロニクの去った扉を見つめる。
「……ふぅん、なるほど」
その呟きとともに、 レオン が部屋へと足を踏み入れた。
場の緊張がようやく解けかけたその瞬間に、
彼の どこか気楽そうな声 が響く。
「ヴェロニクの捕縛、お疲れさまです。いやぁ、まさかあの人がナイフを振り回すとは。でも、これでようやく公爵邸も少しは落ち着きそうですねぇ?」
「レオン」
エリオットが静かに顔を上げた。
ヴェロニクの連行を見届けた後も、まだ部屋には張り詰めた空気が残っていた。
「状況はどうですか?」
「ええ、公爵邸の内部は ほぼ制圧 できました。ヴェロニクの側についていた連中も、大半は抵抗せずに降伏。まぁ、無茶な抵抗をしても無駄だってことは、彼らも理解してるんでしょう」
レオンは肩をすくめ、朗らかに続ける。
「それと、例の 新しい執事さん 、あの人もなかなかしぶといですねぇ?」
「ラグランのことか?」
シグルドが目を細めた。
「ああ、そうそう。彼、クラウス侯爵からの派遣でしたけど——どうも 最初からきな臭いと思ってたみたいでしてね」
レオンはくすくすと笑う。
「ああ、だから彼は僕たちをここに案内したんですね」
「 素直な裏切りですよね~」
レオンは可笑しそうに言った。
ラグランはヴェロニク側の人間だと思っていたが、彼自身、 あまりヴェロニクに肩入れする気はなかった のかもしれない。
「まぁ、結局のところ 自分の身の安全が最優先 だったってことでしょうねぇ。クラウス侯爵がここまで派手に動いた時点で、公爵家が無傷で済むはずないってことくらい、彼も分かっていたんでしょう」
レオンは軽く手をひらひらと振ると、
少しばかり 真剣な表情 に戻る。
「で、クラウス侯爵のほうですが……もう 片付いているんじゃないですかね?」
エリオットが眉をひそめる。
「……どういう意味です?」
「王宮側の兵も動いてるはずですよ。ことがことですから」
レオンは意味ありげに笑う。
「しっかし……お粗末な計画すぎません?王家簒奪を狙うにしては 手際が悪すぎる 。ヴェロニクが公爵家を完全に掌握できるとでも思ってたんですかねぇ?」
「……なるほど」
シグルドが短く吐き捨てる。
「要するに クラウス侯爵は既に追い詰められているということか」
「ええ、そういうことです」
レオンは軽く肩をすくめる。
「なので、あとは 王宮で報告を聞けば済む話 じゃないですかね?」
そう言って、レオンは アドリアン に視線を移した。
アドリアンはまだ ヴェロニクの去った扉 を見つめている。
「……レオン」
シグルドが低く呼ぶと、レオンはにこりと笑った。
「はーい、じゃあ 公爵閣下の護送 は自分が担当しますねぇ。傷の手当てもしませんとね。まぁ、ヴェロニクほどの罪ではありませんが、彼にも それ相応の責任 を取っていただかないと」
アドリアンは何も言わずにレオンに従った。
もはや 抵抗する気はない のだろう。
「……私をどうするつもりだ」
「まぁ、とりあえず 王宮までご同行願いましょうか 。裁きは、それからですね」
レオンは軽やかに笑うと、
アドリアンの前に手を差し出した。
「さ、行きましょうか?」
アドリアンは 一瞬だけ エリオットを見た。
「……」
だが、彼は何も言わず、
ゆっくりと レオンに従うように歩き出す 。
「さて、それじゃあ僕らはこれで」
レオンが手をひらひらと振りながら、アドリアンを連れて部屋を出て行く。
足音が遠ざかると、部屋にはエリオットとシグルドだけが残った。
「……これで、ようやく終わりですね」
エリオットは静かに息をついた。
シグルドは、無言で彼を見つめる。
「君は……ヴェロニクをどうしたい?」
「僕に何か決めれることは少ないと思いますが僕は……許します」
エリオットは、そうはっきりと告げた。
シグルドの表情が僅かに動く。
「……なぜだ?」
「僕も彼と 同じ立場に陥るのは御免だから です」
エリオットは静かに続ける。
「憎しみに囚われて、誰かを恨み続けた結果、彼はあんなことになった。僕は、そうなりたくない」
「……そうか」
シグルドの瞳が、少しだけ陰る。
「私は……許せない」
珍しく、彼の声が 感情を帯びていた 。
「殺してやりたいほどに、許せない」
「……」
エリオットは、一瞬だけ 息を呑む 。
(珍しいな……)
シグルドは感情をあまり表に出さない男だ。
なのに、今は 明らかに怒りを滲ませている 。
「なぜ……そこまで?」
シグルドは、静かに瞳を伏せた。
「……君が死んだからだ」
エリオットの心臓が、強く跳ねる。
「……僕が、死んだ?」
エリオットは繰り返す。
死んではいない。死んだのは、あの時だ。
未来でもあり過去でもある、あの時。
まさか、とエリオットは息を飲む。
けれど、それはありえない……はずだ。
「……僕は生きていますよ、陛下」
「……ああ」
シグルドは、わずかに唇を引き結んだ。
シグルドの瞳が、 暗く光る 。
「……そうだな。……いや、少し、気が昂っただけだ」
シグルドは、そう誤魔化すように言い、エリオットから視線を逸らす。
「……とにかく、一度王宮に戻るぞ」
エリオットは、小さく頷いた。
公爵家の混乱は 一応の決着 を見た。
だが、 まだ終わっていないこと があるのは確かだった。
(この人は……何を隠して……?)
シグルドの背中を見ながら、エリオットは何か胸の奥に引っかかるものを感じた。
「……っ!」
エリオットの前に、別の影が割り込んだ。
ヴェロニクの動きを止めたのは、他ならぬ アドリアン だった。
「アドリアン!?」
ヴェロニクの目が大きく見開かれる。
「なぜ——!!」
ナイフはアドリアンのわき腹に突き立っていた。
刃は深く刺さってはいなかったが、それでも白いシャツを赤く染め始めている。
彼は痛みを感じさせる素振りも見せず、ただ ヴェロニクを抱きしめた 。
「……お前は、こんなことをする人間じゃなかった」
低く、静かに囁かれた言葉が、ヴェロニクの耳に届いた。
「違う……!」
ヴェロニクはかぶりを振る。
「私は……こんなはずじゃ……!」
彼の声が震え、指先から力が抜ける。
ナイフが、カラン、と床に落ちた。
「……僕がここにいなければ、あなたは公爵夫人として満足できたんですか?」
エリオットが静かに問いかけた。
ヴェロニクは歯を食いしばる。
「お前がいたからだ! お前がいたから、アドリアンは私を——」
「違う」
アドリアンの声が鋭く割り込んだ。
「エリオットがいたからではない。……ヴェロニク、違う……」
その言葉が、ヴェロニクの胸に突き刺さる。
「嘘だ……嘘だ……!」
彼は必死に否定しようとした。
だが、アドリアンは揺るがない。
「私はお前を愛していた。だが、それは エリオットを否定するものではなかった ……エリオットが公爵夫人として振る舞い、お前は私の隣にいる——それが私の、愚かな理想だった」
ヴェロニクの目に、涙が滲む。
「そんなの……私は、そんなの望んでいなかった……!」
「……そうだろうな」
アドリアンは苦笑し、ヴェロニクの肩を掴んだ。
「だが、お前はそれを エリオットのせいにした 。私のせいではなく、お前自身の歪みを、エリオットのせいにした。違うか? 私は、ずっと欲望のためにお前を利用していたのに」
「私は……私は……」
ヴェロニクの唇が震える。
その時、静かな声が響いた。
「……いい加減にしたらどうですか?」
エリオットが小さく息を吐く。
「ヴェロニク」
冷静なまなざしが、彼を貫く。
「あなたのしてきたことを悔いるなら、それに相応しい責任を取るべきだ」
「責任……?」
ヴェロニクは苦々しく口にする。
「何を……今さら……」
歯を食いしばりながら、ヴェロニクは睨みつけるようにエリオットを見た。
「お前のせいだろう! すべて、お前がいたから……!」
声が震えている。
「お前がいなければ、私は……私は、公爵夫人としてアドリアンの傍に——」
「僕があなたに何かしましたか?」
エリオットの言葉は静かだった。
「僕は、決められた通りにここに嫁いできた。それだけです」
ヴェロニクの視界が揺らぐ。
エリオットの冷静な声が、頭の奥に響いて離れない。
「そして、僕は僕に向けられた刃を防ぎました。その結果があなたに向かった。それだけのことではないですか?」
ヴェロニクの呼吸が浅くなる。
(そんなはずはない……私は……私は……)
エリオットがすべてを奪ったのだ。
自分が、公爵夫人としてアドリアンの隣に立つはずだったのに。
アドリアンの愛を独占するはずだったのに。
「何も、していない……?」
ヴェロニクは愕然としたように目を見開く。
そうだ。エリオットは……何もしていない。
ヴェロニクを愛人の座から引きずり落とそうとしたわけでもない。
ただそこにいて、運命の通りに公爵夫人として存在していただけだ。
(私が……間違っていた?)
ヴェロニクの脳裏に、これまでの出来事が鮮やかに蘇る。
エリオットが初めて公爵邸に足を踏み入れた日。
自分が「番」としてアドリアンに紹介された日。
その瞬間にエリオットの瞳に浮かんだ、わずかな戸惑い。
そしてそれに感じた優越感。
何をすれば良かったのだろうか、自分は。
自分を選んでくれとアドリアンに直訴をすれば良かったのか。
それとも、アドリアンの望みを聞けばよかったのか。
──どちらにしろ、それは受け入れられたのか?
ヴェロニクはアドリアンを見る。
何も、わからなかった。
「違う! お前がいたから、私は——!」
言い募ろうとしたヴェロニクの声を、別の声が遮った。
「違う」
それは、アドリアンだった。
ヴェロニクは、その低く静かな声に凍りついたように口を閉じる。
「エリオットがいたからではない。……そうだろう? ヴェロニク」
アドリアンの瞳が、ヴェロニクを真っすぐに捉える。
「お前を選ばなかったのは、私だ」
アドリアンの声音は冷静だった。
そこには、今までヴェロニクが知っていた甘い響きはなかった。
心臓を、誰かの手で握り潰されたような感覚だった。
「私は……どちらも大事にできると思い込んでいた。自分の理想こそが最適だと信じていた」
ヴェロニクは、かぶりを振る。
(違う……そんなの、違う!)
「でも、私はお前を選ばなかった。エリオットを大切にすることも、お前を選ぶこともできなかった」
「やめろ……」
「私は、ただの愚か者だった」
ヴェロニクの膝が、がくりと揺らぐ。
アドリアンは……ヴェロニクを愛していた。
でも、それは「選ぶ」こととは違ったのだ。
最初から——ヴェロニクは「特別」ではなかったのか?
ヴェロニクはただ、床を見つめた。
そこに、彼の望んでいた「公爵夫人」の姿はなかった。
あるのは——壊れた理想の残骸だけだった。
「公爵閣下」
エリオットはアドリアンに向き直った。
「僕は、あなたを見捨てたのではなく、あなたが最初に僕を捨てたのです。結婚式の日に。これは恨み事ではない。唯の事実として申し上げますよ」
アドリアンの目がわずかに揺れた。
「……そう、だな」
彼は静かに言った。
「私は、自分がすべてを両立できると 思い上がっていた 。お前を傷つけ、お前の心を見ようともしなかった。ヴェロニクのことも……」
エリオットは静かに息を吐く。
「ええ。でも、もうそれも終わりです」
「ヴェロニク・クレイヴン」
シグルドが前に出て、冷ややかな声で言った。
「貴様を国家反逆の罪で拘束する」
開けられたままの扉から入ってきた兵士たちがヴェロニクの両腕を捕らえる。
「……っ!」
ヴェロニクは最後の抵抗を試みるように暴れかけたが、アドリアンがそっと首を振った。
「ヴェロニク、行くんだ」
「……っ……!」
ヴェロニクは、アドリアンを見つめる。
(なぜ……? なぜ、そんな顔をするんだ……?)
アドリアンの表情には、もはや怒りも、憎しみもない。
ただ、深い 慈しみ があった。
「ヴェロニク」
アドリアンは、静かに言葉を紡ぐ。
「……私は、待っている」
ヴェロニクの目が揺れる。
アドリアンは静かに微笑んでいた。
それは 慈しみと、どこか寂しげな笑み だった。
「……待つ?」
「お前が償うべきことを償い、やるべきことを終えたら……私が迎えに行く」
アドリアンの声は柔らかく、だが 確信を持っていた 。
「私にも何らかの沙汰はあるだろうが」
「……そんな」
ヴェロニクは、言葉を失った。
ヴェロニクはアドリアンを見上げた。
目の前の男は、これまで何度も自分のために微笑んでくれたはずの男だ。
なのに今は、その表情がどこか遠い。
ヴェロニクの視界がぼやける。
頬を伝うものの正体が、涙であることに気づいたのは、それから数秒後のことだった。
「……連れて行け」
シグルドの一声で、兵士たちがヴェロニクを連れ去る。
ヴェロニクは最後に、ほんの一瞬だけ振り返った。
アドリアンが、まだそこにいるのを見て、再び前を向いた。
彼はただ、静かに歩き続けるしかなかった——。
エリオットは静かにアドリアンを見た。
「……あなたは、どうするのですか?」
「私は——私も罪を償うべきなのだろう……ヴェロニクがああいった行動をとったのは私のせいでもある」
アドリアンは小さく息を吐き、ヴェロニクの去った扉を見つめる。
「……ふぅん、なるほど」
その呟きとともに、 レオン が部屋へと足を踏み入れた。
場の緊張がようやく解けかけたその瞬間に、
彼の どこか気楽そうな声 が響く。
「ヴェロニクの捕縛、お疲れさまです。いやぁ、まさかあの人がナイフを振り回すとは。でも、これでようやく公爵邸も少しは落ち着きそうですねぇ?」
「レオン」
エリオットが静かに顔を上げた。
ヴェロニクの連行を見届けた後も、まだ部屋には張り詰めた空気が残っていた。
「状況はどうですか?」
「ええ、公爵邸の内部は ほぼ制圧 できました。ヴェロニクの側についていた連中も、大半は抵抗せずに降伏。まぁ、無茶な抵抗をしても無駄だってことは、彼らも理解してるんでしょう」
レオンは肩をすくめ、朗らかに続ける。
「それと、例の 新しい執事さん 、あの人もなかなかしぶといですねぇ?」
「ラグランのことか?」
シグルドが目を細めた。
「ああ、そうそう。彼、クラウス侯爵からの派遣でしたけど——どうも 最初からきな臭いと思ってたみたいでしてね」
レオンはくすくすと笑う。
「ああ、だから彼は僕たちをここに案内したんですね」
「 素直な裏切りですよね~」
レオンは可笑しそうに言った。
ラグランはヴェロニク側の人間だと思っていたが、彼自身、 あまりヴェロニクに肩入れする気はなかった のかもしれない。
「まぁ、結局のところ 自分の身の安全が最優先 だったってことでしょうねぇ。クラウス侯爵がここまで派手に動いた時点で、公爵家が無傷で済むはずないってことくらい、彼も分かっていたんでしょう」
レオンは軽く手をひらひらと振ると、
少しばかり 真剣な表情 に戻る。
「で、クラウス侯爵のほうですが……もう 片付いているんじゃないですかね?」
エリオットが眉をひそめる。
「……どういう意味です?」
「王宮側の兵も動いてるはずですよ。ことがことですから」
レオンは意味ありげに笑う。
「しっかし……お粗末な計画すぎません?王家簒奪を狙うにしては 手際が悪すぎる 。ヴェロニクが公爵家を完全に掌握できるとでも思ってたんですかねぇ?」
「……なるほど」
シグルドが短く吐き捨てる。
「要するに クラウス侯爵は既に追い詰められているということか」
「ええ、そういうことです」
レオンは軽く肩をすくめる。
「なので、あとは 王宮で報告を聞けば済む話 じゃないですかね?」
そう言って、レオンは アドリアン に視線を移した。
アドリアンはまだ ヴェロニクの去った扉 を見つめている。
「……レオン」
シグルドが低く呼ぶと、レオンはにこりと笑った。
「はーい、じゃあ 公爵閣下の護送 は自分が担当しますねぇ。傷の手当てもしませんとね。まぁ、ヴェロニクほどの罪ではありませんが、彼にも それ相応の責任 を取っていただかないと」
アドリアンは何も言わずにレオンに従った。
もはや 抵抗する気はない のだろう。
「……私をどうするつもりだ」
「まぁ、とりあえず 王宮までご同行願いましょうか 。裁きは、それからですね」
レオンは軽やかに笑うと、
アドリアンの前に手を差し出した。
「さ、行きましょうか?」
アドリアンは 一瞬だけ エリオットを見た。
「……」
だが、彼は何も言わず、
ゆっくりと レオンに従うように歩き出す 。
「さて、それじゃあ僕らはこれで」
レオンが手をひらひらと振りながら、アドリアンを連れて部屋を出て行く。
足音が遠ざかると、部屋にはエリオットとシグルドだけが残った。
「……これで、ようやく終わりですね」
エリオットは静かに息をついた。
シグルドは、無言で彼を見つめる。
「君は……ヴェロニクをどうしたい?」
「僕に何か決めれることは少ないと思いますが僕は……許します」
エリオットは、そうはっきりと告げた。
シグルドの表情が僅かに動く。
「……なぜだ?」
「僕も彼と 同じ立場に陥るのは御免だから です」
エリオットは静かに続ける。
「憎しみに囚われて、誰かを恨み続けた結果、彼はあんなことになった。僕は、そうなりたくない」
「……そうか」
シグルドの瞳が、少しだけ陰る。
「私は……許せない」
珍しく、彼の声が 感情を帯びていた 。
「殺してやりたいほどに、許せない」
「……」
エリオットは、一瞬だけ 息を呑む 。
(珍しいな……)
シグルドは感情をあまり表に出さない男だ。
なのに、今は 明らかに怒りを滲ませている 。
「なぜ……そこまで?」
シグルドは、静かに瞳を伏せた。
「……君が死んだからだ」
エリオットの心臓が、強く跳ねる。
「……僕が、死んだ?」
エリオットは繰り返す。
死んではいない。死んだのは、あの時だ。
未来でもあり過去でもある、あの時。
まさか、とエリオットは息を飲む。
けれど、それはありえない……はずだ。
「……僕は生きていますよ、陛下」
「……ああ」
シグルドは、わずかに唇を引き結んだ。
シグルドの瞳が、 暗く光る 。
「……そうだな。……いや、少し、気が昂っただけだ」
シグルドは、そう誤魔化すように言い、エリオットから視線を逸らす。
「……とにかく、一度王宮に戻るぞ」
エリオットは、小さく頷いた。
公爵家の混乱は 一応の決着 を見た。
だが、 まだ終わっていないこと があるのは確かだった。
(この人は……何を隠して……?)
シグルドの背中を見ながら、エリオットは何か胸の奥に引っかかるものを感じた。
1,387
あなたにおすすめの小説

【完結】愛されたかった僕の人生
Kanade
BL
✯オメガバース
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
お見合いから一年半の交際を経て、結婚(番婚)をして3年。
今日も《夫》は帰らない。
《夫》には僕以外の『番』がいる。
ねぇ、どうしてなの?
一目惚れだって言ったじゃない。
愛してるって言ってくれたじゃないか。
ねぇ、僕はもう要らないの…?
独りで過ごす『発情期』は辛いよ…。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
✻改稿版を他サイトにて投稿公開中です。

そばかす糸目はのんびりしたい
楢山幕府
BL
由緒ある名家の末っ子として生まれたユージン。
母親が後妻で、眉目秀麗な直系の遺伝を受け継がなかったことから、一族からは空気として扱われていた。
ただ一人、溺愛してくる老いた父親を除いて。
ユージンは、のんびりするのが好きだった。
いつでも、のんびりしたいと思っている。
でも何故か忙しい。
ひとたび出張へ出れば、冒険者に囲まれる始末。
いつになったら、のんびりできるのか。もう開き直って、のんびりしていいのか。
果たして、そばかす糸目はのんびりできるのか。
懐かれ体質が好きな方向けです。


「オレの番は、いちばん近くて、いちばん遠いアルファだった」
星井 悠里
BL
大好きだった幼なじみのアルファは、皆の憧れだった。
ベータのオレは、王都に誘ってくれたその手を取れなかった。
番にはなれない未来が、ただ怖かった。隣に立ち続ける自信がなかった。
あれから二年。幼馴染の婚約の噂を聞いて胸が痛むことはあるけれど、
平凡だけどちゃんと働いて、それなりに楽しく生きていた。
そんなオレの体に、ふとした異変が起きはじめた。
――何でいまさら。オメガだった、なんて。
オメガだったら、これからますます頑張ろうとしていた仕事も出来なくなる。
2年前のあの時だったら。あの手を取れたかもしれないのに。
どうして、いまさら。
すれ違った運命に、急展開で振り回される、Ωのお話。
ハピエン確定です。(全10話)
2025年 07月12日 ~2025年 07月21日 なろうさんで完結してます。

男装の麗人と呼ばれる俺は正真正銘の男なのだが~双子の姉のせいでややこしい事態になっている~
さいはて旅行社
BL
双子の姉が失踪した。
そのせいで、弟である俺が騎士学校を休学して、姉の通っている貴族学校に姉として通うことになってしまった。
姉は男子の制服を着ていたため、服装に違和感はない。
だが、姉は男装の麗人として女子生徒に恐ろしいほど大人気だった。
その女子生徒たちは今、何も知らずに俺を囲んでいる。
女性に囲まれて嬉しい、わけもなく、彼女たちの理想の王子様像を演技しなければならない上に、男性が女子寮の部屋に一歩入っただけでも騒ぎになる貴族学校。
もしこの事実がバレたら退学ぐらいで済むわけがない。。。
周辺国家の情勢がキナ臭くなっていくなかで、俺は双子の姉が戻って来るまで、協力してくれる仲間たちに笑われながらでも、無事にバレずに女子生徒たちの理想の王子様像を演じ切れるのか?
侯爵家の命令でそんなことまでやらないといけない自分を救ってくれるヒロインでもヒーローでも現れるのか?

結婚初夜に相手が舌打ちして寝室出て行こうとした
紫
BL
十数年間続いた王国と帝国の戦争の終結と和平の形として、元敵国の皇帝と結婚することになったカイル。
実家にはもう帰ってくるなと言われるし、結婚相手は心底嫌そうに舌打ちしてくるし、マジ最悪ってところから始まる話。
オメガバースでオメガの立場が低い世界
こんなあらすじとタイトルですが、主人公が可哀そうって感じは全然ないです
強くたくましくメンタルがオリハルコンな主人公です
主人公は耐える我慢する許す許容するということがあんまり出来ない人間です
倫理観もちょっと薄いです
というか、他人の事を自分と同じ人間だと思ってない部分があります
※この主人公は受けです
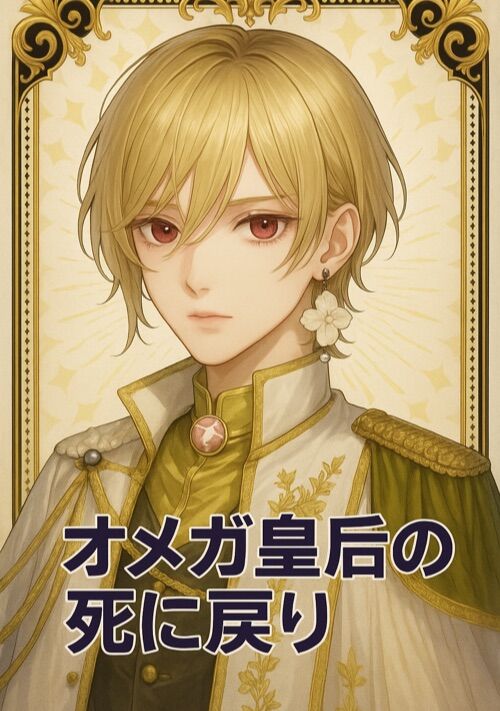
【完結・ルート分岐あり】オメガ皇后の死に戻り〜二度と思い通りにはなりません〜
ivy
BL
魔術師の家門に生まれながら能力の発現が遅く家族から虐げられて暮らしていたオメガのアリス。
そんな彼を国王陛下であるルドルフが妻にと望み生活は一変する。
幸せになれると思っていたのに生まれた子供共々ルドルフに殺されたアリスは目が覚めると子供の頃に戻っていた。
もう二度と同じ轍は踏まない。
そう決心したアリスの戦いが始まる。

【完結】家も家族もなくし婚約者にも捨てられた僕だけど、隣国の宰相を助けたら囲われて大切にされています。
cyan
BL
留学中に実家が潰れて家族を失くし、婚約者にも捨てられ、どこにも行く宛てがなく彷徨っていた僕を助けてくれたのは隣国の宰相だった。
家が潰れた僕は平民。彼は宰相様、それなのに僕は恐れ多くも彼に恋をした。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















