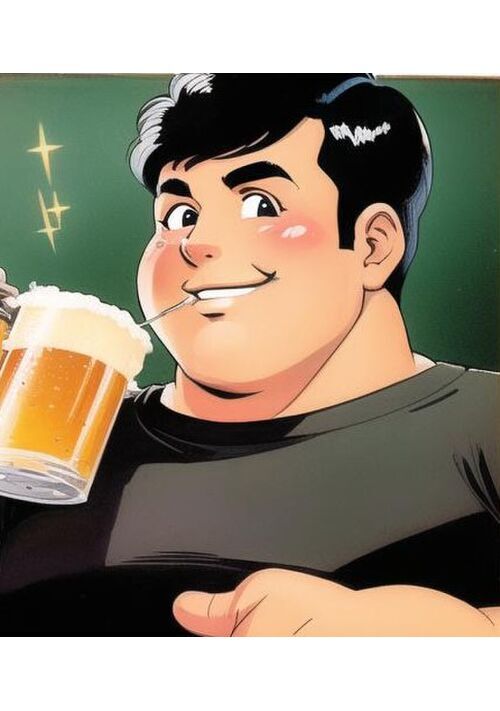36 / 57
3巻
3-3
しおりを挟む
「あれが、五徳猫さん……」
「有栖さん、見えますか」
「はい。尻尾が二本生えている、可愛い猫さんです」
「猫ではニャい。わたしは立派な五徳猫だニャ」
素早く訂正を入れた五徳猫は、くあ、とあくびとともに身体を伸ばす。
仕草はやはり、愛くるしい猫だ。が、これは口にしないほうがいいだろう。
「わたしに一体何の用かニャ。そちらは確か、最近山神さまが懇意にされていると噂の女子だニャ。しかしあいにくわたしには、山神さまに褒めそやされるような覚えも、お叱りを受けるような覚えもニャいぞ」
「……山神」
「孝太朗さんの字のようなものです、有栖さん」
以前孝太朗が使った解説をさくっと有栖に入れ、日鞠は話を進める。
「今回の訪問は、孝太朗さんの指示ではありません。私たちが、あなたにぜひご相談をと思って赴きました」
「相談?」
五徳猫の目が、まん丸に開かれた。
「文車妖妃さんから、五徳猫さんは火の取り扱いに長けていて、料理上手な方なのだと聞きました。辺りのあやかしの皆さんに料理をよく振る舞われ、とても喜ばれているということも」
「ふむ。まあ、自慢じゃニャいが、そのとおりだニャ」
五徳猫がもふもふの胸をくいっと張る。可愛い。
「実は私たち、今料理指南をしてくださる方を探しているんです。五徳猫さん。ぜひ、私たちの料理指南役を引き受けていただけませんか」
「あなたの力をお借りしたいんです。どうかお願いします、五徳猫さん」
日鞠と有栖が、揃って深く頭を下げた。
しんしんと降り積もる雪が辺りを包み、周囲の音は遠ざかっていく。
どきどきと五徳猫の返答を待っていると、「ニャー」と愛くるしい猫の鳴き声が聞こえた。
「お主ら二人の用件は理解した。ただ悪いが、その願いを聞き届けることはできないニャ」
「そう、ですか。あの、もしよろしければ理由を伺っても?」
「……理由なんてないニャ! ただ、気が向かない。それだけニャ!」
言い切ると、五徳猫はふん、と顔を背けた。
実のところ、日鞠は文車妖妃からこんな話も聞いていた。
この街の五徳猫は確かに料理の腕はあるが、性格は猫らしく風の吹くまま気の赴くまま。素直に協力を願い出ても、首を縦に振る確率は五分五分だと。
「五徳猫さん」
しょんぼり眉を下げていた日鞠の耳に、凜とした声が届いた。
「お願いします。勝手な話ではありますが私、どうしても自分で作った料理を届けたい方がいるんです。今まで何度も料理に挑戦しては無理だと諦めていたのですが、それでも諦めたくないと思える、大切な人なんです」
「有栖さん……」
「突然押しかけた挙句、失礼なのは重々承知しております。それでも、何とか五徳猫さんのお力をお借りしたいんです。どうか、よろしくお願いいたします」
「ウニャッ!?」
「あ、あ、有栖さん!?」
次の瞬間、有栖はごく自然な所作で雪道の上に膝をつき、深く頭を下げた。
その美しい土下座に一瞬虚を突かれた日鞠だったが、我に返ると慌てて声をかける。
「有栖さんっ、こんな雪道に座り込むのは……!」
「大丈夫ですよ。それに、今回五徳猫さんに頭を下げるべきは、私のほうですから」
迷いのない毅然とした表情に、はっと息を呑んだのは日鞠だけではなかった。
「もちろん、必要なお礼はさせていただきます。あやかし界の知識が足りずに恐縮ですが、五徳猫さんが希望されるものを誠心誠意ご用意します。なのでどうか、詳しいお話だけでも」
「わ、わ、わかった! お主の想いは痛いほど理解した! だから、ひとまず立つのニャ! 早くするのニャ! さもないとっ」
「五徳猫さん?」
「……身体を冷やしてしまうニャろう!?」
叫んだ五徳猫は、石垣の穴の中から堪らずといった様子で飛び出してきた。
次の瞬間、雪に触れた愛らしい猫足の毛が一気に逆立つ。
「うぐ! しゃ、しゃ、しゃ……」
「しゃ?」
「……しゃむいニャ……」
そう言い残した直後、五徳猫は青い顔をして倒れ込んでしまった。
目を剥いた日鞠たちは、慌てて五徳猫のもとへ駆け寄る。
抱き上げたその身体は、まるで氷のように冷たかった。
五徳猫は、名前を『ゴト』といった。
あやかしを目にできた数少ない人間からは『ミケ』『タマ』『ゴロ』など好き勝手に呼ばれていたが、自分は五徳猫だという強い意志からその名を名乗ることを選んだ。
「ゴトさん、あの石垣の穴から動きたくても動けずにいたんですね」
「まったく情けない話だニャ。寒さで体調を崩して倒れるニャんて」
昏倒してしまったゴトは、急遽有栖の自宅へ匿われることとなった。
今は一人用のソファー席に丸くなり、言葉を交わせる程度まで回復している。
とはいえ、まだまだ身体は冷え切っているらしい。有栖が持ってきたふわふわの膝掛けに、ゴトは素直に頬を寄せた。
「わたしも若い頃は、雪道だろうと氷の上だろうと構わず食材の下見に出回っていたんだがニャ。気づけば寒さが苦手になっていて、今では雪に触れるだけで身体が冷え切り、うまく動けなくなってしまうのニャ」
「確かに今の時期、冷え症状で悩む方は少なくありませんよね。最近の薬膳カフェでも、身体を温めてくれる薬膳茶がよくオーダーされています」
現に日鞠自身も身体が冷えがちで、家の中ではもこもこのカーディガンを羽織っている。
対して孝太朗はといえば、夏冬ともに濃紺のスウェット姿で、目にするたびに「寒くありませんか?」と尋ねたくなるほどだ。
「まだ小さく震えていますね。ゴトさん、もしよければ私の膝に乗りませんか。そのほうがじっくり温まることができるかもしれません」
「け、結構だニャ! 知り合って間もない人間の膝に乗るニャんて、わたしのポリシーに反するニャ! 断固拒否だニャ!」
「そうでしたか……では、ひとまず暖炉の火を強くしますね」
「ウニャ」
ゴトと有栖のどこか微笑ましいやりとりを目にしながら、日鞠は一人キッチンに立っていた。
道途中のスーパーで買い足した食材の下ごしらえを済ませ、手早く料理を進めていく。
「よーし、できました! 身体の芯からぽかぽかになる、孝太朗さん直伝の薬膳雑炊です!」
「美味しそうな香りですね。それに、彩りもとても綺麗です」
「ウニャアアア……」
テーブルに並べられた皿の中身を見て、有栖とゴトはぱあっと瞳を輝かせた。
耐熱用のお皿によそった雑炊には、生姜やニンニク、にんじんやタマネギなどの野菜をたっぷり入れている。
白米に少量のもち米を加え、昆布出汁でとろとろになるまで煮詰めた雑炊の香りは、それだけでも食欲を刺激した。
「ゴトさん、熱すぎたら言ってくださいね。冷たい昆布出汁を少し取り分けてありますから」
「わたしは五徳猫だニャ。普通の猫と違って、熱いものも問題なく食すことができる!」
ふん、と鼻を鳴らしながらも、食欲はあるらしいゴトの様子に、日鞠はほっと安堵する。
用意した雑炊をそっとひと舐めすると、ゴトははっと目を見開いた。
「お味はいかがでしょうか」
「……美味しい」
ぽつりとこぼれた言葉だった。
「とってもとっても美味しいニャ。いまだ凍りついていた身体の先が、じわじわと温まっていくような心地がする。色とりどりの野菜も食欲をそそるニャ……」
「よかった。料理上手なゴトさんにそう言ってもらえて嬉しいです」
「ま、まあ。さすがは山神さま直伝というだけはあるかニャ!」
慌ててツンのコメントを加えたゴトの様子に、日鞠と有栖はそっと微笑み合った。
「日鞠さんが作ってくださった雑炊、本当に身体の内から温まりますね。これでゴトさんの冷え症状も解消されるでしょうか」
「いや。わたしの場合、残念ながら一食雑炊を食べただけでは一時的に冷えがマシになるだけだニャ。今までの経験上、きっとすぐに寒さが舞い戻ってしまうニャね」
「すみませんでした。私がしつこく食い下がったばかりに、ゴトさんをあの石垣の穴から出してしまうことになってしまって」
レンゲを置き、有栖はゴトに向かって深く頭を下げた。
「別に謝られるようなことではないニャ。冷え体質はそもそもお主のせいではないし、あの中から出ようとしたのもただの気まぐれニャ」
「でもゴトさんはあのとき、私の身体が冷えてしまうことを心配してくださったんですよね?」
有栖の指摘に、ゴトは言葉を詰まらせる。
雪道で膝をついた有栖に、ゴトは即座に立ち上がるよう促し、慌てて駆け寄ろうとまでした。
恐らくは自分自身が辛い冷えに苦しめられているからこそ、有栖の身を案じたのだろう。
とても優しいあやかしだ。
「思えば、頼みごとをしている身ながら、私はゴトさんに何もしてあげられていませんね。ゴトさんをこの家にお連れしたところで、私は日鞠さんのようなお食事を作ることができません。作ったとしても、農家さんが手間暇かけて育てられた野菜たちを爆発させて、消し炭のような料理しかお出しできず、ゴトさんは謎の腹痛に見舞われるのが目に見えています」
「爆発……」
「謎の腹痛……」
有栖から語られる確信めいた予言に、ゴトと日鞠はぽつりと呟く。
「せめて、お店で何かお惣菜を買ってきます。あとは、カイロや湯たんぽも。他にも、何か少しでも、ゴトさんの冷え症状を軽減させるようなものを」
自身を責めるような有栖の言葉に、ゴトはしばらく無言のまま雑炊の皿を見つめていた。
「……いや。それは不要だニャ。ちょいと、そこのお主」
「は、はいっ」
ゴトが声をかけたのは、有栖ではなく日鞠のほうだった。
「山神さま直伝の薬膳雑炊の作り方。山神さまさえ許可をくだされば、ぜひわたしに教えてほしいニャ。教えてくれるというニャら、指南役を引き受けてやってもいい」
「……! はい! すぐに、確認してみますね!」
「ゴトさん?」
「ふん。乗りかかった船ニャね。幸いこの家の中は暖房がきいていて身体も動かしやすいし、何もせずに惰眠を貪るのも普通の猫のようで気分が悪い」
ぷいっとそっぽを向きながら、ゴトはどこか早口でまくし立てた。
「わたしがここで匿われているうちは、料理下手と聞くお主の力になってあげてもいいニャ。言っておくが、わたしの指導は甘くないニャよ」
「はい! ありがとうございます……!」
笑顔で頷いた有栖は、ゴトの身体をぎゅうっと腕の中に閉じ込める。
美しい淑女からの熱い抱擁を受けたゴトは、顔を真っ赤にして全身の毛を逆立てた。
それから数日が経った。
「なーんかおかしい」
「類さん?」
午前シフトを終えた昼休憩の時間帯。四人席でいつもどおり昼食を取っていると、類が突然呟いた。
「俺の作るまかないに文句があるなら、勝手に外で調達してこい」
「違う違う。孝太朗の作るまかないはいつもとても美味しくいただいていますって。そうじゃなくて、他にちょっと気になってることがあるんだよねえ」
「気になってること?」
「有栖ちゃんのこと」
類の口から出た人物の名に、日鞠はびくりと肩を揺らした。
そんな日鞠に気づいているのかいないのか、対面席に座る類はプレートに並ぶパンケーキをナイフで綺麗に切り分けていく。
「最近、有栖ちゃんになかなか会う時間が取れないんだ。休日の予定を聞いても断られちゃうし、仕事上がりはすぐに家に帰っちゃうし」
「ついこの間カフェに来てただろ」
「あれからもう五日は経ってるの! こんなに長い間会えないのは初めてでしてね! 恋人と同居してる人は黙っててくれますー!?」
「そうか。なら俺たちは時間まで二階にこもる」
「うそうそごめん! 二人にまで見捨てられたら、類さん寂しくて死んじゃう……!」
しくしくと泣き真似をする類に、孝太朗は心底面倒くさそうにため息をついた。それでも浮かした腰を戻すあたり、孝太朗は優しい。
「だ、大丈夫ですよ類さん。きっと有栖さん、お仕事が色々と立て込んでいるだけですから」
「そうかなあ。でも今日も、昼休みの時間だけでも会えない? って聞いたんだけど、やることがあるからって取り付く島もなかったし」
「それだけ大切な用事があるってことじゃねえのか」
「……バレンタインの準備をしてくれてるのかなって、思ってたんだけど」
鋭すぎるその推測に、日鞠は再びびくりと肩を揺らした。
「それもきっと間違っていないと思うんだけど。何となーく、それだけじゃないような気がするんだよね。これは完全に俺の勘なんだけど、俺以外の誰かと頻繁に会ってるみたいな、いやーな予感が」
「大丈夫です!!」
ばん、とテーブルに手を叩きつけながら、日鞠は声を張った。
突然の大声に、類はもちろん、隣席の孝太朗も目を見開いている。
「有栖さんは、類さんのことが大好きなんですから! もしかすると類さんの言うとおり、ほんの少しは内緒にしていることもあるかもしれません! でも! 類さんに喜んでもらおうと、今の有栖さんは一生懸命なんです! そのことは、誰よりも私が保証しますっ!」
「日鞠ちゃん」
「だからその、類さんは心配しないで、有栖さんのことを信じてあげてくれませんか……!」
真面目でしっかり者の有栖のことだ。
きっと隙間時間を見つけてはチョコレート作りについて学び、一目散に帰宅してはゴトの熱血指導を受けているのだろう。
そんな有栖の変化に気づかない類ではない。
それでも、その一途な想いを疑ってほしくはなかった。
「ありがとう。日鞠ちゃん」
穏やかな口調で告げられた感謝の言葉に、日鞠ははっと我に返った。
「実は結構本気で凹んでたんだけどね。日鞠ちゃんに断言されたら、妙に安心しちゃったよ」
「よかったです。類さんも、本当に有栖さんのことが大好きなんですね」
「……そう真正面から聞かれちゃうと、何だかめちゃくちゃ恥ずかしいかも……?」
「お前、恥じらいなんて感情があったのか」
「俺もつい最近知りました……」
ため息交じりに机に突っ伏した類だったが、その頬は僅かに赤く染まっていた。
いつもは三百六十度どこから見ても完璧な笑顔をたたえるイケメンさんが、今は一人の女性への想いに右往左往している。
そんな友人の新たな一面を目にして、日鞠は胸がじわりと温かくなるのを感じた。
その後の午後シフト中、類は時折大窓の向こうを眺めては想い人の来訪を待ちわびていた。
日鞠も、恐らくは孝太朗もそのことに気づいていたが、どちらもそれを口にすることはなく営業時間を終えた。
翌日の夕方。仕事上がりに有栖と落ち合った日鞠は、再び彼女の家にお邪魔していた。
「よかった。ゴトさんの冷えの症状も、随分とよくなっているみたいですね」
「うむ。山神さま直伝の薬膳雑炊のおかげニャ。やはり身体を温めるのは内と外の両方からが一番だニャ。今では短い間なら、外に出ても平気になってきたニャ!」
「わあ、それはよかったです」
「日鞠さん、紅茶をどうぞ。ゴトさんには、ハチミツ入りのホットミルクです」
「ありがとうございます、有栖さん」
「うニャ。いただくニャ」
そう言ってミルクのほうへ移動するゴトは、以前よりも動きが軽やかで毛並みもつやつやと健康そうだ。
「ゴトさんのお料理指南のお話も聞きました。ゴトさんは人に料理を教えるのがとってもお上手なんですね」
「最初は有栖の不得手さに愕然としたがニャ。ひとつひとつの動きを、有栖が理解できるように説明していっただけニャ。野菜を刻むときの力加減やら、卵の殻を割るときの心持ちなんかをニャ」
「なるほど。卵の殻を割るときの心持ちですか」
確かに、日鞠は工程のみの説明に留まり、「どのように」「どのくらいの強さで」といった説明が抜けていたように思う。
料理初心者にもしっかりと寄り添うことのできるゴトの温かな心持ちに、日鞠は自然と笑みを浮かべた。
「今では私も、日鞠さんに教えていただいた薬膳雑炊を、なんとか作れるようになったんですよ」
「わあ! すごいです、すごいです、有栖さん!」
まるで自分のことのようにはしゃいでしまう。
何せ以前二人でこのキッチンに立ったときは、製菓用チョコレートが瞬く間に消し飛んでしまったほどなのだ。
それだけにこの数日、有栖がどれだけ努力をしてきたのかが理解できる。
愛の力は、やっぱり偉大だ。
「有栖さんの薬膳雑炊のおかげもあって、ゴトさんの冷え症状も目を見張るほど改善されたんですね」
「まあ、それもあるがニャ。きっとそれだけではないニャ」
小さく首を傾げる有栖にそっと視線を向けたあと、ゴトは答えた。
「恥ずかしい話だがニャ。ここ最近、わたしは人との関わり合いがめっきりなくなっていたのニャ。そもそもあやかしを視認できる者がほとんどおらず、目の前に出てみてもみんなわたしを素通りニャ。昔は人間の住まいに入り込んでは、火付け役として重宝されたというのにニャ」
「ゴトさん」
「これも時代の流れニャね。わかってはいるのだが、心の奥底では受け入れがたかったようだニャ。人と関わろうとしては失敗するのを繰り返し、不貞腐れたわたしは何年も何年もあの石垣の穴から動かない時間を過ごした。その結果が、この冷え症状というわけニャね」
「ゴトさんは、人との交流が大好きだったんですね」
日鞠の言葉に、ゴトは無言で頷く。
五徳猫は囲炉裏の火付け役。そんなふうに人から感謝されてきたゴトが抱えてきた寂しさは、自分たちの想像をはるかに超えるものに違いない。
有栖がそっと、ゴトの前足に触れた。ゴトの三角耳がぴくんと揺れたが、拒絶の言葉が出ることはなかった。
「有栖さん、見えますか」
「はい。尻尾が二本生えている、可愛い猫さんです」
「猫ではニャい。わたしは立派な五徳猫だニャ」
素早く訂正を入れた五徳猫は、くあ、とあくびとともに身体を伸ばす。
仕草はやはり、愛くるしい猫だ。が、これは口にしないほうがいいだろう。
「わたしに一体何の用かニャ。そちらは確か、最近山神さまが懇意にされていると噂の女子だニャ。しかしあいにくわたしには、山神さまに褒めそやされるような覚えも、お叱りを受けるような覚えもニャいぞ」
「……山神」
「孝太朗さんの字のようなものです、有栖さん」
以前孝太朗が使った解説をさくっと有栖に入れ、日鞠は話を進める。
「今回の訪問は、孝太朗さんの指示ではありません。私たちが、あなたにぜひご相談をと思って赴きました」
「相談?」
五徳猫の目が、まん丸に開かれた。
「文車妖妃さんから、五徳猫さんは火の取り扱いに長けていて、料理上手な方なのだと聞きました。辺りのあやかしの皆さんに料理をよく振る舞われ、とても喜ばれているということも」
「ふむ。まあ、自慢じゃニャいが、そのとおりだニャ」
五徳猫がもふもふの胸をくいっと張る。可愛い。
「実は私たち、今料理指南をしてくださる方を探しているんです。五徳猫さん。ぜひ、私たちの料理指南役を引き受けていただけませんか」
「あなたの力をお借りしたいんです。どうかお願いします、五徳猫さん」
日鞠と有栖が、揃って深く頭を下げた。
しんしんと降り積もる雪が辺りを包み、周囲の音は遠ざかっていく。
どきどきと五徳猫の返答を待っていると、「ニャー」と愛くるしい猫の鳴き声が聞こえた。
「お主ら二人の用件は理解した。ただ悪いが、その願いを聞き届けることはできないニャ」
「そう、ですか。あの、もしよろしければ理由を伺っても?」
「……理由なんてないニャ! ただ、気が向かない。それだけニャ!」
言い切ると、五徳猫はふん、と顔を背けた。
実のところ、日鞠は文車妖妃からこんな話も聞いていた。
この街の五徳猫は確かに料理の腕はあるが、性格は猫らしく風の吹くまま気の赴くまま。素直に協力を願い出ても、首を縦に振る確率は五分五分だと。
「五徳猫さん」
しょんぼり眉を下げていた日鞠の耳に、凜とした声が届いた。
「お願いします。勝手な話ではありますが私、どうしても自分で作った料理を届けたい方がいるんです。今まで何度も料理に挑戦しては無理だと諦めていたのですが、それでも諦めたくないと思える、大切な人なんです」
「有栖さん……」
「突然押しかけた挙句、失礼なのは重々承知しております。それでも、何とか五徳猫さんのお力をお借りしたいんです。どうか、よろしくお願いいたします」
「ウニャッ!?」
「あ、あ、有栖さん!?」
次の瞬間、有栖はごく自然な所作で雪道の上に膝をつき、深く頭を下げた。
その美しい土下座に一瞬虚を突かれた日鞠だったが、我に返ると慌てて声をかける。
「有栖さんっ、こんな雪道に座り込むのは……!」
「大丈夫ですよ。それに、今回五徳猫さんに頭を下げるべきは、私のほうですから」
迷いのない毅然とした表情に、はっと息を呑んだのは日鞠だけではなかった。
「もちろん、必要なお礼はさせていただきます。あやかし界の知識が足りずに恐縮ですが、五徳猫さんが希望されるものを誠心誠意ご用意します。なのでどうか、詳しいお話だけでも」
「わ、わ、わかった! お主の想いは痛いほど理解した! だから、ひとまず立つのニャ! 早くするのニャ! さもないとっ」
「五徳猫さん?」
「……身体を冷やしてしまうニャろう!?」
叫んだ五徳猫は、石垣の穴の中から堪らずといった様子で飛び出してきた。
次の瞬間、雪に触れた愛らしい猫足の毛が一気に逆立つ。
「うぐ! しゃ、しゃ、しゃ……」
「しゃ?」
「……しゃむいニャ……」
そう言い残した直後、五徳猫は青い顔をして倒れ込んでしまった。
目を剥いた日鞠たちは、慌てて五徳猫のもとへ駆け寄る。
抱き上げたその身体は、まるで氷のように冷たかった。
五徳猫は、名前を『ゴト』といった。
あやかしを目にできた数少ない人間からは『ミケ』『タマ』『ゴロ』など好き勝手に呼ばれていたが、自分は五徳猫だという強い意志からその名を名乗ることを選んだ。
「ゴトさん、あの石垣の穴から動きたくても動けずにいたんですね」
「まったく情けない話だニャ。寒さで体調を崩して倒れるニャんて」
昏倒してしまったゴトは、急遽有栖の自宅へ匿われることとなった。
今は一人用のソファー席に丸くなり、言葉を交わせる程度まで回復している。
とはいえ、まだまだ身体は冷え切っているらしい。有栖が持ってきたふわふわの膝掛けに、ゴトは素直に頬を寄せた。
「わたしも若い頃は、雪道だろうと氷の上だろうと構わず食材の下見に出回っていたんだがニャ。気づけば寒さが苦手になっていて、今では雪に触れるだけで身体が冷え切り、うまく動けなくなってしまうのニャ」
「確かに今の時期、冷え症状で悩む方は少なくありませんよね。最近の薬膳カフェでも、身体を温めてくれる薬膳茶がよくオーダーされています」
現に日鞠自身も身体が冷えがちで、家の中ではもこもこのカーディガンを羽織っている。
対して孝太朗はといえば、夏冬ともに濃紺のスウェット姿で、目にするたびに「寒くありませんか?」と尋ねたくなるほどだ。
「まだ小さく震えていますね。ゴトさん、もしよければ私の膝に乗りませんか。そのほうがじっくり温まることができるかもしれません」
「け、結構だニャ! 知り合って間もない人間の膝に乗るニャんて、わたしのポリシーに反するニャ! 断固拒否だニャ!」
「そうでしたか……では、ひとまず暖炉の火を強くしますね」
「ウニャ」
ゴトと有栖のどこか微笑ましいやりとりを目にしながら、日鞠は一人キッチンに立っていた。
道途中のスーパーで買い足した食材の下ごしらえを済ませ、手早く料理を進めていく。
「よーし、できました! 身体の芯からぽかぽかになる、孝太朗さん直伝の薬膳雑炊です!」
「美味しそうな香りですね。それに、彩りもとても綺麗です」
「ウニャアアア……」
テーブルに並べられた皿の中身を見て、有栖とゴトはぱあっと瞳を輝かせた。
耐熱用のお皿によそった雑炊には、生姜やニンニク、にんじんやタマネギなどの野菜をたっぷり入れている。
白米に少量のもち米を加え、昆布出汁でとろとろになるまで煮詰めた雑炊の香りは、それだけでも食欲を刺激した。
「ゴトさん、熱すぎたら言ってくださいね。冷たい昆布出汁を少し取り分けてありますから」
「わたしは五徳猫だニャ。普通の猫と違って、熱いものも問題なく食すことができる!」
ふん、と鼻を鳴らしながらも、食欲はあるらしいゴトの様子に、日鞠はほっと安堵する。
用意した雑炊をそっとひと舐めすると、ゴトははっと目を見開いた。
「お味はいかがでしょうか」
「……美味しい」
ぽつりとこぼれた言葉だった。
「とってもとっても美味しいニャ。いまだ凍りついていた身体の先が、じわじわと温まっていくような心地がする。色とりどりの野菜も食欲をそそるニャ……」
「よかった。料理上手なゴトさんにそう言ってもらえて嬉しいです」
「ま、まあ。さすがは山神さま直伝というだけはあるかニャ!」
慌ててツンのコメントを加えたゴトの様子に、日鞠と有栖はそっと微笑み合った。
「日鞠さんが作ってくださった雑炊、本当に身体の内から温まりますね。これでゴトさんの冷え症状も解消されるでしょうか」
「いや。わたしの場合、残念ながら一食雑炊を食べただけでは一時的に冷えがマシになるだけだニャ。今までの経験上、きっとすぐに寒さが舞い戻ってしまうニャね」
「すみませんでした。私がしつこく食い下がったばかりに、ゴトさんをあの石垣の穴から出してしまうことになってしまって」
レンゲを置き、有栖はゴトに向かって深く頭を下げた。
「別に謝られるようなことではないニャ。冷え体質はそもそもお主のせいではないし、あの中から出ようとしたのもただの気まぐれニャ」
「でもゴトさんはあのとき、私の身体が冷えてしまうことを心配してくださったんですよね?」
有栖の指摘に、ゴトは言葉を詰まらせる。
雪道で膝をついた有栖に、ゴトは即座に立ち上がるよう促し、慌てて駆け寄ろうとまでした。
恐らくは自分自身が辛い冷えに苦しめられているからこそ、有栖の身を案じたのだろう。
とても優しいあやかしだ。
「思えば、頼みごとをしている身ながら、私はゴトさんに何もしてあげられていませんね。ゴトさんをこの家にお連れしたところで、私は日鞠さんのようなお食事を作ることができません。作ったとしても、農家さんが手間暇かけて育てられた野菜たちを爆発させて、消し炭のような料理しかお出しできず、ゴトさんは謎の腹痛に見舞われるのが目に見えています」
「爆発……」
「謎の腹痛……」
有栖から語られる確信めいた予言に、ゴトと日鞠はぽつりと呟く。
「せめて、お店で何かお惣菜を買ってきます。あとは、カイロや湯たんぽも。他にも、何か少しでも、ゴトさんの冷え症状を軽減させるようなものを」
自身を責めるような有栖の言葉に、ゴトはしばらく無言のまま雑炊の皿を見つめていた。
「……いや。それは不要だニャ。ちょいと、そこのお主」
「は、はいっ」
ゴトが声をかけたのは、有栖ではなく日鞠のほうだった。
「山神さま直伝の薬膳雑炊の作り方。山神さまさえ許可をくだされば、ぜひわたしに教えてほしいニャ。教えてくれるというニャら、指南役を引き受けてやってもいい」
「……! はい! すぐに、確認してみますね!」
「ゴトさん?」
「ふん。乗りかかった船ニャね。幸いこの家の中は暖房がきいていて身体も動かしやすいし、何もせずに惰眠を貪るのも普通の猫のようで気分が悪い」
ぷいっとそっぽを向きながら、ゴトはどこか早口でまくし立てた。
「わたしがここで匿われているうちは、料理下手と聞くお主の力になってあげてもいいニャ。言っておくが、わたしの指導は甘くないニャよ」
「はい! ありがとうございます……!」
笑顔で頷いた有栖は、ゴトの身体をぎゅうっと腕の中に閉じ込める。
美しい淑女からの熱い抱擁を受けたゴトは、顔を真っ赤にして全身の毛を逆立てた。
それから数日が経った。
「なーんかおかしい」
「類さん?」
午前シフトを終えた昼休憩の時間帯。四人席でいつもどおり昼食を取っていると、類が突然呟いた。
「俺の作るまかないに文句があるなら、勝手に外で調達してこい」
「違う違う。孝太朗の作るまかないはいつもとても美味しくいただいていますって。そうじゃなくて、他にちょっと気になってることがあるんだよねえ」
「気になってること?」
「有栖ちゃんのこと」
類の口から出た人物の名に、日鞠はびくりと肩を揺らした。
そんな日鞠に気づいているのかいないのか、対面席に座る類はプレートに並ぶパンケーキをナイフで綺麗に切り分けていく。
「最近、有栖ちゃんになかなか会う時間が取れないんだ。休日の予定を聞いても断られちゃうし、仕事上がりはすぐに家に帰っちゃうし」
「ついこの間カフェに来てただろ」
「あれからもう五日は経ってるの! こんなに長い間会えないのは初めてでしてね! 恋人と同居してる人は黙っててくれますー!?」
「そうか。なら俺たちは時間まで二階にこもる」
「うそうそごめん! 二人にまで見捨てられたら、類さん寂しくて死んじゃう……!」
しくしくと泣き真似をする類に、孝太朗は心底面倒くさそうにため息をついた。それでも浮かした腰を戻すあたり、孝太朗は優しい。
「だ、大丈夫ですよ類さん。きっと有栖さん、お仕事が色々と立て込んでいるだけですから」
「そうかなあ。でも今日も、昼休みの時間だけでも会えない? って聞いたんだけど、やることがあるからって取り付く島もなかったし」
「それだけ大切な用事があるってことじゃねえのか」
「……バレンタインの準備をしてくれてるのかなって、思ってたんだけど」
鋭すぎるその推測に、日鞠は再びびくりと肩を揺らした。
「それもきっと間違っていないと思うんだけど。何となーく、それだけじゃないような気がするんだよね。これは完全に俺の勘なんだけど、俺以外の誰かと頻繁に会ってるみたいな、いやーな予感が」
「大丈夫です!!」
ばん、とテーブルに手を叩きつけながら、日鞠は声を張った。
突然の大声に、類はもちろん、隣席の孝太朗も目を見開いている。
「有栖さんは、類さんのことが大好きなんですから! もしかすると類さんの言うとおり、ほんの少しは内緒にしていることもあるかもしれません! でも! 類さんに喜んでもらおうと、今の有栖さんは一生懸命なんです! そのことは、誰よりも私が保証しますっ!」
「日鞠ちゃん」
「だからその、類さんは心配しないで、有栖さんのことを信じてあげてくれませんか……!」
真面目でしっかり者の有栖のことだ。
きっと隙間時間を見つけてはチョコレート作りについて学び、一目散に帰宅してはゴトの熱血指導を受けているのだろう。
そんな有栖の変化に気づかない類ではない。
それでも、その一途な想いを疑ってほしくはなかった。
「ありがとう。日鞠ちゃん」
穏やかな口調で告げられた感謝の言葉に、日鞠ははっと我に返った。
「実は結構本気で凹んでたんだけどね。日鞠ちゃんに断言されたら、妙に安心しちゃったよ」
「よかったです。類さんも、本当に有栖さんのことが大好きなんですね」
「……そう真正面から聞かれちゃうと、何だかめちゃくちゃ恥ずかしいかも……?」
「お前、恥じらいなんて感情があったのか」
「俺もつい最近知りました……」
ため息交じりに机に突っ伏した類だったが、その頬は僅かに赤く染まっていた。
いつもは三百六十度どこから見ても完璧な笑顔をたたえるイケメンさんが、今は一人の女性への想いに右往左往している。
そんな友人の新たな一面を目にして、日鞠は胸がじわりと温かくなるのを感じた。
その後の午後シフト中、類は時折大窓の向こうを眺めては想い人の来訪を待ちわびていた。
日鞠も、恐らくは孝太朗もそのことに気づいていたが、どちらもそれを口にすることはなく営業時間を終えた。
翌日の夕方。仕事上がりに有栖と落ち合った日鞠は、再び彼女の家にお邪魔していた。
「よかった。ゴトさんの冷えの症状も、随分とよくなっているみたいですね」
「うむ。山神さま直伝の薬膳雑炊のおかげニャ。やはり身体を温めるのは内と外の両方からが一番だニャ。今では短い間なら、外に出ても平気になってきたニャ!」
「わあ、それはよかったです」
「日鞠さん、紅茶をどうぞ。ゴトさんには、ハチミツ入りのホットミルクです」
「ありがとうございます、有栖さん」
「うニャ。いただくニャ」
そう言ってミルクのほうへ移動するゴトは、以前よりも動きが軽やかで毛並みもつやつやと健康そうだ。
「ゴトさんのお料理指南のお話も聞きました。ゴトさんは人に料理を教えるのがとってもお上手なんですね」
「最初は有栖の不得手さに愕然としたがニャ。ひとつひとつの動きを、有栖が理解できるように説明していっただけニャ。野菜を刻むときの力加減やら、卵の殻を割るときの心持ちなんかをニャ」
「なるほど。卵の殻を割るときの心持ちですか」
確かに、日鞠は工程のみの説明に留まり、「どのように」「どのくらいの強さで」といった説明が抜けていたように思う。
料理初心者にもしっかりと寄り添うことのできるゴトの温かな心持ちに、日鞠は自然と笑みを浮かべた。
「今では私も、日鞠さんに教えていただいた薬膳雑炊を、なんとか作れるようになったんですよ」
「わあ! すごいです、すごいです、有栖さん!」
まるで自分のことのようにはしゃいでしまう。
何せ以前二人でこのキッチンに立ったときは、製菓用チョコレートが瞬く間に消し飛んでしまったほどなのだ。
それだけにこの数日、有栖がどれだけ努力をしてきたのかが理解できる。
愛の力は、やっぱり偉大だ。
「有栖さんの薬膳雑炊のおかげもあって、ゴトさんの冷え症状も目を見張るほど改善されたんですね」
「まあ、それもあるがニャ。きっとそれだけではないニャ」
小さく首を傾げる有栖にそっと視線を向けたあと、ゴトは答えた。
「恥ずかしい話だがニャ。ここ最近、わたしは人との関わり合いがめっきりなくなっていたのニャ。そもそもあやかしを視認できる者がほとんどおらず、目の前に出てみてもみんなわたしを素通りニャ。昔は人間の住まいに入り込んでは、火付け役として重宝されたというのにニャ」
「ゴトさん」
「これも時代の流れニャね。わかってはいるのだが、心の奥底では受け入れがたかったようだニャ。人と関わろうとしては失敗するのを繰り返し、不貞腐れたわたしは何年も何年もあの石垣の穴から動かない時間を過ごした。その結果が、この冷え症状というわけニャね」
「ゴトさんは、人との交流が大好きだったんですね」
日鞠の言葉に、ゴトは無言で頷く。
五徳猫は囲炉裏の火付け役。そんなふうに人から感謝されてきたゴトが抱えてきた寂しさは、自分たちの想像をはるかに超えるものに違いない。
有栖がそっと、ゴトの前足に触れた。ゴトの三角耳がぴくんと揺れたが、拒絶の言葉が出ることはなかった。
応援ありがとうございます!
0
お気に入りに追加
662
1 / 5
この作品を読んでいる人はこんな作品も読んでいます!
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる
本作については削除予定があるため、新規のレンタルはできません。
このユーザをミュートしますか?
※ミュートすると該当ユーザの「小説・投稿漫画・感想・コメント」が非表示になります。ミュートしたことは相手にはわかりません。またいつでもミュート解除できます。
※一部ミュート対象外の箇所がございます。ミュートの対象範囲についての詳細はヘルプにてご確認ください。
※ミュートしてもお気に入りやしおりは解除されません。既にお気に入りやしおりを使用している場合はすべて解除してからミュートを行うようにしてください。