7 / 24
六話 血と肉
しおりを挟む
裏路地街の肉屋は、店先に肉塊が無造作に敷き詰められ、羽虫が群がり、お世辞にも清潔とは言い難い。
目の前の店先には、色とりどりの花が咲き誇る花壇があり、とても同じ商品を扱っているようには見えなかった。
しかし花の香に、獣肉特有の生臭さが混じっているため、看板に偽りはないのだろう。苦手な臭いにリアムは一歩退いた。
動きに合わせて、清涼感のある香りが鼻孔をくすぐり、途端にふわりと気分が上向きになる。
リアムに追いついたヴィクターは、訝しげに店先を見やり、
「ここは認可を受けている店だぞ」
疑うような眼差しをリアムに注いだ。
――ここに来て嘘なんかつくわけないじゃないか。
リアムの中で、ふつふつと苛立ちが沸き起こってくる。
「でも、今までのなかで、一番臭います」
断言するリアムに、ヴィクターは片眉を上げた。
――僕が調査に協力していないと思っているの?
酒場の仕事の合間に、休む時間を削っているのだ。リアムは、頑張りが報われず、涙ぐみそうになる。
「……確かに、影響がでるほど臭うみたいだな」
ヴィクターはポケットから厚手のハンカチを取り出すと、リアムの鼻先に押し付けた。
「むっ!」
リアムは目を見張り、ヴィクターを睨みつける。
「バニシャに当てられてるぞ。鼻、塞いどけ」
リアムは、ほろ苦い煙草の香りに、冷静さが戻ってきた。
――ぼ、僕はなんて失礼なことを!
後悔するリアムを置き去りに、ヴィクターは迷いなく肉屋の扉を引き開けた。
店内には入り口を囲むようにショーケースが設置され、中には、肉の塊が並んでいた。干し肉よりも生生しく紅い肉塊に、リアムは思わずヴィクターの背中に隠れ、コートの裾を掴んでしまった。
ふと見やった先で、牛や豚の頭部に空いた眼窩と目があい、血の気がひく。
「……おい、こんなところで倒れるなよ」
ぐらついたリアムの背中を、ヴィクターは片腕で支えた。
「す、すみません……」
リアムは赤面し、ヴィクターはますます眉をしかめる。
「これはこれは。ルージェンド様ではないですか。お父上はご息災ですかな?」
右手のショーケース横から、壮年の男が口元を緩め出迎えた。口ひげは短く整えられ清潔感に溢れている。
「ああ、殺しても死なないくらいだ」
「であれば、シティ•ロドルナは安泰ですな。……勤務中と見えますが、当店にはどのような御用で?」
コートの影から見え隠れするリアムに視線を向けつつも、口ひげの男はヴィクターに尋ねた。
「最近、取り扱い指定品を仕入れたか?」
「ええ、一週間前に肉の臭み消しに何種類か香草を購入いたしましたが……」
「在庫を見せてもらいたい」
ヴィクターの有無を言わせぬ問いに慣れているのか、口ひげの男は理由を尋ねることもなく、「こちらにどうぞ」と優雅にショーケースの裏側にヴィクターとリアムを招いた。
奥の扉を抜けた先には、細い廊下が続き、突き当りに橙色の灯りに照らされた大扉が見えた。
口ひげの男は、チョッキのポケットから数多の鍵がぶら下がったキーホルダーを取り出す。複雑な突起が彫られた鍵に、リアムは釘付けになった。
「大層な錠だな」
「一応、当店の財産なものですから。新参者の【肉屋】が狙ってくるかもしれません」
「同業者同士で物騒だな。狩人は平等に仕事をこなしているはずだが?」
ガチャンと鍵が噛み合う音が廊下に響く。口ひげの男は片側の取っ手を思い切り引っ張った。
「そりゃあ、大森林のそばで大切に育てられた家畜は、平等に市場に出ますよ。大森林で狩られた魔獣もしかりです。ロドルナ全てに大森林の恵みは、分配される。……表向きは、ですがね」
部屋の中は薄暗く、リアムは怖気づいたものの、口ひげの男とヴィクターは歩みを止めない。リアムは必死に彼らの後を追った。
口ひげの男が壁に手のひらをかざすと、天井がじんわりと発光する。
「最新のガス燈です」
天井に蛇のように管が這い、等間隔にランプシェードが設置されている。それらが照らし出すのは。
「ひっ」
縄で吊るされた大小さまざまなピンク色の物体だった。生き物であった原型をとどめていないが、手足がついていたであろう凹凸に、リアムは喉をヒクつかせた。
「大した品揃えだ」
「仮にも富裕層街で百年以上、舌の肥えた紳士淑女の皆さまのご要望にお応えしてきましたからな。ここにないものは絶滅種の肉ぐらいです」
肉のカーテンを横目に、三人は奥に進んだ。血の臭いがリアムの鼻を通り過ぎていく。ヴィクターが貸してくれたハンカチで口元を覆い、リアムは吐き気をこらえた。
足元がふらつき、僅かな床板の狭間につま先を引っ掛け転んでしまう。
顔が床に近づいた瞬間、脳を揺さぶられる幻覚に襲われた。両手で身体を支えるも、額から汗が伝い、自分の影に重なるように水滴が落ちる。
どくどくと心臓が血液を送りだし、身体をリアムではない何かに変えようとするようで。
「おい……顔が真っ青だぞ」
ヴィクターが心配そうにリアムの顔を覗き込んだ。こんなに薄暗い中でも分かるほどなのかと、リアムは頬に手を当てた。
じっとり汗ばみ、冷たくなっている。リアムと床を見比べたヴィクターは、床についたリアムの手に手を重ねた。
「え……!」
驚くリアムの手の甲ごとヴィクターは床板を押し込む。すると小さな取っ手が床から飛び出した。
――なんだ、床に仕掛けがあったからか……。
ヴィクターに心配されたと不謹慎にも喜んでしまったリアムは、肩を落とした。
「地下室か……? 店主、この下に何が――」
振り向いたヴィクターは凍りついたように動きを止めた。リアムもつられて振り返り、あんぐりと口を開けてしまう。
「……勝手に貯蔵庫に入ってもらっちゃ困ります」
ヴィクターよりも上背のありそうな長身の男が、肉切り包丁を片手に二人を見下ろしていた。
目の前の店先には、色とりどりの花が咲き誇る花壇があり、とても同じ商品を扱っているようには見えなかった。
しかし花の香に、獣肉特有の生臭さが混じっているため、看板に偽りはないのだろう。苦手な臭いにリアムは一歩退いた。
動きに合わせて、清涼感のある香りが鼻孔をくすぐり、途端にふわりと気分が上向きになる。
リアムに追いついたヴィクターは、訝しげに店先を見やり、
「ここは認可を受けている店だぞ」
疑うような眼差しをリアムに注いだ。
――ここに来て嘘なんかつくわけないじゃないか。
リアムの中で、ふつふつと苛立ちが沸き起こってくる。
「でも、今までのなかで、一番臭います」
断言するリアムに、ヴィクターは片眉を上げた。
――僕が調査に協力していないと思っているの?
酒場の仕事の合間に、休む時間を削っているのだ。リアムは、頑張りが報われず、涙ぐみそうになる。
「……確かに、影響がでるほど臭うみたいだな」
ヴィクターはポケットから厚手のハンカチを取り出すと、リアムの鼻先に押し付けた。
「むっ!」
リアムは目を見張り、ヴィクターを睨みつける。
「バニシャに当てられてるぞ。鼻、塞いどけ」
リアムは、ほろ苦い煙草の香りに、冷静さが戻ってきた。
――ぼ、僕はなんて失礼なことを!
後悔するリアムを置き去りに、ヴィクターは迷いなく肉屋の扉を引き開けた。
店内には入り口を囲むようにショーケースが設置され、中には、肉の塊が並んでいた。干し肉よりも生生しく紅い肉塊に、リアムは思わずヴィクターの背中に隠れ、コートの裾を掴んでしまった。
ふと見やった先で、牛や豚の頭部に空いた眼窩と目があい、血の気がひく。
「……おい、こんなところで倒れるなよ」
ぐらついたリアムの背中を、ヴィクターは片腕で支えた。
「す、すみません……」
リアムは赤面し、ヴィクターはますます眉をしかめる。
「これはこれは。ルージェンド様ではないですか。お父上はご息災ですかな?」
右手のショーケース横から、壮年の男が口元を緩め出迎えた。口ひげは短く整えられ清潔感に溢れている。
「ああ、殺しても死なないくらいだ」
「であれば、シティ•ロドルナは安泰ですな。……勤務中と見えますが、当店にはどのような御用で?」
コートの影から見え隠れするリアムに視線を向けつつも、口ひげの男はヴィクターに尋ねた。
「最近、取り扱い指定品を仕入れたか?」
「ええ、一週間前に肉の臭み消しに何種類か香草を購入いたしましたが……」
「在庫を見せてもらいたい」
ヴィクターの有無を言わせぬ問いに慣れているのか、口ひげの男は理由を尋ねることもなく、「こちらにどうぞ」と優雅にショーケースの裏側にヴィクターとリアムを招いた。
奥の扉を抜けた先には、細い廊下が続き、突き当りに橙色の灯りに照らされた大扉が見えた。
口ひげの男は、チョッキのポケットから数多の鍵がぶら下がったキーホルダーを取り出す。複雑な突起が彫られた鍵に、リアムは釘付けになった。
「大層な錠だな」
「一応、当店の財産なものですから。新参者の【肉屋】が狙ってくるかもしれません」
「同業者同士で物騒だな。狩人は平等に仕事をこなしているはずだが?」
ガチャンと鍵が噛み合う音が廊下に響く。口ひげの男は片側の取っ手を思い切り引っ張った。
「そりゃあ、大森林のそばで大切に育てられた家畜は、平等に市場に出ますよ。大森林で狩られた魔獣もしかりです。ロドルナ全てに大森林の恵みは、分配される。……表向きは、ですがね」
部屋の中は薄暗く、リアムは怖気づいたものの、口ひげの男とヴィクターは歩みを止めない。リアムは必死に彼らの後を追った。
口ひげの男が壁に手のひらをかざすと、天井がじんわりと発光する。
「最新のガス燈です」
天井に蛇のように管が這い、等間隔にランプシェードが設置されている。それらが照らし出すのは。
「ひっ」
縄で吊るされた大小さまざまなピンク色の物体だった。生き物であった原型をとどめていないが、手足がついていたであろう凹凸に、リアムは喉をヒクつかせた。
「大した品揃えだ」
「仮にも富裕層街で百年以上、舌の肥えた紳士淑女の皆さまのご要望にお応えしてきましたからな。ここにないものは絶滅種の肉ぐらいです」
肉のカーテンを横目に、三人は奥に進んだ。血の臭いがリアムの鼻を通り過ぎていく。ヴィクターが貸してくれたハンカチで口元を覆い、リアムは吐き気をこらえた。
足元がふらつき、僅かな床板の狭間につま先を引っ掛け転んでしまう。
顔が床に近づいた瞬間、脳を揺さぶられる幻覚に襲われた。両手で身体を支えるも、額から汗が伝い、自分の影に重なるように水滴が落ちる。
どくどくと心臓が血液を送りだし、身体をリアムではない何かに変えようとするようで。
「おい……顔が真っ青だぞ」
ヴィクターが心配そうにリアムの顔を覗き込んだ。こんなに薄暗い中でも分かるほどなのかと、リアムは頬に手を当てた。
じっとり汗ばみ、冷たくなっている。リアムと床を見比べたヴィクターは、床についたリアムの手に手を重ねた。
「え……!」
驚くリアムの手の甲ごとヴィクターは床板を押し込む。すると小さな取っ手が床から飛び出した。
――なんだ、床に仕掛けがあったからか……。
ヴィクターに心配されたと不謹慎にも喜んでしまったリアムは、肩を落とした。
「地下室か……? 店主、この下に何が――」
振り向いたヴィクターは凍りついたように動きを止めた。リアムもつられて振り返り、あんぐりと口を開けてしまう。
「……勝手に貯蔵庫に入ってもらっちゃ困ります」
ヴィクターよりも上背のありそうな長身の男が、肉切り包丁を片手に二人を見下ろしていた。
0
あなたにおすすめの小説

拝啓、目が覚めたらBLゲームの主人公だった件
碧月 晶
BL
さっきまでコンビニに向かっていたはずだったのに、何故か目が覚めたら病院にいた『俺』。
状況が分からず戸惑う『俺』は窓に映った自分の顔を見て驚いた。
「これ…俺、なのか?」
何故ならそこには、恐ろしく整った顔立ちの男が映っていたのだから。
《これは、現代魔法社会系BLゲームの主人公『石留 椿【いしどめ つばき】(16)』に転生しちゃった元平凡男子(享年18)が攻略対象たちと出会い、様々なイベントを経て『運命の相手』を見つけるまでの物語である──。》
────────────
~お知らせ~
※第3話を少し修正しました。
※第5話を少し修正しました。
※第6話を少し修正しました。
※第11話を少し修正しました。
※第19話を少し修正しました。
※第22話を少し修正しました。
※第24話を少し修正しました。
※第25話を少し修正しました。
※第26話を少し修正しました。
※第31話を少し修正しました。
※第32話を少し修正しました。
────────────
※感想(一言だけでも構いません!)、いいね、お気に入り、近況ボードへのコメント、大歓迎です!!
※表紙絵は作者が生成AIで試しに作ってみたものです。

呪われた辺境伯は、異世界転生者を手放さない
波崎 亨璃
BL
ーーー呪われた辺境伯に捕まったのは、俺の方だった。
異世界に迷い込んだ駆真は「呪われた辺境伯」と呼ばれるレオニスの領地に落ちてしまう。
強すぎる魔力のせいで、人を近づけることができないレオニス。
彼に触れれば衰弱し、最悪の場合、命を落とす。
しかしカルマだけはなぜかその影響を一切受けなかった。その事実に気づいたレオニスは次第にカルマを手放さなくなっていく。
「俺に触れられるのは、お前だけだ」
呪いよりも重い執着と孤独から始まる、救済BL。
となります。

劣等アルファは最強王子から逃げられない
東
BL
リュシアン・ティレルはアルファだが、オメガのフェロモンに気持ち悪くなる欠陥品のアルファ。そのことを周囲に隠しながら生活しているため、異母弟のオメガであるライモントに手ひどい態度をとってしまい、世間からの評判は悪い。
ある日、気分の悪さに逃げ込んだ先で、ひとりの王子につかまる・・・という話です。

禁書庫の管理人は次期宰相様のお気に入り
結衣可
BL
オルフェリス王国の王立図書館で、禁書庫を預かる司書カミル・ローレンは、過去の傷を抱え、静かな孤独の中で生きていた。
そこへ次期宰相と目される若き貴族、セドリック・ヴァレンティスが訪れ、知識を求める名目で彼のもとに通い始める。
冷静で無表情なカミルに興味を惹かれたセドリックは、やがて彼の心の奥にある痛みに気づいていく。
愛されることへの恐れに縛られていたカミルは、彼の真っ直ぐな想いに少しずつ心を開き、初めて“痛みではない愛”を知る。
禁書庫という静寂の中で、カミルの孤独を、過去を癒し、共に歩む未来を誓う。

【8話完結】ざまぁされて廃嫡されたバカ王子とは俺のことです。
キノア9g
BL
廃嫡され全てを失った元王子。地道に生きたいのにハイスペ幼馴染が逃がしてくれません。
あらすじ
「第二王子カイル、お前を廃嫡する」
傲慢な振る舞いを理由に、王位継承権も婚約者も失い、国外追放されたカイル。
絶望の最中、彼に蘇ったのは「ブラック企業で使い潰された前世の記憶」だった。
「もう二度と、他人任せにはしない」
前世の反省を活かし、隣国の冒険者ギルドで雑用係(清掃員)として地道にやり直そうとするカイル。しかし、そんな彼を追いかけてきたのは、隣国の貴族であり幼馴染のレオナードだった。
「君がどんな立場になろうと、僕にとっては君は君だ」
落ちぶれたカイルに変わらぬ愛を注ぎ、元婚約者の悪意ある噂からも守り抜くレオナード。
すべてを失った元バカ王子が、社畜根性と幼馴染の溺愛によって幸せを掴むまでの、再起と愛の物語。
全8話。

龍の寵愛を受けし者達
樹木緑
BL
サンクホルム国の王子のジェイドは、
父王の護衛騎士であるダリルに憧れていたけど、
ある日偶然に自分の護衛にと推す父王に反する声を聞いてしまう。
それ以来ずっと嫌われていると思っていた王子だったが少しずつ打ち解けて
いつかはそれが愛に変わっていることに気付いた。
それと同時に何故父王が最強の自身の護衛を自分につけたのか理解す時が来る。
王家はある者に裏切りにより、
無惨にもその策に敗れてしまう。
剣が苦手でずっと魔法の研究をしていた王子は、
責めて騎士だけは助けようと、
刃にかかる寸前の所でとうの昔に失ったとされる
時戻しの術をかけるが…

【完結】君を知らないまま、恋をした
一ノ瀬麻紀
BL
体調を崩し入院した篠宮真白(しのみやましろ)は、制限のある生活を送ることになった。
そんな中、真白は自由に走り回れるもう一つの世界を知る。
そこで過ごす時間は、思うように動けなかった真白にとって、大切なものだった。
仮想空間での出会いや経験を通して、真白の世界は少しずつ広がっていく。
そして真白が本当の気持ちに気づいた時、すべてが繋がり始める――。
※
タイトル及びあらすじ変更しました。(2/10)
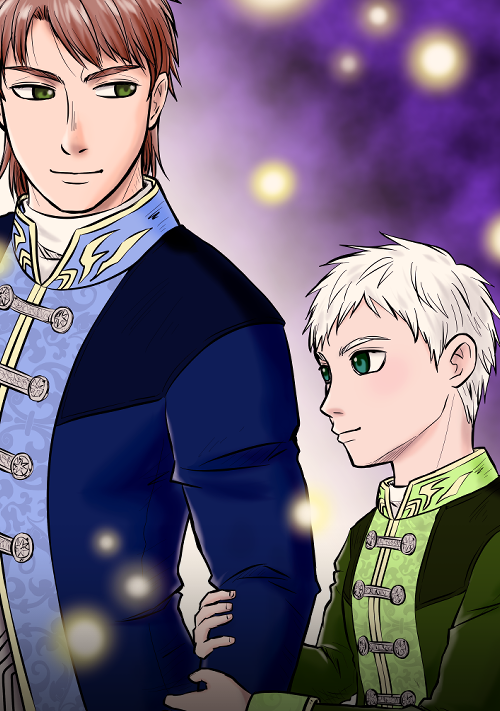
天涯孤独になった少年は、元軍人の優しいオジサンと幸せに生きる
ir(いる)
BL
※2025/11 プロローグを追加しました
ファンタジー。最愛の父を亡くした後、恋人(不倫相手)と再婚したい母に騙されて捨てられた12歳の少年。30歳の元軍人の男性との出会いで傷付いた心を癒してもらい、恋(主人公からの片思い)をする物語。
※序盤は主人公が悲しむシーンが多いです。
※主人公と相手が出会うまで、少しかかります(28話)
※BL的展開になるまでに、結構かかる予定です。主人公が恋心を自覚するようでしないのは51話くらい?
※女性は普通に登場しますが、他に明確な相手がいたり、恋愛目線で主人公たちを見ていない人ばかりです。
※同性愛者もいますが、異性愛が主流の世界です。なので主人公は、男なのに男を好きになる自分はおかしいのでは?と悩みます。
※主人公のお相手は、保護者として主人公を温かく見守り、支えたいと思っています。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















