6 / 17
第5章・捲土重来ーけんどちょうらいー
しおりを挟む
エレベーターが止まった。
階数表示はB1、地下1階だ。
重い音を響かせて、扉が開いていく。
そこは床も壁もコンクリートむき出しの小さな部屋だった。明かりがついてはいるが、小さい電灯だけなので薄暗い。
「妙なふいんきの場所だな」
「雰囲気よ、ウロタエくん」
「ふぃーんきだろ。ちゃんと言えてるだろ」
「うん、そうね」
あきれ顔で麻衣子が応える。
言えてるよな?
立ち往生しているおれ達の頭上から、再び声が聞こえた。
『ここは美術館。君達には、ぜひぼくの作品を楽しんでもらいたいと思ってね』
「作品?」
『作品と言っても、絵画や彫刻といった小難しいものじゃあないよ。ぼくの作品は子供が大好きなゲーム。全部クリアできれば、ぼくがいる部屋にたどり着くようになっているよ』
「ゲームって何をするんだよ?」
「ロロは無事なの?」
「攻略できなかったらどうなる?」
おれ達が口々に騒ぐが返事はない。
一方的に言い放ち声は聞こえなくなった。通信を切られたか、それとも無視されているのか。
スポットライトがともり、部屋の中央を照らす。
エンジ色のテーブルクロスをかけられた丸テーブルがあらわれた。その上には、1枚のメニュースタンドと4枚のカードが置いてある。
「これがゲームに使う道具ってこと?」
麻衣子がメニュースタンドを手に取った。
「不用意に触るなよ」
「なーに? 太郎ってばビビってるの?」
ビビリはしないが不気味だろ。まだ謎の声の正体も目的もわからないんだ。
章純と希未も警戒心を隠そうともせず、エレベーターから出てすぐの所で様子を見ている。
「平気だって。みんなこっち来てよ」
麻衣子に呼ばれ、みんながテーブルに集まった。
スポットライトの中で、みんなでメニュースタンドを見る。
・ひとりにひとつ。
・カードは君を示すカギ。
・絶対に忘れないで。
メニュースタンドに書いてあったのは、この3行だけだった。
何か仕掛けがあるかと、裏返したりライトにすかしたりしたが、隠れたメッセージは無かった。
「カードってこれだよな?」
メニュースタンドと一緒にテーブルに並んでいた4枚の真っ白なカードから、1枚を手に取ってみた。
交通系ICカードのように厚みと硬さがあるカードだ。
裏返すとトランプの模様がある。
「スペードの6だ」
ほかの3枚もめくってみる。
ハートのK、ダイヤの5、クローバーの8。
マークも数字もバラバラだ。
「これで何かをすればいいのか? 順番通りに並べ直すとか」
「ひとりにひとつって書いてあるよ。なら順番ではなく、ひとり1枚持つことに意味があるんじゃないかな?」
「そうねー、今の所、他にヒントもないし」
「みんな、どれをとる?」
おれは最初にめくったスペードの6を選んだ。
「わたし、キング・オブ・ハートがいい」
希美はハートのKを選んだ。ハートマークに加え、1枚だけ絵札と言うのにひかれたのだろう。
「わたしはダイヤのカードにするわ」
「じゃあ、ぼくはクローバーの8だね」
これで、それぞれ1枚ずつ。
おれがスペードの6、麻衣子はダイヤの5、章純はクローバーの8、希未はハートのKだ。
4人がカードを手に取ったのと同時に、室内の照明の光量が変化した。おれ達がいる場所から向こう側の壁まで続く照明は明るさが増し、それ意外の照明は逆に消灯寸前まで暗くなった。
まるでショーの花道のように一直線に道が引かれたようだ。
「ここを進めってことだよな?」
「暗い所に何か隠れてないかな?」
希未が言うように、おれ達の周りが明るいのと他が暗くなったことで、ただでさえ暗かった室内が、さらに暗く感じるようになった。
さっきまではかろうじて見えていた壁も闇の中に消えている。
しかし、おれ達には他に行動の選択肢がない。左右の暗闇に警戒しながら進んでいった。
その先には100インチ以上ある大きなモニターがあった。
『もー、待ちくたびれちゃったよ。君達、臆病すぎー』
モニターに電源が入り画面が映った。そこには大きい丸い頭をした、三等身の白いネコのようなぬいぐるみがいる。
「ゆ、ゆるキャラ?」
『そ、この美術館のイメージキャラクターのレマッグくんだよー』
画面の中でレマッグくんと名乗ったネコのぬいぐるみが、腰を左右に降って、おどけてみせる。
「お前がロロを連れ去ったのか?」
『連れ去ったなんて人聞きが悪いな。ワンちゃんなら、ぼくの隣で寝てるよ』
映像がレマッグくんの足元に替わると、バスケットの中で丸くなって寝ているロロの姿が映った。
「ロロちゃん、可愛いー」
「こんな状況で、なんてのん気な」
「いつもはお昼寝してる時間だから」
『みんな、ちゃんとカードは持って来たかな?』
「これか?」
テーブルで手に入れたトランプカードをレマッグくんに見せる。モニター越しで見えるのかはわからないけど。
『うんうん、それそれ。それじゃあ、第1ゲームを始めちゃおうか』
レマッグくんが作品と称するゲーム。
おれ達に緊張が走る。
『ゲームはみんなも知っているジャンケンをアレンジしたゲーム。ひとりずつ、ぼくとジャンケンをして、誰かひとりでも先に勝ちを言えれば全員クリアだよ。最初だからイージーモードぜんかーい」
「水木くん、イージーモードって何?」
「簡単って意味だよ」
ジャンケンは運と確率がモノを言うゲーム。4人のうち誰かひとりでも勝てばいいのであれば、勝率はかなり高くなる。
レマッグくんが言う通り、イージーモードだ。
『さてさて、さくーっとはじめちゃおうか。カードの数字が大きい子から順番に。チャンスはひとり1回だよ』
「カードの数字順か」
一番大きいのはKのカード。1番目は、希未だ。
「わ、わたしから?」
「大丈夫よ。ただのジャンケンだし、後にわたし達もいるんだし」
麻衣子が希未の肩をたたき励ます。
希未は顔を上げ麻衣子と顔を合わせる。次いで章純、おれとも顔を合わせた。
おれも章純も、ただ無言でうなずいた。この状況でかける言葉が見つからなかったからだ。
『はじめるよー』
モニターの中のレマッグくんが右手を振り上げた。
『じゃーん、けーん……』
「じゃ、んっ、けーん」
希未も慌てて右手を出した。
『ぽん!』
「ぽん!」
レマが出した手は、パー。
希未の手は、チョキ。
一発勝負で希未の、おれ達側の勝ちだ。
「さすがホビット!」
「さすが運のよさ全振り!」
「あれ? ほめられてる気がしないよ」
『ぼくの勝ちだねーっ』
ブブーッと大きなブザー音が鳴って、モニターの上部に大きなバツがあらわれた。
一瞬、何が起こったかがわからず、おれ達の動きが止まった。
沈黙を破ったのは、章純だった。
「な、何言ってるんだよ。溝辺さんがチョキで、そっちがパーなんだ。勝ったのは溝辺さんだろ」
「そうだぜ。ちゃんと確認しろ!」
「ルールは守ってよね!」
『言いがかりはやめてよね。ぼくは最初にちゃーんとルールは説明したよ』
おれ達の抗議にもレマッグくんは態度を崩さない。
ルールは説明した。
この結果はルール通りと言うことか。
レマッグくんのさっきの言葉を思い出せ。
ーーゲームはみんなも知っているジャンケンをアレンジしたゲーム。
つまり、ただのジャンケンではなく、プラスアルファの要素があるということか。
「負けた方が勝ちってことかな?」
今の結果だけを見れば、章純の推理が正しく感じる。
しかし、確証はないが何かが引っ掛かる。まだ何か見落としがある気がする。
『次は誰かなー?』
Kの次に大きい数字を持つカードは、章純のクローバーの8だ。
章純が一歩前に出る。
「章純、大丈夫なのか?」
「うん。ちゃんと、負けてくる!」
振り返り、妙に自信ありげな笑みを返す章純。こいつは希未とは正反対に、常日頃から運が悪い。ガチャガチャでは同じキャラが3回連続で出たり、コンビニのキャラクターくじも1番下の賞しか引けたことがない。
その運の悪さを、このゲームでも発揮できるか。
『じゃーん、けーん……』
「ぽん!」
レマが出した手は、チョキ。
章純の手は、パー。
宣言通り、章純は負けた。
『ぼくの勝ちだねーっ』
「な、なんで。負けた方が勝ちになるんじゃ?」
『おいおい。ジャンケンに負けたら勝ちなんて、ぼくは一度も言ってないよ。そっちで勝手に、そう思っただけじゃないか』
ブブーッと大きなブザー音が鳴って、モニターにふたつ目の大きなバツがあらわれた。
「勝ってもダメ、負けてもダメじゃ、わたし達にどうしようもないじゃん」
希未が肩を落とし床に崩れ落ちる。今にも泣きだしそうだ。
突然こんなことに巻き込まれたんだ、無理もない。
『つぎは誰かなー?』
こっちの様子などお構いなしに、レマッグくんがおどけた態度で次戦を促す。
次の勝負をするのは、スペードの6を持っているおれだ。
「おい、レマッグって言ったな?」
『いえっす。フルネームはレマッグくんだけどね、親しみを込めてレマって呼んでね』
「だったら、レマ。ひとつ聞かせてほしい」
『何かな? ぼくのスリーサイズ? ちなみに好きなタイプはガッシリしたアスリートタイプだから、残念ながら君は圏外だね』
こいつ女なのか。どうでもいいけど。
「これはゲームなんだな?」
『そうだよ、ゲームさ。ぼくと君達の真剣勝負だ』
「そうか。それさえ聞ければいい」
ジャンケンを始めるため、右手を前に出す。
『始めるよ。じゃーん、けーん』
「ポン!」
レマの出した手は、チョキ。
おれの手は、パー。
『ぼ……』
「おれの勝ちだ!」
高らかに宣言した。レマよりも先に。
ピンポーンと音が鳴り、モニターに大きなマルがあらわれた。
「やっぱりな」
「なんで? ぼくも、さっき負けたのに」
まだ状況が読めない章純が目を丸くする。
「さっきのレマのルール説明を思い出すんだ」
ーーゲームはみんなも知っているジャンケンをアレンジしたゲーム。
ーーひとりずつ、ぼくとジャンケンをして、誰かひとりでも先に勝ちを言えれば全員クリアだよ。
この中で一番印象に残るのは、ジャンケンをアレンジしたゲームという部分。だからこそ章純はジャンケンの勝ち負けがゲーム結果につながる、そう解釈した。
ここが最初の罠だ。
「このゲームは、ジャンケンをアレンジしたゲームであって、ジャンケンのゲームではない」
「ジャンケンじゃない?」
「このルールで重要なのは後半部分」
ーー誰かひとりでも先に勝ちを言えれば全員クリアだよ。
「この部分」
「え、それじゃあ、まさか」
「そう。このゲームはジャンケンをした後に『先に勝ったと言った方が勝ち』になるゲームなんだよ」
全員がおれとモニターの中のレマに注目する。
『あはははは、せいかーい。よく、そこにたどり着けたね』
お腹を抱えて笑うレマを映したモニターが、ゆっくりとせり上がっていく。
『第1ゲームはクリアーにしてあげる。でもイージーモードはこれでおしまい。次からはこうはいかないよ』
レマはそう言い残し、モニターごと天井に消えていった。
モニターがあった場所の後ろには、横開きの自動ドアがあった。降りて来る時に乗った搬入用のエレベーターと違い、今度のは普通の乗用エレベーターだ。
「入れってことだよな?」
「他に道もなさそうだし」
振り返ると、ここに来る時に道代わりだった照明もいつの間にか消えていた。数メートル先もわからない暗闇になっている。
引き返す道は閉ざされていた。
おれ達4人は意を決して、エレベータに乗り込んだ。
中に入ってすぐ扉が閉まり、今度は上に向かって動き出した。
「でも太郎。よくルールの意味に気づいたわね」
「うん。わたしもビックリしちゃった」
「冷静になって考えるとなるほどって思うけど、あの状況だとなかなか気づけないと思うよ」
麻衣子だけでなく、希未と章純も、おれが勝ったことを称賛してくれる。
ちょっと気分がいい。
「さっきレマに、これはゲームかと聞いた時に、ゲームだって答えただろ? ゲームは参加するプレイヤー全員に勝てる可能性がないと成立しない。どちらか片方だけが有利なワンサイドゲームは、ゲームじゃなくてただの一方的な暴力だ」
「なるほどね。ゲーム好きの太郎らしい思考回路だわ」
「まあな」
ロロを捕まえたり、おれ達を一方的に参加させたりと、レマはどう考えても悪いやつだ。
でも、この一点。
ゲームに対しての姿勢だけは、おれは本物だと思う。
ゲームを作品と呼ぶところからも、それは感じとれる。
だからだろうか。怒りとか恐怖とか不安とは違う、強い感情がおれの中に生まれ始めていた。
次はどんなゲームが待っているのだろう。
少し、この状況を楽しみ始めていた。
階数表示はB1、地下1階だ。
重い音を響かせて、扉が開いていく。
そこは床も壁もコンクリートむき出しの小さな部屋だった。明かりがついてはいるが、小さい電灯だけなので薄暗い。
「妙なふいんきの場所だな」
「雰囲気よ、ウロタエくん」
「ふぃーんきだろ。ちゃんと言えてるだろ」
「うん、そうね」
あきれ顔で麻衣子が応える。
言えてるよな?
立ち往生しているおれ達の頭上から、再び声が聞こえた。
『ここは美術館。君達には、ぜひぼくの作品を楽しんでもらいたいと思ってね』
「作品?」
『作品と言っても、絵画や彫刻といった小難しいものじゃあないよ。ぼくの作品は子供が大好きなゲーム。全部クリアできれば、ぼくがいる部屋にたどり着くようになっているよ』
「ゲームって何をするんだよ?」
「ロロは無事なの?」
「攻略できなかったらどうなる?」
おれ達が口々に騒ぐが返事はない。
一方的に言い放ち声は聞こえなくなった。通信を切られたか、それとも無視されているのか。
スポットライトがともり、部屋の中央を照らす。
エンジ色のテーブルクロスをかけられた丸テーブルがあらわれた。その上には、1枚のメニュースタンドと4枚のカードが置いてある。
「これがゲームに使う道具ってこと?」
麻衣子がメニュースタンドを手に取った。
「不用意に触るなよ」
「なーに? 太郎ってばビビってるの?」
ビビリはしないが不気味だろ。まだ謎の声の正体も目的もわからないんだ。
章純と希未も警戒心を隠そうともせず、エレベーターから出てすぐの所で様子を見ている。
「平気だって。みんなこっち来てよ」
麻衣子に呼ばれ、みんながテーブルに集まった。
スポットライトの中で、みんなでメニュースタンドを見る。
・ひとりにひとつ。
・カードは君を示すカギ。
・絶対に忘れないで。
メニュースタンドに書いてあったのは、この3行だけだった。
何か仕掛けがあるかと、裏返したりライトにすかしたりしたが、隠れたメッセージは無かった。
「カードってこれだよな?」
メニュースタンドと一緒にテーブルに並んでいた4枚の真っ白なカードから、1枚を手に取ってみた。
交通系ICカードのように厚みと硬さがあるカードだ。
裏返すとトランプの模様がある。
「スペードの6だ」
ほかの3枚もめくってみる。
ハートのK、ダイヤの5、クローバーの8。
マークも数字もバラバラだ。
「これで何かをすればいいのか? 順番通りに並べ直すとか」
「ひとりにひとつって書いてあるよ。なら順番ではなく、ひとり1枚持つことに意味があるんじゃないかな?」
「そうねー、今の所、他にヒントもないし」
「みんな、どれをとる?」
おれは最初にめくったスペードの6を選んだ。
「わたし、キング・オブ・ハートがいい」
希美はハートのKを選んだ。ハートマークに加え、1枚だけ絵札と言うのにひかれたのだろう。
「わたしはダイヤのカードにするわ」
「じゃあ、ぼくはクローバーの8だね」
これで、それぞれ1枚ずつ。
おれがスペードの6、麻衣子はダイヤの5、章純はクローバーの8、希未はハートのKだ。
4人がカードを手に取ったのと同時に、室内の照明の光量が変化した。おれ達がいる場所から向こう側の壁まで続く照明は明るさが増し、それ意外の照明は逆に消灯寸前まで暗くなった。
まるでショーの花道のように一直線に道が引かれたようだ。
「ここを進めってことだよな?」
「暗い所に何か隠れてないかな?」
希未が言うように、おれ達の周りが明るいのと他が暗くなったことで、ただでさえ暗かった室内が、さらに暗く感じるようになった。
さっきまではかろうじて見えていた壁も闇の中に消えている。
しかし、おれ達には他に行動の選択肢がない。左右の暗闇に警戒しながら進んでいった。
その先には100インチ以上ある大きなモニターがあった。
『もー、待ちくたびれちゃったよ。君達、臆病すぎー』
モニターに電源が入り画面が映った。そこには大きい丸い頭をした、三等身の白いネコのようなぬいぐるみがいる。
「ゆ、ゆるキャラ?」
『そ、この美術館のイメージキャラクターのレマッグくんだよー』
画面の中でレマッグくんと名乗ったネコのぬいぐるみが、腰を左右に降って、おどけてみせる。
「お前がロロを連れ去ったのか?」
『連れ去ったなんて人聞きが悪いな。ワンちゃんなら、ぼくの隣で寝てるよ』
映像がレマッグくんの足元に替わると、バスケットの中で丸くなって寝ているロロの姿が映った。
「ロロちゃん、可愛いー」
「こんな状況で、なんてのん気な」
「いつもはお昼寝してる時間だから」
『みんな、ちゃんとカードは持って来たかな?』
「これか?」
テーブルで手に入れたトランプカードをレマッグくんに見せる。モニター越しで見えるのかはわからないけど。
『うんうん、それそれ。それじゃあ、第1ゲームを始めちゃおうか』
レマッグくんが作品と称するゲーム。
おれ達に緊張が走る。
『ゲームはみんなも知っているジャンケンをアレンジしたゲーム。ひとりずつ、ぼくとジャンケンをして、誰かひとりでも先に勝ちを言えれば全員クリアだよ。最初だからイージーモードぜんかーい」
「水木くん、イージーモードって何?」
「簡単って意味だよ」
ジャンケンは運と確率がモノを言うゲーム。4人のうち誰かひとりでも勝てばいいのであれば、勝率はかなり高くなる。
レマッグくんが言う通り、イージーモードだ。
『さてさて、さくーっとはじめちゃおうか。カードの数字が大きい子から順番に。チャンスはひとり1回だよ』
「カードの数字順か」
一番大きいのはKのカード。1番目は、希未だ。
「わ、わたしから?」
「大丈夫よ。ただのジャンケンだし、後にわたし達もいるんだし」
麻衣子が希未の肩をたたき励ます。
希未は顔を上げ麻衣子と顔を合わせる。次いで章純、おれとも顔を合わせた。
おれも章純も、ただ無言でうなずいた。この状況でかける言葉が見つからなかったからだ。
『はじめるよー』
モニターの中のレマッグくんが右手を振り上げた。
『じゃーん、けーん……』
「じゃ、んっ、けーん」
希未も慌てて右手を出した。
『ぽん!』
「ぽん!」
レマが出した手は、パー。
希未の手は、チョキ。
一発勝負で希未の、おれ達側の勝ちだ。
「さすがホビット!」
「さすが運のよさ全振り!」
「あれ? ほめられてる気がしないよ」
『ぼくの勝ちだねーっ』
ブブーッと大きなブザー音が鳴って、モニターの上部に大きなバツがあらわれた。
一瞬、何が起こったかがわからず、おれ達の動きが止まった。
沈黙を破ったのは、章純だった。
「な、何言ってるんだよ。溝辺さんがチョキで、そっちがパーなんだ。勝ったのは溝辺さんだろ」
「そうだぜ。ちゃんと確認しろ!」
「ルールは守ってよね!」
『言いがかりはやめてよね。ぼくは最初にちゃーんとルールは説明したよ』
おれ達の抗議にもレマッグくんは態度を崩さない。
ルールは説明した。
この結果はルール通りと言うことか。
レマッグくんのさっきの言葉を思い出せ。
ーーゲームはみんなも知っているジャンケンをアレンジしたゲーム。
つまり、ただのジャンケンではなく、プラスアルファの要素があるということか。
「負けた方が勝ちってことかな?」
今の結果だけを見れば、章純の推理が正しく感じる。
しかし、確証はないが何かが引っ掛かる。まだ何か見落としがある気がする。
『次は誰かなー?』
Kの次に大きい数字を持つカードは、章純のクローバーの8だ。
章純が一歩前に出る。
「章純、大丈夫なのか?」
「うん。ちゃんと、負けてくる!」
振り返り、妙に自信ありげな笑みを返す章純。こいつは希未とは正反対に、常日頃から運が悪い。ガチャガチャでは同じキャラが3回連続で出たり、コンビニのキャラクターくじも1番下の賞しか引けたことがない。
その運の悪さを、このゲームでも発揮できるか。
『じゃーん、けーん……』
「ぽん!」
レマが出した手は、チョキ。
章純の手は、パー。
宣言通り、章純は負けた。
『ぼくの勝ちだねーっ』
「な、なんで。負けた方が勝ちになるんじゃ?」
『おいおい。ジャンケンに負けたら勝ちなんて、ぼくは一度も言ってないよ。そっちで勝手に、そう思っただけじゃないか』
ブブーッと大きなブザー音が鳴って、モニターにふたつ目の大きなバツがあらわれた。
「勝ってもダメ、負けてもダメじゃ、わたし達にどうしようもないじゃん」
希未が肩を落とし床に崩れ落ちる。今にも泣きだしそうだ。
突然こんなことに巻き込まれたんだ、無理もない。
『つぎは誰かなー?』
こっちの様子などお構いなしに、レマッグくんがおどけた態度で次戦を促す。
次の勝負をするのは、スペードの6を持っているおれだ。
「おい、レマッグって言ったな?」
『いえっす。フルネームはレマッグくんだけどね、親しみを込めてレマって呼んでね』
「だったら、レマ。ひとつ聞かせてほしい」
『何かな? ぼくのスリーサイズ? ちなみに好きなタイプはガッシリしたアスリートタイプだから、残念ながら君は圏外だね』
こいつ女なのか。どうでもいいけど。
「これはゲームなんだな?」
『そうだよ、ゲームさ。ぼくと君達の真剣勝負だ』
「そうか。それさえ聞ければいい」
ジャンケンを始めるため、右手を前に出す。
『始めるよ。じゃーん、けーん』
「ポン!」
レマの出した手は、チョキ。
おれの手は、パー。
『ぼ……』
「おれの勝ちだ!」
高らかに宣言した。レマよりも先に。
ピンポーンと音が鳴り、モニターに大きなマルがあらわれた。
「やっぱりな」
「なんで? ぼくも、さっき負けたのに」
まだ状況が読めない章純が目を丸くする。
「さっきのレマのルール説明を思い出すんだ」
ーーゲームはみんなも知っているジャンケンをアレンジしたゲーム。
ーーひとりずつ、ぼくとジャンケンをして、誰かひとりでも先に勝ちを言えれば全員クリアだよ。
この中で一番印象に残るのは、ジャンケンをアレンジしたゲームという部分。だからこそ章純はジャンケンの勝ち負けがゲーム結果につながる、そう解釈した。
ここが最初の罠だ。
「このゲームは、ジャンケンをアレンジしたゲームであって、ジャンケンのゲームではない」
「ジャンケンじゃない?」
「このルールで重要なのは後半部分」
ーー誰かひとりでも先に勝ちを言えれば全員クリアだよ。
「この部分」
「え、それじゃあ、まさか」
「そう。このゲームはジャンケンをした後に『先に勝ったと言った方が勝ち』になるゲームなんだよ」
全員がおれとモニターの中のレマに注目する。
『あはははは、せいかーい。よく、そこにたどり着けたね』
お腹を抱えて笑うレマを映したモニターが、ゆっくりとせり上がっていく。
『第1ゲームはクリアーにしてあげる。でもイージーモードはこれでおしまい。次からはこうはいかないよ』
レマはそう言い残し、モニターごと天井に消えていった。
モニターがあった場所の後ろには、横開きの自動ドアがあった。降りて来る時に乗った搬入用のエレベーターと違い、今度のは普通の乗用エレベーターだ。
「入れってことだよな?」
「他に道もなさそうだし」
振り返ると、ここに来る時に道代わりだった照明もいつの間にか消えていた。数メートル先もわからない暗闇になっている。
引き返す道は閉ざされていた。
おれ達4人は意を決して、エレベータに乗り込んだ。
中に入ってすぐ扉が閉まり、今度は上に向かって動き出した。
「でも太郎。よくルールの意味に気づいたわね」
「うん。わたしもビックリしちゃった」
「冷静になって考えるとなるほどって思うけど、あの状況だとなかなか気づけないと思うよ」
麻衣子だけでなく、希未と章純も、おれが勝ったことを称賛してくれる。
ちょっと気分がいい。
「さっきレマに、これはゲームかと聞いた時に、ゲームだって答えただろ? ゲームは参加するプレイヤー全員に勝てる可能性がないと成立しない。どちらか片方だけが有利なワンサイドゲームは、ゲームじゃなくてただの一方的な暴力だ」
「なるほどね。ゲーム好きの太郎らしい思考回路だわ」
「まあな」
ロロを捕まえたり、おれ達を一方的に参加させたりと、レマはどう考えても悪いやつだ。
でも、この一点。
ゲームに対しての姿勢だけは、おれは本物だと思う。
ゲームを作品と呼ぶところからも、それは感じとれる。
だからだろうか。怒りとか恐怖とか不安とは違う、強い感情がおれの中に生まれ始めていた。
次はどんなゲームが待っているのだろう。
少し、この状況を楽しみ始めていた。
0
あなたにおすすめの小説
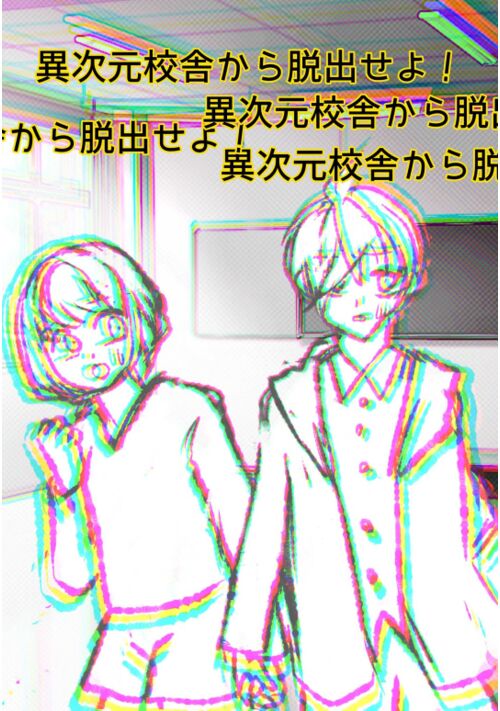
エマージェンシー!狂った異次元学校から脱出せよ!~エマとショウマの物語~
とらんぽりんまる
児童書・童話
第3回きずな児童書大賞で奨励賞を頂きました。
ありがとうございました!
気付いたら、何もない教室にいた――。
少女エマと、少年ショウマ。
二人は幼馴染で、どうして自分達が此処にいるのか、わからない。
二人は学校の五階にいる事がわかり、校舎を出ようとするが階段がない。
そして二人の前に現れたのは恐ろしい怪異達!!
二人はこの学校から逃げることはできるのか?
二人がどうなるか最後まで見届けて!!

カリンカの子メルヴェ
田原更
児童書・童話
地下に掘り進めた穴の中で、黒い油という可燃性の液体を採掘して生きる、カリンカという民がいた。
かつて迫害により追われたカリンカたちは、地下都市「ユヴァーシ」を作り上げ、豊かに暮らしていた。
彼らは合言葉を用いていた。それは……「ともに生き、ともに生かす」
十三歳の少女メルヴェは、不在の父や病弱な母に代わって、一家の父親役を務めていた。仕事に従事し、弟妹のまとめ役となり、時には厳しく叱ることもあった。そのせいで妹たちとの間に亀裂が走ったことに、メルヴェは気づいていなかった。
幼なじみのタリクはメルヴェを気遣い、きらきら輝く白い石をメルヴェに贈った。メルヴェは幼い頃のように喜んだ。タリクは次はもっと大きな石を掘り当てると約束した。
年に一度の祭にあわせ、父が帰郷した。祭当日、男だけが踊る舞台に妹の一人が上がった。メルヴェは妹を叱った。しかし、メルヴェも、最近みせた傲慢な態度を父から叱られてしまう。
そんな折に地下都市ユヴァーシで起きた事件により、メルヴェは生まれてはじめて外の世界に飛び出していく……。
※本作はトルコのカッパドキアにある地下都市から着想を得ました。

王女様は美しくわらいました
トネリコ
児童書・童話
無様であろうと出来る全てはやったと満足を抱き、王女様は美しくわらいました。
それはそれは美しい笑みでした。
「お前程の悪女はおるまいよ」
王子様は最後まで嘲笑う悪女を一刀で断罪しました。
きたいの悪女は処刑されました 解説版

極甘独占欲持ち王子様は、優しくて甘すぎて。
猫菜こん
児童書・童話
私は人より目立たずに、ひっそりと生きていたい。
だから大きな伊達眼鏡で、毎日を静かに過ごしていたのに――……。
「それじゃあこの子は、俺がもらうよ。」
優しく引き寄せられ、“王子様”の腕の中に閉じ込められ。
……これは一体どういう状況なんですか!?
静かな場所が好きで大人しめな地味子ちゃん
できるだけ目立たないように過ごしたい
湖宮結衣(こみやゆい)
×
文武両道な学園の王子様
実は、好きな子を誰よりも独り占めしたがり……?
氷堂秦斗(ひょうどうかなと)
最初は【仮】のはずだった。
「結衣さん……って呼んでもいい?
だから、俺のことも名前で呼んでほしいな。」
「さっきので嫉妬したから、ちょっとだけ抱きしめられてて。」
「俺は前から結衣さんのことが好きだったし、
今もどうしようもないくらい好きなんだ。」
……でもいつの間にか、どうしようもないくらい溺れていた。

未来スコープ ―キスした相手がわからないって、どういうこと!?―
米田悠由
児童書・童話
「あのね、すごいもの見つけちゃったの!」
平凡な女子高生・月島彩奈が偶然手にした謎の道具「未来スコープ」。
それは、未来を“見る”だけでなく、“課題を通して導く”装置だった。
恋の予感、見知らぬ男子とのキス、そして次々に提示される不可解な課題──
彩奈は、未来スコープを通して、自分の運命に深く関わる人物と出会っていく。
未来スコープが映し出すのは、甘いだけではない未来。
誰かを想う気持ち、誰かに選ばれない痛み、そしてそれでも誰かを支えたいという願い。
夢と現実が交錯する中で、彩奈は「自分の気持ちを信じること」の意味を知っていく。
この物語は、恋と選択、そしてすれ違う想いの中で、自分の軸を見つけていく少女たちの記録です。
感情の揺らぎと、未来への確信が交錯するSFラブストーリー、シリーズ第2作。
読後、きっと「誰かを想うとはどういうことか」を考えたくなる一冊です。

先祖返りの姫王子
春紫苑
児童書・童話
小国フェルドナレンに王族として生まれたトニトルスとミコーは、双子の兄妹であり、人と獣人の混血種族。
人で生まれたトニトルスは、先祖返りのため狼で生まれた妹のミコーをとても愛し、可愛がっていた。
平和に暮らしていたある日、国王夫妻が不慮の事故により他界。
トニトルスは王位を継承する準備に追われていたのだけれど、馬車での移動中に襲撃を受け――。
決死の逃亡劇は、二人を離れ離れにしてしまった。
命からがら逃げ延びた兄王子と、王宮に残され、兄の替え玉にされた妹姫が、互いのために必死で挑む国の奪還物語。

生贄姫の末路 【完結】
松林ナオ
児童書・童話
水の豊かな国の王様と魔物は、はるか昔にある契約を交わしました。
それは、姫を生贄に捧げる代わりに国へ繁栄をもたらすというものです。
水の豊かな国には双子のお姫様がいます。
ひとりは金色の髪をもつ、活発で愛らしい金のお姫様。
もうひとりは銀色の髪をもつ、表情が乏しく物静かな銀のお姫様。
王様が生贄に選んだのは、銀のお姫様でした。

【完結】またたく星空の下
mazecco
児童書・童話
【第15回絵本・児童書大賞 君とのきずな児童書賞 受賞作】
※こちらはweb版(改稿前)です※
※書籍版は『初恋×星空シンバル』と改題し、web版を大幅に改稿したものです※
◇◇◇冴えない中学一年生の女の子の、部活×恋愛の青春物語◇◇◇
主人公、海茅は、フルート志望で吹奏楽部に入部したのに、オーディションに落ちてパーカッションになってしまった。しかもコンクールでは地味なシンバルを担当することに。
クラスには馴染めないし、中学生活が全然楽しくない。
そんな中、海茅は一人の女性と一人の男の子と出会う。
シンバルと、絵が好きな男の子に恋に落ちる、小さなキュンとキュッが詰まった物語。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















