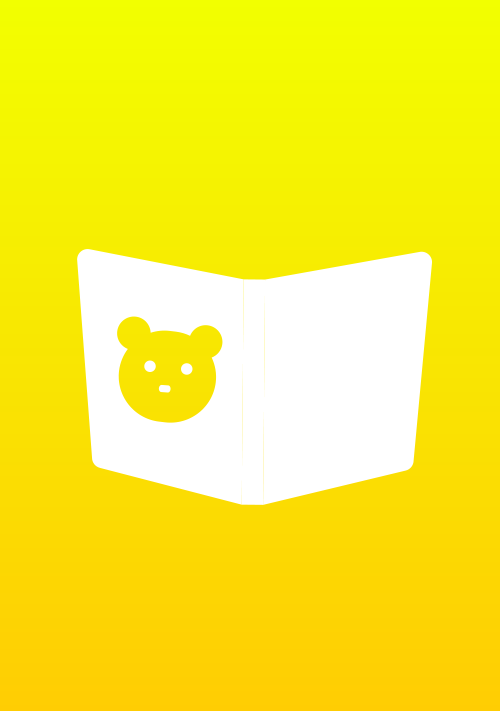7 / 21
第2話 : 始業 [3]
しおりを挟む
「そうみたい。」 桃香は特に違う点がないようだ。 事実、ただ1学年終えたからといって大きな差がありそうもない。
「私も特別なことはないと思う。」祐希も視線を弁当に固定したまま淡々と答える。
「何それ!あの無感情な反応。 面白くないね。華やかな桜がこんなに満開の日にあんなくすんだ言葉ばかり並べるなんて。 だから新入生が必要なんだよ! 雰囲気に活力を吹き込む真っ青な新入生が。」紗耶香は眉をひそめ、言葉尻を曇らせる。
「これを狙ったんだ。 ここで会おうと言った本当の目的がそれだよね?」桃香もその目的を内心知っていたのに何か言うのが負担だったが、紗耶香が先に冗談を言いながら取り出す。
「まあ…と言ったら怒るかな?」紗耶香も素直に納得する。 疑いという疑いはすべて受けておいて、厚かましく言い逃れをするのもおかしい。 結局、率直に打ち明けたわけだから、かえってよかった。 気まずい言い訳よりは自然な答えだ。
「じゃあ、どうするつもり? ずっとそのように口を閉じているつもりなの?」催促し続ければ、2人が感情に勝てず和解するだろう。 その過程で矢が紗耶香に向けられたりもしたが、とにかく結果が望ましいだけならいい。
「適当な解決策がある? 早く仲直りして新入生をどうやってもらうか決めたい。」紗耶香は他の解決策がないことをニヤニヤしながら強調する。
「じゃあ、こうするのはどう? 祐希の基準通りに一人を選んで、私の基準通りに一人を選ぶんだ。 二人に小説を書かせて、今回の文化祭で我が校の生徒を対象に投票するんだ。 二つの中で誰の小説がもっと好きなのか。 より多くの票を得た側を新入部員に選ぶこと。 また、その人を選んだ人が文芸部を率いる権限を得ること。いいんじゃない? 今年まだ部長を決めてもいないじゃない? 勝った人が部長になるんだよ。」 桃香が祐希に先に提案する。 紗耶香の催促に押されて無理やり仲直りをしても、これが本気でなければ意味がない。 むしろこうするのがいい。 お互いに文句なしに受け入れることができるだろう。
「さあ…ちょっと待って… 本当に二人で仲直りするの?」紗耶香は予想から外れた会話内容に不安になる。 何か間違ったことに気付く。 本当に望んだ姿はこれではなかった。
「よし!その提案を受け入れるよ。」祐希もやはりこれが和解のための最良の方法だと思う。 勝者と敗者が分かれる明快な結果になれば、喜んで受け入れることができそうだ。
「うん、いいね。」 桃香は祐希が自信満々に受け止めているのに気づく。 彼女は自分が負けるとは思わない。 賭けの勝者になって彼に従わせるのが目的だ。
「よし。もう決まったから、早く昼食を食べて教室に戻ろう。」 桃香はお弁当をこっそり取り出しながら言う。 これ以上紗耶香が割り込んで賭けの本質を曇らせないことを願う。 余地さえ残らないように言葉を一度に切ってしまう。
祐希は本屋で会った少女が頭の中をかすめる。 その少女が同じ学校に通う学生で、そのように劇的に会ったのが運命なら、その意図に符合する人かもしれないという気がする。 これといった方法がない状況なら、偶然を一度信じてみるのも悪くない。
彼らは何も言わずに各自弁当を空け始め、桜の香りに酔って熱くなった雰囲気が消える前に昼休みが終わる。
祐希は昼食を食べ終わって教室に戻るが、その考えにとらわれて授業に集中できない。
座って悩んでばかりいては答えがない。 行動に移す時だ。 別に約束をしたわけでもないくせに、このような期待をするのは馬鹿なことだと思うが、駄目元で一回試してみよう。
時間は流れて学校の日課が終わるのを知らせる鐘が鳴る。
祐希はまるでこの瞬間だけを待っていたかのように、弾丸のように教室を蹴って出る。 授業中ずっと焦りを抑えるために胸が詰まったようにもどかしかった自分に与える補償だ。 その少女に会った本屋に行ってみることにする。 2人の間に何の関連性があるのかも分からず、そこでまた会えるかも断言できないが、これが現在としては最善だ。 本当に必然なら、単なる偶然でなければ、漠然と期待するしかない。
桃香も実力のある新入生を連れてこようとするに違いない。 純粋な好奇心と情熱に重点を置く自分は、この賭けで不利な立場かもしれないが、あきらめることはできない。 ただ部長の座を欲しがっているのではない。 桃香の価値観を変えてあげるのが本当の目的だ。 部長になるのは勝利に伴う一種の補償に過ぎない。
一方、桃香も本格的に自分の価値観に合致しながら賭けで勝利をもたらす人を探そうとする。 そのように大口をたたきながら犯したことを考えると、まず頭を下げて入ることはできない。 自尊心がそんな恥ずかしいことを許さない。 今すぐどこで人を救うか分からず途方に暮れるばかりだが、どうせ条件は同じだ。 自分だけでなく、祐希も同じだろう。
「とりあえず、学校の図書館に行ってみたほうがいいと思う。」 自分の期待に符合する部員を救う広報ポスターを貼ろうとする目的もあるが、そのように本に集中していれば漠然と良い考えが浮かぶかもしれないという期待感もあるためだ。
そのチラシは偶然小説の余韻が消える前に結末が見たくて図書館に来た弘の関心を引く。
「あの…文芸部?」彼は好奇心に打ち勝つことができなかったので彼女に話しかける。
「失礼ですが、どなたですか?」彼女は一歩下がって警戒心に満ちた表情で尋ねる。
「ふと小説に興味ができたんだけど…」 彼は慎重に言い出す。
「う~ん… すみません。 うちの部ではそんな人をもらうわけではないんですよ。 一応入ろうとする動機が私たちの富の方向に合わないようですね。」 彼女はやはり笑いながら一気に断る。 特に、自分がこのポスターを掲げている本当の目的を考えると、その答えにおのずと笑いが出るほどだ。 自分の信念がどれほど強いかをすべての部員に見せ、荒唐無稽な主張だけを掲げる祐希を口もきけないようにすると固く決心した彼女がこのような人に会うのは、もしかしたら運命のいたずらかもしれない。
「そんな人を受けないというのはどういう意味ですか? ただ本を読むことに興味があり、ただ小説の話をしたいだけではないですか?」一気に断る理由が何なのか知りたくなる。
「全然違うんですよ。 私たちの部ではレベルの高い文学人が入ってきて、この文芸部の発展に貢献することを願っています。」 彼女は胸の奥底で沸き立つ不快感と怒りを抑えようと努力している。 このように親切に言ってくれれば、気付いて退くのが正常だ。
「ああ、そうですか?」彼はやっと勇気を出して入りたいという話を切り出したのに冷静な返事だけ返ってくるので、ただ残念に思わずにはいられない。
「そんな初心者はお断りします。 特にこの瞬間が私たちの富のためにどれほど重要かを考えればですね。」彼女はやはり断固とした口調で彼が食い下がる余地を残さないようにする。
簡単にできるという考え自体が傲慢だったのかもしれないが、彼女の冷淡な話し方に彼はもっと頑固になる。 単に本に対する興味が生じたという理由だけでなく、彼女の否定的な反応に刺激されてそのまま入りたいという漠然とした意地が生じる。
「それではテストのようなものがあるんですか?」彼は自分がその条件を満たすために直ちに必要なものが何なのか疑問に思わずにはいられない。
「何の話ですか。」 彼女は彼がそのような反応を見せるのがただあきれるばかりだ。
「入部テスト。」もしかしたら極めて当然な質問なのに、訳もなく認めたくなくて返事を避ける彼女に不満を感じるのかもしれない。
「だから初心者は私たちの文芸部で受けないと言いました。」今すぐ適当な人を探しても足りないところに、このような無意味な口論ばかりしているので胸から沸き上がる怒りが限界に達するようだ。
「初心者は受けないということは実力があれば受けるということではないですか?」喜んで挑戦することにする。 通過すれば良いことだが、脱落しても決して時間の無駄ではない。 きちんと結果を受け入れるためには、必ずそうする必要がある。
「ほう…自信がありそうだね。」 彼女はただ根拠のない自信に違いないという考えで否定的な口調で一貫する。
「条件を備えていると証明すればいいのではないですか?」 答えは明快だ。 彼女が本当に望んでいることと、彼自身が何をすべきか明確になったので、これ以上言う必要はない。
「いいですね。それでは部員を一人ご紹介します。 私は正直、あなたが私たちの文芸部にふさわしい人かどうかはよく分かりませんが、その友達は本当にあなたのような人を切実に探しているんですよ。 一度声をかけてみてください。」 いったんその意欲は認めざるを得ないので、祐希の連絡先を彼に直接渡す。
賭けで勝ちたい欲に駆られて思いついた計画に期待をかけてみることにする。 このような初心者は祐希に任せ、自分は適当に才能のある部員を探せば自然とその勝利を手に入れることができるだろう。
一方、祐希はやはり書店に到着する。 彼女は同じ学校の生徒かもしれないことに漠然とした希望を抱いている。 彼はこの気持ちをどう表現すればいいのか分からず、緊張感で体が自然に震える。
彼彼は本屋で見つけた光景に目を疑わざるを得ない。 彼女が同じ席に立っていて、甚だしくは学校の制服を着ているのを見ると、とても信じられない。
「ねえ…」彼は彼女がこの前のように逃げるのではないかと慎重に近づいて挨拶をする。
「え?」彼女も音がする方に首をかしげ、一気に彼がこの前ここで会った人だということを思い出す。 道を歩いていて偶然会ったら確かに気づかなかったはずだが、実際にここで見ると彼が誰なのかはっきり思い出すことができる。 その時の記憶を書店という場所に関連させて頭の中から引き出す。
「こんにちは。私を覚えていますか?」彼はかなり前にあったことなので、ひょっとして忘れたのではないかと心配で彼女にもっと慎重に接する。
「この前ぶつかったあの人! まさにここで!」と彼女は突然大声で叫ぶ。
「覚えていますか?」びっくりするが、むしろ彼女がそのような反応を見せるのを喜んでいる。
「この学校に学生だったようですね? このような不思議な偶然が。」 彼は彼女のランドセルに付いた学校のキーホルダーを見つける。 彼女も下校途中に本屋に立ち寄ったと確信している。
「そうですね。それは私が言いたいことですね。 栞奈です。 お会いできて嬉しいです。」 彼女も興奮して先にあいさつをすることができなかった。
「はい、祐希と申します。」 彼は短くその挨拶を受け入れる。
「本が好きみたいですね。」 彼女を文芸部の一員として受け入れたいという考えがあるが、関心があるかどうかから確認しなければならない。 いきなり入ってこいと言うのは失礼に違いない。
「はい! 本当に好きです! 文を書くことにもそれなりに自信があります。 また、私の小説を必ず見せたい人がいるんですよ。」いたずらに変な自慢げに聞こえるか心配でちょっと恥ずかしくもしているが、いざ先に勧誘した人は彼なので、彼女自身がこのように大げさに騒ぐもこれといった関係がなさそうだ。
「同じ学校に通う人にこうやって会うのも大きな偶然なんですが、実はうちの文芸部で今回新入を募集しています。」 彼はその時になってようやく慎重に本当の目的を持ち出す。
「うーん… 偶然だとおっしゃいましたが、違うかもしれません。 私たちが偶然だと感じる多くの偶然は、実は偶然のように感じられるほど驚くほど劇的に当てはまる必然だと思います。 実は私もその文芸部については大体知っています。 そうでなくても興味があったので、訪ねて行こうとしました。」 彼女はその突然の申し出に驚くどころか、まるで待っていたかのように平然と応じる。 正式に入部を要請する前に、このように部員に会うのももしかしたら運命かもしれない。
「本当ですか?嬉しい話ですね。」特別な説明なしに対話が急速に進行しているようで幸いだ。 よく通じる人のようだ。
「今手に持っている本、結構好きなんですね。」 ちょうどその瞬間に彼はこの前あったことを偶然思い出して尋ねる。 彼女が憚らなければ、長年の疑問を解消する良い機会だ。
「あ…これですか? 好きです。でも僕が感じるには、 単純に好きな感情を超えて 何かもっとあると思います。 私に夢というものを植えてくれた物なんです。 ただそのようにだけ分かってほしいです。 後でまた別のところで縁があったら、お知らせします。」
「この前に本屋で持っていた本もその本ではなかったですか。」 彼女が慌てて落とした本だということを鮮明に覚えている。
「はい、そうです。 よく覚えていらっしゃいますね。 なんでまた同じものを買うんだ? という意味ですよね。」 彼女はにっこり笑いながら茶目っ気のある声で尋ねる。
「あ… 違います。 そんな意味は。」実際に彼女がそのように答えると、純粋な好奇心で言った質問に過ぎないのに、まるで何か大きな過ちでも犯したかのように申し訳なくなる。 手を振って強く否定する。
「実は、今日新しく付き合った友達にあげたんですよ。 それで新しく一つ買いに来ました。 ぼんやりしている姿を見ては到底我慢できませんでした。 読み終わって感想まで言ってくれと言ったのがちょっと強圧的だったような気もしますが、実は! 後で感想を聞く時に聞きたい言葉があったからです。 本のプレゼントに私が込めた意味を知ってほしいということで、私の真心がきちんと伝わったのか気になるのです。 本という媒体を通じて誰かに真心が伝えられるならば、これは単純な文以上の価値があると思います。」 単純に言葉で表現しにくいことを表現できる手段。 これが本という媒体の最大の魅力だと思います。 彼女も誰かの文を通じて誰かの真心を伝えてもらい、そのために他人に自分の心を伝える媒体としてこれを選んだのだと思います。
「ああ、はい。」 彼は彼女の言っていることがどういう意味なのか分からず首をかしげる。
「はい。」 彼女はやはり短く答える。
ぎこちない静寂が流れる。 沈黙は栞奈に心を打ち明けろと促すが、対話を交わす相手も、不便な雰囲気もそんな率直な夢の話には似合わない。 彼女はプレッシャーの中で中途半端に立っているよりむしろ立ち去った方がましだ。
「あ!ここでこうしていてはいけません。 やることがあるんですよ。」 突然何か急なことが思い浮かんだように手をたたいてはさっと振り向く。
「はい、大丈夫です。」 何か残念だが、もっと執拗に問い詰めても反発心だけを刺激すると思う。
彼はただ立ち去る彼女をじっと見ているだけだ。 ひとしきり嵐が吹き荒れたようにあっけらかんだ。
彼女が目の前で消えたことを確認してから何か見逃したことがあるようでじっくり振り返ってみると、本について話すのに夢中になって連絡先を交換するのを忘れた。 少し残念ではあるが、特に心配にはならない。 彼女が勝手に訪ねてくると言ったので、どうしても彼女との連絡が再び続くという信頼がある。 単純な偶然に過ぎないという考えでただ不安だったが、これが実際にまともに当てはまることを両目で確認すると、必ず続く縁という自信に変わったのだ。
初日から目的に合った人を見つけることに成功した。 少し前までは漠然としていたが、思ったよりうまくいっているようだ。
初日から目的に合った人を見つけることに成功した。 少し前までは漠然としていたが、思ったよりうまくいっているようだ。
「私も特別なことはないと思う。」祐希も視線を弁当に固定したまま淡々と答える。
「何それ!あの無感情な反応。 面白くないね。華やかな桜がこんなに満開の日にあんなくすんだ言葉ばかり並べるなんて。 だから新入生が必要なんだよ! 雰囲気に活力を吹き込む真っ青な新入生が。」紗耶香は眉をひそめ、言葉尻を曇らせる。
「これを狙ったんだ。 ここで会おうと言った本当の目的がそれだよね?」桃香もその目的を内心知っていたのに何か言うのが負担だったが、紗耶香が先に冗談を言いながら取り出す。
「まあ…と言ったら怒るかな?」紗耶香も素直に納得する。 疑いという疑いはすべて受けておいて、厚かましく言い逃れをするのもおかしい。 結局、率直に打ち明けたわけだから、かえってよかった。 気まずい言い訳よりは自然な答えだ。
「じゃあ、どうするつもり? ずっとそのように口を閉じているつもりなの?」催促し続ければ、2人が感情に勝てず和解するだろう。 その過程で矢が紗耶香に向けられたりもしたが、とにかく結果が望ましいだけならいい。
「適当な解決策がある? 早く仲直りして新入生をどうやってもらうか決めたい。」紗耶香は他の解決策がないことをニヤニヤしながら強調する。
「じゃあ、こうするのはどう? 祐希の基準通りに一人を選んで、私の基準通りに一人を選ぶんだ。 二人に小説を書かせて、今回の文化祭で我が校の生徒を対象に投票するんだ。 二つの中で誰の小説がもっと好きなのか。 より多くの票を得た側を新入部員に選ぶこと。 また、その人を選んだ人が文芸部を率いる権限を得ること。いいんじゃない? 今年まだ部長を決めてもいないじゃない? 勝った人が部長になるんだよ。」 桃香が祐希に先に提案する。 紗耶香の催促に押されて無理やり仲直りをしても、これが本気でなければ意味がない。 むしろこうするのがいい。 お互いに文句なしに受け入れることができるだろう。
「さあ…ちょっと待って… 本当に二人で仲直りするの?」紗耶香は予想から外れた会話内容に不安になる。 何か間違ったことに気付く。 本当に望んだ姿はこれではなかった。
「よし!その提案を受け入れるよ。」祐希もやはりこれが和解のための最良の方法だと思う。 勝者と敗者が分かれる明快な結果になれば、喜んで受け入れることができそうだ。
「うん、いいね。」 桃香は祐希が自信満々に受け止めているのに気づく。 彼女は自分が負けるとは思わない。 賭けの勝者になって彼に従わせるのが目的だ。
「よし。もう決まったから、早く昼食を食べて教室に戻ろう。」 桃香はお弁当をこっそり取り出しながら言う。 これ以上紗耶香が割り込んで賭けの本質を曇らせないことを願う。 余地さえ残らないように言葉を一度に切ってしまう。
祐希は本屋で会った少女が頭の中をかすめる。 その少女が同じ学校に通う学生で、そのように劇的に会ったのが運命なら、その意図に符合する人かもしれないという気がする。 これといった方法がない状況なら、偶然を一度信じてみるのも悪くない。
彼らは何も言わずに各自弁当を空け始め、桜の香りに酔って熱くなった雰囲気が消える前に昼休みが終わる。
祐希は昼食を食べ終わって教室に戻るが、その考えにとらわれて授業に集中できない。
座って悩んでばかりいては答えがない。 行動に移す時だ。 別に約束をしたわけでもないくせに、このような期待をするのは馬鹿なことだと思うが、駄目元で一回試してみよう。
時間は流れて学校の日課が終わるのを知らせる鐘が鳴る。
祐希はまるでこの瞬間だけを待っていたかのように、弾丸のように教室を蹴って出る。 授業中ずっと焦りを抑えるために胸が詰まったようにもどかしかった自分に与える補償だ。 その少女に会った本屋に行ってみることにする。 2人の間に何の関連性があるのかも分からず、そこでまた会えるかも断言できないが、これが現在としては最善だ。 本当に必然なら、単なる偶然でなければ、漠然と期待するしかない。
桃香も実力のある新入生を連れてこようとするに違いない。 純粋な好奇心と情熱に重点を置く自分は、この賭けで不利な立場かもしれないが、あきらめることはできない。 ただ部長の座を欲しがっているのではない。 桃香の価値観を変えてあげるのが本当の目的だ。 部長になるのは勝利に伴う一種の補償に過ぎない。
一方、桃香も本格的に自分の価値観に合致しながら賭けで勝利をもたらす人を探そうとする。 そのように大口をたたきながら犯したことを考えると、まず頭を下げて入ることはできない。 自尊心がそんな恥ずかしいことを許さない。 今すぐどこで人を救うか分からず途方に暮れるばかりだが、どうせ条件は同じだ。 自分だけでなく、祐希も同じだろう。
「とりあえず、学校の図書館に行ってみたほうがいいと思う。」 自分の期待に符合する部員を救う広報ポスターを貼ろうとする目的もあるが、そのように本に集中していれば漠然と良い考えが浮かぶかもしれないという期待感もあるためだ。
そのチラシは偶然小説の余韻が消える前に結末が見たくて図書館に来た弘の関心を引く。
「あの…文芸部?」彼は好奇心に打ち勝つことができなかったので彼女に話しかける。
「失礼ですが、どなたですか?」彼女は一歩下がって警戒心に満ちた表情で尋ねる。
「ふと小説に興味ができたんだけど…」 彼は慎重に言い出す。
「う~ん… すみません。 うちの部ではそんな人をもらうわけではないんですよ。 一応入ろうとする動機が私たちの富の方向に合わないようですね。」 彼女はやはり笑いながら一気に断る。 特に、自分がこのポスターを掲げている本当の目的を考えると、その答えにおのずと笑いが出るほどだ。 自分の信念がどれほど強いかをすべての部員に見せ、荒唐無稽な主張だけを掲げる祐希を口もきけないようにすると固く決心した彼女がこのような人に会うのは、もしかしたら運命のいたずらかもしれない。
「そんな人を受けないというのはどういう意味ですか? ただ本を読むことに興味があり、ただ小説の話をしたいだけではないですか?」一気に断る理由が何なのか知りたくなる。
「全然違うんですよ。 私たちの部ではレベルの高い文学人が入ってきて、この文芸部の発展に貢献することを願っています。」 彼女は胸の奥底で沸き立つ不快感と怒りを抑えようと努力している。 このように親切に言ってくれれば、気付いて退くのが正常だ。
「ああ、そうですか?」彼はやっと勇気を出して入りたいという話を切り出したのに冷静な返事だけ返ってくるので、ただ残念に思わずにはいられない。
「そんな初心者はお断りします。 特にこの瞬間が私たちの富のためにどれほど重要かを考えればですね。」彼女はやはり断固とした口調で彼が食い下がる余地を残さないようにする。
簡単にできるという考え自体が傲慢だったのかもしれないが、彼女の冷淡な話し方に彼はもっと頑固になる。 単に本に対する興味が生じたという理由だけでなく、彼女の否定的な反応に刺激されてそのまま入りたいという漠然とした意地が生じる。
「それではテストのようなものがあるんですか?」彼は自分がその条件を満たすために直ちに必要なものが何なのか疑問に思わずにはいられない。
「何の話ですか。」 彼女は彼がそのような反応を見せるのがただあきれるばかりだ。
「入部テスト。」もしかしたら極めて当然な質問なのに、訳もなく認めたくなくて返事を避ける彼女に不満を感じるのかもしれない。
「だから初心者は私たちの文芸部で受けないと言いました。」今すぐ適当な人を探しても足りないところに、このような無意味な口論ばかりしているので胸から沸き上がる怒りが限界に達するようだ。
「初心者は受けないということは実力があれば受けるということではないですか?」喜んで挑戦することにする。 通過すれば良いことだが、脱落しても決して時間の無駄ではない。 きちんと結果を受け入れるためには、必ずそうする必要がある。
「ほう…自信がありそうだね。」 彼女はただ根拠のない自信に違いないという考えで否定的な口調で一貫する。
「条件を備えていると証明すればいいのではないですか?」 答えは明快だ。 彼女が本当に望んでいることと、彼自身が何をすべきか明確になったので、これ以上言う必要はない。
「いいですね。それでは部員を一人ご紹介します。 私は正直、あなたが私たちの文芸部にふさわしい人かどうかはよく分かりませんが、その友達は本当にあなたのような人を切実に探しているんですよ。 一度声をかけてみてください。」 いったんその意欲は認めざるを得ないので、祐希の連絡先を彼に直接渡す。
賭けで勝ちたい欲に駆られて思いついた計画に期待をかけてみることにする。 このような初心者は祐希に任せ、自分は適当に才能のある部員を探せば自然とその勝利を手に入れることができるだろう。
一方、祐希はやはり書店に到着する。 彼女は同じ学校の生徒かもしれないことに漠然とした希望を抱いている。 彼はこの気持ちをどう表現すればいいのか分からず、緊張感で体が自然に震える。
彼彼は本屋で見つけた光景に目を疑わざるを得ない。 彼女が同じ席に立っていて、甚だしくは学校の制服を着ているのを見ると、とても信じられない。
「ねえ…」彼は彼女がこの前のように逃げるのではないかと慎重に近づいて挨拶をする。
「え?」彼女も音がする方に首をかしげ、一気に彼がこの前ここで会った人だということを思い出す。 道を歩いていて偶然会ったら確かに気づかなかったはずだが、実際にここで見ると彼が誰なのかはっきり思い出すことができる。 その時の記憶を書店という場所に関連させて頭の中から引き出す。
「こんにちは。私を覚えていますか?」彼はかなり前にあったことなので、ひょっとして忘れたのではないかと心配で彼女にもっと慎重に接する。
「この前ぶつかったあの人! まさにここで!」と彼女は突然大声で叫ぶ。
「覚えていますか?」びっくりするが、むしろ彼女がそのような反応を見せるのを喜んでいる。
「この学校に学生だったようですね? このような不思議な偶然が。」 彼は彼女のランドセルに付いた学校のキーホルダーを見つける。 彼女も下校途中に本屋に立ち寄ったと確信している。
「そうですね。それは私が言いたいことですね。 栞奈です。 お会いできて嬉しいです。」 彼女も興奮して先にあいさつをすることができなかった。
「はい、祐希と申します。」 彼は短くその挨拶を受け入れる。
「本が好きみたいですね。」 彼女を文芸部の一員として受け入れたいという考えがあるが、関心があるかどうかから確認しなければならない。 いきなり入ってこいと言うのは失礼に違いない。
「はい! 本当に好きです! 文を書くことにもそれなりに自信があります。 また、私の小説を必ず見せたい人がいるんですよ。」いたずらに変な自慢げに聞こえるか心配でちょっと恥ずかしくもしているが、いざ先に勧誘した人は彼なので、彼女自身がこのように大げさに騒ぐもこれといった関係がなさそうだ。
「同じ学校に通う人にこうやって会うのも大きな偶然なんですが、実はうちの文芸部で今回新入を募集しています。」 彼はその時になってようやく慎重に本当の目的を持ち出す。
「うーん… 偶然だとおっしゃいましたが、違うかもしれません。 私たちが偶然だと感じる多くの偶然は、実は偶然のように感じられるほど驚くほど劇的に当てはまる必然だと思います。 実は私もその文芸部については大体知っています。 そうでなくても興味があったので、訪ねて行こうとしました。」 彼女はその突然の申し出に驚くどころか、まるで待っていたかのように平然と応じる。 正式に入部を要請する前に、このように部員に会うのももしかしたら運命かもしれない。
「本当ですか?嬉しい話ですね。」特別な説明なしに対話が急速に進行しているようで幸いだ。 よく通じる人のようだ。
「今手に持っている本、結構好きなんですね。」 ちょうどその瞬間に彼はこの前あったことを偶然思い出して尋ねる。 彼女が憚らなければ、長年の疑問を解消する良い機会だ。
「あ…これですか? 好きです。でも僕が感じるには、 単純に好きな感情を超えて 何かもっとあると思います。 私に夢というものを植えてくれた物なんです。 ただそのようにだけ分かってほしいです。 後でまた別のところで縁があったら、お知らせします。」
「この前に本屋で持っていた本もその本ではなかったですか。」 彼女が慌てて落とした本だということを鮮明に覚えている。
「はい、そうです。 よく覚えていらっしゃいますね。 なんでまた同じものを買うんだ? という意味ですよね。」 彼女はにっこり笑いながら茶目っ気のある声で尋ねる。
「あ… 違います。 そんな意味は。」実際に彼女がそのように答えると、純粋な好奇心で言った質問に過ぎないのに、まるで何か大きな過ちでも犯したかのように申し訳なくなる。 手を振って強く否定する。
「実は、今日新しく付き合った友達にあげたんですよ。 それで新しく一つ買いに来ました。 ぼんやりしている姿を見ては到底我慢できませんでした。 読み終わって感想まで言ってくれと言ったのがちょっと強圧的だったような気もしますが、実は! 後で感想を聞く時に聞きたい言葉があったからです。 本のプレゼントに私が込めた意味を知ってほしいということで、私の真心がきちんと伝わったのか気になるのです。 本という媒体を通じて誰かに真心が伝えられるならば、これは単純な文以上の価値があると思います。」 単純に言葉で表現しにくいことを表現できる手段。 これが本という媒体の最大の魅力だと思います。 彼女も誰かの文を通じて誰かの真心を伝えてもらい、そのために他人に自分の心を伝える媒体としてこれを選んだのだと思います。
「ああ、はい。」 彼は彼女の言っていることがどういう意味なのか分からず首をかしげる。
「はい。」 彼女はやはり短く答える。
ぎこちない静寂が流れる。 沈黙は栞奈に心を打ち明けろと促すが、対話を交わす相手も、不便な雰囲気もそんな率直な夢の話には似合わない。 彼女はプレッシャーの中で中途半端に立っているよりむしろ立ち去った方がましだ。
「あ!ここでこうしていてはいけません。 やることがあるんですよ。」 突然何か急なことが思い浮かんだように手をたたいてはさっと振り向く。
「はい、大丈夫です。」 何か残念だが、もっと執拗に問い詰めても反発心だけを刺激すると思う。
彼はただ立ち去る彼女をじっと見ているだけだ。 ひとしきり嵐が吹き荒れたようにあっけらかんだ。
彼女が目の前で消えたことを確認してから何か見逃したことがあるようでじっくり振り返ってみると、本について話すのに夢中になって連絡先を交換するのを忘れた。 少し残念ではあるが、特に心配にはならない。 彼女が勝手に訪ねてくると言ったので、どうしても彼女との連絡が再び続くという信頼がある。 単純な偶然に過ぎないという考えでただ不安だったが、これが実際にまともに当てはまることを両目で確認すると、必ず続く縁という自信に変わったのだ。
初日から目的に合った人を見つけることに成功した。 少し前までは漠然としていたが、思ったよりうまくいっているようだ。
初日から目的に合った人を見つけることに成功した。 少し前までは漠然としていたが、思ったよりうまくいっているようだ。
応援ありがとうございます!
0
お気に入りに追加
0
1 / 2
この作品を読んでいる人はこんな作品も読んでいます!
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる