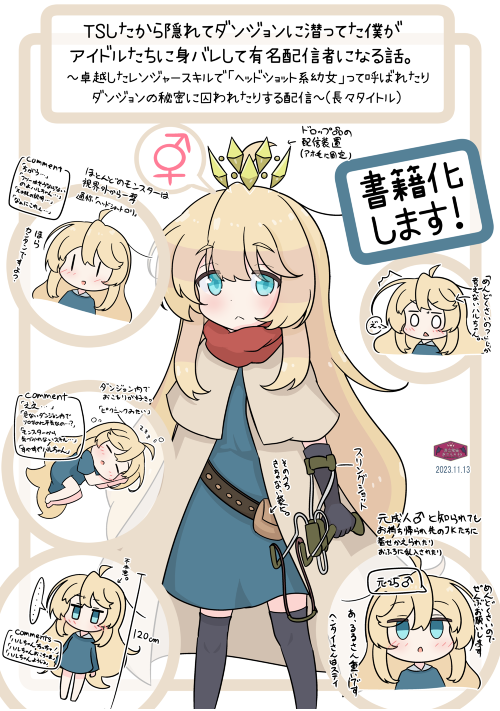38 / 90
1806年/冬
調理≪エイミー・チップ≫
しおりを挟む
射撃を繰り返していたら、朝食を食いっぱぐれてしまったどころか、もう昼食が近い。
でも、射撃の興奮が治まる、とあまりに空腹すぎて、昼食前に、少しでも何か食べたかった。
調理場のオバちゃんたちは、既に昼食の準備も終わりに近く、忙しそうだった。
それでも、憐れに思ったのか、ジャガイモをくれた。
カマドも全部使っているが、フライドポテトを揚げているので、食べたかったら、自分で芋を切れ、ということらしい。
フライドポテトも、既に素揚げだけでなく、粉をつけて揚げるバージョンが開発され、二大派閥として、ファンを二分していた。
そこに、マヨネーズ派、塩のみ派、などの小クラスタが派生している。
本当は、ケチャップとか、ウスターソースとかもあればいいのだけど、まだ発明されていないし、作り方もわからない。
あの味を再現するには、今でも高価な、スパイスが必要なんだろうな。
なんて、考えながら、ジャガイモを切る。
とにかく、早く食べたいので、薄く切って、揚げさせてもらった。
熱いうちに、塩をふって、冷ます。
手で触れるくらいになったので、手づかみし、慎重にフーフーして大口を開けた、ところで凝視するオバちゃんたちと、目が合った。
ギラギラとしたその目に、三秒は、耐えたと思う。
俺は、敗北を認め、ジャガイモを皿に戻し、彼女らに差し出した。
全員に分けるため、かなり小くされて、俺以外の口に入る。
くわっと目を見開き、一斉に、俺を睨む。
「これ、なんて料理だい?」
「い、いや、適当につくったから・・・」
前世(?)の記憶での名前、ポテトチップを言うわけにもいかない。
その後、「エイミー・チップ」の名で学園で一大ブームを起こすのだか、今現在、俺の腹は悲しげに鳴っていた。
教師ローザ・ロッテルーノは、「エイミー・チップ」を食べるために、忙しく口を動かしながら、呟いた。
「また、エイミー?」
素揚げ、粉つき、薄揚げ、と三大勢力に分かれた芋揚げのファンは、オバちゃんたちも巻き込み、新作が考えられ、試食されていた。
結果、服のサイズが合わなくなる子が増え、マヨネーズ・クラスタは、急速に勢力を失っていった。
でも、射撃の興奮が治まる、とあまりに空腹すぎて、昼食前に、少しでも何か食べたかった。
調理場のオバちゃんたちは、既に昼食の準備も終わりに近く、忙しそうだった。
それでも、憐れに思ったのか、ジャガイモをくれた。
カマドも全部使っているが、フライドポテトを揚げているので、食べたかったら、自分で芋を切れ、ということらしい。
フライドポテトも、既に素揚げだけでなく、粉をつけて揚げるバージョンが開発され、二大派閥として、ファンを二分していた。
そこに、マヨネーズ派、塩のみ派、などの小クラスタが派生している。
本当は、ケチャップとか、ウスターソースとかもあればいいのだけど、まだ発明されていないし、作り方もわからない。
あの味を再現するには、今でも高価な、スパイスが必要なんだろうな。
なんて、考えながら、ジャガイモを切る。
とにかく、早く食べたいので、薄く切って、揚げさせてもらった。
熱いうちに、塩をふって、冷ます。
手で触れるくらいになったので、手づかみし、慎重にフーフーして大口を開けた、ところで凝視するオバちゃんたちと、目が合った。
ギラギラとしたその目に、三秒は、耐えたと思う。
俺は、敗北を認め、ジャガイモを皿に戻し、彼女らに差し出した。
全員に分けるため、かなり小くされて、俺以外の口に入る。
くわっと目を見開き、一斉に、俺を睨む。
「これ、なんて料理だい?」
「い、いや、適当につくったから・・・」
前世(?)の記憶での名前、ポテトチップを言うわけにもいかない。
その後、「エイミー・チップ」の名で学園で一大ブームを起こすのだか、今現在、俺の腹は悲しげに鳴っていた。
教師ローザ・ロッテルーノは、「エイミー・チップ」を食べるために、忙しく口を動かしながら、呟いた。
「また、エイミー?」
素揚げ、粉つき、薄揚げ、と三大勢力に分かれた芋揚げのファンは、オバちゃんたちも巻き込み、新作が考えられ、試食されていた。
結果、服のサイズが合わなくなる子が増え、マヨネーズ・クラスタは、急速に勢力を失っていった。
応援ありがとうございます!
0
お気に入りに追加
236
1 / 3
この作品を読んでいる人はこんな作品も読んでいます!
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる