22 / 35
第21章 望遠鏡の君
しおりを挟む
温室から戻ってくると、宮殿で三人に与えられた部屋には誰もいませんでした。温室で手に入れた吐出草のことを早く二人に伝えたかったのに、リンもフラッフィも一向に姿を現しません。せっかちな人みたいに、エレンは部屋の中を行ったり来たりしました。
夜になってまもなく、リンは女の子から逃げるように戻ってきました。しかしフラッフィは深夜になっても帰ってきません。エレンは三人揃ったところで報告したかったので、一緒にフラッフィを探しにいこうと何度か提案しましたが、そのうち帰ってくるよと言って、リンはなかなか腰を上げようとしません。それどころか、エレンとの気まずい雰囲気に耐えられなくなったのか、しばらくすると、リンは何も言わずに部屋を出て行ってしまいました。
「リンの薄情者!」
フラッフィを探して、広い城の中を歩いていたエレンは、苛々しているばっかりに、お城の奥まで来ていました。ここは王様の部屋だから近づかないように、と侍従に言われていた場所だったのに。エレンは踵を返そうとして、何かを踏んづけたことに気がつきました。それはレースを何枚も重ねた襞襟でした。
フラッフィもこんなのをつけていたっけと思い出して、エレンははっとしました。こんな細い首の持ち主が、フラッフィ以外にいるでしょうか。襞襟をつけている人はごまんといましたが、こんなに短い輪では、赤ちゃんだって首が入りません。エレンは襞襟を握りしめると、そっと王様の部屋に続く階段を登りはじめました。
最上階には王様の居室に通じる長い廊下と、さらに高い塔に繋がる螺旋階段がありました。エレンはどちらに行くべきかまるで検討がつきませんでしたが、王様の部屋の前には、こっくりしてはいるものの、兵隊が二人ついていたので、とりあえず行けるところまで螺旋階段を登ってみることにしました。
おそるおそる暗い螺旋階段を登っていくと、上の方から幼い女の子の声が聞こえてきました。
「どうして私の言うことが聞けないの」
「早く放してよ。僕は友達と旅をしないといけないんだ」
聞き覚えのある声に、エレンは思わず目で確認せずにはいられませんでした。
細く開いた扉の奥に、リボンで椅子に縛り付けられたフラッフィと、ラズベリー色の髪をした女の子の後ろ姿があります。
「友達? そんなの忘れなさいよ。これからあなたの友達は私だけなんだから」
髪の毛の豊かな女の子がヒステリックにこう言ったので、エレンはなんとなく事情が分かりました。友達のいないこの子は、きっとどこかでフラッフィを見初め、誘拐したのです。そしてエレンの勘が外れていなければ、この女の子はおそらくこの国の王女さまです。だって王様に一番近くて、しかも王様より奥の安全な部屋にいる子どもです。王様が溺愛する娘以外の誰がそんなところに住めるでしょう。
「頭のいいくまさん、分かったら親友の誓いをしましょう」
そういって王女は小さな銀のナイフを取り出しました。その切っ先は、暗い部屋にありながら、ロウソクの光を拾ってきらりと光っています。
「お互い以外と遊んだら、いまから流す血が流れきるまで後悔するの。ロマンチックでしょう」
「嫌だいやだ! そんなので切らないで」
フラッフィはばたばた暴れましたが、身体を縛っているリボンがかえって食い込んだだけでした。
「どうせ逃げられないんだから大人しくしていて。大丈夫、ちょっとチクッとするだけよ」
女の子はフラッフィの腕を押さえつけると、ナイフを握り直しました。
「やめろ! そんなの友達じゃない!」
エレンは咄嗟に部屋へ躍り出ました。しかし王女はナイフを取り落としただけで、フラッフィを素早く抱きかかえると、一目散に逃げ出しました。
王女があまりに素早く身を眩ましたので、エレンは危うく二人を見失いそうになりました。しかし王女が倒した真鍮の望遠鏡がカランと音を立てたので、エレンは秘密の階段を見つけることができました。
「あの子、フラッフィを監視していたんだ」
望遠鏡を拾い上げると、エレンは先を急ぎました。
翻る王女の長い髪を追って、エレンが入り込んだのは衣装部屋。そこは男の子のエレンですら息を飲むような煌びやかな空間で、絹をふんだんに使った贅沢なドレスや、繊細な刺繍の施されたレースのガウン、それにいかにも珍しい毛皮でできた美しいコートがこれでもかと並んでいます。天井から吊るされた服はどれも、自分が一番美しいと思い込んでいるような高飛車な佇まいでしたが、実際どれも甲乙付け難い麗しさ。なので、一様にそのプライドと長い裾を痛ませないように丁重に保管されているのでした。
数多あるドレスの中に、ひとつだけ白いドレスがあることに、エレンは気がつきました。それは他のものに比べるとデザインが古く、装飾もあまりされていないのですが、だからこそ保っていられる普遍的な美しさがきらりと光るドレスで、お姫様が着るには少し大きすぎるように思われました。
燦然と輝く純白のドレスに、エレンが手を触れようとしたその瞬間、何かがしゃらしゃら鳴りました。見れば、向こうの方にあるスワロフスキーのローブが微かに揺れています。エレンはお姫様を追っていたことを思い出して、そちらへ急ぎました。しかし幾重にも重なったカーテンのようなドレスたちが道を阻み、エレンを弄ぶのでした。
重たく纏わりついてくるドレスのトンネルを抜けると、そこは鏡が張り巡らされた試着室のようなところでした。色々な大きさや歪み方をする虚像のエレンが、あっちからもこっちからも本物のエレンを見ています。
遊園地で行ったミラーハウスみたい。エレンはいつもみたいに誰かと遭遇しないかしらと思いました。でも本当に誰かが来たらそれはそれでこわいかもしれないな。
エレンがそんなことを考えていると、ある鏡に王女の横顔が映りました。エレンがそちらへ向かって走り出した次の瞬間、エレンは誰かとぶつかってひっくり返りました。
「エレン!」
ぶつかった人物が、エレンを助け起こしました。
「会えてよかったよ。ここは一人でいるには不気味なところなんだもの」
それはこわくもなんともないリンでした。
「リン! どうしてここが分かったの?」
エレンが聞くと、リンは王様に聞いてやってきたのだと言いました。
「キルステン姫がフラッフィをつれて立てこもっているんだって?」
「あの子、キルステンていうんだ。さっきすぐそこにいたの、リンは見なかった?」
「いや。でもまだそう遠くには行っていないはずさ」
そういうとリンはずんずん進みはじめました。
次に二人が迷いこんだのは、人形で埋め尽くされた子ども部屋。ここにはありとあらゆる種類の人形があって、フラッフィのような動物をかたどったものや、人間そっくりの小さな着せ替え人形、それに横にすると目を閉じる不気味なものもありました。しかしどれも遊んだら遊びっぱなしに置かれていて、まるで人形の墓場です。
壁も天井も床も、出口すら見えないこの部屋で、無数の目が二人を見つめています。エレンはラッセが話していた、何度捨てても戻ってくる人形のことを思い出して、ぞくりとしました。と、どこかからエレンたちをあざ笑う女の子の声が響き渡りました。
「お探しのものは見つかったかしら」
キルステン姫です。王女は二人を挑発しているのです。二人はムキになって、人形の山を無我夢中で探しました。しかし、掘り起こしても掘り起こしても人形が降って湧いてくるので、エレンはだんだん自分もここの人形の一体になったのではないかと思いました。しかしそのとき、レネに似た猫のぬいぐるみと目が合って、エレンはどきりとしました。
「エレン、大丈夫か」
自分を覗き込んでいるのが生きた人間の目だと分かると、エレンは小さく頷いて立ち上がりました。
悪夢のような部屋から抜け出して、今度二人の前に立ちはだかったのは、広大無辺の緑の迷路でした。外の空気を吸った瞬間、エレンは部屋の中よりずっといいと思いました。しかしこの果てしない迷路をすすむとなると話は別です。エレンはなんとか外側からまわり込めないかときょろきょろしましたが、壁は永遠左右に伸びていて、目の前の入り口以外に通れそうなところはありません。しかしリンはなんともけろっとしています。
「リンは平気なの。こんなところに入り込んだら今度こそ迷子になっちゃうよ」
「まさか!」
リンはいかにもおかしそうに笑うと、緑の壁に手を突っ込みました。
何本かの尊い犠牲を払って這い上ると、リンはエレンに手を差し出しました。なんとリンは迷路の上をすすむつもりのようでした。エレンはなんだか府に落ちませんでしたが、リンはむしろ自分の狡猾さを誇りに思っているような節さえあります。
「君って本当にいつでも真っ向勝負なんだから。自分から迷い込むなんて愚の骨頂!」
エレンを垣根の上に引っぱり上げると、リンは手で庇を作って、遠くを見やりました。
「本当は輪郭を行けば確かなんだけど、この迷路は大きすぎる。適当に最短ルートを通ろう」
早速手近なブロックに目星をつけると、リンはひょいと飛び移りました。
苦々しいことに、二人はあっという間にゴールにたどり着きました。リンなんてとっくに垣根から飛び降りて、次の目的地に向かって、すたすた歩いています。エレンはがさがさ音を立てながら、なんとか地面に降りると、小走りにリンを追いました。
植物を模した装飾的な門扉をくぐると、そこは甘美な香り漂う薔薇園でした。普段お母さんがつけている薔薇の香水はあまり好きではありませんが、ここのさっぱりとした、けれど気品ある香りを、エレンは気に入りました。
「プリンセス・キルステン」
足元に置かれたキャンドルを見ていたリンが呟きました。そういえば薔薇を照らしているのは、月明かりを邪魔しない程度の謙虚なライティングだけでしたっけ。
「この薔薇、王様が大金をかけて開発させたんだと」
そう言うとリンは、なにか物思いに沈んだ様子でじっと薔薇を見つめました。
「僕、あっちを見てみる」
センチメンタルになったリンを置いて、エレンはひとり先を急ぎました。
薔薇を見て自分の運命を悲観したのか、はたまた自分と同じく王様の子どもである王女に何か思うところがあったのかもしれませんが、ブルーになったリンに付き合うほど、エレンはお人好しではありません。なんていったって妹の大親友で、いまはエレンの大切な友達でもあるフラッフィが、いまこの瞬間も拘束されているのです。
特に当てもありませんでしたが、エレンは黙々と歩きました。すると歩き出してまもなく、エレンは暗い庭の中に、ほんのりと明るい場所があることに気がつきました。
そこは色とりどりの紙ランタンに照らされた、小さなガーデンパーティの会場でした。綺麗な小花柄のクロスをひいた長いテーブルのまわりには、どれ一つとして同じもののない木の椅子が並び、花を浮かべたガラスの器の横には、まだ湯気の出ているティーカップや食べかけのお菓子が並んでいます。つい先ほどまで誰かがいたのです。
エレンがあたりを見回すと、ちょうど小さな梯子が木の上にするする消えていくところでした。
王女が潜伏していたのは、ツリーハウスならぬ、木の上に作られた小さな白いテントでした。テントがあるのはそんなに高いところではありませんでしたが、エレンでは届きそうにありません。エレンはリンがいたらいいのにと思いましたが、こういうときにいないのがリンなのです。エレンは仕方なく木の上のお姫様に呼びかけました。
「キルステン姫。あなたとお話したいんだけど」
エレンは誘拐犯に屈したくありませんでしたが、人質をとられているので、不本意ながら丁寧に話ました。しかし王女はいままでずっとそうだったことが一瞬で分かる、威圧的な物言いをしました。
「あなた、誰よ」
本当は殴り込んでやりたいところでしたが、エレンはぐっと堪えました。
「僕はその子の友達だ。早くフラッフィを放して」
「嫌よ。この子は私のものなんだから。衛兵を呼ぶ前にとっとお帰りなさい。いま引き下がればこのことは不問にしてあげるわ」
なんという傲慢さ! エレンだって負けていられません。
「本当の友達なら、友達が喜ぶことをするべきだ。君がやっているのは友達の心を失うことだし、こんなもので監視しておいて友達になんてなれるもんか!」
エレンが望遠鏡を振りかざすと、フラッフィはいいぞ、と声援を送りました。
「友達友達、うるさいわね! あなたには他にも友達がいるでしょう。私にはこの子しかいないの。一人くらい譲ってくれてもいいじゃない!」
「友達は一人だけにする必要ない。フラッフィの友達には、君も僕もなれる。それに君の友達にだって僕はなれる。みんながみんなの友達になれるんだ」
すると王女は食い気味に言いました。
「嘘よ。みんな私をのけ者にするんだわ。これまでだってそうだった。私はいつも独りぼっち」
エレンは事情が分かりませんでしたから、それはいい友達でなかったんだと言いました。
「いいえ、みんないい子だったわ。でも私がみんなと違うから、友達でいられなくなるの」
「・・・身分が違うから?」
できるだけ想像を巡らせて、エレンは言ってみました。けれど、返ってきたのは思わぬ答えでした。
「私には呪いがかけられているの」
どこかで聞いたことがある理由です。しかしどんな理由があるにせよ、フラッフィを虜にする理由にはなりません。
「僕もフラッフィも気にしないけど、君がそんなに気にするなら一緒に呪いを解こうよ」
エレンは密かに祈りました。今度は聞いたことのない方法でありますように!
「あなたのような子どもでは無理よ。王子様の真実の愛のキスしか、呪いを解けないんだから」
王女の告白は、エレンが一番おそれていたことでした。しかももっと悪いことに、エレンのすぐうしろにはいつからかリンがいたのです。一体いつの間に来たのでしょう。
リンはしばらく黙ったまま、テーブルの上にあった林檎を弄んでいましたが、やがて意を決したように、テントのある木の幹に手をかけました。
「だめだ! それは王女様じゃなくて自分のためなんだろう? そんなことをしたら王女様は・・・」
エレンは慌てて、リンを引き止めました。しかしリンは首を横に振って、大丈夫だからとでもいうように唇に指を押し当てると、ひょいと木に登ってしまいました。
「王女様、あなたの呪いを解きにきました。お願いですからその美しい顔をお見せ下さい」
テントの前にひざまずいたリンは甘い言葉を囁きました。しかし王女はしのごの言うばかりで、なかなか姿を見せようとしません。
「あぁ、もうじれったい」
痺れを切らしたリンは、とうとうテントに入ってしまいました。王女の悲鳴がして、エレンは王女に逃げるよう伝えるべく、大きく息を吸いにかかりました。しかし次の瞬間、フラッフィを抱いたリンが出てきたので、エレンはほっとして、へなへなとその場に座り込みました。
フラッフィをエレンに託すと、リンは自分も木から下りようと太い幹に手をかけました。しかしふと手をとめると、テントの中の王女様に、一緒に帰ろうと声を掛けました。すると王女はすんすん泣きながら言いました。
「どうして私にキスしてくれなかったの」
リンはちょっと目をぱちくりさせましたが、やがてお子様だったから、と言いました。
エレンにはリンの真意が分かりませんでした。リンは本当にフラッフィをたすけるために、あのくさいセリフで王女を油断させたのでしょうか。それとも実は、自分の呪いを解くために王女に近づいたのではないでしょうか。実際顔を見たら運命を感じなかった―ただ単に好みでなかった―ので、キスをしなかったということも考えられます。だとしたら、それをストレートに言わなかったのは、せめてものリンの優しさです。突き詰めれば、相手の死を意味するキスをしないことが、最大の優しさなのですが。
「たった一回キスしてくれれば、その問題は解決するのに。それならどうしてお父様に会いに行ったりしたの。私との結婚を許してもらうためじゃないの」
キルステン王女はむすっとしました。
「たしかに僕はお伺いに行ったさ。しかしそれは別の交渉のためだ。けれど王様は逆に、僕に交渉をしたんだ。娘の呪いを解いてくれたら、何でも願いを叶えようと」
リンは大きくひとつ溜息をつくと、テントの奥でごねていた王女を抱きかかえて木から飛び降りました。王女は、声から想像していたよりずっと幼い、七、八歳の少女でした。
「まさかこんなチンチクリンにキスしなきゃいけないなんて思わなかったんだよ。美人ならしてもいいかなと思ったけど」
王女に頬を打たれながらも、リンがなにか吹っ切れたように、あっけらかんとこう言ったので、エレンはがっかりしました。やっぱりリンはフラッフィを救出するためではなく、自分の呪いを解くためにお姫様に近づいたのです。顔を見たら子どもだったので、死なせるのが可哀想になってやめたというのなら、さっきの発言も救いようがあります。しかしそんなことを考えるほど、リンに思いやりがあるとは思えません。ただ王女がタイプでなかった、と彼ははっきり言いましたもの。
「それで、君にかけられたのはどういう呪いなの」
リンがこう尋ねると、その質問にはわんわん泣いている王女ではなく、フラッフィが答えました。なんでも王女は、本当は十六歳なのですが、あるときから成長がとまり、しかもそのときどきによって体の大きさが変わるというのです。
「朝は十歳なのに、昼は生まれたての赤ちゃん、夜には五歳になったりするの。これじゃお友達との関係もうまくいかないでしょう」
リンの腕から下りたお姫様が、悲劇のヒロインにどっぷり浸りながらこう言うと、たしかに体は一回り小さくなりました。
「本人は法則がないと主張しているけど、僕が観察した限り、精神年齢に応じた姿になっているね。その証拠にティーン以上になることはない」
フラッフィが皮肉ると、さっきまで目を潤ませていたお姫様は、目を三角にしてフラッフィを睨みました。
「ははぁ。それでやけくそになって、誘拐したフラッフィと空しいガーデンパーティをしてたんだ」
先ほど王女がフラッフィに突きつけていた銀のナイフを拾ったリンは、刃が折り畳まれている枝の部分の彫り物を物珍しそうに眺めながら、こう言いました。しかし王女は本当に傷ついた顔をしました。
「それは本当のガーデンパーティに出られなかったからよ。お父様は、私を塔の外に出してくれないの。私を恥じているんだわ」
リンが弄んでいた折りたたみナイフを取り落としそうになったとき、王女が少し大きくなったのがエレンには分かりました。どうやらフラッフィの予想が当たっているようです。
「ねぇ。こういう風になったのはいつから? 何かきっかけがあったの」
エレンが尋ねると、王女が口を開く前に、別の人物が取ってかわりました。それは娘が心配で見に来た王様でした。
「これはこの子の母親が亡くなってからだ。王妃は亡くなる直前まで、娘のことを気にしていてね。口を開けば、こんなにわがままなまま大人になって平気なのかしら、と呟いていた。そしてあれがいよいよ最期というとき、自分が嫁入りのときに着てきたドレスを持ってこさせてこう言ったのだ。あの子がこのままこのドレスに袖を通すくらいなら、いっそのこと子どものままでいますように、と」
王様は滲んだ涙を拭いました。
エレンはあの純白のドレスのことを思い出しました。あれだけ王妃のものだったから、他のドレスより古めかしく、サイズが大きかったのでしょう。
「王女様が実年齢に合った精神の持ち主になれば、そもそもキスなんて必要ないんじゃないですか」
例のナイフで林檎の皮を剥いていたリンは、自分の不履行を責められないよう、予防線を張りました。
「この子の部屋を見ただろう。あんなに沢山の洋服やおもちゃを与える親がどこにいる? 王様はお姫様に甘々なのさ。お姫様のご機嫌をとるためなら、僕を見殺しにするくらい」
フラッフィは鼻をフンと鳴らしました。エレンもこれには賛成しました。
「王様。失礼ですけど、子育ての仕方を考えた方がいいと思います。本当に王女様のことを考えるなら、叱ったり、我慢させたりすることが必要なんです。きっと」
エレンがこう進言すると、一番年下のくせにしっかりしているなとリンは感心しました。
「薄々は分かっていたのだ。しかしいざ娘の顔を見ると・・・王妃の最期の願いだというのに情けない。しかしここはひとつ、これほど親身になってくれた諸君に、娘のことを頼めないだろうか。私だとどうしても厳しくできないから」
王様の発言に一同は動揺しました。だってフラッフィは王女に誘拐された被害者だし、リンは王女を振った男で、ともすると王女を死に追いやる要注意人物なのです。それにエレンは通りがかりのただの男の子です。
「先ほどは身に過ぎたことを言いましたけど、僕たちは最適でないと思います。僕は猫を探し出して石を吐き出させなければなりませんし。王女さまのお相手などとても」
エレンは必死に御託を並べました。もちろんリンとフラッフィもそれぞれの理由をできるだけあげて、いかに自分たちがふさわしくないかを全力でプレゼンテーションしました。しかし王様にはまったく響いていないらしく、「またまたご謙遜を」と一蹴されただけでした。
エレンたちと王様が終わりなき攻防をいつまでも続いていると、先ほどから王様に何か言いたそうにしていた衛兵が、ついに空咳をしました。すると王様はやっと気がついて、きれいにセットされた髪をちょっと跳ねさせると、何かあったかと尋ねました。
「はい、王様。例の猫が北極へ行く流氷観光船に乗り込んだとの情報が複数入りました」
「流氷観光船? 次の船はいつ出るんですか」
エレンが逸る気持ちを抑えて尋ねると、王様は首を横に振りました。
「急ぎ余の砕氷船の準備をさせよう。あれなら観光船より速いから追いつけるかもしれん」
エレンは思わずフラッフィの手をとって飛び上がりました。王様はなんて太っ腹なのでしょう。しかし喜んだのも束の間、それは修理中です、と衛兵が言ったので、エレンは文字通りがっくり肩を落としました。
「それなら私の飛行船を出しましょう。あれならいますぐにだって出発できるもの」
キルステンがこう提案すると、王様はさすが我が娘と叫びました。しかし飛行船を出すということは、エレンたちが王女を預かるということです。まさかあなたの飛行船は借りるけれど、あなたは仲間はずれにしますなんて言えないじゃないですか。
エレンたちを察した王様はおおらかにこう言いました。
「そんなに気負う必要はない。ただ友人として、この子と時間を過ごしてくれんかね。ちょうど北極はオーロラのシーズンだから、一緒に眺めてやるだけでいい。それにこの子にはこの国の代表として恥ずかしくないよう、北極のことを勉強させてある。きっと役に立つがね」
王様にここまで言われては断ることはできません。エレンは年貢の納め時というのはこういうことを言うのだなと思いました。
夜になってまもなく、リンは女の子から逃げるように戻ってきました。しかしフラッフィは深夜になっても帰ってきません。エレンは三人揃ったところで報告したかったので、一緒にフラッフィを探しにいこうと何度か提案しましたが、そのうち帰ってくるよと言って、リンはなかなか腰を上げようとしません。それどころか、エレンとの気まずい雰囲気に耐えられなくなったのか、しばらくすると、リンは何も言わずに部屋を出て行ってしまいました。
「リンの薄情者!」
フラッフィを探して、広い城の中を歩いていたエレンは、苛々しているばっかりに、お城の奥まで来ていました。ここは王様の部屋だから近づかないように、と侍従に言われていた場所だったのに。エレンは踵を返そうとして、何かを踏んづけたことに気がつきました。それはレースを何枚も重ねた襞襟でした。
フラッフィもこんなのをつけていたっけと思い出して、エレンははっとしました。こんな細い首の持ち主が、フラッフィ以外にいるでしょうか。襞襟をつけている人はごまんといましたが、こんなに短い輪では、赤ちゃんだって首が入りません。エレンは襞襟を握りしめると、そっと王様の部屋に続く階段を登りはじめました。
最上階には王様の居室に通じる長い廊下と、さらに高い塔に繋がる螺旋階段がありました。エレンはどちらに行くべきかまるで検討がつきませんでしたが、王様の部屋の前には、こっくりしてはいるものの、兵隊が二人ついていたので、とりあえず行けるところまで螺旋階段を登ってみることにしました。
おそるおそる暗い螺旋階段を登っていくと、上の方から幼い女の子の声が聞こえてきました。
「どうして私の言うことが聞けないの」
「早く放してよ。僕は友達と旅をしないといけないんだ」
聞き覚えのある声に、エレンは思わず目で確認せずにはいられませんでした。
細く開いた扉の奥に、リボンで椅子に縛り付けられたフラッフィと、ラズベリー色の髪をした女の子の後ろ姿があります。
「友達? そんなの忘れなさいよ。これからあなたの友達は私だけなんだから」
髪の毛の豊かな女の子がヒステリックにこう言ったので、エレンはなんとなく事情が分かりました。友達のいないこの子は、きっとどこかでフラッフィを見初め、誘拐したのです。そしてエレンの勘が外れていなければ、この女の子はおそらくこの国の王女さまです。だって王様に一番近くて、しかも王様より奥の安全な部屋にいる子どもです。王様が溺愛する娘以外の誰がそんなところに住めるでしょう。
「頭のいいくまさん、分かったら親友の誓いをしましょう」
そういって王女は小さな銀のナイフを取り出しました。その切っ先は、暗い部屋にありながら、ロウソクの光を拾ってきらりと光っています。
「お互い以外と遊んだら、いまから流す血が流れきるまで後悔するの。ロマンチックでしょう」
「嫌だいやだ! そんなので切らないで」
フラッフィはばたばた暴れましたが、身体を縛っているリボンがかえって食い込んだだけでした。
「どうせ逃げられないんだから大人しくしていて。大丈夫、ちょっとチクッとするだけよ」
女の子はフラッフィの腕を押さえつけると、ナイフを握り直しました。
「やめろ! そんなの友達じゃない!」
エレンは咄嗟に部屋へ躍り出ました。しかし王女はナイフを取り落としただけで、フラッフィを素早く抱きかかえると、一目散に逃げ出しました。
王女があまりに素早く身を眩ましたので、エレンは危うく二人を見失いそうになりました。しかし王女が倒した真鍮の望遠鏡がカランと音を立てたので、エレンは秘密の階段を見つけることができました。
「あの子、フラッフィを監視していたんだ」
望遠鏡を拾い上げると、エレンは先を急ぎました。
翻る王女の長い髪を追って、エレンが入り込んだのは衣装部屋。そこは男の子のエレンですら息を飲むような煌びやかな空間で、絹をふんだんに使った贅沢なドレスや、繊細な刺繍の施されたレースのガウン、それにいかにも珍しい毛皮でできた美しいコートがこれでもかと並んでいます。天井から吊るされた服はどれも、自分が一番美しいと思い込んでいるような高飛車な佇まいでしたが、実際どれも甲乙付け難い麗しさ。なので、一様にそのプライドと長い裾を痛ませないように丁重に保管されているのでした。
数多あるドレスの中に、ひとつだけ白いドレスがあることに、エレンは気がつきました。それは他のものに比べるとデザインが古く、装飾もあまりされていないのですが、だからこそ保っていられる普遍的な美しさがきらりと光るドレスで、お姫様が着るには少し大きすぎるように思われました。
燦然と輝く純白のドレスに、エレンが手を触れようとしたその瞬間、何かがしゃらしゃら鳴りました。見れば、向こうの方にあるスワロフスキーのローブが微かに揺れています。エレンはお姫様を追っていたことを思い出して、そちらへ急ぎました。しかし幾重にも重なったカーテンのようなドレスたちが道を阻み、エレンを弄ぶのでした。
重たく纏わりついてくるドレスのトンネルを抜けると、そこは鏡が張り巡らされた試着室のようなところでした。色々な大きさや歪み方をする虚像のエレンが、あっちからもこっちからも本物のエレンを見ています。
遊園地で行ったミラーハウスみたい。エレンはいつもみたいに誰かと遭遇しないかしらと思いました。でも本当に誰かが来たらそれはそれでこわいかもしれないな。
エレンがそんなことを考えていると、ある鏡に王女の横顔が映りました。エレンがそちらへ向かって走り出した次の瞬間、エレンは誰かとぶつかってひっくり返りました。
「エレン!」
ぶつかった人物が、エレンを助け起こしました。
「会えてよかったよ。ここは一人でいるには不気味なところなんだもの」
それはこわくもなんともないリンでした。
「リン! どうしてここが分かったの?」
エレンが聞くと、リンは王様に聞いてやってきたのだと言いました。
「キルステン姫がフラッフィをつれて立てこもっているんだって?」
「あの子、キルステンていうんだ。さっきすぐそこにいたの、リンは見なかった?」
「いや。でもまだそう遠くには行っていないはずさ」
そういうとリンはずんずん進みはじめました。
次に二人が迷いこんだのは、人形で埋め尽くされた子ども部屋。ここにはありとあらゆる種類の人形があって、フラッフィのような動物をかたどったものや、人間そっくりの小さな着せ替え人形、それに横にすると目を閉じる不気味なものもありました。しかしどれも遊んだら遊びっぱなしに置かれていて、まるで人形の墓場です。
壁も天井も床も、出口すら見えないこの部屋で、無数の目が二人を見つめています。エレンはラッセが話していた、何度捨てても戻ってくる人形のことを思い出して、ぞくりとしました。と、どこかからエレンたちをあざ笑う女の子の声が響き渡りました。
「お探しのものは見つかったかしら」
キルステン姫です。王女は二人を挑発しているのです。二人はムキになって、人形の山を無我夢中で探しました。しかし、掘り起こしても掘り起こしても人形が降って湧いてくるので、エレンはだんだん自分もここの人形の一体になったのではないかと思いました。しかしそのとき、レネに似た猫のぬいぐるみと目が合って、エレンはどきりとしました。
「エレン、大丈夫か」
自分を覗き込んでいるのが生きた人間の目だと分かると、エレンは小さく頷いて立ち上がりました。
悪夢のような部屋から抜け出して、今度二人の前に立ちはだかったのは、広大無辺の緑の迷路でした。外の空気を吸った瞬間、エレンは部屋の中よりずっといいと思いました。しかしこの果てしない迷路をすすむとなると話は別です。エレンはなんとか外側からまわり込めないかときょろきょろしましたが、壁は永遠左右に伸びていて、目の前の入り口以外に通れそうなところはありません。しかしリンはなんともけろっとしています。
「リンは平気なの。こんなところに入り込んだら今度こそ迷子になっちゃうよ」
「まさか!」
リンはいかにもおかしそうに笑うと、緑の壁に手を突っ込みました。
何本かの尊い犠牲を払って這い上ると、リンはエレンに手を差し出しました。なんとリンは迷路の上をすすむつもりのようでした。エレンはなんだか府に落ちませんでしたが、リンはむしろ自分の狡猾さを誇りに思っているような節さえあります。
「君って本当にいつでも真っ向勝負なんだから。自分から迷い込むなんて愚の骨頂!」
エレンを垣根の上に引っぱり上げると、リンは手で庇を作って、遠くを見やりました。
「本当は輪郭を行けば確かなんだけど、この迷路は大きすぎる。適当に最短ルートを通ろう」
早速手近なブロックに目星をつけると、リンはひょいと飛び移りました。
苦々しいことに、二人はあっという間にゴールにたどり着きました。リンなんてとっくに垣根から飛び降りて、次の目的地に向かって、すたすた歩いています。エレンはがさがさ音を立てながら、なんとか地面に降りると、小走りにリンを追いました。
植物を模した装飾的な門扉をくぐると、そこは甘美な香り漂う薔薇園でした。普段お母さんがつけている薔薇の香水はあまり好きではありませんが、ここのさっぱりとした、けれど気品ある香りを、エレンは気に入りました。
「プリンセス・キルステン」
足元に置かれたキャンドルを見ていたリンが呟きました。そういえば薔薇を照らしているのは、月明かりを邪魔しない程度の謙虚なライティングだけでしたっけ。
「この薔薇、王様が大金をかけて開発させたんだと」
そう言うとリンは、なにか物思いに沈んだ様子でじっと薔薇を見つめました。
「僕、あっちを見てみる」
センチメンタルになったリンを置いて、エレンはひとり先を急ぎました。
薔薇を見て自分の運命を悲観したのか、はたまた自分と同じく王様の子どもである王女に何か思うところがあったのかもしれませんが、ブルーになったリンに付き合うほど、エレンはお人好しではありません。なんていったって妹の大親友で、いまはエレンの大切な友達でもあるフラッフィが、いまこの瞬間も拘束されているのです。
特に当てもありませんでしたが、エレンは黙々と歩きました。すると歩き出してまもなく、エレンは暗い庭の中に、ほんのりと明るい場所があることに気がつきました。
そこは色とりどりの紙ランタンに照らされた、小さなガーデンパーティの会場でした。綺麗な小花柄のクロスをひいた長いテーブルのまわりには、どれ一つとして同じもののない木の椅子が並び、花を浮かべたガラスの器の横には、まだ湯気の出ているティーカップや食べかけのお菓子が並んでいます。つい先ほどまで誰かがいたのです。
エレンがあたりを見回すと、ちょうど小さな梯子が木の上にするする消えていくところでした。
王女が潜伏していたのは、ツリーハウスならぬ、木の上に作られた小さな白いテントでした。テントがあるのはそんなに高いところではありませんでしたが、エレンでは届きそうにありません。エレンはリンがいたらいいのにと思いましたが、こういうときにいないのがリンなのです。エレンは仕方なく木の上のお姫様に呼びかけました。
「キルステン姫。あなたとお話したいんだけど」
エレンは誘拐犯に屈したくありませんでしたが、人質をとられているので、不本意ながら丁寧に話ました。しかし王女はいままでずっとそうだったことが一瞬で分かる、威圧的な物言いをしました。
「あなた、誰よ」
本当は殴り込んでやりたいところでしたが、エレンはぐっと堪えました。
「僕はその子の友達だ。早くフラッフィを放して」
「嫌よ。この子は私のものなんだから。衛兵を呼ぶ前にとっとお帰りなさい。いま引き下がればこのことは不問にしてあげるわ」
なんという傲慢さ! エレンだって負けていられません。
「本当の友達なら、友達が喜ぶことをするべきだ。君がやっているのは友達の心を失うことだし、こんなもので監視しておいて友達になんてなれるもんか!」
エレンが望遠鏡を振りかざすと、フラッフィはいいぞ、と声援を送りました。
「友達友達、うるさいわね! あなたには他にも友達がいるでしょう。私にはこの子しかいないの。一人くらい譲ってくれてもいいじゃない!」
「友達は一人だけにする必要ない。フラッフィの友達には、君も僕もなれる。それに君の友達にだって僕はなれる。みんながみんなの友達になれるんだ」
すると王女は食い気味に言いました。
「嘘よ。みんな私をのけ者にするんだわ。これまでだってそうだった。私はいつも独りぼっち」
エレンは事情が分かりませんでしたから、それはいい友達でなかったんだと言いました。
「いいえ、みんないい子だったわ。でも私がみんなと違うから、友達でいられなくなるの」
「・・・身分が違うから?」
できるだけ想像を巡らせて、エレンは言ってみました。けれど、返ってきたのは思わぬ答えでした。
「私には呪いがかけられているの」
どこかで聞いたことがある理由です。しかしどんな理由があるにせよ、フラッフィを虜にする理由にはなりません。
「僕もフラッフィも気にしないけど、君がそんなに気にするなら一緒に呪いを解こうよ」
エレンは密かに祈りました。今度は聞いたことのない方法でありますように!
「あなたのような子どもでは無理よ。王子様の真実の愛のキスしか、呪いを解けないんだから」
王女の告白は、エレンが一番おそれていたことでした。しかももっと悪いことに、エレンのすぐうしろにはいつからかリンがいたのです。一体いつの間に来たのでしょう。
リンはしばらく黙ったまま、テーブルの上にあった林檎を弄んでいましたが、やがて意を決したように、テントのある木の幹に手をかけました。
「だめだ! それは王女様じゃなくて自分のためなんだろう? そんなことをしたら王女様は・・・」
エレンは慌てて、リンを引き止めました。しかしリンは首を横に振って、大丈夫だからとでもいうように唇に指を押し当てると、ひょいと木に登ってしまいました。
「王女様、あなたの呪いを解きにきました。お願いですからその美しい顔をお見せ下さい」
テントの前にひざまずいたリンは甘い言葉を囁きました。しかし王女はしのごの言うばかりで、なかなか姿を見せようとしません。
「あぁ、もうじれったい」
痺れを切らしたリンは、とうとうテントに入ってしまいました。王女の悲鳴がして、エレンは王女に逃げるよう伝えるべく、大きく息を吸いにかかりました。しかし次の瞬間、フラッフィを抱いたリンが出てきたので、エレンはほっとして、へなへなとその場に座り込みました。
フラッフィをエレンに託すと、リンは自分も木から下りようと太い幹に手をかけました。しかしふと手をとめると、テントの中の王女様に、一緒に帰ろうと声を掛けました。すると王女はすんすん泣きながら言いました。
「どうして私にキスしてくれなかったの」
リンはちょっと目をぱちくりさせましたが、やがてお子様だったから、と言いました。
エレンにはリンの真意が分かりませんでした。リンは本当にフラッフィをたすけるために、あのくさいセリフで王女を油断させたのでしょうか。それとも実は、自分の呪いを解くために王女に近づいたのではないでしょうか。実際顔を見たら運命を感じなかった―ただ単に好みでなかった―ので、キスをしなかったということも考えられます。だとしたら、それをストレートに言わなかったのは、せめてものリンの優しさです。突き詰めれば、相手の死を意味するキスをしないことが、最大の優しさなのですが。
「たった一回キスしてくれれば、その問題は解決するのに。それならどうしてお父様に会いに行ったりしたの。私との結婚を許してもらうためじゃないの」
キルステン王女はむすっとしました。
「たしかに僕はお伺いに行ったさ。しかしそれは別の交渉のためだ。けれど王様は逆に、僕に交渉をしたんだ。娘の呪いを解いてくれたら、何でも願いを叶えようと」
リンは大きくひとつ溜息をつくと、テントの奥でごねていた王女を抱きかかえて木から飛び降りました。王女は、声から想像していたよりずっと幼い、七、八歳の少女でした。
「まさかこんなチンチクリンにキスしなきゃいけないなんて思わなかったんだよ。美人ならしてもいいかなと思ったけど」
王女に頬を打たれながらも、リンがなにか吹っ切れたように、あっけらかんとこう言ったので、エレンはがっかりしました。やっぱりリンはフラッフィを救出するためではなく、自分の呪いを解くためにお姫様に近づいたのです。顔を見たら子どもだったので、死なせるのが可哀想になってやめたというのなら、さっきの発言も救いようがあります。しかしそんなことを考えるほど、リンに思いやりがあるとは思えません。ただ王女がタイプでなかった、と彼ははっきり言いましたもの。
「それで、君にかけられたのはどういう呪いなの」
リンがこう尋ねると、その質問にはわんわん泣いている王女ではなく、フラッフィが答えました。なんでも王女は、本当は十六歳なのですが、あるときから成長がとまり、しかもそのときどきによって体の大きさが変わるというのです。
「朝は十歳なのに、昼は生まれたての赤ちゃん、夜には五歳になったりするの。これじゃお友達との関係もうまくいかないでしょう」
リンの腕から下りたお姫様が、悲劇のヒロインにどっぷり浸りながらこう言うと、たしかに体は一回り小さくなりました。
「本人は法則がないと主張しているけど、僕が観察した限り、精神年齢に応じた姿になっているね。その証拠にティーン以上になることはない」
フラッフィが皮肉ると、さっきまで目を潤ませていたお姫様は、目を三角にしてフラッフィを睨みました。
「ははぁ。それでやけくそになって、誘拐したフラッフィと空しいガーデンパーティをしてたんだ」
先ほど王女がフラッフィに突きつけていた銀のナイフを拾ったリンは、刃が折り畳まれている枝の部分の彫り物を物珍しそうに眺めながら、こう言いました。しかし王女は本当に傷ついた顔をしました。
「それは本当のガーデンパーティに出られなかったからよ。お父様は、私を塔の外に出してくれないの。私を恥じているんだわ」
リンが弄んでいた折りたたみナイフを取り落としそうになったとき、王女が少し大きくなったのがエレンには分かりました。どうやらフラッフィの予想が当たっているようです。
「ねぇ。こういう風になったのはいつから? 何かきっかけがあったの」
エレンが尋ねると、王女が口を開く前に、別の人物が取ってかわりました。それは娘が心配で見に来た王様でした。
「これはこの子の母親が亡くなってからだ。王妃は亡くなる直前まで、娘のことを気にしていてね。口を開けば、こんなにわがままなまま大人になって平気なのかしら、と呟いていた。そしてあれがいよいよ最期というとき、自分が嫁入りのときに着てきたドレスを持ってこさせてこう言ったのだ。あの子がこのままこのドレスに袖を通すくらいなら、いっそのこと子どものままでいますように、と」
王様は滲んだ涙を拭いました。
エレンはあの純白のドレスのことを思い出しました。あれだけ王妃のものだったから、他のドレスより古めかしく、サイズが大きかったのでしょう。
「王女様が実年齢に合った精神の持ち主になれば、そもそもキスなんて必要ないんじゃないですか」
例のナイフで林檎の皮を剥いていたリンは、自分の不履行を責められないよう、予防線を張りました。
「この子の部屋を見ただろう。あんなに沢山の洋服やおもちゃを与える親がどこにいる? 王様はお姫様に甘々なのさ。お姫様のご機嫌をとるためなら、僕を見殺しにするくらい」
フラッフィは鼻をフンと鳴らしました。エレンもこれには賛成しました。
「王様。失礼ですけど、子育ての仕方を考えた方がいいと思います。本当に王女様のことを考えるなら、叱ったり、我慢させたりすることが必要なんです。きっと」
エレンがこう進言すると、一番年下のくせにしっかりしているなとリンは感心しました。
「薄々は分かっていたのだ。しかしいざ娘の顔を見ると・・・王妃の最期の願いだというのに情けない。しかしここはひとつ、これほど親身になってくれた諸君に、娘のことを頼めないだろうか。私だとどうしても厳しくできないから」
王様の発言に一同は動揺しました。だってフラッフィは王女に誘拐された被害者だし、リンは王女を振った男で、ともすると王女を死に追いやる要注意人物なのです。それにエレンは通りがかりのただの男の子です。
「先ほどは身に過ぎたことを言いましたけど、僕たちは最適でないと思います。僕は猫を探し出して石を吐き出させなければなりませんし。王女さまのお相手などとても」
エレンは必死に御託を並べました。もちろんリンとフラッフィもそれぞれの理由をできるだけあげて、いかに自分たちがふさわしくないかを全力でプレゼンテーションしました。しかし王様にはまったく響いていないらしく、「またまたご謙遜を」と一蹴されただけでした。
エレンたちと王様が終わりなき攻防をいつまでも続いていると、先ほどから王様に何か言いたそうにしていた衛兵が、ついに空咳をしました。すると王様はやっと気がついて、きれいにセットされた髪をちょっと跳ねさせると、何かあったかと尋ねました。
「はい、王様。例の猫が北極へ行く流氷観光船に乗り込んだとの情報が複数入りました」
「流氷観光船? 次の船はいつ出るんですか」
エレンが逸る気持ちを抑えて尋ねると、王様は首を横に振りました。
「急ぎ余の砕氷船の準備をさせよう。あれなら観光船より速いから追いつけるかもしれん」
エレンは思わずフラッフィの手をとって飛び上がりました。王様はなんて太っ腹なのでしょう。しかし喜んだのも束の間、それは修理中です、と衛兵が言ったので、エレンは文字通りがっくり肩を落としました。
「それなら私の飛行船を出しましょう。あれならいますぐにだって出発できるもの」
キルステンがこう提案すると、王様はさすが我が娘と叫びました。しかし飛行船を出すということは、エレンたちが王女を預かるということです。まさかあなたの飛行船は借りるけれど、あなたは仲間はずれにしますなんて言えないじゃないですか。
エレンたちを察した王様はおおらかにこう言いました。
「そんなに気負う必要はない。ただ友人として、この子と時間を過ごしてくれんかね。ちょうど北極はオーロラのシーズンだから、一緒に眺めてやるだけでいい。それにこの子にはこの国の代表として恥ずかしくないよう、北極のことを勉強させてある。きっと役に立つがね」
王様にここまで言われては断ることはできません。エレンは年貢の納め時というのはこういうことを言うのだなと思いました。
0
あなたにおすすめの小説

独占欲強めの最強な不良さん、溺愛は盲目なほど。
猫菜こん
児童書・童話
小さな頃から、巻き込まれで絡まれ体質の私。
中学生になって、もう巻き込まれないようにひっそり暮らそう!
そう意気込んでいたのに……。
「可愛すぎる。もっと抱きしめさせてくれ。」
私、最強の不良さんに見初められちゃったみたいです。
巻き込まれ体質の不憫な中学生
ふわふわしているけど、しっかりした芯の持ち主
咲城和凜(さきしろかりん)
×
圧倒的な力とセンスを持つ、負け知らずの最強不良
和凜以外に容赦がない
天狼絆那(てんろうきずな)
些細な事だったのに、どうしてか私にくっつくイケメンさん。
彼曰く、私に一目惚れしたらしく……?
「おい、俺の和凜に何しやがる。」
「お前が無事なら、もうそれでいい……っ。」
「この世に存在している言葉だけじゃ表せないくらい、愛している。」
王道で溺愛、甘すぎる恋物語。
最強不良さんの溺愛は、独占的で盲目的。

笑いの授業
ひろみ透夏
児童書・童話
大好きだった先先が別人のように変わってしまった。
文化祭前夜に突如始まった『笑いの授業』――。
それは身の毛もよだつほどに怖ろしく凄惨な課外授業だった。
伏線となる【神楽坂の章】から急展開する【高城の章】。
追い詰められた《神楽坂先生》が起こした教師としてありえない行動と、その真意とは……。

かつて聖女は悪女と呼ばれていた
朔雲みう (さくもみう)
児童書・童話
「別に計算していたわけではないのよ」
この聖女、悪女よりもタチが悪い!?
悪魔の力で聖女に成り代わった悪女は、思い知ることになる。聖女がいかに優秀であったのかを――!!
聖女が華麗にざまぁします♪
※ エブリスタさんの妄コン『変身』にて、大賞をいただきました……!!✨
※ 悪女視点と聖女視点があります。
※ 表紙絵は親友の朝美智晴さまに描いていただきました♪


生贄姫の末路 【完結】
松林ナオ
児童書・童話
水の豊かな国の王様と魔物は、はるか昔にある契約を交わしました。
それは、姫を生贄に捧げる代わりに国へ繁栄をもたらすというものです。
水の豊かな国には双子のお姫様がいます。
ひとりは金色の髪をもつ、活発で愛らしい金のお姫様。
もうひとりは銀色の髪をもつ、表情が乏しく物静かな銀のお姫様。
王様が生贄に選んだのは、銀のお姫様でした。

あだ名が242個ある男(実はこれ実話なんですよ25)
tomoharu
児童書・童話
え?こんな話絶対ありえない!作り話でしょと思うような話からあるある話まで幅広い範囲で物語を考えました!ぜひ読んでみてください!数年後には大ヒット間違いなし!!
作品情報【伝説の物語(都道府県問題)】【伝説の話題(あだ名とコミュニケーションアプリ)】【マーライオン】【愛学両道】【やりすぎヒーロー伝説&ドリームストーリー】【トモレオ突破椿】など
・【やりすぎヒーロー伝説&ドリームストーリー】とは、その話はさすがに言いすぎでしょと言われているほぼ実話ストーリーです。
小さい頃から今まで主人公である【紘】はどのような体験をしたのかがわかります。ぜひよんでくださいね!
・【トモレオ突破椿】は、公務員試験合格なおかつ様々な問題を解決させる話です。
頭の悪かった人でも公務員になれることを証明させる話でもあるので、ぜひ読んでみてください!
特別記念として実話を元に作った【呪われし◯◯シリーズ】も公開します!
トランプ男と呼ばれている切札勝が、トランプゲームに例えて次々と問題を解決していく【トランプ男】シリーズも大人気!
人気者になるために、ウソばかりついて周りの人を誘導し、すべて自分のものにしようとするウソヒコをガチヒコが止める【嘘つきは、嘘治の始まり】というホラーサスペンスミステリー小説

王女様は美しくわらいました
トネリコ
児童書・童話
無様であろうと出来る全てはやったと満足を抱き、王女様は美しくわらいました。
それはそれは美しい笑みでした。
「お前程の悪女はおるまいよ」
王子様は最後まで嘲笑う悪女を一刀で断罪しました。
きたいの悪女は処刑されました 解説版
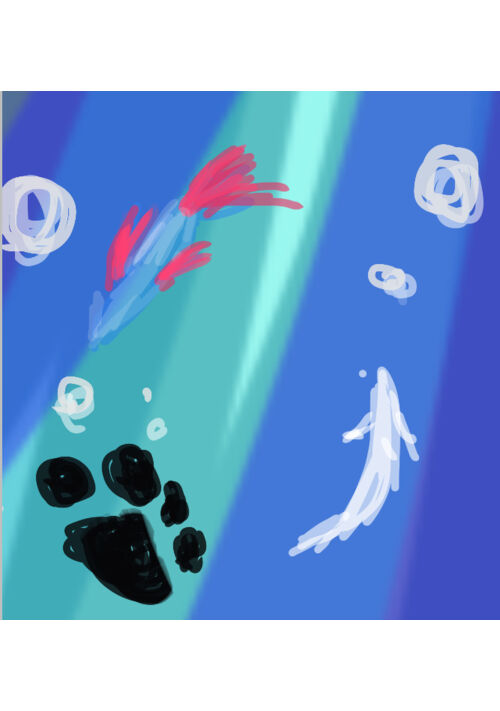
25匹の魚と猫と
ねこ沢ふたよ
児童書・童話
コメディです。
短編です。
暴虐無人の猫に一泡吹かせようと、水槽のメダカとグッピーが考えます。
何も考えずに笑って下さい
※クラムボンは笑いません
25周年おめでとうございます。
Copyright©︎
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















