35 / 35
終章 スコウキャッタ・ターミナル再び
しおりを挟む
ロイヤルブルーの王室専用列車に乗った、エレンはこれまでのことを思い出していました。
エレンの誕生日の晩、突如現われた猫。それにその猫を追う二人組。彼らから逃げるためにトラムに飛び乗ったのは、ずいぶん昔のことのようです。
エレンは膝で眠っているレネを撫でました。すると隣にいたキルステンがわっと泣き出しました。
「さよならも言わずに行ってしまうなんて、フラッフィが可哀想」
エレンとレネが帰ることを、エレンはフラッフィに言っていませんでした。フラッフィは、エレンたちが帰るといえば絶対に一緒に来ますが、せっかくこちらで楽しくやっているのに、また苦労をかけるのが嫌だったのです。それにドラゴンはレネが強い心の持ち主だと言っていました。紆余曲折あるはずですが、きっとレネはやれるはずです。
「本当にいいの? いまなら間に合うのに」
リンは列車を出すのを先延ばしにしていました。しかしエレンが固い意志を持って、首を横に振ったので、列車はまもなく動き出しました。
三人と一匹を乗せた列車が、まもなくターミナルというところまでやってくると、キルステンはもうすぐスコウキャッタ・ターミナルだ、と教えてくれました。オレグたちが平行諸島と呼んでいたプラットホーム群は、王都では「スコウキャッタ・ターミナル」と呼ばれているのです。
「スコウキャッタは『森の猫』という意味なの。どうしてこんな名前がついたのかは、私も知らないのだけれど」
キルステンがこう言うと、レネ猫は目をつぶったまま、耳をくるくる動かしました。何か言いたいことがあるようです。
レネが人間に戻ったら、最初にこのことを聞かなきゃ。そういえばレネとはずっと話をしないんだっけ。
エレンが優しくのどをかいてやると、レネ猫は喉をごろごろ鳴らしました。
かつてターミナルを取り囲み、オレグとロロの船を運んできた水はすっかり引いていました。そしてヴァイキング船の代わりに、ホームとホームをつなぐように列車が待ち構えています。これは滅多にないことで、このときでないと出口や階段のないこのターミナルで乗継ぎすることはできないのだ、とリンは言いました。
しかし王室専用列車が十二番ホーム入って、エレンがすべての列車のドアを通り、一番線のトラムに乗るのも時間の問題というところで、何本かの列車がカタタンと音を出して発車してしまいました。
「これじゃ一番線に行けないわ」
キルステンがおろおろすると、リンは自分を責めました。
「くそ。僕がいつまでも列車を出さなかったから」
「いいんだ、二人とも。どうにかなるよ」
エレンがどうやって一番ホームに行くか考えていると、チンチンという音がしました。
「あれを見ろ!」
リンは、エレンの肩を痛いくらいぐっと掴みました。
それはエレンにお別れを言いにきた人たちの乗った様々な乗物でした。同じ線路を走っているのが信じられないくらい多様な乗り物たちが、次々にやってきます。
空いていたホームにそれぞれの乗物が乗り入れ、整然と肩を並べると、見事な七本の架け橋ができました。しかもそれぞれ全然違うデザインなのに、エレンの前のドアだけぴしっと揃って、ベルゲン行きの列車まで一直線なのです。エレンは迷わず、最初の列車に乗り込みました。
十一番線の、ウォーホランディのトマト色の列車から飛び出してきたのは、ダイナーのおかみさん。
「勝手に帰っちゃうなんて淋しいじゃない」
「おばさん!」
おかみさんに抱きしめられて、エレンはもう泣いてもいいやと思いました。
「ウォーホランディは結局ケチャップの街として生きることになったのよ。もちろんちゃんと洗えるやつですけどね。でもおかげで私のスパイスの売上はいまいちなの」
おばさんがエレンの涙を拭いていると、リンをスカウトした若手リポーターが顔を出しました。
「エレン。誰が来ていると思う?」
エレンが首を傾げていると、リポーターはなんとあのケーニヒを引っ張ってきました。大きな体を申し訳なさそうに小さくしたケーニヒは、手錠こそされていませんが、彼のすぐ後ろには見張りの警官がついています。
「ちゃんとお詫びしたくて。それにお礼も。君らは僕のこころを洗濯してくれた」
ケーニヒは明らかにフラッフィを探していました。しかしエレンが訳ありげに握手を求めると、彼はそれに応じて、フラッフィにもよろしくと言いました。
「あまり時間がないんだ。急ぎなさい」
ちゃっかりカメラを回していたリポーターは腕時計を見ました。エレンはおばさんともう一度手短にハグをすると、リポーターと握手して、次の列車へ急ぎました。
次に二人を迎えてくれたのは、アウディとウィデの平和列車で、ここには負けん気の強い看護師ニカや、エレンと友達になった博士少年や軍曹、それにヤギのドクター・ブッシュも駆けつけていました。
「あんた、まったく大したものよ。私は長くナースをしているから分かるんだけど、長く付き合うっていうのは本当に大変なこと。でもこの子なら大丈夫」
ニカはレネに頬ずりをすると、エレンに似ていると言いました。すると、奥の方から背の高い女性に付き添われた一人の老人が道をあけてくれと言いました。それはこのカラフルな電車のデザイナーのターセと、娘とその作品に乗ってご満悦な様子のディケーレ老人でした。
「活躍は聞いたわ。闇に光を見いだすのは一番難しいこと。でも忘れないで。光がなければ色は失われてしまうし、逆に光さえあれば取り戻せる。あなたのカンバスをあなた色に仕上げて」
ターセはその芸術の手を、エレンの頭に載せました。
「人生は山あり谷あり。こんなはずじゃなかったと思うことが、この先何度もあるだろう。しかしそれを続けることにこそ意味がある。ときには負けてもいい。負けるが勝ちということもある。大丈夫。君ならどこでだってやっていける」
死にたいと言っていたのが嘘のように、穏やかで力強い老人のことばを聞きながら、エレンはその手を握って、何度も頷きました。
元から停まっていた列車を何台か通り抜けたあとに出迎えたのは、極夜を思わせる美しい紺色の寝台列車。エレンは入ってすぐに、神々しい犬たちに取り囲まれたので何事かと思いました。しかしそんなエレンを見て嬉しそうに笑う人物がありました。それは氷の民の兄妹アドゥラルトクとイクニクでした。
「北極から来てくれたの。遠かっただろうに」
エレンがお礼を言うと、ゾフィを抱いていた男の子は照れて、そんなに遠くないやいと言いました。
「お兄ちゃんたらあれ以来、ずっとああなのよ。最近では犬たちより可愛がっているくらい」
妹がくすくす笑うと、男の子は目を白黒させて、アルベルトにゾフィを押しつけました。
「びっくりしただろ、エレン。まさか列車に犬がのっているとは思わないものなぁ」
アルベルトはそう言うと、これは近く開通する北極特急で、人間だけでなく動物たちも乗れるのだと教えてくれました。
「将来的には地下のものたちも乗れるようにしたいんだ」
アルベルトは目を輝かせました。飛行船を訪ねてきた雪男のような恐ろしさは跡形もありません。
「ちょっとそろそろエレンを貸してくださらない?」
大きなアルベルトの後ろから現われたのは、なんと対人恐怖症だったフォルトゥーナ。長かった髪は、かなり大胆なボブヘアーになって、印象ががらりと違います。
「フォルトゥーナ、君も来てくれたの? でも人に会うの、大丈夫だった?」
エレンがこう言うと、フォルトゥーナはおかしそうに口を押さえて、こう言いました。
「前髪が生え揃っただけで全然気分が違うの。いまでは人に見られたいと思うことすらあるわ。でも今日は一本あなたにあげなくてはと思って」
フォルトゥーナはそういって前髪に手を伸ばしましたが、エレンは慌てて止めました。一本抜いたら止まらなくなってしまうのが目に見えていたのです。
「そんな大事なもの、もらえないよ。それから今後一切髪の毛は誰にもあげないで。君の美しさが損なわれるのは心が痛むから」
するとここで、アルベルトにひっついていたゾフィがピーピー鳴きはじめました。時間がないから急げというのです。エレンは、アルベルトごとゾフィを抱きしめました。
「みんな、ありがとう。世界で一番寒いところに、世界で一番温かい人たちがいること、僕、忘れない」
それまで明るかったアルベルトは、急に思いがいっぱいになったのか、悪い癖で、エレンの手を離そうとしませんでした。しかしやがて一言、元気でなと言うと、泣くのを見られないように横を向き、手をひらひら振って送り出してくれました。
残りのプラットホームと乗物より、渡り歩いてきた方が多くなってきた頃、エレンは次の足場がないと思いました。しかしエレンが困って下を見ていると、頭上から声がしました。
「おったまげられましたこと?」
それは女装していたときのオレグの口まねをした、ロロの声でした。
見上げてすぐ、エレンは息を飲みました。それはあの金のドラゴンの背に乗ったヴァイキングの子どもたちでした。
「オレグ! ロロ!」
ドラゴンが高度を下げてくれたので、エレンは二人と熱い抱擁を交わしました。
「水がないっていうから困っていたんだ。そしたらドラゴンが乗れって言ってくれて。もう興奮しっぱなしさ」
オレグは鼻の穴を膨らました。しかしロロが、オレグの口真似で「お兄様はびびっておいでなのよ」と言ったので、お兄さんは弟を小突きました。
「オーロフじいさんも来たがっていたんだけど、色々準備があってね。近く、リンさんが結婚相手を連れてくるんだって。でも結婚するってことは呪いが解けたってことだよね。それとも呪いを解くために結婚するのかな」
小声で話していたオレグは、十二番線でこちらを見守っているリンと隣のキルステンを見ました。
「綺麗な人なのに可哀想だね」
ロロがこう言ったので、エレンはあの人が呪いを解いたのだと教えてやりました。すると二人はもっと詳しく知りたがりましたが、エレンには話している時間がありません。
「詳しくは本人たちに聞いて。君から借りた服も忘れずにもらってよ!」
そういうと、エレンとレネは最後のホームに向かいました。
しかし今度こそ足場はありません。エレンは上も下も何度も確認しましたが、まったく何もありません。しかもベルゲン行きのトラムは、当然のように、ブオンとエンジンをかけはじめたではありませんか。エレンが今度こそ嫌な汗をかくのを覚悟した瞬間、誰かが遠くから呼びました。
「エレーン!」
それはこちらに向かって走ってくる、セレブ御用達リムジンに乗ったアルフォンスとガストンでした。
「二人とも! どうして?」
リムジンがちょうどエレンの前に停車すると、ガストンはまるで自分で走ったかのようにひーひー言いました。
「間に合ってよかった!」
「少し遅かったらどうなっていたことか! まったくこんな大事なときに何をしていたんだ!」
しどろもどろする相棒に、大スター・アルフォンスは追い打ちをかけました。
「私が悪いの。ガストンに忘れ物をとってきてって頼んだから」
いつのまにか渡ってきたキルステンが擁護すると、リンも続けます。
「そうそう。むしろ褒められてもいいくらい」
「ふん。よっぽど大事なものだったんだろうな?」
アルフォンスが捨て台詞を吐くと、車の中から聞き覚えのある声がしました。
「そうでしょうとも!」
それはご立腹の洗濯くまさん、フラッフィでした。
「フラッフィ! どうして?」
「置いて行くなんてひどいよ。レネのお腹の中では一緒に頑張ろうって言ったのに」
「ごめんよ。でも君のためだと思ったんだ」
フラッフィの伸ばした腕をエレンがとると、今度はそのエレンの腕をリンがつかみました。
「言い訳はあとあと。早くしないと電車に遅れるよ」
せっかくの白リムジンを、アルフォンスが男前にも足場にしてくれたおかげで、エレンとレネ猫とフラッフィはとうとう一番ホームにたどり着きました。
「さぁ後生だから乗った乗った」
リンにつつかれながらも、みんなと本当に最後の抱擁をすると、エレンたちは最終車両の、一番後方の座席に陣取りました。
すると窓を開けてとばかりに、リンはガラスをこつこつ叩きました。しかしエレンが窓を上にずらし開けると、覗き込んできたのはいまや素敵な女性の顔つきをしたキルステンでした。
「エレン、それからレネちゃん。フラッフィを誘拐したりしてごめんなさい。いままでずっと謝らなきゃと思っていたんだけど、なかなか言い出せなくて」
キルステンが目をまっ赤にしているので、エレンもフラッフィもおちゃらけないと泣いてしまいそうでした。
「また大きくなったんじゃない」
キルステンはもうと言って、泣き笑いしました。しかしそうこうしているうちに発車の汽笛が鳴りました。
カタタタン、カタタタンとトラムが動き始め、オレグやロロ、ディケーレ老人やニカ、アルベルトたちが一斉にさようならと手を振り出しました。しかしリンは、エレンと目を合わせようとしません。
けれどトラムがだいぶ調子をつかんできて、もうあとはスピードに乗せるだけというとき、リンは突然走り出しました。キルステンは注意しましたが、リンは走るのをやめません。
それどころか走る速度をぐんぐん上げて、やがてエレンたちの窓のところに追いつくと、並走しながらぐっと拳を突き出しました。そこでエレンも、同じように拳を突き出して、リンのそれとゴツンとやりました。するとリンは、それまで見たことのないような屈託のない笑顔でたった一言、こう言いました。
「またな」
急に色んな思いが込み上げてきて、エレンはことばを失いました。話したいことは山のようにあるのです。しかしいまはもうそのときではありません。
「またねー!」
エレンがあらん限りの声で叫ぶと、みんなもエレンに負けない大声で応えます。
エレンはいつまでもいつまでも手を振り続けました。しかし物語の常で、みんなの顔も声もどんどん小さくなり、やがて列車も、ホーム群も見えなくなりました。しかし遠くなればなるほど、みんなが近くにいるような気がして、エレンは背筋の伸びる思いがするのでした。
* * *
いつの間にか眠ってしまったエレンは、車窓に差し込む朝日で目を覚ましました。
トラムはもう止まっていて、レネは猫としても人間としてもいないし、フラッフィの姿も見えません。エレンはまだうす暗い外の様子を見ようと、窓に目を凝らしました。するとすぐ近くのドアが開いて、駅員さんが入ってきました。
「おやおや、迷子かな。一体どうやって入り込んだんだろう」
駅員は目をぱちくりさせました。エレンは、ここはどこか尋ねました。
「駅さ。ベルゲン駅。君、お家はどこかね?」
おじさんは小さい子どもに聞くように、目線を合わせて聞きました。そこでエレンは坂の上のやりかけ線路の近くだと答えました。
「大学の方か。それなら隣の電車に乗るといい」
「でも僕、お金を持っていないんです」
エレンがこういうと、おじさんは、今日はいいから、と言いました。けれどエレンはムキになってポケットを探りました。しかしでてきたのはスコウキャッタ・ターミナルについたときに拾ったチョコレート金貨だけでした。
「ははは。今日のあの列車の運転手が私でよかったな。さあもう出発の時間だ。おや。これは君のかい?」
駅員は座席の下から何かを引っ張り上げました。それはもう動かなくなったフラッフィでした。
エレンがフラッフィを受け取ると、駅員は時計を見ました。
「大切な物は落とさないようにしないとな。しかし急ごう。駅員は十秒でも遅れるとまずいんだ」
「あの僕、やっぱり自分で帰ります。そんなに遠いところじゃないし」
「なに。お金のことなら心配いらないよ。始発でどうせ客もいないんだ。無駄運転になるよりは乗ってくれた方がおじさんも嬉しいし」
しかしエレンは首を横に振りました。
「僕、自分で帰りたいんです。それに道は分かっていますから」
引き止める駅員にすばやく会釈すると、エレンはトラムから軽やかに降りました。
まだお母さんもお父さんも寝ているはずです。二人を起こさないように、家にはそっと入らなくちゃ。それにレネも。
フラッフィを抱いて、エレンは夜明けのベルゲンの街に踏み出しました。
終わり
エレンの誕生日の晩、突如現われた猫。それにその猫を追う二人組。彼らから逃げるためにトラムに飛び乗ったのは、ずいぶん昔のことのようです。
エレンは膝で眠っているレネを撫でました。すると隣にいたキルステンがわっと泣き出しました。
「さよならも言わずに行ってしまうなんて、フラッフィが可哀想」
エレンとレネが帰ることを、エレンはフラッフィに言っていませんでした。フラッフィは、エレンたちが帰るといえば絶対に一緒に来ますが、せっかくこちらで楽しくやっているのに、また苦労をかけるのが嫌だったのです。それにドラゴンはレネが強い心の持ち主だと言っていました。紆余曲折あるはずですが、きっとレネはやれるはずです。
「本当にいいの? いまなら間に合うのに」
リンは列車を出すのを先延ばしにしていました。しかしエレンが固い意志を持って、首を横に振ったので、列車はまもなく動き出しました。
三人と一匹を乗せた列車が、まもなくターミナルというところまでやってくると、キルステンはもうすぐスコウキャッタ・ターミナルだ、と教えてくれました。オレグたちが平行諸島と呼んでいたプラットホーム群は、王都では「スコウキャッタ・ターミナル」と呼ばれているのです。
「スコウキャッタは『森の猫』という意味なの。どうしてこんな名前がついたのかは、私も知らないのだけれど」
キルステンがこう言うと、レネ猫は目をつぶったまま、耳をくるくる動かしました。何か言いたいことがあるようです。
レネが人間に戻ったら、最初にこのことを聞かなきゃ。そういえばレネとはずっと話をしないんだっけ。
エレンが優しくのどをかいてやると、レネ猫は喉をごろごろ鳴らしました。
かつてターミナルを取り囲み、オレグとロロの船を運んできた水はすっかり引いていました。そしてヴァイキング船の代わりに、ホームとホームをつなぐように列車が待ち構えています。これは滅多にないことで、このときでないと出口や階段のないこのターミナルで乗継ぎすることはできないのだ、とリンは言いました。
しかし王室専用列車が十二番ホーム入って、エレンがすべての列車のドアを通り、一番線のトラムに乗るのも時間の問題というところで、何本かの列車がカタタンと音を出して発車してしまいました。
「これじゃ一番線に行けないわ」
キルステンがおろおろすると、リンは自分を責めました。
「くそ。僕がいつまでも列車を出さなかったから」
「いいんだ、二人とも。どうにかなるよ」
エレンがどうやって一番ホームに行くか考えていると、チンチンという音がしました。
「あれを見ろ!」
リンは、エレンの肩を痛いくらいぐっと掴みました。
それはエレンにお別れを言いにきた人たちの乗った様々な乗物でした。同じ線路を走っているのが信じられないくらい多様な乗り物たちが、次々にやってきます。
空いていたホームにそれぞれの乗物が乗り入れ、整然と肩を並べると、見事な七本の架け橋ができました。しかもそれぞれ全然違うデザインなのに、エレンの前のドアだけぴしっと揃って、ベルゲン行きの列車まで一直線なのです。エレンは迷わず、最初の列車に乗り込みました。
十一番線の、ウォーホランディのトマト色の列車から飛び出してきたのは、ダイナーのおかみさん。
「勝手に帰っちゃうなんて淋しいじゃない」
「おばさん!」
おかみさんに抱きしめられて、エレンはもう泣いてもいいやと思いました。
「ウォーホランディは結局ケチャップの街として生きることになったのよ。もちろんちゃんと洗えるやつですけどね。でもおかげで私のスパイスの売上はいまいちなの」
おばさんがエレンの涙を拭いていると、リンをスカウトした若手リポーターが顔を出しました。
「エレン。誰が来ていると思う?」
エレンが首を傾げていると、リポーターはなんとあのケーニヒを引っ張ってきました。大きな体を申し訳なさそうに小さくしたケーニヒは、手錠こそされていませんが、彼のすぐ後ろには見張りの警官がついています。
「ちゃんとお詫びしたくて。それにお礼も。君らは僕のこころを洗濯してくれた」
ケーニヒは明らかにフラッフィを探していました。しかしエレンが訳ありげに握手を求めると、彼はそれに応じて、フラッフィにもよろしくと言いました。
「あまり時間がないんだ。急ぎなさい」
ちゃっかりカメラを回していたリポーターは腕時計を見ました。エレンはおばさんともう一度手短にハグをすると、リポーターと握手して、次の列車へ急ぎました。
次に二人を迎えてくれたのは、アウディとウィデの平和列車で、ここには負けん気の強い看護師ニカや、エレンと友達になった博士少年や軍曹、それにヤギのドクター・ブッシュも駆けつけていました。
「あんた、まったく大したものよ。私は長くナースをしているから分かるんだけど、長く付き合うっていうのは本当に大変なこと。でもこの子なら大丈夫」
ニカはレネに頬ずりをすると、エレンに似ていると言いました。すると、奥の方から背の高い女性に付き添われた一人の老人が道をあけてくれと言いました。それはこのカラフルな電車のデザイナーのターセと、娘とその作品に乗ってご満悦な様子のディケーレ老人でした。
「活躍は聞いたわ。闇に光を見いだすのは一番難しいこと。でも忘れないで。光がなければ色は失われてしまうし、逆に光さえあれば取り戻せる。あなたのカンバスをあなた色に仕上げて」
ターセはその芸術の手を、エレンの頭に載せました。
「人生は山あり谷あり。こんなはずじゃなかったと思うことが、この先何度もあるだろう。しかしそれを続けることにこそ意味がある。ときには負けてもいい。負けるが勝ちということもある。大丈夫。君ならどこでだってやっていける」
死にたいと言っていたのが嘘のように、穏やかで力強い老人のことばを聞きながら、エレンはその手を握って、何度も頷きました。
元から停まっていた列車を何台か通り抜けたあとに出迎えたのは、極夜を思わせる美しい紺色の寝台列車。エレンは入ってすぐに、神々しい犬たちに取り囲まれたので何事かと思いました。しかしそんなエレンを見て嬉しそうに笑う人物がありました。それは氷の民の兄妹アドゥラルトクとイクニクでした。
「北極から来てくれたの。遠かっただろうに」
エレンがお礼を言うと、ゾフィを抱いていた男の子は照れて、そんなに遠くないやいと言いました。
「お兄ちゃんたらあれ以来、ずっとああなのよ。最近では犬たちより可愛がっているくらい」
妹がくすくす笑うと、男の子は目を白黒させて、アルベルトにゾフィを押しつけました。
「びっくりしただろ、エレン。まさか列車に犬がのっているとは思わないものなぁ」
アルベルトはそう言うと、これは近く開通する北極特急で、人間だけでなく動物たちも乗れるのだと教えてくれました。
「将来的には地下のものたちも乗れるようにしたいんだ」
アルベルトは目を輝かせました。飛行船を訪ねてきた雪男のような恐ろしさは跡形もありません。
「ちょっとそろそろエレンを貸してくださらない?」
大きなアルベルトの後ろから現われたのは、なんと対人恐怖症だったフォルトゥーナ。長かった髪は、かなり大胆なボブヘアーになって、印象ががらりと違います。
「フォルトゥーナ、君も来てくれたの? でも人に会うの、大丈夫だった?」
エレンがこう言うと、フォルトゥーナはおかしそうに口を押さえて、こう言いました。
「前髪が生え揃っただけで全然気分が違うの。いまでは人に見られたいと思うことすらあるわ。でも今日は一本あなたにあげなくてはと思って」
フォルトゥーナはそういって前髪に手を伸ばしましたが、エレンは慌てて止めました。一本抜いたら止まらなくなってしまうのが目に見えていたのです。
「そんな大事なもの、もらえないよ。それから今後一切髪の毛は誰にもあげないで。君の美しさが損なわれるのは心が痛むから」
するとここで、アルベルトにひっついていたゾフィがピーピー鳴きはじめました。時間がないから急げというのです。エレンは、アルベルトごとゾフィを抱きしめました。
「みんな、ありがとう。世界で一番寒いところに、世界で一番温かい人たちがいること、僕、忘れない」
それまで明るかったアルベルトは、急に思いがいっぱいになったのか、悪い癖で、エレンの手を離そうとしませんでした。しかしやがて一言、元気でなと言うと、泣くのを見られないように横を向き、手をひらひら振って送り出してくれました。
残りのプラットホームと乗物より、渡り歩いてきた方が多くなってきた頃、エレンは次の足場がないと思いました。しかしエレンが困って下を見ていると、頭上から声がしました。
「おったまげられましたこと?」
それは女装していたときのオレグの口まねをした、ロロの声でした。
見上げてすぐ、エレンは息を飲みました。それはあの金のドラゴンの背に乗ったヴァイキングの子どもたちでした。
「オレグ! ロロ!」
ドラゴンが高度を下げてくれたので、エレンは二人と熱い抱擁を交わしました。
「水がないっていうから困っていたんだ。そしたらドラゴンが乗れって言ってくれて。もう興奮しっぱなしさ」
オレグは鼻の穴を膨らました。しかしロロが、オレグの口真似で「お兄様はびびっておいでなのよ」と言ったので、お兄さんは弟を小突きました。
「オーロフじいさんも来たがっていたんだけど、色々準備があってね。近く、リンさんが結婚相手を連れてくるんだって。でも結婚するってことは呪いが解けたってことだよね。それとも呪いを解くために結婚するのかな」
小声で話していたオレグは、十二番線でこちらを見守っているリンと隣のキルステンを見ました。
「綺麗な人なのに可哀想だね」
ロロがこう言ったので、エレンはあの人が呪いを解いたのだと教えてやりました。すると二人はもっと詳しく知りたがりましたが、エレンには話している時間がありません。
「詳しくは本人たちに聞いて。君から借りた服も忘れずにもらってよ!」
そういうと、エレンとレネは最後のホームに向かいました。
しかし今度こそ足場はありません。エレンは上も下も何度も確認しましたが、まったく何もありません。しかもベルゲン行きのトラムは、当然のように、ブオンとエンジンをかけはじめたではありませんか。エレンが今度こそ嫌な汗をかくのを覚悟した瞬間、誰かが遠くから呼びました。
「エレーン!」
それはこちらに向かって走ってくる、セレブ御用達リムジンに乗ったアルフォンスとガストンでした。
「二人とも! どうして?」
リムジンがちょうどエレンの前に停車すると、ガストンはまるで自分で走ったかのようにひーひー言いました。
「間に合ってよかった!」
「少し遅かったらどうなっていたことか! まったくこんな大事なときに何をしていたんだ!」
しどろもどろする相棒に、大スター・アルフォンスは追い打ちをかけました。
「私が悪いの。ガストンに忘れ物をとってきてって頼んだから」
いつのまにか渡ってきたキルステンが擁護すると、リンも続けます。
「そうそう。むしろ褒められてもいいくらい」
「ふん。よっぽど大事なものだったんだろうな?」
アルフォンスが捨て台詞を吐くと、車の中から聞き覚えのある声がしました。
「そうでしょうとも!」
それはご立腹の洗濯くまさん、フラッフィでした。
「フラッフィ! どうして?」
「置いて行くなんてひどいよ。レネのお腹の中では一緒に頑張ろうって言ったのに」
「ごめんよ。でも君のためだと思ったんだ」
フラッフィの伸ばした腕をエレンがとると、今度はそのエレンの腕をリンがつかみました。
「言い訳はあとあと。早くしないと電車に遅れるよ」
せっかくの白リムジンを、アルフォンスが男前にも足場にしてくれたおかげで、エレンとレネ猫とフラッフィはとうとう一番ホームにたどり着きました。
「さぁ後生だから乗った乗った」
リンにつつかれながらも、みんなと本当に最後の抱擁をすると、エレンたちは最終車両の、一番後方の座席に陣取りました。
すると窓を開けてとばかりに、リンはガラスをこつこつ叩きました。しかしエレンが窓を上にずらし開けると、覗き込んできたのはいまや素敵な女性の顔つきをしたキルステンでした。
「エレン、それからレネちゃん。フラッフィを誘拐したりしてごめんなさい。いままでずっと謝らなきゃと思っていたんだけど、なかなか言い出せなくて」
キルステンが目をまっ赤にしているので、エレンもフラッフィもおちゃらけないと泣いてしまいそうでした。
「また大きくなったんじゃない」
キルステンはもうと言って、泣き笑いしました。しかしそうこうしているうちに発車の汽笛が鳴りました。
カタタタン、カタタタンとトラムが動き始め、オレグやロロ、ディケーレ老人やニカ、アルベルトたちが一斉にさようならと手を振り出しました。しかしリンは、エレンと目を合わせようとしません。
けれどトラムがだいぶ調子をつかんできて、もうあとはスピードに乗せるだけというとき、リンは突然走り出しました。キルステンは注意しましたが、リンは走るのをやめません。
それどころか走る速度をぐんぐん上げて、やがてエレンたちの窓のところに追いつくと、並走しながらぐっと拳を突き出しました。そこでエレンも、同じように拳を突き出して、リンのそれとゴツンとやりました。するとリンは、それまで見たことのないような屈託のない笑顔でたった一言、こう言いました。
「またな」
急に色んな思いが込み上げてきて、エレンはことばを失いました。話したいことは山のようにあるのです。しかしいまはもうそのときではありません。
「またねー!」
エレンがあらん限りの声で叫ぶと、みんなもエレンに負けない大声で応えます。
エレンはいつまでもいつまでも手を振り続けました。しかし物語の常で、みんなの顔も声もどんどん小さくなり、やがて列車も、ホーム群も見えなくなりました。しかし遠くなればなるほど、みんなが近くにいるような気がして、エレンは背筋の伸びる思いがするのでした。
* * *
いつの間にか眠ってしまったエレンは、車窓に差し込む朝日で目を覚ましました。
トラムはもう止まっていて、レネは猫としても人間としてもいないし、フラッフィの姿も見えません。エレンはまだうす暗い外の様子を見ようと、窓に目を凝らしました。するとすぐ近くのドアが開いて、駅員さんが入ってきました。
「おやおや、迷子かな。一体どうやって入り込んだんだろう」
駅員は目をぱちくりさせました。エレンは、ここはどこか尋ねました。
「駅さ。ベルゲン駅。君、お家はどこかね?」
おじさんは小さい子どもに聞くように、目線を合わせて聞きました。そこでエレンは坂の上のやりかけ線路の近くだと答えました。
「大学の方か。それなら隣の電車に乗るといい」
「でも僕、お金を持っていないんです」
エレンがこういうと、おじさんは、今日はいいから、と言いました。けれどエレンはムキになってポケットを探りました。しかしでてきたのはスコウキャッタ・ターミナルについたときに拾ったチョコレート金貨だけでした。
「ははは。今日のあの列車の運転手が私でよかったな。さあもう出発の時間だ。おや。これは君のかい?」
駅員は座席の下から何かを引っ張り上げました。それはもう動かなくなったフラッフィでした。
エレンがフラッフィを受け取ると、駅員は時計を見ました。
「大切な物は落とさないようにしないとな。しかし急ごう。駅員は十秒でも遅れるとまずいんだ」
「あの僕、やっぱり自分で帰ります。そんなに遠いところじゃないし」
「なに。お金のことなら心配いらないよ。始発でどうせ客もいないんだ。無駄運転になるよりは乗ってくれた方がおじさんも嬉しいし」
しかしエレンは首を横に振りました。
「僕、自分で帰りたいんです。それに道は分かっていますから」
引き止める駅員にすばやく会釈すると、エレンはトラムから軽やかに降りました。
まだお母さんもお父さんも寝ているはずです。二人を起こさないように、家にはそっと入らなくちゃ。それにレネも。
フラッフィを抱いて、エレンは夜明けのベルゲンの街に踏み出しました。
終わり
0
この作品の感想を投稿する
みんなの感想(1件)
あなたにおすすめの小説

独占欲強めの最強な不良さん、溺愛は盲目なほど。
猫菜こん
児童書・童話
小さな頃から、巻き込まれで絡まれ体質の私。
中学生になって、もう巻き込まれないようにひっそり暮らそう!
そう意気込んでいたのに……。
「可愛すぎる。もっと抱きしめさせてくれ。」
私、最強の不良さんに見初められちゃったみたいです。
巻き込まれ体質の不憫な中学生
ふわふわしているけど、しっかりした芯の持ち主
咲城和凜(さきしろかりん)
×
圧倒的な力とセンスを持つ、負け知らずの最強不良
和凜以外に容赦がない
天狼絆那(てんろうきずな)
些細な事だったのに、どうしてか私にくっつくイケメンさん。
彼曰く、私に一目惚れしたらしく……?
「おい、俺の和凜に何しやがる。」
「お前が無事なら、もうそれでいい……っ。」
「この世に存在している言葉だけじゃ表せないくらい、愛している。」
王道で溺愛、甘すぎる恋物語。
最強不良さんの溺愛は、独占的で盲目的。

笑いの授業
ひろみ透夏
児童書・童話
大好きだった先先が別人のように変わってしまった。
文化祭前夜に突如始まった『笑いの授業』――。
それは身の毛もよだつほどに怖ろしく凄惨な課外授業だった。
伏線となる【神楽坂の章】から急展開する【高城の章】。
追い詰められた《神楽坂先生》が起こした教師としてありえない行動と、その真意とは……。

あだ名が242個ある男(実はこれ実話なんですよ25)
tomoharu
児童書・童話
え?こんな話絶対ありえない!作り話でしょと思うような話からあるある話まで幅広い範囲で物語を考えました!ぜひ読んでみてください!数年後には大ヒット間違いなし!!
作品情報【伝説の物語(都道府県問題)】【伝説の話題(あだ名とコミュニケーションアプリ)】【マーライオン】【愛学両道】【やりすぎヒーロー伝説&ドリームストーリー】【トモレオ突破椿】など
・【やりすぎヒーロー伝説&ドリームストーリー】とは、その話はさすがに言いすぎでしょと言われているほぼ実話ストーリーです。
小さい頃から今まで主人公である【紘】はどのような体験をしたのかがわかります。ぜひよんでくださいね!
・【トモレオ突破椿】は、公務員試験合格なおかつ様々な問題を解決させる話です。
頭の悪かった人でも公務員になれることを証明させる話でもあるので、ぜひ読んでみてください!
特別記念として実話を元に作った【呪われし◯◯シリーズ】も公開します!
トランプ男と呼ばれている切札勝が、トランプゲームに例えて次々と問題を解決していく【トランプ男】シリーズも大人気!
人気者になるために、ウソばかりついて周りの人を誘導し、すべて自分のものにしようとするウソヒコをガチヒコが止める【嘘つきは、嘘治の始まり】というホラーサスペンスミステリー小説

かつて聖女は悪女と呼ばれていた
朔雲みう (さくもみう)
児童書・童話
「別に計算していたわけではないのよ」
この聖女、悪女よりもタチが悪い!?
悪魔の力で聖女に成り代わった悪女は、思い知ることになる。聖女がいかに優秀であったのかを――!!
聖女が華麗にざまぁします♪
※ エブリスタさんの妄コン『変身』にて、大賞をいただきました……!!✨
※ 悪女視点と聖女視点があります。
※ 表紙絵は親友の朝美智晴さまに描いていただきました♪


生贄姫の末路 【完結】
松林ナオ
児童書・童話
水の豊かな国の王様と魔物は、はるか昔にある契約を交わしました。
それは、姫を生贄に捧げる代わりに国へ繁栄をもたらすというものです。
水の豊かな国には双子のお姫様がいます。
ひとりは金色の髪をもつ、活発で愛らしい金のお姫様。
もうひとりは銀色の髪をもつ、表情が乏しく物静かな銀のお姫様。
王様が生贄に選んだのは、銀のお姫様でした。

14歳で定年ってマジ!? 世界を変えた少年漫画家、再起のノート
谷川 雅
児童書・童話
この世界、子どもがエリート。
“スーパーチャイルド制度”によって、能力のピークは12歳。
そして14歳で、まさかの《定年》。
6歳の星野幸弘は、将来の夢「世界を笑顔にする漫画家」を目指して全力疾走する。
だけど、定年まで残された時間はわずか8年……!
――そして14歳。夢は叶わぬまま、制度に押し流されるように“退場”を迎える。
だが、そんな幸弘の前に現れたのは、
「まちがえた人間」のノートが集まる、不思議な図書室だった。
これは、間違えたままじゃ終われなかった少年たちの“再スタート”の物語。
描けなかった物語の“つづき”は、きっと君の手の中にある。
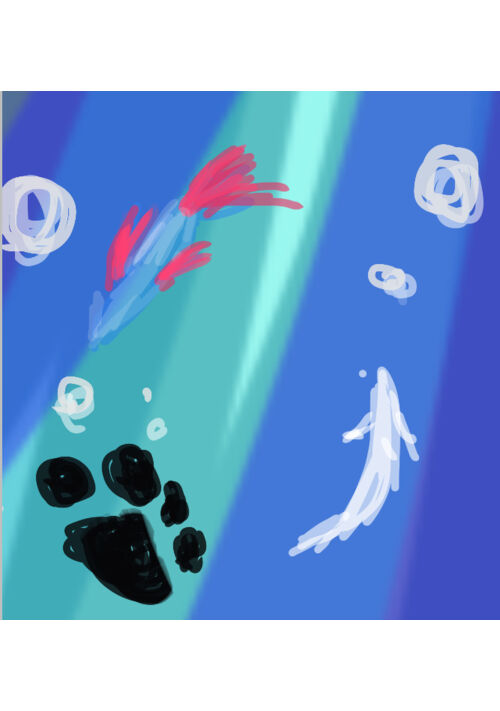
25匹の魚と猫と
ねこ沢ふたよ
児童書・童話
コメディです。
短編です。
暴虐無人の猫に一泡吹かせようと、水槽のメダカとグッピーが考えます。
何も考えずに笑って下さい
※クラムボンは笑いません
25周年おめでとうございます。
Copyright©︎
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる
本作については削除予定があるため、新規のレンタルはできません。
このユーザをミュートしますか?
※ミュートすると該当ユーザの「小説・投稿漫画・感想・コメント」が非表示になります。ミュートしたことは相手にはわかりません。またいつでもミュート解除できます。
※一部ミュート対象外の箇所がございます。ミュートの対象範囲についての詳細はヘルプにてご確認ください。
※ミュートしてもお気に入りやしおりは解除されません。既にお気に入りやしおりを使用している場合はすべて解除してからミュートを行うようにしてください。





















(私の勘違いなら申し訳ありませんが、)兄と妹の名前がローマ字のアナグラムになっていて面白いです。
EREN→RENE
偶然見つけました。