4 / 10
第一幕 新しい世界
第三話
しおりを挟む
一時間後。
長くて格式ばったリヒャルトの閉会の辞を持って、華やかな祭の幕は閉じた。
貴族達の見送りを終え、城内が落ち着いた頃にジークフリートは義父に呼ばれ執務室へと呼ばれた。
「失礼します。」
そう言ってジークフリートが執務室の中へと入ると、リヒャルトが椅子に座って待っていた。
金髪緑眼、その顔立ちは、なるほどジークムントに似ていたが、彼に比べどこか少しやつれている。
「ジーク、今日は大変だっただろ?疲れていないかい?」
リヒャルトは、ジークフリートを気遣うように優しく微笑む。
「大丈夫です。・・・お気遣い、ありがとうございます。」
「途中でいなくなったから、気分でも悪くなったのではないかと心配していたのだよ。」
「・・・・・・すみません。・・・それより、お話とは・・・?」
それを聞きリヒャルトは椅子から立ち上がると、ちらりと不安そうにジークフリートを見つめる。
「あぁ・・・。いや、その・・・アカデミーの件なのだが・・・。やはり、城から出て行くのか?」
リヒャルトの不安そうな目線に気づき、ジークフリートは申し訳なさそうな顔をして答えた。
「はい・・・。」
ジークフリートの返事を聞いてリヒャルトは“あぁ”と、首を横に振った。
「別にアカデミーでなくとも、城でも勉強は十分にできるだろうに。ましてや寄宿制なんて・・・。もしかして、今の家庭教師に不満なのかい?それならすぐにやめさせてもっと優秀なものを呼ぼう。ああ!それとも、周りの召使達が何か粗相をしたのかい?それなら・・・。」
「あの!いえ・・・不満とか、そういうのではなくて・・・。このことは、大分前から決めていたことなのです。城にいるだけでは、見えてこないこともありますし・・・。それに、同じ世代の人たちと一緒に学んでみたいのです。以前からの夢だったのですが、ただ、母さんが・・・。・・・いえ、母さんの薔薇祭が終わるまでは、ここにいてあげなければならないと思っていて・・・それで、その・・・・・・だから・・・。」
そこまで言うとジークフリートは目線を下にそらし、口ごもってしまった。
アカデミーとは、学問や武芸を習う場所でいわゆる学校である。七~十一歳の子供が通うアカデミーを初等、十二歳~十五歳を中等、十六歳~十九歳を高等とする。
アカデミーは、比較的裕福な家庭の子供が通うものだったが、戦乱後、初等アカデミーまでを義務教育とするようになった。
が、現実はそうはいかず、まだまだ普及できていない状態である。
ちなみに、アカデミーは共学ではなく男女別が基本である。
ジークフリートは今年で、十七になるので高等アカデミーに当たるのだが、今まで専属の家庭教師が城で教えていたので彼は生まれてこの方アカデミーというものに行ったことがなかった。
実際、家柄が侯爵以上になるとジークフリートのように家に専属の家庭教師をつけるという者が多かったのだが。
「そうか・・・。いや、お前の心は変わらないだろうとは思っていたし、無理にとめるつもりなんてない。・・・・・・ただ、な・・・・・・。」
リヒャルトは、苦笑いをすると窓の外の空を見上げた。
「義父さん・・・。」
ジークフリートが困惑したような顔をするとリヒャルトは我に返り、今度はにこりと微笑みながら穏やかな口調で言う。
「・・・・・・カレン王立アカデミーは、教師生徒共に優れた者ばかりの名門校だ。きっと多くのことが学べるだろう。」
ジークフリートはその言葉を聞き、安堵した。
「ああ、そうだ、ジーク。君に紹介しておきたい人がいるんだ。もうすでに、応接室で待ってもらっているんだがね。」
そう言うと、リヒャルトは応接室へとつながっているドアに手をかける。ジークフリートは、一体誰なのだろうと思いながら義父の後についていくと、そこには品のよい男が一人、ソファに腰掛けていた。
「やあ、お話は終わりましたかな?」
その男はリヒャルトたちを見ると、ゆっくりと立ち上がった。
年は、二十代後半から三十代前半といったところであろうか。深い緑色の瞳に肩まである藍色の髪を後ろで一つに束ねている。
臙脂色に金の刺繍の入った別珍のロングジャケットに深緑のタイ。そして黒の皮のパンツにロングブーツと少し派手目な格好であるが彼の器量がそうさせているのかあまり気になることもなく、逆に落ち着いた感じにまとまっていた。
「お待たせして申し訳ありません。・・・ジーク、こちらはウィンダミア侯爵といってね、カレン地方にお住まいなんだ。今度、お前がカレンに行くにあたってぜひ紹介しておこうと思って、お呼び立てしたのだよ。」
リヒャルトがそう説明すると、男は片手を胸に当てて一礼した。
「ファーディナント・ウィンダミアと申します。爵位は侯爵。種族はセカンドになります。以後お見知りおきを。」
このファーディナントという男、まだ若いのだが堂々としていて何か貫禄のある雰囲気を漂わせている。その雰囲気に圧倒されていたジークフリートは、はっと我に返りあわてて礼をした。
「あ・・・ジークフリート・ヴォルフェ・ヴァルハラです。本日は、わざわざお越しいただいて、感謝します。」
「侯爵のウィンダミア家とは古くからの付き合いでね。お前は小さくて覚えていないだろうけれど、昔はよくこの城にいらっしゃっていたのだよ。」
「この度、ジークフリート様がご入学されるというアカデミーの近くに我が城がございます。何か困ったことがあれば、いつでもいらして下さい。私でよければ、お相手いたしますよ。」
ファーディナントは、にこりと微笑んだ。その優しそうな笑みにつられて、自然とジークフリートの顔もほころぶ。
彼の笑顔は、皆がいつも使う媚やへつらいのようなものとは違うとジークフリートは思った。
心からの笑顔・・・といったところであろうか、何となくだが、そんな感じがしたのだ。
ジークフリートがそんなことを思っている間、ファーディナントとリヒャルトは政治や国の情勢など何やら難しい話を、二、三交わしていた。
途中ファーディナントが窓際に置かれている柱時計をちらりと見たところで、それらの話は中断された。
「お会いして早々に申し訳ないのですが、このあと少し、私用がありまして。そろそろ失礼してもよろしいでしょうか?私としては、もう少しゆっくりしていきたいところなのですが・・・。」
ファーディナントが残念そうにそう言うと、リヒャルトは呼び鈴を鳴らそうとした。
「ええ。今日はありがとうございます。今、使いの者を呼びましょう。」
それを聞いたジークフリートは、呼び鈴を鳴らすのをあわてて止め、リヒャルトに申し出た。
「義父上、使いの者を呼ばずとも、私が侯爵をお送りいたします。」
「そうだな・・・では、そうしてもらおうか。・・・よろしいでしょうか、侯爵?」
「もちろんですよ。」
ファーディナントは快く承諾すると、またにっこりと微笑んだのだった。
長くて格式ばったリヒャルトの閉会の辞を持って、華やかな祭の幕は閉じた。
貴族達の見送りを終え、城内が落ち着いた頃にジークフリートは義父に呼ばれ執務室へと呼ばれた。
「失礼します。」
そう言ってジークフリートが執務室の中へと入ると、リヒャルトが椅子に座って待っていた。
金髪緑眼、その顔立ちは、なるほどジークムントに似ていたが、彼に比べどこか少しやつれている。
「ジーク、今日は大変だっただろ?疲れていないかい?」
リヒャルトは、ジークフリートを気遣うように優しく微笑む。
「大丈夫です。・・・お気遣い、ありがとうございます。」
「途中でいなくなったから、気分でも悪くなったのではないかと心配していたのだよ。」
「・・・・・・すみません。・・・それより、お話とは・・・?」
それを聞きリヒャルトは椅子から立ち上がると、ちらりと不安そうにジークフリートを見つめる。
「あぁ・・・。いや、その・・・アカデミーの件なのだが・・・。やはり、城から出て行くのか?」
リヒャルトの不安そうな目線に気づき、ジークフリートは申し訳なさそうな顔をして答えた。
「はい・・・。」
ジークフリートの返事を聞いてリヒャルトは“あぁ”と、首を横に振った。
「別にアカデミーでなくとも、城でも勉強は十分にできるだろうに。ましてや寄宿制なんて・・・。もしかして、今の家庭教師に不満なのかい?それならすぐにやめさせてもっと優秀なものを呼ぼう。ああ!それとも、周りの召使達が何か粗相をしたのかい?それなら・・・。」
「あの!いえ・・・不満とか、そういうのではなくて・・・。このことは、大分前から決めていたことなのです。城にいるだけでは、見えてこないこともありますし・・・。それに、同じ世代の人たちと一緒に学んでみたいのです。以前からの夢だったのですが、ただ、母さんが・・・。・・・いえ、母さんの薔薇祭が終わるまでは、ここにいてあげなければならないと思っていて・・・それで、その・・・・・・だから・・・。」
そこまで言うとジークフリートは目線を下にそらし、口ごもってしまった。
アカデミーとは、学問や武芸を習う場所でいわゆる学校である。七~十一歳の子供が通うアカデミーを初等、十二歳~十五歳を中等、十六歳~十九歳を高等とする。
アカデミーは、比較的裕福な家庭の子供が通うものだったが、戦乱後、初等アカデミーまでを義務教育とするようになった。
が、現実はそうはいかず、まだまだ普及できていない状態である。
ちなみに、アカデミーは共学ではなく男女別が基本である。
ジークフリートは今年で、十七になるので高等アカデミーに当たるのだが、今まで専属の家庭教師が城で教えていたので彼は生まれてこの方アカデミーというものに行ったことがなかった。
実際、家柄が侯爵以上になるとジークフリートのように家に専属の家庭教師をつけるという者が多かったのだが。
「そうか・・・。いや、お前の心は変わらないだろうとは思っていたし、無理にとめるつもりなんてない。・・・・・・ただ、な・・・・・・。」
リヒャルトは、苦笑いをすると窓の外の空を見上げた。
「義父さん・・・。」
ジークフリートが困惑したような顔をするとリヒャルトは我に返り、今度はにこりと微笑みながら穏やかな口調で言う。
「・・・・・・カレン王立アカデミーは、教師生徒共に優れた者ばかりの名門校だ。きっと多くのことが学べるだろう。」
ジークフリートはその言葉を聞き、安堵した。
「ああ、そうだ、ジーク。君に紹介しておきたい人がいるんだ。もうすでに、応接室で待ってもらっているんだがね。」
そう言うと、リヒャルトは応接室へとつながっているドアに手をかける。ジークフリートは、一体誰なのだろうと思いながら義父の後についていくと、そこには品のよい男が一人、ソファに腰掛けていた。
「やあ、お話は終わりましたかな?」
その男はリヒャルトたちを見ると、ゆっくりと立ち上がった。
年は、二十代後半から三十代前半といったところであろうか。深い緑色の瞳に肩まである藍色の髪を後ろで一つに束ねている。
臙脂色に金の刺繍の入った別珍のロングジャケットに深緑のタイ。そして黒の皮のパンツにロングブーツと少し派手目な格好であるが彼の器量がそうさせているのかあまり気になることもなく、逆に落ち着いた感じにまとまっていた。
「お待たせして申し訳ありません。・・・ジーク、こちらはウィンダミア侯爵といってね、カレン地方にお住まいなんだ。今度、お前がカレンに行くにあたってぜひ紹介しておこうと思って、お呼び立てしたのだよ。」
リヒャルトがそう説明すると、男は片手を胸に当てて一礼した。
「ファーディナント・ウィンダミアと申します。爵位は侯爵。種族はセカンドになります。以後お見知りおきを。」
このファーディナントという男、まだ若いのだが堂々としていて何か貫禄のある雰囲気を漂わせている。その雰囲気に圧倒されていたジークフリートは、はっと我に返りあわてて礼をした。
「あ・・・ジークフリート・ヴォルフェ・ヴァルハラです。本日は、わざわざお越しいただいて、感謝します。」
「侯爵のウィンダミア家とは古くからの付き合いでね。お前は小さくて覚えていないだろうけれど、昔はよくこの城にいらっしゃっていたのだよ。」
「この度、ジークフリート様がご入学されるというアカデミーの近くに我が城がございます。何か困ったことがあれば、いつでもいらして下さい。私でよければ、お相手いたしますよ。」
ファーディナントは、にこりと微笑んだ。その優しそうな笑みにつられて、自然とジークフリートの顔もほころぶ。
彼の笑顔は、皆がいつも使う媚やへつらいのようなものとは違うとジークフリートは思った。
心からの笑顔・・・といったところであろうか、何となくだが、そんな感じがしたのだ。
ジークフリートがそんなことを思っている間、ファーディナントとリヒャルトは政治や国の情勢など何やら難しい話を、二、三交わしていた。
途中ファーディナントが窓際に置かれている柱時計をちらりと見たところで、それらの話は中断された。
「お会いして早々に申し訳ないのですが、このあと少し、私用がありまして。そろそろ失礼してもよろしいでしょうか?私としては、もう少しゆっくりしていきたいところなのですが・・・。」
ファーディナントが残念そうにそう言うと、リヒャルトは呼び鈴を鳴らそうとした。
「ええ。今日はありがとうございます。今、使いの者を呼びましょう。」
それを聞いたジークフリートは、呼び鈴を鳴らすのをあわてて止め、リヒャルトに申し出た。
「義父上、使いの者を呼ばずとも、私が侯爵をお送りいたします。」
「そうだな・・・では、そうしてもらおうか。・・・よろしいでしょうか、侯爵?」
「もちろんですよ。」
ファーディナントは快く承諾すると、またにっこりと微笑んだのだった。
0
あなたにおすすめの小説

復讐の鎖に繋がれた魔王は、光に囚われる。
篠雨
BL
予言の魔王として闇に閉ざされた屋敷に隔離されていたノアール。孤独な日々の中、彼は唯一の光であった少年セレを、手元に鎖で繋ぎ留めていた。
3年後、鎖を解かれ王城に連れ去られたセレは、光の勇者としてノアールの前に戻ってきた。それは、ノアールの罪を裁く、滅却の剣。
ノアールが死を受け入れる中、勇者セレが選んだのは、王城の命令に背き、彼を殺さずに再び鎖で繋ぎ直すという、最も歪んだ復讐だった。
「お前は俺の獲物だ。誰にも殺させないし、絶対に離してなんかやらない」
孤独と憎悪に囚われた勇者は、魔王を「復讐の道具」として秘密裏に支配下に置く。しかし、制御不能な力を持つ勇者を恐れた王城は、ついに二人を排除するための罠を仕掛ける。
歪んだ愛憎と贖罪が絡み合う、光と闇の立場が逆転した物語――彼らの運命は、どこへ向かうのか。

何故よりにもよって恋愛ゲームの親友ルートに突入するのか
風
BL
平凡な学生だったはずの俺が転生したのは、恋愛ゲーム世界の“王子”という役割。
……けれど、攻略対象の女の子たちは次々に幸せを見つけて旅立ち、
気づけば残されたのは――幼馴染みであり、忠誠を誓った騎士アレスだけだった。
「僕は、あなたを守ると決めたのです」
いつも優しく、忠実で、完璧すぎるその親友。
けれど次第に、その視線が“友人”のそれではないことに気づき始め――?
身分差? 常識? そんなものは、もうどうでもいい。
“王子”である俺は、彼に恋をした。
だからこそ、全部受け止める。たとえ、世界がどう言おうとも。
これは転生者としての使命を終え、“ただの一人の少年”として生きると決めた王子と、
彼だけを見つめ続けた騎士の、
世界でいちばん優しくて、少しだけ不器用な、じれじれ純愛ファンタジー。

残念でした。悪役令嬢です【BL】
渡辺 佐倉
BL
転生ものBL
この世界には前世の記憶を持った人間がたまにいる。
主人公の蒼士もその一人だ。
日々愛を囁いてくる男も同じ前世の記憶があるらしい。
だけど……。
同じ記憶があると言っても蒼士の前世は悪役令嬢だった。
エブリスタにも同じ内容で掲載中です。

貴方に復讐しようと、思っていたのに。
黒狐
BL
前世、馬車の事故で亡くなった令嬢(今世は男)の『私』は、幽霊のような存在になってこの世に残っていた。
婚約者である『彼』が私と婚約破棄をする為に細工をしたのだと考え、彼が無惨な末路を迎える様を見てやろうと考えていた。
しかし、真実はほんの少し違っていて…?
前世の罪や罰に翻弄される、私と彼のやり直しの物語。
⭐︎一部残酷な描写があります、ご注意下さい。

劣等アルファは最強王子から逃げられない
東
BL
リュシアン・ティレルはアルファだが、オメガのフェロモンに気持ち悪くなる欠陥品のアルファ。そのことを周囲に隠しながら生活しているため、異母弟のオメガであるライモントに手ひどい態度をとってしまい、世間からの評判は悪い。
ある日、気分の悪さに逃げ込んだ先で、ひとりの王子につかまる・・・という話です。
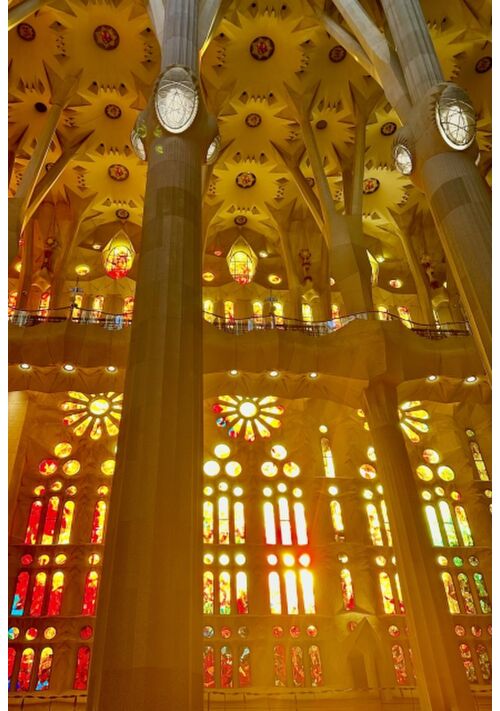
優秀な婚約者が去った後の世界
月樹《つき》
BL
公爵令嬢パトリシアは婚約者である王太子ラファエル様に会った瞬間、前世の記憶を思い出した。そして、ここが前世の自分が読んでいた小説『光溢れる国であなたと…』の世界で、自分は光の聖女と王太子ラファエルの恋を邪魔する悪役令嬢パトリシアだと…。
パトリシアは前世の知識もフル活用し、幼い頃からいつでも逃げ出せるよう腕を磨き、そして準備が整ったところでこちらから婚約破棄を告げ、母国を捨てた…。
このお話は捨てられた後の王太子ラファエルのお話です。

君さえ笑ってくれれば最高
大根
BL
ダリオ・ジュレの悩みは1つ。「氷の貴公子」の異名を持つ婚約者、ロベルト・トンプソンがただ1度も笑顔を見せてくれないことだ。感情が顔に出やすいダリオとは対照的な彼の態度に不安を覚えたダリオは、どうにかロベルトの笑顔を引き出そうと毎週様々な作戦を仕掛けるが。
(クーデレ?溺愛美形攻め × 顔に出やすい素直平凡受け)
異世界BLです。

隊長さんとボク
ばたかっぷ
BL
ボクの名前はエナ。
エドリアーリアナ国の守護神獣だけど、斑色の毛並みのボクはいつもひとりぼっち。
そんなボクの前に現れたのは優しい隊長さんだった――。
王候騎士団隊長さんが大好きな小動物が頑張る、なんちゃってファンタジーです。
きゅ~きゅ~鳴くもふもふな小動物とそのもふもふを愛でる隊長さんで構成されています。
えろ皆無らぶ成分も極小ですσ(^◇^;)本格ファンタジーをお求めの方は回れ右でお願いします~m(_ _)m
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















