7 / 10
第一幕 新しい世界
第六話
しおりを挟む
ジークフリートは疲れきった表情で、城の離れにある自分専用の小さな館へと帰ってきた。
この館は、寝室を初めとした二、三の部屋から成っている小さなもので、三年ほど前にリヒャルトから貰ったものである。
もちろん自室は城内にもあるのだが、ジークフリートはそこにいると大勢の使用人たちの目や客人たちの出入りが気になり、常々それを煩わしく感じていた。
そんなある日のこと、いつものようにリヒャルトに何か欲しいものはあるかと聞かれたので、ジークフリートは病弱なことを理由に静かで落ち着いて休める場所が欲しいと、冗談半分で彼に言ってみた。
すると、リヒャルトはこれに快く承諾してくれたのである。元・使用人の館で空き家になっていたところをすぐさま改築し、ジークフリートに専用の離れとして何のためらいもなくリヒャルトは与えてくれた。
これにはさすがのジークフリートも驚いたが、喧騒から離れたいという気持ちの方が強かったので、気が咎めたもののこの好意に甘えることにしたのだった。
この館を貰ってからというもの、ジークフリートはほとんど毎日といっていいほどそこで生活するようになった。本来ならば食事は家族そろってするものであったが、彼はまたもや体の調子が悪いと言っては食事すらもそこで取るようにしていた。ジークフリートに甘いリヒャルトは、無理をしてはならないからと彼を咎めたりはせず好きなようにさせていた。(もちろん、ジークムントはそのことについて怒っているが)そのおかげで、ジークフリートの引きこもり癖は増す一方であった。
「お帰りなさいませ、ジークフリート様。」
ジークフリートが館の扉を開けると、そこには黒の給仕服を着た若い男が立っていた。
年のころは二十代後半、黒い髪に緑色の瞳。この男の名前は、ルードヴィヒ・ヒンデンブルクといい、ヴァルティである。
ルードヴィヒの母親はエルダお抱えの使用人の一人で、彼もまた、幼い頃よりヴァルハラ家に仕えてきた。そしてジークフリートが生まれると、彼専任の執事になるよう任されたのであった。物心ついた時からずっとルードヴィヒはそばにいたので、ジークフリートも彼には少なからず本心が言えるようである。
「今、お茶をお入れしますね。・・・どうでしたか、薔薇祭は?」
「疲れた・・・。」
ジークフリートは一言そう言うと、ソファにどさっと倒れこむようにして座った。ルードヴィヒはそれを見て、くすっと笑った。
「ジークフリート様は、いつもそうおっしゃいますね。」
「じゃあ、聞かないで。」
ふてくされたようにジークフリートが言うと、“申し訳ありません”とルードヴィヒは、ちっとも反省していない口調で応じた。
「どうぞ。」
ルードヴィヒは、紅茶の入ったカップをジークフリートに手渡した。ジークフリートはそれを受け取ると、ため息交じりで再び話しはじめた。
「あと・・・ジークムントに嫌味を言われたよ・・・。」
「ジークムント様にですか?・・・これもまた、いつもの如く・・・ですね。」
「あぁ、どうすれば仲良くなれるのだろうか・・・。僕は努力しているつもりなのに・・・。」
「ジークフリート様の方から、もっとお話をされてはどうですか?」
「僕が・・・?ジークムントに?・・・話すことなんて何も。」
それを聞いてルードヴィヒは、毎度のことながらと呆れた。毎回ジークフリートは仲良くしたいのにとぼやいてはこの始末。この兄弟の仲はずっとこの調子なのではないかと、ルードヴィヒはその度に思っていた。
「せっかくよい気持ちでいたところに・・・・・・ああ!そうだった!!」
ジークフリートは何かを思い出したようにそう言うと、立ち上がって嬉しそうな顔でルードヴィヒを見上げた。
「そう!ルーイ、聞いて!今日、すてきな人に出会ったよ。」
「すてきな人・・・ですか?」
「うん。ウィンダミア侯爵といってね、カレンに住んでいらっしゃるからと義父さんが紹介してくれたのだけど・・・・まだ若いのに貫禄があって、紳士的で・・・とても感じのよい方だった・・・。」
普段、他人に無関心のジークフリートが夢見心地で次々と喋る姿にルードヴィヒは驚いた。
「・・・めずらしいですね。ジークフリート様がそこまでおっしゃるなんて。」
「ん?そうかな?・・・でも、本当にすてきな方なんだよ。僕も侯爵を見習わなければ・・・。」
いつも口数が少なく、暗い表情ばかりのジークフリートが嬉しそうに話すのを見て、ルードヴィヒもにこにこと微笑む。
「ああ、そういえばリヒャルト様からプレゼントを預かっておりますよ。」
「プレゼント?それならさっき会った時に渡せばよかったのに・・・。」
「それですと、ジークフリート様がお受け取りにならないからでしょう。・・・あちらにお置きしておりますのでご覧下さい。」
見ると、暖炉のそばに綺麗に包装された箱が山積みになって置いてある。
「こんなに・・・?」
「はい。ジークフリート様のお好きなチョコレート、それから外出用の洋服、あとは確か・・・宝飾類もあるとお聞きしました。」
それを聞いてジークフリートは呆れかえり、ため息を吐いた。
「あぁ・・・。洋服はこの前貰ったばかりなのに・・・また、こんなにも・・・。」
「ジークフリート様がアカデミーに行かれるので、リヒャルト様もお寂しいのでしょう・・・。」
「寂しい・・・ね。・・・ルーイ、僕はそのうちこの館を改築して、ミュージアムでもつくることにするよ・・・。」
ジークフリートはそんな皮肉を言うと、納得のいかなさそうな顔でプレゼントの箱の一つを手に取った。ワインレッドの包装にかかるゴールドのリボンをジークフリートがほどいていると、ふいにルードヴィヒが口を開いた。
「・・・・・・でも、本当に行ってしまわれるのですね。・・・私も寂しくなります。」
それを聞いたジークフリートは、持っていた箱をソファに放り投げるとルードヴィヒに抱きついた。
「あぁ、ルーイ・・・僕もだよ。ルーイも連れていけたら・・・!」
「・・・それでは、あまり意味がないでしょう?」
ルードヴィヒはくすっと笑った。
「アカデミーは、きっとすてきな所ですよ。・・・私はここから毎日、ジークフリート様のことを想っています。」
「ルーイ・・・ありがとう・・・。」
ジークフリートは寂しそうに微笑むと、ルードヴィヒの両頬にキスをした。
これから、この城を出て新しい生活が始まる。ルードヴィヒとも離れ、初めて城以外の場所で生活するジークフリートにとってそれは不安であったが、重い鎖につながれたこの牢獄から出ることができるのなら・・・と、彼は見知らぬ自由の土地に期待や様々な思いを馳せてやまなかった。
この館は、寝室を初めとした二、三の部屋から成っている小さなもので、三年ほど前にリヒャルトから貰ったものである。
もちろん自室は城内にもあるのだが、ジークフリートはそこにいると大勢の使用人たちの目や客人たちの出入りが気になり、常々それを煩わしく感じていた。
そんなある日のこと、いつものようにリヒャルトに何か欲しいものはあるかと聞かれたので、ジークフリートは病弱なことを理由に静かで落ち着いて休める場所が欲しいと、冗談半分で彼に言ってみた。
すると、リヒャルトはこれに快く承諾してくれたのである。元・使用人の館で空き家になっていたところをすぐさま改築し、ジークフリートに専用の離れとして何のためらいもなくリヒャルトは与えてくれた。
これにはさすがのジークフリートも驚いたが、喧騒から離れたいという気持ちの方が強かったので、気が咎めたもののこの好意に甘えることにしたのだった。
この館を貰ってからというもの、ジークフリートはほとんど毎日といっていいほどそこで生活するようになった。本来ならば食事は家族そろってするものであったが、彼はまたもや体の調子が悪いと言っては食事すらもそこで取るようにしていた。ジークフリートに甘いリヒャルトは、無理をしてはならないからと彼を咎めたりはせず好きなようにさせていた。(もちろん、ジークムントはそのことについて怒っているが)そのおかげで、ジークフリートの引きこもり癖は増す一方であった。
「お帰りなさいませ、ジークフリート様。」
ジークフリートが館の扉を開けると、そこには黒の給仕服を着た若い男が立っていた。
年のころは二十代後半、黒い髪に緑色の瞳。この男の名前は、ルードヴィヒ・ヒンデンブルクといい、ヴァルティである。
ルードヴィヒの母親はエルダお抱えの使用人の一人で、彼もまた、幼い頃よりヴァルハラ家に仕えてきた。そしてジークフリートが生まれると、彼専任の執事になるよう任されたのであった。物心ついた時からずっとルードヴィヒはそばにいたので、ジークフリートも彼には少なからず本心が言えるようである。
「今、お茶をお入れしますね。・・・どうでしたか、薔薇祭は?」
「疲れた・・・。」
ジークフリートは一言そう言うと、ソファにどさっと倒れこむようにして座った。ルードヴィヒはそれを見て、くすっと笑った。
「ジークフリート様は、いつもそうおっしゃいますね。」
「じゃあ、聞かないで。」
ふてくされたようにジークフリートが言うと、“申し訳ありません”とルードヴィヒは、ちっとも反省していない口調で応じた。
「どうぞ。」
ルードヴィヒは、紅茶の入ったカップをジークフリートに手渡した。ジークフリートはそれを受け取ると、ため息交じりで再び話しはじめた。
「あと・・・ジークムントに嫌味を言われたよ・・・。」
「ジークムント様にですか?・・・これもまた、いつもの如く・・・ですね。」
「あぁ、どうすれば仲良くなれるのだろうか・・・。僕は努力しているつもりなのに・・・。」
「ジークフリート様の方から、もっとお話をされてはどうですか?」
「僕が・・・?ジークムントに?・・・話すことなんて何も。」
それを聞いてルードヴィヒは、毎度のことながらと呆れた。毎回ジークフリートは仲良くしたいのにとぼやいてはこの始末。この兄弟の仲はずっとこの調子なのではないかと、ルードヴィヒはその度に思っていた。
「せっかくよい気持ちでいたところに・・・・・・ああ!そうだった!!」
ジークフリートは何かを思い出したようにそう言うと、立ち上がって嬉しそうな顔でルードヴィヒを見上げた。
「そう!ルーイ、聞いて!今日、すてきな人に出会ったよ。」
「すてきな人・・・ですか?」
「うん。ウィンダミア侯爵といってね、カレンに住んでいらっしゃるからと義父さんが紹介してくれたのだけど・・・・まだ若いのに貫禄があって、紳士的で・・・とても感じのよい方だった・・・。」
普段、他人に無関心のジークフリートが夢見心地で次々と喋る姿にルードヴィヒは驚いた。
「・・・めずらしいですね。ジークフリート様がそこまでおっしゃるなんて。」
「ん?そうかな?・・・でも、本当にすてきな方なんだよ。僕も侯爵を見習わなければ・・・。」
いつも口数が少なく、暗い表情ばかりのジークフリートが嬉しそうに話すのを見て、ルードヴィヒもにこにこと微笑む。
「ああ、そういえばリヒャルト様からプレゼントを預かっておりますよ。」
「プレゼント?それならさっき会った時に渡せばよかったのに・・・。」
「それですと、ジークフリート様がお受け取りにならないからでしょう。・・・あちらにお置きしておりますのでご覧下さい。」
見ると、暖炉のそばに綺麗に包装された箱が山積みになって置いてある。
「こんなに・・・?」
「はい。ジークフリート様のお好きなチョコレート、それから外出用の洋服、あとは確か・・・宝飾類もあるとお聞きしました。」
それを聞いてジークフリートは呆れかえり、ため息を吐いた。
「あぁ・・・。洋服はこの前貰ったばかりなのに・・・また、こんなにも・・・。」
「ジークフリート様がアカデミーに行かれるので、リヒャルト様もお寂しいのでしょう・・・。」
「寂しい・・・ね。・・・ルーイ、僕はそのうちこの館を改築して、ミュージアムでもつくることにするよ・・・。」
ジークフリートはそんな皮肉を言うと、納得のいかなさそうな顔でプレゼントの箱の一つを手に取った。ワインレッドの包装にかかるゴールドのリボンをジークフリートがほどいていると、ふいにルードヴィヒが口を開いた。
「・・・・・・でも、本当に行ってしまわれるのですね。・・・私も寂しくなります。」
それを聞いたジークフリートは、持っていた箱をソファに放り投げるとルードヴィヒに抱きついた。
「あぁ、ルーイ・・・僕もだよ。ルーイも連れていけたら・・・!」
「・・・それでは、あまり意味がないでしょう?」
ルードヴィヒはくすっと笑った。
「アカデミーは、きっとすてきな所ですよ。・・・私はここから毎日、ジークフリート様のことを想っています。」
「ルーイ・・・ありがとう・・・。」
ジークフリートは寂しそうに微笑むと、ルードヴィヒの両頬にキスをした。
これから、この城を出て新しい生活が始まる。ルードヴィヒとも離れ、初めて城以外の場所で生活するジークフリートにとってそれは不安であったが、重い鎖につながれたこの牢獄から出ることができるのなら・・・と、彼は見知らぬ自由の土地に期待や様々な思いを馳せてやまなかった。
0
あなたにおすすめの小説

復讐の鎖に繋がれた魔王は、光に囚われる。
篠雨
BL
予言の魔王として闇に閉ざされた屋敷に隔離されていたノアール。孤独な日々の中、彼は唯一の光であった少年セレを、手元に鎖で繋ぎ留めていた。
3年後、鎖を解かれ王城に連れ去られたセレは、光の勇者としてノアールの前に戻ってきた。それは、ノアールの罪を裁く、滅却の剣。
ノアールが死を受け入れる中、勇者セレが選んだのは、王城の命令に背き、彼を殺さずに再び鎖で繋ぎ直すという、最も歪んだ復讐だった。
「お前は俺の獲物だ。誰にも殺させないし、絶対に離してなんかやらない」
孤独と憎悪に囚われた勇者は、魔王を「復讐の道具」として秘密裏に支配下に置く。しかし、制御不能な力を持つ勇者を恐れた王城は、ついに二人を排除するための罠を仕掛ける。
歪んだ愛憎と贖罪が絡み合う、光と闇の立場が逆転した物語――彼らの運命は、どこへ向かうのか。

何故よりにもよって恋愛ゲームの親友ルートに突入するのか
風
BL
平凡な学生だったはずの俺が転生したのは、恋愛ゲーム世界の“王子”という役割。
……けれど、攻略対象の女の子たちは次々に幸せを見つけて旅立ち、
気づけば残されたのは――幼馴染みであり、忠誠を誓った騎士アレスだけだった。
「僕は、あなたを守ると決めたのです」
いつも優しく、忠実で、完璧すぎるその親友。
けれど次第に、その視線が“友人”のそれではないことに気づき始め――?
身分差? 常識? そんなものは、もうどうでもいい。
“王子”である俺は、彼に恋をした。
だからこそ、全部受け止める。たとえ、世界がどう言おうとも。
これは転生者としての使命を終え、“ただの一人の少年”として生きると決めた王子と、
彼だけを見つめ続けた騎士の、
世界でいちばん優しくて、少しだけ不器用な、じれじれ純愛ファンタジー。

残念でした。悪役令嬢です【BL】
渡辺 佐倉
BL
転生ものBL
この世界には前世の記憶を持った人間がたまにいる。
主人公の蒼士もその一人だ。
日々愛を囁いてくる男も同じ前世の記憶があるらしい。
だけど……。
同じ記憶があると言っても蒼士の前世は悪役令嬢だった。
エブリスタにも同じ内容で掲載中です。

貴方に復讐しようと、思っていたのに。
黒狐
BL
前世、馬車の事故で亡くなった令嬢(今世は男)の『私』は、幽霊のような存在になってこの世に残っていた。
婚約者である『彼』が私と婚約破棄をする為に細工をしたのだと考え、彼が無惨な末路を迎える様を見てやろうと考えていた。
しかし、真実はほんの少し違っていて…?
前世の罪や罰に翻弄される、私と彼のやり直しの物語。
⭐︎一部残酷な描写があります、ご注意下さい。

劣等アルファは最強王子から逃げられない
東
BL
リュシアン・ティレルはアルファだが、オメガのフェロモンに気持ち悪くなる欠陥品のアルファ。そのことを周囲に隠しながら生活しているため、異母弟のオメガであるライモントに手ひどい態度をとってしまい、世間からの評判は悪い。
ある日、気分の悪さに逃げ込んだ先で、ひとりの王子につかまる・・・という話です。
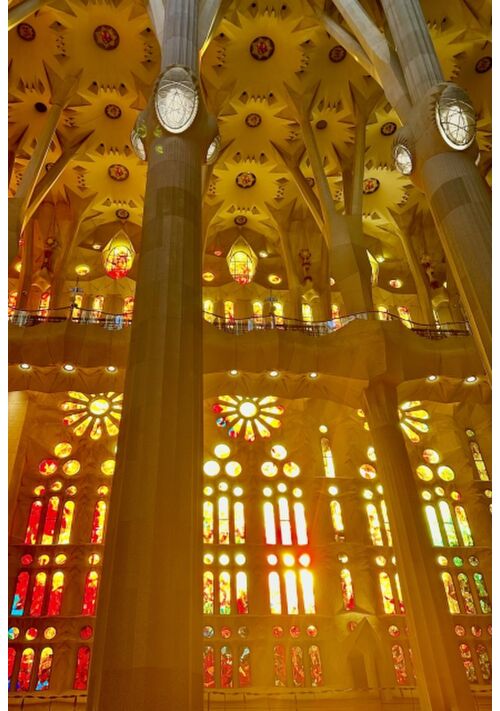
優秀な婚約者が去った後の世界
月樹《つき》
BL
公爵令嬢パトリシアは婚約者である王太子ラファエル様に会った瞬間、前世の記憶を思い出した。そして、ここが前世の自分が読んでいた小説『光溢れる国であなたと…』の世界で、自分は光の聖女と王太子ラファエルの恋を邪魔する悪役令嬢パトリシアだと…。
パトリシアは前世の知識もフル活用し、幼い頃からいつでも逃げ出せるよう腕を磨き、そして準備が整ったところでこちらから婚約破棄を告げ、母国を捨てた…。
このお話は捨てられた後の王太子ラファエルのお話です。

君さえ笑ってくれれば最高
大根
BL
ダリオ・ジュレの悩みは1つ。「氷の貴公子」の異名を持つ婚約者、ロベルト・トンプソンがただ1度も笑顔を見せてくれないことだ。感情が顔に出やすいダリオとは対照的な彼の態度に不安を覚えたダリオは、どうにかロベルトの笑顔を引き出そうと毎週様々な作戦を仕掛けるが。
(クーデレ?溺愛美形攻め × 顔に出やすい素直平凡受け)
異世界BLです。

隊長さんとボク
ばたかっぷ
BL
ボクの名前はエナ。
エドリアーリアナ国の守護神獣だけど、斑色の毛並みのボクはいつもひとりぼっち。
そんなボクの前に現れたのは優しい隊長さんだった――。
王候騎士団隊長さんが大好きな小動物が頑張る、なんちゃってファンタジーです。
きゅ~きゅ~鳴くもふもふな小動物とそのもふもふを愛でる隊長さんで構成されています。
えろ皆無らぶ成分も極小ですσ(^◇^;)本格ファンタジーをお求めの方は回れ右でお願いします~m(_ _)m
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















