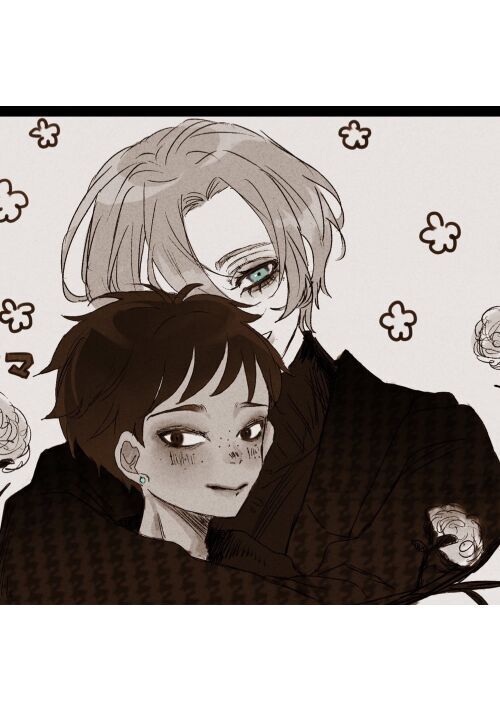34 / 37
dessert:美食
2.「弔餐会」
しおりを挟む12月22日深夜零時。ホーム――海辺の教会へ帰って参りました。
「僕も行く」、と最後まで粘っていたモアを屋敷に残し、同行してくれたのはアールです。
「これだけは譲れない」と発した後、エルにバトンタッチしてしまいましたが。
「アー……エル、足元気をつけてくださいね。階段が急ですから」
「お気遣いどうも。今度呼び間違えたら、酷いことになるからな」
突然暴れられるのだけは勘弁です。まったく、なぜこのタイミングで入れ替わってしまったのか。
エルと小声で言い合ううちに、礼拝堂の入り口までたどり着きました。途端に、忘れていた震えが指先へ戻ってきます。
あぁ神様、お父様――もはや私に、シスターとして祈る資格はありませんが。それでも「ロリッサ」として祈ることをお許しください。
屋根の天辺にそびえる十字架を見上げ、祈りを捧げます。シスター・アグネスが困難な任務へ向かう時も、まだ幼いブラザーが高熱を出した時も、ずっとこうしてきたのです。
やがて祈りの手に、温かい手が重なりました。
「そんなものに縋るな。自分の目で見て、事実を受け止めろよ」
迷いのないエルの横顔に、ゆっくり頷きます。
礼拝堂のドアを開くと、真夜中の懺悔室に明かりが灯っていました。壁の向こうから、かすかに人の気配がします。
「こんばんは」、と小窓に声をかけてみると。窓の隙間から、シワの寄った細い手が伸びてきました。
「えっ?」
「招待状を渡せってことだろ」
アールに促されるまま、ノットから受け取っていた封筒を老婆へ手渡すと。「お待ちしておりました」と、しわがれ声が響きました。
ドアが開かれた先には、黒いローブのご老人が待っていました。まったく知らない方が、なぜウチの懺悔室に入り込んでいるのでしょう。
彼女はランタンを揺らしながら、地下収納の蓋を開きます。普段ものが詰め込まれているそこは空になっていて、さらに下へ続く階段がありました。
「こんなものがあるなんて、知らなかったわ」
エルの手を借り、古い石段を降りていくと。その先には、礼拝堂と同等の広さを誇るホールが広がっていました。
古めかしい鉄製のシャンデリアの下、仮面をつけた高貴な方々が十数名あまり。老若男女問わず、5つある真紅の円卓に着席しています。
歓談中の彼らは私たちがホールに降り立つと、一斉に静まり返りました。
「ようこそ、最後のお客様」
囁き声や好奇の視線が飛び交う中。祭壇へと続く道の先から、仮面をつけた祭服の男性が近づいてきます。
「あなた方はこちらのお席へどうぞ」
彼がノットに違いないと、声を聞く間もなく分かりました。
エルとこっそり視線を交わし、案内されるままに無人の円卓へ着席しました。
これがグルマンディーズの集い――会長の合図によって、秘密の晩餐会がはじまりました。誰もがマナーを取り払い、テーブルを彩る料理を貪っています。
銀のナイフとフォークを自由に切って、刺して。
「おい。何を出されても食べるなよ」
「言われなくても分かってます! 食事に来たわけじゃありませんし」
やがてメインディッシュの肉料理が、黒いローブの給仕係によって振る舞われるようになった頃。ふと、正面の祭壇に乗っている棺桶に目が行きました。
「食事の席に棺桶って……どうして?」
呟きに対し、エルは無言のままナイフを手に取りました。ソテーを切り分け、ミディアムに焼けた中を観察しています。
「ちょっと、食べるなってさっき自分で――」
「食べないよ。確認してるだけ」
何の確認か尋ねようとする前に、グラスの音がはっきりと響き渡りました。やがて祭壇前に立つノットが、静まり返った空間で一礼します。
「今晩は『特別会員』の皆様ご存知の通り。急遽、刑を受けた彼を弔う会となります。彼は我らがグルマンディーズ12年来のメンバー、そして――食人鬼(グルマン)でもありました」
食人鬼はやはりグルマンディーズの一員――。
「メインディッシュの前に……彼の人生を回顧し、代わりに告解をいたしましょう」
ノットが「彼」と呼ぶ食人鬼は、医者の息子として生まれた、平民ながらも裕福な家の子どもだったといいます。信心深い彼はやがて医者ではなく司祭の道を志し、神学校へ入学。勉学に秀でていた彼は驚異的な速さで出世し、ついにはビショップの位にまで昇進。この教会の筆頭神父に――。
「ウソ! そんなはず……だってビショップは、お父様は……」
円卓に足をかけ、飛びあがろうとした瞬間。エルに足と腕を掴まれました。
なぜそんな嘘をつくのか。今すぐノットの側に駆けつけて問いただしたいのですが。
「お願いです。どうか最後までお聞きください」
仮面の下から漂う深い苦しみの影に、これ以上体が動かなくなりました。「今は耐えて」、とエルに元のイスへ引きずり降ろされます。
「彼は真に神の代行者、誰に対しても慈悲深いお方でした。それはここにいらっしゃる皆様も、よくご存知のことでしょう」
エルのビクともしない手を振り解くことができれば、今すぐ悪ふざけを止めさせられるというのに。
「改めて申し上げますが、私は生まれながらの『美食家(グルメ)』です」
「は……?」
途端に緩んだエルの手が、力なく離れていきました。
「エル、騙されないで! それもウソに決まって――」
「嘘ではありません」
妙な迫力を帯びた否定に、先の言葉が途切れました。
以前モアが図書館で教えてくれたことが、今になって鮮明に浮かび上がります。ノットが「美食家」というのなら、彼は――人の肉を喰らう者。
「ですが家系図にあったノットの実には、ナイフとフォークの印はありませんでした」
「時勢に合わせて、父母はこの事実を他の家族にまで秘匿し、私は人と違うことへの恐怖に苛まれながら生きていました。ですがとある医師の紹介でビショップ――神父エブライヒと出会った15歳のある日。私は自分の生まれ持った性質を前向きに受け入れることができたのです」
そんな、私は――。
「魔人病について研究していた彼は、私を真に理解しようと、なんと自らも『美食家』になりました。私は彼の献身に……深く感動しました。初めて、他人から受け入れられたのです。誰にも打ち明けることのできない、私の性質を」
ノットのことも、そしてお父様のことも、何ひとつ知らなかったのです。愛すべき家族、守りたい小さな世界――そんな彼らについて、何ひとつ。
「では、いかにして彼が『食人家』ではなく『食人鬼』となってしまったのか。それは皆さんもご存知の通り、人肉が常人にとって高いリスクを伴う食材であることが原因なのです。彼は魔人病を患ってしまった」
魔人病――たしかにビショップは、ここのところ体調を崩していらっしゃいました。ですがそれは、本当にここ数か月の話です。食人鬼の最初の被害者は、もう1年近く前だというのに。
「ビショップはこの十年以上、特に変わった様子はありませんでした。人肉の素晴らしさを知り、罪人の肉体を弔うグルマンディーズの集会に参加してくださること以外は」
本当に、至って常人だった。そうノットは続けます。しかし1年前に異変が始まった、とも。
「『肉が食べたい』……そう口にすることが多くなったのです。それでも些細な事だったので放っておいたのですが――正義を隠れ蓑に、ビショップは非公式な食事を始めるようになりました」
ノットが食人鬼の正体に気づき始めたのは3か月前、3人目の犠牲者が出た後。そして食人鬼がビショップだと確信したのは、私とノットが事件現場で鉢合わせたあの夜。
後日ノットがビショップへ証拠を突きつけても、彼はとぼけた様子もなく否定したといいます。すでに記憶と意識の混濁が起き、自身の犯行であることを認識できていなかった、と。
「こうして世間を騒がす食人鬼は生まれました……そして先日。すべての犠牲者に関する証拠を集め、彼を現行犯で捕えたことで、ようやく彼を裁くに至ったのです」
そこまで話し終えたノットは、赤ワインのグラスを掲げました。
「さぁ、同志の皆様。代理の告解を終えた今、我々がすることはただひとつ……杯をお取りください」
涙を流すメンバーは次々と杯を取り、天に向けて掲げています。「エブライヒに」、と。
再び賑わいを取り戻した円卓の中、ここだけがまるで別空間のようでした。固まっているエルを横目に立ち上がり、今度こそノットへ近づいていきます。一歩進むごとに生暖かい液体で手のひらが濡れるのも構わず、棺桶のある祭壇まで。
「ノット……」
「ロリッサ……私も信じられない気持ちです。ですがあなたには、彼の行いのすべてを聞く権利があるはず。ですから、その前にせめてひと目だけでも。ビショップのお顔を拝見してください」
一粒も信じられない気持ちが止まらず、棺桶の蓋が開いてもそれは同じでした。ですがいざ亡骸の顔を目にすると――白ユリの中眠るお顔は、見間違えようもありません。
7歳の頃からずっと私の父として、時には師として導いてくださった彼――。
「お父、さま……」
花に囲まれ眠るビショップの、蒼白のお顔に手を伸ばすと。一滴の赤が指を伝い、頬に小さな花が咲きます。花を愛し、花に囲まれて笑っていた人――ですが、白ユリは少しも似合いません。
やがて白に塗り潰されていく視界の端に、黒い外套がチラつきました。振り返ると、エルが肩を支えてくれています。
「そろそろ俺にも種明かししろよ、ノット」
憤怒を秘めた赤眼が睨みつけているのは、棺を黙って見降ろしているノットです。
「取引の通り、俺たちはこいつに『食人鬼じゃない』と言わなかった」
「え……?」
エルとアールが私に、身の潔白を主張しなかった――説明を求めても、肩を掴む力が強まるだけでした。
「ご先祖様の肖像を破壊しようが、紋章に唾吐きかけようが、俺たちが忌々しい『マダーマム』だってことは死ぬまで変わらない。神職に就いたってな。よく分かってるだろ? だったら家族として、俺の信頼に相応しい誠意を見せろよ」
血が滲むほど肩に食い込んだ、エルの右手。そこにそっと手を添えると「ごめん」と、らしくない言葉と共に手が離れていこうとします。
赤く濡れたエルの指先をとっさに掴み、俯いたままのノットを見上げました。
「どうしてお父様もノットも、ずっと黙っていたの? どうしてお父様が、こんなことに……っ」
「私は救えなかった……いえ。こうなったのも、すべて私のせいなんです」
美食と美談に酔いしれる歓声の中。ノットが話してくれたのは、ここへ至るまでに何度も聞いた病の話でした。魔人病によって起こる意識の混濁――ビショップは空腹になると理性を失いつつあったというのです。
それが発症したのは、10か月前。
「覚えていますか? 1人目の被害者、リィンベル嬢は天文塔職員ハーモニア伯のご子息。ハーモニア伯は黎明教会を『権力を持ち過ぎた危険分子』と裏で弾劾し、当教会にも何かと面倒ごとを押し付けていらっしゃいました」
ノットとポッピング菓子店の裏にある古宿を調査したことは覚えています。ですが、ハーモニア伯と教会のしがらみについては何も知りません。あの時、ノットはそこまで詳しく教えてくれませんでした。
「2人目の被害者、ゾルディ夫人。彼女の夫である町の神父にはあなたも一緒にお会いしましたね。彼は教義の革新を進める立場でありながら、天文塔への非公式なパイプをいくつも築き、教会内部の腐敗を進めていました」
1人目、2人目――つまりノットが言いたいことは、動機です。食人鬼が彼女たちを的確に狙ったのは、教会を脅かす人物たちを苦しめるため、その親族を狙ったのだと。
「ここまでは、食欲を抑えきれない自らの食事(おこない)を正当化するため。ですが3件目からはそれほどの理性すらなくなり、食欲のままに殺人を犯し食事を行った……これまで完璧だった証拠隠滅も、粗が出るようになったのです」
粗と言っても、天文塔の職員ですら気づかなかったようなことです。それを3件目が起こった時点で、ノットはビショップが犯人だと気づいたというのです。それは同じ嗜好をもつからこそ分かる点だったと、ノットは告白しました。
「最初は正面から諭そうと、探りを入れつつビショップを説得しようとしました。ですが記憶が混濁しているのか聞く耳を持たず……その間にも、4人目の犠牲者が出てしまったのです。ビショップを尾行したというのに、犯行を防げなかった」
「じゃあ、あの夜私が見たのはやっぱり……」
「まさかつけられているとは思いませんでした。よりにもよって、あなたに」
ノットがマダーマム家の敷地へ帰っていくところ。その場面を、私はあの夜目撃したというのです。
「なるほどね。で、3件目以降は証拠があったのに、すぐに神父様を告発しなかったのは何でさ。こいつと一緒に捜査ごっこがしたかったわけじゃないだろ?」
「すでに申し上げた通り、1から2件目までの証拠隠滅は完璧でした。そして最初は動機も見抜けなかった。先ほどお話したことはすべて、この3か月でようやく集めることができた情報ですから。彼の行ったすべてを断罪するためには、必要な時間だったと思います」
ノットとビショップの間にもまた、私が知ることのない絆があったはず。それでもノットはビショップを庇うのではなく、断罪を選択した――私がマダーマム家にいる間、それほどの覚悟をもって彼は動いていたというのです。
「『指輪を貸せ』っていうのは、お前の不注意で自分の指輪を拾われていたから、コイツからの疑いを逸らすためだったわけか。あとは『潜入してくるヤツの気を引け』、だったか?」
鋭い言葉に肩を揺らしたノットは、こちらへ遠慮がちな視線を向けました。それでもノットが口を噤んだままでいると、エルは喧騒に負けない声量で「言えよ」と放ちます。
「あなたが潜入捜査へ行く少し前、ビショップが『あなたを食べたい』と口にしたから」
私を、食べたい――?
「通常は理性がはたらくものです。理性をもって耐えれば、別の肉で代用できます。ですが先天的な食人家である私と違い、ビショップの精神と肉体は未熟なものでした。ここ最近はアグネスが気づくほど、食欲への制御が利かなくなっていたのです」
ビショップの具合が良くない。そう最初に教えてくれたのは、シスター・アグネスでした。ノットがビショップの不調を私に黙っていたのは、すべて知っていたから――。
「ビショップはよくできたお人でしたから、口にはしませんでしたが。他の誰よりも、特にあなたを大切にしていました。ですがその愛は、『魔人病』を発症した彼の中で執着に変わる……だからあなたを守るために、ビショップを裁くことを決意したのです」
「じゃあ古宿と町の教会の調査は、あれは食人鬼の正体を探るためじゃなくて――」
ビショップが食人鬼だという裏付けを補強するための、ただの材料探し。そう、ノットは低い声で囁きます。
「あなたがマダーマム家へ潜入すると聞いて、最初は気が気ではありませんでしたが……結果ビショップとあなたを引き離せたため、好都合でした」
「じゃあエルとアールに『潜入してくるヤツの気を引け』、なんてお願いをしてたのは……私の注意を、マダーマム家の中に引かせるため?」
ノットもエルも頷いてはくれませんでした。それでも分かります。私はまんまと無実の人たちを疑い続けていたのだと。
そして何も知らないうちに、世界の半分を失っていたのです。
「アハ、あはは……」
「そうだったんですね」、とノットを見上げた顔は、笑えていたのでしょうか。それとも泣いていたのでしょうか。
顔の感覚が薄れているのはさておき、どうしても気になることを尋ねておかねば。
「ねぇノット。お父様の『中身』はどこへやったの?」
なぜそんなに怯えたような目をするのでしょうか。ノットも、エルまでも。
支えてくれていたエルの手を離し、席からこっそり持ち出していた銀のナイフを握りました。その先端で、皿の上のメインディッシュを突き刺します。
「コレ、もしかして……あは、ははは」
どうりでお父様のお腹の中に、溢れんばかりの白ユリが詰まっているわけです。
「あぁ神様、お父様! みんな……だったのです」
愛する方たちの声がまったく聞こえない中、空洞を満たす咀嚼音だけがはっきりと聞こえてきました。お父様の肉を貪る、卑しい音が。
麗しき、忌々しき美食家の方々にナイフの切先を定めると。全身の血が煮え立つような、心地良い高揚感に包まれました。
「ロリッサ!」
誰かの呼び声に構わず、ナイフを振り上げた瞬間。
真っ暗な中に、身も心も転がり落ちていきました。目を開けようとしても瞼が開きません。聞こえない、感じない――ただ胸の中心で脈打つ、心臓以外の「何か」を感じます。
その「何か」の拍動は、愛しい彼らに触られた時に感じる「気持ちいい」と少しだけ似ていました。
応援ありがとうございます!
0
お気に入りに追加
24
1 / 2
この作品を読んでいる人はこんな作品も読んでいます!
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる