1 / 1
第一話 初恋
しおりを挟む
「なんであんなにかっこいいんだろうね~」
「ほんとほんと、めっちゃ好き!」
あれは小学6年生の修学旅行。夜の自由時間ではあたりまえのように恋バナをしていた。私の親友の彩が七瀬響のことを話していた。響というのは私達と同じクラスで顔よし、性格よし、それでいて勉強も運動もできる完璧な人で楓の好きな人。男子からも女子からも人気があって、「王子」なんて呼ばれてたり。確かにかっこいいし、少女漫画にでてくるような男の子だ。でも私は全く興味がなかった。私はもともと男の子と接するのが苦手であまり話したことがない。だから今まで男の子を好きになったことは一度もなかったし、恋する気持ちなんて分かるはずもない。恋をしたくないわけじゃない。私だって皆みたいに男の子と話したりして仲良くなりたい。でも男の子が苦手な私は自分から話しかけることなんて出来ず、もちろん相手から話しかけられることもないので男の子との接点はなかった。きっと私はこれから先恋をすることなんてないんだろう。そう諦めていた。
小学校を卒業して少し経った頃、私は父の急な転勤により新しい場所に引っ越しをすることになった。行く予定だった中学校には行けなくなる。つまり入学する中学校には小学校の時の友達が一人もいないということだ。小学校の時から転校は何回かしていた。転校して数週間はいつも休み時間などが一人、そんなのは当たり前だ。それだけならまだいい。二人組を組むときなんてクラスの人数が偶数なのに私の存在なんて知らないかのように三人組が一つできて私は一人で。漫画や小説だったら転校生って質問責めにあったりして、皆からたくさん話しかけられるのに現実はそんな甘くなくて。誰も話しかけてくれないし挨拶すらしてくれない。中学校に行ったらきっとクラス内では既にグループができてしまっているだろう。それなのに友達なんてできるのかな、と私は不安でたまらなかった。いつもそう、親の都合で仲良くなった友達ともあっさりお別れ。子供のことなんて考えてくれない。私はただでさえ人見知りで友達つくるのが下手なのに気にかけてもくれない。小学校の卒業式、私と親友三人は中学校で新しい友達ができてもずっと四人で一緒に学校に行くと約束したのに。卒業後に引っ越しが決まったためお別れも言えず、三人は私がいないことを知らない。自分達に引っ越すことを内緒にして一緒に学校に行く約束をしたなんて、ひどいと思われるだろう。そんなモヤモヤした嫌な気持ちのまま中学校生活は始まった。
春休みは昨日が最後だった。今日からは朝起きて制服を着て登校する。春休み何もする気がでなくて昼近くまで寝ていたことと、昨日の夜不安で眠れなかったせいで太陽の光がやけに眩しい。前を歩く三人組は仲良しグループだろうか。周りを見てみると皆友達と楽しそうに話しながら歩いている。一人で歩いているのは私だけ。約束していた親友のことを思い出して、一緒に行く友達がいる羨ましさと一人とぼとぼ歩く寂しさが一気にこみ上げてきた。学校に着いても私はずっと一人だった。こんなことならもう少し寝ておけばよかったと後悔しながら自分の席に静かに座っていた。知ってる人がいないので、最初は休み時間は絵を描いていた。すると前の席の星野明莉ちゃんが「わぁ、その絵上手だね!」
と笑顔で褒めてくれた。今まで人に褒められたことがなかったのでその一言がすごく嬉しかった。その日から明莉ちゃんと話すようになって毎日話しているうちに私の周りには人が増えていった。友達と話したり、遊んだりするのが楽しくて入学したばかりの頃の不安は嘘のように消えていった。
しばらくすると席替えをした。明莉ちゃんや他の友達とは結構離れてしまった。それだけではない。隣の席の楓芽君は静かであまり話さないから教科書忘れちゃったらどうしよう、話し合いできるかなとか色々気になっていた。私は小学校の時から算数が苦手だった。数学で分からない問題があった時、ちょうど隣同士で話し合いをすることになった。楓芽君のノートを見てみるとすでに答えがかいてあった。難しい問題で皆が苦戦しているのに解けちゃうなんてすごい。なんて思ってる場合じゃない。数学の先生は難しい問題になると隣同士で話し合いをさせる。そこまではいい。話し合いが終わると出席番号がかいてあるくじをひいて、出た番号の人が答えなければならない。だから誰があてるか分からないし、自分があたる可能性は充分にある。答えられなければ真面目に授業を受けていない、と怒られるのは有名な話だ。だからこの問題を理解しないといけない。私は解き方が全然わからない。でも話したことのない楓芽君に聞いて嫌な顔されるかもしれないと困っていた、その時だった。
「それ、さっきの方程式使えばできる。」
急に隣から声が聞こえてきてびっくり…え?隣?そっと隣を見ると楓芽君が私を見ていた。困っているのを察してくれたようで、分かりやすく説明してくれた。テストでもいい点をとっていて、頭の良さは私とでは比べものにならないくらいだった。そんな楓芽君と仲良くなれるのか心配になり、男の子が苦手な私はますます自分から話しかけられなかった。その日の昼の休み時間、「如月さん」と私を呼ぶ声が聞こえた。その声は隣からだったので楓芽君なのはすぐに分かった。横を見ると楓芽君が私に話し始めて、少し驚いた。特に大事な話じゃなかったから何で話しかけられたのか分からなかったけど笑顔で話してくれたことと、私を笑わせようとしてくれていたことからきっと話しかけやすいようにしてくれたんだろうと思った。最初は話しかけにくいと思っていたけど本当は優しくて面白かった。人は見かけによらないというのはこういう事なんだと改めて実感した。話していくうちに私と楓芽君は仲良くなって休み時間もよく話すように。ある時、好きな人の話をした。楓芽君の好きな人は小坂華さんという人で、趣味が同じで好きになったんだって。クラスは違うけど一度だけ見たことがあった。目はぱっちりで、顔が整っていて可愛かったので一度見ただけで記憶に残っていた。それに笑顔で友達と話しているのを見て、性格もよさそうだったので好きになるのも当たり前のような気がした。
中学校に入ってから二度目の席替え。楓芽君とは席が離れて話さなくなった。話さなくなると毎日が少し寂しくて。席替えなんてしたくなかったのに。楓芽君は私の友達と席が隣になって休み時間とかたくさん話していた。ただ話しているだけなのに二人が話しているのを見るとギュッと胸が締め付けられるように苦しかった。私の友達に笑顔で話さないでよ。その笑顔は私だけに向けてよ。そんなことを思ってしまう自分が恥ずかしくて仕方なかった。私って性格悪いなぁなんて。私は少しずつ思い始めていた。感じたことのない初めて知るこの複雑な気持ち、これが恋なのかもしれないということを。友達と話していても、授業を聞いていても、いつも頭の隅には楓芽君がいた。この恋が叶わないことなんて分かってる。これ以上傷つくのはもう嫌だ。気持ちを伝えちゃったらきっともう話せなくなってしまう、気まずくなりたくない。結局自分のことばかり考えているのに呆れながらもやっぱり友達のままでいたいと思った。友達のままでいれば毎日顔を見られるし、話すことだってできる。頭では理解しているのにこの気持ちを閉じ込めることは出来なかった。
「ほんとほんと、めっちゃ好き!」
あれは小学6年生の修学旅行。夜の自由時間ではあたりまえのように恋バナをしていた。私の親友の彩が七瀬響のことを話していた。響というのは私達と同じクラスで顔よし、性格よし、それでいて勉強も運動もできる完璧な人で楓の好きな人。男子からも女子からも人気があって、「王子」なんて呼ばれてたり。確かにかっこいいし、少女漫画にでてくるような男の子だ。でも私は全く興味がなかった。私はもともと男の子と接するのが苦手であまり話したことがない。だから今まで男の子を好きになったことは一度もなかったし、恋する気持ちなんて分かるはずもない。恋をしたくないわけじゃない。私だって皆みたいに男の子と話したりして仲良くなりたい。でも男の子が苦手な私は自分から話しかけることなんて出来ず、もちろん相手から話しかけられることもないので男の子との接点はなかった。きっと私はこれから先恋をすることなんてないんだろう。そう諦めていた。
小学校を卒業して少し経った頃、私は父の急な転勤により新しい場所に引っ越しをすることになった。行く予定だった中学校には行けなくなる。つまり入学する中学校には小学校の時の友達が一人もいないということだ。小学校の時から転校は何回かしていた。転校して数週間はいつも休み時間などが一人、そんなのは当たり前だ。それだけならまだいい。二人組を組むときなんてクラスの人数が偶数なのに私の存在なんて知らないかのように三人組が一つできて私は一人で。漫画や小説だったら転校生って質問責めにあったりして、皆からたくさん話しかけられるのに現実はそんな甘くなくて。誰も話しかけてくれないし挨拶すらしてくれない。中学校に行ったらきっとクラス内では既にグループができてしまっているだろう。それなのに友達なんてできるのかな、と私は不安でたまらなかった。いつもそう、親の都合で仲良くなった友達ともあっさりお別れ。子供のことなんて考えてくれない。私はただでさえ人見知りで友達つくるのが下手なのに気にかけてもくれない。小学校の卒業式、私と親友三人は中学校で新しい友達ができてもずっと四人で一緒に学校に行くと約束したのに。卒業後に引っ越しが決まったためお別れも言えず、三人は私がいないことを知らない。自分達に引っ越すことを内緒にして一緒に学校に行く約束をしたなんて、ひどいと思われるだろう。そんなモヤモヤした嫌な気持ちのまま中学校生活は始まった。
春休みは昨日が最後だった。今日からは朝起きて制服を着て登校する。春休み何もする気がでなくて昼近くまで寝ていたことと、昨日の夜不安で眠れなかったせいで太陽の光がやけに眩しい。前を歩く三人組は仲良しグループだろうか。周りを見てみると皆友達と楽しそうに話しながら歩いている。一人で歩いているのは私だけ。約束していた親友のことを思い出して、一緒に行く友達がいる羨ましさと一人とぼとぼ歩く寂しさが一気にこみ上げてきた。学校に着いても私はずっと一人だった。こんなことならもう少し寝ておけばよかったと後悔しながら自分の席に静かに座っていた。知ってる人がいないので、最初は休み時間は絵を描いていた。すると前の席の星野明莉ちゃんが「わぁ、その絵上手だね!」
と笑顔で褒めてくれた。今まで人に褒められたことがなかったのでその一言がすごく嬉しかった。その日から明莉ちゃんと話すようになって毎日話しているうちに私の周りには人が増えていった。友達と話したり、遊んだりするのが楽しくて入学したばかりの頃の不安は嘘のように消えていった。
しばらくすると席替えをした。明莉ちゃんや他の友達とは結構離れてしまった。それだけではない。隣の席の楓芽君は静かであまり話さないから教科書忘れちゃったらどうしよう、話し合いできるかなとか色々気になっていた。私は小学校の時から算数が苦手だった。数学で分からない問題があった時、ちょうど隣同士で話し合いをすることになった。楓芽君のノートを見てみるとすでに答えがかいてあった。難しい問題で皆が苦戦しているのに解けちゃうなんてすごい。なんて思ってる場合じゃない。数学の先生は難しい問題になると隣同士で話し合いをさせる。そこまではいい。話し合いが終わると出席番号がかいてあるくじをひいて、出た番号の人が答えなければならない。だから誰があてるか分からないし、自分があたる可能性は充分にある。答えられなければ真面目に授業を受けていない、と怒られるのは有名な話だ。だからこの問題を理解しないといけない。私は解き方が全然わからない。でも話したことのない楓芽君に聞いて嫌な顔されるかもしれないと困っていた、その時だった。
「それ、さっきの方程式使えばできる。」
急に隣から声が聞こえてきてびっくり…え?隣?そっと隣を見ると楓芽君が私を見ていた。困っているのを察してくれたようで、分かりやすく説明してくれた。テストでもいい点をとっていて、頭の良さは私とでは比べものにならないくらいだった。そんな楓芽君と仲良くなれるのか心配になり、男の子が苦手な私はますます自分から話しかけられなかった。その日の昼の休み時間、「如月さん」と私を呼ぶ声が聞こえた。その声は隣からだったので楓芽君なのはすぐに分かった。横を見ると楓芽君が私に話し始めて、少し驚いた。特に大事な話じゃなかったから何で話しかけられたのか分からなかったけど笑顔で話してくれたことと、私を笑わせようとしてくれていたことからきっと話しかけやすいようにしてくれたんだろうと思った。最初は話しかけにくいと思っていたけど本当は優しくて面白かった。人は見かけによらないというのはこういう事なんだと改めて実感した。話していくうちに私と楓芽君は仲良くなって休み時間もよく話すように。ある時、好きな人の話をした。楓芽君の好きな人は小坂華さんという人で、趣味が同じで好きになったんだって。クラスは違うけど一度だけ見たことがあった。目はぱっちりで、顔が整っていて可愛かったので一度見ただけで記憶に残っていた。それに笑顔で友達と話しているのを見て、性格もよさそうだったので好きになるのも当たり前のような気がした。
中学校に入ってから二度目の席替え。楓芽君とは席が離れて話さなくなった。話さなくなると毎日が少し寂しくて。席替えなんてしたくなかったのに。楓芽君は私の友達と席が隣になって休み時間とかたくさん話していた。ただ話しているだけなのに二人が話しているのを見るとギュッと胸が締め付けられるように苦しかった。私の友達に笑顔で話さないでよ。その笑顔は私だけに向けてよ。そんなことを思ってしまう自分が恥ずかしくて仕方なかった。私って性格悪いなぁなんて。私は少しずつ思い始めていた。感じたことのない初めて知るこの複雑な気持ち、これが恋なのかもしれないということを。友達と話していても、授業を聞いていても、いつも頭の隅には楓芽君がいた。この恋が叶わないことなんて分かってる。これ以上傷つくのはもう嫌だ。気持ちを伝えちゃったらきっともう話せなくなってしまう、気まずくなりたくない。結局自分のことばかり考えているのに呆れながらもやっぱり友達のままでいたいと思った。友達のままでいれば毎日顔を見られるし、話すことだってできる。頭では理解しているのにこの気持ちを閉じ込めることは出来なかった。
0
この作品の感想を投稿する
あなたにおすすめの小説

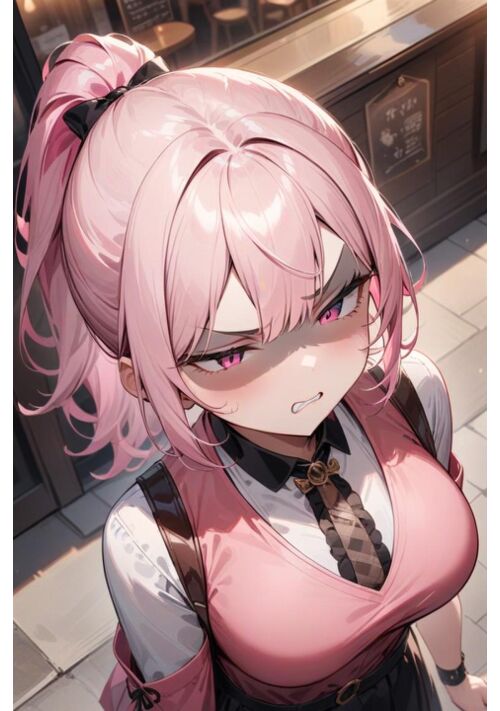
【朗報】俺をこっぴどく振った幼馴染がレンカノしてたので2時間15,000円でレンタルしてみました
田中又雄
恋愛
俺には幼稚園の頃からの幼馴染がいた。
しかし、高校進学にあたり、別々の高校に行くことになったため、中学卒業のタイミングで思い切って告白してみた。
だが、返ってきたのは…「はぁ!?誰があんたみたいなのと付き合うのよ!」という酷い言葉だった。
それからは家は近所だったが、それからは一度も話をすることもなく、高校を卒業して、俺たちは同じ大学に行くことになった。
そんなある日、とある噂を聞いた。
どうやら、あいつがレンタル彼女なるものを始めたとか…。
気持ち悪いと思いながらも俺は予約を入れるのであった。
そうして、デート当日。
待ち合わせ場所に着くと、後ろから彼女がやってきた。
「あ、ごめんね!待たせちゃっ…た…よ…ね」と、どんどんと顔が青ざめる。
「…待ってないよ。マイハニー」
「なっ…!?なんであんたが…!ばっかじゃないの!?」
「あんた…?何を言っているんだい?彼女が彼氏にあんたとか言わないよね?」
「頭おかしいんじゃないの…」
そうして、ドン引きする幼馴染と俺は初デートをするのだった。

幼馴染の許嫁
山見月あいまゆ
恋愛
私にとって世界一かっこいい男の子は、同い年で幼馴染の高校1年、朝霧 連(あさぎり れん)だ。
彼は、私の許嫁だ。
___あの日までは
その日、私は連に私の手作りのお弁当を届けに行く時だった
連を見つけたとき、連は私が知らない女の子と一緒だった
連はモテるからいつも、周りに女の子がいるのは慣れいてたがもやもやした気持ちになった
女の子は、薄い緑色の髪、ピンク色の瞳、ピンクのフリルのついたワンピース
誰が見ても、愛らしいと思う子だった。
それに比べて、自分は濃い藍色の髪に、水色の瞳、目には大きな黒色の眼鏡
どうみても、女の子よりも女子力が低そうな黄土色の入ったお洋服
どちらが可愛いかなんて100人中100人が女の子のほうが、かわいいというだろう
「こっちを見ている人がいるよ、知り合い?」
可愛い声で連に私のことを聞いているのが聞こえる
「ああ、あれが例の許嫁、氷瀬 美鈴(こおりせ みすず)だ。」
例のってことは、前から私のことを話していたのか。
それだけでも、ショックだった。
その時、連はよしっと覚悟を決めた顔をした
「美鈴、許嫁をやめてくれないか。」
頭を殴られた感覚だった。
いや、それ以上だったかもしれない。
「結婚や恋愛は、好きな子としたいんだ。」
受け入れたくない。
けど、これが連の本心なんだ。
受け入れるしかない
一つだけ、わかったことがある
私は、連に
「許嫁、やめますっ」
選ばれなかったんだ…
八つ当たりの感覚で連に向かって、そして女の子に向かって言った。


俺が宝くじで10億円当選してから、幼馴染の様子がおかしい
沢尻夏芽
恋愛
自他共に認める陰キャ・真城健康(まき・けんこう)は、高校入学前に宝くじで10億円を当てた。
それを知る、陽キャ幼馴染の白駒綾菜(しらこま・あやな)はどうも最近……。
『様子がおかしい』
※誤字脱字、設定上のミス等があれば、ぜひ教えてください。
現時点で1話に繋がる話は全て書き切っています。
他サイトでも掲載中。

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。


とっていただく責任などありません
まめきち
恋愛
騎士団で働くヘイゼルは魔物の討伐の際に、
団長のセルフイスを庇い、魔法陣を踏んでしまう。
この魔法陣は男性が踏むと女性に転換するもので、女性のヘイゼルにはほとんど影響のない物だった。だか国からは保証金が出たので、騎士を辞め、念願の田舎暮らしをしようとしたが!?
ヘイゼルの事をずっと男性だと思っていたセルフイスは自分のせいでヘイゼルが職を失っただと思って来まい。
責任を取らなければとセルフイスから、
追いかけられる羽目に。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















