6 / 43
第6話
しおりを挟む
その日、彼らと放課後に遊ぶ約束はしていなかった。
テストが終わって、七月の終わり。
小西は部活に精を出し、橘は何やら家の用事だとか。漆原は女漁りに出かけていった。
本田たちは、女子グループで遊ぶらしい。本田に上原も一緒にどう?と誘われたが、女子三人の中に男の俺一人というのは居心地が悪い。
丁重に断ると、本田は口をぷくっと膨らませて、もう誘ってやんないと言って去っていった。
俺は特にどこかに行く予定もなかったが、足はそのまま町の方に向かった。
自分の記憶との照合を町でも行いたかったのかもしれない。
一人で本屋に行ったり、服屋に行ったりと目に入った店には興味がなくとも、とにかく入ってみた。
しかし、ヒマな放課後の時間つぶしにしては十分に楽しめた。
変わりゆく町に、残る店、消える店。消える人、物。すべてが新鮮に見えて、そうして俺のあやふやな記憶に刻まれていくのは快感だった。
自分の存在を明確に感じられたからかもしれない。
そうして、放課後を満喫し、帰り際、またあの公園に向かった。
もう夏ということもあり、制服越しに汗が吹き出し、肌に服が張り付いて気持ちが悪い。しかし、これもまた青春と呑気にベンチにこしかけ、自販機で買った缶コーヒーを飲む。
何故かホットを買ってしまったことも、別に後悔していない。それにしても町を2時間近く歩いたな。明日は筋肉痛だなと憂鬱にもならない。
そんな気分になる夕焼けの空。
朱色に染め上げて、今日を終わらせる。
そんな空を眺めながら、ふと考える。
青春、朱夏、白秋、玄冬と季節を表す言葉は四季すべてにあるのに、青春だけ注目度が違う。若く血がたぎるイメージだ。
皆、この言葉が好きだし、この言葉に囚われている節さえある。
しかし、俺は朱夏という言葉の方が好きだ。
朱夏は確か25歳から60歳までの言葉だったか、色恋に、仕事、家庭を持つなど、社会的責任を問われる歳月。所謂、責任を伴う自由とは、自分というものを痛いほど理解させられる。
それが、高校生でありながら一番、自分に当てはまる言葉だなと感じたのだ。
自分という存在について考えながら、コーヒーを飲んでいると、時刻は七時を回っており、夜の帳は開いていた。
そうして、自分の存在について考えていることなんて、まさしく青春。青臭いことこの上ないと一人恥ずかしくなって、缶コーヒーを飲み干した。
そうして、飲み終えた缶を持っていることに嫌気が指してきた時、ふと顔を上げると、こちらに歩いてくる女性が視界に入った。
その女性は長い髪を一つまとめにして、こちらに颯爽と歩いてくる。そうして、公園の端に立った街灯の下に来ると、見知った顔が見えた。
宮藤(みやふじ)さんは手に近所の本屋の袋を持ち、軽い足取りでこちらに歩いてくる。
その姿に見惚れながら、息をのんだ。
暗がりの公園にて女子を見て、息をのむ男子というのも気味の悪い絵面である。そうして、彼女が近くに来るのを待って、声をかけた。
この数カ月ずっと話しかけようと考えていながら、その機会がやっと巡ってきたのだ。このチャンスを逃す手はない。
「あれ………えっと宮藤さん?」
俺は自分の声が少しばかり上擦っているのを感じ、また自分の手足が同時に出ていることに気が付く。
これでは挙動不審な男。気持ち悪い男だという印象を彼女に与えてしまうと考え、少し彼女と距離を置いて、立ち止まる。
彼女はこちらに顔を上げると、訝しむような表情を見せる。
そうして、顎に手を当て、その小さな口を開いた。
「………えっと。上原くん?」
その声は鈴の音のように綺麗な声音であった。
耳心地の良いその声で子守唄でも歌われれば、俺は今すぐ、赤子のように眠りに就くだろう。
そして、話をしようと彼女を見るも、何故か怯えた表情でこちらを見ている。朝起こしに来る妹と同じ表情である。
……あれ?何か怖がらせるような事したかな?
ああ。そうか。俺って不良だったな。
喧嘩を生業にしてるみたいな不良と夜の公園で出会う恐怖を俺は今、彼女に味わわせているのか。
もっと優しく声をかけていたら、こんなフウに怖がれなかったかもしれない。しかし、気のある子に声をかけるだけでこんなに心が揺さぶられるものだろうか?
彼女を一目見たその時、俺は好きだとか、綺麗だなって気持ちだけではなく、もっと違う感情に支配されていた。
なんと言っていいのか分からない感情の波。
ただそこで生きていて、本を読む彼女がただ愛おしく、ただ安心し、泣きそうになっていた。
変な記憶に振り回され、変な感情を持つようになれば、もう気持ちが悪いのを通り越して、恐怖すら感じる。
しかし、彼女に覚えたこの感情はえらく暖かみのある、ひだまりのような感情で、すっと心に入り込み、俺は彼女と話してみたいと思ったのだ。
「ごめん。俺みたいなのに話しかけられるのって嫌だよな?」
俺のその言葉に彼女は眉を顰めて、何か言葉を探している。
「……えっと。私の名前。知ってたんだって驚いてしまって」
彼女の言葉に一瞬、何の話か分からず、こちらも眉間に皺が寄ってしまうが、少しでも彼女に怖がられたくなく、その皺を手で解す。
「いやいや。だって同じクラスだし」
「そうですけど。………私、影薄いから」
彼女は気恥ずかしそうに声を漏らすと、手に持った小さな袋を微かに揺らした。
そうして、街灯に下に立つ彼女を見て、また変な感情に支配されぬよう、話を続ける。
「えっと、買い物の帰り?」
「はい。本屋の帰りで。学校の帰りに寄り道するのは駄目だとは分かってるんですが、読みたい本が出たので………」
寄り道した程度のことを悪い事をしたと恥じらいながら彼女は話す。俺のような悪い噂しか立たない不良とは雲泥の差がある。そんな彼女の模範的な生き方に多少、たじろいでしまう。
確かに、それはこんな娘は俺のような人間と進んで関わることはないだろう。
「そうなんだ………教室でもいつも本を読んでるもんな。俺も本は好きだよ」
俺の言葉に彼女は今までの怯えた表情は鳴りを潜め、微かに笑った。それが嬉しくて、俺は少し体が震えているのを感じた。
「………えっと。………す、すいません。以外だったもので。いえ。上原君は友達も大勢いる方なので忙しい方なのかなって思ってしまって」
「そう?俺って友達多いの?」
彼女の言葉に俺は安易に肯定できない。春の初めに記憶は彼方に飛んで行ってしまったのだから。
「えっと………違うんですか?」
彼女は逆に質問されるとは思わず、少し困ったように眉を顰めた。いや、俺のような人間と長話をしたくないという意思の表れかもしれない。
「どうだろう?………宮藤さんはうちのクラスだと誰と仲が良いの?」
俺の更なる質問にまたもや彼女は困ったように「………仲が良い人ですか」と小さくため息とも取れる声を漏らす。
「飛騨君とはたまに話しますね………他には、他クラスの藤原さんとかですかね」
「そうなんだ………えっと………あの、宮藤さん。もしよければ、俺と友達からでいいのでどうだろう?これからも話してもらえませんか?」
俺は勢いのままに彼女に言った。
ずっと話しながら、この機を逃せば、二度と話すこともないかもしれないとそう思っていたのだ。
彼女は教室でもいつも本を読んでいるらしい。しかし、俺は周りに橘だったり、漆原までいる。俺が一人で彼女に話しかければ、目立ってしまう可能性は否めず、彼女に迷惑をかけてしまうだろう。
ここが勝負の時だ。
俺の急な提案に彼女は「え?」と漏らし固まってしまった。
沈黙が二人の間に訪れる。その間も俺の心臓の鼓動は大きくなっていく。
俺はいてもたってもいられず、彼女に連絡先をと携帯を出して、彼女のいる街灯の下へと駆け寄った。
そうして、俺の顔が明るみに出て、彼女と初対面を交わすと、それは突然起こった。
彼女は何故か、俺の顔を見た瞬間、急に涙を流し、そうして、何かに怯えたように激しく動揺しているのだ。
まるで幽霊にでも会ったように、目は大きく見開かれ、揺れる瞳から涙が溢れる。
彼女は全身が震えだし、俺から後ずさる。
そうして、震える自身の身を抱きしめながら、「……何?これ?………えっ?」とずっと何かを呟いている。
先ほどまでの表情は崩れて、歪んだ表情のまま、ただひたすら号泣する彼女にどうしていいか分からずこちらも動揺してしまう。
「どうしたの!?宮藤さん!?」
俺の言葉は彼女に届いていないのか、彼女は未だ、身を震わせ、ついには立っていられなくなったのかその場にしゃがみこんでしまう。
顔を覆い、ただ嗚咽が聞こえてきて、俺は額に浮いた汗が滴るのを感じる。
自分が想像以上に狼狽しており、どうにかこの事態を収拾しなくてはと思ったのだ。
これはただ事ではない。
彼女は何か自病でも抱えているのではないかと。
「本当にどうしたの?具合が悪いの?救急車呼ぼうか?」
俺は彼女が辛そうに肩を揺らして、泣いているので、背中をさすろうかと彼女に触れると、彼女の悲鳴が木霊した。
それは悲痛な叫びで、その叫びが鼓膜を震わせるのと同時に指に静電気が走ったように俺はすぐに彼女から手を引いた。
その瞬間、変な記憶がまたも流れ込んできた。
しかし、それは特別なものではない。
単なる、日常のありふれた1ページ。
朝、出かけに俺は急いでいて、彼女に声をかけずに玄関の戸を閉めた。いつもは立鏡の前でネクタイを締め直し、ハンカチ、ポケットティッシュを持ったか彼女とチェックする。
しかし、その日に限って、寝起きのまま、直ぐに家を出た。
そうして、マンションの一室から出ると、すぐにバス停へと向かう。
その日は曇っており、今にも降りだしそうな空の下、傘を忘れていることに気が付く。
しかし、今から家に戻っていたのでは遅刻してしまう。
そうして、いつも歩きなれているバス停までの道を後悔と共に歩いていた。
いや、違う。
そんなことを後悔しているのか?
違う。
そんなことではない。
では何を後悔しているのだろう?
そうか。
何故、あの日に限って、何も声をかけずに家を出たのだろうと。それを後悔していたのか。
なんだ。
そんなことだ。
その程度のことであり。それがずっと心残りだった。
だから最後まで気は休まらず、罪悪感の中で俺は。俺は。
「………えっと上原くん? 」
俺は宮藤さんの声で意識を取り戻す。
俺は何を見ていたのだろう?視線を彼女に移すと、その目は泣いていたせいか赤く腫れており、髪も乱れていた。
第三者に見られれば、何か俺が彼女に良からぬことをしていたと誤解されてもおかしくない。
彼女は先ほどのようにもう取り乱してはおらず、ちゃんと意志のこもった目で俺を見た。
「どうして泣いているんですか?」
彼女は小さな声でそう聞いてきた。
俺は自身の頬を伝う涙を手で拭い、ふと我に返る。
何故、泣いているのだろう。しかし、心には懴悔の念が残っている。何に対する気持ちなのかも理解できない。
言葉に出来ぬ感情が自分の中に渦巻いており、彼女と視線を交わすとその感情は一層、強く心に響いた。
「なんでだろう………なんで泣いているんだろう」
俺の言葉を聞いていながら、彼女は泣きはらした顔をハンカチで拭うと、俺の顔を見た。
そうして、「違う。違う。上原くんじゃない。じゃあ誰?」と呟いた。
「何のこと?」
「………すいません。今は一人にしてほしいんです」
そう言って俺の方を見る。それは自分でも感情の整理ができていない様子であり、また俺を拒絶しているようにも思えた。
俺は彼女のその言葉を聞いて、公園を後にした。
帰り際、何故かこれで良かったのではないかとすら思った。
俺は彼女と出会わないほうがいいと、もう話さない方が良いと、そう夜風に諭された気がした。そうして空を見ながらため息とともに笑みまで零れた。
別れ際、彼女は笑顔に努めて、俺と別れた。
その表情は記憶にあった誰かの笑顔に酷く似ていた。
テストが終わって、七月の終わり。
小西は部活に精を出し、橘は何やら家の用事だとか。漆原は女漁りに出かけていった。
本田たちは、女子グループで遊ぶらしい。本田に上原も一緒にどう?と誘われたが、女子三人の中に男の俺一人というのは居心地が悪い。
丁重に断ると、本田は口をぷくっと膨らませて、もう誘ってやんないと言って去っていった。
俺は特にどこかに行く予定もなかったが、足はそのまま町の方に向かった。
自分の記憶との照合を町でも行いたかったのかもしれない。
一人で本屋に行ったり、服屋に行ったりと目に入った店には興味がなくとも、とにかく入ってみた。
しかし、ヒマな放課後の時間つぶしにしては十分に楽しめた。
変わりゆく町に、残る店、消える店。消える人、物。すべてが新鮮に見えて、そうして俺のあやふやな記憶に刻まれていくのは快感だった。
自分の存在を明確に感じられたからかもしれない。
そうして、放課後を満喫し、帰り際、またあの公園に向かった。
もう夏ということもあり、制服越しに汗が吹き出し、肌に服が張り付いて気持ちが悪い。しかし、これもまた青春と呑気にベンチにこしかけ、自販機で買った缶コーヒーを飲む。
何故かホットを買ってしまったことも、別に後悔していない。それにしても町を2時間近く歩いたな。明日は筋肉痛だなと憂鬱にもならない。
そんな気分になる夕焼けの空。
朱色に染め上げて、今日を終わらせる。
そんな空を眺めながら、ふと考える。
青春、朱夏、白秋、玄冬と季節を表す言葉は四季すべてにあるのに、青春だけ注目度が違う。若く血がたぎるイメージだ。
皆、この言葉が好きだし、この言葉に囚われている節さえある。
しかし、俺は朱夏という言葉の方が好きだ。
朱夏は確か25歳から60歳までの言葉だったか、色恋に、仕事、家庭を持つなど、社会的責任を問われる歳月。所謂、責任を伴う自由とは、自分というものを痛いほど理解させられる。
それが、高校生でありながら一番、自分に当てはまる言葉だなと感じたのだ。
自分という存在について考えながら、コーヒーを飲んでいると、時刻は七時を回っており、夜の帳は開いていた。
そうして、自分の存在について考えていることなんて、まさしく青春。青臭いことこの上ないと一人恥ずかしくなって、缶コーヒーを飲み干した。
そうして、飲み終えた缶を持っていることに嫌気が指してきた時、ふと顔を上げると、こちらに歩いてくる女性が視界に入った。
その女性は長い髪を一つまとめにして、こちらに颯爽と歩いてくる。そうして、公園の端に立った街灯の下に来ると、見知った顔が見えた。
宮藤(みやふじ)さんは手に近所の本屋の袋を持ち、軽い足取りでこちらに歩いてくる。
その姿に見惚れながら、息をのんだ。
暗がりの公園にて女子を見て、息をのむ男子というのも気味の悪い絵面である。そうして、彼女が近くに来るのを待って、声をかけた。
この数カ月ずっと話しかけようと考えていながら、その機会がやっと巡ってきたのだ。このチャンスを逃す手はない。
「あれ………えっと宮藤さん?」
俺は自分の声が少しばかり上擦っているのを感じ、また自分の手足が同時に出ていることに気が付く。
これでは挙動不審な男。気持ち悪い男だという印象を彼女に与えてしまうと考え、少し彼女と距離を置いて、立ち止まる。
彼女はこちらに顔を上げると、訝しむような表情を見せる。
そうして、顎に手を当て、その小さな口を開いた。
「………えっと。上原くん?」
その声は鈴の音のように綺麗な声音であった。
耳心地の良いその声で子守唄でも歌われれば、俺は今すぐ、赤子のように眠りに就くだろう。
そして、話をしようと彼女を見るも、何故か怯えた表情でこちらを見ている。朝起こしに来る妹と同じ表情である。
……あれ?何か怖がらせるような事したかな?
ああ。そうか。俺って不良だったな。
喧嘩を生業にしてるみたいな不良と夜の公園で出会う恐怖を俺は今、彼女に味わわせているのか。
もっと優しく声をかけていたら、こんなフウに怖がれなかったかもしれない。しかし、気のある子に声をかけるだけでこんなに心が揺さぶられるものだろうか?
彼女を一目見たその時、俺は好きだとか、綺麗だなって気持ちだけではなく、もっと違う感情に支配されていた。
なんと言っていいのか分からない感情の波。
ただそこで生きていて、本を読む彼女がただ愛おしく、ただ安心し、泣きそうになっていた。
変な記憶に振り回され、変な感情を持つようになれば、もう気持ちが悪いのを通り越して、恐怖すら感じる。
しかし、彼女に覚えたこの感情はえらく暖かみのある、ひだまりのような感情で、すっと心に入り込み、俺は彼女と話してみたいと思ったのだ。
「ごめん。俺みたいなのに話しかけられるのって嫌だよな?」
俺のその言葉に彼女は眉を顰めて、何か言葉を探している。
「……えっと。私の名前。知ってたんだって驚いてしまって」
彼女の言葉に一瞬、何の話か分からず、こちらも眉間に皺が寄ってしまうが、少しでも彼女に怖がられたくなく、その皺を手で解す。
「いやいや。だって同じクラスだし」
「そうですけど。………私、影薄いから」
彼女は気恥ずかしそうに声を漏らすと、手に持った小さな袋を微かに揺らした。
そうして、街灯に下に立つ彼女を見て、また変な感情に支配されぬよう、話を続ける。
「えっと、買い物の帰り?」
「はい。本屋の帰りで。学校の帰りに寄り道するのは駄目だとは分かってるんですが、読みたい本が出たので………」
寄り道した程度のことを悪い事をしたと恥じらいながら彼女は話す。俺のような悪い噂しか立たない不良とは雲泥の差がある。そんな彼女の模範的な生き方に多少、たじろいでしまう。
確かに、それはこんな娘は俺のような人間と進んで関わることはないだろう。
「そうなんだ………教室でもいつも本を読んでるもんな。俺も本は好きだよ」
俺の言葉に彼女は今までの怯えた表情は鳴りを潜め、微かに笑った。それが嬉しくて、俺は少し体が震えているのを感じた。
「………えっと。………す、すいません。以外だったもので。いえ。上原君は友達も大勢いる方なので忙しい方なのかなって思ってしまって」
「そう?俺って友達多いの?」
彼女の言葉に俺は安易に肯定できない。春の初めに記憶は彼方に飛んで行ってしまったのだから。
「えっと………違うんですか?」
彼女は逆に質問されるとは思わず、少し困ったように眉を顰めた。いや、俺のような人間と長話をしたくないという意思の表れかもしれない。
「どうだろう?………宮藤さんはうちのクラスだと誰と仲が良いの?」
俺の更なる質問にまたもや彼女は困ったように「………仲が良い人ですか」と小さくため息とも取れる声を漏らす。
「飛騨君とはたまに話しますね………他には、他クラスの藤原さんとかですかね」
「そうなんだ………えっと………あの、宮藤さん。もしよければ、俺と友達からでいいのでどうだろう?これからも話してもらえませんか?」
俺は勢いのままに彼女に言った。
ずっと話しながら、この機を逃せば、二度と話すこともないかもしれないとそう思っていたのだ。
彼女は教室でもいつも本を読んでいるらしい。しかし、俺は周りに橘だったり、漆原までいる。俺が一人で彼女に話しかければ、目立ってしまう可能性は否めず、彼女に迷惑をかけてしまうだろう。
ここが勝負の時だ。
俺の急な提案に彼女は「え?」と漏らし固まってしまった。
沈黙が二人の間に訪れる。その間も俺の心臓の鼓動は大きくなっていく。
俺はいてもたってもいられず、彼女に連絡先をと携帯を出して、彼女のいる街灯の下へと駆け寄った。
そうして、俺の顔が明るみに出て、彼女と初対面を交わすと、それは突然起こった。
彼女は何故か、俺の顔を見た瞬間、急に涙を流し、そうして、何かに怯えたように激しく動揺しているのだ。
まるで幽霊にでも会ったように、目は大きく見開かれ、揺れる瞳から涙が溢れる。
彼女は全身が震えだし、俺から後ずさる。
そうして、震える自身の身を抱きしめながら、「……何?これ?………えっ?」とずっと何かを呟いている。
先ほどまでの表情は崩れて、歪んだ表情のまま、ただひたすら号泣する彼女にどうしていいか分からずこちらも動揺してしまう。
「どうしたの!?宮藤さん!?」
俺の言葉は彼女に届いていないのか、彼女は未だ、身を震わせ、ついには立っていられなくなったのかその場にしゃがみこんでしまう。
顔を覆い、ただ嗚咽が聞こえてきて、俺は額に浮いた汗が滴るのを感じる。
自分が想像以上に狼狽しており、どうにかこの事態を収拾しなくてはと思ったのだ。
これはただ事ではない。
彼女は何か自病でも抱えているのではないかと。
「本当にどうしたの?具合が悪いの?救急車呼ぼうか?」
俺は彼女が辛そうに肩を揺らして、泣いているので、背中をさすろうかと彼女に触れると、彼女の悲鳴が木霊した。
それは悲痛な叫びで、その叫びが鼓膜を震わせるのと同時に指に静電気が走ったように俺はすぐに彼女から手を引いた。
その瞬間、変な記憶がまたも流れ込んできた。
しかし、それは特別なものではない。
単なる、日常のありふれた1ページ。
朝、出かけに俺は急いでいて、彼女に声をかけずに玄関の戸を閉めた。いつもは立鏡の前でネクタイを締め直し、ハンカチ、ポケットティッシュを持ったか彼女とチェックする。
しかし、その日に限って、寝起きのまま、直ぐに家を出た。
そうして、マンションの一室から出ると、すぐにバス停へと向かう。
その日は曇っており、今にも降りだしそうな空の下、傘を忘れていることに気が付く。
しかし、今から家に戻っていたのでは遅刻してしまう。
そうして、いつも歩きなれているバス停までの道を後悔と共に歩いていた。
いや、違う。
そんなことを後悔しているのか?
違う。
そんなことではない。
では何を後悔しているのだろう?
そうか。
何故、あの日に限って、何も声をかけずに家を出たのだろうと。それを後悔していたのか。
なんだ。
そんなことだ。
その程度のことであり。それがずっと心残りだった。
だから最後まで気は休まらず、罪悪感の中で俺は。俺は。
「………えっと上原くん? 」
俺は宮藤さんの声で意識を取り戻す。
俺は何を見ていたのだろう?視線を彼女に移すと、その目は泣いていたせいか赤く腫れており、髪も乱れていた。
第三者に見られれば、何か俺が彼女に良からぬことをしていたと誤解されてもおかしくない。
彼女は先ほどのようにもう取り乱してはおらず、ちゃんと意志のこもった目で俺を見た。
「どうして泣いているんですか?」
彼女は小さな声でそう聞いてきた。
俺は自身の頬を伝う涙を手で拭い、ふと我に返る。
何故、泣いているのだろう。しかし、心には懴悔の念が残っている。何に対する気持ちなのかも理解できない。
言葉に出来ぬ感情が自分の中に渦巻いており、彼女と視線を交わすとその感情は一層、強く心に響いた。
「なんでだろう………なんで泣いているんだろう」
俺の言葉を聞いていながら、彼女は泣きはらした顔をハンカチで拭うと、俺の顔を見た。
そうして、「違う。違う。上原くんじゃない。じゃあ誰?」と呟いた。
「何のこと?」
「………すいません。今は一人にしてほしいんです」
そう言って俺の方を見る。それは自分でも感情の整理ができていない様子であり、また俺を拒絶しているようにも思えた。
俺は彼女のその言葉を聞いて、公園を後にした。
帰り際、何故かこれで良かったのではないかとすら思った。
俺は彼女と出会わないほうがいいと、もう話さない方が良いと、そう夜風に諭された気がした。そうして空を見ながらため息とともに笑みまで零れた。
別れ際、彼女は笑顔に努めて、俺と別れた。
その表情は記憶にあった誰かの笑顔に酷く似ていた。
0
あなたにおすすめの小説

とっていただく責任などありません
まめきち
恋愛
騎士団で働くヘイゼルは魔物の討伐の際に、
団長のセルフイスを庇い、魔法陣を踏んでしまう。
この魔法陣は男性が踏むと女性に転換するもので、女性のヘイゼルにはほとんど影響のない物だった。だか国からは保証金が出たので、騎士を辞め、念願の田舎暮らしをしようとしたが!?
ヘイゼルの事をずっと男性だと思っていたセルフイスは自分のせいでヘイゼルが職を失っただと思って来まい。
責任を取らなければとセルフイスから、
追いかけられる羽目に。

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

サンスクミ〜学園のアイドルと偶然同じバイト先になったら俺を3度も振った美少女までついてきた〜
野谷 海
恋愛
「俺、やっぱり君が好きだ! 付き合って欲しい!」
「ごめんね青嶋くん……やっぱり青嶋くんとは付き合えない……」
この3度目の告白にも敗れ、青嶋将は大好きな小浦舞への想いを胸の内へとしまい込んで前に進む。
半年ほど経ち、彼らは何の因果か同じクラスになっていた。
別のクラスでも仲の良かった去年とは違い、距離が近くなったにも関わらず2人が会話をする事はない。
そんな折、将がアルバイトする焼鳥屋に入ってきた新人が同じ学校の同級生で、さらには舞の親友だった。
学校とアルバイト先を巻き込んでもつれる彼らの奇妙な三角関係ははたしてーー
⭐︎第3部より毎週月・木・土曜日の朝7時に最新話を投稿します。
⭐︎もしも気に入って頂けたら、ぜひブックマークやいいね、コメントなど頂けるととても励みになります。
※表紙絵、挿絵はAI作成です。
※この作品はフィクションであり、作中に登場する人物、団体等は全て架空です。

迷子を助けたら生徒会長の婚約者兼女の子のパパになったけど別れたはずの彼女もなぜか近づいてくる
九戸政景
恋愛
新年に初詣に来た父川冬矢は、迷子になっていた頼母木茉莉を助け、従姉妹の田母神真夏と知り合う。その後、真夏と再会した冬矢は真夏の婚約者兼茉莉の父親になってほしいと頼まれる。
※こちらは、カクヨムやエブリスタでも公開している作品です。


クラスメイトの王子様系女子をナンパから助けたら。
桜庭かなめ
恋愛
高校2年生の白石洋平のクラスには、藤原千弦という女子生徒がいる。千弦は美人でスタイルが良く、凛々しく落ち着いた雰囲気もあるため「王子様」と言われて人気が高い。千弦とは教室で挨拶したり、バイト先で接客したりする程度の関わりだった。
とある日の放課後。バイトから帰る洋平は、駅前で男2人にナンパされている千弦を見つける。普段は落ち着いている千弦が脚を震わせていることに気付き、洋平は千弦をナンパから助けた。そのときに洋平に見せた笑顔は普段みんなに見せる美しいものではなく、とても可愛らしいものだった。
ナンパから助けたことをきっかけに、洋平は千弦との関わりが増えていく。
お礼にと放課後にアイスを食べたり、昼休みに一緒にお昼ご飯を食べたり、お互いの家に遊びに行ったり。クラスメイトの王子様系女子との温かくて甘い青春ラブコメディ!
※特別編4が完結しました!(2026.2.22)
※小説家になろうとカクヨムでも公開しています。
※お気に入り登録、いいね、感想などお待ちしております。

天才天然天使様こと『三天美女』の汐崎真凜に勝手に婚姻届を出され、いつの間にか天使の旦那になったのだが...。【動画投稿】
田中又雄
恋愛
18の誕生日を迎えたその翌日のこと。
俺は分籍届を出すべく役所に来ていた...のだが。
「えっと...結論から申し上げますと...こちらの手続きは不要ですね」「...え?どういうことですか?」「昨日、婚姻届を出されているので親御様とは別の戸籍が作られていますので...」「...はい?」
そうやら俺は知らないうちに結婚していたようだった。
「あの...相手の人の名前は?」
「...汐崎真凛様...という方ですね」
その名前には心当たりがあった。
天才的な頭脳、マイペースで天然な性格、天使のような見た目から『三天美女』なんて呼ばれているうちの高校のアイドル的存在。
こうして俺は天使との-1日婚がスタートしたのだった。
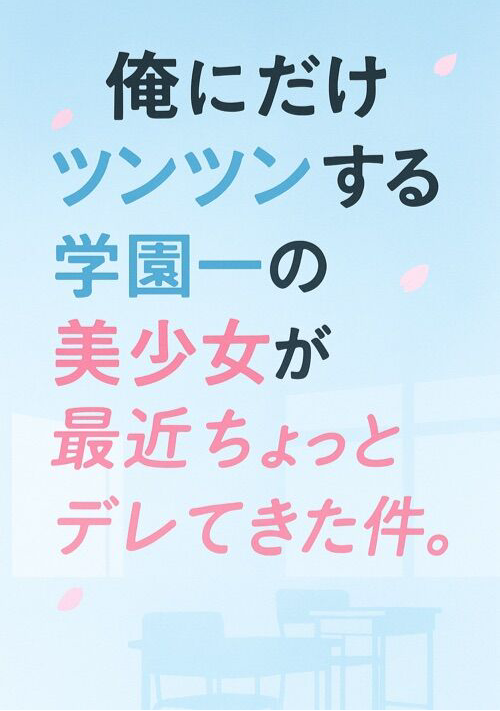
俺にだけツンツンする学園一の美少女が、最近ちょっとデレてきた件。
甘酢ニノ
恋愛
彼女いない歴=年齢の高校生・相沢蓮。
平凡な日々を送る彼の前に立ちはだかるのは──
学園一の美少女・黒瀬葵。
なぜか彼女は、俺にだけやたらとツンツンしてくる。
冷たくて、意地っ張りで、でも時々見せるその“素”が、どうしようもなく気になる。
最初はただの勘違いだったはずの関係。
けれど、小さな出来事の積み重ねが、少しずつ2人の距離を変えていく。
ツンデレな彼女と、不器用な俺がすれ違いながら少しずつ近づく、
焦れったくて甘酸っぱい、青春ラブコメディ。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















