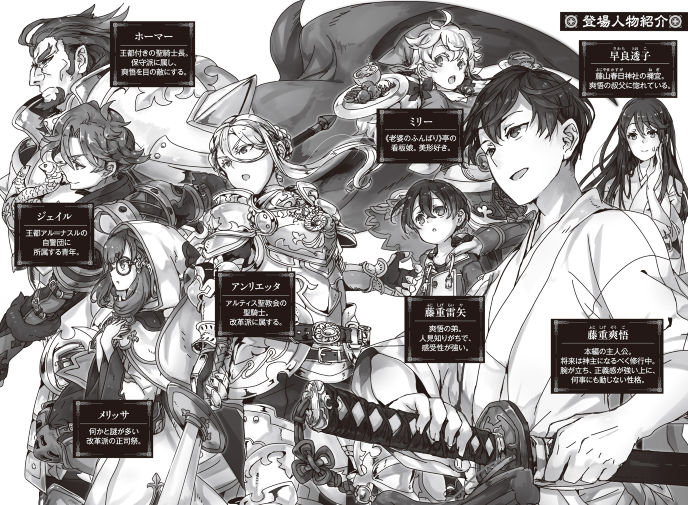1 / 80
1巻
1-1
しおりを挟む序章
夜半――
関東地方の某県某市にある藤山春日神社。その境内で、跡取り息子の藤重爽悟は、木刀を手に素振りをしていた。
叔父であり宮司である藤重梓馬は他の神社の手伝いで不在、姉でイギリス留学中の佐保が帰宅するのは数日後だ。
その代わり、社務所兼自宅に禰宜である早良透子が泊まり込んでくれている。神職の朝は早いので、当然床に就くのも早い。
弟の雷矢もいるのだが、今日は部屋の明かりが消えているのでもう眠っているだろう。
爽悟も平時であればとっくに眠っている時間だが、なぜだか妙に胸がざわついて、眠ることができなかった。こんなとき、普段なら弓を引くのだが、こう夜も遅くなっては的が見えずそれも叶わない。爽悟はざわつく心を鎮めるべく、木刀を振って体を動かすことにしたのだった。素振りと言っても、適当に振り回すのではない。習い覚えた一つ一つの型を、正確に、力強く再現する。
藤山春日神社の歴史は江戸幕府成立以前に遡るが、はっきりしたところはわからない。明確にその建立年月日を裏付ける史料は残っていないのだ。しかし、古い神社であることは事実である。
奈良に存在する春日大社を総本山とする春日神社は、全国各地に点在する。その神徳は幅広く、立身出世、武運長久等々。節操がないとも思えるが、春日神自体が天野小屋根命、経津主命、建御雷神、比売神の四柱をひとまとめにしたものなのだからある意味当然とも言える。典型的な勧請型神社だ。
藤山春日神社は、どういった経緯でか、この地域に住まうようになった藤原氏の傍流が、氏神である春日神を祀るために建立したのが成り立ちと言われる。宮司を務める藤重家は、代々その祭祀を務めてきた家来筋で、極めて奇跡的なことに、今日まで数百年の間、世襲が絶えることなく、今日まで続いている。
経津主命は剣の神だから、将来宮司になる爽悟も当然剣の道に長けていなければならない。亡き父も、現在の宮司を務める叔父もそうして来たのだから、自分もそうすることに異論はない。
幼い時分に父母を亡くして以来、藤山春日神社を継ぐことは、爽悟にとってある種の執念となった。剣道、弓道、合気道、書道といった自分を磨くための習い事には、一切手を抜かなかった。学問にも精を出した。神職に就く者として相応しい、美しい立ち居振る舞いも常日頃から心がけている。
結果、爽悟は孤独だった。周囲の子供たちは、あらゆる面で秀でる爽悟を敬して遠ざけるか、宗教家の子として侮辱するかのいずれかであった。気のおけない友人などほとんどいなかった。けれど、爽悟は後悔していない。
両親が事故で亡くなったのは、爽悟がまだ幼い頃だった。物心がついているかも怪しい頃だが、爽悟はその日のことを鮮明に覚えている。まだ子供だった自分にも、父と母がもうどこにもいない、ということくらいは理解できた。泣きじゃくる爽悟に、姉の佐保は自分も涙を堪えながら言った。
――お父さんとお母さんは神様になったの。神様になって、ずっと、ずーっと……神社でわたしたちを守ってくれるのよ。
魂の実在を無邪気に信じられるほど、今の爽悟は純真ではない。けれど、仮に科学が魂の存在を否定したとしても、彼岸へと旅立った人々が遺していくものは確かにある。
爽悟は素振りをやめて、空を見上げた。ひなびた地方都市だが、肉眼で捉えることのできる星の数は多いとは言えない。人がその数を増やすにつれて、星たちは姿を消していく。人は死んだら星になるのだ、と言う者もいる。本当に星が人の魂なのだとしたら、なんとも皮肉なことである。
科学の発達によって、人は自らを死から遠ざけることができたが、それゆえに、より死を恐れるようになった。死してなおその先があると思うからこそ、人は死を受け入れることができるのではないのか。
魂の不在が証明されたとき、人はどこに『その先』を見ればよいのか。
爽悟は、答えは『ここ』にあるのだと思ってきた。
最後に改築されたのは江戸時代末期のことだという。ただひたすらに古いだけの、華やかさも文化財的価値もさしたるものではない、神社の建造物。
けれど、ざわめきに満ちた人里にあって、ここだけはずっと変わらず、静けさを保ち続けてきた。幾たびも巡る季節のなかで、少しずつその姿を変えながらも、人々は神に願いを、あるいは感謝をささげ続けてきた。
爽悟はそっと目を閉じ、自分がここに立つまでの数百年に、思いを馳せる。
その瞬間――
第一章 見習い神主、異世界へ
エルナト王国は、アルレシャ大陸南西部に位置する海沿いの国である。かつてはその国土の半分が森と山に覆われ、魔物とエルフを筆頭とする亜人種が跋扈していた魔境であった。
だが、旧神聖グラフィアス帝国の台頭とともに森は切り開かれ、人間の住む平野は広がっていった。それでも、国土の内に占める森林の割合は極めて多い。
かつてはこの近辺も、アルレシャ大陸のほぼ全土を支配した帝国の一領土であった。
しかし、盛者必衰とはよく言ったものである。皇帝の崩御により、神聖グラフィアス帝国の宮廷は、跡目争いで紛糾した。その隙を狙っていた有力な貴族たちが次々と蜂起。神聖グラフィアス帝国は滅び、多くの小国が乱立することになる。
エルナト王国も、元をたどればそういった国の一つであった。
現在、群雄割拠する乱世は一区切りつき、エルナト王国はそれなりの勢力を持つ国に落ち着いていた。
エルナト王国の王都アル=ナスルは、レサト川の中流を背にする城塞都市である。戦争に備えて築かれた砦を中心に作られており、お世辞にも風光明媚とは言いがたい。
とはいえ、城塞都市というのも今では名ばかりだ。多くの街道が交わるため、建国王ミッシェルが築いた城郭の外側にも、好き勝手に人々が住み着いてしまったのだ。無秩序に広がったそれらの居住区では、治安も悪くなりがちだし、最近大きな火災まであった。
火災の跡地には、アルティス聖教会によって大きな聖堂が建てられるという。
火災の原因となった落雷は神――審判者による神罰であり、その怒りを鎮めるために聖堂を建てなければならない、というのが大陸全土に広く権勢を誇っているアルティス聖教会の主張だ。
もっともらしく言ってはいるが、結局のところ、この話の裏には建設費用という金の存在がある。教会と豪商たちが繋がっているのは明白であったが、そんなのは今に始まったことでもない。
聖堂建築の予定地は、瓦礫の撤去を終えたばかりで、昨日まで更地だった――はずだ。しかし今そこに、奇妙な建造物が在った。
まず真っ先に目につくのは、明るい赤で塗られた門のようなモニュメントだ。二つの大きな柱の上部に、二つの緩やかに湾曲した梁を渡している。二つの梁の間には、何か不思議な文字らしきものが並んでいる。見たことのない文字だった。
続いて目を引くのは、石で作られた囲いだ。背の高い大人の男ならまたいで通れる程度の高さ。これでは柵としての意味などないように思える。石造りの囲いの中には木々が立ち並んでいた。その中にもやはり奇妙な建造物がいくつかあるのはわかるのだが、木々に視線が遮られて、詳細をはっきりとうかがい知ることはできなかった。門のようなモニュメントは、門のような形をしているだけで、鍵はおろか扉すらなかった。だから入ろうと思えば誰だって入れるものの、誰一人として内部を改めようとはしない。
しかし、いつしか謎の建造物の前には、どこから噂を聞きつけたのだか、野次馬やら、聖堂を建てるべくここで働くはずだった労働者やらが人だかりを成している。
これに困ったのは、ちょうど向かいで営まれる酒場《老婆のふんばり》亭の看板娘、ミリーだった。
店の外からこの様子を眺めているミリーは、店主夫婦の一人娘だ。つややかな赤みの金髪、目はぱっちりとして大きく、鼻は小さく、唇はぽってりと分厚く、そして何より胸が大きかった。数年前までは恥ずかしいと思っていたが、接客業をしていると、他人の視線に対して耐性ができてくるものである。
そんなミリーが看板娘を務める『老婆のふんばり亭』は、これは審判者の思し召しか、と思えるくらい綺麗に延焼を免れていた。そのため、火事の翌日からもう通常営業を再開していたのだが、人だかりのせいで今日は開店休業状態である。
無学なミリーに、建築のことはよくわからないが、これは新たな様式の聖堂なのだろうか。いや、それにしては斬新すぎるし、年季が入り過ぎているように思う。
そもそも、ミリーが正気であるならば、昨夜までここに建物なんてなかった。一体どうやって建てられたのか想像もつかない。
困ってはいるが、ここまで突飛な状況だと、どこか傍観者のような気持ちである。
しかし、聖堂建設のために呼び集められた人々はそうも言ってられない。流れ者ならまたどこか別の場所へ行けば済む話であろうが、元々王都に根を下ろしている大工は違う。このまま建設中止にでもなれば、下手をすれば年単位でスケジュールが空になってしまうのだ。
そんな大工の棟梁の一人で《老婆のふんばり》亭の常連客のアイヴァンも、きっとそうだろう。彼は、門弟を引き連れて毎日お金を落としてくれるし、気風が良く、職人らしい振る舞いにも好感が持てた。母のメアリーの尻に敷かれっぱなしの父親のラルフとはまるで違うよな、とミリーは思っていた。
ふと、サイという同じ年くらいの見習い大工の少年のことを思い出し、心配になった。明るくてお喋りなお調子者だったけれど、これで心が折れて仕事をやめたりはしないだろうか。
あれこれ考えていたミリーは、野次馬をどうにかするのも諦めて、店の扉に手をかける。
そこに、野太い声をかける者がいた。
「おう、ミリーちゃん」
「親方さん」
棟梁のアイヴァンだ。いつもは商売道具を肩に担いでいる人物だが、今日は手ぶらだ。この状況では仕事どころではないだろう。
「今日お仕事は――ってそれどころじゃないわよね。一体どうなってるの?」
ミリーが問うと、アイヴァンも困ったように腕を組んだ。
「いや、それがな。俺にもよくわからねぇんだよ。朝現場に行ったら、もう人がゴミみたいになっててよ。――教会の連中は来たか?」
「ううん、今日はまだ誰も。来たのかも知れないけど、あたしは知らない」
ミリーがかぶりをふれば、アイヴァンが、そうかと口をへの字にした。
「呑気なもんだな――そりゃそうとミリーちゃん、サイの奴を見てないか?」
「サイ? あのお喋りがどうかしたの?」
「いやな、真っ先に騒ぎそうな奴の面を見てねぇから、ちょっと気になってよ」
「あたしも常連さんに色々聞いてみる――けど、親方さん、これからどうするの」
アイヴァンは、そんなこと俺にもわからん、と言いたげに肩を竦めた。
「それより妙な建物だなぁ、こいつぁ。こんな様式の建物は、見たことも聞いたこともねぇや」
「やっぱり大工としては気になるもの?」
「そりゃあまあな……できればちゃんと中を見たいもんだが――これだけ人がいると、ロクすっぽ見えやしねぇなぁ」
二人が野次馬たちと大差ないやり取りを交わしていたところ、野次馬たちの喧騒がフェードアウトし、その群れが二つに割れた。
「――噂をすればってやつか」
人垣を割って現れたのは、豪華な鎧に身を包んだ大柄な男だ。白金の鎧の胸元には、アルティスのシンボルである双頭の蛇を象った紋様が刻まれている。白金色の板金鎧は、アルティス聖教会の聖騎士長のシンボルだ。
彫りの深い顔立ちはなかなか整っていて、威厳を漂わせているが、はっきり言って、濃い。雄臭い。ミリーの好みではなかった。
「――ホーマー聖騎士長、御自らお出ましってわけね。時間がかかるわけだわ」
男のくせに化粧でもしてたのかしらね、とミリーは小さく毒づいた。大きな都市ならどこにでもいる聖騎士だが、聖騎士長はそんな聖騎士の大隊を束ねる存在だ。与えられている権限は大きく、特に一国の首都に駐在する聖騎士の長ともなれば、相当な地位にあり、下手をすれば一教区を束ねる司教より大きな権力を持っていると言ってよいだろう。
それだけの地位と力がある人物だ。かなりの数の護衛を引き連れていて当然だが――ぞろぞろと、少々過剰に思える気がする。
「――ありゃあ、潰しに来てるな」
「――どういうこと?」
「――教会の威信にかけてってやつだろ。どんな大魔法だか知らんが、聖堂の建設予定地でこんだけ派手な悪戯が仕掛けられたんだ。何としても潰したいところだろうよ」
俺としちゃあ、仕事が増えて助かるがねと、アイヴァンは面白くなさそうに腕を組んだ。
「――悪戯にしてはちょっと、手が込みすぎじゃない?」
一夜にしてこれだけの建物と林を作り出すなど、どう考えても不可能だ。それこそ神の御業でもない限り。
「――だからこそ潰しておきたいんだろうよ」
この“悪戯”が神の御業であるとしたら、聖堂建立の計画は審判者アルティスの意に反した行いであるとなる。あるいは、異教の神の御業であるとしたら、アルティスの力がそれに劣ると証明されたことになる。いずれにしても、教会にとって不都合なのだ。
とはいえ、人の口に戸は立てられない。
アイヴァンとミリーが内緒話をしている間にも、ホーマー聖騎士長を先頭とした行列は、門――のようなモニュメント――をくぐっていった。
――動くには、ちょっと遅すぎるし、やり方が派手すぎるよな。
ミリーもアイヴァンも、そんなように思った。
***
王都では、一部の要人が住む区画を除いて、王国側で警備の兵を配置していない。
ミリーやアイヴァンたちが暮らす城郭外部の下町については、原則、街の有志が役所に形ばかり許可を得て武装し、警邏を行っている。いわゆる自警団だ。
最初は、他に職のある者が手の空いているときに行うボランティアだった自警団だが、都市が発展するにつれて、兼業では賄いきれなくなり、それに専念する者を必要とするようになる。専念する――つまり、職業とするとなると、色々問題も出てくる。それは金と、信頼と、人材の問題であった。
団員の指導、詰所の提供、武器防具など備品の供給、何より彼らの生活に必要な給金など。
現在その大半は教会から提供されている。
だから自警団は、教会の連中が悪さをしても、よほど露骨なものでない限り見逃さざるを得ない。結果、王都ではおおよそ人類の考え得る不正の全てが蔓延るような事態に陥っている。本来もっとも強く規制すべきアルティス聖教会が、商人とねんごろになっているのだから、始末に負えない。
教会が崇める神――審判者というより、聖職者たちが許す、と言ったら許されるのだ。理屈ではなく、そういう社会なのだ。
――納得が行かない。
詰所となっている掘っ建て小屋で、ジェイルは今日何度目か知れないため息をついた。
ジェイルは自警団の一員だ。年の頃は二十代前半。結婚適齢期であり、顔も性格も悪くないので異性からの誘いは絶えないのだが、色々と事情があって未だに独身を通している。
教会や商人たちに手綱を握られている自警団だが、双方との折り合いは必ずしも良いとは言えない。日々の生活がかかっているからしぶしぶ従ってはいるものの、団員の中には彼らに反発を抱いている者も少なくはないのだ。自警団に入る人間の大半が、最初は正義感に燃えて任に就くのだから、これはなんら不思議な話ではない。
ジェイルもそんなサイレント・マジョリティの一人である。彼はいつもどこか苛立っているが、今日はいつにもまして苛立っていた。
自分の縄張りで謎の建造物出現という大異変が起きたのに、お偉い司教様からのお達しで、足止めを喰らっているのだ。教会寄りの連中がどうだかは知らないが、少なくともジェイルはそう指示されている。
曰く、かの地での異変であれば、審判者の意思であるかも知れぬ。されば、神職に就く者によって、まずは場を改めねばならぬ。自警団は一切手出し無用。持ち場を動くな。
もっともらしいことを言ってはいるが、つまり自分の土地での変事に際して、面子を潰されたくないということだ。ところが、当の教会が未だ何の手も打っていない。人々は朝から異変に気づいたので、今はもう大変な騒ぎになっている。
ジェイルは端整な顔を歪めて貧乏ゆすりを始めていた。この数時間で、自警団は何もしないのか、と何度聞かれたかわからない。しないのではない、したくてもできないのだ。
もっとも、教会とよろしくやっている派閥の者はその限りではない。カルガモの雛のように聖騎士たちに付き従ってみせることで、治安維持組織としての体裁は保つつもりなのだろう。
ジェイルも自分一人でこの事態の収拾をつけられるとは思わない。ただ、腰の重い聖騎士団の動きを待っていては日が暮れる。
教会の機嫌を損ねれば間違いなく首が飛ぶだろうが、いい加減うんざりしていた。いよいよもって教会のお達しを無視して現場に足を踏み入れようかと腰を上げたとき、それを見計らったかのように掘っ建て小屋の扉が開かれた。
入ってきたのは二人の女だった。片方は背の高い女だ。年はジェイルと同じくらいだろう。仰々しい銀色の甲冑に身をまとっている。双頭の魚を象った紋章のついたそれは、明らかに教会聖騎士のものであると知れた。
女騎士は、アルレシャ大陸においてはさほど珍しい存在ではない。ただ往々にして、女戦士からは、色気というか、女らしさというものが感じられないので、そういう観点から見れば、この女騎士は極めて珍しい存在であると言えた。
切れ長の双眸にすらりと通った鼻梁。長く伸ばした淡い金髪。文句なしの美女と言える。大仰な板金鎧さえもその美貌を際立たせていた。
また、腕っ節に自信のあるジェイルから見ても、この女がただのお飾りでないことはわかる。重い板金鎧を着て歩きまわるには、相当な筋力が必要だからだ。
もう片方の女は、まだ少女と言ってもよさそうな外見だった。モノトーンだが質のいいローブをまとっているあたり、おそらくは正司祭だろう。十代後半か。ただ童顔なだけかも知れないが、いずれにしても、この若さで司祭なのだとしたら結構な才媛にちがいない。だが、とにかく地味である。
王国においても高価な眼鏡をかけており、司祭としての格はそれなりに高いと推測できるが、まるで威厳というものが感じられない。服に着られている感も否めなかった。聖騎士は司祭に従うものだが、どう見てもこの少女の方が従者である。
「……こんなところに何か御用ですかね?」
しかし、こんな若い司祭がいるなら、噂くらいは流れてきそうなものだ。見かけない顔だな、とジェイルは内心で首を捻る。
「突然のご訪問、お詫びいたします。わたくしどもは今日の朝方、街についたばかりでして――事情がよく呑み込めていないのですが、何が起きているのでしょう?」
「はっ?」
ジェイルは表情を作るのも忘れて、思わず頓狂な声を上げていた。そんなこと、他の司祭に聞けばいい話だ。
「失礼。私は教会聖騎士のアンリエッタ・ウィルマーだ。彼女は正司祭のメリッサ。我々は、異変を察したマザー・クレアの命によりこの街に馳せ参じたのだが、他の司祭に事情を尋ねてもなかなかまともな返答がなくてな。遅参のほどはお詫び申し上げる。貴殿がジェイル殿でお間違いないか?」
「あ――いや、ジェイルは確かに俺ですが……マザー・クレアっていうと、ベネトナシュ修道院から?」
基本、教会の人間は縄張り意識が強い。彼女らが厄介払いにされてここに来たことは想像に難くない。
「よくご存じで。ええと、何が起こっているのか、ジェイルさんは把握しておられますか?」
ベネトナシュ修道院は、エルナト王国でも最大の女子修道院である。その長マザー・クレアは齢七十を超える老女だが、その人徳の致すところはこの王都まで届いている。ジェイルも兼ねてから聞き及んでいたほどで、彼女の使いであれば信用に足る人物なのだろう。
「はい。ご説明します」
ジェイルは居住まいをただし、掻いつまんで事情を説明する。
落雷による火災が発生し、その跡地に聖堂が建てられる予定であったこと。そこに今朝方謎の建造物が出現したこと。教会の牽制のおかげで、自警団はおろか王国の兵士たちも手が出せていないこと。
話を聞いたメリッサは、ちっとも悪くないのに自分が悪いことをしたかのように頭を下げた。
「申し訳ございません。やはりわたくしたちの都合で、ジェイルさんたちにはご迷惑をおかけしているようです」
「いや、別にあんたに謝ってほしいわけじゃないんですよ。頭を上げてください」
頭を掻いたジェイルに、メリッサは苦笑する。一部の聖職者たちによる汚職は、もはや公然の秘密であるし、そのために純粋な信仰心が損なわれることは、彼女のように善良な司祭にとっては頭の痛い問題なのだろう。かといってこの若さでは、手の出しようもあるまい。
「我々としてはそのあたりの事情も色々とお尋ねしたいのだが、差し当たっては聖騎士の暴走を止める必要があるな。ジェイル殿、この街はどうにも入り組んでいて困る。すまないが、案内を頼めないだろうか」
がちゃがちゃと音を立てて、アンリエッタが頭を下げる。
「そう畏まらなくていいですよ。道案内くらいいくらでも――まあ、それで済みそうにないのが問題ですがね」
ジェイルは軽く肩を竦め、槍を手にとった。集まってる人数が人数なんで、多少手荒なことになるかも知れません、と付け加えておくのを忘れない。メリッサの顔が少し引きつった。
「ジェイル殿、随分腕に自信があるようだが、話を聞く限り、聖騎士はそれなりの人数が集まってるのだろう?」
掘っ建て小屋を三人で出て、形ばかりの鍵をかけるジェイルに、アンリエッタが忠告混じりの声をかけるが、当のジェイルは不敵に笑ってみせた。
「いや、何しろここいらは治安が悪くてね、荒事には慣れてんだ。ロクに人も斬ったことがない教会聖騎士の一束くらい、蹴散らしてやりますよ」
ジェイルの遠慮ない物言いに、並んで歩きはじめたアンリエッタは苦笑いする。
「同じ教会聖騎士としては耳の痛い話だな――まあ、否定はしないが」
「お二人とも、なぜ荒事が前提なんですか! わ、わたくしは嫌ですよ、話し合いで決着をつけましょう」
歩幅の都合上早歩きになるメリッサが、慌てて二人の剣呑な発想を咎める。
「わたくしの術はその、性質上――手加減というものがしづらいのです」
最後の一言で、全く説得力がなくなった。
「……メリッサ。君はいつも通り援護に徹してくれ」
「は、はい、自重します」
「ああ、お二人さん、ちょっと待ってくださいね。様子を探りますんで……《大いなる福音よ、我が耳を打て》」
ジェイルは目を閉じて、《神聖語》を詠唱する。自らを加護する《使徒》に呼びかけ、体を巡る《魂の質量》を引き渡して奇跡を呼ぶのが、この世界における一般的な魔法――厳密に言うと、法術だ。
教会の洗礼を受け、アルティスに帰依することで、個人差はあれど誰もがこうした術を扱うことができるようになる。アルティス聖教会が絶大な権勢を誇っている理由の一つだ。
「まあ、《遠耳》ですか。また珍しい術ですね」
「メリッサ、静かに」
口を挟んだメリッサを、アンリエッタが咎める。
この手の術で、自分に必要な情報を選り分けるのは難しい。一自警団員に過ぎない身でそれをやってのけているジェイルの技術に、メリッサは感嘆し、思わず声をあげてしまったのだ。
「――急いだ方が良さそうですね。聖騎士長が件の建物の住人に接触したらしい。どうにも剣呑な雰囲気です」
0
あなたにおすすめの小説

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

私が王子との結婚式の日に、妹に毒を盛られ、公衆の面前で辱められた。でも今、私は時を戻し、運命を変えに来た。
MayonakaTsuki
恋愛
王子との結婚式の日、私は最も信頼していた人物――自分の妹――に裏切られた。毒を盛られ、公開の場で辱められ、未来の王に拒絶され、私の人生は血と侮辱の中でそこで終わったかのように思えた。しかし、死が私を迎えたとき、不可能なことが起きた――私は同じ回廊で、祭壇の前で目を覚まし、あらゆる涙、嘘、そして一撃の記憶をそのまま覚えていた。今、二度目のチャンスを得た私は、ただ一つの使命を持つ――真実を突き止め、奪われたものを取り戻し、私を破滅させた者たちにその代償を払わせる。もはや、何も以前のままではない。何も許されない。

ネグレクトされていた四歳の末娘は、前世の経理知識で実家の横領を見抜き追放されました。これからはもふもふ聖獣と美食巡りの旅に出ます。
☆ほしい
ファンタジー
アークライト子爵家の四歳の末娘リリアは、家族から存在しないものとして扱われていた。食事は厨房の残飯、衣服は兄姉のお下がりを更に継ぎ接ぎしたもの。冷たい床で眠る日々の中、彼女は高熱を出したことをきっかけに前世の記憶を取り戻す。
前世の彼女は、ブラック企業で過労死した経理担当のOLだった。
ある日、父の書斎に忍び込んだリリアは、ずさんな管理の家計簿を発見する。前世の知識でそれを読み解くと、父による悪質な横領と、家の財産がすでに破綻寸前であることが判明した。
「この家は、もうすぐ潰れます」
家族会議の場で、リリアはたった四歳とは思えぬ明瞭な口調で破産の事実を突きつける。激昂した父に「疫病神め!」と罵られ家を追い出されたリリアだったが、それは彼女の望むところだった。
手切れ金代わりの銅貨数枚を握りしめ、自由を手に入れたリリア。これからは誰にも縛られず、前世で夢見た美味しいものをたくさん食べる生活を目指す。

戦場帰りの俺が隠居しようとしたら、最強の美少女たちに囲まれて逃げ場がなくなった件
さん
ファンタジー
戦場で命を削り、帝国最強部隊を率いた男――ラル。
数々の激戦を生き抜き、任務を終えた彼は、
今は辺境の地に建てられた静かな屋敷で、
わずかな安寧を求めて暮らしている……はずだった。
彼のそばには、かつて命を懸けて彼を支えた、最強の少女たち。
それぞれの立場で戦い、支え、尽くしてきた――ただ、すべてはラルのために。
今では彼の屋敷に集い、仕え、そして溺愛している。
「ラルさまさえいれば、わたくしは他に何もいりませんわ!」
「ラル様…私だけを見ていてください。誰よりも、ずっとずっと……」
「ねぇラル君、その人の名前……まだ覚えてるの?」
「ラル、そんなに気にしなくていいよ!ミアがいるから大丈夫だよねっ!」
命がけの戦場より、ヒロインたちの“甘くて圧が強い愛情”のほうが数倍キケン!?
順番待ちの寝床争奪戦、過去の恋の追及、圧バトル修羅場――
ラルの平穏な日常は、最強で一途な彼女たちに包囲されて崩壊寸前。
これは――
【過去の傷を背負い静かに生きようとする男】と
【彼を神のように慕う最強少女たち】が織りなす、
“甘くて逃げ場のない生活”の物語。
――戦場よりも生き延びるのが難しいのは、愛されすぎる日常だった。
※表紙のキャラはエリスのイメージ画です。

愛された側妃と、愛されなかった正妃
編端みどり
恋愛
隣国から嫁いだ正妃は、夫に全く相手にされない。
夫が愛しているのは、美人で妖艶な側妃だけ。
連れて来た使用人はいつの間にか入れ替えられ、味方がいなくなり、全てを諦めていた正妃は、ある日側妃に子が産まれたと知った。自分の子として育てろと無茶振りをした国王と違い、産まれたばかりの赤ん坊は可愛らしかった。
正妃は、子育てを通じて強く逞しくなり、夫を切り捨てると決めた。
※カクヨムさんにも掲載中
※ 『※』があるところは、血の流れるシーンがあります
※センシティブな表現があります。血縁を重視している世界観のためです。このような考え方を肯定するものではありません。不快な表現があればご指摘下さい。

王子を身籠りました
青の雀
恋愛
婚約者である王太子から、毒を盛って殺そうとした冤罪をかけられ収監されるが、その時すでに王太子の子供を身籠っていたセレンティー。
王太子に黙って、出産するも子供の容姿が王家特有の金髪金眼だった。
再び、王太子が毒を盛られ、死にかけた時、我が子と対面するが…というお話。

クラス転移したけど、皆さん勘違いしてません?
青いウーパーと山椒魚
ファンタジー
加藤あいは高校2年生。
最近ネット小説にハマりまくっているごく普通の高校生である。
普通に過ごしていたら異世界転移に巻き込まれた?
しかも弱いからと森に捨てられた。
いやちょっとまてよ?
皆さん勘違いしてません?
これはあいの不思議な日常を書いた物語である。
本編完結しました!
相変わらず話ごちゃごちゃしていると思いますが、楽しんでいただけると嬉しいです!
1話は1000字くらいなのでササッと読めるはず…

【完結】辺境に飛ばされた子爵令嬢、前世の経営知識で大商会を作ったら王都がひれ伏したし、隣国のハイスペ王子とも結婚できました
いっぺいちゃん
ファンタジー
婚約破棄、そして辺境送り――。
子爵令嬢マリエールの運命は、結婚式直前に無惨にも断ち切られた。
「辺境の館で余生を送れ。もうお前は必要ない」
冷酷に告げた婚約者により、社交界から追放された彼女。
しかし、マリエールには秘密があった。
――前世の彼女は、一流企業で辣腕を振るった経営コンサルタント。
未開拓の農産物、眠る鉱山資源、誠実で働き者の人々。
「必要ない」と切り捨てられた辺境には、未来を切り拓く力があった。
物流網を整え、作物をブランド化し、やがて「大商会」を設立!
数年で辺境は“商業帝国”と呼ばれるまでに発展していく。
さらに隣国の完璧王子から熱烈な求婚を受け、愛も手に入れるマリエール。
一方で、税収激減に苦しむ王都は彼女に救いを求めて――
「必要ないとおっしゃったのは、そちらでしょう?」
これは、追放令嬢が“経営知識”で国を動かし、
ざまぁと恋と繁栄を手に入れる逆転サクセスストーリー!
※表紙のイラストは画像生成AIによって作られたものです。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる
本作については削除予定があるため、新規のレンタルはできません。
このユーザをミュートしますか?
※ミュートすると該当ユーザの「小説・投稿漫画・感想・コメント」が非表示になります。ミュートしたことは相手にはわかりません。またいつでもミュート解除できます。
※一部ミュート対象外の箇所がございます。ミュートの対象範囲についての詳細はヘルプにてご確認ください。
※ミュートしてもお気に入りやしおりは解除されません。既にお気に入りやしおりを使用している場合はすべて解除してからミュートを行うようにしてください。