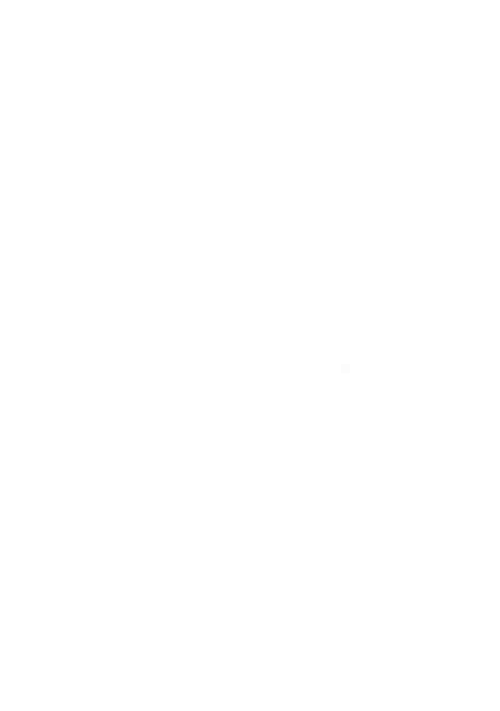60 / 68
四章
3☆
しおりを挟む
どうしようもなく悶々としている。
自宅待機の指示を守るため、一定期間屋敷内で過ごすことになる。いつもなら苦にならない、何の変哲もない時間。それが今は仇となっていた。書斎のことから気を逸らせず、ため息が止まらない。
少しでも意識すると、半身が勃ち上がってくるのだ。
「な、なんで……」
その衝動を抑えるため壁を見、頭を打ち付けようとして……それも出来なかった。こんなの卑怯だ。壁の代わりに手の甲をつける。
あんな弱った声を聞かせられたら、気を使わないはずがない。自分を痛めつけるという対策が取れない。これ以上苦しませないように、なんて同情している俺は、一体何なのだろう。
「うぅぅ……」
どうにか騙し騙し、本を読み、身体を動かし、警備具を磨き手入れをしながら、それでも平静を保てない場合はイーライと他愛のない話をして、夜まで耐えた。
夜まで耐えて、限界だった。
「何やってんだ、俺……」
寝室のベッドの上、壁に背中をつけて視線を下げる。寝間着を内側から押し上げヒクつく半身。それを人差し指だけでたどたどしく弄っていた。本当に、何をしているのだろう。目を閉じ、記憶に鮮明に残る動きを再現する。
「んっ……、ぅ……」
縁の部分を引っかくように刺激すれば、布越しの鋭くじれったい感覚に腰が跳ね、吐息が漏れた。
「はぁ……」
前まではここも、こんなに感じることは無かった。それにどう触るかなんて意識することも無かった。ただ右手で握って、上下に動かすだけ。
魔女と関わってから少しずつ、確実に変化してきている自分に恐怖する。それでも湧き上がる欲、己を慰めるためそれを露出させた。
とろりと溢れる先走りを纏わせ、いつものように手を動かし始める。
「ぁ、……ぅ、……ふっ……」
ゆるゆると気持ちがいい。多めに息を吐いて声量を落とす。徐々に積み重なる快感に、何となく周りを見回した。ランプにぼんやりと照らされた室内に、変化はない。何かの気配さえ感じられない。何を期待しているのだろう。
「……んっ」
小刻みに扱きながら、ベッドサイドにある貴重品入れに手を伸ばした。開けて、その中にある物を取り出す。
――魔女のハンカチ……。
見つめて、何となく頬擦りした。肌触りは良いが、やはりあの香りはしない。すっかり消えてしまっている。
「っ……、んっ……」
何故か悲しくなって、段々と肺に溜まる空気が重くなってきた。
「……んん、……ん」
イきたいのに、もう少しでイける気がするのに、一向にその時は訪れない。いつもより強めに握ってみても、どうしても半身は満足しなかった。
「うぅ……」
やはり理性が邪魔をする。頭の片隅で自分が問いかけてくる。“お前は何をしているんだ、心を一定に保て”と。欲に溺れるな、欲するな。それが何をもたらすのか、理解しているのか。
「くっ……」
求めて、何も得られなかった過去を思い出せ。求めて、全てを傷つけた過去を思い出せ。最後に後悔するのはいつも自分だ。
「うううぅ……!」
内面に向けていた視線を上げ、周りを見回す。相変わらず変化は無く、冷えた空気に温もりが無い。
ほら見ろ、自覚しろ。求めるな。
「……は、ははっ……」
乾いた笑いが漏れる。何故なら葛藤している内に手の中のモノは――すっかり萎えてしまっていたから。
諦めがついて、手と元気が無くなった半身をハンカチで拭いた。機能しない自己嫌悪で歯噛みする。嫌な音が鳴った。
「大丈夫、落ち着け。これで良いんだ……」
眉間にシワを寄せ目を閉じ、深呼吸する。
「寂しくない。俺にはイーライがいる。他には何もいらない」
心の平穏を保って、一定のまま。永遠の不変を目指すんだ。自分はそうでなければならない、あらなければならない。
「早くあいつを捕まえて、解呪して、日常に戻る」
呪文のように決意を唱え終え、目を開けるとベッドから降りた。
こっちが手詰まりでも国が探してくれる。事情を話して、解呪をしたらさよならだ。決してあいつの思い通りになんて、なってやらない。
汚れてしまったハンカチを洗いに、寝室を出て洗面所まで歩く。薄暗い廊下を歩きながら、手の中のハンカチを見た。丸角の可愛らしい女物のハンカチ。捨ててしまえばいいのに、何故まだ手元に置いているのだろう。
ドアを開けて洗面台の蛇口を捻り、生地が傷まないよう優しく洗いながら考える。
……思い通りになんてなってやらない。だが、機会があるならちゃんと話をしてみたい。向き合って、あいつの考えを理解してみたい。あいつは本当に、何を考えているのだろう。こちらに苦痛を与えるつもりはなく、ただ快楽を与えてくる、その目的はなんだ。
“いっぱい出して、たくさん出して!”
反応しかける半身を意志で抑え込む。
「……そう、だな」
心に引っかかった単語をまとめるため、声に出してみた。
「まるで射精訓練……、みたいな?」
辿り着いた馬鹿馬鹿しい答えに笑ってしまう。そんな訳あるか。そんなもの、あいつに何の得がある。
目の前の鏡を見れば、頼りなさげに口を歪める男がいた。独りでハンカチを洗っている、情けない男だ。そいつは鏡の世界に視線を走らせて、小さく呟いた。
「……俺はイーライさえいれば、それでいい……」
視線を落とす。溜めた水に映る憂いを帯びた表情。それは過去に散々人殺し、悪魔、厄介者と罵られた、子供の面影を残していた――。
※※※
ふわふわとまどろみの中、夢と現実の狭間を漂う。自分の内面を掘り返すなんて滅多にやらないことだが、今は疲れているみたいだ。止めておけばいいのに、思考が形どってしまう。
もう誰も遊んではくれない、もう誰も褒めてはくれない、もう誰も俺が求めるものを与えてはくれない。
通常なら与えられるはずのそれを、子供のうちに取り上げられ、大人になってしまったから。わかっている、知っている、諦めている。
だから捨て切れない欲求を頭の隅っこに追いやって、閉じ込めた。退屈な毎日に“幸せ”と名付けて、そいつを刺激しないように過ごしてきた。
それで十分に満たされ、今まで穏やかな人生を過ごしてきたはずなんだ。これからもそれは変わらないはずで、はずだった。どうしてこうなった。何を間違えた。
――耳元で誰かが甘く囁いてくる。
“ねぇ、アルトス。二週間経つけどまだ私を見つけられないの? あーあ、余裕すぎて笑っちゃうんだけど”
うるさい、まだ勝負はついていない。勝手に笑っていろ。必ず見つけ出して、その高みから引きずり下ろしてやる。
“ねぇ、アルトス。あの時どうして舌を噛まなかったの? 私に気を使ってる? 壁に頭も打ち付けなかったよね。ふふ、やっぱりそう? アルトスはいい子だねぇ。よしよし!”
やめろ、撫でるな。俺はペットじゃない。これはあれだ、俺だって痛いのは嫌いなんだ。
“ふうん。ねぇ、アルトス。この子、朝から凄く元気だよ? 服の上から弄ってあげようか? すりすりって……ほら、大きくなった”
お前! 朝から、なに、して……! き、気持ちよくなんか無い! やめろ、俺はそんなもの求めてなんか、んっ、あ、あっ――。
「あっ! や、やめろって!」
腕の中のそれを抱き締めて、言葉とは裏腹に腰を押し付けていた。寝起きで緩んだ理性に本能が勝る。身体が悦び、甘い刺激に目を開けて――。
「あ……」
腕の中を見ると、それはただの枕だった。何を期待していたのか、気分が急降下する。
「う……」
下半身を確認すると朝立ちしていた。無意識に枕へ擦り付けていたのか? いや、でも……。
視線を彷徨わせる。
――温もりがあったんだ。
自分でも理解出来ないくらい独り駄々をこね始め、更に強く枕を抱き締めた。
「なんで、どうしてこんな夢を……」
悲しくなって枕に顔を埋める。ぐるぐると無意味に思考が回って、息を吸い込み気が付いた。
香りがする……?
慌てて上体を起こし枕を持ち上げてみた。すると昨日洗って窓際に干しておいたはずのハンカチが、畳まれた状態で枕下に置いてあった。
――たっぷりと、花の香りを吸って。
掴み上げる手が震える。
あの感覚、やっぱりあいつはいたんだ。寝ているうちに、来ていたんだ。何故起こさなかった。何故こんな風に、残り香だけを置いていく。
「こ、こんな、……もう……」
閉じ込めていたはずの欲求が、もっと、もっとと性欲に引きずられ顔を出す。違う、こんなの俺じゃない。堪らず叫んだ。
「もう、やめてくれ! 何なんだよこれは!! 関わるならちゃんと関われよ!! つかず離れずが一番厄介なんだ!! 何をさせたい、何がしたい!? やめてくれよ! 本当にもう、こんな、……ひどい、こと……!」
まるで拷問のような仕打ちに目頭が熱くなる。波のように押し寄せては引いていく、魔女の戯れ。駄目だ、耐えろ、負けを認めるのか。泣いたら負けだ。
「俺はお前なんか……大嫌いだ!!」
甘く堕落を囁かれるせいで心はグチャグチャで、元凶のハンカチを掴んでゴミ箱に投げ捨てようとした。振りかぶって、後は手を離せばいいだけなのに。
「大嫌いだ……!」
離せない。逆に握り締めて、うなだれた。自分が理解できない。やめてくれ、この感情はなんだ。ベッドが軋んで、音が鳴る。
「イーライ……」
だから完璧な従者を求めた。決してこんな風に俺を傷つけることがない、完璧な従者を。
ハンカチを枕元に放って、寝室から飛び出した。従者を探して、独りで暮らすには広すぎる屋敷を駆ける。
「イーライ、イーライ!」
階段を駆け下り叫んで、厨房から出てきた従者が驚きの表情と共にこちらを見た。
「アルトス様?」
駆け寄って、一瞬だけ迷って、その胸に縋りつく。
「イーライ、俺を抱き締めてくれ……」
「! 喜んで」
ゆっくりと背中に腕が回され、そっと抱き締められた。優しい抱擁。
「もう少しだけ、強めに……」
「承知いたしました」
望み通り強めに抱き締められる。丁度いい圧迫感。こっちもイーライの背中に腕を回して、抱き締め返した。恥を捨てて、その首元に頭の重みを預ける。
「アルトス様……? いかがなさいましたか?」
イーライに体温は無い。触れてきた生物の体温をそっくりそのまま返す加工が施されている、変温体だ。つまり温かくもないし、冷たくもない。それが何より満たされる、心地いい感触のはずだった。
「ごめん……。多分、嫌な夢を見たんだ。だから、だから……」
でもこれはなんだ。安心はするが、何故か満たされない。捨て切れない欲の強さに動揺する。
そんな感情を切り捨てるため、音が鳴るほど紳士服を握り締め、目を瞑った。
「――アルトス様」
口を噤んで肩を震わすだけの情けない主に、これは本当に出来た従者だ。何も聞かず、当然のようにあやしてくれる。後頭部に手を添えられ、優しく背中を撫でられた。
「朝食が済んだら調髪いたしましょう。前髪が随分伸びてしまいましたね」
首を傾け見上げる、視線を合わせたそれは穏やかに微笑んでいた。手櫛で髪を整え分けられ、今回はこれぐらいにしましょうかと提案される。いつも任せきりのため、こちらでは良し悪しの判断が出来ない。だが、イーライが良いと言うのなら、それは最適解なのだろう。抱き締める腕に力を込めて、同意を返した。
適度な距離を取りつつ、日常を、平穏を取り戻そうとしてくれている、一番の理解者。
「ありがとう、イーライ……」
イーライが居なければ、とっくの昔にこんな人生も諦めていた。かけがえのない家族なんだ。父親であり、母親でもあり、苦楽を共にする兄弟だった。心地のよい声音に、徐々に荒んだ精神が落ち着いてくる。
良かった、まだ戻れる。いつもの自分に。
「俺、イーライのこと……大好きだ」
「存じております」
らしくない高慢な応えに、色めく赤瞳を見上げた。その表情は乏しいなりに嬉しそうだ。
「はは! こんなイーライ初めてだよ」
「私も、こんなアルトス様は初めてです。貴方様は中々私のことを頼ってくださいませんから」
ポンポンと背中を叩かれ、抱き合う現状を思い出した。気恥ずかしくなって、身体を離し笑い合う。
俺はイーライが隣にいてくれたらそれでいい。
一時的であっても、従者のお陰ですっかり魔女を忘れることが出来た。
自宅待機の指示を守るため、一定期間屋敷内で過ごすことになる。いつもなら苦にならない、何の変哲もない時間。それが今は仇となっていた。書斎のことから気を逸らせず、ため息が止まらない。
少しでも意識すると、半身が勃ち上がってくるのだ。
「な、なんで……」
その衝動を抑えるため壁を見、頭を打ち付けようとして……それも出来なかった。こんなの卑怯だ。壁の代わりに手の甲をつける。
あんな弱った声を聞かせられたら、気を使わないはずがない。自分を痛めつけるという対策が取れない。これ以上苦しませないように、なんて同情している俺は、一体何なのだろう。
「うぅぅ……」
どうにか騙し騙し、本を読み、身体を動かし、警備具を磨き手入れをしながら、それでも平静を保てない場合はイーライと他愛のない話をして、夜まで耐えた。
夜まで耐えて、限界だった。
「何やってんだ、俺……」
寝室のベッドの上、壁に背中をつけて視線を下げる。寝間着を内側から押し上げヒクつく半身。それを人差し指だけでたどたどしく弄っていた。本当に、何をしているのだろう。目を閉じ、記憶に鮮明に残る動きを再現する。
「んっ……、ぅ……」
縁の部分を引っかくように刺激すれば、布越しの鋭くじれったい感覚に腰が跳ね、吐息が漏れた。
「はぁ……」
前まではここも、こんなに感じることは無かった。それにどう触るかなんて意識することも無かった。ただ右手で握って、上下に動かすだけ。
魔女と関わってから少しずつ、確実に変化してきている自分に恐怖する。それでも湧き上がる欲、己を慰めるためそれを露出させた。
とろりと溢れる先走りを纏わせ、いつものように手を動かし始める。
「ぁ、……ぅ、……ふっ……」
ゆるゆると気持ちがいい。多めに息を吐いて声量を落とす。徐々に積み重なる快感に、何となく周りを見回した。ランプにぼんやりと照らされた室内に、変化はない。何かの気配さえ感じられない。何を期待しているのだろう。
「……んっ」
小刻みに扱きながら、ベッドサイドにある貴重品入れに手を伸ばした。開けて、その中にある物を取り出す。
――魔女のハンカチ……。
見つめて、何となく頬擦りした。肌触りは良いが、やはりあの香りはしない。すっかり消えてしまっている。
「っ……、んっ……」
何故か悲しくなって、段々と肺に溜まる空気が重くなってきた。
「……んん、……ん」
イきたいのに、もう少しでイける気がするのに、一向にその時は訪れない。いつもより強めに握ってみても、どうしても半身は満足しなかった。
「うぅ……」
やはり理性が邪魔をする。頭の片隅で自分が問いかけてくる。“お前は何をしているんだ、心を一定に保て”と。欲に溺れるな、欲するな。それが何をもたらすのか、理解しているのか。
「くっ……」
求めて、何も得られなかった過去を思い出せ。求めて、全てを傷つけた過去を思い出せ。最後に後悔するのはいつも自分だ。
「うううぅ……!」
内面に向けていた視線を上げ、周りを見回す。相変わらず変化は無く、冷えた空気に温もりが無い。
ほら見ろ、自覚しろ。求めるな。
「……は、ははっ……」
乾いた笑いが漏れる。何故なら葛藤している内に手の中のモノは――すっかり萎えてしまっていたから。
諦めがついて、手と元気が無くなった半身をハンカチで拭いた。機能しない自己嫌悪で歯噛みする。嫌な音が鳴った。
「大丈夫、落ち着け。これで良いんだ……」
眉間にシワを寄せ目を閉じ、深呼吸する。
「寂しくない。俺にはイーライがいる。他には何もいらない」
心の平穏を保って、一定のまま。永遠の不変を目指すんだ。自分はそうでなければならない、あらなければならない。
「早くあいつを捕まえて、解呪して、日常に戻る」
呪文のように決意を唱え終え、目を開けるとベッドから降りた。
こっちが手詰まりでも国が探してくれる。事情を話して、解呪をしたらさよならだ。決してあいつの思い通りになんて、なってやらない。
汚れてしまったハンカチを洗いに、寝室を出て洗面所まで歩く。薄暗い廊下を歩きながら、手の中のハンカチを見た。丸角の可愛らしい女物のハンカチ。捨ててしまえばいいのに、何故まだ手元に置いているのだろう。
ドアを開けて洗面台の蛇口を捻り、生地が傷まないよう優しく洗いながら考える。
……思い通りになんてなってやらない。だが、機会があるならちゃんと話をしてみたい。向き合って、あいつの考えを理解してみたい。あいつは本当に、何を考えているのだろう。こちらに苦痛を与えるつもりはなく、ただ快楽を与えてくる、その目的はなんだ。
“いっぱい出して、たくさん出して!”
反応しかける半身を意志で抑え込む。
「……そう、だな」
心に引っかかった単語をまとめるため、声に出してみた。
「まるで射精訓練……、みたいな?」
辿り着いた馬鹿馬鹿しい答えに笑ってしまう。そんな訳あるか。そんなもの、あいつに何の得がある。
目の前の鏡を見れば、頼りなさげに口を歪める男がいた。独りでハンカチを洗っている、情けない男だ。そいつは鏡の世界に視線を走らせて、小さく呟いた。
「……俺はイーライさえいれば、それでいい……」
視線を落とす。溜めた水に映る憂いを帯びた表情。それは過去に散々人殺し、悪魔、厄介者と罵られた、子供の面影を残していた――。
※※※
ふわふわとまどろみの中、夢と現実の狭間を漂う。自分の内面を掘り返すなんて滅多にやらないことだが、今は疲れているみたいだ。止めておけばいいのに、思考が形どってしまう。
もう誰も遊んではくれない、もう誰も褒めてはくれない、もう誰も俺が求めるものを与えてはくれない。
通常なら与えられるはずのそれを、子供のうちに取り上げられ、大人になってしまったから。わかっている、知っている、諦めている。
だから捨て切れない欲求を頭の隅っこに追いやって、閉じ込めた。退屈な毎日に“幸せ”と名付けて、そいつを刺激しないように過ごしてきた。
それで十分に満たされ、今まで穏やかな人生を過ごしてきたはずなんだ。これからもそれは変わらないはずで、はずだった。どうしてこうなった。何を間違えた。
――耳元で誰かが甘く囁いてくる。
“ねぇ、アルトス。二週間経つけどまだ私を見つけられないの? あーあ、余裕すぎて笑っちゃうんだけど”
うるさい、まだ勝負はついていない。勝手に笑っていろ。必ず見つけ出して、その高みから引きずり下ろしてやる。
“ねぇ、アルトス。あの時どうして舌を噛まなかったの? 私に気を使ってる? 壁に頭も打ち付けなかったよね。ふふ、やっぱりそう? アルトスはいい子だねぇ。よしよし!”
やめろ、撫でるな。俺はペットじゃない。これはあれだ、俺だって痛いのは嫌いなんだ。
“ふうん。ねぇ、アルトス。この子、朝から凄く元気だよ? 服の上から弄ってあげようか? すりすりって……ほら、大きくなった”
お前! 朝から、なに、して……! き、気持ちよくなんか無い! やめろ、俺はそんなもの求めてなんか、んっ、あ、あっ――。
「あっ! や、やめろって!」
腕の中のそれを抱き締めて、言葉とは裏腹に腰を押し付けていた。寝起きで緩んだ理性に本能が勝る。身体が悦び、甘い刺激に目を開けて――。
「あ……」
腕の中を見ると、それはただの枕だった。何を期待していたのか、気分が急降下する。
「う……」
下半身を確認すると朝立ちしていた。無意識に枕へ擦り付けていたのか? いや、でも……。
視線を彷徨わせる。
――温もりがあったんだ。
自分でも理解出来ないくらい独り駄々をこね始め、更に強く枕を抱き締めた。
「なんで、どうしてこんな夢を……」
悲しくなって枕に顔を埋める。ぐるぐると無意味に思考が回って、息を吸い込み気が付いた。
香りがする……?
慌てて上体を起こし枕を持ち上げてみた。すると昨日洗って窓際に干しておいたはずのハンカチが、畳まれた状態で枕下に置いてあった。
――たっぷりと、花の香りを吸って。
掴み上げる手が震える。
あの感覚、やっぱりあいつはいたんだ。寝ているうちに、来ていたんだ。何故起こさなかった。何故こんな風に、残り香だけを置いていく。
「こ、こんな、……もう……」
閉じ込めていたはずの欲求が、もっと、もっとと性欲に引きずられ顔を出す。違う、こんなの俺じゃない。堪らず叫んだ。
「もう、やめてくれ! 何なんだよこれは!! 関わるならちゃんと関われよ!! つかず離れずが一番厄介なんだ!! 何をさせたい、何がしたい!? やめてくれよ! 本当にもう、こんな、……ひどい、こと……!」
まるで拷問のような仕打ちに目頭が熱くなる。波のように押し寄せては引いていく、魔女の戯れ。駄目だ、耐えろ、負けを認めるのか。泣いたら負けだ。
「俺はお前なんか……大嫌いだ!!」
甘く堕落を囁かれるせいで心はグチャグチャで、元凶のハンカチを掴んでゴミ箱に投げ捨てようとした。振りかぶって、後は手を離せばいいだけなのに。
「大嫌いだ……!」
離せない。逆に握り締めて、うなだれた。自分が理解できない。やめてくれ、この感情はなんだ。ベッドが軋んで、音が鳴る。
「イーライ……」
だから完璧な従者を求めた。決してこんな風に俺を傷つけることがない、完璧な従者を。
ハンカチを枕元に放って、寝室から飛び出した。従者を探して、独りで暮らすには広すぎる屋敷を駆ける。
「イーライ、イーライ!」
階段を駆け下り叫んで、厨房から出てきた従者が驚きの表情と共にこちらを見た。
「アルトス様?」
駆け寄って、一瞬だけ迷って、その胸に縋りつく。
「イーライ、俺を抱き締めてくれ……」
「! 喜んで」
ゆっくりと背中に腕が回され、そっと抱き締められた。優しい抱擁。
「もう少しだけ、強めに……」
「承知いたしました」
望み通り強めに抱き締められる。丁度いい圧迫感。こっちもイーライの背中に腕を回して、抱き締め返した。恥を捨てて、その首元に頭の重みを預ける。
「アルトス様……? いかがなさいましたか?」
イーライに体温は無い。触れてきた生物の体温をそっくりそのまま返す加工が施されている、変温体だ。つまり温かくもないし、冷たくもない。それが何より満たされる、心地いい感触のはずだった。
「ごめん……。多分、嫌な夢を見たんだ。だから、だから……」
でもこれはなんだ。安心はするが、何故か満たされない。捨て切れない欲の強さに動揺する。
そんな感情を切り捨てるため、音が鳴るほど紳士服を握り締め、目を瞑った。
「――アルトス様」
口を噤んで肩を震わすだけの情けない主に、これは本当に出来た従者だ。何も聞かず、当然のようにあやしてくれる。後頭部に手を添えられ、優しく背中を撫でられた。
「朝食が済んだら調髪いたしましょう。前髪が随分伸びてしまいましたね」
首を傾け見上げる、視線を合わせたそれは穏やかに微笑んでいた。手櫛で髪を整え分けられ、今回はこれぐらいにしましょうかと提案される。いつも任せきりのため、こちらでは良し悪しの判断が出来ない。だが、イーライが良いと言うのなら、それは最適解なのだろう。抱き締める腕に力を込めて、同意を返した。
適度な距離を取りつつ、日常を、平穏を取り戻そうとしてくれている、一番の理解者。
「ありがとう、イーライ……」
イーライが居なければ、とっくの昔にこんな人生も諦めていた。かけがえのない家族なんだ。父親であり、母親でもあり、苦楽を共にする兄弟だった。心地のよい声音に、徐々に荒んだ精神が落ち着いてくる。
良かった、まだ戻れる。いつもの自分に。
「俺、イーライのこと……大好きだ」
「存じております」
らしくない高慢な応えに、色めく赤瞳を見上げた。その表情は乏しいなりに嬉しそうだ。
「はは! こんなイーライ初めてだよ」
「私も、こんなアルトス様は初めてです。貴方様は中々私のことを頼ってくださいませんから」
ポンポンと背中を叩かれ、抱き合う現状を思い出した。気恥ずかしくなって、身体を離し笑い合う。
俺はイーライが隣にいてくれたらそれでいい。
一時的であっても、従者のお陰ですっかり魔女を忘れることが出来た。
応援ありがとうございます!
0
お気に入りに追加
4
1 / 5
この作品を読んでいる人はこんな作品も読んでいます!
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる