2 / 6
1
しおりを挟む
2018年の夏、僕はグアムに降り立った。
タラップを降りた瞬間に立ち上る、肌にまとわりつく熱の感触だけで、ここが彼女の最後の土地だとあらためて思い知らされた。
目的は特にはっきりしていなかった。
ただ、彼女の見ていた景色を見ると何かが掴めるかもしれない。その思いだけが、僕がこの島へ訪れた理由であった。
荷物を受け取ると、空港の散策はせず足早にタクシーへ乗り込む。
運転手に行き先を告げると、イヤホンで耳を塞ぐ。とくに音楽をかけるわけでもない。ただ、一人になりたかっただけだ。
タクシーの窓から景色を眺めていると、彼女が最後に送ってきた数枚の写真を思い出す。
逆光気味の海、大きな影を落とす雲、聳え立つ椰子の木。
窓越しに流れるそれらは、どれもが彼女の不在を僕へと語りかけた。
ホテルに着いたのは夕方だった。
ロビーにある巨大な水槽の魚影がゆらめき、その影をしばらく眺めていたら、胸の奥に沈んでいた何かがほんの少しだけ軽くなった気がした。
荷物を置き、じっとしていると逆に落ち着かなくて、エレベーターで一階へ降りた。
ロビーの横には、ホテルに併設された小さなバーがあった。
曇ったガラス越しに見える赤いネオンが湿った風の粒で少し滲んでいた。
とりあえず一杯だけ、そんな気持ちで僕は扉を押した。
夕方と夜の境目の時間で、店内はまだ空いていた。
カウンターの端に腰を下ろして、氷をぼんやり眺めながらウイスキーを口に含む。
店内には陽気な音楽が流れていたが、それがさらに自分がどこか遠くへ置き去りにされたようで、どこか落ち着かなかった。
しばらくして、隣の椅子が静かに引かれる気配がした。
ひとりの男が腰を下ろし、軽くため息をつく。そしてカウンター奥のスタッフに向かってウイスキーを注文した。
「隣に座って悪いね、ジャッキー」
彼は僕に向かってそう言った。
「人違いじゃないか?」
僕は思わずそう返すと、彼ははっとしたように目を瞬かせ、すぐに笑って肩をすくめた。
「悪い、気にしないでくれ。アジア人を見るとつい"ジャッキー"って呼んじまうんだ。ジャッキーチェンが好きでね」
悪びれる様子もないその言い方が妙に自然で、酔った観光客特有の押しつけがましさもなかった。
「旅行かい?」
男はグラスを傾けながら、気取った様子もなく言った。
「まあ、そんなところかな」
曖昧に返すと、彼は少しだけ首を傾げた。
酔っているというより、僕の言葉を探るような仕草だった。
「みんな"まあ"とか"そんなところ"とか言うけどさ」
彼はそう言ってカウンターの木目をなぞった。
「本当の目的がある人ほど、その言葉は氷が溶けた後の酒のように薄くなる。そう思わないか?」
図星を刺されたような気がして、少しだけ沈黙した。
「そんな哲学じみたことを言うために話しかけたのか?」
僕がそう言うと、男は肩を揺らして笑った。
「いやいや。ただの癖みたいなもんだよ。人と話すときは、まず“探る”ところから入るんだ」
「探られてるわけだ」
「悪気はないさ。ほら、仕事柄、人を観察することが多くてな」
仕事柄――
その言い方が、妙に耳に残った。
「仕事って?」
「ん? ああ……」
彼は少し視線を泳がせてから、わざとらしく肩をすくめてみせた。
隠すというより、はぐらかすことに慣れているような態度だった。
「まあ、観光客に付き合う仕事さ。案内したり、喋ったりするだけのね」
ガイド、とまでは言わない。
でも、ほとんどそれであった。
「で、君は何を見に来たんだ?」
男は唐突に問いを投げた。
質問の組み立てが雑なのではなく、それ以外は必要ないと思っているような響きだった。
「海だよ」
と答えると、彼は満足そうにうなずいた。
「海はいいな。運が良ければ――」
一拍置いて、彼は声を少しだけ落とした。
「――クジラが見られる」
クジラ、という言葉が店内の薄い音楽より静かに、しかし確かに響いた。
「この島の辺りにはな、ときどき、変わったやつが現れるんだ」
「変わった?」
「群れに入れないんだ。どうにも鳴き声の周波数が違うらしい」
そうして彼は何事もないように言った。
「海を見に来たんだろ? 一緒に行ってみないか」
僕は返事をためらったが、彼はそれさえ織り込み済みのように静かに微笑んだ。
「まあ、考えておきな。でも……」
彼はグラスの氷を指先で転がしながら言った。
「君みたいな奴は、大体来るんだ」
その言葉に、胸のどこかが小さく軋んだ。
彼と軽く会釈を交わしてから、僕はまだ半分ほど残っていたウイスキーを飲み干し、静かに席を立った。
店を出ると、夜気が少しだけ湿っていて、ロビーのガラスに映る自分の影がどこか遠くの人のように見えた。
エレベーターで部屋に戻る途中、さっきの会話がいくつか繰り返し浮かんでは消えた。
"周波数の外にいるやつ"
"群れに入れない"
彼の言葉はどれも、それだけで閉じた意味を持っていて、説明も補足も必要ないような響きがあった。
部屋に戻り、靴を脱いで床に座り込むと、窓の外から波の音がかすかに届いた。
辺りは真っ暗で夜の海は見えなかったが、闇の向こうで確かに波音の気配だけはあった。
明日、海へ出るのか――
そう思った途端、胸の奥に小さな震えのようなものが走った。
それが期待なのか、不安なのか、自分でもよく分からないまま僕はベッドに身体を倒した。
照明を落とすと、真っ黒な天井がゆっくりと揺れているように見えた。
きっと疲れていたのだと思う。考えようとすればするほど頭の中の言葉が全部、海中を漂う泡のように天井に吸い込まれていく。
そんな浮遊感の中で、僕はそっと瞼を閉じた。
タラップを降りた瞬間に立ち上る、肌にまとわりつく熱の感触だけで、ここが彼女の最後の土地だとあらためて思い知らされた。
目的は特にはっきりしていなかった。
ただ、彼女の見ていた景色を見ると何かが掴めるかもしれない。その思いだけが、僕がこの島へ訪れた理由であった。
荷物を受け取ると、空港の散策はせず足早にタクシーへ乗り込む。
運転手に行き先を告げると、イヤホンで耳を塞ぐ。とくに音楽をかけるわけでもない。ただ、一人になりたかっただけだ。
タクシーの窓から景色を眺めていると、彼女が最後に送ってきた数枚の写真を思い出す。
逆光気味の海、大きな影を落とす雲、聳え立つ椰子の木。
窓越しに流れるそれらは、どれもが彼女の不在を僕へと語りかけた。
ホテルに着いたのは夕方だった。
ロビーにある巨大な水槽の魚影がゆらめき、その影をしばらく眺めていたら、胸の奥に沈んでいた何かがほんの少しだけ軽くなった気がした。
荷物を置き、じっとしていると逆に落ち着かなくて、エレベーターで一階へ降りた。
ロビーの横には、ホテルに併設された小さなバーがあった。
曇ったガラス越しに見える赤いネオンが湿った風の粒で少し滲んでいた。
とりあえず一杯だけ、そんな気持ちで僕は扉を押した。
夕方と夜の境目の時間で、店内はまだ空いていた。
カウンターの端に腰を下ろして、氷をぼんやり眺めながらウイスキーを口に含む。
店内には陽気な音楽が流れていたが、それがさらに自分がどこか遠くへ置き去りにされたようで、どこか落ち着かなかった。
しばらくして、隣の椅子が静かに引かれる気配がした。
ひとりの男が腰を下ろし、軽くため息をつく。そしてカウンター奥のスタッフに向かってウイスキーを注文した。
「隣に座って悪いね、ジャッキー」
彼は僕に向かってそう言った。
「人違いじゃないか?」
僕は思わずそう返すと、彼ははっとしたように目を瞬かせ、すぐに笑って肩をすくめた。
「悪い、気にしないでくれ。アジア人を見るとつい"ジャッキー"って呼んじまうんだ。ジャッキーチェンが好きでね」
悪びれる様子もないその言い方が妙に自然で、酔った観光客特有の押しつけがましさもなかった。
「旅行かい?」
男はグラスを傾けながら、気取った様子もなく言った。
「まあ、そんなところかな」
曖昧に返すと、彼は少しだけ首を傾げた。
酔っているというより、僕の言葉を探るような仕草だった。
「みんな"まあ"とか"そんなところ"とか言うけどさ」
彼はそう言ってカウンターの木目をなぞった。
「本当の目的がある人ほど、その言葉は氷が溶けた後の酒のように薄くなる。そう思わないか?」
図星を刺されたような気がして、少しだけ沈黙した。
「そんな哲学じみたことを言うために話しかけたのか?」
僕がそう言うと、男は肩を揺らして笑った。
「いやいや。ただの癖みたいなもんだよ。人と話すときは、まず“探る”ところから入るんだ」
「探られてるわけだ」
「悪気はないさ。ほら、仕事柄、人を観察することが多くてな」
仕事柄――
その言い方が、妙に耳に残った。
「仕事って?」
「ん? ああ……」
彼は少し視線を泳がせてから、わざとらしく肩をすくめてみせた。
隠すというより、はぐらかすことに慣れているような態度だった。
「まあ、観光客に付き合う仕事さ。案内したり、喋ったりするだけのね」
ガイド、とまでは言わない。
でも、ほとんどそれであった。
「で、君は何を見に来たんだ?」
男は唐突に問いを投げた。
質問の組み立てが雑なのではなく、それ以外は必要ないと思っているような響きだった。
「海だよ」
と答えると、彼は満足そうにうなずいた。
「海はいいな。運が良ければ――」
一拍置いて、彼は声を少しだけ落とした。
「――クジラが見られる」
クジラ、という言葉が店内の薄い音楽より静かに、しかし確かに響いた。
「この島の辺りにはな、ときどき、変わったやつが現れるんだ」
「変わった?」
「群れに入れないんだ。どうにも鳴き声の周波数が違うらしい」
そうして彼は何事もないように言った。
「海を見に来たんだろ? 一緒に行ってみないか」
僕は返事をためらったが、彼はそれさえ織り込み済みのように静かに微笑んだ。
「まあ、考えておきな。でも……」
彼はグラスの氷を指先で転がしながら言った。
「君みたいな奴は、大体来るんだ」
その言葉に、胸のどこかが小さく軋んだ。
彼と軽く会釈を交わしてから、僕はまだ半分ほど残っていたウイスキーを飲み干し、静かに席を立った。
店を出ると、夜気が少しだけ湿っていて、ロビーのガラスに映る自分の影がどこか遠くの人のように見えた。
エレベーターで部屋に戻る途中、さっきの会話がいくつか繰り返し浮かんでは消えた。
"周波数の外にいるやつ"
"群れに入れない"
彼の言葉はどれも、それだけで閉じた意味を持っていて、説明も補足も必要ないような響きがあった。
部屋に戻り、靴を脱いで床に座り込むと、窓の外から波の音がかすかに届いた。
辺りは真っ暗で夜の海は見えなかったが、闇の向こうで確かに波音の気配だけはあった。
明日、海へ出るのか――
そう思った途端、胸の奥に小さな震えのようなものが走った。
それが期待なのか、不安なのか、自分でもよく分からないまま僕はベッドに身体を倒した。
照明を落とすと、真っ黒な天井がゆっくりと揺れているように見えた。
きっと疲れていたのだと思う。考えようとすればするほど頭の中の言葉が全部、海中を漂う泡のように天井に吸い込まれていく。
そんな浮遊感の中で、僕はそっと瞼を閉じた。
0
あなたにおすすめの小説

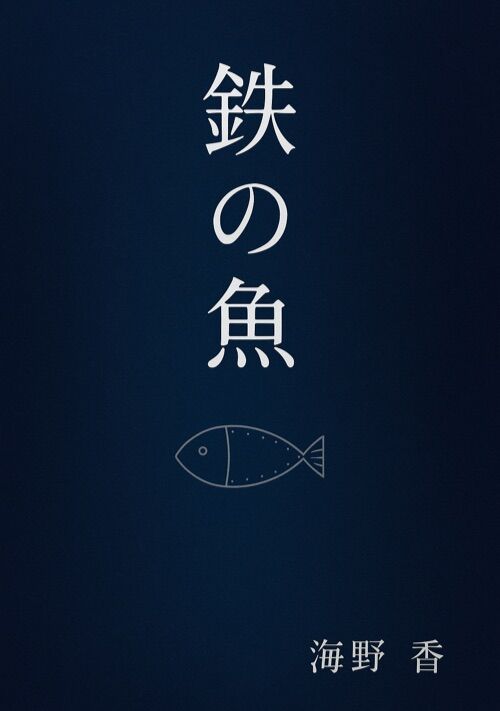
鉄の魚
海野 香
現代文学
失われた夢と残された言葉。
水泳選手として将来を渇望されていた彼女は、事故により足を失い、文学に全てを賭けた少年は、病の床で静かに筆を置いた。
それぞれの「喪失」を引き継いで生きる僕は、二人の残した全て──夢、言葉、そして沈黙──それらを受け止め、やがて筆を取る。
二匹の「鉄の魚」は、深く冷たい水底で、かつてまだ魚だった頃の夢を見続ける。
──これは、残された者の物語である。


あるフィギュアスケーターの性事情
蔵屋
恋愛
この小説はフィクションです。
しかし、そのようなことが現実にあったかもしれません。
何故ならどんな人間も、悪魔や邪神や悪神に憑依された偽善者なのですから。
この物語は浅岡結衣(16才)とそのコーチ(25才)の恋の物語。
そのコーチの名前は高木文哉(25才)という。
この物語はフィクションです。
実在の人物、団体等とは、一切関係がありません。

極上イケメン先生が秘密の溺愛教育に熱心です
朝陽七彩
恋愛
私は。
「夕鶴、こっちにおいで」
現役の高校生だけど。
「ずっと夕鶴とこうしていたい」
担任の先生と。
「夕鶴を誰にも渡したくない」
付き合っています。
♡-♡-♡-♡-♡-♡-♡-♡-♡-♡-♡-♡-♡-♡-♡-♡-♡
神城夕鶴(かみしろ ゆづる)
軽音楽部の絶対的エース
飛鷹隼理(ひだか しゅんり)
アイドル的存在の超イケメン先生
♡-♡-♡-♡-♡-♡-♡-♡-♡-♡-♡-♡-♡-♡-♡-♡-♡
彼の名前は飛鷹隼理くん。
隼理くんは。
「夕鶴にこうしていいのは俺だけ」
そう言って……。
「そんなにも可愛い声を出されたら……俺、止められないよ」
そして隼理くんは……。
……‼
しゅっ……隼理くん……っ。
そんなことをされたら……。
隼理くんと過ごす日々はドキドキとわくわくの連続。
……だけど……。
え……。
誰……?
誰なの……?
その人はいったい誰なの、隼理くん。
ドキドキとわくわくの連続だった私に突如現れた隼理くんへの疑惑。
その疑惑は次第に大きくなり、私の心の中を不安でいっぱいにさせる。
でも。
でも訊けない。
隼理くんに直接訊くことなんて。
私にはできない。
私は。
私は、これから先、一体どうすればいいの……?

ママと中学生の僕
キムラエス
大衆娯楽
「ママと僕」は、中学生編、高校生編、大学生編の3部作で、本編は中学生編になります。ママは子供の時に両親を事故で亡くしており、結婚後に夫を病気で失い、身内として残された僕に精神的に依存をするようになる。幼少期の「僕」はそのママの依存が嬉しく、素敵なママに甘える閉鎖的な生活を当たり前のことと考える。成長し、性に目覚め始めた中学生の「僕」は自分の性もママとの日常の中で処理すべきものと疑わず、ママも戸惑いながらもママに甘える「僕」に満足する。ママも僕もそうした行為が少なからず社会規範に反していることは理解しているが、ママとの甘美な繋がりは解消できずに戸惑いながらも続く「ママと中学生の僕」の営みを描いてみました。


ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















