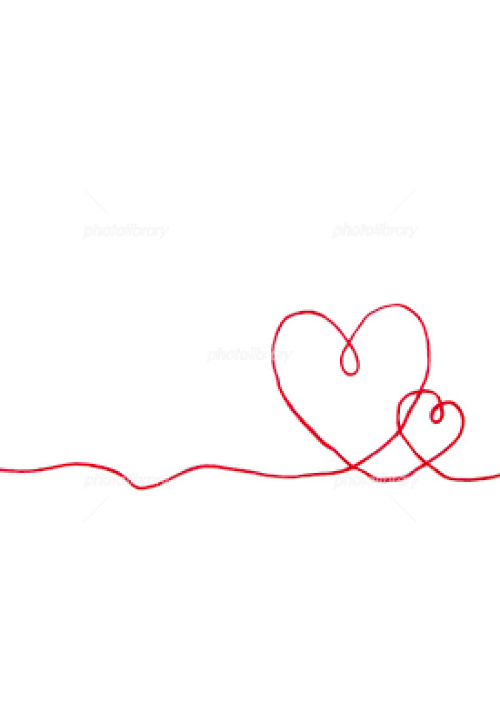1 / 16
1巻
1-1
しおりを挟むプロローグ
いつか、白馬の王子様が迎えに来てくれる。
ヴィオレット・フォン・マッキンリーはそう夢見ていた。
幼い頃から十八歳になった今まで、ずっと。
理想の王子様の身長は、あまり高くないほうがいい。小柄なヴィオレットと差がありすぎてしまうから。
細身だけれどほどよく筋肉があって、顔は優しげだと素敵だ。
金髪碧眼で、声は優しいテノール。さりげなく「愛してるよ」などと甘い言葉をささやいてくれるような、いかにも王子様という人がいい。
もちろん本物の王子様でなくていい。
ヴィオレットだけを大事にしてくれる人であれば、それだけで。
けれど、彼女はその夢が恐らくかなわないであろうことを分かっていた。
ヴィオレットは普通の人間ではないからだ。
母方の祖母がエルフだったらしく、ヴィオレットはその特性を受け継いでいる。
髪は水色で、瞳はアメジストのように輝く紫色。耳は長くて、先がとがっているのだ。
エルフは存在こそ知られているが、人里に姿を見せることは稀で、詳しいことは分かっていない。
いくつかの書物によると、彼らは華奢で肌が白く、長くとがった耳を持つとある。
髪は水色や薄緑など華やかな色が多く、瞳の色素は薄いという。
そして、皆この世のものとは思えないほど美しいらしい。
さらには強い魔力も持ち、とても長寿なのだそうだ。
そんなエルフから受け継いだ容姿により、ヴィオレットは悩みを抱えることとなる。
華やかな水色の髪と紫の目は、彼女の意思とは関係なく、どこにいても注目された。
ヴィオレットの住むオルレーヌ国では、黒や茶色など落ち着いた色合いの髪や瞳を持つ人が多い。そのため、彼女の容姿は目立つのだ。
それだけでなく、ヴィオレットの華奢な体と色白の肌はエルフを連想させ、特にとがった長い耳は、あまりにも普通の人間と異なっていた。
その耳を一目見れば、誰もが彼女はエルフだと言うだろう。
人々はヴィオレットを避け、彼女を遠巻きに見てはひそひそ話をするばかり。
ごく稀に話しかけられたと思うと、大抵は髪と瞳の色、耳の形を揶揄された。幼い頃、男の子たちに「気持ち悪い」「化け物」と言われたこともある。
その記憶は、今でも彼女の中にトラウマとして残っていた。
そんなヴィオレットと違い、彼女の母は普通の容姿で、祖母から受け継いだのは紫の目だけだった。
つまり、ヴィオレットに現れたエルフの特性は、先祖返りというものだ。
エルフだと聞く祖母はヴィオレットが生まれる前に亡くなっているため、会ったことがない。髪は黒く、とがった耳を持たない母が、エルフの血を引いているとは到底思えなかった。そのため、幼い頃のヴィオレットは、本当は自分は両親の子供ではないのかも、と心を痛めたこともあった。けれど両親が愛情を込めてヴィオレットを育ててくれたのは事実だし、母と同じ紫色の瞳には血のつながりを感じている。
とはいえ今でも、「なぜ私はエルフの先祖返りとして生まれてしまったのだろう」と悩み続けていた。
こんな自分が、誰かと恋愛をして結婚できるとは思えない。
だからせめて、白馬の王子様のお迎えを夢想してみる。夢を見ることだけなら、ヴィオレットにも許されるのだから。
1 エルフの先祖返りだとご存知なのですか?
「ヴィオレット」
朝食のあと、父のマッキンリー伯爵に呼ばれ、ヴィオレットは緊張で身を硬くした。
「はい」
愛称の「ヴィー」ではなく本名を呼ぶのは、当主として真面目な話をする、ということだ。
「実はお前に縁談が来ていてね」
こほんと咳払いをして、伯爵が言いにくそうに告げる。
伯爵の隣に座る夫人も、複雑な顔をしていた。
ヴィオレットは、突然の話に戸惑いを隠せない。彼女は、男性が苦手だからだ。
幼い頃、人間離れした容姿を男の子たちにからかわれたトラウマから、特に同年代の男性が苦手になってしまった。
伯爵家に男性の使用人はいるが、祖父の代から仕えてくれている者ばかり。皆高齢なので、身近な男性で一番年が近いのは父の伯爵である。
そんな状況が、ヴィオレットに若い男性への免疫をますますなくさせていた。
しかし、不安な気持ちがある一方で、浮き足立っている部分もあった。
ヴィオレットは現実の男性が苦手なぶん、本を読んで理想の男性像を膨らませてしまっていたのだ。
普通の人間ではない自分を、いつか王子様が迎えに来てくれるかもしれない。
ずっとそう夢見てきたヴィオレットは、ドキドキしながら伯爵に尋ねた。
「お相手は、どのような方でしょう」
「その……公爵家の方だ」
「どちらの公爵様ですか」
「アブルーン大陸のマルス王国の方なのだが……」
マルス王国というと、ヴィオレットの暮らすオルレーヌ国から海をはさんだ向こうにある国だ。温暖な気候によるものか陽気な国民性で、近隣には並ぶ国がないほどの大国である。
そんな国の公爵との縁談となれば、条件は申し分ないのに、なぜか伯爵は情報を小出しにしてくる。よほど言いづらい相手なのだろうか。
ヴィオレットはじりじりしながら相手の名前が出てくるのを待った。
伯爵は一つ息を吐いてから、ようやく相手の素性が分かる情報を発する。
「『疾風の黒豹』という二つ名の……」
伯爵の言葉を聞いて、ヴィオレットは目をみはった。
世間の噂話に疎いヴィオレットの耳にすら、その名前は届いている。
アーノルド・フォン・フィリップ公爵。
この春、王宮騎士団の小隊長から昇格し、若くして騎士団長に任命された人物だ。
彼の剣は風のように速く、捉えた敵は絶対に逃さない。
獲物を見据える目は肉食獣のようで、彼の動きのしなやかさと褐色の肌から『疾風の黒豹』と二つ名がつけられたらしい。
剣に滴る獲物の血を見るのが何より好きだとか、物騒な噂も流れている。
ヴィオレットは彼に会ったことがないので、知っていることは噂の域を出ない。
しかし、少なくとも彼女の「理想の王子様」と、彼がかけ離れているだろうことは想像にかたくなかった。
相手が誰か分かった途端、ヴィオレットは地獄の業火に焼かれるような、悲痛という言葉では到底言い表せない気持ちになってしまった。
「ヴィ、ヴィー。大丈夫か」
みるみるうちに表情が硬く、顔色も悪くなっていくヴィオレット。
そんな彼女に、伯爵が思わずといったように声をかける。
「嫌なら、この縁談はお断りを……」
「いいえ……。お受けします」
フィリップ公爵家に比べて、家柄的に格下であるマッキンリー伯爵家から縁談を断ることはできない。そのことを、ヴィオレットはよく分かっていた。
「私はフィリップ公爵との縁談をお受けします。お父様……」
悲痛な声ではあったが、ヴィオレットははっきりと承諾した。
とはいえヴィオレットには、他の人と決定的に異なる点がある。
そこに一縷の望みをかけて、ヴィオレットは伯爵に尋ねた。
「公爵様は、私がエルフの先祖返りだとご存知なのですか?」
結婚相手に、得体の知れない先祖返りの娘をわざわざ選ぶはずがない。知らなかったのであれば……
(フィリップ公爵のほうから、この縁談を白紙に戻してもらえるかもしれない)
そう思ったのだが、ヴィオレットの希望はあっさりと打ち砕かれた。
「もちろん。そのことも含めて、ヴィーが公爵様のお好みにあてはまったそうだ」
「お好み? ……私が?」
ヴィオレットは大きなアメジスト色の目を瞬かせた。男性から好意を向けられたことなどないので、好みだと言ってくれる人がいるとは思わなかったのだ。
「詳しい話はお父様もお聞きになっていないそうだけど、気になるならお会いになってから尋ねてみなさいな」
軽い口調で夫人が補足する。
「エルフの先祖返りを花嫁に望む方が、本当にいらっしゃるのですか?」
目を丸くするヴィオレットを見て、夫人がクスクス笑う。
「少なくとも公爵様はそうみたいね。それにヴィーはとても可愛いわ。私が今まで会った女性の中で一番」
「ご自分の娘だからそう思うだけです。……現に、私はよく男の子にいじめられていましたし」
両親をはじめとする屋敷の人間だけは、昔からヴィオレットを手放しで褒めてくれた。だが、完全に身内の欲目だと思う。
「え? ……ああ、そう。あなた、まだ気づいていないのね。まあいいわ。知らなくても問題ないでしょうし」
夫人はうんうんと何度も頷き、一人で納得していた。
気づいていないとはなんのことだろう。聞いてみたものの、のらりくらりとかわされ、結局教えてもらえなかった。
「ヴィーがお嫁に行ったら、離れて暮らさなければならないのは寂しいわ……でもマルス王国なら数時間で行き来できるから大丈夫よね。映話機もあるし」
映話機は離れた相手と話せる、魔力の込められた道具だ。相手の映像が映し出され、会話をすることができる。平民にはおよそ手の出ない代物だが、貴族の間ではごく普通に使われていた。きっと公爵家にもあることだろう。
大陸間には橋が架けられており、魔法で走る汽車を使えば短時間で往復できる。そのため、離れたところにある他国とはいえ、それほど距離を感じることはないだろう。
夫人が席を立ち、優しくヴィオレットの手をとった。
「色々噂はあるけれど、騎士団長を任されるなんて、実力も人格も優れている何よりの証よ。あなたは噂に惑わされず、公爵様だけを信じなさい」
「はい……。お母様」
ヴィオレットは素直に頷いたものの、夫人の言葉は心に響かなかった。悲愴感は消えず、重い鉛玉を呑み込んだような気分だ。
一方で、こんな自分を選んでくれるなんて、とてもありがたいことだと思う。しかも相手は公爵かつ騎士団長ととても地位が高く、もったいないくらいだ。
多少の難があるのだとしても、ヴィオレット以上に条件のよい令嬢との縁談がいくらでもあっただろう。
(私の何を気に入ってくれたのかは分からないけれど、この縁談から逃れられないのであれば、精いっぱい妻として努めよう。私を選んでくれたことをできるだけ後悔させないように)
ヴィオレットはそう心に決めたのだった。
✿ ❀ ✿
ヴィオレットに縁談が来る数か月前のこと。
フィリップ公爵家の当主アーノルドは、久しぶりの休日を自分の屋敷で過ごしていた。
二十八歳にして、王宮騎士団の団長に任命された彼には、なかなか休む暇がない。
アーノルドは、褐色の肌と金髪碧眼を持った美丈夫である。
マルス王国において、褐色の肌は一般的だ。しかし、この国では濃い色の髪と目を持つ人が多く、金髪碧眼は珍しい。
彼の髪と目は、外国から嫁いできた前公爵夫人から受け継いだものだ。
長身で、きりっと整った顔立ちをしており、常に無表情なせいか子供には怖がられてしまうことが多い。
そんな彼は、目立つ見た目に反して無口かつ内向的である。
一年を通して暖かいマルス王国の国民は陽気で明るく、特に若者は暇さえあれば街に出て異性と遊んでいる。
しかしアーノルドは、この休日に屋敷から出ようとはせず、庭で剣の素振りをしていた。
そんな彼を見て、執事長のコンラッドが「若いのに他にすることはないんですか」と嫌味を言ってきたため、今は自室に引っ込んでいる。
コンラッドの両親はフィリップ公爵家に仕えており、アーノルドと彼は兄弟のように育った。コンラッドが執事としてアーノルドに仕えるようになってからも、その関係は変わっていない。
「アーノルド様、いらっしゃるんでしょう? 入りますよ」
形だけのノックをしたコンラッドが、ドアを開けて入ってきた。
いつも通りきっちりと銀髪を撫でつけた彼は、銀縁のメガネを押しあげながら、その奥の青い目を鋭く光らせる。
コンラッドも肌は褐色だが、髪と目の色は外国から嫁いできた母親に由来する。
彼は呆れ顔で、窓際のソファーに腰かけたアーノルドに近づいた。
けれどアーノルドはコンラッドを完全に無視して、熱心に剣を布で磨いている。
アーノルドはいつも、休日に素振りや道具の手入れをしたり、戦術の本を読んだりするのだ。
はーっと剣に息を吹きかけ、布で磨き上げると、アーノルドはぴかぴかになったそれに自分の顔が映り込むのを見て頷いた。
一方コンラッドは、苦々しい顔で主人を見つめる。
「私は先ほど『街にお出かけになってはいかがですか』というつもりで、声をかけたんですがね」
「……街に出てもすることがないから、家にいるほうがいい。街に出たら女性にも絡まれるし、面倒くさい」
アーノルドは磨き終わった剣をサイドテーブルに置く。
すらりとした長身に、きりっと整った顔立ちのアーノルドは、女性から誘いを受けることが多い。この国の人間にしては珍しく口下手なところも、「可愛い」らしい。
アーノルドが女性から言い寄られるのにうんざりしていることを、コンラッドは当然知っている。けれどこのおせっかいな執事はそんなことにおかまいなく小言を言ってくるのだ。
アーノルドは、何かコンラッドの気をそらせるものはないかと視線を走らせ、彼の手に擦り傷があるのを見つけた。
「手……怪我してる」
アーノルドの言葉に、コンラッドは自分の手に視線を落とす。
「ああ、本当ですね。でも、擦り傷なので大丈夫ですよ」
その言葉を無視して、アーノルドはコンラッドの傷に手をかざし、呪文を唱えた。
「……アウローラクラルスクーラト」
しばらくしてアーノルドが手をのけると、傷はすっかり治っていた。回復魔法を使ったのだ。
アーノルドをはじめとして、ほとんどの貴族は魔力を持っている。魔力の量は爵位の高さに比例するとされており、魔力を持っている平民はかなり稀だ。
アーノルドは公爵にしては魔力が少ないほうだが、簡単な魔法を使うのに問題はない。
魔法は地、水、風、火、光、闇の六つの属性に分類され、その中で自分に合った属性の魔法しか使えない。
『疾風の黒豹』として人々から恐れられているアーノルドは、攻撃力の高い火属性だと思われがちだが、回復魔法を主とする光属性の魔法を得意としていた。
「……気をつけろよ。じゃあな」
「はい。ありがとうございます、アーノルド様」
頭を下げて部屋を出ようとしたコンラッドは、すぐに踵を返した。
「って、そうじゃない。私はまだ本題を話していません」
コンラッドは幼い頃からアーノルドとともに過ごしてきたため、物言いに容赦がない。
「……ちっ」
戻ってきたコンラッドに、アーノルドは舌打ちする。
「私はずっと、早く結婚しなさいと言っているじゃないですか。騎士団長ともなれば妻がいたほうが好ましいですし、妻帯者は女性にしつこく絡まれませんよ」
騎士団長に就任してからというもの、コンラッドは「早く結婚しろ」とうるさい。
アーノルドは顔をしかめた。
「あんたもう二十八ですよ?」
「……さっきは『若い』って言った」
のらりくらりとこの話題から逃げようとするものの、コンラッドのギラギラした双眸からは、今日こそは逃すものかという強い意思を感じる。
確かに二十八歳という年齢は若いが、この国の貴族の結婚適齢期は成人である十八歳から二十代前半だ。公爵家の人間ともなれば、成人してすぐに結婚していても珍しくはない。
「あんた、未婚のままですむと思ってませんよね? ご希望がないなら私の好みで相手を選び、縁談をとりつけますが」
しつこいコンラッドに辟易して、アーノルドはようやく重い口を開いた。
「……理知的で思慮深く、控えめ」
「はい。あとは?」
これはコンラッドも想定していたようで、先を促してくる。
「……小柄で小動物っぽい人」
「小動物……。庇護欲をそそられるとかですか? あんたそんななりして、可愛いもの好きですもんね。で、あとは?」
「エルフ」
「はぁ?」
最後に出した条件に、コンラッドが声をあげた。
主人を見るとは到底思えない目つきで、コンラッドはアーノルドを睨みつける。まさか主人が人外の相手を望むとは、さすがの彼も思わなかったのだろう。
「その条件に完璧にあてはまる女性がいるなら、結婚でもなんでもしてやる」
アーノルドはぶっきらぼうに言った。
ともあれ、これだけの条件に合致する、適齢期の令嬢などいるはずがない。
(これでしばらくは平穏に暮らせる)
拳を握り締めてわなわなと震えるコンラッドを無視して、アーノルドは戦術の本を開いたのだった。
だがアーノルドの予想を大きく裏切って、平穏は三か月と続かなかった。
その日、帰宅したアーノルドが自室に入ると、コンラッドはこほん、とわざとらしく咳払いをして口を開いた。
「ご結婚のことですが」
(まだ言っているのか。しつこいやつめ)
アーノルドは眉をひそめながらソファーに腰かけた。
家督をアーノルドに譲り、ほとんど家を空けている両親は「仕事が忙しい間は無理に結婚しなくてよい」と寛容だ。しかし、コンラッドはアーノルドが成人してからというもの、「結婚して跡継ぎを作るのは貴族の義務だ」と口うるさかった。
騎士団長に就任してからはさらにひどくなり、「結婚しろ」「跡継ぎを作れ」とオウムのように繰り返していた。結婚相手に求める条件を伝えてからはしばらく何も言われなかったので、もう諦めたものだと安堵していたのだが……
もちろん、跡継ぎを作るのが貴族の義務であることは十分理解している。だが、ゆくゆくは養子をとるか、兄の子供に家を継がせればよいと考えていた。
そもそも、アーノルドが出した条件にあてはまり、かつ悪名高い『疾風の黒豹』に嫁いでもいいという奇特な女性がいるとは思えない。
ささやかれている噂は根も葉もないものだが、街で声をかけてくる女性たちだって、アーノルドが『疾風の黒豹』だと分かれば、ほとんどが逃げていくに違いない。
「そんなに公爵家の跡継ぎがほしければ、兄上に公爵位を継いでいただけばいい。……兄上のほうが当主にふさわしいのだから」
兄に家を継ぐ意思がなく、父も次男であるアーノルドが継いでも構わないというから、現在当主をしているだけだ。アーノルドは兄が爵位を受け継ぐ気になるまで、家を預かっているという意識が強い。
「あんた、まだそんなことを言ってるんですか。あのバカは年単位で帰ってこないんだから、いい加減諦めてください」
アーノルドは爵位を継いでから、たびたび「自分より兄がふさわしい」と言っていた。さすがに聞き飽きたらしいコンラッドは、アーノルドの言葉を一蹴し、淡々とある報せを告げた。
「結婚式が一月後に決まりました。聖堂も押さえて、招待状もお出ししております。王宮への休暇申請も終えました」
「……冗談がすぎる」
信じがたくて悪態をつく。
「冗談だと思われるなら、ご友人や相手の女性に確認してください」
普段通り飄々としているコンラッドに、無性に腹が立つ。
話がここまで進んでしまっていたら、今から白紙に戻すのはさすがに無理だろう。
「条件がかんっぺきにあてはまる女性となら、結婚するんですよね? ご自分のおっしゃられたことはたがえませんよね、騎士団長?」
コンラッドはわざと煽るような言い方をしてきた。
「……するよ。すればいいんだろ」
渋々ではあるが了承したアーノルドに、コンラッドは満足そうに頷いた。
「私があらゆる伝手を使って、相手を探したんですからね! そう言ってもらわないと困ります。いつもそうやって素直だったら助かるんですが。アーノルド様も昔は『コンラッド、コンラッド』ってあとをついてきて可愛らしかったのに、最近は反抗するようになって……あ、覚えてます? 私の仕事を手伝うって言ってくれたのはいいんですけど、干そうとした洗濯物を全部庭にぶちまけて、メイドのマリーに二人で怒られて夕食抜きに――」
コンラッドが懐かしそうに話しはじめたのを聞き、アーノルドはため息をついた。
(……思い出話なんて、コンラッドも年をとったな)
コンラッドはまだ三十歳になったばかりだが、最近妙に年寄りくさくなった気がする。
ここまで来てはもう逃げられないので、結婚はする。
だが、いくらもしないうちに花嫁は逃げ出すだろう。自分は女性を楽しませることができない面白みのない人間である上、悪名高い『疾風の黒豹』なのだから。
✿ ❀ ✿
結婚まで一月弱。
縁談を受けてからのヴィオレットは多忙だった。
マルス王国のマナーを学ぶため、家庭教師がついたからだ。オルレーヌ国とマルス王国は言語も違うが、ヴィオレットはすでにマルス王国の公用語を修得していたため、新たに覚える必要はなかった。
公爵家からは多額の支度金やドレスや靴が贈られた。ただ贅を尽くしているだけではなく、どれも趣向が凝らしてある。
すぐさまヴィオレットがお礼の手紙を送ると、執事長が代理で返事をくれた。公爵は手紙をしたためるのが苦手なのだそうだ。
その手紙には、次のようなことが書かれていた。
贈り物が気に入ってもらえたことを、公爵も喜んでいる。色々な噂を聞いているだろうし他国に嫁ぐ不安もあると思う。けれど、ヴィオレットに苦労をかけることは絶対にないので、心配しないでほしい。
特に、『主人は見た目は怖いかもしれないし誤解されやすいですが、決してヴィオレット様に害をなすことはありません』と強調してあったのには、思わず笑ってしまったのだった。
そうしているうちに結婚の準備は着々と進み、厳しかった冬ももうすぐ終わろうとしていた。春が来れば、オルレーヌ国では色々な花が咲き誇る。ヴィオレットは、その様子を楽しむ前にマルス王国へ行くことになる。
「ヴィオレットお嬢様、よろしいでしょうか」
自室で荷物の整理をしていると、短くドアがノックされた。
ヴィオレットの側仕えである、メイドのノアだ。彼女は、ヴィオレットが幼い頃から面倒を見てくれていて、嫁ぎ先にも一緒に来てくれることになっている。
そのためにノアはマルス王国の言葉を勉強し、あっという間に日常会話程度は話せるようになった。
「どうぞ、入って」
ヴィオレットが声をかけると、ノアが一礼して部屋に入ってきた。
「エミリエンヌ様がお見えなのですが、お通ししてもよろしいですか? それとも、応接室でお話しになりますか?」
応援ありがとうございます!
0
お気に入りに追加
3,092
1 / 5
この作品を読んでいる人はこんな作品も読んでいます!
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる
本作については削除予定があるため、新規のレンタルはできません。
このユーザをミュートしますか?
※ミュートすると該当ユーザの「小説・投稿漫画・感想・コメント」が非表示になります。ミュートしたことは相手にはわかりません。またいつでもミュート解除できます。
※一部ミュート対象外の箇所がございます。ミュートの対象範囲についての詳細はヘルプにてご確認ください。
※ミュートしてもお気に入りやしおりは解除されません。既にお気に入りやしおりを使用している場合はすべて解除してからミュートを行うようにしてください。