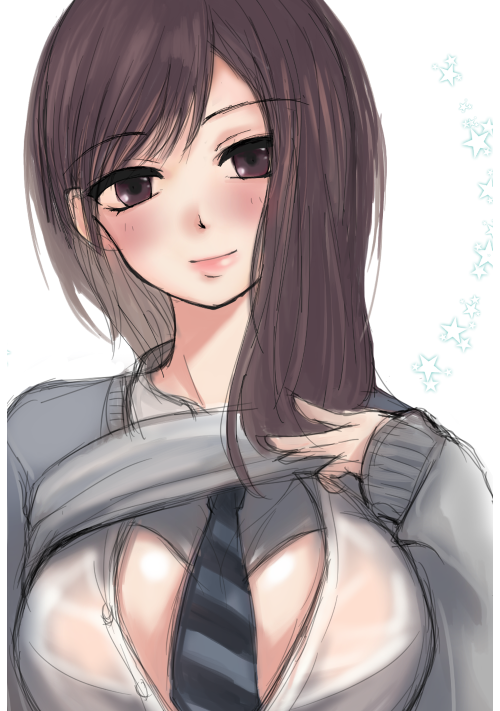67 / 449
5巻
5-3
しおりを挟む説明会が終わり、生徒達は父兄と合流すべく教室を飛び出していく。
小学部の一年生は集団生活を学ぶために、一年間の寮生活が義務付けられている。週末の休息日と長期休暇の時だけは帰省が許されるが、子ども達にとっては明日の朝までが両親と過ごす最後のひと時と言えるのだ。
ティアは教師に指示された第三会議室へ行かなくてはならない。特に時間の指定はなかったので、校舎から人気が引いてから動こうと、のんびり荷物をまとめていた。
「あの……」
遠慮がちに声をかけられ、ティアは後ろを振り向く。
「あら、アデル。ご両親がお待ちではないの?」
「う、うん。そうだけど、一応、お礼をと思って」
「お礼?」
髪の隙間から覗く瞳は、まっすぐにティアを捉えている。教室には、既にアデルとティアしかいなかった。先ほどまでの緊張感に耐えられなかったのか、他の教室よりも生徒の引きが早かったようだ。
「うん。言ってくれたから。これが『証』だって。あたしがまだちっさい時に、ひぃばあちゃんが言ったんだ。『これは、戦士の証だ』って」
アデルは小さな時から、こめかみのところにあるウロコのような皮膚が嫌で仕方がなかった。光を反射するそれは、人とは違うのだという『証』。だから、前髪を伸ばして隠していた。光に当たらないように、なるべく下を向いていたのだ。
「これを見て近づいてくる奴らは、『異種族の迫害に反対』とか言いながら、可哀想な人を見るような目を向けてきた。あいつらは偽善者だ。けど、あんたは違う。なんでだ?」
臆さずにまっすぐ見つめてくるティア。そんな人物にアデルは初めて出会った。教師達でさえ、見ないように目をそらしていたのだ。
アデルには不思議だった。ティアに見られても、全然気にならなかったのだ。こめかみに意識を向けられても、気まずく感じる事はない。
「なんでと言われても……多分、あなたが出会ってきた人達は、異種族と本当の意味で付き合った事がないんじゃないかしら? 人と違う特徴って、どうしても目が行ってしまうわ。けど、それがあって当たり前のものなら、そうはならないでしょう?」
「……目の色が違うとか?」
「そうね。エルフは耳が長く尖っているし、魔族は髪や目が独特の色をしている。獣人族は、耳や尻尾がある。でも、それがその種族にとって……その人にとって当たり前のものなら、そんなに気にならないわよね」
そう言いながらもティアは、苛立ちを感じていた。わざわざ『異種族の迫害に反対』と言いながら、アデルに近づく者がいるという事に。しかし、それを表情には出さず、わずかに苦笑する。
「けど……そうね……あなたの場合は、あなた自身が気にしすぎているのではないかしら。その髪も、見られたくないと思っているから伸ばしてるんじゃないの? あなた自身が『見られていないか』常に意識しているから、必要以上に気になるんだと思うわ」
「それは……そうかも……」
気になる場所を意識してしまうのは、見られる方も同じだとティアは思う。
「ふふっ。私の友人の中にはエルフも魔族も獣人族も、竜人族もいるのよ」
「え? と、友達にいるのっ?」
「ええ。……あぁ、そろそろ行かなくては。また明日お会いしましょう」
「うん……さようなら……」
「ふふ、さようなら」
戸惑うアデルの様子が可愛らしい。そう思いつつ、ティアは教室を後にした。
会議室に向かって廊下を歩きながら、入学式の時に見た教師の顔ぶれを思い出す。
「やっぱり、いなかった」
フェルマー学園の創立は、約六百年前。バトラール王国に創られた当時は、まだ小さな学園だった。
様々な種族や身分の子どもが通い、将来は冒険者として世界中を渡り歩く事を視野に入れた学園。教師達も人族だけでなく、エルフ、魔族、ドワーフ、獣人族、竜人族と、それぞれの分野に特化した種族の者達で構成されていた。
それなのに今は、貴族の子どもが多くを占め、教師もサクヤ以外は全て人族だった。
「あの様子じゃあ、サク姐さんが獣人族だって事も知られてないんだろうな……」
会議室のある本館。その一階に、創立者フェルマー・マランドの肖像画があった。その前に立つと、ティアは懐かしさを覚える。
(フェルマー先生……)
肖像画の中のフェルマーは、あの頃のままの姿をしていた。銀糸のような髪をまとめ上げ、夫である竜人族のマートゥファル・マランドとお揃いのイヤリングをしている。ブルーダイヤのイヤリングは、青く深い色合いの瞳にとても良く似合っていた。
フェルマーは、バトラール王家専属の教師の一人だった。週に三日、歴史学の担当だ。
しばらく肖像画を見つめていたティアは、感傷を振り払うようにゆっくりと目を離す。そして会議室に着くまでに心を落ち着けようと、その場に留まりそうになる足を踏み出すのだった。
長机を四角く並べて配置した、会議用の大きな部屋。そこにはベリアローズとエルヴァスト、そしてウルスヴァンもいた。
「ティア、席はここだ。意外と早かったな。友人はできたか?」
エルヴァストが楽しそうに話しかけてきた。
「残念。お友達になり損ねた子ならいたけどねぇ」
小声で話すティアに、ベリアローズは眉を寄せた。
「ティア……もしかして、ずっとあの路線でいくつもりか?」
入学式の時のティアは、ベリアローズがクラスメイト達から散々聞かされた『聖女のような少女』『深窓の伯爵令嬢』というイメージ通りだった。
この学園に来てから、何度否定したか知れない。だが、その美少女然とした容姿とも相まって、本来のティアのイメージとはかけ離れた伯爵令嬢像が、完璧に出来上がっているのだ。
「なぁに? お兄様。こんな私はお嫌い?」
「いや、というより、大っ変っ不安だ」
「は?」
妙に力を入れて切り返された事に、ティアは微笑みながらも目を細める。すると、ベリアローズは慌てて続けた。
「し、仕方ないだろうっ。自分の胸に手を当てて、よく思い出してみろっ。出会って間もない僕に、お前は一体何をしたっ?」
「う~ん……体力作りのためのトレーニングメニューをプレゼントしなかった?」
間違いない。根性無しの継嗣では困ると、スペシャルメニューを考えたはずだ。だが、どうやらベリアローズの認識は違うらしい。
「僕は覚えているぞっ。突然部屋のドアを蹴破ったティアに『弱っちいお兄様。鍛えてやるから表へ出ろっ』なんて言われて無理やり連行された後、マティの餌扱いされて噛みつかれたっ」
涙目になって当時を思い出すベリアローズ。
ティアは、それがどうしたのかと首を傾げる。
「え? 何? もしかして、私がクラスメイトを鍛えるとでも思ったの? 確かに軟弱なバカ貴族が多そうだし、ここにいたら簡単に親に泣きつく事もできないもんね。この一年の間に色々と教育を……」
「するなよっ?」
「やめてくださいっ!」
静かに会話を聞いていたウルスヴァンも慌てて止める。
「いや、意外にありか?」
「エルっ」
「殿下っ!」
まさかのエルヴァストの同意に、ベリアローズ達は悲鳴を上げそうな勢いだ。そんな彼らを安心させるつもりでティアは言った。
「まぁまぁ、落ち着いて。今までみたいな力業はやらないって。だって軟弱すぎて面白くないもん。うっかりプチっと潰しちゃいそうだし、自制するためにも、しばらくはこのイメージでいくよ」
それを聞いた三人は、心の底から納得した。『これは本音だ』と。
ティアは、今まで関わってきた多くの者達を変えた。完全に力業で。それをやったところで、使い物にならなくなるような根性無しはいなかったのだ。
ベリアローズは軟弱な方だったが、負けん気が強かった。騎士学校出の三人組――通称『三バカ』も、目標に向かう意志が強かったため、一度心が折れてもすぐに復活した。
マクレート家の四兄妹やルクス、病弱だった母シアン。皆、変わろうという想いが強かったため、ティアに負けじとついてきた。
だが、ここにいるのは、まだまだ世界を知らないお子様達だ。ティアに正面から喧嘩を売る勇気もないだろう。ティアが今までのようにやれば、彼らは間違いなく潰れてしまう。
「やめてくださいね。相手は幼い子ども達なんです。叩いても立ち上がる、騎士達とは違うんですよ?」
ウルスヴァンが懇願するように言う。女王様バージョンのティアが国の騎士達に行った教育的指導は、未だウルスヴァンの中で色褪せる事のない悪夢だった。
「やだなぁ。だから今はやらないって。あ、でも……女王様と令嬢ってそんなに違わないよね……」
「ダメですよっ? あんな事をしたら子ども達が死んでしまいますっ!」
真っ青になったウルスヴァンは、今夜、絶対にあの時の夢を見るだろう。完全にトラウマになっているようだ。
「ティア、あまりウルをいじめてくれるな。それと、気になったんだが『今は』なのか?」
エルヴァストは苦笑しながらも、徐々に楽しそうな笑みに変わる。どうやら実の兄であるベリアローズよりも、ティアの事を分かっているようだ。
「ふふっ。だって段階を踏めば、もっと楽しめるでしょう?」
呆然としていたベリアローズが、はっとしてティアを問いただそうとする。
その時ドアが開き、多くの教師や生徒達がぞろぞろと入ってきた。
「お待たせいたしました」
そうして、それぞれ二十名近い教師と生徒が席についたのだった。
「これより、今期最初の代表会を始めます」
開始の言葉を口にしたのは、学園長のダンフェール・マランドだ。
今でも学園長の職は、フェルマー・マランドの直系子孫が継いでいる。魔力が高い上に、竜人族の血が入っているため、彼らの寿命は長い。ダンフェールも見た目は五十代くらいに見えるが、実際は百歳近い高齢だった。
今回この場に集った教師は、小・中・高それぞれの学部をまとめる学部長三名。更に、各学年の学年主任が九名。普段はこの十二名と学園長だけが出席するのだが、今日は今期初の会議という事で、ウルスヴァンを含めた新任教師五名も同席している。
一方、生徒は男女関係なく、各学年二人ずつ。成績や素行を見て学園側が選任した模範生達だ。ベリアローズとエルヴァストがいるのも、高学部三年の代表だからである。新入生の代表は、まだ人物的な評価ができないので、入試の成績をもとに上位二人が選出された。
今年の代表はティアと、新入生の中では最も位の高いドーバン侯爵家の三男――キルシュ・ドーバンだった。
「――では、今期はこのメンバーで代表会を行います」
進行役である高学部の学部長が生徒の名を一人一人読み上げ、今期の代表の顔ぶれを確認したところで、すぐに解散となった。代表の生徒は成績トップの模範生でなくてはならないので、まれに入れ替わりが発生する。ベリアローズとエルヴァストは、高学部から代表となった例外中の例外だ。
最も替わりやすいのが小学部の一年と二年。二年生の代表二人も、今回初めて会議に参加したようだ。
左隣のキルシュが立ち上がったのを見て、ティアは笑顔で挨拶をする。クラスが違うので、これが初顔合わせだったのだ。
「ご挨拶が遅れました。三組のティアラール・ヒュースリーです。これからよろしくお願いしますね」
誰もが魅了される最高の笑顔。だが、キルシュ少年の反応は意外なものだった。
「ふん、僕に媚を売るな。気持ち悪い。これだから計算高い女は……。言っておくが、負けたとは思っていないからな。次は僕が一番だ」
それだけ言って、ティアと目を合わせる事もなく、キルシュは部屋を出ていった。
焦ったのはティアの後ろで聞いていたベリアローズとエルヴァスト、そしてウルスヴァンだ。他の教師達は眉をひそめながらも部屋を出ていき、生徒達も関わらないでおこうと、足早に去っていく。残されたのは、ティア達四人だけだった。
「ふ、ふふっ。なんだろう……あのツンツンした感じ。とっても懐かしいわっ」
突然、楽しそうに笑い出したティアに、他の三人は息を呑む。
「くくくっ、これは是非とも調きょ……じゃなかった、広い世界を教えてあげないと。貴族病は、早期治療が大切だもの。若いうちじゃなきゃね。末期になったら死ななきゃ治らなくなるものっ」
今まで大人しくしていた反動か、ティアは絶好調だった。これにはエルヴァストでさえ頬を引きつらせる。
「な、なんだろう……悪魔が目覚めたような危機感を覚える」
笑顔で振り向いたティアは、嬉しそうに言った。
「今の見たっ? 聞いたっ? あの感じ、初めて会った時のお兄様みたいじゃないっ? 精一杯、虚勢を張ってる感じとか、女を馬鹿にする感じとか!! 何あの子っ、楽しすぎなんだけど!!」
テンションはマックスだ。新しいおもちゃを見つけた時のような輝きを放っている。
「……ベル……お前の時もこんな感じだったのか? その……よく耐えたな」
「ううっ……ま、間違いない。この顔は、一番初めにマティをけしかけた時の顔だ……」
ティアの笑顔は、ベリアローズの心の傷をしっかりと抉ったらしい。見かねたエルヴァストが、よく頑張ったなと肩を叩いて励ます。その二人の後ろでは、ウルスヴァンが震えながら悲鳴を上げた。
「だ、誰が止めるんですっ? ダメですよっ? 侯爵家が消えてしまいますっ!!」
侯爵家が消えたら、国の一大事だ。ウルスヴァンは、その可能性に凍りつく。
「楽しい! 楽しすぎるわ! 学園なんて冒険者生活の合間の暇潰し程度にしか考えてなかったのに、こんなにも楽しい遊び場だったなんて!」
「待て待て。遊び場じゃないぞ。勉強する場所だ」
「やだなぁ、エル兄様。私にとっては勉強だって遊びのうち。余暇の楽しみでしかないんだもの。あくまでメインは冒険者としての活動なのよ」
そこでティアは、急に表情を真剣なものに変えた。
「それにね、気に入らなかったの、この学園。創立当初は、教師にも生徒にも色んな種族がいた。それなのに、いつの間にか人族至上主義の、バカ貴族の巣窟になってるんだもの」
フェルマーの肖像画を見た時に、違和感を覚えた。今の学園の在り方と、かつてフェルマーが望んでいた世界との違い。それがティアには腹立たしかった。そして、先ほどのキルシュ少年の言葉で火がついたのだ。
「『国境のない学校を創りたい』」
「それは?」
ティアの呟きに、エルヴァストが首を傾げる。
「フェルマー先生の言葉。この学園は種族の枠を越えて、それぞれの文化や技術を教え合い、助け合って、より良い関係と新しい世界を作りたいって願いから創られたの。でも、今日見た限り、そんな願いはどこにも感じられなかったわ」
人族の、それも貴族の子どもしかいないこの学園の現状が、ティアは残念で仕方がなかった。
「変えるよ」
ティアはニヤリと笑う。他の三人は、反射的にビクリと体を震わせた。
「変えてみせるわ。ここは、この国の未来を創る者達が集う場所。なら、ここの人達の意識を変えれば、国を変える事に繋がるわよね」
国の次代を担う貴族の子どもが集っているのだ。彼らを変えられれば、国の在り方も変わる。
「ふふふっ、待ってなさい。人族至上主義なんてもの、叩き潰してやるわ」
ここからが、新たな舞台の幕開けだ。遥か遠くで、あの似非天使が微笑んでいるのを感じる。
(せいぜい見ていなさい。女神じゃない。私がこの世界を変えてやるわ)
女神としての使命だからではなく、ティア自身が望む世界を実現させるのだ。
第二章 女神の新しい友人
アデル・マランドは一人、両親の待つ教室へ向かっていた。その間に思い出すのは、ティアの事だ。
(あんな人もいるんだ……)
アデルにとって、ティアの言葉や態度は衝撃的だった。両親でさえ、アデルにどう接して良いのか分からず、腫れ物に触るような感じでいるのだ。
竜人族と結婚したフェルマーは、マランドの一族の中では異端だった。その直系子孫がこの学園を守ってきたのだが、フェルマーが理想としたものは、長い年月の中で変えられてしまっていた。
マランドの一族は、貴族として生きるために、異種族を否定しなくてはならなかった。だからこそ、一族の中に異種族の血が入っている事を忌まわしく思っていたのだ。
そんな中、生まれたのがアデルだった。両親は、彼女が竜人族の先祖返りである事を必死で隠そうとしてきた。マランド家に竜人族の血が入っている事は周知の事実だが、先祖返りだと知られれば、他の貴族達から爪弾きにされる。
だからアデルは、ずっと孤独だった。悪いのは自分だ。両親の怯えた態度も、世間の冷たい目も、全て自分のせい。そう思うしかなかったのだ。
教室に近づくと、多くの生徒と親達が連れ立って出てきた。
アデルは前髪で顔を隠しながら進む。
しかし、注意が足りなかったのだろう。何かにつまずき、転んでしまった。一瞬、ウロコのような皮膚が見えてしまったらしく、多くの人が大袈裟にアデルを避ける。
「あの子よ」
「例の混ざり者か」
「竜人族ですって」
「いやだわ。野蛮な種族だと聞きましてよ」
そんな言葉が聞こえてくる。きっと両親は、部屋の隅で耳を塞いでいる事だろう。アデルの目に涙が滲むが、流れないように、溢れないように必死で堪えた。大丈夫。いつもの事だと心を落ち着かせる。
その時、白くて滑らかな手が差し伸べられた。
「大丈夫? 怪我をしているかもしれないわ。こちらへいらっしゃい」
顔を上げたアデルの前には、可愛らしい女性と優しげな男性がいた。
「シアン。ここは人が多いから、あちらの教室へ入ろう。……君、立てるかい?」
「え? あ、はい……」
驚きすぎて涙が止まった。立ち上がったアデルに、男性が言う。
「あぁ、膝を擦りむいてしまっているね。ゆっくりでいいから、こっちへおいで」
「私の手に掴まって」
二人と一緒に空き教室へ向かうと、椅子に座らされた。
「女の子だもの、傷が残ったら大変だわ。ちゃんと手当てしなくてはね。娘が来れば治してくれるけれど、水で拭いておかなくちゃ。フィスターク、このハンカチを濡らしてきて」
女性――シアンがハンカチを差し出すと、フィスタークと呼ばれた男性がそれを持って出ていった。
「あなたのご両親は、どこにいらっしゃるのかしら。探してくるから待っていて」
そう言って、今度はシアンが部屋を出ていく。
しかし、すぐに困った顔で戻ってきた。
「私ったら、あなたのお名前を聞くのを忘れていたわ」
「あ、アデル・マランドです」
「マランドさんね。分かったわ」
少し不安になるアデル。けれど、シアンはちゃんと両親を連れてきた。
両親がアデルの目の前にやってくる。
「アデル……私達は帰るぞ。寮でしっかりな」
「あなた、急ぎましょう……」
二人は入り口付近で待つシアンに聞こえないよう、小さな声で言った。
「そんな怪我、放っておいても大丈夫だろう。早くあのご婦人にお礼を言って、寮に戻れ」
そう続ける父親に、アデルは震えた。せっかく乾いた涙が、再び滲んでくる。
だが、別に優しくされたかったわけではない。この人達はいつもこうだった。期待なんてしないと割り切ったおかげで、涙を流さずに済んだ。
立ち上がるために足に力を入れた時、フィスタークが戻ってきた。
「遅くなってすまないね」
「あ……」
アデルが動こうとする前に、ハンカチを受け取ったシアンが素早く歩み寄る。そして、その場に膝を突いて、擦りむいた膝を優しく押さえてくれた。
「痛い? ごめんなさいね。でも、女の子はお肌には気を付けないと」
「え、あ……」
肌と言われて、咄嗟にこめかみを押さえてしまった。異質な皮膚を隠さなくてはと思ったのだ。その反応に、シアンはフワリと微笑む。
「あら、隠してしまうの? 七色に光って綺麗だわ。それを見せるためにも、前髪をまとめるアクセサリーが欲しいところね。どう思う? フィスターク」
フィスタークの方を振り向いて、楽しそうに言うシアン。それに、フィスタークが優しい微笑みを浮かべて答える。
「ふふ、シアン。学園ではあまり華美にしてはいけないだろう? でも、そうだね……シルバーのサークレットのようなものが似合いそうだ」
「そうよねっ。ティアちゃんにお願いしようかしら」
良い事を思いついたと笑顔を輝かせるシアンに、フィスタークが苦笑する。
「シアン。彼女のご両親が驚いておられるよ」
「まぁ、私ったら。ごめんなさいね」
なんだか勢いのある女性だが、少し抜けているようだ。こんな人が母親なら楽しいだろうなとアデルは思う。
そのシアンが突然、真面目な顔で立ち上がり、両親をまっすぐに見た。
「不躾かもしれませんが、一つ言わせていただきます。どのような世界であろうと、子どもの自由を奪ってはなりませんわ。そのような権利は、親であってもないのです」
「「……」」
ガラリと変わった雰囲気と声音に、両親達は気圧されてしまっていた。
「子どもは自由です。だからこそ、わたくし達には見えない……いえ、見えなくなった世界を見る事ができます。子ども達は天使ですわ。狭くなってしまった大人の世界に風を通して、広げてくれるのです。だから感謝しなくてはいけませんわ。見えなくなってしまったものを見つけてくれる子ども達に」
「「……っ」」
その言葉に、両親は感銘を受けたようだ。表情が穏やかになり、どこか張り詰めていた空気も消える。
「それに貴族だからといって、異種族を否定しなくてはならないわけではありません」
フィスタークがこちらに近づきながら、両親の心を見透かしたように言った。
「世界は人族だけのものではない。それにみんなが気付けば、きっと素晴らしい世界が見られるでしょう。マランドさん。あなたの先祖であるこの学園の創立者は、とても素敵な方だったと聞いています。その夫であった方も、素晴らしい才能を持った竜人族なのだそうです」
彼はシアンの肩を愛おしそうに抱いて、優しく微笑んだ。
「え……」
驚く両親に向かって、フィスタークは続ける。
「ご先祖の話が聞きたくなったら、我が街サルバへおいでください。当時のお二人を知る方がいらっしゃいますから」
「サルバ……あっ、ヒュースリー伯爵様でしたかっ。これは失礼いたしました」
「いや、身分などお気になさらず。今の私達は、同じ年頃の子どもを持つ親でしかありませんよ」
そう言って朗らかに笑う彼に、両親は目を見開いている。
そこで、ようやくアデルは気付いた。
「ヒュースリーって、ティアラールさんの……?」
アデルは名前を覚えるのが苦手だが、ティアの名前だけは覚えていた。
「そうよ。もしかして、ティアちゃんと同じクラスなのかしら?」
シアンの言葉に、アデルは反射的に頷く。すると、シアンはまた素敵な笑顔を見せた。
「是非ティアちゃんとお友達になってちょうだい。きっと楽しいわ。そうしたら、うちに遊びに来てちょうだいね」
「そうだね。遊びに来ると良い。ティアには、同じ年頃の友人がいなくてね。歓迎するよ」
社交辞令でなく、本当に歓迎してくれるらしい。そんな二人の様子に、両親だけでなくアデルも呆気に取られていた。
「あ、でも、私なんかが友達に……」
なれるだろうか。友達なんてものが、自分にできるとは思えなかった。
しかし、ティアの両親は断言する。
「なれるさ」
「なれるわ」
その時、開いたままだったドアをノックする音が聞こえた。
◆ ◆ ◆
ティア達は代表会が終わると、父兄の待つ控え室へと向かった。
「ティア。分かっているとは思うが、学園での破壊行動は慎んでくれ」
「そうだな。物も人も壊してはいけないぞ」
ベリアローズとエルヴァストは、学園での注意事項を思いついたそばから吹き込んでいた。ただしその内容は、ティア限定のものだ。
「もう、お兄様達は私をなんだと……」
要約すると『暴れるな』という事なのだ。むやみに喧嘩を買わない、売らせないというものから始まり、学園内での攻撃魔術の禁止や、精霊王との接触の禁止など、ティアがやりそうな事を次々と潰していく二人。それだけティアを理解しているという事なのだが、当然ティアは不満だった。
「喧嘩を買うなと言ったところで、大人しく回避するような妹ではないだろう」
「攻撃魔術を禁止しただけでは、甘いだろう」
自信ありげな態度の兄達に、ティアは内心舌打ちした。
喧嘩を買うなと言われれば、盛大に売らせてもらう。攻撃魔術を使うなと言われれば、精霊王達に頼んで同様の事象を起こす。それがティアなのだ。
応援ありがとうございます!
0
お気に入りに追加
4,565
1 / 5
この作品を読んでいる人はこんな作品も読んでいます!
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる
本作については削除予定があるため、新規のレンタルはできません。
このユーザをミュートしますか?
※ミュートすると該当ユーザの「小説・投稿漫画・感想・コメント」が非表示になります。ミュートしたことは相手にはわかりません。またいつでもミュート解除できます。
※一部ミュート対象外の箇所がございます。ミュートの対象範囲についての詳細はヘルプにてご確認ください。
※ミュートしてもお気に入りやしおりは解除されません。既にお気に入りやしおりを使用している場合はすべて解除してからミュートを行うようにしてください。