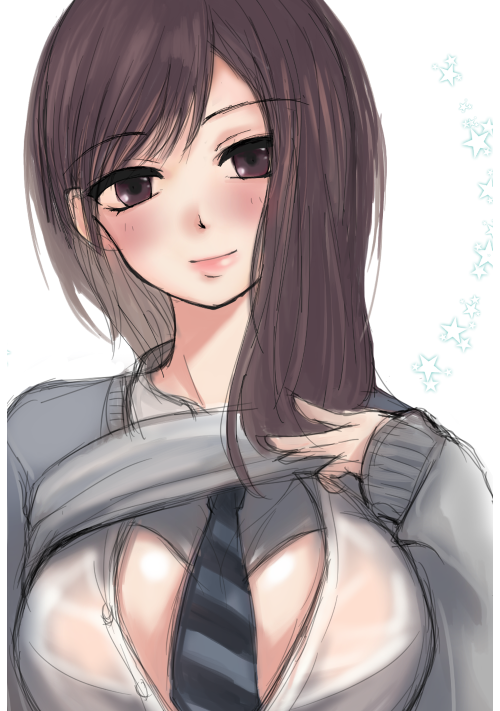98 / 449
7巻
7-2
しおりを挟む
苦々しい思いを抱きながら式を終えたローズは、密かに学園街にある宿屋に足を運んでいた。
ローズは公爵の庶子で、つい半年前までは隣国ウィストの貧しい母子家庭で暮らしていた。しかし半年前、病弱だった母が死してすぐ、神子と呼ばれる少女からの使いが現れた。
彼らは、ローズを実の父であるリザラント公爵と引き合わせた。更にローズは『女神サティアの生まれ変わり』であると、神子から託宣を受けたのだ。
目まぐるしく運命が変わったその日の夜、ローズは夢を見た。それは、ローズがサティアとして生きていた過去の情景。反乱軍を率いて城に乗り込んだ時の夢だった。
「本当に、私がサティアなんだ……」
ローズは確信した。間違いなく自分がサティアの生まれ変わりであると。そんなローズに神子がこう言ったのだ。
「サティア様。あなたは自ら望んで再び地上に降りてこられたのです。かつて、彼の国があった場所。そこの王家に戻り、世界を平和に導く。それがあなたの運命なのです」
「そう……そうだわ。私はあの場所に戻らなくては……」
その頃、まさに運命であるかのように、王太子が婚約者を探していた。その上、自分は公爵家の令嬢になったのだ。もはや疑いようもなく、天はその道を示していた。それなのに、それを邪魔する者がいたのだ。
「ウィストの王女が王太子の婚約者ですって? ははっ、愚かなことだわ。でも私はサティアだもの。あの時も天は試練を課した。これを乗り越えてこその私よね」
それを裏付けるかのように、公爵はローズを自領に引き取った後、王妃となっても恥ずかしくない知識や振る舞い方を身につけさせた。国で随一の学園への入学手続きも取った今、運命はローズを王太子妃にしようとしているとしか思えない。
「あと、足りないのはそうねぇ……優秀な騎士かしら?」
常にサティアに付き従っていた最強の女騎士、アリア・マクレート。そんな存在が手元にいないのは不満だった。だが、それも近いうちに解消すると神子は言った。
「サティアである私に天は味方するはず。それなのにっ……」
学園の代表としてローズは挨拶をするつもりだった。そうすることで、学園の全ての人々に自分の存在を認識させる。誰も無視できない女神の生まれ変わりとして、畏敬の念を抱かせるはずだった。
しかし、学園から許可は下りず、ふたを開けてみればまだ幼い小学部の少女が代表として挨拶をしたのである。
あの場所と、羨望の視線は、全てローズのものだったはずだ。
「なんて無礼なっ……屈辱だわ!」
その光景を思い出すと、キリキリと奥歯が鳴る。そこへ待っていた人物がやってきた。
「お待たせして申し訳ありません、姫」
「スィール。良いのですよ。あなたと私の仲ではありませんか」
「っ、過分なお言葉、痛み入ります」
まだ十代の幼さを残す黒髪の青年。彼はかつて反乱軍を率いた青年スィールの生まれ変わりだ。今は剣ではなく、神の魔導具である『神具』を手にしている。だが、今生でもサティアの願う未来のために動いてくれていた。
「それで、計画はどうなっていますか?」
神子が主体となって活動している『神の王国』という組織。それは、サティアを助ける者達によって作られたものだ。真の平和を実現させるため、この世界を神が願う姿へと変えるための実行部隊。きっと彼らは、かつて密かに王国を守っていた、クィーグ部隊の末裔なのだろう。ローズはそう考えていた。
「順調です。新たに『神具』の使い手も見つかったとジェルバ様が仰っていました。そちらの調整が終わり次第、この国に神の威光を知らしめることができるでしょう」
「ええ、そうね。託宣の方は?」
神子を通じて神教会へと下ろされる神託。それを根拠として、ローズを王太子妃にすべきだと王家に伝える手はずになっている。
「そちらは少し時間がかかるかもしれません。どうしてか、ここフリーデル王国の神教会は託宣を受け入れないのです」
「……どういうことです?」
スィールの話によれば、フリーデル王国の神教会は『そのような託宣が下るはずがない』と突っぱねているらしい。女神サティアの生まれ変わりであるローズも賛同していると告げても、結果は同じだという。むしろ『それならば尚のこと信じることはできない』と追い返されたそうだ。
「この国にはエルフがおりますし、異種族の悪しき考えが蔓延しているのでしょう。ですが、心配はいりません。きっと神のご意思が知れ渡れば、それらも払うことができましょう。そのためにも必ずや今回の計画を成功させてみせます。私は今も昔も変わらず、サティア様に従う者なのですから」
「スィール……そうね。あなたがいれば、きっと成すことができるわ。何より、こちらには天使だってついているんですもの」
ローズ達は知らない。己の境遇に酔いしれ、思い込みで突き進む先に何が待ち受けているのかを。それが本物のサティアと仲間達の怒りに触れることになるとは、考えもしなかったのだ。
◆ ◆ ◆
入学式が終わり、代表会のメンバーであるティアやキルシュもようやく解放された。その日の午後、二人はヒュースリー伯爵家の別邸で待っていた級友のアデル・マランドと合流し、学園街の地下へと潜る。
フェルマー学園を創設したフェルマー・マランドと共に、歴史を記録する役割を担ってきた妖精族のシルキー。彼女に会いに、ティア達はたびたびここへやってきていた。
「ああっ、疲れたぁぁぁ」
「お疲れ様、ティア、キルシュ」
アデルがシルキーと一緒にお茶の用意をして労ってくれる。フェルマーの子孫であるアデルが手伝ってくれるとあって、シルキーもいつも以上にご機嫌だ。ちなみに今日のお茶請けはストレス発散を兼ねて、昨晩ティアが作った焼き菓子だった。
「ありがとう、アデル」
「すまない」
一息つけたことで肩の力が抜ける。そんなティアを見て、アデルがおかしそうに笑った。
「なんか、ティアって本当にイメージ変わるよね。今日の挨拶の時なんて、周りのみんなが放心状態だったよ?」
「まったくだな。新入生の父兄など、全員教会の参拝者かと思ったぞ」
その言葉にティアも笑ってしまう。
「あはは。それは私も思った。すっごい祈ってたよねぇ。顔が引きつりそうになったもん」
壇上からだと、とてもよく見えるのだ。それまで眠そうにしていた者達まで目を見開いて、思わずといったように両手の指を組んでいた。そんな生徒や教師、そして父兄達の様子は、ある意味滑稽だった。
そろそろ免疫ができてきたはずの生徒や教師達でさえそうなのだ。慣れていない父兄はもう仕方がないと割り切った。しかし、そんな中で目を引いた生徒が二人いた。
「そういえば、例の編入生ってのはどういう人達だったんだ?」
タイミングの良いキルシュの質問に、ティアは首を傾げた。
「あれ? 興味ないんじゃなかったの? 関係ないって言ってたじゃん」
高学部の三年ならば自分達には関係ないと話したのは一昨日のことだ。不思議そうなティアに、キルシュは思いっきり顔をしかめてみせる。
「バカな編入生のせいで挨拶をすることになったと、さんざん愚痴ったのはどこの誰だ?」
「は~い、私で~す。そっか、気になっちゃった?」
「当たり前だ」
不貞腐れたようなキルシュの表情を見て、心配してくれたのだと分かり、少し嬉しくなったのは秘密だ。
「なになに? 編入生?」
アデルも興味津々の様子である。
「そ。高学部の三年生に二人。両方とも女性だよ。一人はローズ・リザラント。リザラント公爵家の令嬢なんだけど、これが高飛車で嫌味な女らしくてね。自分が代表の挨拶をするって駄々こねたんだって。おかげで私がやることになったのよ」
公爵家の血を引く者であるということをひけらかし、何かにつけて自身が上位であると示したがる傾向があるようだ。
「問題発言も多くて、初日から教師陣が頭を抱えてたわ」
公爵令嬢である自分は優遇されるべきだとか、この学園には自分より身分の高い者はいないのだから従って当然だとかいう態度。挙げ句の果てに、『私は女神サティアの生まれ変わり』発言である。それは頭も痛くなるというものだ。
「うわぁ、ティアがいかにも嫌いそう」
「うん。既に駆逐対象リストに入ってる」
「駆逐っ……穏便にな?」
キルシュはそう言うが、腹の立つ貴族の見本みたいなものだ。今すぐ張り倒したいのを我慢できているのは、まだ会っていないからだろう。
「それで、もう一人は?」
アデルが呑気に促す。ティアのやることにそれほど間違ったことはないと、アデルは信じて疑わない。ティアが嫌いならば、自分も好きにはなれないと思っているのだろう。
「もう一人はねぇ。ウィストの第一王女」
「えっ!?」
「王女様ぁ!?」
やっぱり驚くよねとティアは笑う。
「元々、色んな国で遊学を楽しまれていたらしくて、最後の一年はいずれ王妃になるこの国で、ってことみたい」
「ふぅ~ん。勉強熱心な王女様だね」
学園長の話を聞いた限り、実際かなり勤勉で真面目な性格らしい。
「まあ、学園長に頼まれたからフォローはするけど、何か起こりそうな場合以外は放っておくつもり」
そう言った途端、キルシュとアデルは困ったような表情で顔を見合わせる。きっとティアは色々と巻き込まれるだろうな、とそこには書いてあった。
そんな二人の肩にシルキーがそっと手を置く。三人はお茶を堪能するティアを気の毒そうに見つめたのだった。
◆ ◆ ◆
ティア達が帰った後の部屋は静かだ。シルキーは、いつものように部屋の掃除を始める。しかし、幾分かして来客の気配に手を止めた。
この地下の空間は全てシルキーが管理している。侵入者は即刻叩き出す仕組みだ。万が一にもこの部屋まで辿り着くなんてことは起きない。こちらが招き入れでもしない限り絶対だ。
しかし、例外中の例外がたった一人だけいる。
その人はコツリコツリと規則正しい足音を響かせながら部屋までやってきた。
金の眩い髪と、光を反射して色合いを変える鈍色の瞳。白と金を基調とした服は、気高い彼の存在を美しく引き立てていた。
《よう。元気か?》
言葉の響きから、それが人でないことは明らかだ。声帯を通ってはいるが、その声は魂にも届く。そして、彼の背中には美しい透明の羽が二対あった。
《見れば分かりますでしょう。それよりも王。このように何度もおいでになられてよろしいのですか?》
人族には聞こえないシルキーの声も、その人には受け取ることができた。
《構わんさ。我が城は鉄壁。誰も来ることのなくなった王の間に、ただ座っているだけでは不健康すぎるだろう》
《……その生活を五百年はお続けだったはずですが?》
《はっはっはっ……それを言うな!》
この気安い妖精族の王は、つい先日まで引きこもり生活を続けていた。ダンジョンと呼ばれる地下の迷宮。妖精族はそこを管理し住処としている。この地下の空間もシルキーにとってのそれだ。
魔力の源である魔素によって生まれるのは精霊と同じだが、妖精族は精霊と違って明確な体を持つ。人族と同じく、誰の目にも見える存在としてこの世界に生きている。しかし、その性質から、魔素の多い場所でしか活動できず、地上のどこにでも棲めるというわけではない。
妖精王は、そんな妖精達の棲む場所の魔素を調整する役目を負っていた。
ただし、同じ妖精族でもシルキーだけは違う。彼女達は家に憑き、そこに住まう人々の放つ魔力を魔素代わりにして生き続けるのだ。だから、この場所も妖精王の管理下にはない。
王がシルキーのもとへひょっこりと顔を出したのは、半年ほど前。地下の通路は学園街の下に張り巡らされているだけでなく、少々遠方にある王のダンジョンにも繋がっていたのだ。
《だってなぁ。フィンの奴はフテ寝したまま起きねぇし、最近はダンジョンに潜ろうって気骨のある冒険者もいねぇ。それで俺はどう楽しめというんだ?》
簡単に言うと、いい加減に退屈すぎて外出したくなったのだ。構ってくれる人を求めて彷徨い出したともいえる。何千年と生きる妖精族にとっても、五百年という時間は短くなかったらしい。
《それに、あの子が生まれ変わってきたんだ。早く会いたいじゃないかっ》
《ならば会われればよろしいのに》
妖精王は昔、娘のように可愛がっていた少女が生まれ変わったと知って出てきたのだ。だが、なぜか自分から会おうとはしない。その理由がこれだ。
《俺は妖精王だぞ? ダンジョンのボスだぞ? 冒険者であるあの子が会いに来るまで待っててやるのが筋ってもんだろう》
《……待てなさそうですけどね》
《だから、それを言うなってっ》
会いたくて仕方がなくて、自分の存在を思い出して欲しくて、その子の母親から預かっていた物をわざわざ持ってきたのが半年前のことだ。それをシルキーから少女に渡してもらったのだが、残念ながら気付いてもらえていないらしい。
《会いたいが……今はちょいマズい。やっぱりどうにもきな臭くてな》
王は真面目な顔で腕を組んで唸る。最近、少々気になることがあるのだ。
《……それでは会えるのは当分先ですね》
《だからそれを言うなってっ。俺だって傷つくんだからな?》
目下の心配事が解決するまで、あの子をダンジョンには呼べない。大切な少女を危険な目に遭わせることはしたくない。
《そんな傷心の王に、あの子の作った焼き菓子をお分け……しようと思ったのですが、先ほど食べ終わってしまいました》
硬めが好きだというその子の作った焼き菓子は歯ごたえが癖になるのだ。取っておこうと思っても、手を出せばついつい食べ切ってしまう。
《なんでだよっ。残しておけよっ。しまいには泣くぞっ》
《まさか、昨日いらして今日も来られるとは思わないじゃないですか。残念です》
《お前、俺のこと嫌いだろっ》
《……どうなんでしょう?》
《聞くなよっ。あぁっ、クソっ、やっぱり、さっさと会いに来いよぉぉぉっ》
嘆く王の声が、その子に届くことはなかった。
◆ ◆ ◆
その日の夜。ティアは怒濤のように過ぎた今日までの日々を思い、別邸のベッドで目を閉じていた。しかし、しばらくして不意に身を起こし、ベッドから出て窓を開ける。
「シリウス」
彼をその名で呼ぶのはティアだけだ。シリウスと呼ばれた黒装束の青年……クィーグ部隊の三番手シルは、二階にある部屋にひらりと入ってきた。
「ごめんね。なかなか時間が取れなくて」
「いえ。問題ありません」
ティアは数日前、シルに頼み事をしていた。しかし、それについての報告は入学式が終わって落ち着くまで待ってもらっていたのだ。
「それで、里の方はどうだった?」
ベッドに座り、シルの報告を聞こうと目を向ける。すると、いつも無表情なシルの顔に少しだけ苛立ちが見えた気がした。
「何かあった?」
いつものシルらしくない。彼の表情が更に曇る。
「里長は……承服できないと……証を見せるようにと言われました」
「うん? 証?」
「はい。サティア様である証を……本物のサティア様ならば王宮の地下に秘されているものを白日のもとに晒すことができるだろうと……」
シルは目を細め、ティアから視線をそらす。悔しいと、その顔には書いてあった。
「なるほどね。まあ、でもそれもそうか。そうそう信じられないよね」
自分がサティアの生まれ変わりであることは分かっているが、それを信じろと他人に言うことはできない。過去の出来事をどれほど知っていたとしても、確かめる術はないし、証とするのは難しいのだ。
未だに周りに言えないのもそれが理由だ。しかし、そんな中でもシルはティアを信じていた。
「そんなことはありません! 本来ならば、ティア様を疑うなどあってはならないのですっ」
「いや、無茶だよ?」
そんな指摘もシルには届きそうにない。こんな時の対処法は分かっている。
「それに、無理に協力してもらう必要はないんだ。元々カル姐のところで調査が進んでるみたいだし、何より、私にはシリウスだけで充分だよ」
「っ……」
ティアが隣国のウィストとサガンを怪しいと思ったのは、魔王カルツォーネからもたらされた情報によるものだ。魔族は『神の王国』の魔工師ジェルバを追っている。その過程で『神の王国』がウィストとサガンに拠点を構えているらしいと知った。人族の国ならば、魔族よりも人であるクィーグの方が動きやすいだろうと思ったティアは、里長に協力を頼んで欲しいとシルにお願いしたのだ。
「でも、王宮の地下かぁ……ちょっと気にはなってたんだよね~」
「ティア様、ですが……」
何も里長の言うことを聞かなくてもいいとシルは考えているようだ。その顔は実に不満そうに見えた。
「いいのいいの。ちょっとした散策だよ。別に認めて欲しいとかじゃないもん。言ったでしょ? シルだけでいいんだよ。だいたい、私を試そうなんて良い度胸だよね~。ってことで、明日にでもエル兄様の様子を見がてら遊んでくるよ」
「はぁ……ティア様がよろしいのであれば。ですが、もしその結果、里長がおこがましくも認めるなどと言ってきた場合は、容赦なく切り捨てください。あのような者達、ティア様の傍にいるには相応しくありません」
シルはかなり怒っているようだ。ここまで感情を顕わにし、言葉にするのは初めてだった。
「ははっ。うんうん。何度も言うけど、シルだけでいいからね」
「はいっ」
自信満々に返事をするシルを見て、ふと誰かと似ている気がした。だが、上手く思い出せない。だからティアは、誤魔化すように明日の予定を口にする。
「よしっ。それじゃ、明日は王宮探索っ。エル兄様には栄養ドリンクをお土産に持っていこう」
学園を卒業してから毎日、王宮での仕事に忙殺されているらしい第二王子エルヴァスト。ひと月ぶりに顔を見に行くことになるが、果たして元気でやっているだろうかと、ティアは思いをはせるのだった。
◆ ◆ ◆
過去の情景はいつも唐突に夢に見る。ティアが女神の力を持っているからなのか、前世の記憶を持つからなのかは分からない。けれど、それはいつも意味なく見られるものではない。決まって何かの暗示なのだ。夢から覚めた時、覚えていられるかどうかは定かでないが、予感として残るものではあった。
これは幼い頃から繰り返されており、それほど珍しいことではない。だが、夢に見るのはティア自身がほとんど関わっていない出来事も多く、いつだって少し離れた場所から見つめることしかできない。だから、これはきっとティアではなく、世界が記憶している光景なのだろう。
真っ赤な長い髪を揺らしながら王城の廊下を駆けるのは、ハイヒューマンであり、バトラール王国の王妃であるマティアスだ。護衛の騎士達はとても追いつけないが、彼女が向かう部屋は分かっているので、そこに上手く配置された騎士達によってなんとか規律は保たれている。
その部屋の扉を、声をかけるよりも先に開け、マティアスは中へと入っていく。
マティアスが最初に声をかけた相手は王宮の薬学師だ。
「ライラは大丈夫かっ」
中央のベッドに横になっているのは、白銀に近い金色の髪を枕に広げて荒い息をする、第六王妃のライラだった。
「い、今、薬を呑んでいただけたところです」
その薬学師の声を合図にライラが目を開ける。薄い青色の瞳は熱に浮かされ、涙で潤んでいた。
「っ……マティアス様……子ども達は……」
掠れた声で尋ねるライラに、マティアスは近くまで顔を寄せて優しく答える。
「心配いらない。リュカもシェスカも今日は熱を出していないよ」
「そうですか……申し訳ありません……」
いつもライラは『申し訳ありません』『お手を煩わせてすみません』と、朦朧とした意識の中で言う。だが、マティアスとしては笑ってくれるだけで充分だ。
六人の王妃の中で最も年下。そんなライラを他の王妃達は皆、妹のように思っている。
体のあまり強くないライラは元々、魔力循環が上手くいっていなかったのだ。そこへ双子を身ごもってしまった。
双子は昔から高い魔力を持って生まれてくると言われている。その影響で母体は魔力の循環不良を起こし、産むのにもかなりの負担を伴う。母子共に無事でお産を終えることさえ稀だと言われていた。
だが、王宮に詰めている薬学師や治療師、魔術師達は優秀だ。だから、ライラもなんとか双子を産むことができた。ただし、産後の状態は良いとは言えない。
双子自身も生まれながらに高い魔力を持つことで、それを暴走させやすく、常に命の危険に晒されている。それでも生きているのは、優秀な魔術師達やマティアスのおかげだろう。
「もうお休み。薬が効いてくるまで傍にいてやるよ」
「はい……」
こんな時は夫であるサティルが来るべきなのだが、二日に一度は倒れるような状態のライラのところには、王としての政務もあって来られない。
何より、サティルは不器用なのだ。貴族達から無理矢理あてがわれた王妃達を愛せず、愛するのはマティアスのみと宣言したこともある。だからせめて、マティアスがこうして代わりに傍にいるようにしていた。
ライラもそれで良いと笑う。王妃達と一緒にいる方が楽しいというのはライラの正直な気持ちなのだ。特にマティアスを慕っている。だからマティアスもライラが可愛くて仕方がなかった。
ローズは公爵の庶子で、つい半年前までは隣国ウィストの貧しい母子家庭で暮らしていた。しかし半年前、病弱だった母が死してすぐ、神子と呼ばれる少女からの使いが現れた。
彼らは、ローズを実の父であるリザラント公爵と引き合わせた。更にローズは『女神サティアの生まれ変わり』であると、神子から託宣を受けたのだ。
目まぐるしく運命が変わったその日の夜、ローズは夢を見た。それは、ローズがサティアとして生きていた過去の情景。反乱軍を率いて城に乗り込んだ時の夢だった。
「本当に、私がサティアなんだ……」
ローズは確信した。間違いなく自分がサティアの生まれ変わりであると。そんなローズに神子がこう言ったのだ。
「サティア様。あなたは自ら望んで再び地上に降りてこられたのです。かつて、彼の国があった場所。そこの王家に戻り、世界を平和に導く。それがあなたの運命なのです」
「そう……そうだわ。私はあの場所に戻らなくては……」
その頃、まさに運命であるかのように、王太子が婚約者を探していた。その上、自分は公爵家の令嬢になったのだ。もはや疑いようもなく、天はその道を示していた。それなのに、それを邪魔する者がいたのだ。
「ウィストの王女が王太子の婚約者ですって? ははっ、愚かなことだわ。でも私はサティアだもの。あの時も天は試練を課した。これを乗り越えてこその私よね」
それを裏付けるかのように、公爵はローズを自領に引き取った後、王妃となっても恥ずかしくない知識や振る舞い方を身につけさせた。国で随一の学園への入学手続きも取った今、運命はローズを王太子妃にしようとしているとしか思えない。
「あと、足りないのはそうねぇ……優秀な騎士かしら?」
常にサティアに付き従っていた最強の女騎士、アリア・マクレート。そんな存在が手元にいないのは不満だった。だが、それも近いうちに解消すると神子は言った。
「サティアである私に天は味方するはず。それなのにっ……」
学園の代表としてローズは挨拶をするつもりだった。そうすることで、学園の全ての人々に自分の存在を認識させる。誰も無視できない女神の生まれ変わりとして、畏敬の念を抱かせるはずだった。
しかし、学園から許可は下りず、ふたを開けてみればまだ幼い小学部の少女が代表として挨拶をしたのである。
あの場所と、羨望の視線は、全てローズのものだったはずだ。
「なんて無礼なっ……屈辱だわ!」
その光景を思い出すと、キリキリと奥歯が鳴る。そこへ待っていた人物がやってきた。
「お待たせして申し訳ありません、姫」
「スィール。良いのですよ。あなたと私の仲ではありませんか」
「っ、過分なお言葉、痛み入ります」
まだ十代の幼さを残す黒髪の青年。彼はかつて反乱軍を率いた青年スィールの生まれ変わりだ。今は剣ではなく、神の魔導具である『神具』を手にしている。だが、今生でもサティアの願う未来のために動いてくれていた。
「それで、計画はどうなっていますか?」
神子が主体となって活動している『神の王国』という組織。それは、サティアを助ける者達によって作られたものだ。真の平和を実現させるため、この世界を神が願う姿へと変えるための実行部隊。きっと彼らは、かつて密かに王国を守っていた、クィーグ部隊の末裔なのだろう。ローズはそう考えていた。
「順調です。新たに『神具』の使い手も見つかったとジェルバ様が仰っていました。そちらの調整が終わり次第、この国に神の威光を知らしめることができるでしょう」
「ええ、そうね。託宣の方は?」
神子を通じて神教会へと下ろされる神託。それを根拠として、ローズを王太子妃にすべきだと王家に伝える手はずになっている。
「そちらは少し時間がかかるかもしれません。どうしてか、ここフリーデル王国の神教会は託宣を受け入れないのです」
「……どういうことです?」
スィールの話によれば、フリーデル王国の神教会は『そのような託宣が下るはずがない』と突っぱねているらしい。女神サティアの生まれ変わりであるローズも賛同していると告げても、結果は同じだという。むしろ『それならば尚のこと信じることはできない』と追い返されたそうだ。
「この国にはエルフがおりますし、異種族の悪しき考えが蔓延しているのでしょう。ですが、心配はいりません。きっと神のご意思が知れ渡れば、それらも払うことができましょう。そのためにも必ずや今回の計画を成功させてみせます。私は今も昔も変わらず、サティア様に従う者なのですから」
「スィール……そうね。あなたがいれば、きっと成すことができるわ。何より、こちらには天使だってついているんですもの」
ローズ達は知らない。己の境遇に酔いしれ、思い込みで突き進む先に何が待ち受けているのかを。それが本物のサティアと仲間達の怒りに触れることになるとは、考えもしなかったのだ。
◆ ◆ ◆
入学式が終わり、代表会のメンバーであるティアやキルシュもようやく解放された。その日の午後、二人はヒュースリー伯爵家の別邸で待っていた級友のアデル・マランドと合流し、学園街の地下へと潜る。
フェルマー学園を創設したフェルマー・マランドと共に、歴史を記録する役割を担ってきた妖精族のシルキー。彼女に会いに、ティア達はたびたびここへやってきていた。
「ああっ、疲れたぁぁぁ」
「お疲れ様、ティア、キルシュ」
アデルがシルキーと一緒にお茶の用意をして労ってくれる。フェルマーの子孫であるアデルが手伝ってくれるとあって、シルキーもいつも以上にご機嫌だ。ちなみに今日のお茶請けはストレス発散を兼ねて、昨晩ティアが作った焼き菓子だった。
「ありがとう、アデル」
「すまない」
一息つけたことで肩の力が抜ける。そんなティアを見て、アデルがおかしそうに笑った。
「なんか、ティアって本当にイメージ変わるよね。今日の挨拶の時なんて、周りのみんなが放心状態だったよ?」
「まったくだな。新入生の父兄など、全員教会の参拝者かと思ったぞ」
その言葉にティアも笑ってしまう。
「あはは。それは私も思った。すっごい祈ってたよねぇ。顔が引きつりそうになったもん」
壇上からだと、とてもよく見えるのだ。それまで眠そうにしていた者達まで目を見開いて、思わずといったように両手の指を組んでいた。そんな生徒や教師、そして父兄達の様子は、ある意味滑稽だった。
そろそろ免疫ができてきたはずの生徒や教師達でさえそうなのだ。慣れていない父兄はもう仕方がないと割り切った。しかし、そんな中で目を引いた生徒が二人いた。
「そういえば、例の編入生ってのはどういう人達だったんだ?」
タイミングの良いキルシュの質問に、ティアは首を傾げた。
「あれ? 興味ないんじゃなかったの? 関係ないって言ってたじゃん」
高学部の三年ならば自分達には関係ないと話したのは一昨日のことだ。不思議そうなティアに、キルシュは思いっきり顔をしかめてみせる。
「バカな編入生のせいで挨拶をすることになったと、さんざん愚痴ったのはどこの誰だ?」
「は~い、私で~す。そっか、気になっちゃった?」
「当たり前だ」
不貞腐れたようなキルシュの表情を見て、心配してくれたのだと分かり、少し嬉しくなったのは秘密だ。
「なになに? 編入生?」
アデルも興味津々の様子である。
「そ。高学部の三年生に二人。両方とも女性だよ。一人はローズ・リザラント。リザラント公爵家の令嬢なんだけど、これが高飛車で嫌味な女らしくてね。自分が代表の挨拶をするって駄々こねたんだって。おかげで私がやることになったのよ」
公爵家の血を引く者であるということをひけらかし、何かにつけて自身が上位であると示したがる傾向があるようだ。
「問題発言も多くて、初日から教師陣が頭を抱えてたわ」
公爵令嬢である自分は優遇されるべきだとか、この学園には自分より身分の高い者はいないのだから従って当然だとかいう態度。挙げ句の果てに、『私は女神サティアの生まれ変わり』発言である。それは頭も痛くなるというものだ。
「うわぁ、ティアがいかにも嫌いそう」
「うん。既に駆逐対象リストに入ってる」
「駆逐っ……穏便にな?」
キルシュはそう言うが、腹の立つ貴族の見本みたいなものだ。今すぐ張り倒したいのを我慢できているのは、まだ会っていないからだろう。
「それで、もう一人は?」
アデルが呑気に促す。ティアのやることにそれほど間違ったことはないと、アデルは信じて疑わない。ティアが嫌いならば、自分も好きにはなれないと思っているのだろう。
「もう一人はねぇ。ウィストの第一王女」
「えっ!?」
「王女様ぁ!?」
やっぱり驚くよねとティアは笑う。
「元々、色んな国で遊学を楽しまれていたらしくて、最後の一年はいずれ王妃になるこの国で、ってことみたい」
「ふぅ~ん。勉強熱心な王女様だね」
学園長の話を聞いた限り、実際かなり勤勉で真面目な性格らしい。
「まあ、学園長に頼まれたからフォローはするけど、何か起こりそうな場合以外は放っておくつもり」
そう言った途端、キルシュとアデルは困ったような表情で顔を見合わせる。きっとティアは色々と巻き込まれるだろうな、とそこには書いてあった。
そんな二人の肩にシルキーがそっと手を置く。三人はお茶を堪能するティアを気の毒そうに見つめたのだった。
◆ ◆ ◆
ティア達が帰った後の部屋は静かだ。シルキーは、いつものように部屋の掃除を始める。しかし、幾分かして来客の気配に手を止めた。
この地下の空間は全てシルキーが管理している。侵入者は即刻叩き出す仕組みだ。万が一にもこの部屋まで辿り着くなんてことは起きない。こちらが招き入れでもしない限り絶対だ。
しかし、例外中の例外がたった一人だけいる。
その人はコツリコツリと規則正しい足音を響かせながら部屋までやってきた。
金の眩い髪と、光を反射して色合いを変える鈍色の瞳。白と金を基調とした服は、気高い彼の存在を美しく引き立てていた。
《よう。元気か?》
言葉の響きから、それが人でないことは明らかだ。声帯を通ってはいるが、その声は魂にも届く。そして、彼の背中には美しい透明の羽が二対あった。
《見れば分かりますでしょう。それよりも王。このように何度もおいでになられてよろしいのですか?》
人族には聞こえないシルキーの声も、その人には受け取ることができた。
《構わんさ。我が城は鉄壁。誰も来ることのなくなった王の間に、ただ座っているだけでは不健康すぎるだろう》
《……その生活を五百年はお続けだったはずですが?》
《はっはっはっ……それを言うな!》
この気安い妖精族の王は、つい先日まで引きこもり生活を続けていた。ダンジョンと呼ばれる地下の迷宮。妖精族はそこを管理し住処としている。この地下の空間もシルキーにとってのそれだ。
魔力の源である魔素によって生まれるのは精霊と同じだが、妖精族は精霊と違って明確な体を持つ。人族と同じく、誰の目にも見える存在としてこの世界に生きている。しかし、その性質から、魔素の多い場所でしか活動できず、地上のどこにでも棲めるというわけではない。
妖精王は、そんな妖精達の棲む場所の魔素を調整する役目を負っていた。
ただし、同じ妖精族でもシルキーだけは違う。彼女達は家に憑き、そこに住まう人々の放つ魔力を魔素代わりにして生き続けるのだ。だから、この場所も妖精王の管理下にはない。
王がシルキーのもとへひょっこりと顔を出したのは、半年ほど前。地下の通路は学園街の下に張り巡らされているだけでなく、少々遠方にある王のダンジョンにも繋がっていたのだ。
《だってなぁ。フィンの奴はフテ寝したまま起きねぇし、最近はダンジョンに潜ろうって気骨のある冒険者もいねぇ。それで俺はどう楽しめというんだ?》
簡単に言うと、いい加減に退屈すぎて外出したくなったのだ。構ってくれる人を求めて彷徨い出したともいえる。何千年と生きる妖精族にとっても、五百年という時間は短くなかったらしい。
《それに、あの子が生まれ変わってきたんだ。早く会いたいじゃないかっ》
《ならば会われればよろしいのに》
妖精王は昔、娘のように可愛がっていた少女が生まれ変わったと知って出てきたのだ。だが、なぜか自分から会おうとはしない。その理由がこれだ。
《俺は妖精王だぞ? ダンジョンのボスだぞ? 冒険者であるあの子が会いに来るまで待っててやるのが筋ってもんだろう》
《……待てなさそうですけどね》
《だから、それを言うなってっ》
会いたくて仕方がなくて、自分の存在を思い出して欲しくて、その子の母親から預かっていた物をわざわざ持ってきたのが半年前のことだ。それをシルキーから少女に渡してもらったのだが、残念ながら気付いてもらえていないらしい。
《会いたいが……今はちょいマズい。やっぱりどうにもきな臭くてな》
王は真面目な顔で腕を組んで唸る。最近、少々気になることがあるのだ。
《……それでは会えるのは当分先ですね》
《だからそれを言うなってっ。俺だって傷つくんだからな?》
目下の心配事が解決するまで、あの子をダンジョンには呼べない。大切な少女を危険な目に遭わせることはしたくない。
《そんな傷心の王に、あの子の作った焼き菓子をお分け……しようと思ったのですが、先ほど食べ終わってしまいました》
硬めが好きだというその子の作った焼き菓子は歯ごたえが癖になるのだ。取っておこうと思っても、手を出せばついつい食べ切ってしまう。
《なんでだよっ。残しておけよっ。しまいには泣くぞっ》
《まさか、昨日いらして今日も来られるとは思わないじゃないですか。残念です》
《お前、俺のこと嫌いだろっ》
《……どうなんでしょう?》
《聞くなよっ。あぁっ、クソっ、やっぱり、さっさと会いに来いよぉぉぉっ》
嘆く王の声が、その子に届くことはなかった。
◆ ◆ ◆
その日の夜。ティアは怒濤のように過ぎた今日までの日々を思い、別邸のベッドで目を閉じていた。しかし、しばらくして不意に身を起こし、ベッドから出て窓を開ける。
「シリウス」
彼をその名で呼ぶのはティアだけだ。シリウスと呼ばれた黒装束の青年……クィーグ部隊の三番手シルは、二階にある部屋にひらりと入ってきた。
「ごめんね。なかなか時間が取れなくて」
「いえ。問題ありません」
ティアは数日前、シルに頼み事をしていた。しかし、それについての報告は入学式が終わって落ち着くまで待ってもらっていたのだ。
「それで、里の方はどうだった?」
ベッドに座り、シルの報告を聞こうと目を向ける。すると、いつも無表情なシルの顔に少しだけ苛立ちが見えた気がした。
「何かあった?」
いつものシルらしくない。彼の表情が更に曇る。
「里長は……承服できないと……証を見せるようにと言われました」
「うん? 証?」
「はい。サティア様である証を……本物のサティア様ならば王宮の地下に秘されているものを白日のもとに晒すことができるだろうと……」
シルは目を細め、ティアから視線をそらす。悔しいと、その顔には書いてあった。
「なるほどね。まあ、でもそれもそうか。そうそう信じられないよね」
自分がサティアの生まれ変わりであることは分かっているが、それを信じろと他人に言うことはできない。過去の出来事をどれほど知っていたとしても、確かめる術はないし、証とするのは難しいのだ。
未だに周りに言えないのもそれが理由だ。しかし、そんな中でもシルはティアを信じていた。
「そんなことはありません! 本来ならば、ティア様を疑うなどあってはならないのですっ」
「いや、無茶だよ?」
そんな指摘もシルには届きそうにない。こんな時の対処法は分かっている。
「それに、無理に協力してもらう必要はないんだ。元々カル姐のところで調査が進んでるみたいだし、何より、私にはシリウスだけで充分だよ」
「っ……」
ティアが隣国のウィストとサガンを怪しいと思ったのは、魔王カルツォーネからもたらされた情報によるものだ。魔族は『神の王国』の魔工師ジェルバを追っている。その過程で『神の王国』がウィストとサガンに拠点を構えているらしいと知った。人族の国ならば、魔族よりも人であるクィーグの方が動きやすいだろうと思ったティアは、里長に協力を頼んで欲しいとシルにお願いしたのだ。
「でも、王宮の地下かぁ……ちょっと気にはなってたんだよね~」
「ティア様、ですが……」
何も里長の言うことを聞かなくてもいいとシルは考えているようだ。その顔は実に不満そうに見えた。
「いいのいいの。ちょっとした散策だよ。別に認めて欲しいとかじゃないもん。言ったでしょ? シルだけでいいんだよ。だいたい、私を試そうなんて良い度胸だよね~。ってことで、明日にでもエル兄様の様子を見がてら遊んでくるよ」
「はぁ……ティア様がよろしいのであれば。ですが、もしその結果、里長がおこがましくも認めるなどと言ってきた場合は、容赦なく切り捨てください。あのような者達、ティア様の傍にいるには相応しくありません」
シルはかなり怒っているようだ。ここまで感情を顕わにし、言葉にするのは初めてだった。
「ははっ。うんうん。何度も言うけど、シルだけでいいからね」
「はいっ」
自信満々に返事をするシルを見て、ふと誰かと似ている気がした。だが、上手く思い出せない。だからティアは、誤魔化すように明日の予定を口にする。
「よしっ。それじゃ、明日は王宮探索っ。エル兄様には栄養ドリンクをお土産に持っていこう」
学園を卒業してから毎日、王宮での仕事に忙殺されているらしい第二王子エルヴァスト。ひと月ぶりに顔を見に行くことになるが、果たして元気でやっているだろうかと、ティアは思いをはせるのだった。
◆ ◆ ◆
過去の情景はいつも唐突に夢に見る。ティアが女神の力を持っているからなのか、前世の記憶を持つからなのかは分からない。けれど、それはいつも意味なく見られるものではない。決まって何かの暗示なのだ。夢から覚めた時、覚えていられるかどうかは定かでないが、予感として残るものではあった。
これは幼い頃から繰り返されており、それほど珍しいことではない。だが、夢に見るのはティア自身がほとんど関わっていない出来事も多く、いつだって少し離れた場所から見つめることしかできない。だから、これはきっとティアではなく、世界が記憶している光景なのだろう。
真っ赤な長い髪を揺らしながら王城の廊下を駆けるのは、ハイヒューマンであり、バトラール王国の王妃であるマティアスだ。護衛の騎士達はとても追いつけないが、彼女が向かう部屋は分かっているので、そこに上手く配置された騎士達によってなんとか規律は保たれている。
その部屋の扉を、声をかけるよりも先に開け、マティアスは中へと入っていく。
マティアスが最初に声をかけた相手は王宮の薬学師だ。
「ライラは大丈夫かっ」
中央のベッドに横になっているのは、白銀に近い金色の髪を枕に広げて荒い息をする、第六王妃のライラだった。
「い、今、薬を呑んでいただけたところです」
その薬学師の声を合図にライラが目を開ける。薄い青色の瞳は熱に浮かされ、涙で潤んでいた。
「っ……マティアス様……子ども達は……」
掠れた声で尋ねるライラに、マティアスは近くまで顔を寄せて優しく答える。
「心配いらない。リュカもシェスカも今日は熱を出していないよ」
「そうですか……申し訳ありません……」
いつもライラは『申し訳ありません』『お手を煩わせてすみません』と、朦朧とした意識の中で言う。だが、マティアスとしては笑ってくれるだけで充分だ。
六人の王妃の中で最も年下。そんなライラを他の王妃達は皆、妹のように思っている。
体のあまり強くないライラは元々、魔力循環が上手くいっていなかったのだ。そこへ双子を身ごもってしまった。
双子は昔から高い魔力を持って生まれてくると言われている。その影響で母体は魔力の循環不良を起こし、産むのにもかなりの負担を伴う。母子共に無事でお産を終えることさえ稀だと言われていた。
だが、王宮に詰めている薬学師や治療師、魔術師達は優秀だ。だから、ライラもなんとか双子を産むことができた。ただし、産後の状態は良いとは言えない。
双子自身も生まれながらに高い魔力を持つことで、それを暴走させやすく、常に命の危険に晒されている。それでも生きているのは、優秀な魔術師達やマティアスのおかげだろう。
「もうお休み。薬が効いてくるまで傍にいてやるよ」
「はい……」
こんな時は夫であるサティルが来るべきなのだが、二日に一度は倒れるような状態のライラのところには、王としての政務もあって来られない。
何より、サティルは不器用なのだ。貴族達から無理矢理あてがわれた王妃達を愛せず、愛するのはマティアスのみと宣言したこともある。だからせめて、マティアスがこうして代わりに傍にいるようにしていた。
ライラもそれで良いと笑う。王妃達と一緒にいる方が楽しいというのはライラの正直な気持ちなのだ。特にマティアスを慕っている。だからマティアスもライラが可愛くて仕方がなかった。
応援ありがとうございます!
0
お気に入りに追加
4,565
1 / 5
この作品を読んでいる人はこんな作品も読んでいます!
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる
本作については削除予定があるため、新規のレンタルはできません。
このユーザをミュートしますか?
※ミュートすると該当ユーザの「小説・投稿漫画・感想・コメント」が非表示になります。ミュートしたことは相手にはわかりません。またいつでもミュート解除できます。
※一部ミュート対象外の箇所がございます。ミュートの対象範囲についての詳細はヘルプにてご確認ください。
※ミュートしてもお気に入りやしおりは解除されません。既にお気に入りやしおりを使用している場合はすべて解除してからミュートを行うようにしてください。