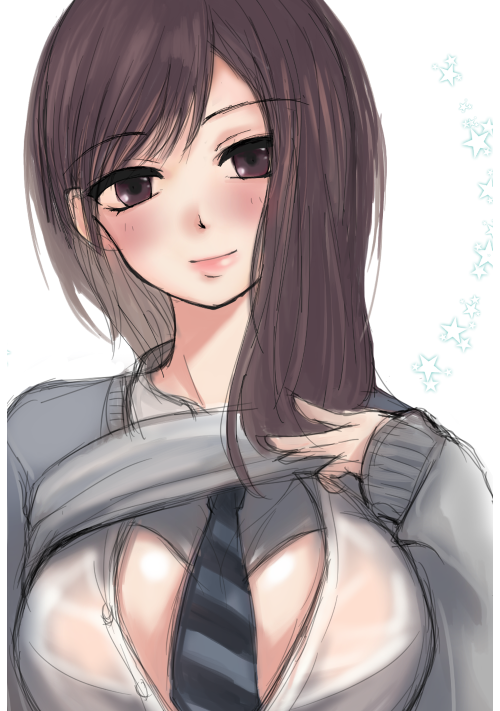99 / 449
7巻
7-3
しおりを挟む
「熱が下がったら、庭園でお茶をしような」
そう言って頭を撫でると、ほどなくして寝息が聞こえてくる。触れたところから魔力の循環を正常なものへと戻したので、先ほどよりは楽になったようだ。
「お前達も休め。しばらくは私がついている」
「はい。それでは失礼いたします」
薬学師達も連日のように対応しなくてはならないため、気の休まる時がない。少しでも時間があるならば休んでもらわなくては。
ライラと二人だけになった部屋で、マティアスは呟く。
「……すまない……」
マティアスはこの時、既に気付いていた。自身の余命があと数年もないことに。そして彼女が死ねば、ライラや双子もほどなく限界を迎えるだろう。
「お前を治したくても時間が足りない……何より世情がそれを許さない」
ライラを治療するには、エルフの持つ薬学の知識が必要だ。けれど、数年前から人族の国の多くが異種族との交流を制限していた。これにより、エルフ達は自身の知識はもちろん、薬さえ他国に流さなくなったのだ。
もちろんマティアスと親しいエルフはいるが、マティアスがいるからと言って一つの国を優遇すれば、それが火種となって戦が始まる可能性がある。たとえ友人同士であっても、それはやるべきではないとお互い理解していた。
そうした事情のせいでライラを治療する薬は手に入らない。
一方、双子の方はといえば、王家の血によるものか普通の双子より更に魔力が高く、小さな体ではすぐに魔力過剰を起こしてしまう。それを上手く外から操作し、放出してやらなくてはならない状態だ。
その技術は現在、魔術師長とマティアスにしかない。だが魔術師長は高齢で、日に何度も対応できなかった。
今のうちに他の魔術師達に技を習得させようとしても、対象となる双子と同じくらいか、それを上回る魔力を持っていないと無理なのだ。
「これも魔族に頼めば、なんとかなるかもしれんのにな……」
魔族の子ども達は総じて高い魔力を持って生まれる。それでも生存できるのは、特殊な魔導具によってこれに対処しているからだ。しかし、魔族もエルフと同じように魔導具や技術の提供をやめた。魔導具については人族に悪用されないようにと、密かに回収するほどの徹底ぶりだ。
なぜこんなことになってしまったのだろうとマティアスは考える。原因として思い当たる者達はいた。かつて交戦したことのある相手。なぜその時、始末しなかったのか。それを思うと今でも腸が煮えくり返る。
「『ブルーブラッド』……次があったなら、必ず息の根を止めてやる」
この世への未練が残りそうな予感に、マティアスは奥歯を噛みしめる。残りの人生、こうして王宮に留まっている状態では、奴らに出会える確率はほぼゼロに近い。
「フィズ」
クィーグの頭領の名を呼ぶ。すると、音もなく一つの影が部屋の隅に現れた。
「『ブルーブラッド』という組織について調べてくれ。それと、異種族を否定することは不利益でしかないという噂も流せ」
「はっ」
こんなことは、ただの付け焼き刃でしかない。それでも、民達に疑問を抱かせることができればと思う。
「……魔力操作はティアに覚えさせるか。それから、双子が六歳になったら妖精王に加護をもらうように言って……」
やれることは沢山ある。マティアスは深く穏やかな寝息を立てるライラの傍を離れ、部屋を出ていく。少しでもあがいてみせようと一歩を踏み出すのだった。
第二章 女神の手を取る者達
ティアは、新学期の初日の授業を終え、一人王宮へ忍び込んでいた。
「エル兄様の部屋は、っと」
忍び込んだとはいえ気配を完全に消しているわけでも、コソコソと泥棒よろしく静かに動いているわけでもない。気安く街を散策するような足取りだ。肩には学園街からついてきた赤い小さなドラゴンが乗っている。
《キュっ》
「うん。あっちだね。フラムも分かるんだ?」
《キュ~ゥ》
ティアがフラムと呼んだそのドラゴンは、ティアと誓約している歴とした魔獣だ。今は小さくなっているが、本当の姿は既に成体と同じで、大きな家ほどもある。
ドラゴンは本来、人族が誓約できるような魔獣ではない。だが、運命の采配とでも言うのだろうか。ティアは前世のフラムと出会い、その魂を輪廻の輪に返したのだ。
今は伯爵家の別邸で昼寝をしているであろう、ティアの相棒マティ。最強の魔獣と呼ばれるディストレアの子どもで、その子の母がフラムの前世だ。けれど、ティアと違ってフラムはそのことを覚えてはいない。
つい半年前にその事実を知ったティアは、二匹で楽しそうに遊ぶ様を見て嬉しくなるのだが、それは秘密だ。
「それにしても、なんて分かりやすい配置……仕方ない。ちょっとサービスしてやるか」
警備兵たちの気配を読みながら、王宮全体の配置を頭の中で確認する。城というのはどこもそう変わらない。どの辺りに謁見の間があり、王の執務室があるか。更に宝物庫や武器庫に至るまでが人員の配置からも推測可能なのだ。
ティアは見つかることなく歩き回る。手には大きな見取り図を持っており、非常に目立つにもかかわらず、一度として見つかりそうになることはなかった。
一時間後、見取り図に警備兵の配置の修正案を記入し終えると、タイミング良く知り合いを見つけて声をかける。
「やっほ、ビアンさん」
「っ、お嬢さん!? ど、どうしてこんな……王宮のど真ん中に……」
そこにいたのは、第二王子エルヴァストの護衛である近衛騎士のビアンだ。エルヴァストが城に戻った今、彼に張りついている必要はなく、父親である近衛隊長から多くの雑務を押しつけられているらしい。ティアとも浅からぬ縁があり、騎士らしく爽やかで気の良いお兄さんだ。
しかし、どうにもティアと話す時は困り顔が多い。
「ちょっと探検してた」
「はあ……どなたの許可で?」
「うーん、私?」
「……そうですか」
こうしたやりとりは、前世で傍にいた女騎士を思い起こさせる。
感傷に浸りそうになりながらも、ティアは用件を思い出した。
「これ、良かったらもらって」
「なんですか? ……って、城の見取り図っ!? いや、警備兵の配置図ですか!?」
ビアンが目を丸くするのも仕方がない。これを描いたティア自身、実に良くできた見取り図だと思うのだ。
「それと修正案ね。めちゃくちゃ忍び歩きしやすかったから、つい出来心で」
「出来心でやれる範疇を超えてますから! こ、これをどうしろと!?」
ビアンは動揺していた。こんなものを手渡されては怖いと言わんばかりだ。
「参考にして、配置し直せって言ってんの。私って親切でしょ?」
「その親切が怖い……って、なんでもないですっ……」
ギロリと音が聞こえるくらい睨んでやれば、ビアンは紙を素早く折り畳んで目をそらした。
今回は聞かなかったことにしてやろうと、ティアはビアンに背を向ける。
「それじゃ、私は行くね」
「えっ? ど、どちらへ?」
怖々と問いかけてくるビアンに、ティアは少しだけ振り向いて、ウィンクしながら素直に教えてやった。
「エル兄様のところと、ここの地下にね♪」
《キュキュ~》
「はい?」
混乱中のビアンを残し、ティアとフラムはまっすぐエルヴァストの部屋に向かうのだった。
やがて休憩しに帰ってきたエルヴァストを、ティアとフラムは部屋でくつろぎながら迎えた。
「あ、お疲れ様ぁ」
《キュっ》
「ティア!? それにフラムまで……」
さすがのエルヴァストも、まさか自分の部屋でティアが紅茶を淹れてくつろいでいるなどとは想像しなかったようだ。テーブルの上には、リボン付きの薬瓶が置かれている。
「まあ、こっちでお茶でも飲みなよ。特製の滋養強壮ドリンクも差し入れしとくね」
「あ、ああ……ありがとう」
一体ここはどこだったかとエルヴァストは内心首を傾げてしまう。椅子に座ると、フラムが挨拶するように肩に止まり、小さな顔をスリスリと頬に擦り付ける。
「ふっ、久しぶりだなフラム」
《キュゥ~》
甘えたがりなフラムは、皆の癒やしだ。部屋に入ってきた時のエルヴァストの表情は、ひどく疲れて強張っていたが、それが一気に解れたようだ。
「お仕事、大変みたいだね」
「え? ああ……色々と学ぶことが多い。たったひと月前までの学生生活が、もう懐かしいよ」
エルヴァストは将来、王となる兄の補佐をする立場になる。そのため、実践して学べとばかりに多くの仕事を回されているらしい。もちろん、王達の指導のもとでだ。
「そっか」
数年前まで、側妃の子である自分は王太子の身代わりでしかないと思っていたエルヴァスト。しかし、冒険者としてBランクに匹敵する実力を身につけた今、誰に言われるまでもなく、何があっても王太子を守り抜いてみせるという強い意志を持っていた。
ただ道具として利用されることを受け入れたのではない。自分自身の意思で決めた生き方だった。体と共に心も強く成長したことは、エルヴァストも実感しているようだ。
「それより、ただ私の顔を見に来ただけではないんだろう?」
ティアの淹れた熱いくらいの紅茶を飲み、体に染み込んでいくその温かさを感じながら、エルヴァストがそう尋ねてくる。今度はどんな楽しいことを思いついたのだろうと興味津々な様子が見て取れた。
こんな時、秘密にしたり誤魔化したりするのは卑怯だろう。だから、ちゃんと次の企みを口にする。
「これからここの地下を探検しようと思ってね」
「地下を? そんなところがある……のか?」
王宮の地下に王族用の脱出路などがあるのは定番だ。だが、エルヴァストの記憶の中にはなかったようだ。
「さっきから地下の気配を探ってみてたんだけど、結構怪しい臭いがするね。入り口は宝物庫の隣かなって思ってるんだけど……どうです?」
ドアの方に目を向けて問いかけるティア。そこに誰がいるのか、エルヴァストも気配で分かったようだ。
「……母上?」
ゆっくりとドアを開けて入ってきたのは、エルヴァストの母エイミールだった。
ビアンから、ティアが地下に行こうとしていると聞いたエイミールは、王の許可を取って仕事を抜け出してきたらしい。普段と変わらない王妃付きのメイド服を着用している。
元々メイドとして王宮に上がった彼女は、自ら進んで王妃の影武者となった。王に見初められて側妃となった後も、メイド服を着て王妃の傍に控えているのだ。
「どちらで地下の情報を?」
「知り合いから聞いた、って言っておきます」
「そうですか……」
王家がクィーグ一族のことを把握しているかどうかは微妙だ。シルから聞いた話では、未だ森で隠れ暮らしているらしいので、王家の方から聞かれない限り言うべきではないだろう。
ただ、メイドでありながら隠密行動も取れるらしいエイミールならば、クィーグ一族のことも知っているかもしれない。
そう思ったティアが曖昧な答えを返すと、エイミールは何かを決意した表情で告げた。
「では、ご案内いたします」
「え、いいの?」
まさか協力してくれるとは思っていなかった。そこへ、エルヴァストが申し出る。
「私も行く。よろしいでしょうか、母上」
「……」
この二人の互いへの接し方はとても拙く硬い。だが、エイミールがエルヴァストを大切に思っているのをティアは知っている。エイミールと友人として付き合いのあるティアの父母や、メイドとしての技術を直接指導した家令のリジットから聞いているのだ。
エイミールはエルヴァストに強くあって欲しいと考えていた。王宮では様々な人々が勝手な憶測で心ない言葉を口にする。それに負けないよう、不当な扱いをもはね除けられる強さを身につけて欲しいと願い、時に冷たくあしらっていた。
そんな思いを知らないのはエルヴァストだけ。お互いを理解するためには、少しでも一緒にいられる時間を作ることが必要だろう。だからティアもエルヴァストに加勢する。
「いいよね、エイミールさん」
「……いいでしょう」
渋々といった様子ではあるが、許可をもらえたので良しとする。エルヴァストもほっとしているのが分かった。
エイミールの案内で部屋を出て、ティアが予想した通り宝物庫の傍まで来た。その横に隠し扉があり、一人ずつ中に入っていく。
暗くて狭い通路をエイミールについて進む。少なくとも脱出用の通路ではなさそうだ。脱出用ならば外へ向かうはずが、王宮の中央へと向かっているのだから。
「この先に、一部の者しか知らない特別な部屋があるのです」
「そんなところが?」
エルヴァストは、初めて知る王宮の裏通路に興奮しきりだ。
しばらく歩いていると、床が傾斜になっているのを感じた。どうやら、緩やかに地下へ入っているようだ。
「この辺り……もしかして離宮?」
離宮の下に繋がっているのではないかとティアは見当を付ける。そこで、いつの間にか高くなった天井に、ふと違和感を覚えた。
灯りが届かないその天井に、何かの模様が見えたのだ。
「あの模様は災厄除けの……まさかっ」
「どうしたんだ?」
ティアは、その模様を知っている。それは、かつて多くの国の王宮にあった隔離部屋への入り口の印。魔術の影響を受けないための結界のようなものだ。
「あれでお気付きになられるとは……ここは、王宮に生まれた双子を禍とならぬように封じるための離宮です」
「双子がいるのっ?」
目の前に迫った扉は、冷たい印象のある黒くて大きな扉だ。それに手をかけたエイミールは、苦々しげに顔を歪めて言った。
「はい……ご存じかもしれませんが、王族の子どもは七つの祝福の儀を受けるまで公にされることはありません」
「あ……」
エルヴァストが小さな声を漏らす。双子が生まれたことは耳にしていた。だが、まだ幼い弟達の存在を知っているのは王族と一部の貴族達だけだ。
生まれたと聞いた時、同時に王位継承順位についても聞かされた。側妃の子である自分よりも王妃の子である弟達の方が上であると。それを聞いた時の衝撃は今でも胸に残っている。
しかし、エルヴァストは一度としてその存在を目にしたことがなかった。エルヴァスト自身は七つになる前に兄王子と対面していたというのにだ。
ゆっくりと押し開かれた扉の中には、地下とは思えないほど明るい部屋がある。
「あちらが、第一王女のイルーシュ様と第三王子のカイラント様です」
二人の子どもが身を寄せ合い、ソファーに埋もれながらこちらを不安げに見ていた。
天蓋付きの大きなベッドに、沢山の玩具とぬいぐるみ。
天井から吊るされた飾りも可愛らしく、見た目はただの楽しそうな子ども部屋でしかなかった。
「双子……」
お人形のように肩まで伸びたストレートの金髪。片方はそれをツインテールにしている。まだ幼い二人の子どもは、手を取り合って縮こまっていた。
「イルーシュ様、カイラント様。お父上とお母上のご友人であるティア様です。それと……私の息子であるエルヴァストです」
「「……」」
不安げなその表情をよく見れば、向かって右側にいる子どもは目の色が濃い緑色をした男の子。左の子どもの目は薄い緑色で、髪がツインテールになっていることから女の子だろう。
そういえば王妃の瞳の色も、母シアンや兄ベリアローズのように美しい緑色をしていたなとティアは思い出す。
「ここには、王様や王妃様が来ることもあるの?」
「王室規定により、会うことはかないません」
「そう……はぁぁぁ。こればっかりは本当、なんでちゃんと対処しなかったのかって、すっごく後悔してるよ」
「ティア様?」
《キュキュ?》
ティアは大きなため息を吐きながら、頭を抱えて屈み込む。それから小さく呟いた。
「……ごめんね、リュカ、シェスカ……ライラ様」
「おい、ティア?」
弟達との初対面に驚いていたはずのエルヴァストまで、心配そうに声をかけてくる。
「あぁぁぁぁぁっ、もうっ!」
「っ!?」
ティアは何もかもを吐き出すように大きく叫んで立ち上がると、スタスタと双子に近付く。
びくりと身をすくませて、警戒する子猫のように縮こまる二人に、手を差し出した。
「さっさと出るよっ」
「「……」」
固く結ばれた二人の口元を見て、ティアは顔を顰める。それから強引に手を取った。
「冷たい手だなぁ……ん? これってまさか」
「どうされました?」
手を取ったまま、ティアはまた屈み込む。脱力して、思わずといった感じだ。
「エイミールさん、この子達の声を聞いたことは?」
「え? ……あ、いえ。それが一度もないのです」
「やっぱり、これだけの魔力を持ってると、そうなるか……」
ティアには感じられた。この二人の魔力は、王宮の魔術師長クラスにも匹敵すると。
「今、何歳?」
「あの、王子達は……」
エイミールが答える前に、ティアには二つの声が聞こえてくる。
((ろく……))
「そっか。六歳か」
((うん))
「ティア様? なぜお判りに?」
エイミールは、驚きに目を見開いている。それも当然だ。彼女は王子達の年齢を伝えていないのだから。それなのに、なぜかティアには分かったのだ。
「ちゃんとこの子達から聞いた」
「え? ですが、王子達は言葉を……」
エイミールだけではない。エルヴァストにもそんな言葉は聞こえなかったし、双子が今まで声を出したことがないのは確かだった。
「話せるよ。ただ、この子達は念話で話してる」
「念話?」
二人の魔力は大きい。それを持て余し、声を出す代わりに念話で会話するようになってしまったのだろう。彼らにとっては、声に出すよりもその方が容易だったのだ。
「それは、マティが話すのと同じってことか?」
そう尋ねたのはエルヴァストだ。エイミールもマティの存在は知っているが、喋るという認識はない。
「そう。双子って、魔力が強い子が多いんだ。うちにいるマクレート家の双子もそう。中には、体に支障をきたすくらい強い子達もいる。そうなると、こうやって精霊さえ入れない場所に閉じ込められている子達は、魔力を持て余して、弱って死んでしまうこともある」
「そんなっ。王子達はっ」
命の危険があると聞き、エイミールは居ても立っても居られないようだ。そんな彼女を安心させるために、ティアは二人の状態を繋いだ手から感じ取る。
「大丈夫。この子達は上手くコントロールできてる。できてなかったら、今頃ここにいないよ。こういうのは、たいてい三つまでに決まるんだ」
((できてる))
「そうだね」
ティアは手をゆっくりと離して、笑みを浮かべながら二人の頭を撫でた。
「念話ができるのなら、なぜ今まで母上には聞こえなかったんだ?」
エルヴァストは、マティの例を知っているからこそ不思議に思ったのだろう。マティの声は、誰にでも聞こえる。
「魔力の波長を合わせないと聞こえないんだよ。マティはあれで、全部の人の波長に合うように魔力を調整してるんだ。でも、この子達はそこまでできない」
((できない?))
「できるようにはなるけど、それよりも声を出そうか」
((こえ?))
揃って首を傾げる様子は、とても愛らしい。
「だから、ここから出よう」
((でる?))
「ティア様? いけませんっ。王室を危険に晒すことは……」
「危険なんてないよ」
((きけん~))
その言葉の響きが気に入ったらしい。二人は無邪気に手を取り合って揺れていた。
「あのね、エイミールさん。そもそも双子が禍を呼ぶなんて、不幸な偶然が重なったことで生まれた迷信でしかないんだよ」
「え……」
だからこそ、あの頃、正しい事実を広めていれば良かった。それはティアにとって、とても大きな後悔なのだ。弟妹達が早くに亡くなってしまったことで、その意義をティアは見いだせなくなった。けれど、やるべきだったのだ。その後に生まれてくる子ども達のために。
「本当に?」
王妃の影武者として生きるエイミールにとって、王妃は大切な主人であり、王は自分の夫でもある。王太子レイナルートとエルヴァストのことも守りたいと思っていた。だからこそ、イルーシュとカイラントが王室規定で幽閉されていても、助け出そうとは思えなかった。王家が危険に晒されることだけは絶対に避けたかったからだ。
「エイミールさんは心配性だよね。ねぇ、仮に何か良くないことが起こるとして、王家にどんな禍があると思う?」
「えっ?」
エイミールが息を呑む。ティアは振り返り、少し意地の悪い笑みを浮かべた。
「ねぇ、どんなことだとエイミールさんは思う?」
今、エイミールの頭の中では様々な思考が渦巻いているのだろう。顔色が悪い気がする。
長い沈黙が続くと、エルヴァストが珍しく苦言を呈した。
「ティア、母上をからかうのは……」
王家を守ろうとするエイミールの気持ちが、エルヴァストには痛いほど分かっているのだ。
「はいはい。ちゃんと説明するよ」
ティアは大袈裟に肩をすくめてみせると、未だにどんな顔をしたらいいのか分からないといった様子のエイミールに、迷信が生まれた理由を説明した。
「双子が生まれると、王家にとって不幸なことが起きる確率が高いんだ。だから、禍を招くって言われるようになったの」
「不幸……」
((ふこぉ?))
イルーシュとカイラントは不思議そうにティアを見上げていた。そんな二人に安心しろと笑みを向け、ティアは再び口を開く。
「双子の出産には、母子共に命の危険が伴う。双子の出生率が低いのはそのせい。昔はね、王家が今より小さかったし、王様はちゃんと自分が愛した女の人と結婚してた。そんな王様にとって、王妃の死は辛いものでしょ? もし王妃が無事だったとしても、生まれるはずの子どもが生まれなかったら、それはそれでショックだよね」
どちらが死んでも、王家に影が落ちる。王妃が死ねば、王はその原因である子どもに会いたいと思えなくなるだろう。それが転じて、無事に生まれた子ども達をも遠ざけるべきだと言われるようになった。そしていつしか、王家の双子は不幸を呼ぶと囁かれるようになったのだ。
そう言って頭を撫でると、ほどなくして寝息が聞こえてくる。触れたところから魔力の循環を正常なものへと戻したので、先ほどよりは楽になったようだ。
「お前達も休め。しばらくは私がついている」
「はい。それでは失礼いたします」
薬学師達も連日のように対応しなくてはならないため、気の休まる時がない。少しでも時間があるならば休んでもらわなくては。
ライラと二人だけになった部屋で、マティアスは呟く。
「……すまない……」
マティアスはこの時、既に気付いていた。自身の余命があと数年もないことに。そして彼女が死ねば、ライラや双子もほどなく限界を迎えるだろう。
「お前を治したくても時間が足りない……何より世情がそれを許さない」
ライラを治療するには、エルフの持つ薬学の知識が必要だ。けれど、数年前から人族の国の多くが異種族との交流を制限していた。これにより、エルフ達は自身の知識はもちろん、薬さえ他国に流さなくなったのだ。
もちろんマティアスと親しいエルフはいるが、マティアスがいるからと言って一つの国を優遇すれば、それが火種となって戦が始まる可能性がある。たとえ友人同士であっても、それはやるべきではないとお互い理解していた。
そうした事情のせいでライラを治療する薬は手に入らない。
一方、双子の方はといえば、王家の血によるものか普通の双子より更に魔力が高く、小さな体ではすぐに魔力過剰を起こしてしまう。それを上手く外から操作し、放出してやらなくてはならない状態だ。
その技術は現在、魔術師長とマティアスにしかない。だが魔術師長は高齢で、日に何度も対応できなかった。
今のうちに他の魔術師達に技を習得させようとしても、対象となる双子と同じくらいか、それを上回る魔力を持っていないと無理なのだ。
「これも魔族に頼めば、なんとかなるかもしれんのにな……」
魔族の子ども達は総じて高い魔力を持って生まれる。それでも生存できるのは、特殊な魔導具によってこれに対処しているからだ。しかし、魔族もエルフと同じように魔導具や技術の提供をやめた。魔導具については人族に悪用されないようにと、密かに回収するほどの徹底ぶりだ。
なぜこんなことになってしまったのだろうとマティアスは考える。原因として思い当たる者達はいた。かつて交戦したことのある相手。なぜその時、始末しなかったのか。それを思うと今でも腸が煮えくり返る。
「『ブルーブラッド』……次があったなら、必ず息の根を止めてやる」
この世への未練が残りそうな予感に、マティアスは奥歯を噛みしめる。残りの人生、こうして王宮に留まっている状態では、奴らに出会える確率はほぼゼロに近い。
「フィズ」
クィーグの頭領の名を呼ぶ。すると、音もなく一つの影が部屋の隅に現れた。
「『ブルーブラッド』という組織について調べてくれ。それと、異種族を否定することは不利益でしかないという噂も流せ」
「はっ」
こんなことは、ただの付け焼き刃でしかない。それでも、民達に疑問を抱かせることができればと思う。
「……魔力操作はティアに覚えさせるか。それから、双子が六歳になったら妖精王に加護をもらうように言って……」
やれることは沢山ある。マティアスは深く穏やかな寝息を立てるライラの傍を離れ、部屋を出ていく。少しでもあがいてみせようと一歩を踏み出すのだった。
第二章 女神の手を取る者達
ティアは、新学期の初日の授業を終え、一人王宮へ忍び込んでいた。
「エル兄様の部屋は、っと」
忍び込んだとはいえ気配を完全に消しているわけでも、コソコソと泥棒よろしく静かに動いているわけでもない。気安く街を散策するような足取りだ。肩には学園街からついてきた赤い小さなドラゴンが乗っている。
《キュっ》
「うん。あっちだね。フラムも分かるんだ?」
《キュ~ゥ》
ティアがフラムと呼んだそのドラゴンは、ティアと誓約している歴とした魔獣だ。今は小さくなっているが、本当の姿は既に成体と同じで、大きな家ほどもある。
ドラゴンは本来、人族が誓約できるような魔獣ではない。だが、運命の采配とでも言うのだろうか。ティアは前世のフラムと出会い、その魂を輪廻の輪に返したのだ。
今は伯爵家の別邸で昼寝をしているであろう、ティアの相棒マティ。最強の魔獣と呼ばれるディストレアの子どもで、その子の母がフラムの前世だ。けれど、ティアと違ってフラムはそのことを覚えてはいない。
つい半年前にその事実を知ったティアは、二匹で楽しそうに遊ぶ様を見て嬉しくなるのだが、それは秘密だ。
「それにしても、なんて分かりやすい配置……仕方ない。ちょっとサービスしてやるか」
警備兵たちの気配を読みながら、王宮全体の配置を頭の中で確認する。城というのはどこもそう変わらない。どの辺りに謁見の間があり、王の執務室があるか。更に宝物庫や武器庫に至るまでが人員の配置からも推測可能なのだ。
ティアは見つかることなく歩き回る。手には大きな見取り図を持っており、非常に目立つにもかかわらず、一度として見つかりそうになることはなかった。
一時間後、見取り図に警備兵の配置の修正案を記入し終えると、タイミング良く知り合いを見つけて声をかける。
「やっほ、ビアンさん」
「っ、お嬢さん!? ど、どうしてこんな……王宮のど真ん中に……」
そこにいたのは、第二王子エルヴァストの護衛である近衛騎士のビアンだ。エルヴァストが城に戻った今、彼に張りついている必要はなく、父親である近衛隊長から多くの雑務を押しつけられているらしい。ティアとも浅からぬ縁があり、騎士らしく爽やかで気の良いお兄さんだ。
しかし、どうにもティアと話す時は困り顔が多い。
「ちょっと探検してた」
「はあ……どなたの許可で?」
「うーん、私?」
「……そうですか」
こうしたやりとりは、前世で傍にいた女騎士を思い起こさせる。
感傷に浸りそうになりながらも、ティアは用件を思い出した。
「これ、良かったらもらって」
「なんですか? ……って、城の見取り図っ!? いや、警備兵の配置図ですか!?」
ビアンが目を丸くするのも仕方がない。これを描いたティア自身、実に良くできた見取り図だと思うのだ。
「それと修正案ね。めちゃくちゃ忍び歩きしやすかったから、つい出来心で」
「出来心でやれる範疇を超えてますから! こ、これをどうしろと!?」
ビアンは動揺していた。こんなものを手渡されては怖いと言わんばかりだ。
「参考にして、配置し直せって言ってんの。私って親切でしょ?」
「その親切が怖い……って、なんでもないですっ……」
ギロリと音が聞こえるくらい睨んでやれば、ビアンは紙を素早く折り畳んで目をそらした。
今回は聞かなかったことにしてやろうと、ティアはビアンに背を向ける。
「それじゃ、私は行くね」
「えっ? ど、どちらへ?」
怖々と問いかけてくるビアンに、ティアは少しだけ振り向いて、ウィンクしながら素直に教えてやった。
「エル兄様のところと、ここの地下にね♪」
《キュキュ~》
「はい?」
混乱中のビアンを残し、ティアとフラムはまっすぐエルヴァストの部屋に向かうのだった。
やがて休憩しに帰ってきたエルヴァストを、ティアとフラムは部屋でくつろぎながら迎えた。
「あ、お疲れ様ぁ」
《キュっ》
「ティア!? それにフラムまで……」
さすがのエルヴァストも、まさか自分の部屋でティアが紅茶を淹れてくつろいでいるなどとは想像しなかったようだ。テーブルの上には、リボン付きの薬瓶が置かれている。
「まあ、こっちでお茶でも飲みなよ。特製の滋養強壮ドリンクも差し入れしとくね」
「あ、ああ……ありがとう」
一体ここはどこだったかとエルヴァストは内心首を傾げてしまう。椅子に座ると、フラムが挨拶するように肩に止まり、小さな顔をスリスリと頬に擦り付ける。
「ふっ、久しぶりだなフラム」
《キュゥ~》
甘えたがりなフラムは、皆の癒やしだ。部屋に入ってきた時のエルヴァストの表情は、ひどく疲れて強張っていたが、それが一気に解れたようだ。
「お仕事、大変みたいだね」
「え? ああ……色々と学ぶことが多い。たったひと月前までの学生生活が、もう懐かしいよ」
エルヴァストは将来、王となる兄の補佐をする立場になる。そのため、実践して学べとばかりに多くの仕事を回されているらしい。もちろん、王達の指導のもとでだ。
「そっか」
数年前まで、側妃の子である自分は王太子の身代わりでしかないと思っていたエルヴァスト。しかし、冒険者としてBランクに匹敵する実力を身につけた今、誰に言われるまでもなく、何があっても王太子を守り抜いてみせるという強い意志を持っていた。
ただ道具として利用されることを受け入れたのではない。自分自身の意思で決めた生き方だった。体と共に心も強く成長したことは、エルヴァストも実感しているようだ。
「それより、ただ私の顔を見に来ただけではないんだろう?」
ティアの淹れた熱いくらいの紅茶を飲み、体に染み込んでいくその温かさを感じながら、エルヴァストがそう尋ねてくる。今度はどんな楽しいことを思いついたのだろうと興味津々な様子が見て取れた。
こんな時、秘密にしたり誤魔化したりするのは卑怯だろう。だから、ちゃんと次の企みを口にする。
「これからここの地下を探検しようと思ってね」
「地下を? そんなところがある……のか?」
王宮の地下に王族用の脱出路などがあるのは定番だ。だが、エルヴァストの記憶の中にはなかったようだ。
「さっきから地下の気配を探ってみてたんだけど、結構怪しい臭いがするね。入り口は宝物庫の隣かなって思ってるんだけど……どうです?」
ドアの方に目を向けて問いかけるティア。そこに誰がいるのか、エルヴァストも気配で分かったようだ。
「……母上?」
ゆっくりとドアを開けて入ってきたのは、エルヴァストの母エイミールだった。
ビアンから、ティアが地下に行こうとしていると聞いたエイミールは、王の許可を取って仕事を抜け出してきたらしい。普段と変わらない王妃付きのメイド服を着用している。
元々メイドとして王宮に上がった彼女は、自ら進んで王妃の影武者となった。王に見初められて側妃となった後も、メイド服を着て王妃の傍に控えているのだ。
「どちらで地下の情報を?」
「知り合いから聞いた、って言っておきます」
「そうですか……」
王家がクィーグ一族のことを把握しているかどうかは微妙だ。シルから聞いた話では、未だ森で隠れ暮らしているらしいので、王家の方から聞かれない限り言うべきではないだろう。
ただ、メイドでありながら隠密行動も取れるらしいエイミールならば、クィーグ一族のことも知っているかもしれない。
そう思ったティアが曖昧な答えを返すと、エイミールは何かを決意した表情で告げた。
「では、ご案内いたします」
「え、いいの?」
まさか協力してくれるとは思っていなかった。そこへ、エルヴァストが申し出る。
「私も行く。よろしいでしょうか、母上」
「……」
この二人の互いへの接し方はとても拙く硬い。だが、エイミールがエルヴァストを大切に思っているのをティアは知っている。エイミールと友人として付き合いのあるティアの父母や、メイドとしての技術を直接指導した家令のリジットから聞いているのだ。
エイミールはエルヴァストに強くあって欲しいと考えていた。王宮では様々な人々が勝手な憶測で心ない言葉を口にする。それに負けないよう、不当な扱いをもはね除けられる強さを身につけて欲しいと願い、時に冷たくあしらっていた。
そんな思いを知らないのはエルヴァストだけ。お互いを理解するためには、少しでも一緒にいられる時間を作ることが必要だろう。だからティアもエルヴァストに加勢する。
「いいよね、エイミールさん」
「……いいでしょう」
渋々といった様子ではあるが、許可をもらえたので良しとする。エルヴァストもほっとしているのが分かった。
エイミールの案内で部屋を出て、ティアが予想した通り宝物庫の傍まで来た。その横に隠し扉があり、一人ずつ中に入っていく。
暗くて狭い通路をエイミールについて進む。少なくとも脱出用の通路ではなさそうだ。脱出用ならば外へ向かうはずが、王宮の中央へと向かっているのだから。
「この先に、一部の者しか知らない特別な部屋があるのです」
「そんなところが?」
エルヴァストは、初めて知る王宮の裏通路に興奮しきりだ。
しばらく歩いていると、床が傾斜になっているのを感じた。どうやら、緩やかに地下へ入っているようだ。
「この辺り……もしかして離宮?」
離宮の下に繋がっているのではないかとティアは見当を付ける。そこで、いつの間にか高くなった天井に、ふと違和感を覚えた。
灯りが届かないその天井に、何かの模様が見えたのだ。
「あの模様は災厄除けの……まさかっ」
「どうしたんだ?」
ティアは、その模様を知っている。それは、かつて多くの国の王宮にあった隔離部屋への入り口の印。魔術の影響を受けないための結界のようなものだ。
「あれでお気付きになられるとは……ここは、王宮に生まれた双子を禍とならぬように封じるための離宮です」
「双子がいるのっ?」
目の前に迫った扉は、冷たい印象のある黒くて大きな扉だ。それに手をかけたエイミールは、苦々しげに顔を歪めて言った。
「はい……ご存じかもしれませんが、王族の子どもは七つの祝福の儀を受けるまで公にされることはありません」
「あ……」
エルヴァストが小さな声を漏らす。双子が生まれたことは耳にしていた。だが、まだ幼い弟達の存在を知っているのは王族と一部の貴族達だけだ。
生まれたと聞いた時、同時に王位継承順位についても聞かされた。側妃の子である自分よりも王妃の子である弟達の方が上であると。それを聞いた時の衝撃は今でも胸に残っている。
しかし、エルヴァストは一度としてその存在を目にしたことがなかった。エルヴァスト自身は七つになる前に兄王子と対面していたというのにだ。
ゆっくりと押し開かれた扉の中には、地下とは思えないほど明るい部屋がある。
「あちらが、第一王女のイルーシュ様と第三王子のカイラント様です」
二人の子どもが身を寄せ合い、ソファーに埋もれながらこちらを不安げに見ていた。
天蓋付きの大きなベッドに、沢山の玩具とぬいぐるみ。
天井から吊るされた飾りも可愛らしく、見た目はただの楽しそうな子ども部屋でしかなかった。
「双子……」
お人形のように肩まで伸びたストレートの金髪。片方はそれをツインテールにしている。まだ幼い二人の子どもは、手を取り合って縮こまっていた。
「イルーシュ様、カイラント様。お父上とお母上のご友人であるティア様です。それと……私の息子であるエルヴァストです」
「「……」」
不安げなその表情をよく見れば、向かって右側にいる子どもは目の色が濃い緑色をした男の子。左の子どもの目は薄い緑色で、髪がツインテールになっていることから女の子だろう。
そういえば王妃の瞳の色も、母シアンや兄ベリアローズのように美しい緑色をしていたなとティアは思い出す。
「ここには、王様や王妃様が来ることもあるの?」
「王室規定により、会うことはかないません」
「そう……はぁぁぁ。こればっかりは本当、なんでちゃんと対処しなかったのかって、すっごく後悔してるよ」
「ティア様?」
《キュキュ?》
ティアは大きなため息を吐きながら、頭を抱えて屈み込む。それから小さく呟いた。
「……ごめんね、リュカ、シェスカ……ライラ様」
「おい、ティア?」
弟達との初対面に驚いていたはずのエルヴァストまで、心配そうに声をかけてくる。
「あぁぁぁぁぁっ、もうっ!」
「っ!?」
ティアは何もかもを吐き出すように大きく叫んで立ち上がると、スタスタと双子に近付く。
びくりと身をすくませて、警戒する子猫のように縮こまる二人に、手を差し出した。
「さっさと出るよっ」
「「……」」
固く結ばれた二人の口元を見て、ティアは顔を顰める。それから強引に手を取った。
「冷たい手だなぁ……ん? これってまさか」
「どうされました?」
手を取ったまま、ティアはまた屈み込む。脱力して、思わずといった感じだ。
「エイミールさん、この子達の声を聞いたことは?」
「え? ……あ、いえ。それが一度もないのです」
「やっぱり、これだけの魔力を持ってると、そうなるか……」
ティアには感じられた。この二人の魔力は、王宮の魔術師長クラスにも匹敵すると。
「今、何歳?」
「あの、王子達は……」
エイミールが答える前に、ティアには二つの声が聞こえてくる。
((ろく……))
「そっか。六歳か」
((うん))
「ティア様? なぜお判りに?」
エイミールは、驚きに目を見開いている。それも当然だ。彼女は王子達の年齢を伝えていないのだから。それなのに、なぜかティアには分かったのだ。
「ちゃんとこの子達から聞いた」
「え? ですが、王子達は言葉を……」
エイミールだけではない。エルヴァストにもそんな言葉は聞こえなかったし、双子が今まで声を出したことがないのは確かだった。
「話せるよ。ただ、この子達は念話で話してる」
「念話?」
二人の魔力は大きい。それを持て余し、声を出す代わりに念話で会話するようになってしまったのだろう。彼らにとっては、声に出すよりもその方が容易だったのだ。
「それは、マティが話すのと同じってことか?」
そう尋ねたのはエルヴァストだ。エイミールもマティの存在は知っているが、喋るという認識はない。
「そう。双子って、魔力が強い子が多いんだ。うちにいるマクレート家の双子もそう。中には、体に支障をきたすくらい強い子達もいる。そうなると、こうやって精霊さえ入れない場所に閉じ込められている子達は、魔力を持て余して、弱って死んでしまうこともある」
「そんなっ。王子達はっ」
命の危険があると聞き、エイミールは居ても立っても居られないようだ。そんな彼女を安心させるために、ティアは二人の状態を繋いだ手から感じ取る。
「大丈夫。この子達は上手くコントロールできてる。できてなかったら、今頃ここにいないよ。こういうのは、たいてい三つまでに決まるんだ」
((できてる))
「そうだね」
ティアは手をゆっくりと離して、笑みを浮かべながら二人の頭を撫でた。
「念話ができるのなら、なぜ今まで母上には聞こえなかったんだ?」
エルヴァストは、マティの例を知っているからこそ不思議に思ったのだろう。マティの声は、誰にでも聞こえる。
「魔力の波長を合わせないと聞こえないんだよ。マティはあれで、全部の人の波長に合うように魔力を調整してるんだ。でも、この子達はそこまでできない」
((できない?))
「できるようにはなるけど、それよりも声を出そうか」
((こえ?))
揃って首を傾げる様子は、とても愛らしい。
「だから、ここから出よう」
((でる?))
「ティア様? いけませんっ。王室を危険に晒すことは……」
「危険なんてないよ」
((きけん~))
その言葉の響きが気に入ったらしい。二人は無邪気に手を取り合って揺れていた。
「あのね、エイミールさん。そもそも双子が禍を呼ぶなんて、不幸な偶然が重なったことで生まれた迷信でしかないんだよ」
「え……」
だからこそ、あの頃、正しい事実を広めていれば良かった。それはティアにとって、とても大きな後悔なのだ。弟妹達が早くに亡くなってしまったことで、その意義をティアは見いだせなくなった。けれど、やるべきだったのだ。その後に生まれてくる子ども達のために。
「本当に?」
王妃の影武者として生きるエイミールにとって、王妃は大切な主人であり、王は自分の夫でもある。王太子レイナルートとエルヴァストのことも守りたいと思っていた。だからこそ、イルーシュとカイラントが王室規定で幽閉されていても、助け出そうとは思えなかった。王家が危険に晒されることだけは絶対に避けたかったからだ。
「エイミールさんは心配性だよね。ねぇ、仮に何か良くないことが起こるとして、王家にどんな禍があると思う?」
「えっ?」
エイミールが息を呑む。ティアは振り返り、少し意地の悪い笑みを浮かべた。
「ねぇ、どんなことだとエイミールさんは思う?」
今、エイミールの頭の中では様々な思考が渦巻いているのだろう。顔色が悪い気がする。
長い沈黙が続くと、エルヴァストが珍しく苦言を呈した。
「ティア、母上をからかうのは……」
王家を守ろうとするエイミールの気持ちが、エルヴァストには痛いほど分かっているのだ。
「はいはい。ちゃんと説明するよ」
ティアは大袈裟に肩をすくめてみせると、未だにどんな顔をしたらいいのか分からないといった様子のエイミールに、迷信が生まれた理由を説明した。
「双子が生まれると、王家にとって不幸なことが起きる確率が高いんだ。だから、禍を招くって言われるようになったの」
「不幸……」
((ふこぉ?))
イルーシュとカイラントは不思議そうにティアを見上げていた。そんな二人に安心しろと笑みを向け、ティアは再び口を開く。
「双子の出産には、母子共に命の危険が伴う。双子の出生率が低いのはそのせい。昔はね、王家が今より小さかったし、王様はちゃんと自分が愛した女の人と結婚してた。そんな王様にとって、王妃の死は辛いものでしょ? もし王妃が無事だったとしても、生まれるはずの子どもが生まれなかったら、それはそれでショックだよね」
どちらが死んでも、王家に影が落ちる。王妃が死ねば、王はその原因である子どもに会いたいと思えなくなるだろう。それが転じて、無事に生まれた子ども達をも遠ざけるべきだと言われるようになった。そしていつしか、王家の双子は不幸を呼ぶと囁かれるようになったのだ。
応援ありがとうございます!
0
お気に入りに追加
4,565
1 / 5
この作品を読んでいる人はこんな作品も読んでいます!
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる
本作については削除予定があるため、新規のレンタルはできません。
このユーザをミュートしますか?
※ミュートすると該当ユーザの「小説・投稿漫画・感想・コメント」が非表示になります。ミュートしたことは相手にはわかりません。またいつでもミュート解除できます。
※一部ミュート対象外の箇所がございます。ミュートの対象範囲についての詳細はヘルプにてご確認ください。
※ミュートしてもお気に入りやしおりは解除されません。既にお気に入りやしおりを使用している場合はすべて解除してからミュートを行うようにしてください。