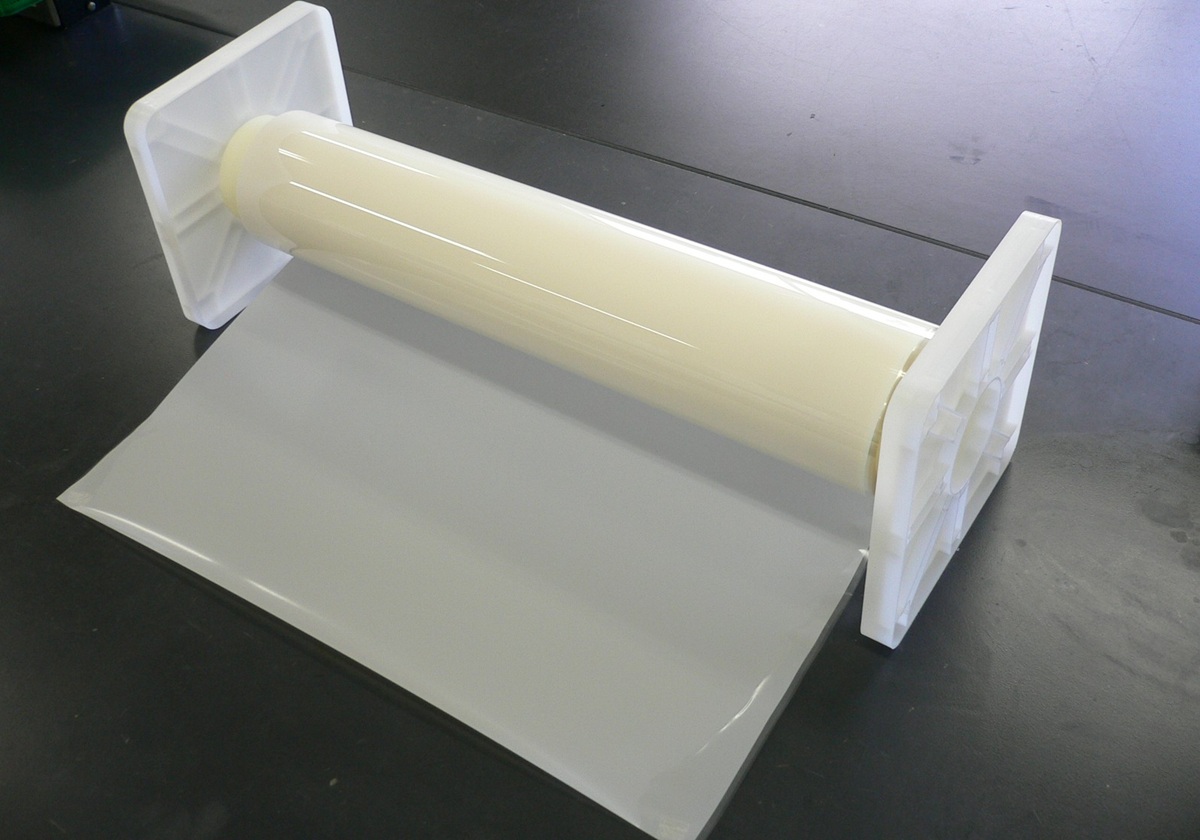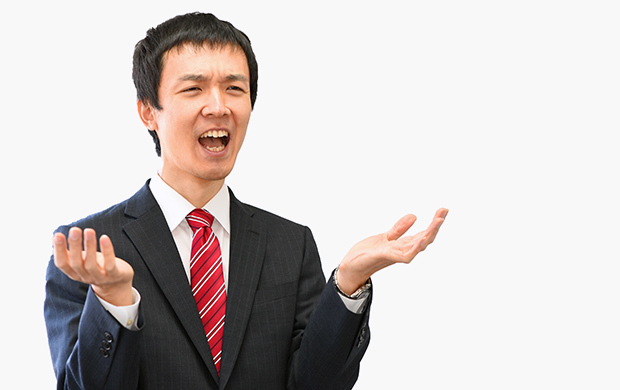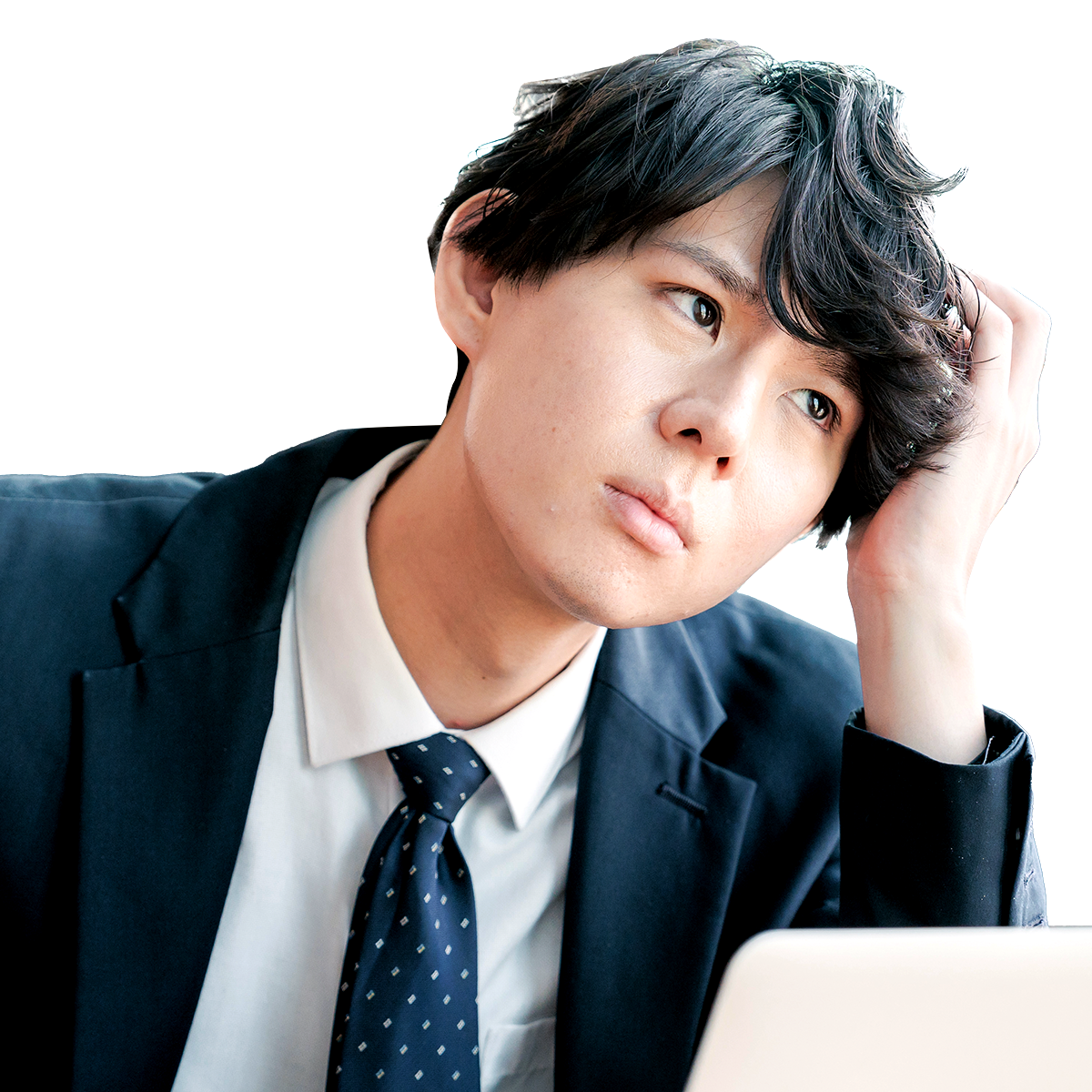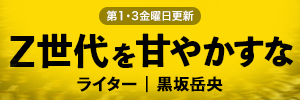すき家、コロナでも売上“増”の謎…吉野家はダメージ小、松屋は大、明暗分かれた理由
2020.09.07
ビジネスジャーナル

新型コロナウイルス流行の影響により、飲食業界各社が苦境に立たされているが、テイクアウト需要も高そうな大手牛丼チェーンの「吉野家」「すき家」「松屋」、いわゆる“牛丼御三家”も例外ではないようだ。
まず直近3カ月の既存店売上高の前年同月比を見てみよう。
【吉野家】
・5月:7.3%減
・6月:12.3%減
・7月:5.7%減
【すき家】
・5月:9.2%減
・6月:8.7%減
・7月:2.7%増
【松屋(松屋フーズ)】
・5月:23.2%減
・6月:16.8%減
・7月:11.6%減
すき家は7月に前年の売上高を上回り復調の兆しを見せているものの、吉野家と松屋は前年割れ続き。特に松屋に至っては、毎月2桁以上の減と悲惨な結果となっている。
また、吉野家グループは業績悪化を受け、今年度中に国内外のグループ店舗約3300店のうち、最大150店を閉店すると発表している。国内の吉野家の閉店予定は40店舗とされているが、いずれにしても普段利用している店舗が閉店の憂き目にあう可能性もあるということだ。
新型コロナの影響で大きなダメージを受けている牛丼チェーンだが、新型コロナ第二波、第三波以降にどう対応していけばいいのだろうか。フードアナリストの重盛高雄氏に解説してもらう。
牛丼御三家、コロナ流行以前からの近年の取り組み
最初に吉野家、すき家、松屋の近年の戦略を振り返ってみよう。重盛氏によると、「新型コロナ流行以前から各社の取り組みは、それぞれ差別化が図られている」という。
「吉野家は客層を広げていこうという戦略が見受けられますね。例えば器の大きさの変更や、子供向けにポケモンとコラボした『ポケ盛』といった牛丼メニューの開発などを行っています。また一部店舗では若い女性でも入りやすいように、向かいの客と視線が合いにくいような形にカウンターを設計するといった取り組みも進めていますね。
松屋でも新しい客層を呼び込むために、テーブルの非対面と対面の部分を臨機応変に分けて工夫しています。ちなみに以前からそうでしたが、今のご時世を考えると、松屋の食券システムは店員がお金に直接触れる必要がないので、結果的に時代に合ったスタイルとなっているといえるでしょう。
すき家は近年、毎月配布している定期券の普及に力を入れており、それがだいぶ浸透してきている印象です。ですから、その定期券の取り組み以前よりも、確実に固定客がついているというのが強みといえますね。また、他チェーンに比べ期間限定メニューや数量限定メニューにも力を入れています。やはりそういった普段と違うメニューなどがあると目に留まりやすく、集客効果も高いのでしょう」(重盛氏)
業績悪化により吉野家が国内40店舗の閉店を予定しているが、吉野家のこの一手はどうだろうか。
「これ以上、業績悪化させないための苦肉の策でしょうから、40店舗閉店しても状況が好転することはないと思います。また、吉野家が閉店するといっても、すき家、松屋がそのおこぼれにあずかって業績が上がるということも考えにくいです。というのは、吉野家の牛丼の味が好きな吉野家ファンは、近所の行きつけの店舗が閉店したとしても、すき家や松屋に乗り換えるということはなく、変わらず吉野家に行くという方が多いと思いますからね」(重盛氏)
テイクアウト値下げを行った吉野家と松屋の明暗
すき家は近年の取り組みが、コロナ禍でもダメージを最小限に抑えることに功を奏しているのかもしれないが、吉野家と松屋はそうではないようだ。
「牛丼チェーンは、コロナ禍以前からテイクアウト需要もありましたが、基本的にはイートインで回転率を上げて売上高を伸ばすことを主軸にしていました。ですが現在は営業時間が短くなったり、ソーシャルディスタンスのため席数を減らすことで結果的に混んでしまったりしています。“お店に来て食べていただく”という今までのビジネスモデルは、既に崩壊してしまっているのです。今の経営状況を見ると、今後、業績が右肩上がりになっていくことはあまり望めないでしょう」(重盛氏)