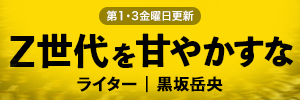PayPayアセットが突然の事業終了、販売戦略の誤算…問われる受託者責任
2025.01.27
ビジネスジャーナル
深野氏によると、すでにこのような状況が形成されていたにもかかわらず、PayPayアセットが売りにしていたのはダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価、いわゆるNYダウに連動するファンドだったという。同指数は確かに米国株の代表的な指標として、テレビや新聞などで日々報道されているメジャーな存在ではある。とはいえ、インデックスファンドというフィールドにおいては傍流にすぎないため、商品設定および販売戦略において、この点を読み違えたことによるスタートダッシュの失敗は大きなつまずきだったと、深野氏は指摘した。
投信業界をサバイブするための「商品構成」「販売戦略」が欠けていた可能性
加えて、忘れてはいけないのが販売会社の問題だ。深野氏が続ける。
「近年ではITを筆頭に、他業界から金融業界や資産運用分野への参入が続いています。この流れに乗り、PayPayは成功した時の利益最大化を狙って、既存のプレイヤーと提携せず自力で立ち上げる道を選んだ。でもPayPayアセットが連携するPayPay証券には正直、売る力がなかったんです。これがたとえば楽天投信投資顧問であれば、楽天証券という大手ネット証券二強の一角が力を入れて売ってくれるのですから、事情がまったく違うわけです。結果論かもしれないけれども、商品構成にしろ販売戦略にしろ、投信業界のことをちゃんとわかっている人が舵を取っていたのかな? という疑問はあります」
グループに運用会社を持ってはいないけれども、売る力のある販売会社と組めればまた展開は違ったのかもしれない、と深野氏はいう。
「これは想像ですが、投信の売り方という部分で、インデックス投資は流行っているし金融庁の肝いりでもあるということで、若干高をくくっていた面があったのかもしれません。本来、どんな商品であれ想定する顧客に自社の商品を認知させるためには、コストをかけてありとあらゆる手を打つ必要があるはずです。まず広告宣伝は最初に考慮すべき手段ですし、今どきはインターネット上でインフルエンサーと組んで展開する、インフルエンサーマーケティングだってあります。はたして自社の商品を認知させ、購買につなげるための努力をどこまでしたのか。販社を巻き込んで、投資信託を売るための包括的な戦略を組めていたのだろうか、いなかったのではないか、ということですよね」
思い返せば、PayPayアセットの親にあたるPayPayは、他のQRコード決済との激しい競争の中で、巨額の販促費用をかけて加盟店にも消費者にも優遇措置をふんだんに行った結果、今の一強体制を勝ち取った。この成功体験があったにもかかわらず、運用会社を育てる時に全く活かされていなかったと解釈することも可能だろう。
「低コストのインデックスファンドを買ってさえいれば、長期運用なら安心、安全、高成績」といえるのか?
ここまで見てきたように、投資信託を設計し、販売戦略を設計し、育てるという流れについて、PayPayアセットは認識不足だったのではないか、というのが深野氏の見立てだ。その背後には、IT企業のマインドと金融業界のルールがまったく異なることが関係しているという。
「仮にPayPayがIT企業のマインド、やり方で金融業界に入ってきたのだとすれば、まずはスピード重視でサービスを始めてから成り行きで対応して、うまくいかなければ事業自体を損切りするというやり方がなじんでいるでしょう。その結果として、過当競争に苦しんだあげく先陣を切って脱出する形になった。素直に解釈すれば、こうなります」
インデックスファンドは指数に連動するオペレーションを行うだけなので、運用の手間がかからないといわれがちだが、そんなに甘いものではないと深野氏は強調する。もはや低コストのチキンレース、つまり我慢比べになっており、降りたい運用会社は他にもあるかもしれない、というのだ。
「結局のところ、低コストのインデックスファンドを買ってさえいれば長期の運用成績は折り紙付きと、安心していたら危ないと言いたいですね。今回、運用会社の規模も重要だと、1つ学ぶことができたのではないでしょうか。つまり人と同じことをやっていれば安全ではないということです。今回のPayPayアセットの廃業で被害を受けた人がいるかもしれませんが、そうでなくても運用を続けていけば暴落には何度も遭遇します。そのつど、何が起こっても自己責任で引き受けていかなければならないのが投資です。ちゃんと自分で勉強して、理解してからやらないとまずいことはお伝えしたいですね」
(文=日野秀規/フリーライター、協力=深野康彦/ファイナンシャルリサーチ代表)