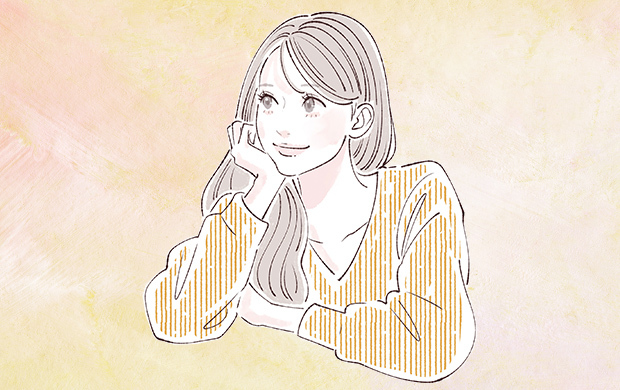1200件の検査を一人で…AI医療機器×地方医療の最前線
2025.08.27
ビジネスジャーナル
「特に自治体での導入は予算を取るのに時間がかかるため、2年は必要だと思います」(同上)
地方で使われている理由は「誤診を防ぐ」ため
こうした状況のなかで、AI内視鏡の導入に踏み切ったのが、和歌山県田辺市にある竹村医院の高原伸明医師だ。年間約1200件の胃カメラ検査を1人で担う高原医師は、導入の理由をこう語る。


「専門医が少ないこの地域では、二重読影や指導体制を整えることは現実的に不可能です。私自身も69歳になり、体力の低下は避けられません。万一のことがあってはいけないと、見落としを防ぐためにAIの力を借りようと考えました」
AIが示す疑わしい箇所に対して、人間がもう一度丁寧に観察を行う──高原医師が導入した使い方は、まさにAIを“補助線”として活用するモデルだ。現時点ではAIだけに任せるのは困難だが、医師がAIの指摘に応じて観察することで、見逃しリスクを減らすことができる。
「進行がん・早期がんを1例ずつ見つけられています。すべてAIのおかげとは言いませんが、少なくとも“見逃さずに済んだ”という安心感はあります」
竹村医院がある田辺市では、専門医はごくわずか。南に下るほど医師は激減し、「ガイドライン通りに診療すれば、診療自体が成立しない」状況だという。地方の病院は経営が厳しく、若手医師はどんどん都市部へ出て行ってしまう。親の代から続く医療機関であっても、子どもを医師として育て上げたにもかかわらず、後継者にはならない??、そんな話も珍しくないという。
医師不足の現実に直面する地方の医療現場。高原医師は、自らが引退すれば「後がいない」状況になると語る。医師会も含めて、開業医と勤務医の意識差があるため、制度改革への動きも鈍いという。
AIは地方医療を救うのか
実際のところ、どのような医療現場ならAIの価値が見いだせるだろうか。率直に高原医師に尋ねたところ、「見落としを防ぎたいという医師には向いているが、研修医のようなレベルでは使いこなせないだろう」とAIの可能性を肯定しつつも、活用は限定的だという見方をした。現状のAIは画像診断での支援が主だが、将来的には問診や一次診断、さらには診療ナビゲーションまで担えるようになることを期待している。
「たとえば問診支援AIがもっと発展して、一次問診をAIが行い、訓練を受けた看護師が診察をして、医師の指示を仰ぐことができるようになれば、医師の数が足りなくてもカバーする体制が作れるかもしれませんね」
地方医療におけるAI医療機器の導入は、単なるテクノロジーの進化ではない。限られた人材・資源の中で「誤診を減らし、医療を持続させる」ための、必要に迫られた選択なのだ。
(寄稿=相馬留美/ジャーナリスト)